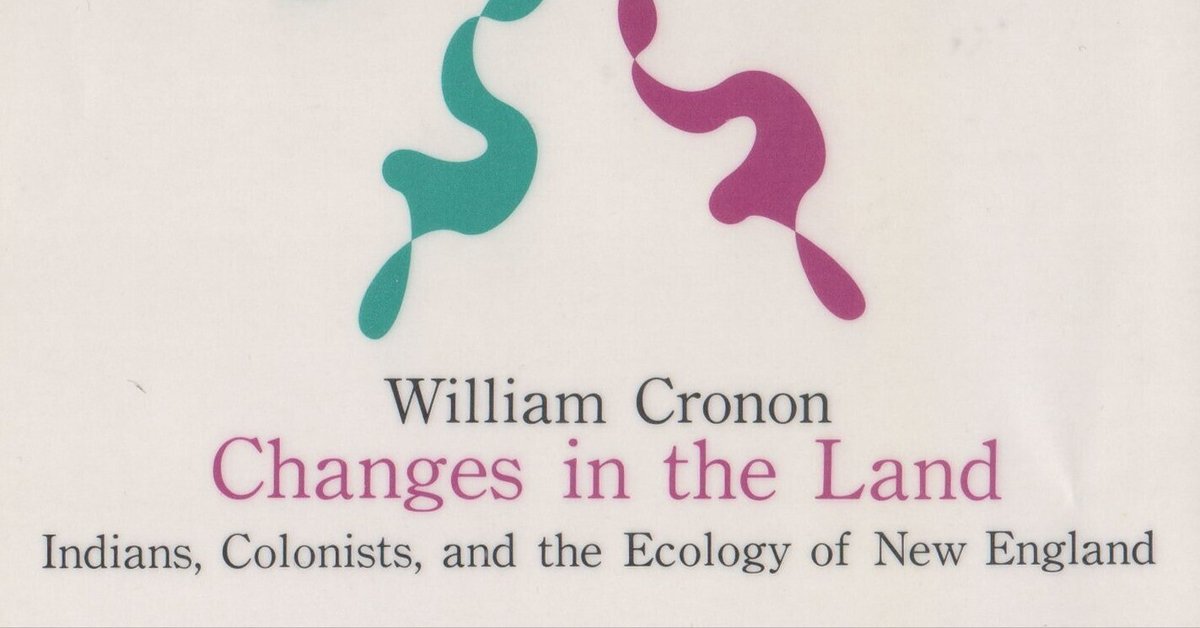
アメリカ先住民の伝統的な営みをめぐる議論の整理 『変貌する大地』から「ウィルダネス論争」、セトラー・コロニアリズムまで
はじめに
カリフォルニアの山火事に関連して様々な言説が飛び交っています。
先住民の伝統知に関しては、場所がどこであれ、言うまでもなく、様々な視点から複合的に考える必要があります。
ここでは、生態学的な知見に加えて、その視点からの議論では見落とされがちな部分にまで視点を広げて、複数の分野の研究史を概観しながら、何が問われているのかを考えてみたいと思います。
当事者の方から見れば至らない点もあると思います。忌憚なくご意見いただけたらと思います。
この記事を書こうと思ったきっかけは、Xにおける以下のポストを見たことです。といっても、直接は引用しません。要約すれば「アメリカの先住民は山火事対策のために野焼きをしていた」という内容です。全くの間違いというわけではないだけに扱いが難しい。
確かに、総じて見れば、多くのアメリカ先住民は火入れを行っていました。しかし、平野部に住む先住民が行っていた火入れは山火事対策だったのでしょうか? 当たり前ですが山がない場所で「山火事対策」のはずがありませんね。もちろん野火全般に対する対策という可能性もありますが、それならばそう書くべきでしょう。この時点でもすでにこの表現の危うさが伝わるかと思います。
昨今、国内外で「伝統的な生態学的知識(Traditional Ecological Knowledge,
TEK)」への関心が高まっているところです。火入れはアメリカ先住民に限らず多くの地域で伝統的に行われてきた行為で、頻繁に取り上げられるテーマです。日本でももちろん古くから火入れは行われており、その価値が見直されつつあります。阿蘇の伝統的な野焼きは、世界農業遺産「阿蘇の草原の維持と持続的農業」の構成要素として評価されています。パンフレットではその効果を以下のように説明しています。
阿蘇は温暖湿潤な気候のため、放っておくとすぐに、やぶ化してしまいます。草原の維持には野焼きなどの人の手入れが必要です。
阿蘇の農業システムでは、草資源の多様な活用がポイントです。世界的に見ても、草資源は放牧や家畜の飼料のみ使われることがほとんどですが、阿蘇ではそれ以外にも、田畑にすき込んだり、野草堆肥を作ったり、茅葺き屋根の材料や燃料として利用するなど、農業システムの中心となる存在として利用されてきました。
また、阿蘇の野焼きの炎は地面をサッと焼くため、温度が上がるのは地表のみで、土中の植物の種や昆虫には影響を与えません。さらに、人々の農業活動により草原環境が維持されたため、絶滅危惧種を含む数多くの草原性植物やそこを住みかとする昆虫や小動物の宝庫となっています。
阿蘇世界農業遺産パンフレット
https://www.giahs-aso.jp/downloads/
https://www.giahs-aso.jp/files/uploads/2014/02/AsoGiahs_Pamphlet.pdf
「世界的に見ても」の部分はやや気になるところですが、それはさておき、このように、野焼きによって得られる効果は多岐にわたります。アメリカ先住民族の火入れは「山火事の防止」のためだけに行われたのでしょうか。もちろん、言うまでもなく、実際にはそこから多種多様な恩恵を受けています。
もっと言えば、「焼かない」選択がなされることもありました。現実には、コミュニティごとに、自然環境に対して多種多様な対応してきた歴史があります。「アメリカ先住民」としてひとくくりにし、その行為を単純化することは、個々のコミュニティが培ってきたそれぞれの文化を無視することになります。先のポストでもっとも問題なのは、この点だとわたしは考えています。
それでは、実際にはどのような対応がなされてきたのかについて、研究史を概観していきましょう。
なお、ここでは、当初のポストの呼称に従って「アメリカ先住民」という表記をとっています。部族にあたる呼称についてはコミュニティという表記をとっています。すでに多くの場所で示されているように、わたし自身はインディアンという呼称でも良いと考えていますが、その点は後段で補足します。
ウィリアム・クロノン『変貌する大地 インディアンと植民者の環境史』(1983年、邦訳1995年)
アメリカ環境史研究を代表する一冊です。わたしも、2000年代前半に大学生をしていたときに、どこかの講義でこの本が生態学的里山論との関連で紹介されていたことを記憶しています。入手性があまりよくないうえに、現地では増補版が出ており、利用するには難点がややあるものの、この分野を勉強する人にとっては必読の一冊です。クロノンの著作はもっと邦訳が出てもよいと思うのですが、現状で訳されているのはたぶんこの1冊だけです。おもしろい本なので、火入れに関する話題と、この研究が引き起こした議論以外の部分は触れないことにします。
同書で扱われいる舞台は1620年から1800年までのニューイングランドです。山火事の話題はカリフォルニアですので、位置的にはまったくの正反対です。ここで問いたいのは「アメリカ先住民」という大きなくくりで考えてよいのか、という点です。
かなり長いですが、段落をふたつほど引用します。
ニューイングランド南部のインディアンの村が環境に与えた影響は、畑地を切り開くこと、あるいは薪のために森を剥ぎ取ってしまうことだけではなかった。インディアンは一年に一度か二度、周囲の森の広い範囲を焼き払ってしまい、このことにイギリス人訪問者はとくに印象づけられたのだった。トマス・モートンは「この野蛮人は、やってきた場所のどこで、その地に火をつけ、一年に二度、春と葉の繁る秋に、それを焼くことが常である」と書いた。ここに、南部の森がそれほどにも開けていて公園のようにみえた理由があるのである。木々が自然にそのように成長したからではなく、インディアンがそうであることを好んだからなのである。ウィリアム・ウッドが観察したように、火は「下生えとゴミの全てを焼き尽くす。そうでもしないとそれらは大きくなりすぎて、この地域を人が通れなくしてしまい、大きな影響を受けている狩猟が台無しになるからだろう」。この結果が、木々の間隔が大きく開いた、灌木の少ない、たくさんの牧草と草本類をもつ森だったのである。「インディアンが居住するこうした場所で、すばらしい地面に、藪、野バラ、やっかいな下生えを見ることがほとんどない」とウッドは言った。下生えと倒木を取り除くことによって、インディアンは、地表面に集積された燃料の全量を小さくおさえたのだった。木以外の小さな植物だけを燃え尽くすので、毎年の火入れは素早く進み、比較的低い温度で燃えて、火は自然に消えたのだった。これらは森の火というよりも地表の火で、普通は大きな木々は含まれず、それで、手に負えなくなるほど大きくなることがほとんどなかった。この種類の火は、狩猟のために獲物を追い込んだり、植え付けのために畑地を開墾したり、ときにはヨーロッパ人侵入者を押しやるのに使われたのだった。
北部インディアンは、こうした焼き払いに関与していなかったようである。彼らは農耕を行わず、特定の場所にあまり縛られていなかったので、ある地点の環境を変える動機をあまりもっていなかった。彼らの主な移動手段はカヌーで、旅をするのに開かれた森をあまり必要としなかった。さらに、北部の木の種の多くは、繰り返して燃やされることにうまく適応していなくて、北部の森は、地面に十分な燃料を蓄積する傾向があり、いったん火が発生すると、いつも林冠に達して、手におえないほど燃えたのだった。ニューイングランドの南部では条件がまったく異なっていた。密度がより高くて、固定した居住地は、より限られた範囲の森林地域の使用を激しいものとしたし、内陸部への旅のほとんどが陸伝いで行われたのだった。南部の森の木々は、いったん成熟すると、短期間の地表火にさらされても、樹皮の焦げつき以上にはほとんど被害を受けなかった。それらは、破壊されると、根から芽を出して自ら再生したのである。クリ、オーク、そしてヒッコリーは、南部内陸部の森の主要な構成種で、実際に、ときどき「芽がすぐ出る堅木」として知られてるのである。この能力を欠いているカナダツガ(ヘムロック)、セイヨウブナ(ビーチ)、そしてセイヨウネズ(ジェニバー)を含む木々と灌木は、繰り返される火によって破壊されてしまう傾向にあった。大きな森林火災の後にしばしば芽を出すストローブ(ホワイトパイン)ですら、定期的な焼きにさらされると芽を出すことができないので枯れてしまいがちになり、活動が多く行われているインディアン居住地の近辺では普通にみられなかったのである。
ウィリアム・クロノン『変貌する大地 インディアンと植民者の環境史』(1983年、邦訳1995年、勁草書房)71〜72ページ
「アメリカ先住民は山火事防止のために野焼きをしていた」と言い切ってしまうことの不味さがおわかりいただけると思います。ニューイングランド南部のアメリカ先住民の火入れは、たしかに大火事を防ぐための知恵といえます。カリフォルニアの森林火災についても当てはまる部分です。しかし、得られた利益はそれだけはないこと、狩猟の効率化、も示唆されています。さらに、北部ではそうはしなかった。必要がなかったし、燃えすぎてしまうから。
クロノンは、さらにこう続けます。
こうして、インディアンの選択的な焼き払いは生態学的遷移の多くの異なった段階にある森を生み出しながら、ニューイングランドの生態系のモザイク的性格を促進させたのだった。とくに、定期的な火は、生態学者が「辺縁(エッジ)効果」と呼ぶことを助長したのだった。森林と草地の間の境界領域に、よく似た広い地域を拡大させることによって、インディアンは、主人である野生動物種のための理想的な生息地を生み出したのである。
ウィリアム・クロノン『変貌する大地 インディアンと植民者の環境史』(1983年、邦訳1995年、勁草書房)73ページ
「モザイク的性格」や「エッジ効果」といったワードから、生態学のエッセンスを感じますね。日本の里山論とも通じる部分です。1983年の時点でこの内容は先駆的です。このあとに続く、イギリス人観察者の目に映るアメリカ先住民、文化的表象の議論も興味深いです。なぜ先住民の男性を怠け者と見てとったのか、についてです。これは実際にこの本を手にとって読んでください。
さて、ここまではアメリカ北東部の話でした。南西部のカリフォルニアではどうだったのでしょうか。これについてはすでに良い文献がありますのでまずはそちらをご参照ください。
西原 和代 文化財論文 文化的火入れが保つ景観─ カリフォルニア先住民の長期的植物資源管理 ─ - 文化財論文検索 - 全国遺跡報告総覧https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/search-article/item/121122
ここでもクロノンの引用からはじまっていますね。この論文では、アメリカ政府の火入れ抑制政策がかえって山火事の規模を大きくしているという研究や、火入れによる生態学的恩恵などに触れたうえで、カリフォルニア州における火入れの研究の状況がまとめられています。
特に重要だと感じるのは、以下の部分です。
このように、文化的火入れの効果は様々で、しかも頻度・季節・範囲によって単一でなく重層的である。長期間にわたって文化的火入れをおこなってきた先住民コミュニティでは、文化的火入れによって形成されてきた景観はそのコミュニティの生業や世界観と分かちがたく結びついており、これを研究するときに単に生態系や植生への影響を検討しようとするとその全体像にたどり着くのは難しくなるだろう。その土地に根差した人々の知識は、西洋的な生態学的知識の作法に則っては表出されないからである。たとえば、火入れがきちんとおこなわれず下草が繁茂し、木の密度が高くなった景観をみて「きたない」「(火を入れて)きれいにしなくては」と感じることが文化的火入れを行う様々な地域で報告されている(Anderson2018、Bird et al.2008、小山2011など)。
西原 和代 文化財論文 文化的火入れが保つ景観─ カリフォルニア先住民の長期的植物資源管理 ─ - 文化財論文検索 - 全国遺跡報告総覧https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/search-article/item/121122
山火事防止の「ために」火入れを行っていた、という表現は、我々の思考様式によって語られる説明です。アメリカ先住民がどう考えていたかは彼らの言語や文化全体を理解した上で考察する必要があります。この指摘のように、一種の「美観」のようなものとそぐわない「から」火入れを行い、「結果的に」山火事を防いでいたのかもしれません。固有の文化的な価値観に基づいて行ってきたことを、我々の現代的な言語に置き換えることは容易ではないのです。火入れという行為が多くのコミュニティで行われてきたからといって、その動機や得られた効果はひとくくりにできるようなものではありません。
まとめると、多様なコミュニティが多様な方法で火を用いたり、あるいは用いなかった。そして、様々な恩恵を受けていた。その内容は「アメリカ先住民」という言葉でひとくくりにできるようなものではない。
先の論文でも示されているように、日本と同様アメリカでも近年文化的火入れの再導入を求める動きが強まっています。「伝統的な生態学的知識(Traditional Ecological Knowledge,TEK)」の研究や実地での利用は生物多様性の保全や気候変動対策、災害対策などの観点からも重要なことですが、こうした技術を現代科学の文脈からだけでなく、先住民の文化的価値観にまで視野を広げて捉えたいものです。
Indigenous Fire Practices Shape our Land - Fire (U.S. National Park Service)
|視点|先住民の土地管理の知恵が制御不能な森林火災と闘う一助になる(ソナリ・コルハトカル テレビ・ラジオ番組「Rising up with Sonali」ホスト) | INPS Japan
上のものはアメリカ合衆国国立公園局の記事、下のものは日本語で読める記事です。
先の火入れのポストをされた方は、ざっと見たところでは、しばしば環境保護運動や団体に批判的なポスト、リポストをしているようですが、こうした活動を支援しているのもまたそうした環境保護団体だったりする点についてはどう考えているのでしょう。
「原生自然(ウィルダネス)は存在するか」
クロノンの主張は論争を招きます。なぜならそれはアメリカの自然保護運動の基盤を揺るがすものだったからです。
アメリカにおける自然保護の精神的、理論的基盤は「原生自然(ウィルダネス、wilderness)」です。原野や荒野と表記されることもあります。
フロンティア開拓者にとってアメリカ大陸は、それまでのユダヤ=キリスト教的な自然観からすれば「呪われた土地」「開拓すべき未開の地」であり、実際に入植者たちは次々と開拓、それがおよそ失われつつあるころ、一転して「守るべき崇高な自然」に転じた、というのが一般的な説明です(例えばナッシュ『原生自然とアメリカ人の精神』、ただしこれについても私は通俗的すぎるように思う)。価値観のロマン主義的転回です。
ギフォード・ピンショーとジョン・ミューアの有名な保全・保護の議論、ヘンリー・デイヴィッド・ソローの超絶主義、アルド・レオポルドの土地倫理などもこの系譜に位置づけられます(前掲書)。これら論者のアメリカ先住民にたいするまなざしはそれぞれだったようですが、ここでは立ち入りません。
こうして生じた原生自然を守ろうという運動は、イエローストーンをはじめとする国立公園制度や原生自然法(Wilderness Act)として政策化されます。
しかしどうでしょう、多くのアメリカ人(入植者)たちが「手つかずの自然」だと信じている場所が、アメリカ先住民たちが様々な方法で相当な規模で利用をしてきた場所だとしたら?
クロノンの主張はアメリカ人(入植者)の信じてきた世界観を揺るがすものです。それを強く信じる人や、こうした思想を基盤に自身の学問や思想を展開している研究者からすれば受け入れられない内容でした。こうして生じたのがいわゆる「ウィルダネス論争」です。
以下、すこし長いですが、これまた必読の文献であるマンの『1491』から論争に関する部分を引用します。
先住民が景観におよぼした影響の大きさを認めることは、ノモス寄りの立場をとることになるのだろう。一九八三年、ウィリアム・クロノンは、ニューイングランドの田園の歴史を詳細につづった画期的な著書、『変貌する大地 インディアンと植民者の環境史』を世に出した。そのなかで彼は、北米東部には一般に考えられているような原生自然は存在しないし、過去何千年も存在したことはなかった、と述べている(この数年後、デネヴァンは、果てしなく広がる原生自然が存在したという思い込みに“原初神話(the pristine myth)”という名をつけた)。このクロノンの原生自然不在説がニューヨーク・タイムズ紙で紹介されると、環境保護論者と生態学者から、クロノンは相対主義とポストモダン哲学に毒されているとの非難が浴びせられた。続いて研究者のあいだでちょっとした論争が持ちあがり、まるで脚注をつけるようにして、さまざまな意見が出てきた。これを受けてポストモダン哲学を批判するエッセー集――この種の書籍にしてはめずらしく、執筆者の多くが生物学者だ――が刊行された。さらに一九九八年には、『原生自然をめぐる最新論集(The Great New Wilderness Debate)』と題したアンソロジーが出版された。その編集にあたってふたりの哲学者〔J・ベアード・キャリコットとマイケル・P・ネルソン〕は、自分たちは「植民地独立後の現代世界で優位に立った家父長的な西洋文明を文化遺産とする」欧米人であるが〔欧米人の学者の意見を偏重することなく、第三世界、第四世界の思想家の論文やエッセーも収録した〕、ときまじめにことわりを入れている。
チャールズ・C.マン『1491―先コロンブス期アメリカ大陸をめぐる新発見』日本放送出版協会、2007年。563〜564ページ
「ポストモダン哲学」という部分に時代を感じますね。この論争は日本でも紹介されており、そこでも構築主義(構成主義)が問題とされています。開龍美は2005年の論文で、クロノンの主張は実在としての自然を無視した社会構成主義的なものであり、人間中心主義への退行であると主張しています。ここで挙げられているクロノンの主張というのは、「ウィルダネス」というものは西洋文明のなかでつくられた概念であり、それに基づく自然保護は「緑の帝国主義」であり「環境正義」を侵害するものである、という1995年の論文の内容です。
しかし、ポストモダン哲学の流行もとうに過ぎた今、『変貌する大地』や『1491』、あとで取り上げる『先住民とアメリカ合衆国の近現代史』などの研究を読み、アメリカ先住民の歴史的な営みや入植者の行為を把握した上で考えるなら、やはり「ウィルダネス」はアメリカ人(入植者)の心の中でつくりあげられたロマン主義的な幻想と考えるべきではないでしょうか。
昨今の「セトラーコロニアリズム(入植者植民地主義/定住型植民地主義)」の議論、例えば「入植者たちが、移住先の土地に留まり、新しい国家を形成し、発展させていくためには、先住民族の排除、および不可視化が戦略的に必要だった」(石山徳子『犠牲区域のアメリカ』)といった指摘を踏まえても、実際に起きた国立公園でのアメリカ先住民の排除を考慮しても、入植者側の理論に基づく一方的な自然保護政策はやはり帝国主義的であると言わざるを得ない、というのがわたしの考えです。もちろん、アメリカ人のアイデンティティや、それによってなされた自然保護も尊重はしたい立場です。わたし自身、身の回りにある山道具を見てもアメリカ的なるものだらけで、偉そうなことを言えたものかと考え込んでしまいまいます。
こうした知的状況がその後もしばらく続いたことが推測されます。例えば、ポタワトミ族の出身の生態学者ロビン・ウォール・キマラーは、『植物と叡智の守り人 ネイティブアメリカンの植物学者が語る・科学・癒し・伝承』のなかで、自身が指導する学生の研究テーマが当初は全く受け入れられなかったことを書いています。アメリカ先住民が伝統的に用いていたスイートグラスの生育に関するもので、伝統的な手法による刈り取りが生育に好影響を及ぼすのではないか、というテーマです。このテーマは論文指導委員会で「植物を刈り取れば個体群に悪い影響を与えるということは誰だって知っている。時間の無駄だよ。悪いが、伝統的知識が云々というの説得力がないと思うね」と学部長に一蹴されてしまいます。手にとって読んでもらいたいのでことの顛末は伏せておきますが、この論文自体はキマラーの所属する研究機関のページで閲覧できますのでリンクを貼っておきます。2006年のものです。日本での生態学的里山論の発展の歴史を振り返ると、2006年時点でもこの状況というのは少し意外な気もします。この温度差についてはもう少し考えてみたいと思っています。キマラーの著作では比較的有名な『コケの自然誌』も良いですね。
The effects of traditional harvesting practices on restored sweetgrass populations. - College of Environmental Science and Forestry
とはいえ、近年は様子が変わってきているようです。「伝統的な生態学的知識(Traditional Ecological Knowledge,TEK)」は先に挙げた記事中でも言及されていますし、ウィルダネスをめぐる議論もhistory.comのような大手サイトの記事でも普通に言及されるようになっています。
「ジョン・ミューアたちがアメリカ西部の壮大さは自然の力でつくられたと信じていたのは、アメリカ先住民たちがたくさん住んでいたことを知らなかったからだ」といった意味です。この記事もおすすめです。
「One of the reasons why John Muir and other naturalists would have believed that the grandeur of Western America was shaped entirely by natural forces is that they had no idea how many Native Americans had once lived there.」
Native Americans Used Fire to Protect and Cultivate Land | HISTORY
https://www.history.com/news/native-american-wildfires
今回のテーマとしては、ここまでで一段落です。再度もとのテーマに戻りますが、いったん別の話題になります。
「(アメリカ)環境倫理」、アメリカ先住民の透明化
ミューア、ピンショー、ソロー、ナッシュ、キャリコットらの一連の議論からアメリカでは「環境倫理」という学問分野が発達しました。日本にも紹介されています。主に鬼頭秀一によるものです。しかし、なぜか「ウィルダネス論争」とその後の展開は紹介されていないようです。アメリカ先住民の迫害については『自然保護を問い直す』でも触れられていますし、クロノンの著作についても氏が関わったシリーズ『環境思想の系譜』でも取り上げられています。しかし、あくまで「環境倫理」の立場から「批判がある」とする受け身の姿勢です。先住民側から見た視点はないようです。これがどのような問題を招くか見ていきます。
まず最近の書籍『都市の緑は誰のものか』の中での論考です。鬼頭は「本質的価値・人間非中心主義」と「道具的価値・人間中心主義」を対立させ、1970年代に成立した自然保護を前者として規定し、それを「環境倫理1.0」と呼びます。そして、その「環境倫理1.0」は「人と深い関わりがある自然の保全の理念にはなりえない」といいます。「環境倫理1.0」では「自然そのものがもともと持っている本質的価値」が重視され、人為の介入によってその価値の毀損されることを否定するため、里山のような二次的自然の保全には有用ではないというのです。
これは、一見それらしく見えますが、かなり危うい議論です。理由はふたつあります。ひとつめは、アメリカ環境倫理の枠組みの批判的克服を訴えながら、参照する視点が常にアメリカ環境倫理のものだからです。「本質的価値」や「道具的価値」といった考え方は、アメリカの国立公園の利活用をめぐる議論からのものです。そのまま残すか、林業等に利用するか、のような。枠組み自体がアメリカのものであるならば、原理的にその克服は不可能なのではないか。そもそもそれらはどのくらい日本の自然保護に当てはまるのか。
ふたつめの理由は、その点、つまり自然保護の歴史をじゅうぶんに把握していないことによる解釈の誤りです。先のわたしの記事でも触れたように、実際には1970年代に各地で巻き起こった自然保護運動は、身近な自然を対象としたものです。すでにそのときから自然と人間の関係は問われていました。当時の多くの文献がそれを示していますし、のちの学術的な文献でも数は少ないですがきちんと触れられています。その時点から議論があったからこそ、1980年代を通してそれが成熟し、1990年代以降の里山論の流行となるのです。鬼頭は自身で自然保護の歴史を渉猟し、内容を整理し、評価することを怠っているように見えます。
「市民運動」の欄がない自然保護年表を作って思うこと|GFB
鬼頭は「環境倫理1.0」の例として、宮脇昭の「潜在自然植生」を例にしているようですが、1970年代に宮脇が行った工場緑化は、人間と自然の関係が問われる工場という人工の場所で行われた一種の自然再生事業です。管理に手をかけなくてよい常緑広葉樹を中心とする宮脇の植樹法は、手つかずの自然を良しとする価値感からというよりは、管理者の利便性に対応して構築されたものです。間伐や落ち葉掃きが要らないう触れ込みは管理者にとって大きなメリットです。在来の樹種を中心とする点はのちの里山保全と変わりません。手つかずの自然を最良とするなら、そもそも工場の建設に反対するのが筋であって、開発を是認し、それに免罪符を売る宮脇の手法は、原生自然の保護とはかけ離れています。宮脇のこの方向性ついては最近かなり良い論考が出ています。ここでは伏せておきますので探してみてください。
鬼頭の議論を踏襲し、ともに『都市の緑は誰のものか』に筆をよせる吉永明弘も同様です。アメリカでの議論と対比させて、「日本では、自然再生という考え方について批判する声はあまりない」としていますが、とんでもない。狭義の自然再生、自然再生推進法(2002年)以降のいわゆる市民参加型公共事業による官民協働の自然再生事業に限っても、当初から恣意的な自然再生が行われることが懸念されており、それゆえ日本生態学会生態系管理専門委員会は2005年に自然再生事業指針を策定しています。その自然再生事業についても、ここでは具体的な名前は挙げませんが多くの問題を抱えるものが存在しており、様々なレベルから批判がなされています。当時流行し、技術思想的にはこの時期の自然再生とルーツを同じくする公共事業型ビオトープについても多くの批判があります。里山概念を海にまで広げた里海概念とそれを援用した開発についても多くの批判があります。より広い意味での自然再生、例えば先の宮脇方式による植樹(1970年代から)や旧建設省の多自然型川づくり(1990年から)などについても、理念のレベルから実際の施工のレベルにいたるまで多数の批判が当時からあります。
こうした事例を整理したうえで「あまりない」と評価するならまだわかるのですが、鬼頭にしても吉永にしてもその形跡が全くありません。一体何を根拠にそう判断したのか示されていません。実態としての自然や自然保護に彼らは関心がないように見えます。生き物のにおいがしません。
鬼頭は、おそらくは、1990年代以降の里山論の隆盛を見て、相対的にそれ以前の自然保護は「手つかずの自然」を守るものばかりだったと思い込んでいるのでしょう。
前提としてまず、「ウィルダネス」を至上とするアメリカ環境倫理の議論が頭にあり、それと勝手につくりあげた1970年代の自然保護像(「環境思想1.0」)を重ね、これらと対置させるかたちで1990年代以降の里山論を「環境倫理2.0」として置く、という構図です。二項対立を乗り越えることを主張しながら、鬼頭の議論はいつも二項対立です。ウィルダネスも幻想で、日本の自然保護像も幻想、その枠に自ら縛られる。自縄自縛です。
遠回りしましたが、ここで「ウィルダネス」の問題に戻ります。
その「ウィルダネス」を至上とするアメリカの自然保護思想は、クロノンらの議論を踏まえるなら「幻想」であり、先住民の存在を透明化することで成立しています。これはセトラーコロニアリズムの一例です。ナッシュが説明するように、アメリカ人の精神性の重要な要素ではあるにしても、これを参照軸とした説明を、現在そのまま受け取ることは難しいでしょう。最低でもウィルダネス論争を踏まえて、また、日本の自然保護の歴史を精査した上で構築し直す必要があります。
逆の姿勢、アメリカ先住民の文化の収奪的利用
日本における「アメリカ環境倫理」の展開がアメリカ先住民の営みを無視するかたちで行われているのとは対照的に、これらを積極的に利用する動きも古くからあります。「アメリカ先住民の知恵を借りよう」です。日本での受容と展開には星川淳による翻訳出版活動の影響など、いくつかのルーツがあるのですが、ここでは割愛します。
実際の例を見てみましょう。西條辰義の「フューチャー・デザイン」におけるイロコイの「7世代」の援用です。西條は二酸化炭素の排出権取引の制度設計など環境経済学の研究から社会哲学の分野に転じた研究者で、実験的な手法を用いながら社会変革を目指す活動をしています。イロコイ連邦とはモホーク族、オナイダ族、オノンダガ族、カユガ族、セネカ族の5つのコミュニティ、のちにタスカローラ族を加えた6つのコミュニティの連合で、独立戦争とその後の領土分割で主権を失うまで、ニューイングランドからオンタリオ湖東岸地域(すなわちクロノンが『変貌する大地』でとりあげた一帯)を勢力範囲としていました。その統治形態や文化から古くから研究の対象となっており、特に女性による統治やワンパムの貨幣的利用、「偉大な法(Great Law of Peace)」は様々な場所で取り上げられています。西條はこのイロコイから「次の7世代後のことも考えよ」というスローガンを借用します。しかし、これが非常に杜撰。
西條の編著による『フューチャー・デザイン 七世代先を見据えた社会』(2015年)では「偉大な結束法」に「まだ生まれていない将来世代を含む世代を念頭におき」等の文言があるとし、それがアメリカ合衆国の政治体制のデザインに影響を与えていると言っています。そして、その影響を受けているはずの合衆国憲法に世代に関する記述がないことを問題視します。
しかし、この解釈は通俗的な誤読です。イロコイの法には実際にはそのような記述はなく、また、合衆国憲法等に与えた影響についても議論があるためです。そのことをどこかで知ったのでしょう、西條は次の『フューチャー・デザインと哲学 世代を超えた対話』(2021年)の自身が担当する章の注で「ただし、そのような記述はイロコイの憲法に相当するThe Great Binding Lawにはないものの、口承で残っているようである(アンダーウッド、1998,p.109)」と釈明、近著『フューチャー・デザイン』(2024年)では、イロコイの統治体制とアメリカ合衆国の政治体制との関連についても論争が継続しているようであると弁明しています。
イロコイの「将来世代のことを考える」という思想は実際に存在するものであり、彼ら(もちろん全員ではなくあり方は多様)のアイデンティティにもなっています。ただし、それは口承による歴史であり、取り扱うためにはオーラルヒストリーの取り扱いに関する訓練――過去数十年繰り返し注意が促されてきた――が必要です。特にアカデミアの人であるならば。それが全くないまま、自説のための単なる道具として取り上げてしまえば、彼らの歴史やアイデンティティを歪めてしまう結果になるのは必定です。
この問題については以下の指摘が簡潔です。
美化された先住民像は、積極的に商品化されてきた。1988年に創業された「セブンス・ジェネレーション」は、洗剤、おむつ、生理用品などを生産している。消費者の健康と安全を守ると同時に自然環境にやさしい製品づくりを目指してきた。
「7世代目」という名称を掲げた同社は、イロコイ連邦の「自分たちが決断を下すときには、7世代あとの子孫への影響を考慮しなければならない」というコンセプトをモットーにしている。商品価格はやや高めに設定されているが、リベラルな思想をもつ、比較的裕福なインテリ層に人気がある。
私はこれまで数多くの保留地を訪ねてきたが、「セブンス・ジェネレーション」の商品を好んで使っている先住民に会ったことはない。
西部劇に登場する野蛮人、スポーツ界のマスコット、ポカホンタスが象徴する女性像、そして環境にやさしい賢者というステレオ・タイプは、いずれも白人に都合よくつくられたイメージでしかない。虚像は常に強烈な印象を残し、先住民が直面する現実だけでなく、アメリカ社会が抱えるさまざまな矛盾と課題を見えにくくしている。
鎌田遵「第28章 ステレオ・タイプ」阿部珠理編著『エリア・スタディーズ149 アメリカ先住民を知るための62章』2016年、明石書店。165ページ
先の石山も同様のことを述べています。アメリカの核開発の現場と先住民の関係を、長きにわたり足を運んで考える中で、「幾重にも絡みあっている」植民地主義の歴史や制度的な差別を目にし、「自然と共生し、環境運動を牽引すべき救世主であるというステレオタイプや、核開発に常に抵抗する立場だという先入観、さらには、「加害者」対「被害者」、「人種差別的な行政、または、企業」対「差別に苦しむ就職人種」といった、単純明快な二項対立の図式は打ち砕かれた」といいます(前掲書、はじめに)。
歴史の誤った解釈や、美化されたイメージの表面的な利用、矛盾や課題の透明化といった失敗は、こうした日本語の、もしくは日本語訳された先行研究を踏まえるだけでも相当程度回避できるはずなのですが、この手のアプローチをとる論者・活動家は往々にしてそれをしません。西條の書籍の注を見ると「7世代」に関する部分の多くをwikipediaやwebページから拾っていたようです。さもありなんです。
西條の研究や活動自体についてはわたしも否定的な立場はとっていません。それ自体でじゅうぶん成立する内容なのに、なぜ軽いノリでイロコイからスローガンを借りて看板にするのか。わたしにはよくわかりません。自説のブランディングのためであるなら即刻やめたほうがいい。
さらに、次のような指摘は昨今流行の思想に対して、それが万能ではないことを知らせてくれます。
入植者植民地主義を永続させる無罪への競争は、マイケル・ハートとアントニオ・ネグリの仕事で人気を博した一九九〇年代の社会運動理論でより洗練されたバージョンとして発展し始めた。三部作の第三巻である『コモンウェルス』は、中世ヨーロッパのコモンズの概念を、現代の社会運動の願望として復活させようとする二一世紀初頭の学術的流行の中で書かれた数ある書籍のひとつである。コモンズに関するほとんどの著作では、「すべての土地を共有する」という呼びかけに関連して、先住民の運命についてはほとんど言及されていない。例えば、カナダの学者であり活動家でもあるナンディタ・シャーマとシンシア・ライトの二人は、先住民の土地の主張や主権を言葉を濁さずはっきりと否定し、それらを外国人嫌いのエリート主義であるとしている。彼らは先住民の主張を「世界中の抑圧から生じるグローバルなディアスポラに照らして逆行する人種差別」と見なしている。
クリーの学者であるロレイン・ル・カンプは、このような北米における先住民の抹殺を「テラヌリズム」と呼んだが、これは発見の教義のもとで、空地とされた土地を「テラ・ヌリウス」(無主の地)と呼んだことに由来する。一種の無過失の歴史観だ。国境も国家もない、すべての人のための漠然としたコモンズという解放された未来の理論から、理論家たちは、植民地主義の国家からの解放のために闘っている先住民のネーションの現在と存在を消し去ってしまう。それによって、脱植民地化、国民性、主権を求める先住民のレトリックやプログラムは、このプロジェクトによれば、無効で無益なものとなってしまうのである。
ロクサーヌ・ダンバー=オルティス『先住民とアメリカ合衆国の近現代史』青土社、2022年。296〜297ページ
コモンズ論も大昔から絶えず俎上にあるテーマですね。「共有地」の歴史性やメカニズムを研究するのは良いでしょう。重要なことです。しかし、「コモンズであれ」という社会運動には注意が必要です。全ての場所や物を共有財産にして良いわけではないからです。先住民の持っていた土地や物、営みの権利は彼らのものであり、他者が一方的に共有化してよい性質のものではありません。昨今のコモンズ論でこの点を指摘しているものを、私はほとんど目にしていません。
もちろん、そもそもの話として、過去に一定期間持続していた共有地が常に持続的で平等であったわけでもありません。そうした例を示す研究は星の数ほど(は盛り過ぎか)あります。例えば丹羽邦男の古典的名著『土地問題の起源』では、明治以降の土地の私有化を問題視しながらも、過去の入会地利用における階級的格差の例についてもきちんと紹介しています。
ネグリとハートの研究については、歴史研究の分野では実証性の薄さから影響はきわめて限定的だったいう指摘があります(北村暁夫「「混沌」から「傲慢」へ「長い一九世紀」におけるヨーロッパと南北アメリカ」『岩波講座 世界歴史16 国民国家と帝国 19世紀』岩波書店、2023年)。これには首肯できる部分が大きいです。
例えば、『アセンブリ』(2017年)の256ページ、「資本主義的貨幣の社会的諸関係」の図です。「貨幣形態の変化に応じて制度化された社会的諸関係を要約」としているので厳密なものではないのかもしれませんが、あまりに単純に図式化しているように思えます。「g. 階級闘争の形態」に対しては、「1. 本源的蓄積」では「民衆闘争ないし農民反乱」、「2. マニュファクチュア大工業」では「労働階級による闘争とストライキ」、「3. 社会的生産」では「生政治的階級闘争と社会ストライキ」が位置づけられています。ここに、日本での、例えば「一揆は階級闘争か」という一連の論争を重ねたとき、本当に成り立つのか私には疑問です。日本だけでなく世界各地で積み上げられたこの分野の実証的研究と、この図は本当に整合するのか。あるものごと理解するために図式化して考えることは重要ですが、図をつくっておいて歴史をそれに当てはめていこうとする行為は手段と目的が転倒しています。
コモンズに関する部分も、先住民の歴史など実証的な研究をしっかり踏まえていれば、容易には言い出せないのではないかと思います。逆に、それがないから自由で大きな語りができるのだろうと。ちなみにですが、オルティスもクロノンやマンの研究を引用しています。先の厳しい指摘は、そうした実証的研究への理解があってこそ成り立つわけですね。
わたし自身も、行政サービスや社会保障、個別の問題でいえば生物多様性の保全であるとか気候変動対策に対しては「公」の役割がある程度大きい方がいいという立場ではあります。しかし、その意識を無自覚に拡大すると、公有化してはいけないものまで公有化しようとしたり、すでに一方的にそうされてしまっているものに対して鈍感になるといった弊害も生じます。気をつけたい部分です。
さて、かなり後段になってしまいましたが、「インディアン」という呼称についてです。私はオルティスの「著者ノート」や、阿部珠理『アメリカ先住民 民族再生に向けて』(2005年)の「アメリカン・インディアン」という呼称への回帰」等の議論から、インディアンという呼称を用いることは問題ないと考えています。ただし、オルティスが指摘するように、そこに「エージェンシー(行為主体性)」を安易に重ねることには注意が必要です。オルティスはそうした行為を、植民地主義の犠牲者に自らの死の責任負わせたり、「出会い」や「対話」のような美化された構図に改ざんする、「一方的な強盗殺人への謝罪」だと強く糾弾しています。アメリカ合衆国の憲法や政治体制にイロコイの知恵が採用されている、といった考えもその類でしょう。わたし自身はジュディス・バトラーの一連の議論に強く影響を受けており、行為主体性の有用性を強く信じていますが、こうした指摘は真摯に受け入れる必要があると感じています。
おわりに
最後です。わたしはある民族には特有の自然観が備わっていて、それが環境問題の解決に役立つ、といった考え方に強い警戒心を持っています。そうした環境決定論的な自然観/人間観の問題については、以前にテーマとして扱っています。
里山ナショナリズムの源流を追う 21世紀環境立国戦略特別部会資料から|GFB
そんなわたしでも、アメリカ先住民(といっても何人かの個人の)の自然観には心を揺さぶられます。先のキマラーもそうですし、チカソー族の作家リンダ・ホーガンの『大地に抱かれて』もそうです。キマラーの植物に対する洞察や、ホーガンのコウモリの描写からは不思議な高揚感が得られます。生物学的な描写と、それとは一見反するような彼らの循環的な自然観が、衝突せずに縫い目もなくひとつになって成立していて、読んでいるとなんだかふわふわする。もともとそんなふうに世界は二分されていなかったのではないか、このような感覚をみなが持てば世の中なにか変わるのではないか、と思うほどに。

先住民の知恵や文化にそうした魅力があるのは確かです。しかし、そこへ傾倒し過ぎてしまうと直視すべき様々な問題が見えなくなってしまう。そうなると結果的にその魅力的な文化を損なうことなる。惹かれるからこそ慎重でありたい。
さて、このくらいで終わりましょうか。世界には良い書物がたくさんあります。みなさんのさらなる読書体験に、本記事が役立てば幸いです。
参考文献
ウィリアム・クロノン『変貌する大地 インディアンと植民者の環境史』勁草書房、1995年
西原和代 文化財論文 文化的火入れが保つ景観─ カリフォルニア先住民の長期的植物資源管理 ─ - 文化財論文検索 - 全国遺跡報告総覧
https://sitereports.nabunken.go.jp/ja/search-article/item/121122
ナッシュ『原生自然とアメリカ人の精神』ミネルヴァ書房、2015年
チャールズ・C.マン『1491―先コロンブス期アメリカ大陸をめぐる新発見』日本放送出版協会、2007年
William Cronon, ed., Uncommon Ground: Rethinking the Human Place in Nature, New York: W. W. Norton & Co., 1995, 69-90.
https://www.williamcronon.net/writing/Trouble_with_Wilderness_Main.html
J. Baird Callicott, Michael P. Nelson The Great New Wilderness Debate, University of Georgia Press 1998
Michael P. Nelson, J. Baird Callicott The Wilderness Debate Rages On: Continuing the Great New Wilderness Debate,University of Georgia Press 2008
開龍美「ウィルダネスという他者?」岩手大学レポジトリ https://iwate-u.repo.nii.ac.jp/records/12967
石山徳子『犠牲区域のアメリカ 核開発と先住民』岩波書店、2020年
鬼頭秀一『自然保護を問いなおす 環境倫理とネットワーク 』筑摩書房、1996年
『環境思想の系譜 1 環境思想の出現』東海大学出版会、1995年
『環境思想の系譜 2 環境思想と社会』東海大学出版会、1995年
『環境思想の系譜 3 環境思想の多様な展開』東海大学出版会、1995年
太田和彦・吉永明弘(編著)『都市の緑は誰のものか』ヘウレーカ、2024年
西條辰義『フューチャー・デザイン 七世代先を見据えた社会』勁草書房、2015年
西條辰義『フューチャー・デザインと哲学 世代を超えた対話』勁草書房、2021年
西條辰義『フューチャー・デザイン』日本経済新聞出版社、2024年
阿部珠理編著『エリア・スタディーズ149 アメリカ先住民を知るための62章』明石書店、2016年
ロクサーヌ・ダンバー=オルティス『先住民とアメリカ合衆国の近現代史』青土社、2022年
丹羽邦男『土地問題の起源 村と自然と明治維新』平凡社、1989年
『岩波講座 世界歴史16 国民国家と帝国 19世紀』岩波書店、2023年
アントニオ・ネグリ、マイケル・ハート『アセンブリ』岩波書店、2017年
リンダ・ホーガン『大地に抱かれて』青山出版会、1996年
