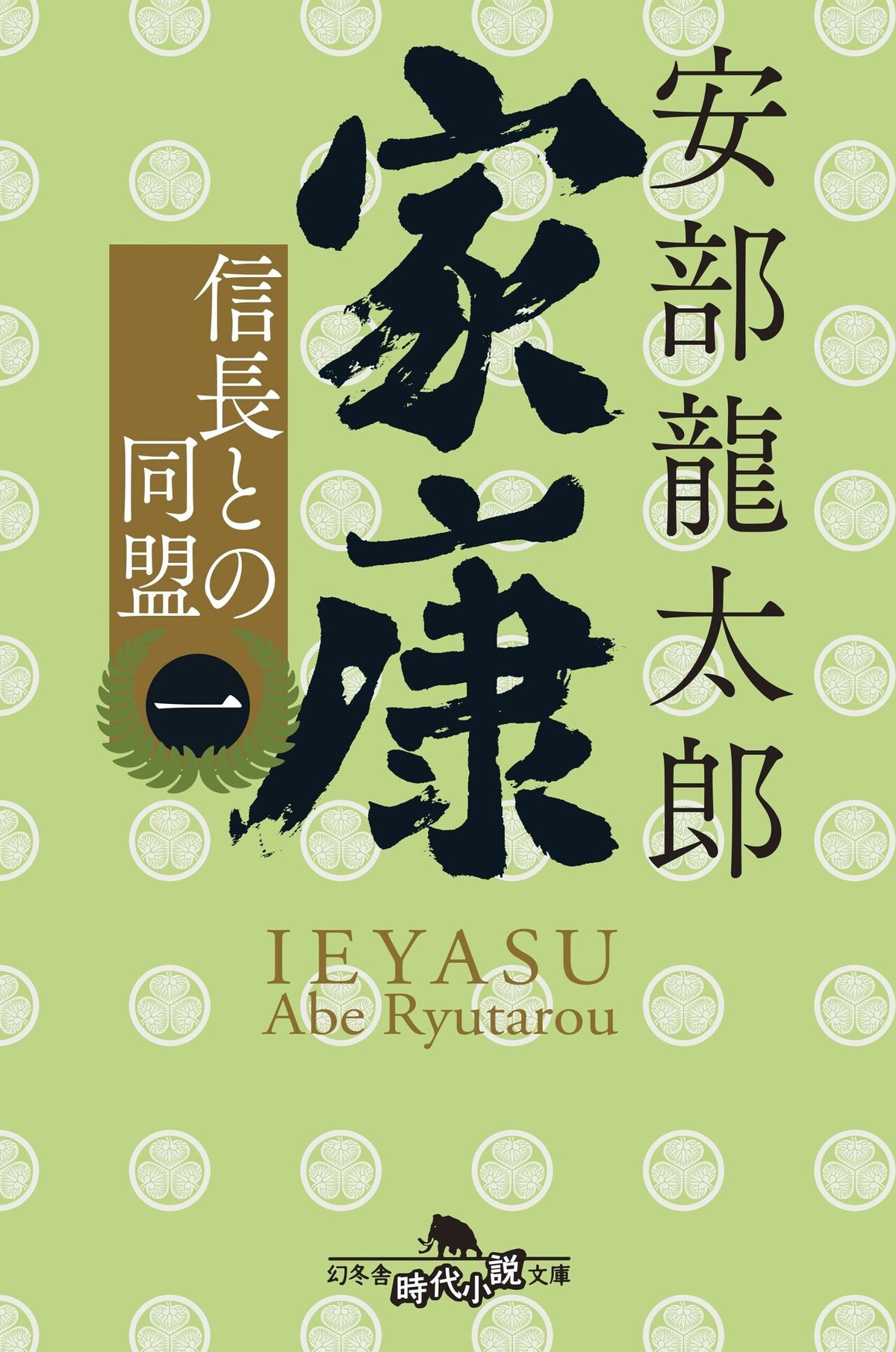まもなく戦が始まる…戦国最後の覇者を描き切った「大河歴史小説」 #1 家康(一)信長との同盟
桶狭間の敗戦を機に、松平元康(のちの家康)は葛藤の末、信長と同盟を結ぶ。単なる領地争いの時代が終わったことを知った元康は、三河一国を領し、欣求浄土の理想を掲げ、平安の世を目指すが……。信長でも秀吉でもなく、なぜ家康が戦国最後の覇者となれたのか? その真実に迫った、安部龍太郎さんの大河歴史小説『家康』(全6巻)。その記念すべき幕開けとなる『家康(一) 信長との同盟』のためし読みをお楽しみください。
* * *
第一章 出陣
五月雨の季節である。
厚い雲がたれこめ、湿気の多い空気があたりをおおっている。海からの生暖かい風が肌にまとわりつくようで、猛暑の季節が近いことを告げていた。

駿府城下、宮の前の屋敷では、松平元康(後の徳川家康)が文机に向かっていた。獅子形の水滴から硯に水をそそぎ、ゆっくりと墨をすっている。
師の太原雪斎から教えられた通り、墨を真っ直ぐに立てて前後に動かしながら、無の境地になろうとしていた。
尾張の織田信長との戦いは目前に迫っている。
駿河、遠江、三河の太守である今川義元は、五月中頃には四万の大軍をひきいて出陣すると決し、仕度をととのえて下知を待てと全軍に命じている。
今川家のご恩をこうむる元康は、三河衆一千余をひきいて先陣をつとめ、伊勢湾に面する大高城に兵糧を入れて、尾張への侵攻にそなえよと命を受けた。
十九歳になる元康は、この大役に勇み立った。
駿府で人質のような暮らしを強いられて十二年。ようやく独立の機会がめぐってきたのである。
華々しい手柄を立て、岡崎城にもどることを認めてもらいたい。帰りを待ちわびている三河の家臣や領民に、元気な姿を見せてやりたい。
その一心で万全の仕度をととのえていたが、ひとつだけ厄介な問題が残っていた。知多半島北部に勢力を張る水野信元が、いまだに恭順の意を示さないのである。
信元は元康の母於大の方の兄である。
初めは今川家に属していたが、元康が生まれた直後に尾張の織田家と手を結んで反旗をひるがえした。
そのために父広忠は於大を離縁して実家に送り返さざるを得なくなり、元康は母と引き離されたのである。
この信元をどうするかが、今度の出陣の大きな問題となった。
信元が拠る刈谷城や緒川城は、尾張に攻め込む際の喉首に位置している。
それゆえ力攻めをさけ、恭順させて身方に引き入れたいと考えた義元は、元康に調略を命じた。
元康は母の伝を頼って信元と連絡を取り、交渉を始めることに成功したが、出陣間近になっても和議を結ぶことができずにいたのだった。
このままでは今川義元が業を煮やし、水野を攻め滅ぼしてから尾張に攻め込むと言い出しかねない。
そうなったなら元康が先陣を命じられるのは必定で、母の実家と刃を交えることになる。
(それだけは、何としてでも避けなければ)
元康は背中を焼かれるような焦燥にかられて交渉をつづけたが、互いの言い分には大きなへだたりがあった。
義元は恭順の証として刈谷城を差し出すように求めたが、信元が応じないので交渉は暗礁に乗り上げたのである。
打つ手を失った元康は、於大の方に文を書くことにした。
この窮状を訴えて信元を説得してもらおうと考えたのだが、今は他家に嫁いでいる母を頼るのは気が引ける。
(こんな頼みごとをして、ご迷惑にならないだろうか)
そんなためらいが、しつこい汚れのように胸にへばりついていた。
元康は時間をかけて墨をすり終え、入念に筆をひたしたが、いつまでたっても書き出しの文章が浮かばない。
真っ白な料紙が威圧するように迫ってくる。
ひるむ自分に腹を立て、
「一筆啓上申し候。母上さまには大過なくお過ごしのことと、お慶び申し上げ候」
斬りつけるように筆を走らせたが、気持ちの整理がついていないので、先の言葉がつづかない。
迷ったまま宙に止めた筆先から墨がしたたり、波紋を描くようにしみが広がった。
「あっ」
元康は思わず声を上げ、苛立ちのあまり料紙をくしゃくしゃに握りつぶした。
庭ではさっきからうるさいほど蛙が鳴いている。
ぽつりぽつりと落ちてきた雨はやがて本降りになり、板屋根を叩くあわただしい音が頭上をおおった。
元康は明かり障子を開けてみた。
糸を引くような驟雨の向こうに、紫陽花が花をつけている。薄紫のみずみずしい色にしばらく目を止め、大きく呼吸を吐いて筆を取り直した。
「殿、奥方さまがお見えでございます」
近習の声とともに襖が開き、瀬名の方(後の築山殿)が入ってきた。
三年前にめとった今川義元の姪である。
去年長子竹千代(後の信康)を産み、二人目の出産をひかえている。丸くせり出したおなかを、大儀そうに両手で抱えていた。
「元康さま、御意を得たいことがございます」
「見ての通り忙しい。大事な書状をしたためているところだ」
「外出するので乗物を回すように申し付けたところ、酒井忠次に拒まれました。元康さまがお命じになったことですか」
瀬名が居丈高に迫った。
気が強く身勝手な上に、義元の姪だという矜持がある。感情が高ぶると、元康を見下した態度を取ることも多かった。

「忠次には乗物や馬、人の出入りを取り締まるように命じている。だが理由もなく拒んだりはしないはずだ」
「実家に行くので乗物が必要だと申しました。ところが殿のお許しがなければ、出すことはできないと言い張るのです。そのような指示をなされたのですか」
「もうすぐ戦が始まる。屋敷とはいえ陣中も同じだ」
だから出入りを制限するのは当たり前だと、元康は角の立たない言い回しをした。
「はっきりおっしゃって下さい。お申し付けになられたのですか」
「ああ、言った」
「ならば外出を許すという書状をお書き下さい。忠次にそれを見せて乗物を出させます」
「俺が出陣している間、ここにいて留守を守ってもらいたい。それが奥方の務めだと、前にも言ったではないか」
「常の時ならそうでしょう。しかし今日明日にも、児が生まれるかもしれないのですよ。実家に帰していただくのは、当たり前ではありませんか」
「乳母のお登志がいるだろう。侍医の源庵にも、何かあったらすぐに駆けつけるように頼んである」
だから心配はないはずだと、元康は苛立ちをおさえてなだめようとした。
駿府に来て以来、人質の境遇に耐えながら、他の武将たちからあなどられないように気を張り詰めてきた。
大事な出陣の前に妻を実家に帰すようなことをしては、これまでの努力が水の泡になりかねなかった。
「何かあってからでは取り返しがつきません。そんなことにならないように、母の側にもどらせてほしいとお願いしているのです」
「ならば義母上に、この屋敷に来てもらえばいいではないか」
「それは無理でございます」
「なぜだ」
「太守さまがご出陣の間、父は今川館の留守役をおおせつかっております。それゆえ母は、屋敷を離れることができないのです」
瀬名の父は今川家の重臣、関口刑部少輔義広である。
義広は義元が留守の間、嫡男氏真を補佐して駿府の守備にあたることになっていた。
「関口どのの手勢は多い。だが俺が出陣している間、この館には五十人ほどしか残してゆくことができぬ。そなたの供にまで人数を割く余裕はないのだ」
「それなら父上から人数をお借りになったらいかがですか。わたくしからお願い申し上げてもいいのですよ」
「そんな不様なことができるか。万一の時に、皆のあざけりを受けるだけだ」
「万一とはどういうことです。太守さまが織田に負けるとでもお思いですか」
瀬名が言葉尻をとらえて言いつのった。
「そんなことは申しておらぬ。出陣中は何が起こるか分からぬゆえ、用心に用心を重ねなければならぬという意味だ」
「ここは駿府です。今川家の都ですよ。織田ごときとの戦で、危ないことが起こるはずがないではありませんか」
「そなたは信長どのを知っているか」
元康は腹にすえかねて反撃に出た。
「いいえ、存じません」
「俺は知っている。織田家の人質になっていた頃、しょっちゅう顔を合わせていた。恐ろしいほど頭のきれるお方だ」
「しかし手勢は三千にも満たないと聞きました。そんな相手に」
「戦の勝敗は軍勢の数で決まるものではない。それに敵は織田ばかりとは限らぬ。太守さまが出陣しておられる間に、甲斐の武田や相模の北条が盟約を破って攻め込んでくるかもしれぬ」
「まあ、まるで今川が攻められるのを待っておられるような口ぶりですね」
「たわけたことを申すな。何が起こっても対処できるように、万全の用意をしておけと言っておるのだ」
「おおせは良く分かりました。それでも竹千代を連れて実家に帰らせていただきます。丈夫な稚児を産むのが、女子の第一の務めですから」
瀬名は悪しからずと言わんばかりに席を立ち、肩をそびやかして去っていった。
(たわけが。勝手にしろ)
元康は後ろ姿をにらみつけ、言えない言葉を叩きつけた。
その時、小姓の松平源七郎(後の康忠)がずぶ濡れになって庭に駆け込んできた。
「と、殿。一大事でございます」
「あわてるな。何事だ」
「おばばさまが、源応院さまがご他界なされました」
「まさか……。昨日お目にかかったばかりだぞ」
「ご、ご生害なされたのでございます」
「そんな、馬鹿な」
元康は筆を取り落とし、裸足のまま表に飛び出した。
「殿、お履物を」
源七郎が草履を差し出したが、ふり向きもせずに雨の中を走りつづけた。
◇ ◇ ◇