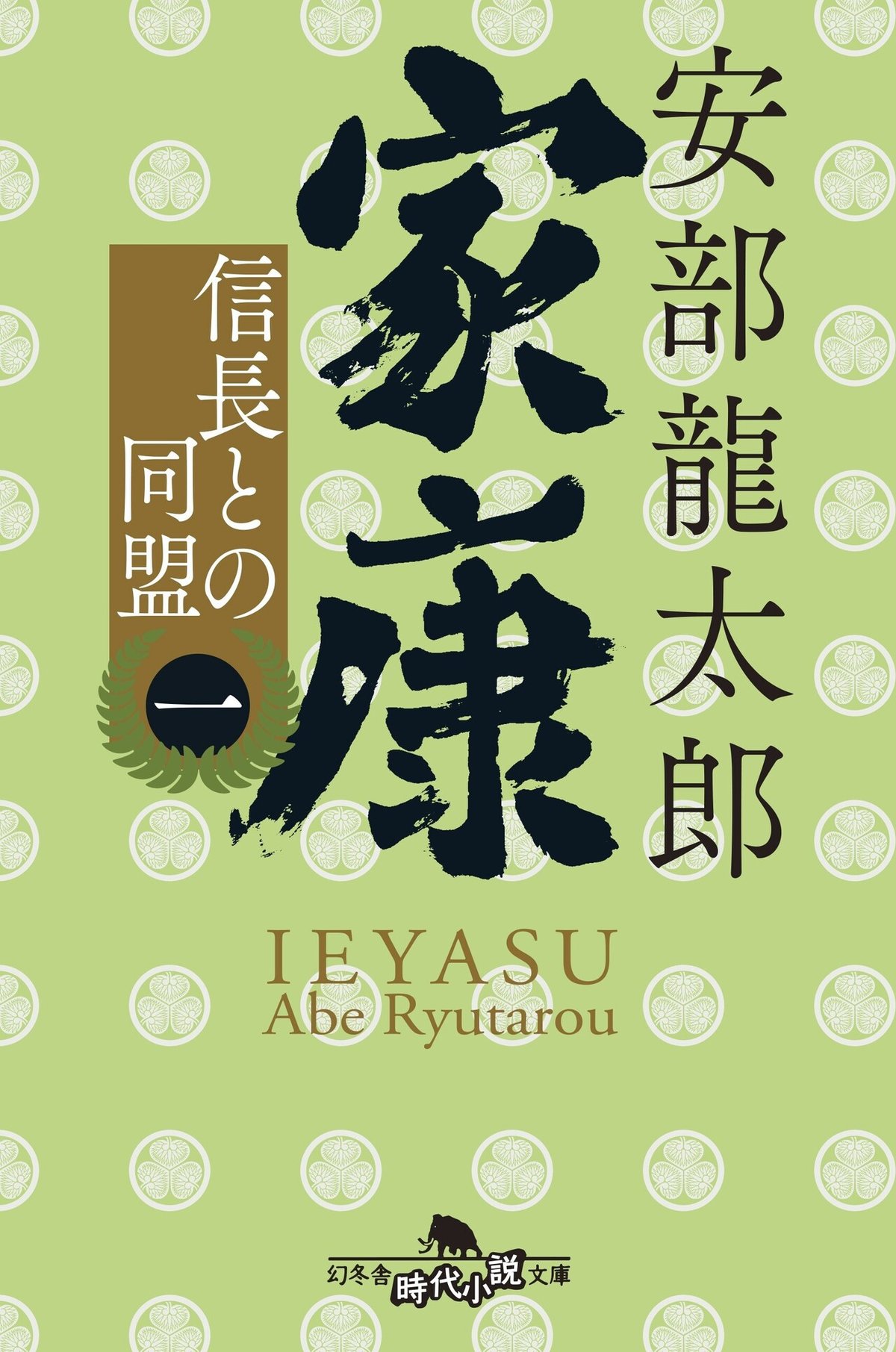重臣たちを集めて…戦国最後の覇者を描き切った「大河歴史小説」 #4 家康(一)信長との同盟
桶狭間の敗戦を機に、松平元康(のちの家康)は葛藤の末、信長と同盟を結ぶ。単なる領地争いの時代が終わったことを知った元康は、三河一国を領し、欣求浄土の理想を掲げ、平安の世を目指すが……。信長でも秀吉でもなく、なぜ家康が戦国最後の覇者となれたのか? その真実に迫った、安部龍太郎さんの大河歴史小説『家康』(全6巻)。その記念すべき幕開けとなる『家康(一) 信長との同盟』のためし読みをお楽しみください。
* * *
急を聞いて駆けつけたのは、平岩親吉、鳥居元忠、石川数正の三人である。
親吉は元康と同い年、元忠は三つ年上、数正は九つ年上。いずれも元康が駿府に来た時から仕え、手足となって働いている。それぞれ個性も持ち味もちがうが、頼り甲斐のある股肱の臣だった。

「殿はこのたび、今川公の馬廻り衆に任じられた」
忠次が元康から聞いたばかりのいきさつを語った。
「三河、遠江の有力武将から送られた人質を預かる難しい役目じゃ。軍勢も二千ちかくになるゆえ、早急に陣立てをしなければならぬ」
「今川公が人質衆を連れて出陣なされるのは、裏切りを防ぐためでございましょうか」
親吉が遠慮なくたずねた。
「さよう。岡部どのは鳴海城、鵜殿氏は大高城を守っておられる。万が一にも敵方に通じることがないようにとの用心であろう」
「四万もの大軍を擁しながら、ずいぶん胆の細いことをなされますな」
「それだけ慎重になっておられるのじゃ。尾張を平定したなら人質を返すと言えば、諸将の士気も高まるであろう」
「ひとつ、おたずねしたい」
元忠が割って入った。
「何かな」
「我らは岡崎で三河衆と合流した後、大高城に入るように命じられており申す。それが変わったということでござろうか」
「殿、それはいかがでございましょうか」
忠次は返答に困り、元康に話を預けた。
「変わってはおるまい。今川公は東海道を西上する時に勇姿を見せよとおおせられた。馬廻り衆をつとめるのは行軍中だけで、岡崎か池鯉鮒に着いたなら大高城行きを命じられるはずじゃ」
元康はそう察していた。
出陣前には、敵に手の内を悟られないように細心の注意を払うのが大将の常である。中でも義元は異常なばかりに用心深い。
一門の側近にしか本心を明かさないので、表情の変化やちょっとした仕草から考えを読み取らなければならなかった。
「それでは預かった人質衆はどうするのでございますか」
元忠がへの字の眉を吊り上げた。
大きな目に強い意志をみなぎらせた、忠義一徹の男だった。
「おそらく池鯉鮒城に預けることになろう。そこから三河勢をひきいて大高城へ向かうことになる」
「人質を行軍させるためだけに馬廻り衆に任じられるとは、何とも解せぬやり方でござるな」
「それは計略あってのことでしょうな」
石川数正がそんなことも分からぬかと言いたげに苦笑した。
眉間が広く鼻が低い間伸びした顔立ちだが、冷静な判断力と頭の切れは家臣の中で随一だった。
「どのような計略でござろうか」
元忠が嚙みつくようにたずねた。
「殿が馬廻り衆として行軍なされば、誰もが今川家の重臣になられたと受け取るであろう。つまり義元公は、この戦が終わっても殿に三河を返すつもりはないと、家臣や領民に示そうとしておられるのじゃ」
「なるほど。わが一門だとおおせられたのは、そのような意味であったか」
元康は初めてそのことに思い当たり、数正の洞察力に感心した。
「問題は岡崎城に入る時でございましょう。殿が赤鳥の旗をかかげておられるのを見たなら、お帰りを待ちわびている家臣や領民が力を落とすにちがいありません」
「しかし馬廻り衆からはずしてくれとは言えまい。そんなことをすればあらぬ疑いをかけられ、ますます危ない持ち場にやられるばかりじゃ」
先走ってうかつなことを言うなと、忠次が釘を刺した。
それではどうするかとそれぞれが思うところを述べたが、名案は浮かばなかった。義元の策は巧妙で、逃れる道はすべて封じられていた。
「出陣は明日の卯の刻(午前六時)だ。忠次と元忠は本隊、親吉と数正は人質衆の指揮をとってくれ」
評定に入る前から、元康はそう決めていた。
「殿、それがしは」
何の役だろうかと源七郎がたずねた。
「お前はこの館に残り、留守役をつとめてくれ」
「そんな馬鹿な。留守役はご老臣のお役目ではありませんか」
「瀬名の出産が迫っておる。しかし出陣中ゆえ実家に帰してやることができぬ。そこで碓井どのに、この館に来ていただくことにした」
瀬名は実家に帰りたがっていたが、源応院が急逝したので断念せざるを得なくなった。
そこで元康の叔母で、源七郎の母である碓井に来てもらい、瀬名の世話をしてもらうことにしたのだった。
「それは母から聞いております。しかし、私がここにいる必要があるのでしょうか」
「碓井どのと瀬名の間を取り持てるのはお前しかいない。それゆえこうして命じておるのだ」
「殿、情けのうございます」
源七郎は膝頭を握りしめ、うつむいて大粒の涙をこぼした。
「小姓として仕えさせていただいた時、常に側にいて生死を共にせよとお命じになりました。そのお言葉を励みに、今日まで身命を賭してお仕えして参りました。それなのに、かような大事の戦にお供をさせていただけないとは……」
嗚咽に喉をふさがれ、後は言葉にならなかった。
その真心に打たれ、誰もがしんみりと黙り込んだ。
忠次は何とかしてほしいと言いたげに元康を見やり、元忠は目を赤くしてもらい泣きしている。

その時、瀬名に案内されて関口義広と北の方がやってきた。
「殿、父上と母上がお出で下されました」
瀬名が嬉しさを押し隠して告げた。
元康はあわてて席を空け、重臣たちと共に義広を迎える姿勢を取った。
「お気遣いは無用でござる。今日は嬉しい知らせをいただき、矢も盾もたまらず推参いたし申した」
従者に酒樽をはこばせ、馬廻り衆への就任と赤鳥の旗をさずけられた祝いを述べた。
「これで貴殿も一門の重臣となられた。大事の戦を前に、これほど目出度いことはない」
「思いがけず過分のお計らいをいただきました。これもお義父上はじめ、皆様方のお引き立てのお陰でございます」
「謙遜なさらずとも良い。すべて貴殿のお人柄と一途なご奉公がもたらしたものじゃ。胸を張って赤鳥の旗をかかげられよ」
「かたじけのうございます。御旗の栄誉を汚さぬように、力を尽くす所存でございます」
元康はそつなく応じながら、義広は今川義元に命じられてこちらの真意をさぐりに来たのではないかと思った。
つい人の心の裏を読もうとするのは、長年の人質暮らしの間に身につけた護身術である。
それを悟られまいと角張った顔に人の良さげな笑みを浮かべるのも、いつの間にか習い性になっていた。
「このたびは瀬名がわがままを言ってご迷惑をおかけ申した。初めてさずかった娘ゆえ、甘やかして育てたのが良くなかったのじゃ」
「とんでもないことでございます。本来ならご実家にもどして出産にそなえさせるべきと存じますが、祖母があのようなことになりましたので、申し訳ないことでございます」
「そうよのう。源応院どのは早まったことをなされた。殿が寛容な措置を取って下されたゆえ、大事には至らなかったが……」
義広は何かを言いたそうだったが、場所柄をわきまえて口にはしなかった。
(やはり、そうか)
義元は源応院に腹を立てていたのだ。
だが怒りをあらわにして元康を窮地に追い込むより、貸しを作って働かせたほうが得策だと判断したようだった。
「ところで祝いのついでに、ひとつ頼みたいことがござってな」
「どのような、ことでございましょうか」
「それはお前から申し上げよ。自分のことだからな」
義広は瀬名を見やって申し付けた。
「殿がご出陣の間、母上が屋敷に来て下さるというのです。よろしゅうございますか?」
「それは願ってもないことだが、ご迷惑ではないでしょうか」
「迷惑どころか、北の方もそうしたいと言い張りおってな。お許しいただければ有り難い」
「かたじけのうございます。そうしていただけば、それがしも心置きなく出陣できまする」
「ついては北の方の侍女や供侍をこちらに詰めさせていただくことになるが、よろしゅうござるな」
「お人数は、いかほど」
「さて。聞いておらぬが、奥や、何人ばかり連れて来るつもりじゃ」
「侍女は二十人、供侍は百人ばかりになりましょう」
北の方は今川義元の妹である。それくらいは当然だと思っているようだが、元康にとってはとんでもないことである。
留守の間に百人もの他家の侍に入られては、屋敷を乗っ取られたも同じだった。
「このように申しておるが、元康どの、いかがでござろうか」
「この屋敷は手狭ゆえ、それほど大人数は入れません。北の方さまが窮屈な思いをなされるのではないでしょうか」
「なあに。これだけの広さがあれば充分でござるよ。出陣中のことゆえ、侍どもは馬屋にでも寝かせれば良いのじゃ」
義広は事もなげに言い切り、それではこれでと席を立った。
残された元康主従は、しばらく口をつぐんで仏頂面を見合わせていた。
「殿、良うございましたな」
酒井忠次が気遣って声をかけた。
「何が」
元康は牛のような目でジロリとにらんだ。
「北の方さまに来ていただけば、奥方さまも安心でございましょう」
「何をおおせられる。他家の兵に屋敷を守ってもらうようでは、三河武士の面目が立ち申さぬ」
鳥居元忠が顔を赤くして言いつのった。
「さよう。これでは妻子を人質に取られたようなものじゃ。あるいは義広どのは」
義元公に命じられたのかもしれぬと、石川数正がうがった見方をした。
「あの……、北の方さまが参られるなら、母が留守役をつとめることはないのではございませんか」
源七郎が遠慮がちにたずねた。
「むろん来ていただくには及ばぬ。叔母上にそう伝えてくれ」
「それではそれがしも、殿のお供をさせていただけるのですね」
念を押して承諾を得ると、源七郎は喜び勇んで碓井のもとに知らせに行った。
◇ ◇ ◇