
「ガオー」 初めての言葉
「ガオー」最初の言葉
今中学生の娘きみどりは、結構おしゃべりです。お年頃なので、お友達といるとそれはそれはうるさいのですが。
そんなきみどりは、実は発語が遅れていました。2歳になっても話し始めず、どうしたものかと考えていました。
きみどりは、何かとって欲しいものがあると「コ!コ!」ととって欲しいものを指差していました。それが伝わるまで、何度でも「コ!コ!」と言い続けていました。
このままではまずいなと思いました。それできみどりが2歳6ヶ月の時に、言語訓練施設が併設してある病院で診察を受けました。
最初に指摘されたのは、きみどりの口腔機能には問題がないだろうということでした。口蓋裂などもなく、歯や舌、喉の奥の方や声帯等にも問題はなさそうだとうことでした。
次に、聞こえの方も問題がないだろうということでした。例えば滲出性中耳炎の場合、鼓膜の内側に液体があり、そのために聞こえが極端に悪くなるということがあります。
きみどりは2歳で言葉も話せないので、それ以上詳しいことは調べられませんでした。
次は言語聴覚士による言葉のアセスメントでした。これは別日に行われました。その結果、きみどりは言葉の理解はできているが、発語の方が0歳台ということでした。
結果は予想していた通り。予想が外れて欲しいと思っていましたが・・・
言語訓練に通うことが決まり、担当の言語聴覚士も決まり、3歳前から言語訓練がスタートしました。
今の診断基準によると、『口腔機能発達不全症』と診断されていたと思います。
詳しくはこちらをご覧ください。
公益財団法人 8020推進財団 https://www.8020zaidan.or.jp/hattatsuhuzen/
それで思い出されるのは、黄緑はよだれが多かったことです。そのため、スタイはしていましたが、いつもびしゃびしゃになっていました。また、噛むことも苦手でした。右の奥歯で噛み始めると右の歯で噛み続けて、左の奥歯で噛み始めると左の奥歯だけで噛んでいました。舌を使って口の中の食べ物を左右に移動させることができなかったのだろうと思います。それに加えて、きみどりは、舌をしょっちゅう出していました。
きみどりは、口の周りの筋肉を連動させて動かすことが苦手だったようです。声を出すこと、声の発声を変えるために、口の周りのさまざまな筋肉を連動させることが必要です。
なおかつ、口の周りの筋肉は自分では目に見て確かめることができません。だからコントロールするために、自分の筋肉や声の音などからのフィードバックを使って修正していくしか手がありません。
また、脳の中では、耳から聞こえてきた「音」を聞き取り、それに合わせた筋肉の動きに変換しなくてはなりません。その返還された指令を筋肉に伝えて、筋肉を連動させることで、さまざまな声をつくりだすことができます。声を出すことって、我々は簡単に行なっていますが、乳幼児にはとても難しいことなのです。また、発達障害や聴覚障害、脳性麻痺などの障害がある場合も同様にとても難しい作業となります。
我々大人も、脳梗塞や脳出血、脳腫瘍やパーキンソン病その他の病気になったり、交通事故や、頭を強く打つなどの怪我により、言葉の聞こえや発語が難しくなったりします。そう言った意味でも、バリアフリーが浸透した社会は、誰もが安心して暮らせる社会と言えると思います。
話は随分とずれてしまいましたが、本題に戻りましょう。
きみどりが2歳8ヶ月の頃、冬の動物園に家族で遊びに行きました。妻は妊娠中で無理はできないので、お弁当を食べた後に、僕ときいろときみどりでライオンを見に行きました。お弁当を食べたベンチから少し登った奥まったところにライオンがいました。初めてライオンを見たきみどりはとっても興奮していました。そしてとても嬉しそうでした。きみどりは、興奮した様子で坂を降りて行きました。
きみどりは、妻のそばに行きました。それからきみどりは、両手を頭の横に持って行き指を折り曲げて、「ガオー!」とライオンの真似をしながら叫びました。
妻も僕もびっくり!!
妻は喜んで「きみどりちゃん、ガオーがいたの。良かったね。」
「ガオー!」と言った意味が通じたと思ったのか、きみどりは、とても嬉そうな表情をしながら、何度も「ガオー!」と言っていました。
僕たち夫婦にとっても、とても印象に残る、きみどりの感動を伝えるための「ガオー!」でした。
この話もときどき、食卓に上ります。
きみどりに関するお話はまだまだありますが、今日はここまで。
今中学生の娘きみどりは、結構おしゃべりです。お年頃なので、お友達といるとそれはそれはうるさいのですが。
そんなきみどりは、実は発語が遅れていました。2歳になっても話し始めず、どうしたものかと考えていました。
きみどりは、何かとって欲しいものがあると「コ!コ!」ととって欲しいものを指差していました。それが伝わるまで、何度でも「コ!コ!」と言い続けていました。
このままではまずいなと思いました。それできみどりが2歳6ヶ月の時に、言語訓練施設が併設してある病院で診察を受けました。

最初に指摘されたのは、きみどりの口腔機能には問題がないだろうということでした。口蓋裂などもなく、歯や舌、喉の奥の方や声帯等にも問題はなさそうだとうことでした。
次に、聞こえの方も問題がないだろうということでした。例えば滲出性中耳炎の場合、鼓膜の内側に液体があり、そのために聞こえが極端に悪くなるということがあります。
きみどりは2歳で言葉も話せないので、それ以上詳しいことは調べられませんでした。
次は言語聴覚士による言葉のアセスメントでした。これは別日に行われました。その結果、きみどりは言葉の理解はできているが、発語の方が0歳台ということでした。
結果は予想していた通り。予想が外れて欲しいと思っていましたが・・・
言語訓練に通うことが決まり、担当の言語聴覚士も決まり、3歳前から言語訓練がスタートしました。

今の診断基準によると、『口腔機能発達不全症』と診断されていたと思います。
詳しくはこちらをご覧ください。
公益財団法人 8020推進財団 https://www.8020zaidan.or.jp/hattatsuhuzen/
それで思い出されるのは、黄緑はよだれが多かったことです。そのため、スタイはしていましたが、いつもびしゃびしゃになっていました。また、噛むことも苦手でした。右の奥歯で噛み始めると右の歯で噛み続けて、左の奥歯で噛み始めると左の奥歯だけで噛んでいました。舌を使って口の中の食べ物を左右に移動させることができなかったのだろうと思います。それに加えて、きみどりは、舌をしょっちゅう出していました。

きみどりは、口の周りの筋肉を連動させて動かすことが苦手だったようです。声を出すこと、声の発声を変えるために、口の周りのさまざまな筋肉を連動させることが必要です。
なおかつ、口の周りの筋肉は自分では目に見て確かめることができません。だからコントロールするために、自分の筋肉や声の音などからのフィードバックを使って修正していくしか手がありません。
また、脳の中では、耳から聞こえてきた「音」を聞き取り、それに合わせた筋肉の動きに変換しなくてはなりません。その返還された指令を筋肉に伝えて、筋肉を連動させることで、さまざまな声をつくりだすことができます。声を出すことって、我々は簡単に行なっていますが、乳幼児にはとても難しいことなのです。また、発達障害や聴覚障害、脳性麻痺などの障害がある場合も同様にとても難しい作業となります。
我々大人も、脳梗塞や脳出血、脳腫瘍やパーキンソン病その他の病気になったり、交通事故や、頭を強く打つなどの怪我により、言葉の聞こえや発語が難しくなったりします。そう言った意味でも、バリアフリーが浸透した社会は、誰もが安心して暮らせる社会と言えると思います。
話は随分とずれてしまいましたが、本題に戻りましょう。

きみどりが2歳8ヶ月の頃、冬の動物園に家族で遊びに行きました。妻は妊娠中で無理はできないので、お弁当を食べた後に、僕ときいろときみどりでライオンを見に行きました。お弁当を食べたベンチから少し登った奥まったところにライオンがいました。初めてライオンを見たきみどりはとっても興奮していました。そしてとても嬉しそうでした。きみどりは、興奮した様子で坂を降りて行きました。
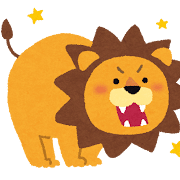
きみどりは、妻のそばに行きました。それからきみどりは、両手を頭の横に持って行き指を折り曲げて、「ガオー!」とライオンの真似をしながら叫びました。
妻も僕もびっくり!!
妻は喜んで「きみどりちゃん、ガオーがいたの。良かったね。」
「ガオー!」と言った意味が通じたと思ったのか、きみどりは、とても嬉そうな表情をしながら、何度も「ガオー!」と言っていました。
僕たち夫婦にとっても、とても印象に残る、きみどりの感動を伝えるための「ガオー!」でした。
この話もときどき、食卓に上ります。
きみどりに関するお話はまだまだありますが、今日はここまで。
