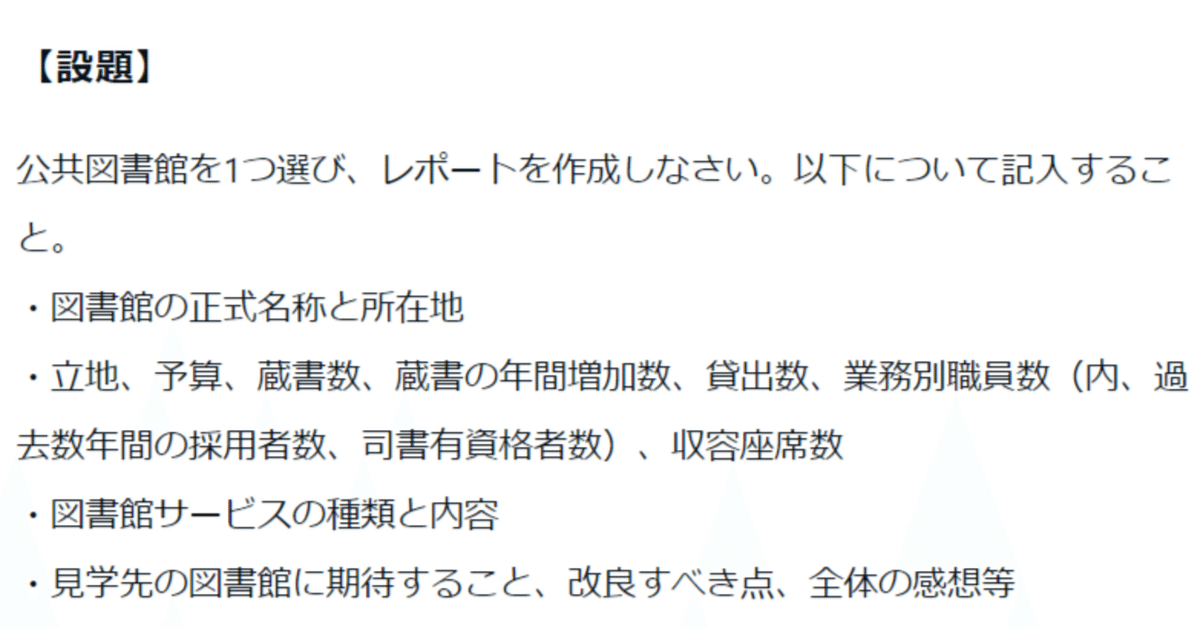
近畿大学 図書館司書 『図書館概論』合格レポート 2024年4月入学
【設題】
公共図書館を1つ選び、レポートを作成しなさい。以下について記入すること。
・図書館の正式名称と所在地
・立地、予算、蔵書数、蔵書の年間増加数、貸出数、業務別職員数(内、過去数年間の採用者数、司書有資格者数)、収容座席数
・図書館サービスの種類と内容
・見学先の図書館に期待すること、改良すべき点、全体の感想等
【レポート】(2,078字)
本レポートでは、XX市で最も蔵書数と利用者の多い中央図書館について論じる。
1.調査対象:XX市立中央図書館
所在地:XXX-XXXX XX県XX市~~
2.立地および数値データ
立地はXX市~に位置し、鉄道および市営バスでアクセス可能である。建物は鉄骨鉄筋コンクリート造で地上X階、延床面積~~㎡である。
XX市の令和5年度図書館運営予算X億X万X千円のうち、中央図書館の運営費がX億X万千円,中央図書館利用者サービス事業費がX億X万X千円と図書館運営予算のうち、中央図書館関連で約XX%占めている。令和4年度の蔵書数は図書がX万X冊、定期刊行物がX種である。令和3年度はX万X冊、令和2年度はX万X冊となっており、3年間でX万冊以上増加している。個人貸出数について館内用の個人貸出はX万X冊、業務別職員数はX人でそのうち司書はX人である。収容座席数は総数X席のうち児童席数がX席、持込パソコン使用可能席はX席である
3.図書館サービスの種類と内容
ここでは、インドの図書館学者ランガナタンによる『図書館学の五法則』の切り口から中央図書館のサービスと内容を見ていきたい。
第1法則において、立地は市内の中心部に位置し、公共交通機関でのアクセスが良く、あらゆる市民に利用しやすい。開館時間は火曜から金曜がX時X分からX時X分、土日祝および月曜はX時X分からX時、火曜から金曜はX時X分からX時X分まで開館している。閲覧席も各フロアに十分に確保されている。図書司書は職員のうち過半数が司書であることから専門的知識をもつスタッフによる運営がなされている
第2法則では、その法則通り中央図書館はあらゆる人が利用可能である。XX市在住または、通勤通学している場合は図書館カードの登録ができ、貸出や予約が図書館及びインターネット上で無料で利用可能である。また、XX市近隣のX市やX市等の市民もXX市立図書館で本を借りることができる。また、心身の障害よる来館が困難な利用者にむけて、図書や雑誌の配送貸出も行っている。
第3法則の通り、どんな図書も利用できる状態になっている。開架性の採用やサービスとして移動図書館の定期的な巡回、1人2点まで14日間借りることのできる電子書籍サービス、点字図書や録音図書などの貸出も行っている
第4法則の図書館利用者の時間節約では、フロアごとに分類された書架配置と入口やエレベーター、階段、フロア内等あらゆる場所への案内設置、HP記載、館内やオンライン上での蔵書検索、レファレンスサービスなど充実した環境が整えられている。
第5法則において、中央図書館も日々サービスの向上を継続している。蔵書数の増加、貸出冊数と期間の拡大により、前年度からX万冊の貸出増加、郵送による図書館カードの登録手続、館内で統一した展示を実施して社会科学や自然科学等の各フロアの分野からの視点での図書紹介、電子書籍サービス開始、館内初会話ができる交流と学びのフロアリニューアルなどの工夫が凝らされている。
4.意見及び感想
私は圧倒的な蔵書数と座席数、アクセスのしやすさから中央図書館をよく利用する。しかし、図書館はあらゆる人に向けて開放しているが、子どもや働く世代の利用者が少なく、利用者層に偏りがあるのではないかと感じる。
XX市の年少人口割合は令和3年1月1日時点でXX.X%だが、図書館の登録者で0~15歳の割合は約X.X%と低い。子どもの図書館の利用については親の影響が大きい。図書館に頻繁に行く親とそうでない親とでは本に触れる機会も大きく変わる。そのため、提案として①図書館訪問機会の促進と②電子書籍サービス拡充を挙げたい。中央図書館の隣にはXXとXXがある。その利用者には中央図書館内のカフェサービス券の配布で提案①を実現させる。提案②では、スマートフォンやタブレット端末を使う子どもが多いことから、子どものみ電子書籍サービス貸出冊数を現在の2点から増やし、複数人が同時に借りられるようにすることで子どもの利用を延ばしたい。
社会人の利用については、朝の営業時間拡充を提案する。朝は午前X時から営業しているが、朝X時前後に始業する会社では、出勤前に図書館に立ち寄ることは難しい。一方で夜は午後X時まで営業している点や営業時間外でも返却ボックスで返却できる。長期休みがある児童・学生や平日も利用可能な高齢者に比べて利用しすい日時が限られている社会人として、朝の営業時間拡充は社会人利用の促進が期待できる。しかし、現時点では予定はないとのことである。
いつも利用している中央図書館について、今回のレポートをきっかけにより深くサービスや取組について深く知ることができた。引き続き、図書館司書の勉強や日々の利用を通して、探索および周りの人たちへ図書館の魅力を広めていきたい。
【参考文献】
XX市 各種計画・報告書など
日本図書館協会『日本の図書館:統計と名簿2022』日本図書館協会2023.3
蔵書検索URL
【講評】
提出お疲れ様です。
設題のポイントをしっかり押さえ、大変よくまとめられています。
詳しく調査したことが内容から伝わってきます。図書館学の五法則を基づいての解釈は素晴らしいです。ちなみに近くの新しいXX県立図書館の最上階は第五法則のまさに最新トレンドと思います。是非見て使ってください。
調査先図書館への所見も非常に首肯できるものです。
この調子で引き続き頑張ってください。
※気になる点
・ウェブサイトを閲覧した日は必ず書きましょう。ウェブサイトはすぐ変わるので、見た日を明記するのが特に大事です。
【感想】
筆者の住んでいる自治体では、市の図書館の詳細データがまとめられているものがあったため、とても書きやすかったです。
司書の勉強し始めたときにレポートを書いたのでランガナタンの図書館の五法則を書きたくなっていたのを覚えています笑
レポートも4日で返却され、講評から応援の言葉をいただき、モチベーションにつながりました
【返却日数】
4日 4/1提出・4/5合格
※注意
レポートの丸写しはしないようにお願いいたします。
皆さんの参考になれば幸いです。
