
ランダムスタート法の再評価
通常、体外受精などを行う場合には、月経周期に合わせて、月経開始3日目から治療を始める、などのプロトコルが一般的です。
現実的に保険診療などでも、
「月経が来たら予約取ってください」
と言われたことがある方も多いのではないでしょうか。
妊孕性温存を実施する際には、月経周期に合わせた治療をしていると、がん治療までの猶予期間を十分に活用できない場合があります。
こんな時に活用される「卵巣刺激法」が
ランダムスタート法
と呼ばれるもので、月経周期のタイミングを選ばずに、その日から始められるというものだと思ってください。
今回はこの研究についての最新論文を紹介したいと思います。
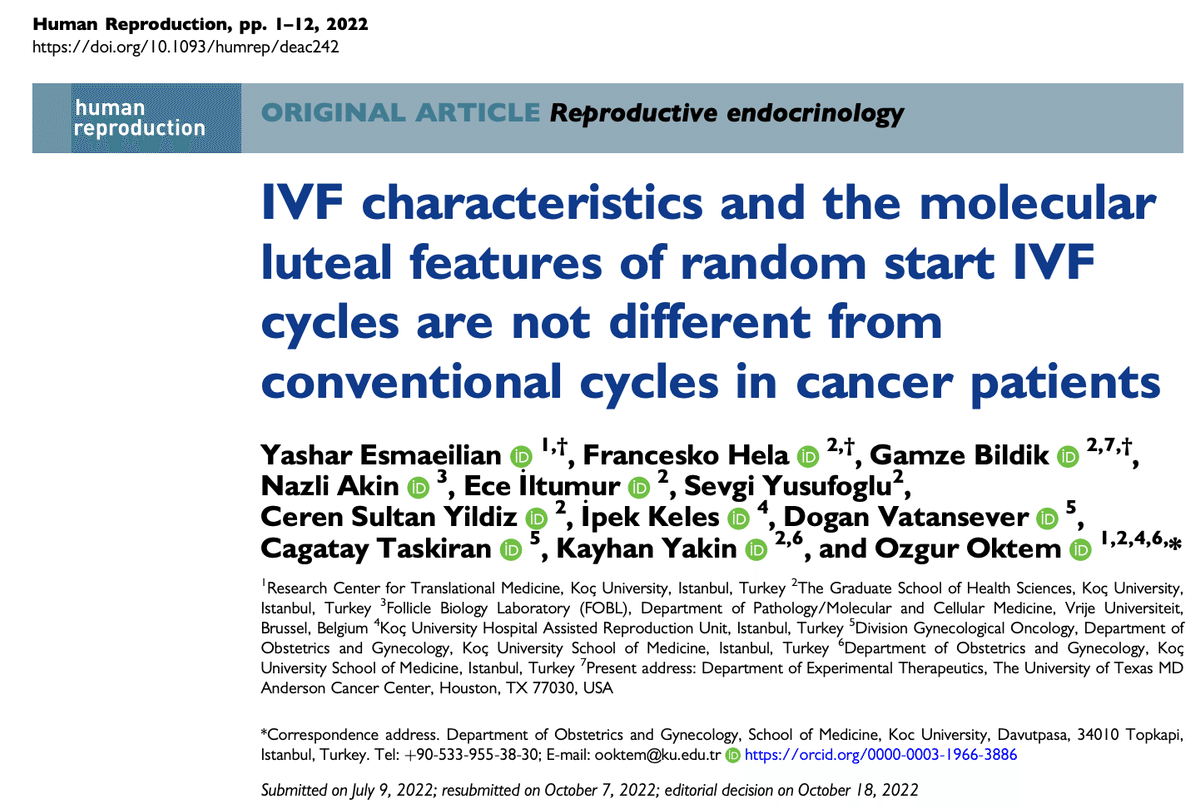
それに加えて、癌の種類が、ホルモン受容体陽性というタイプの方では、
エストロゲンなどのホルモンの上昇を抑えるために、レトロゾールを併用した卵巣刺激を行うのが一般的です。
ランダムスタート法やレトロゾールを併用した卵巣刺激を行った結果、得られる採卵数などは、通常の刺激法と変わらない、ということはこれまで数多く報告されてきました。
具体的には、卵巣刺激と卵母細胞回収の間の時間間隔を効果的に短縮できることがメリットで、これらのサイクルで回収された卵母細胞の数と正倍数体胚発生の能力も従来の刺激プロトコルに匹敵するという報告が多くなされています。
そのため、緊急の癌治療を必要とする女性患者の妊孕性温存のための有効なオプションとして、ランダムスタート法は考えられています。
ですが、通常の場合と比較した遺伝子発現であったり、ホルモンの生成であったりに関する比較検討はこれまでなされてきませんでした。
その比較をしたのが、この研究ということになります。
ランダムスタートといっても、後期の卵胞期なのか、黄体期なのか、ということだけでも違ってくるわけですが、一般的な卵巣刺激法と比較して、ホルモン産生に関する酵素、遺伝子発現の状況をRT-PCRを用いて観察しています。
その結果、
卵胞後期 (LFP) と黄体期 (LP) でランダムに開始される制御された卵巣刺激サイクルは、コレステロールとステロイドホルモンに関与する酵素の発現に関して、卵胞期初期 (EFP) で開始される従来の IVF サイクルと完全に同等であることがわかりました。
生合成経路、ゴナドトロピン受容体の発現、エストラジオール (E 2 ) およびプロゲステロン (P 4 ) の生成に加えて、癌患者におけるゴナドトロピン刺激に対する卵巣応答、卵母細胞の収量、受精率、および胚発生能力の類似性も改めて確認されました。
ということを報告しています。
つまり、これまで見てきた得られた卵子の数などの「結果」だけでなく、それに結びつくまでの、体内に挙動も完全に同じであることが確認された、ということです。
これによって、よりランダムスタート法はがん患者さんはもちろん、多くの方に普及していく可能性があるように思います。
特に、仕事との両立などで悩まれる方もいらっしゃると思いますし、
今すぐ始めたいのに、月経を待たないといけない、というようなストレスも回避できるかもしれません。
もちろん、通常の刺激法を上回る、ということではないので、通常の方法に取って代わるかというとそうではないと思いますが、同じレベルで推奨されて良い卵巣刺激法ではないかと思います。
いいなと思ったら応援しよう!

