
現場実習(事業所実習)に行く前に
はじめに
この記事の対象
この記事は産業医科大学の学生さんを対象に書いていきます。他の大学の医学生・看護学生さんにも参考になると思いますが、関係のないところは読み飛ばしてください。皆さんが少しでも、現場実習を実りのあるものにしていただければ幸いです。
現場実習に行く前に
産業医科大学の学生さんは5年次に1週間(5日間)の産業医学現場実習(以下、現場実習)があります。産業医大の学生は6年間で256時間の産業医学に関するカリキュラムが組まれており、この現場実習も含まれます。多くの学生さんがこの現場実習によって、自身のキャリア選択として、「臨床医になるか」「産業医になるか」を決めようとしているのではないかと思います。しかしながら、この現場実習の受け方(事前準備)によっては、ほとんどキャリア選択の参考にすることができずに、なんとなく産業医というキャリア選択を消してしまっているのではないかと思います。それはとてももったいないことだと思いまして、老婆心ながら、現場実習に行く前にやっておくことの注意点ややっておくとよいことを書いていきたいと思います。 ただし、あくまで個人の意見ですし、知り合い・先輩などにも意見を求めることも併せておすすめしておきます。
注意点
産業保健の時間軸は長い
産業保健活動は時間軸が長いことがほとんどです。季節ものとして、春の健診や秋のストレスチェックがあったり、事業所ごとの繁忙期やイベントがあり、年単位でものごとが進んでいきます。臨床現場でいうところの外科のオペや、救急外来の検査して診断をつけて治療して、といった分単位・時間単位・日単位のスピード感はありません。各事業所ごとにあれやこれやと工夫をこらして産業保健を味わってもらおうと実習を準備してくださっていると思いますが、それでもやはり限界があるんですよね。ながーーーーい時間軸の中のたった5日間であるという理解を持っておくと良いです。
(産業保健の醍醐味として、ダイナミズムというものがあり、組織や企業を動かす、動く瞬間があるということはあるのですが、それは数年かけて、とかじっくり時間をかけた先にあったり、突然動き出すんですよね。それを現場実習で見せるのは超絶ムズイ、というか無理です。)
産業保健は見せにくい
多くの事業所で取り入れてる内容として、労働者との面談があると思います。が、臨床現場のように患者さんがいるわけではなく、面談の(ある意味で)実験台になってくれる方を見つけるのは非常に困難です。病院であっても、喜んで学生さんに情報共有している方ばかりでもないと思いますしね(大学病院が教育機関であるため、患者さんから理解を得やすいとは思います)。一方で、産業保健現場は教育機関ではありませんし、従業員さんもみんながみんな現場実習に理解を示してくれるわけではありません。そして、比較的健康体の労働者の面談は勉強になりにくいので学生さんには見せにくく、逆にシビアな面談には同席させることはできません。また、こちらについても長ーーい時間軸として数ヶ月や1年の経過の中の、たった一回分の面談だったりしますので、その面談の前後の経緯が分からないと、ちんぷんかんになると思います。
産業保健の効果は分かりにくい
産業保健活動の効果はとても分かりにくいです。臨床現場のように、その場で治した、良くした、という分かりやすさはないんですよね。産業保健活動では本人に考えさせたり、伴走するのですが、それは即時的な効果を出せるようなものではないんですよね。効果が分かりにくいからこそ、現場実習の日程の前後になにかがあったか、なにが起きるのか質問したり、想像する力が欠かせません。
産業医科大学のフィロソフィーとして「感謝されない医師」というものがあることは、産業医科大学の学生さんならご存知だと思いますが、産業保健の実践においても、臨床のように感謝されたりすることはないですし、やりがい感がわかりやすく示せるものでもないんです。それは現場実習でもやはりそうなんですよね。
現場実習に行く前に、医学概論のホームページをもう一度覗いてみてもいいかもしれません。改めて読むとマジで沁みますよ(←産業保健変態発言w)。
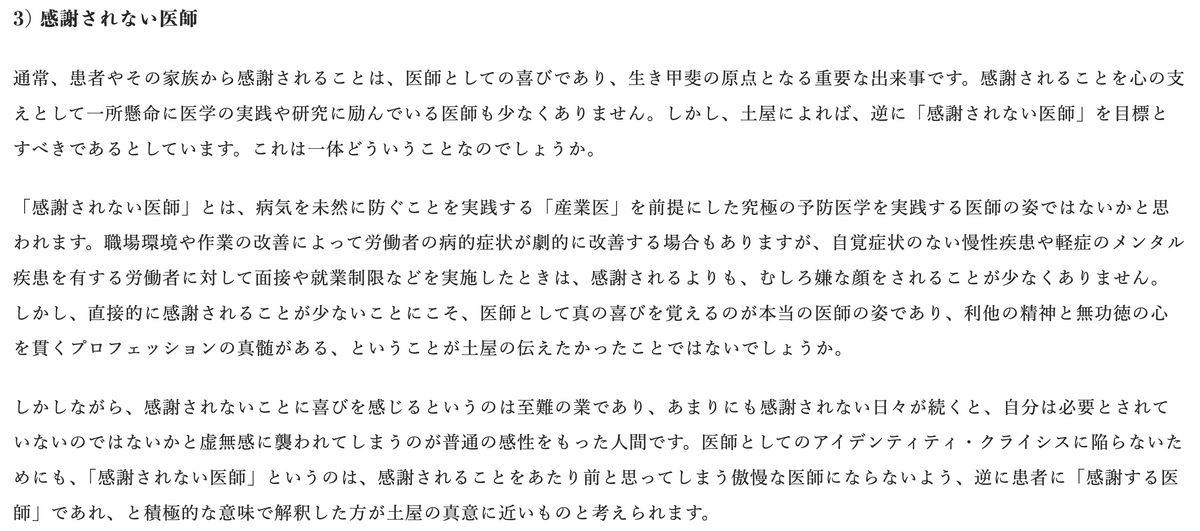
実習を終えても産業医活動をイメージするのはやっぱり無理ゲー
よく「産業医の仕事がイメージできない」という相談を受けます。それはそうですよね、産業医の仕事ぶりを見ることはまずありませんからね。ポリクリで病院を回れば、それぞれの科の医師がどんなことをしているのかがなんとなくわかると思います。一方で、産業医の仕事は地味で地道で泥臭くて時間がかかることの方が多いんですよね。ちょっとした根回しの繰り返しだったり、裏方だったり、脇役だったり、そういう役回りが産業医の仕事なのです。働く人が主役であり、企業の事業活動を後ろから支えるのが産業医なんですよね。働く現場というのは、事故もなく、病気もなく、平和で安全な状態が理想なのです。現場実習の5日間に事故や事件がないことが理想的な状態なのであって、そのために産業医は日々活動しているんです。達人の技ほど簡単そうに見えることがありますが、まさに優秀な産業医ほどなんにもしていないように見えてしまうこともあるのかもしれません。「産業医」って暇そうとかなんにもしていないじゃんって思われる方もいるかもしれませんが、それが実は理想的な状態です。産業医がいなくても平和で安全な状況をつくることが安全衛生活動(産業保健活動)のめざすべき理想の状態なのです。
現場実習を経験したとしても、「産業医活動を完全にイメージできるわけではない」という限界も知っておいていただくといいかなと思います。産業医を目指す方にとっては非常に不安だと思いますが、最低ラインとして、こういう活動をするんだ、くらいの解像度を持つことができればいいのかなと思っています。
産業保健は企業によって全く違う
産業医科大学の医学生さんは、40くらいある(?)現場実習先から選ぶことになり、どこにすればいいのかと悩まれると思います。どこに行けば学べるのか、産業医活動が見れるのか・・・はたまた楽しいのか、遊べるのか、といったお気楽モードの方もいるかもしれませんね。私自身も当時は地元近くで移動が楽しそうだからという理由で実習先を選んだ記憶がありますので、そんなものだと思います。そして、そのような多く現場実習先を選ぶ際には、当たり外れはどうなのか、ということを気にしている学生さんも多いと思いますが、そんな学生さんに伝えたいことは、「産業保健は企業によって全く違う」ということです。臨床現場では標準的な治療法があって、どこもやることは概ね同じです(というか同じことを目指すのが臨床であり、保険診療とも言えます。)。厳密には病院ごとに大きく異なるのでしょうが、ほとんどの学生さんにはそこまで分からないようにも思います。標準治療から大きく外れたことをしているような病院や医師がいれば、それはやべーところ・やべー医師ですよね。一方で、産業保健というのは、企業によってやることがガラリと変わります。業種や企業規模、立地などでも変わりますし、企業と労働衛生機関(健診機関)でもかなり違うことしていますからね。だからこそ産業医学(産業保健)とはなんなのかを知っておくとよいと思います。つまり、産業医学(産業保健)という根っこがあり、その実践の形(=産業保健活動)は企業によってさまざまである、という理解があると良い、ということです。その理解があれば、どの実習先に行っても学びを深めやすいし、そこまで当たり外れは気にならないように思います。というか当たり外れを決めるのは事業所側よりも、学生さん側の知識や姿勢とも言えるかもしれません。
産業医学とは医学、工学、行動科学、心理学などの学際的な科学を基盤とし、人と仕事の適合を目的とした現場で実践される科学である
「産業医学」とは、労働環境や作業条件と、働く人々の健康との関わりを追求する医学です。働く人々が、その生活の中で長い時間をすごすことになる職場。その環境と人々の健康は、切り離せない関係にあります。古くから職場の環境や作業の形態によって、職業病や作業関連疾患など様々な健康問題が発生していました。高度成長期以降も、オフィスの情報化、高齢化、新たな化学物質など、職場には働く人々の健康に関わる環境の変化が生まれています。「産業医学」は、こうした産業活動に関連する健康問題を取り扱う医学の一分野です。疾病の原因探求などの基礎的研究から、働く人々の疾病予防や健康の保持増進などの実践活動まで、幅広い範囲が含まれています。

よりよい実習にするために
産業医の解像度を高めておこう
産業医の解像度を高めるためにいくつかの記事を作成しています。産業医を少しでも考えている人は、産業医の解像度をとことん高めてから現場実習に行くとよいと思います。そこで、解像度を高める方法をいくつか示していきます。受け身の姿勢では、得られるものは半分以下になります。常に求められるのは「積極性」ですので、時間がある限りは手あたり次第読んでみると良いのではないかと思います。
産業医について疑問を整理しておこう
事前の解像度を高めた上で、疑問を整理しておくとよいと思います。現場実習でリアルな産業保健活動を経験できるのだからこそ、そのときに備えて疑問を養い整理していきましょう!(疑問を養うって意味不明ですが)
産業医に関する質問をぶつけよう
前述のとおり、5日間の現場実習で得られる情報は限界があります。だからこそ、自分から進んで質問をぶつけてみてください。以下にいくつかの質問候補をあげておりますが、実際の実習では本当に自分が聞きたいことを聞いてみてくださいね。ぶっちゃけどうなんですか?っていう質問をぶつけなければ現場に行く意味はないですからね。
1. 産業医の役割と業務について
・産業医としての日常業務はどのようなものですか?
・産業医の役割にはどのような責任が含まれますか?
・労働者の健康管理や職場の安全衛生において、産業医の果たす具体的な役割は何ですか?
2. キャリアパスと成長機会
・産業医としてのキャリアパスにはどのような選択肢がありますか?
・臨床との両立はできますか?両立はおすすめですか?
・臨床の専門医をとってから産業医になる道はどうですか?
・産業医としてのキャリアを進める上で、どのようなスキルや資格が重要ですか?
・専門的な研修や継続的な教育の機会はどのように提供されていますか?
3. 仕事のやりがいと挑戦
・産業医として働く中で最もやりがいを感じる瞬間はどのような時ですか?
・産業医としての仕事で直面する主な挑戦や困難は何ですか?
・どのような状況や環境で特にストレスを感じますか?
4. 職場環境と働き方
・産業医の働く環境はどのようなものですか?
・ワークライフバランスをどのように保っていますか?
・産業医としての勤務時間や休日の取り方について教えてください。
5. 具体的なケースや経験
・最近取り組んだ特に印象に残っている事例を教えていただけますか?
・メンタルヘルスに関するケースで、どのような対応をされましたか?
・職場の安全衛生管理において、成功した取り組みを教えてください
6. 産業医の影響力とコミュニケーション
・産業医としての意見や提案が職場全体にどのような影響を与えますか?
・労働者や経営者とのコミュニケーションはどのように行っていますか?
・産業医として効果的なコミュニケーション方法を教えてください。
7. 法令と規制
・労働法規や産業医学に関する法律について、特に重要なものは何ですか?
・法律や規制に準拠するために、どのようなプロセスを踏んでいますか?
・法令遵守に関して特に注意すべき点は何ですか?
8. 未来の展望
・産業医学の分野で今後の展望や期待する変化について教えてください。
・産業医学のどの領域が注目されていますか?
これらの質問をもとに、実習期間中に具体的な情報を収集することで、産業医としてのキャリアをより具体的にイメージし、自分に適したキャリア選択を行うための参考にすることができます。
産業医の見ている景色を知ろう
産業医の見ている景色を知ることも現場実習の意義なのではないかと思います。現場の産業医がなにを考え、どこまでを見ているのか。それは、「上医」の概念を知っておくことが重要だと思っています。「上医」とは、医学概論のホームページには次のように記述されています。
2) 上医を目指す医師
上医という言い方は、西暦454年から473年にかけて書かれました、中国の陳延之の著書『小品方』にある「上医医国、中医医民、下医医病」から来た言葉といわれています。この意味についてはさまざまな解釈がありますが、「上医は国を癒し、中医は人を癒し、下医は病を癒す」というのが一般的な理解です。言い換えると、目前の患者の治療に全力を尽くすのが下医、公衆衛生的予防対策を実践するのが中医、国全体の医療システムにメスを入れてすべての国民が平等な医療の恩恵に授かることができる仕組みをつくるのが上医、という解釈になります。したがって、『小品方』に則して文字通り解釈すれば、上医は政治家や官僚を意味することになります。具体的には、国会議員や医系技官として医療政策や労働衛生政策で活躍する医師が該当します。
しかし、土屋の言うところの「上医」は、治療だけでなく病気が再発しないように予防医学を実践する医師であると同時に、働く人の健康が保持できるように企業上層部に対して組織的な対応が実践できる医師、すなわち企業組織内で医師として有機的に機能する「産業医」を指していることは明らかです。
「産業医こそが上医である」との土屋の独創的な発想によって、産業医科大学が目指す医師像が新たにもう一つ提唱されました。この医師像は、1978年の開学当初にあった産業医に対する負のイメージを根底から払拭することに大きく貢献したものと考えられます。
このことを実践している産業医とはどんなものなのか。産業医はどのような景色を見ているのか。産業医活動は時間軸が長く、やることが幅広いからこそ、単に漫然と現場実習を受けていてもほとんど産業医の実態は分かりません。だからこそ、それをぐいぐい質問してみてください。長年産業医をしてきた諸先輩たちがどんな景色を見ているかを知ることは、(産業医にならなくても)きっと皆さんの人生にとって糧になることだと思います。
訪問先の企業を調べよう
言わずもがなですが、訪問先の企業について調べておくことも非常に重要です。「企業名 健康経営」とか「企業名 産業医」「企業名 産業保健体制」といった検索ワードで調べてみたり、その企業のwikiを眺めてみておくだけでも違います。ちゃんと調べるとしたら、以下の事項を参考にしてください。
1. 企業の基本情報
・会社概要: 企業の設立年、所在地、規模(従業員数、売上高)などの基本情報
・事業内容: 主な事業内容や製品・サービスの概要
・業界情報: 企業が属する業界の特性や市場状況、競合他社について。
2. 組織構造と文化
・組織図: 企業の組織構造、主要な部署や役職の配置
・企業文化: 企業のビジョン、ミッション、価値観
・社内文化や労働環境に関する情報
3. 健康管理体制
・産業医の配置状況: 産業医の人数、配置場所、役割
・健康管理部門: 健康管理部門の構成、主な活動内容
・メンタルヘルス対策: メンタルヘルスケアの取り組みや支援プログラム。 4. 労働環境と福利厚生
・労働時間と休暇制度: 労働時間、残業の実態、休暇制度(有給休暇、特別休暇など)
・福利厚生: 健康保険、年金制度、福利厚生施設(社員食堂、フィットネスセンターなど)の有無
・働き方の柔軟性: リモートワークやフレックスタイム制度の導入状況。
5. 安全衛生管理
・安全衛生方針: 企業の安全衛生に関する方針や目標
・安全衛生委員会: 安全衛生委員会の活動内容や構成メンバー
・災害対策: 災害対策や緊急時対応マニュアルの有無。
6. 職場の健康リスク
・職場環境のリスク要因: 化学物質の取り扱い、騒音、振動、過重労働などのリスク要因
・職業病や労働災害の発生状況: 過去の職業病や労働災害の事例とその対策
7. 教育と研修
・健康管理教育: 従業員向けの健康管理やメンタルヘルス教育の実施状況
・研修プログラム: 新入社員研修や定期的な健康管理研修の内容。
8. 企業の社会的責任(CSR)
・CSR活動: 社会的責任を果たすための活動(環境保護活動、地域貢献活動など)
・サステナビリティの取り組み: サステナビリティに関する目標や具体的な取り組み。
9. その他
最新のニュースやプレスリリース: 企業の最新の動向やニュース。
産業医に興味がない人へ
産業医のキャリアに興味がない人もいると思います。そんな方は、5日間を社会科見学にすることも可能ですし、お客さまとして過ごすことや、いっそのこと観光にあててもいいかもしれませんね(本当はよくないのですが)。とはいっても、やはり有意義に5日間を使って欲しいと私は思っています。そんな方には以下の記事を読んでください。この記事は、産業医研修会で資格を取得したけど産業医活動には従事しない方向けの記事です。産業医のキャリアを目指さないという方にこそ、産業医学の知識を身につけて欲しいと切に願っています。立派な臨床医になりたいのであれば、食わず嫌いをせずに産業医の知識を教養的にでも身につけていただきたいと思っています。
さらに時間があれば産業医の解像度をもっと高めよう
もし時間があれば、現場実習に行く途中の時間とか、前夜のホテルで過ごす際にでも読んでみてください。繰り返しになりますが、事前に情報を入れておいた方が学びは大きくなると思います。進路選択として産業医を考えている人であれば、ぜひ解像度を高めて実習に臨むことをお勧めします!
「note」を読む
「産業医のnote」を集めていますので、ぜひ気になった方のnoteを読んでみてください。
Xで産業保健職をフォローする
X(旧・Twitter)で産業医をフォローしてみてください。ざっとアクティブなアカウントは50-100人くらいはいると思います。産業医のリアルを知ることができますよ。
産業保健関連の書籍を読む
産業医大図書館に産業保健の本が多数置いています。ぜひ読んでみてください。一番のおすすめは、ガチ産業医の「産業医のピットフォール」ですよ笑
「健康経営に関するレポート」を読む
産業医の解像度を高めるための一つのヒントとして「健康経営」があります。健康経営とは、安全衛生活動を経営マターとして捉えることで(経営者が主語)、産業医が主語の産業保健活動・産業衛生活動と内容に大きな違いはありません(実際には違うのですが概ね同じと捉えていただいていいと思います)。そこで、健康経営に積極的に取り組んでいる企業の活動内容を覗き見ることで、産業医活動がより具体的にイメージすることができると思います。例えば、2022年の健康経営銘柄に選ばれた企業の報告書を読んでみてはいかがでしょうか。「健康経営 健康白書」とググればいくつか興味深い報告書が読めます。健康経営において、産業医が果たせる役割は部分的ではありますが、どのように健康経営に位置付けられ、社会・株主にアピールされているか知ることで、産業医のことがより分かるようになると思います。
産業保健の無料雑誌を読む
産業保健界隈で無料の雑誌がいくつかあります。それを読んでみてはいかがでしょうか?一番のおすすめは産業保健21です。こちらも産業医大大学図書館に置いているはずです(置いてたかな?)。
それ以外
終わりに
産業医科大学は、5年次の冬〜6年次の春に入局先を決めなければいけないという非常に難しい状況にあります。そんな状況で、5年次の11月にある現場実習は、キャリア選択にとって超重要な機会です。ほとんど学生さんにとって、よくもわるくも6年間の中でもっとも産業医に触れることができる機会です。だからこそ、少しでも準備をして迎えて欲しいと思っています。他のポリクリローテーションみたいに(?)、行き当たりばったりで過ごして欲しくはないんです。前述のとおり、準備なしで臨めば、たったの5日間で得られる情報は非常に小さくなります。その情報だけで産業医というキャリアを切り捨てて欲しくはないんですよね。あとから後悔しないためにこそ、キャリア選択のために納得行くまでしっかりと悩んでいただきたいと思っていますし、そのためにこそ、この5日間の現場実習をより有意義なものにしていただきたいと思っています。
私も事業所側で学生さんを迎える側だったときには、かなり工夫をして、少しでも産業医学に触れられるように準備をしました。そして、他の事業所の関係者も多大な準備をかけて皆さんの現場実習を支えていただいてくれています。産業医学に興味がないという方も、その準備に応えていただき、真剣に5日間を過ごしていただければと思っています。
もし、産業医についてもっと知りたいという方がいれば、産業生態科学研究所の教員をお尋ねください。医学生への対応は教員の職務の務めであり、産業医を目指している医学生を無下に邪険に扱うことは決してありません(ないはずです)。できるだけアポイントをとって、訪れてみてください。ガチ産業医になにか質問があれば、TwitterでもDMください。もしくは、直接ご連絡くださいませ。
おまけ
調査を通じて出会った、従業員の健康管理に積極的な会社には、4年生の「地域看護学実習」の実習受け入れ先になってもらっています。「地域看護学実習」では、必ず学生に大企業と大田区内の小さな企業の両方を見てもらう機会を設け、環境や規模の違う2つの会社を比較して、その中で働く人たちがどういうことを行っているか、あるいはどういうシステムがあれば、働く人たちが等しく産業保健サービスを受けられるかということを議論してもらいます。というのも病院に入院する患者さんの中には、普段、労働者として働いている方が多々いらっしゃるわけです。本学の学生が看護師となって、そういう患者さんたちと向き合ったとき、なぜこの人たちがこういう病気になったのか、あるいは退院後の生活を考えて、今、どういう支援を行うべきかというイメージを広げられるようになっておくことは、非常に重要です。
