
<民主>と<愛国>戦後日本のナショナリズムと公共性/小熊英二【本要約・ガイド・目次】
『単一民族神話の起源』『“日本人”の境界』で日本を問いなおしてきた著者が、私たちの過去を問い、現在の位置を照らしだす。「戦後」におけるナショナリズムや「公」に関する言説を検証し、その変遷過程を明らかにする。これまで語られることがなかった戦争の記憶と「戦後」の姿が、いま鮮烈によみがえる。
私たちは「戦後」を知らない
あなたは、共産党が日本国憲法の制定に反対し、社会党が改憲をうたい、保守派の首相が第九条を絶賛していた時代を知っているだろうか。戦後の左派知識人たちが、「民族」を賞賛し、「市民」を批判していた時期のことをご存じだろうか。全面講和や安保反対の運動が「愛国」の名のもとに行なわれたことは? 昭和天皇に「憲法第九条を尊重する意志がありますか」という公開質問状が出されたことは?
焼跡と闇市の時代だった「戦後」では、現在からは想像もつかないような、多様な試行錯誤が行なわれていた。そこでは、「民主」という言葉、「愛国」という言葉、「近代」という言葉、「市民」という言葉なども、現在とはおよそ異なる響きをもって、使われていたのである。
一九九〇年代の日本では、戦争責任や歴史をめぐる問題、憲法や自衛隊海外派遣の問題、あるいは「少年犯罪」や「官僚腐敗」などの問題が、たびたび論じられた。しかしそれらの議論が、暗黙の前提にしている「戦後」のイメージは、ほとんどが誤ったものである。誤った前提をもとに議論しても、大きな実りは期待できない。私たちはまず、自分たちが「戦後」をよく知らないということ、「戦後」に対する正確な理解が必要であることを、自覚することから始めるべきだと思う。
この本は、そうした問題意識から出発して、「戦後」におけるナショナリズムと「公(おおやけ)」をめぐる議論が、どのように変遷して現代に至ったかを検証したものである。このテーマを追跡するために、「戦後」の代表的な知識人や事件は、ほとんど網羅することになった。
たとえば丸山眞男・大塚久雄・吉本隆明・江藤淳・竹内好・鶴見俊輔などの思想はもとより、共産党や日教組の論調、歴史学者や文学者などの論争も検証した。憲法や講和、安保闘争、全共闘運動、ベトナム反戦運動などをめぐる議論も、可能なかぎり追跡した。さらに戦争や高度経済成長などが、こうした思想や論調にどのような影響を与えたのかも、重視されている。
結果として本書は、「戦後とは何だったのか」そして「戦争の記憶とは何だったのか」を問いなおし、その視点から現在の私たちのあり方を再検討するものとなった。「私たちはどこから来たのか」、そして「私たちはいまどこにいるのか」を確かめるために、読んでいただきたいと思う。
[著者 小熊英二]
あとがきより
本書は、戦後日本のナショナリズムと「公」にかかわる言説が、敗戦直後から一九七〇年代初頭までに、いかに変遷してきたかを検証したものである。結果として本書は、丸山眞男、大塚久雄、竹内好、吉本隆明、江藤淳、鶴見俊輔など主だった戦後知識人の思想を検証したばかりでなく、憲法や講和問題、戦後歴史学、戦後教育、安保闘争、全共闘運動といった領域までをも視野に含めるものになった。
一九九〇年代の日本では、戦争責任や歴史をめぐる問題が論争となり、新たな右派団体の台頭もあった。また並行して、憲法と自衛隊海外派遣の関係、「日の丸・君が代」などの問題についても論争が発生した。さらに、いわゆる「少年犯罪」や「官僚腐敗」といった問題から、「公」や倫理のあり方をめぐる議論も盛んに行なわれた。
そうした議論を読んでいて感じたのは、他者に届く「言葉」を、多くの人が模索しているということであった。社会の状況が変動してゆくなかで、これまでの「言葉」が効力を失い、新しい「言葉」が探し求められている。そうした焦りや不安感のようなものを、多くの議論に感じとることができた。
ところがもう一つ感じたのは、議論の内容への賛否以前に、それらの議論が前提としている「戦後」認識が誤っているケースが多いことであった。少なからぬ論者が、「戦後の日本」を批判し、「戦後民主主義」の「言葉」の無効性を指摘する。ところがじつは、そう論じる当人が、「戦後の日本」についても、また「戦後民主主義」についても、多くを知っていない。そのように感じられる議論が、少なくなかったのである。
その結果、少なからぬ議論が一人相撲に終わってしまい、焦りと不安感だけが空転しているという印象をうけた。
まずは議論の基礎になる「戦後」への認識を確かにするべきだと考えたことが、本書の研究につながっている。
考えてみれば、「戦後」とは、現代の人びとがもっとも知らない時代の一つである。なぜ知らないのかといえば、「もうわかっている」と、安易に考えすぎているからだろう。たとえば、「憲法」といえば「もうわかっている」と述べる人も、じつは第九条以外の条文をよく知らないことが少なくないように。
そうして研究を始めてみると、「戦後」や「戦後民主主義」というものは、従来自分が漠然と抱いていたイメージとは、およそ異なるものであることがわかってきた。そこには、私などの予想をこえた世界と、思いもよらぬ「言葉」の鉱脈があった。本書は、そうした世界を描きだそうと試みたものである。
各章の内容は目次を参照していただきたいが、筆者の前著と同様、各章は独立して読むことも一応は可能なので、関心のある章から読んでいただくのも一興である。ただし、戦中の「雰囲気」を描写した第1章は、「研究」と称す
るにはやや苦しい記述にならざるを得なかった章なのだが、他のすべての章の背景となるものなので、この章は最初に読んでいただきたい。戦後思想は、それを生みだした人間の戦争体験と切り離して論じることは不可能なものが大部分であり、戦争の状況を知らずして「戦後」を理解することはできない。そのためこれも結果として、本書は戦後思想を検証するなかで、「あの戦争とは何であったか」を再考するものとなった。
なお、本書では十分に言及できなかった日本の植民地支配や沖縄の問題は、前著「〈日本人〉の境界」で詳述したので、そちらを参照していただきたい。本書の第8章でとりあげた国民的歴史学運動と「単一民族」意識の関係、およびそれが沖縄の復帰運動に与えた影響についても、この前著の第2部で詳しく論じた。また女性学の問題提起にたいする本書の姿勢など、いくつかの重要な問題は注で論じたので、ご一読いただければ幸いである。
前著と同じく、本書もまた大冊となった。当初の草稿を半分ほどに圧縮し、収録予定の章を省くなどしたが、それでも四百字詰め原稿用紙にすれば二千五百枚ほどに相当する。こういう大がかりな研究をしていると、「なぜあなたはそうした問題に関心をもったのか」と聞かれることが多い。私はたいてい、「自分でもよくわかりません」と返答している。そう述べると、はぐらかされたように感じる向きが少なくないようだが、これは私の正直な感情である。
そもそも、自分を突き動かしている動機が何であるのかなど、当人自身にわかるはずがない。時折、「自分はこういう経験が出発点になってこの本を書いた」と述べているケースをみるが、私にはそれが信じられない。人間をして、研究などという手間と根気ばかりを要する仕事に、何年も従事させるだけの歪みをもたらした背景や理由が、わずかな分量の紙幅で書けるはずがない。ましてや、自分にとっての「決定的な経験」などというものを、数頁で語れるということが、私には理解できない。決定的であればなおのこと、語る言葉をもたず、沈黙するしかないはずだと思うからである。
そうしたわけで、私は今もって、自分がなぜ前著や本書のような研究をしたのか、自分でも説明できない。過去の経験や記憶の断片をつなぎあわせて、他人を納得させやすいような物語をつくることは容易だが、それはやりたくないのである。しかし、本を出すたびに「なぜあなたは」という質問が絶えないので、以下で私に関連する一つの事件を紹介する。これは私事であるから、公共の紙面をやすことには気がひけるが、お許しをいただきたい。
私の近親者に、シベリアの体験者がいる。彼は敗戦まぎわに徴兵され、一発の弾を撃つ機会もなくソ連軍の捕虜になり、シベリアの収容所で約三年の強制労に従事した。彼は町内の会誌に寄せた回想記で、こう書いている。
昭和二十年八月。私は現役初年兵として、満州東部牡丹江の近郊に居り、ソ連に無条件降伏後捕虜として十月下旬、シベリヤ東部のナタの収容所に連行されました。
写真でよく見るアウシュビッツのユダヤ人収容所のような、三段重ねのかいこ棚に約五百人が、ぎっしりと詰め込まれたのです。
これから先どうなるかわからない精神的不安。重労働にも拘らず飢餓に近い食料不足。日一日と冷気がまし、来るべき極寒を予告する、一言で言えば恐怖に近い寒さ。望郷、飢え、寒さ。ただいつかは帰れることもあるだろうという、希望のみが生命を支えている日でした。
十一月下旬、もう十人もの死者と、何十人もの予定者が出ていました。同年兵の京坂君も栄費失調の症状が出始めました。夜盲になって、早朝の作業整列から雪道を歩いて現場に向う時、私は彼と手をつないでいました。明るくなるまでは、そうしていないと滑って転ぶのです。その内に足がむくんできた故か、靴に入らないと悲しそうに言うようになり、私は何回か押し込んで整列させました。ついに失禁が始まる様になった十二月中旬、労働免除となり医務室に入室しました。しかし勿論何の手当もありません。ただ寝ているだけです。
年もあけた二十一年一月一日。この日はソ連でも休みで、私は午後から見舞いに行きました。病室にはベッドが七・八台あったでしょうか。ペーチカには僅かに石炭が燃えていましたが、温度は上らず、床にはこぼれた水が凍りついて、三重ガラスの窓には、中央部分を除いて水がビッシリ張りつめていました。
私はそこから外を眺めました。ロシヤ人の親子が歩いてゆきます。家々の煙突から煙が上ってゆきます。今の私には遠い世界である、家庭というものが、そこにはありました。
彼の具合は、誰が見てもあと何日もないとわかる程、衰弱していました。何の話をしたか、ほとんど記憶していません。どうせ良い話は何も無いのですから、慰めのきまりきったことしか言わなかったでしょう。
ただ彼が、何か遠くを見つめる様な目をしながらつぶやいた、「今頃、内地でも正月をやっているだろうな」「餅を食べたいなあ」という二つの言葉。これが記憶の片隅に残ったのです。
何日後かに、彼は死にました。私自身、連日の重労働と、冷えのためか、四、五日下痢が続いて、やせ衰えていました。一月何日何時頃死んだのか。どういう形で知ったのか。誰から聞いたのか。全く記憶していません。例えてみれば、風の便りの様なものだったのでしょう。誰もが、他人の消息を気づかう様な、人間的感情が失せていたと思います。御通夜とか式がなかったのは勿論のことでした。当時の私達の生活は、人間としてのものではなかったのです。
私は二十三年八月、復員して舞鶴港に上陸しました。引揚船内の調査で彼の事を記入しました。きっと、これまでの帰国者の知らせで家族の方々は、知っておられるかもしれないと思いながら。
あれだけ待望した帰国でしたが、その後の生活は苦しかった。出征前に勤めていた会社には、シベリア抑留者は共産主義者だという噂のために、体裁良く退職させられました。二十六年二月には結核となり、助骨七本を切る大手術をしたのに、退院できたのは三十一年五月でした。その後、就職、転職、倒産、止むなく四十一年には独立して、小さな商売を始め、その後はどうにか順調な生活が続き、現在に至っています。
その間、毎年正月を迎える度に彼のこと、あの言葉を思い出し、現在の幸せを感謝してきました。だが生活にゆとりが出来る様になってから、形容しにくい、或る思いが、だんだん大きくなってきたのです。
生きて帰ってきたことが、何となく申し訳ない様な気持。何もしないでいて、いいのだろうか。
この後、彼は一九八三年に「京坂君」の兄を採しあて、死亡の状況を説明した。彼はこれによって、「長年の肩の荷をおろした気がして助かった」と感じたが、それから一〇年ほどして、また別の事件に遭遇した。以下は、その新聞報道である。
(「国違えど抑留の苦労同じ-戦後補償裁判の原告」「朝日新聞」一九九六年一一月三〇日)
「私も彼も大日本帝国臣民で、兵役の義務を果たした。今になって国籍を理由に差別するとは、日本人として本当に恥ずかしい」
八王子市の小熊謙二さん(七一)は、そんな思いから、中国河北省に住む元日本兵呉雄根さん(七〇)が九月、東京地裁に起こした訴訟の原告に名を連ねた。呉さんは日本兵としてシベリアに残されながら、慰労金を受給できないのは不当な差別だ、と提言した。
サラリーマンだった小熊さんは、一九四四年十一月に召集され、中国東北部(旧満州)牡丹江の通信連隊に配属された。敗戦直後の五年八月末、シベリアナタの収容所へ。
チタでの初めての冬は、寒さとの闘いだった。収容所の石炭も小麦も服も、ソ連兵に横流しされたあと残りが届いた。翌年からは精神的な苦痛が襲った。政治集会が毎日開かれ、バラックの中で「階級闘争」が繰り広げられた。元将校はさげすまれ、親しかった者同士がののしりあった。
四七年末、別の部隊の兵士だった呉さんが小熊さんのバラックに移ってきた。あの苦しみをともにした者の名と顔は忘れない。小熊さんは四八年八月、舞鶴に復員、呉さんも同年末、中国へ帰国した。
国内では八八年、抑留者を慰労する平和祈念事業が開始されたが、中国籍の呉さんは対象外とされた。雑誌に掲載された呉さんの手記をきっかけに、二人の間で文通が始まった。
小熊さんは二人で分け合おうと、慰労金(国債十万円分)を請求し、「一人の日本人としておわびの気持ち」との手紙に五万円を添え、郵送した。恩給は勤務年数で受給者と欠格者の差別をし、慰労金では国籍を原型にする。政府に怒りがこみあげた。
日本政府に抗議するため、呉さんは三月、来日した。四十八年ぶりに再会した二人は国会議員や政党などを回った。「戦前は日本人だからと兵役の義務を課し、戦後は日本人ではないからと補償から外す。こんな身勝手が許されるのか。文化大革命では『日本軍関係者』と激しい弾圧も受けた」。訴えに対する同情は受けた。が、事態は動かない。
日本人とは何なのだろうか――。小熊さんの怒りは情けなさに変わった。
初公判は来年一月三十日。弁護士は訴状で、小熊さんについてこう記した。「国に良心なくも、この国の国民に良心があることを示してくれた。原告となった意義は日本国の良心と信義の回復にある」と。
この小熊謙二とは、私の父である。呉雄根氏は、旧満州に在住していた朝鮮人であり、戦前には日本国籍があった。前著「〈日本人〉の境界」で検証したように、日本政府は韓国併合のさい、すべての朝鮮人に日本国籍を強制付与し、その後は原則として一切の国籍離脱を許さず、一九四四年には満州在住朝鮮人の戸籍登録を強行して彼らを徴兵した。かつては「満州在住朝鮮系日本国籍人」であり、現在は「中国籍朝鮮系元日本兵」である呉氏もその一人であり、敗戦後には日本国籍を一方的に剥奪されている。
ただし付言しておくと、訴状にいう「日本国の良心と信義の回復」という文言は弁護士の方が書いたものであり、上記の新聞記事も記者がまとめてくれたものであって、私の父は「日本人として」とか「兵役の義務」などという言葉を使うタイプではない。だいたい、商売人としてたたき上げてきた父は、非常に実際的な人間であり、抽象的な思想や議論を好まない。裁判が進行している過程でも、「戦後補償」とか「戦争責任」とか、「日本」とか「アジア」とか、「加害」とか「被害」とかいった言葉は、ほとんど使っていなかった。
父は元日本兵として中国にいたのであるから、「侵略」をしていた「加害者」だったにはちがいない。しかし一方で、敗戦まぎわに微兵されて捕虜となり、強制労働と失業と病気という経験をしたのでは、「被害」の感情が強いのも無理はない。そもそもシベリア抑留は、もちろんソ連が行なったことではあるが、日本側も捕虜となった日本兵を労役に提供することを認める文書を作成していた。要するに日本国家の側は、捕虜にされた日本兵たちを捨て駒に使って、後のソ連政府の心証を少しでも良くしておこうと考えたのだと思われる。
そうした意味で私は、当時の「日本人」はただ一方的に「加害」の間にいたと断じるような形で、「戦後補償問題」や「戦争責任」を論ずる気にはならない。これはもちろん、アジア諸地域が受けた被害を軽視するとか、日本国には加害責任はないといった意味ではない。私が述べているのは、個々のケースは多様であり、また政治的責任には軽重があるはずなのに、抽象化された「日本人」という単位を想定して、その「日本人」の「加害」や「被害」をすることには、根本的に連和を拭えないということである。その「日本人」とはいったい誰のことだ、と聞きたくなるのである。
また個々のケースでも、現実の人間は、なかなかに複雑なものである。父は前述の回想記の末尾では、「指導者というものは、昔も今も同じ様なことを言っています。国を愛する。国を守る。こういう言葉で、どれほど多くの人が犠牲となってきたことでしょう」「当時の軍人達と今の軍人達との意識は変わったでしょうか。軍隊という官僚組織は、そんなに変わるものでしょうか」と述べている。しかしその一方で、父は軍歌を好み、幼いころの私に軍歌を教えた。そのため私は今でも、いくつかの軍歌をそらんじることができる。
裁判の過程では、父の知人である元日本軍兵士の人びとが傍聴に訪れた。呉雄根氏は、法廷で自己の戦争体験を証言するさいに、「日本人」として教え軍歌を裁判官の前で歌った。呉氏と並んで証言席にいた父も、傍聴席にいた元兵士たちも、黙って口を動かしながら唱和した。
もちろん軍歌そのものは、好ましいものとはいえない。父にしても呉氏にしても、もう一度戦中に戻りたいわけでは、さらさらないだろう。しかし、軍歌は好戦的でナショナリスティックだから駄目だというような正論が、こういう場面で何の意味があるだろうか。むしろ、大日本帝国の遺産である軍歌が、法廷で日本政府に抗議するために使用され、国籍をこえた共同意識を生みだしていることに、ある種の感慨を覚えた。
この訴訟は、一九九六年の提訴から、二〇〇〇年二月の東京地裁による請求棄却、同年八月の東京高裁による請求棄却を経て、二〇〇二年三月に最高裁による請求棄却で結審した。棄却の理由は、現状の法律から解釈すれば不当な差別とはいえないというもので、いうなれば門前払いである。
とはいうものの、こうした事件が本書や前著を書く動機になったのかといえば、意識的にはそういうつもりはなかった。上記の事件の経緯に、自分の研究と重なる部分があることについても、「偶然の一致」という感じしかしない。人間は「パブロフの犬」ではないから、ある事件があれば直接にその反応が現われるほど単純ではない。また裁判や捕虜体験は、あくまで基本的には父の問題であって、私はそれに関係したにすぎない。この訴訟が私の研究の背景であるなどと単純化して語られれば、私は違和感を禁じえないし、父も意外に思うだけだろう。
しかし一方で、私は本書で数多くの戦後知識人たちの思想を読んだあげく、人間は結局のところ、自分の動機を自分で理解するなど不可能なのだという結論に達した。私は今もって、研究の動機については、「自分でもよくわからない」と答えるしかない。しかし上述のような父との関係のなかで生きてきたということが、何らかの形で自分の研究に影響しているということも、自分ではわからないが、まったく考えられないことでもあるまい。あとは読者の方々が、ご自由に判断していただければよいと思う。
本書の完成までに、多くの人びとにお世話になった。謹んで感謝を述べたい。
二〇〇二年八月 小熊英二
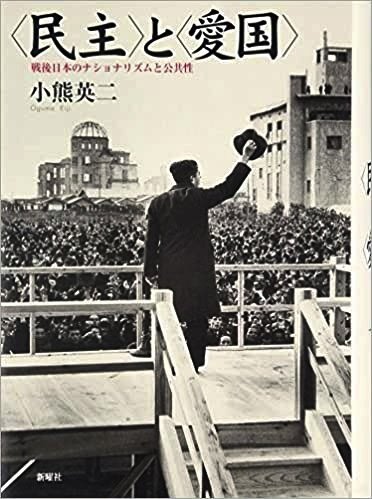
目次紹介
序章
・二つの「戦後」
・「戦後民主主義」の「言葉」
・「言説」と「心情」について
第一部
第1章:モラルの焦土-戦争と社会状況(29)
・セクショナリズムと無責任
・軍需工場の実態
・組織生活と統制経済
・知識人たち
・学徒兵の経験の始まり
・「戦後」の始まる
第2章:総力戦と民主主義-丸山眞男・大塚久雄(67)
・「愛国」としての「民主主義」
・「近代」への再評価
・「国民主義」の思想
・「超国家主義」と「国民主義」
・「近代的人間類型」の創出
・「大衆」への嫌悪
・屈辱の記憶
第3章:忠誠と反逆-敗戦直後の天皇論(107)
・「戦争責任」の追及
・ある少年兵の天皇観
・天皇退位論の台頭
・共産党の「愛国」
・「主体性」と天皇制
・「武士道」と「天皇の解放」
・天皇退位と憲法
・退位論の終息
第4章:憲法愛国主義-第九条とナショナリズム(153)
・ナショナリズムとしての「平和」
・歓迎された第九条
・順応としての平和主義
・共産党の反対論
・「国際貢献」の問題
第5章:左翼の「民族」、保守の「個人」-共産党・保守系知識人(175)
・「悔恨」と共産党
・共産党の愛国論
・戦争と「リベラリスト」
・オールド・リベラリストたち
・「個人」を掲げる保守
・「世代」の相違
第6章:「民族」と「市民」-「政治と文字」論争(209)
・「個人主義」の主張
・戦争体験と「エゴイズム」
・「近代」の再評価
・共産党の「近代主義」批判
・小林秀雄と福田恆存
・「市民」と「難民」
第二部
第7章:貧しさと「単一民族」-一九五〇年代のナショナリズム(255)
・格差とナショナリズム
・「アジア」の再評価
・「反米ナショナリズム
・共産党の民族主義
・一九五五年の転換
・「私」の変容
・「愛する祖国」の意味
第8章:国民的歴史学運動-石母田正・井上清・網野善彦ほか(307)
・孤立からの脱出
・戦後歴史学の出発
・啓蒙から「民族」へ
・民族主義の高潮
・「歴史学の革命」
・運動の終焉
第9章:戦後教育と「民族」-教育学者・日教組(354)
・戦後教育の出発
・戦後左派の「新教育」批判
・アジアへの視点
・共通語音及と民族主義
・「愛国心」の連続
・停滞の訪れ
第10章:「血ぬられた民族主義」の記憶-竹内好(394)
・「政治と文学」の関係
・抵抗としての「十二月八日」
・戦場の悪夢
・二つの「近代」
・「国民文学」の運命
第11章:「自主独立」と「非武装中立」-講和問題から五五年体制まで(447)
・一九五〇年の転換
・アメリカの圧力
・ナショナリズムとしての非武装中立
・アジアへの注目
・国連加盟と賠償問題
・「五五年体制」の確立
第12章:60年安保闘争-「戦後」の分岐点(499)
・桎梏としての「サンフランシスコ体制」
・五月一九日の強行採決
・戦争の記憶と「愛国」
・新しい社会運動
・「市民」の登場
・闘争の終焉
第三部
第13章:大衆社会とナショナリズムー一九六〇年代と全共闘(551)
・高度経済成長と「大衆ナショナリズム」
・戦争体験の風化
・「平和と民主主義」への批判
・新左翼の「民族主義」批判
・全共闘運動の台頭
・ベトナム反戦と「加害」
第14章:「公」の解体-吉本隆明(598)
・「戦中派」の心情
・超越者と「家族」
・「神」への憎悪
・戦争責任の追及
・「捩れの構造」と「大衆」
・安保闘争と戦死者
・国家に抗する「家族」
・「戦死」からの離脱
第15章:「屍臭」への憧憬-江藤淳(656)
・「死」の世代
・没落中産階層の少年
・「死」と「生活者」
・「屍臭」を放つ六○年安保
・アメリカでの「明治」発見
・幻想の死者たち
第16章:死者の越境-鶴見俊輔・小田実(717)
・慰安所員としての戦争体験
・「根底」への志向
・「あたらしい組織論」の発見
・「難死」の思想」
・不定形の運動
・「国家」と「脱走」
結論(793)
・戦争体験と戦後思想
・戦後思想の限界点
・戦争体験の多樣性
・「第三の戦後」
・「護憲」について
・言説の変遷と「名前のないもの」
