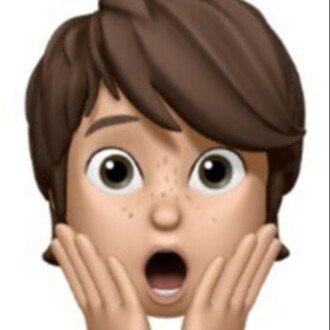【大人探究部】スタンドアップコメディアン「フミ・アベ」の沼にハマる
こんにちは
コロナ陽性から復活したばかりのfuntrapです
この自主隔離中の生活で、仕事と家事を忘れて、3つの沼にハマりました
✔︎韓流ドラマ「Startup」
✔︎MONGOL800
✔︎男闘呼組
✔︎映画「かごめ食堂」
✔︎日系米国人コメディアン Fumi Abe
それぞれの説明もディーーーープにしたいところですが(笑)今回は、4番目の「日系米国人コメディアン Fumi Abe」について、書くことにします。
フミ・アベって誰よ?
昨年の夏、米国の全国ネットのコメディトーク番組に登場した「フミ・アベ」さん。これをたまたま目にした私は、涙したわけです。面白くて。
ちなみに、彼のついては、この日本語の記事を読んでください。
2020年にすでにHeapsが書いてる。早〜!
なお、こちらが彼のサイト
Fumi Abe is a Japanese-American stand-up comedian/writer based in Los Angeles who recently made his TV debut on the Late Show with Stephen Colbert.
He has written for NPR’s “Wait Wait...Don't Tell Me!”, the 2022 TIME100 Gala hosted by Simu Liu, was part of the 2020 Comedy Central Digital Creators Program, and is currently a staff writer on The Late Late Show with James Corden.
He produces and hosts the comedy podcast "Asian Not Asian", which was most recently included in Vulture’s Comedy Podcast Roundup as well as The AV Club’s Podcast series highlights.
元々NYCで活動していた彼ですが、現在はLAに住んでいるそうです。ちなみに、移り住んだLA(というかWest Hollywood)のネタもありますが、面白いよ。
✔︎オハイオ州コロンバスの白人ばっかの町出身
✔︎日本人の両親は父親の仕事の関係で仕方なくオハイオに移住
✔︎元広告代理店出身
✔︎ケーブルTV局「コメディ・セントラル」元勤務
✔︎PodCast "Asian Not Asian"で人気に (レビュー:4.9⭐️!)
勝手な想像ですが、オハイオのコロンバスにお父さんが仕事で移住って、お父さんHonda?!(笑)と思ったら、Honda関係者だった。
そのあたりの人生について、ここでエピソード話してます〜
彼のエピソード、もちろん全部英語しかないんですが、日本語付けたい。。。これは私のNext Projectということで乞うご期待。
さて
スタンドアップコメディーStandup Comedyって何よ?
ここで、スタンドアップコメディーって何?って話しです。
日本のお笑いでいうところの、「一人漫才」かなって思います。
なお、日本語のウィキペディアに書かれている情報は、英語版読み比べると、「内容薄すぎ」てダメだししたいので、下記リストで追記します。
✔︎19世期後半に作られた西洋的なアートの一つ
✔︎ステージに一人で立って話す(*ただし座ってることもあるけどね)
✔︎即興
✔︎お客との対話形式(日本の一人の一方的喋りの漫談とはちょっと違うそうです)
✔︎ルーティーン(日本語と「毎度お馴染み」がぴったりじゃない?)がある
✔︎「ジョーク泥棒」(要は人のネタを取って喋る)はこの世界の最大の罪
【代表的なネタの種類】
Alternative(オルタナティブ): いわゆる一般的に人気のコメディをなじ
DIY: オルタナティブをさらにツイスト効か新しいオルタナティブにしたものCharacter(キャラクター): 「人の性格」とか「特徴」のネタ
Insult(罵り)or roasting(からかい): お客さんや他のコメディアンをネタのして、からかったり罵ったりするネタ
Musical(ミュージカル): 特定の音楽や音楽の歌詞に関するネタObservational(あるある): 生活の中で、見つけた「バカバカしいこと」や「納得いかないこと」を使ったネタ
Satire(風刺): 政治やイデオロギーに関して社会に一般的に受け入れられているステレオタイプを描いたネタ
Surreal(非現実): おかしなことや、全然ロジックの通らないこと話しを並べて話すネタ
でここからがポイント(だと私が思っている)は、
演者の架空の延長とみなされる「自由な形のコメディライティング」によって構成されている
というところ!
要は、コメディアン書くネタはもちろん日本のお笑い芸人さんみたいに「十八番」とか「お箱」とか言われているような、「毎度お馴染み」のネタが必要なんですね。
流れや、そこまでのストーリー展開とか、もちろんちょっとずつ毎回変わるんですけれど、「このコメディアンだったらこのネタ」みたいなのがある。
フミ・アベの代表的ネタ
ちなみに、フミ・アベの一つのネタで、セクシャルなのなしネタで大好きなものをIGからセレクトするとこんな感じ
友達の妹が、Google蹴ってアーミーに行く
「めちゃくちゃギャルな友達の妹が、軍隊いっちゃんだけど、まじ心配」というネタ
ボーイズタウン
ウエストハリウッド(ゲイの街として知られる)と自身の引っ越しをネタにしたもの
GenZ
ニューヨークタイムズに書かれていたGenZについての説明どうなのよーというネタ
こんな感じです。もちろん、スタンドアップコメディーの醍醐味の一つは「下ネタ」なんで(汗)、彼のネタにもいっぱい織り込まれているけれど、個人的には下ネタよりアジア人あるあるとか、社会的な隙間視点を織り込んでいるこういうネタの数々が私は好きになった理由かも〜なんて思います。
でも、正直スタンドアップのネタは下ネタとかも挟まないと45分とかもたないんじゃって思うようになってきている今日この頃です。
スタンドアップコメディー作りの7つのポイント
さて、ここからが本題(笑)
私は文章を「書く」ことを生業としていますが、さらに最近「喋る」機会が増えつつあります
毎週水曜日のClubhouseで1年半以上、本についてのトークとモデレーションをしているのですが、そこに今度子どもたちに探究学習のプログラムを提供する先生役が加わりました。
いづれも人を惹きつける、魅力あるしゃべりが求められるわけです。
そこで、考えたのは「スタンドアップコメディー」のネタ作りから学んだらいいじゃないか、ということでした。
かなりの挑戦になること覚悟です。
元々関西人じゃないし、人の笑いを取りに喋った試しがないので、本当にどこから手を付けたらいいかわからない。大学時代、河合塾のチューター仲間で、大阪出身の同期が「笑い取らないで喋ってことないぜ」と言われて、おったまげたことがありましたが、マジで、奴のマインドが欲しい。
で、見つけたのがこれです。
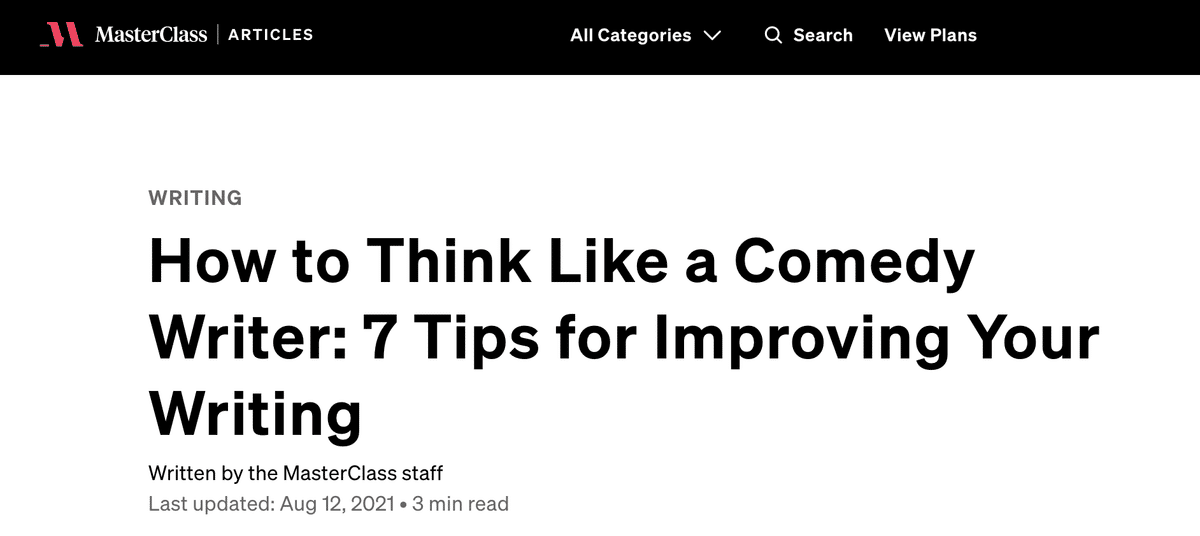
コロナ禍で、おそろしく人気になったと言われているオンラインレッスンサイトの「MasterClass」の紹介ページ。(なので無料で読めます)
コメディー構成作家のように考えるには?あなたの文章をよくする7つのポイント(How to Think Like a Comedy Writer: 7 Tips for Improving Your Writing)
面白い話しで人を笑わせるコツは?タイミング? 誇張した演技力?ユーモアをシェアすることがすごく重要。ユーモアのセンスを共有することは、その一つの要素にすぎないそうです。
他の種類の文章と同じように、綿密な計画、草稿、そして技術が必要です。
このプロセスがうまくいくと、魔法のようにジョークが輝いてくるそうです。
以下丸っとDeepLに翻訳してもらいました
観察眼を磨く。
ユーモア作家も小説家も、一般に人間の行動を執拗にカタログ化する。コメディ作家は、そのスキルをさらに一歩進めて、現実の行動のおかしな点、固有の不条理な点に着目することが多い。内輪のジョークがほとんど通じないのと同じように、あなたの書く観察力や関連性は、観客が持っていない文脈や情報に頼ってはいけません。コメディは共感によって成立します。オーディエンスや読者は、自分が経験したことのある、あるいは自分がその一部であると想像できる状況に最も反応するのです。常套句をひねり出す。
ユーモアは、決まり文句をひねったり、変形させたり、弱体化させることに依存しています。これは、決まり文句に基づいた期待値を設定し、その後に意外な結果を提供することによって行います。ユーモアの文章では、このプロセスを「リフォーミング」と呼びます。優れたコメディ、そして優れた小説は、観客を惹きつけ、推測させるために決まり文句をひねり出すのです。文章構造を試す。
脚本家が大きな笑いを取るためにビジュアルコメディに頼ることがあるように、構文を試すことでそのタイミングのバージョンを提供することができます。面白い表現を文末に置いてみてください。ユーモアは緊張の解放であることが多いので、文が緊張の蓄積を提供し、最後に最も自然に見返りが起こるのです。面白い響きの言葉を使う。
面白い言葉を見つけよう。自分が一番面白いと思う言葉をリストアップして、文章の中で使ってみたり、登場人物に言わせたりしてみましょう。コントラストと不調和を利用する。
あなたの登場人物は恐ろしい状況にあるのでしょうか?例えば、背後から迫ってくるT-Rexではなく、自分のブリーフケースに執着する男のように、軽いものを付け加えましょう。ジョークを書くときはよく対比を使いますが、小説や短編でも同じようにして、読者の興味を引きつけることができます。異なる視点を身につける
模倣とは、ある視点を抽出し呼び起こすことです。あなたの好きなコメディアンがどのように模倣に取り組むか考えてみてください。主人公に肉付けするために、何を参考にすればいいでしょうか。歩き方などの身体的な特徴でしょうか?それとも話し方?その人物の個性や、物語の大きな流れの中での役割を最もよく表しているのは、どんな行動でしょうか。コールバックを活用する。
ユーモアライティングの世界で、より満足度の高いツールの1つがコールバックです。これは、セットやスクリプトの中で以前に行われたジョークを繰り返し引用することです。テレビ番組では、最も忠実な視聴者のためのインジョークとなり、スタンドアップコメディでは、意図的に蛇行したストーリーにスルーラインを提供し、構造を与えることができます。最終的なオチとして機能することもある。
これ、使えるでしょ!と思ったので早速これからしばらく「観察」強化しつつ、ネタ帳みたいなものをつけようと思います♪
お笑い知らずの私の文章、どこまで変化するかしら〜
うふふ。楽しみ。
#スタンドアップコメディー
#フミアベ
#笑い
#笑いの取り方
#構成作家
#アジア人コメディアン
#漫才
#探究
#大人探究部
#MasterClass
いいなと思ったら応援しよう!