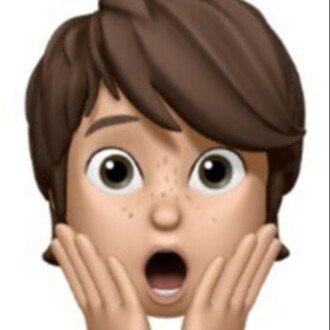【Basketball Mom】チームで最強の"ルールブック"を作ってみた
こんにちは
ミニバスママのfuntrapです
ウェブサイト作りにはじまった、ミニバスチームのDX化。おかげさまで、チーム運営は相当デジタル化されていき、それに合わせて保護者間のコミュニケーションと、コーチ陣とのコミュニケーションも↑。結果として、チームが強くなりました。
これまでのDX化の流れについては、こちらをお読みください。
さて、チームが強くなったこの夏。基本的に子どもたちの練習を見ていて一番感じたことは、
①やっぱりシュート率だよね
②ミニバスノート効果出てるんじゃない?
の2つです。
細かく書いていきますね
①やっぱりシュート率だよね
東京都リーグに所属するチームなので、今年はリーグ戦が前期・後期2回ではなく、ゆるっと感染症対策を鑑みて、6月から11月という長い期間で1リーグ戦戦った形です。
ティップオフした最初の頃は、立て続けに試合が組まれていて、感染症もそこそこ状況でしたので、いろいろな対策をした上で、試合に望んでいました。
4月の新人戦の後、6年生が一人受験勉強でお休みに入り、同時に一人新しいメンバーが加わった形で、かろうじて6年生4人を確保した状態で、リーグ戦に入った我がチーム。
それでも今年は4、5年生の人数が確保できているため、試合では体力の温存を考えながら、「選手の交代」ができるようになりました。なお、これまでは4年以上がフルメンバーで10名前後というチーム構成だったことで、本当に苦戦を強いられてきたことを考えると、
控え選手がこんなにいるってすごい
ことだということを実感しました。(強いチームは強さをキープできる理由もどんどん実感)
今年は実力や人数などで、リーグ戦のグループ決めに一定の計らいがあったそうで、かなり互角に戦える相手が多かったのものの、
「シュート率」の低さがもろに勝敗に影響した結果に
そこでチームが導入したのが、引率保護者による
「シュートカウントシート」です
シートを作って、自チームと対戦チームのシュートカウントを始めました。
要は「見える化」です
これで、
シュートを打っていて入らなくて点数が取れていないのか、シュートそのものが打てないくて入っていないのかが一目でわかりました。
結果は前者。単純に、成功率が低かった。
そこで、感染症の広まりの激しい夏休み、リーグ戦が一時中断したタイミングで、対戦型の練習も控えよう、という中でコーチたちが導入してしたのが「シュート率アップ作戦」と「体力作り」でした。
ゲーム形式で、とにかく毎回練習の中で大量のシュート練習を組み込んだ。これまでチームの方向性としては、チームとしてのグループで練習することを、練習時には集中的にやっていたので、絶対的にシュートの個別練習が足りていませんでした。
そのため、学校の休み時間でひたすらシュートを打ったり、自分でコツコツ公園でバスケしに行ったり、リングを自宅に買って練習したりする子と、練習だけ来てバスケをしている子で大きな差が出ていました。
やはりある程度「量」がものをいう世界。シュートのコツを会得するために、感覚的に掴むためにもシュート練習が必要だったのです。
また体力作りは、4ピリオド最後まで走りきる体力をつけるため、普通に「ひたすら走る」。アップの時に、しっかり走る時間を確保してから練習を始めるようになりました。
そして迎えた区大会で、会場優勝からの準決勝進出を叶えました。これまで1勝もできないことがザラだった区大会で、2勝それも圧勝を経験。
子どもたちはとっても喜びました、それ以上にコーチは飛び上がって喜んでくださった。
しかし実際準決勝にコマを進めたものの、当日は慣れない会場に緊張も隠せない上、メインコーチ不在という状況で、力を出しきれなかった彼ら。
でもこの区大会での会場優勝がきっかけで、その後練習試合のオファーに始まり、子どもたちの自信の高まりに加え、チームの存在感が地域やリーグ内に根付いてきたのが嬉しいです。加えて、夏休み明けの感染症が落ち着いたタイミング再開した体験者の受け入れ後、一気に希望者と入部者が増えました。
結局、この秋だけで、新入部員を10名以上迎えることとなりました。その中には、他の地域の経験者や、外国籍に子どもも含みます。多様性が広がる我がチームの様子はここに書いています。
②ミニバスノート効果出てるんじゃない?
そして、チームが強くなったもう一つの秘訣が、今年導入したミニバスノートです。これまで各メンバーに自由にノートを持ってきてもらい、ミーテイングの時にはそこに記入してもらっていました。
年に数回、コーチがそのノートを回収してみることもあるのですが、所詮「小学生」です。まだ漢字だって怪しい子どももいっぱいいます。ほとんどの子どもは、ミーティングのノートだってまともに取れてないのが現状でした。
そこで、ミーティングノートはフォーマット化し、さらに「試合ノート」を導入しました。試合ノートは試合の結果を書いたり、自分の気持ちや、うまくできたところ、もっとこうしたらよかったことなどを記入するものです。
さらに、これに(私の独断で!!)「保護者からのコメント」と「コーチからのコメント」の欄を作ってみました。
日頃から、家庭でバスケトークしてください!というヘッドコーチたちの意向を、自然に取り入れられるいいきっかけになるのではという思いと、私個人としても自分の息子たちの試合に対する感想(主に褒めること!)を、残しておきたいと思ったことがきっかで導入してみました。
ちなみに、ビデオを見て「すごいね」、「がんばったね」は簡単に言えますが、書くとなると「ここが凄かったね」、「ここがんばったね」ともう少し具体的な言葉を入れざるを得ない。言葉という表現を、忘れずにすみます。
細かいことを文字で残すのは、振り返りにもいいのではないかと思ったのです。
さらに、コーチにもたくさん活用してもらえるように配慮しました。
✔︎シート形式にしたことで、チーム全員から集めてもそれほど重たくない
✔︎子どもたちが何を考え、どう試合に挑んだか、コーチ陣全体で共有がしやすい
✔︎コーチコメント欄を入れることで、しっかり子どもたちの声を聞く意識を持ってもらう
おそらく、子どもたちの考えに納得したり、驚いたりしているのではないか、と思います。何よりもコーチたちがそこに書かれている子どもたちの「データ」を共有し、練習や次の試合に役立てられるようになった。
子どもたちの気持ちの部分も浮き彫りにできるノートを作ることで、小学生のメンタルをしっかり把握してもらえるようになりました。
ノートの次に登場させたルールブック←いまココ
こうして導入したミニバスノートですが、メインは「試合振り返りシート」でした。
新入部員が増えていく中で、限られたコーチ陣で多くの子どもたちに指導をする上で、コーチたちの中で少しずついかに子どもたちにバスケの楽しさだけでなくルールを理解してもらったり、上手くなるために「何が必要な」を意識してもらえるようになるか。そんな話しが出てきたようです。
また保護者と子どもたち。保護者とコーチの共通用語を増やすことが、より円滑なコミュニケーションを作り上げる上で大切!と考え、この秋導入したのが、チームのルールブックでした。
きっかけは、
対戦相手のチームが、チームのルールブックを作られているのを見せてもらったこと。
いいものは、ガンガン導入です。思い立ったら即行動!コーチが導入したいは出来るだけ即導入が今年の保護者代表の方向性です。
ヘッドコーチが、バスケのイロハだけでなく、TO(テーブル・オフィシャルズ)のコンテンツまでまるっと抑えてあるその素晴らしいブックレットを目敏く発見!相手チームさんに了承を得て、参考資料にさせていただきました。
とは言え、チームのカラーもあります。丸写しではなく、見せていただいた資料をベースに、主に低学年の子どもたちの視点で、バスケのルール説明や、うちのチームとして大切にしていることをしっかりと形にすることは何か、このルールブックを作ることをきっかけに、コーチ陣が議論を進めてくださり何度も改訂版を作りました。
何人かの保護者に文字起こしをお願いし、保護者代表が一丸となってまとめに走り、先日無事にリリース。我がチームはファイルに収める形で導入しました。
さ、このルールブック導入でチームはどんな風に変わっていくか!今から楽しみです。
いいなと思ったら応援しよう!