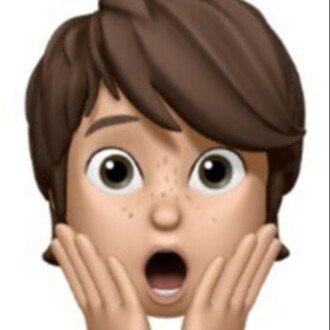【Book Review】成田悠輔著『22世紀の民主主義』を読んで
こんにちは。今日は今話題になっているこの本について、書いてみます。
ちなみに、今7月31日現在、丸善で売れている本3位、ジュンク堂では2位になっているそうです。
成田さん、大人気。
まずはこの本に感想を書く前に
政治と選挙について書かれたこの本を読む前に、私自身についてちょっと書かせてください。
大学で、政治学を学びました。お世辞にも超成績がいい学生だったわけではないです。かと言って、落ちこぼれだったわけでもなく、必修科目の授業は、ちゃんとクラスに出て、ノートも取っていたし、ノートのコピーが出回ることもありました。
ジャーナリズムとマス・コミュニケーションのゼミでは、ファッションという珍しい切り口で卒論書きましたが、社会学やメディア論の観点から、偉そうに分析し仕上げ、大学の研究誌にも投稿し掲載されました。(なので大学の図書館に自分の書いた文章が一生残されている形です→完全に自己満の世界です)
ですが振り返ってみて、大学時代に政治について、仲間や教師たちと「議論」する機会が自分的にあまりにも少なすぎたと感じています。米国に渡り、夫と出会い、夫と彼の仲間たちが日々政治の話題を「酒のつまみ」に語り合う様子をみて、初めて自分の知識や経験が浅はかなことに気づきました。
ちなみに、夫の仲間はDemocratsもRepublicansもいるのですが、前者の支持者はいづれも仕事でも政治に絡んでいる人たちなので、おそらく米国人全てが彼らのように常に議論しているわけではないと思いますが。
日本帰国後、それでも友人たちと、今の政治の問題点について議論する機会はなかなか作れてこれませんでした。それが変わったのは、コロナ禍で、同じ大学出身で、パパ友として「教育」視点でいろいろな意見交換ができる仲間と親交を深めるようになってからです。そしてすっかりハマったClubhouseという音声SNSでした。
後者については、毎週本についてのルームを開設していて、そのモデレーター仲間と、過去2回選挙を前に、政治関連の特別ルームを開きました。普段から政治への関心の高い男性陣、東さんと古山さん2人から、よく政治家の本や、国際政治にまつわる書籍を紹介してもらうこともありますが、この特別ルームでは、もう少し具体的な今の政党の歴史や特色なんかも共有してもらうことで、書籍やニュース記事といった、「文字に書かれたもの」とは違った温度感で、理解することができました。もちろん彼らのバイアスも理解した上でです。
勉強熱心なもう一人の女性モデレーターMieさんは、選挙権を手にしたばかりのお子さんを育てる母親でもあり、私は質問するのが仕事のジャーナリスト。ルーム中は絶えず質問や意見が活発出て、過去政治関連の勉強会ルームは、人数にかかわらず、一人で悶々と考える以上に、有意義な時間になってきたとみんなが感じています。(モデレーター一同いつも面白かった!で終わるんで)
さて、民主主義において、メディア/ジャーナリズムの原点である新聞は、「政治のチェック機能(Government Censorship)」として存在し、発展してきました。しかし、大衆から個人に情報拡散が当たり前になった今、マスメディアの存在価値や意義は大きく変わっています。
ちなみに、この論文はインターネット時代の今はむしろ「Censorship=検閲(政治のチェック機能)」が盛んな時代だ、と言ってます。一方で
ハンガリー、エクアドル、トルコ、ケニアなどの国々では、当局者が批判的なニュースを削除し、国家メディアブランドを構築することによって、ロシア、イラン、中国などの独裁国家を模倣しているのです。また、ジャーナリストを攻撃する鈍重な手段を補完するため、より巧妙な手段を編み出している。
つまり、メディアは政治に攻撃されったり、利用されるようになっているということです。フェイクニュースしかり、その出どころは、ある特定の政治グループを支持する人だったりしています。
実際これだけ多くの情報が溢れる中で、「PV=読まれていることを数字化したもの」が重視されるのは、そのメディア自体に金銭がやり取りされている以上必然であり、結局読まれるモノを提供することにメディアの制作側が流れていってしまうのは、避けようがないのです。
一方、政治に関心を持ったある一定の人の中から、50%そこそこの選挙率で選ばれた政治家に、国と社会の成り行きをお任せする現状。それに対する半ば諦めと、どうでも良い感は、学生時代からぼんやりもちづつけていました。そして、今いくら政治に関わる議論をする機会が増えても、拭えないのが現状です。
そんな中で、成田さんの本を読みました。
読了後の印象
「ワクワク」と合わせて、「妙な絶望感」を感じたのが私の印象です。詳しく書いてみます。
「ワクワクした部分」
私たちが一体どんな政府や政策を望んでいるのかということを語ってくれる情報全てを汲み取ってしまおう。それが私が「民意データ」っという言葉でさっくり呼んでいるモノの正体である
民意を客観的にデータとして汲み取り、アルゴリズムに判断を任せることによって出来上がる民主主義の自動化や無意識データ民主主義という考え方。成田さんはその様子を「民主主義を諦めてみてはどうか」という言葉にもしている。
さらに、アルゴリズムに任せた時、問題が起きたらどうするのかという反論として、こうも言っている
むしろ間違いを歓迎してもよいのではないか。アルゴリズムとランダム選択による間違い込みの込みの選択は、どの選択が正しいのかわからず混乱した私たちに、世界の新しい一面を見せてくれるかもしれないからだ。
これは、言えてる〜と思ったところです。先ほど書いたように、「誰が政治家になっても大して変わらないのでは?」と思っていた自分的には、このくらいやってみてもいいのでは?と思ってしまいました。
さらに、無意識民主主義の思考実験や社会実験を実行している人たちについても、本文で紹介されています。さすが学者の成田さん。「引用」がめちゃくちゃあるので、早速こちらのnote拝読しました。
P235で紹介されている内容ですが、実際このnoteや彼の提案する政策提言まで目を通した人ってどのくらいいるのかなぁ。すごくワクワクする&めちゃくちゃ現実的な内容かと思います。
ぜひともこのあたり今一気に実際に形にできそうなのは、DMMさんあたりかと。
個人的にも、DMMの地方創設事業部さんとお仕事させていただいた経験がありますが、彼らならやってのけそうです〜さらっと!そのお仕事は、ここに。ちなみに、福岡県大川市なら、このネオドリブンな提案聞き入れてくれそうな気がする。
結局人と人との出会いだったりするので、ミラクル起きるといいですね。。
妙な絶望感
一方で、本著から、2つの絶望感も感じてしまいました。
一つ目は冒頭
若者が選挙に行って「政治参加」したくらいでは何も変わらない
を改めて、データに裏付けされて説明された時。
もう一つが
政治家はネコとゴキブリになる
と書いている点です。特にこの点については、間接代議民主主義での政治家のになっている役割を
✔︎政策的な指標を決定し行政機構を使って実行する「調整者・実行者としての政治家」
✔︎政治・立法の顔になって熱狂や非難を引き受け世論のガス抜きをする「アイドル、マスコット、サンドバッグとしての政治家」(P219引用)
と書いていて、特に後者について、いづれ政治家はネコとゴキブリになると、何とも衝撃的な書き方をしています。
さらに、
Vtuberが生身の政治家の代わりになって、誹謗中傷を引き受け、仮装人が鬱や自殺にまで追い込まれるとスッキリする・・・
ちょっと生々しい表現を目にして、正直未来に対してのちょっとした絶望感を感じてしまったわけです。
その上で、先のワクワク感を実装できる社会が、自分が生きているうちに起こりうるのだろうか、、、という「本当の絶望感」に襲われたところです。
ちなみに、この本の感想を聞かれた友人には
日本の社会の仕組みをどんでん返しするには、明治維新並みに宇宙から宇宙人到来が起きるか、太陽フレアで全てストップするか。富士山噴火とか起きないと多分無理。そして後者2つはもしかしたら近々起きるかも。
という若干世紀末的な返答をしました。
しかしながら、成田さんは終わりに
どんな小さなものでもいいから、私たち一人ひとりが民主主義と選挙のビジョンやグランドデザインを考え直していくことが大事なのだと思う。
と書いておられるように、私たち一般市民に今できることは、やはり議論なのかもしれないと思いました。成田さんは学者なので、ご自身がおっしゃるとおり、実装したり、実行するのはきっとこの本を読んで、感じた人たちの中になるのでしょう。
意見交換、議論したい方Welcomeです。
クラハでも、Twittterでも。PMください。
#未来の政治を考える
#本の感想
#thebookoftheday
#成田悠輔
#ワクワクと絶望
いいなと思ったら応援しよう!