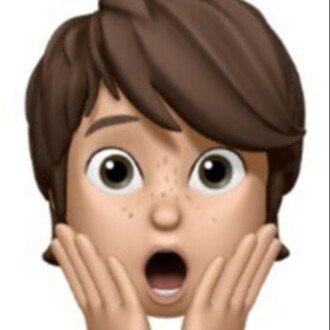Book Clubへの参加を習慣化したら、「読書とは」を問われる経験に、毎回痺れている
今年のはじめから、月に1回、台湾在住台湾系米国人で、社会派の作家、ミシェル・クオさんと大学教授のアルバート・ウーさん夫婦のブッククラブに定期的に参加している。
ミシェルとアルバートが選ぶ本が、日本語に翻訳されているケースはほとんどない。(以前『カラマーゾフの兄弟』がピックアップされたことはあったけれど)
そして、彼らが選ぶ本は、いつも社会や人種や政治的な点で、何らかの課題や疑問を呈するようなことを投げかけた作品ばかり。普段日本の書店で「人気作品」として並ぶ代物とはちょっと違う。
その分、これらの作品が日本語になってリリースされる機会は残念ながらあまりないと思う。そして、いづれの作品も、米国なり英国なり、欧米諸国の政治や社会背景を理解していないで理解することはなかなか難しい。10年米国に住んだ私でも、知識の足りなさに、毎回恥ずかしい思いをしないか必死だ。
だがこういうプレッシャーでもないと、自分の知識はこれ以上広がらないこともわかっているので、ある意味中毒的に自分を追い込んでいる。(割とドM)
さて今月の本は『Orwell's Roese(オーウェルのバラ)』だった。ちなみにAmazonのおかげで、日本でも簡単に本は手に入る。
翻訳家の柴田さんが、SWITCHのオンラインで、こんな風に本を紹介いしていることからも、日本でもすでに知っている人もいるかもしれない。オーウェルと言えば、『1984』が代表作。日本でも名著に挙がる作品で、世界で最も有名な「ディストピア(暗黒な世界←→ユートピア)」を描いた作品だ。
でもオーウェルが「売れない作家」だった時代や、その時代に週刊紙に寄稿していたことなどは、実はあまり知られていないのではないか。
作家の人生や背景を知った上で作品を読むことで、新しい視点を得ることができることを、最近特に感じている。作家に関する本を読んでから、その人が書いた作品を読むと、すごく新鮮だし、染み通るように感じる。(そういう意味で、100分de名著は本当に素晴らしい番組!)
さて今回、レベッカ・ソルニットという作家が、ジョージ・オーウェンの人生の中で、彼が「花を植え、愛で続けた人物だった」という点から、この本を書いている。
私は以前『1984』を手に取って、本から溢れ出すその暗黒なエネルギーに、なかなか読書が進まず、途中で放り出した経験がある。ソルニットは、オーウェルが花に対して感じていた「自然が与える喜び」が、作品の随所に記述されていると指摘しているが、そういう視点でオーウェルの作品を読んでみたら、実は新しい目線で読めるような気がしている。
なのでもう一度、作品を手に取ってみようという気になった。
『Orwell's Roses』の話しに戻ると、本著はオーウェルのバラの話しだけに止まらず、ソ連時代の強制労働とレモンの木の話しや、米国のバラ産業を支えるコロンビアの過酷な労働市場の話しへ飛躍する。
ミシェル・クオやBook Clubのメンバーたちは、レベッカ・ソルニットはとても「正直な」作家だと表現した。反対の感情や感覚を持つ人がいることを想定して書くのではなく、彼女の個人的が持つ「楽観的」で「肯定的な」感情が随所に積み上げられた言葉の数々が書かれていることがその理由だと話す。
それは逆に、社会に対して否定的な部分を捉えがちな人からすると、少しこそばゆい感覚になるのだという。
ソルニットという作家自身、「左派」に属する作家として知られているわけえだが、政治作家という点で共通点を持つオーウェルという作家を、英ガーディアン紙曰く「トレードマーク」というほどの楽観主義な視点から捉え直したこの作品。ファッション誌から、日刊紙まで、米英の著名なメディアがこぞってレビューを掲載するほど。
なるほど。
私にとっては、この本を題材に議論するBook Clubのメンバーたちのやりとりを聞いているだけで、開眼する瞬間の連続だった。それは、作品を読み込んで意見をいう、という以前に、おそらく本を読む姿勢そのものが、なんと稚拙なのか、と気付かされたからかもしれない。
自分だったらどう捉えるか、という視点を持って読み込んでいないことが理由かもしれない。共感する部分にだけ着目し続けているからかもしれない。
批評する目線、疑問を持つ目線が足りない。
さらに改めて本を題材に、人と語り合う経験が圧倒的に少なかったことに気付かされた。
「読書は一人でするもの」
「読書は、自分一人の世界」
そんな風に思って生きてきた。
しかし、違うのかもしれない。
自分が得た知識や、本を通じて見聞きした情報を、もっと人と共有するべきなのだ。それこそ「国語の時間」は「語り合う時間」であるべきなのでは?
読書の楽しみ方そのものをアップデートさせられるほど、今朝もしびれる影響を受けたブッククラブだった。
ちなみに、ミシェルとアルバートがリリースしているニュースレターでは、有識者たちによるエッセイやレポートが送られている。
そして、毎週水曜日の朝のthe Book of the Day!
そろそろスピンオフクラブでも開催したいなぁと思う今日この頃。
どうでしょう?
いいなと思ったら応援しよう!