
『カルピスの効率的な薄め方ではなく、原液の濃度を高めることにより、多くのリソースを割く』
きちんとした文章(しかもちょっと長め)はPCじゃないと無理なので、前振りとしてこちらを共有。
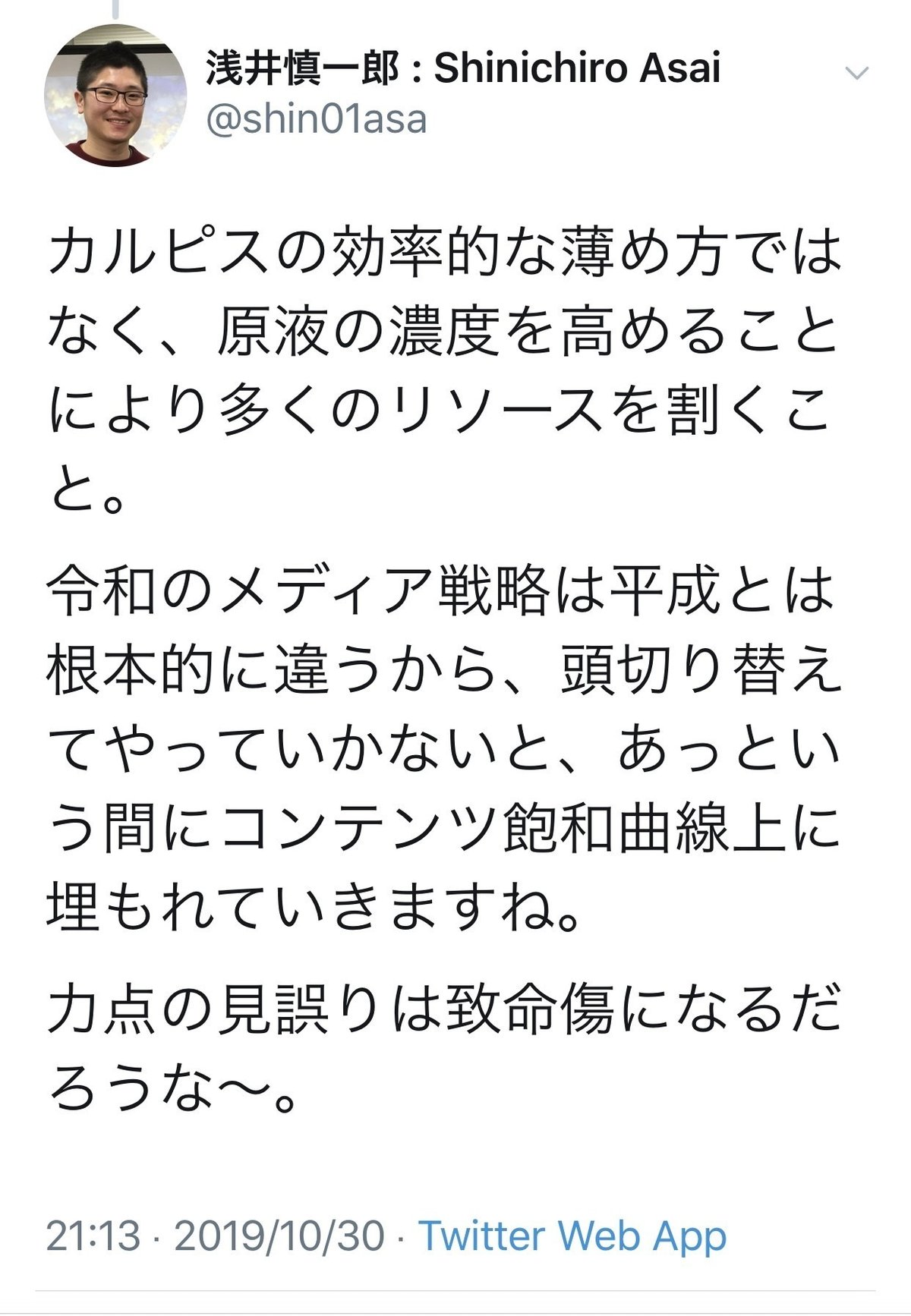
浅井さんのTwitterアカウントはこちら
ほんと、無料でそれこそ高濃度な情報をキャッチアップできるから、Twitter終わったとか全く思わない。Twitter様々。笑
これはあらゆるジャンルに転用できる基礎概念であり、firandoはまさにそうして創り出したのでシェア。

濃度が薄いものを量産するとどうなるか。
ずっと薄いものを作り続けることに、力を注ぐ。薄いものを広げると、更に薄くなる。濃くなることはない。
創ると拡げるは両輪で同時進行、と創るフェーズの時の話をしたけど、この時創るの濃度を限りなく高くすると象徴になり、競合がいない唯一のものになるから、拡げるのフェーズに集中できる期間、使えるリソースが増える。
ちょっと分かりにくい表現かもしれない。
でも、そういうことなの。
ただ思うのは、この濃度を上げる重要性にまず気づけない、って事と
具体的にどう濃度を上げるのか、手段を持たない、って要因があって
だけどこれらは実は『事象を観察する習慣』『気づきを言語化する習慣』『思考を深める習慣』によって解決できる。
要は、考えることから逃げる、向き合うことから逃げると、濃度はいつまで経っても上がらない、なんですよね。
(体調管理のためにあっさりです。)
