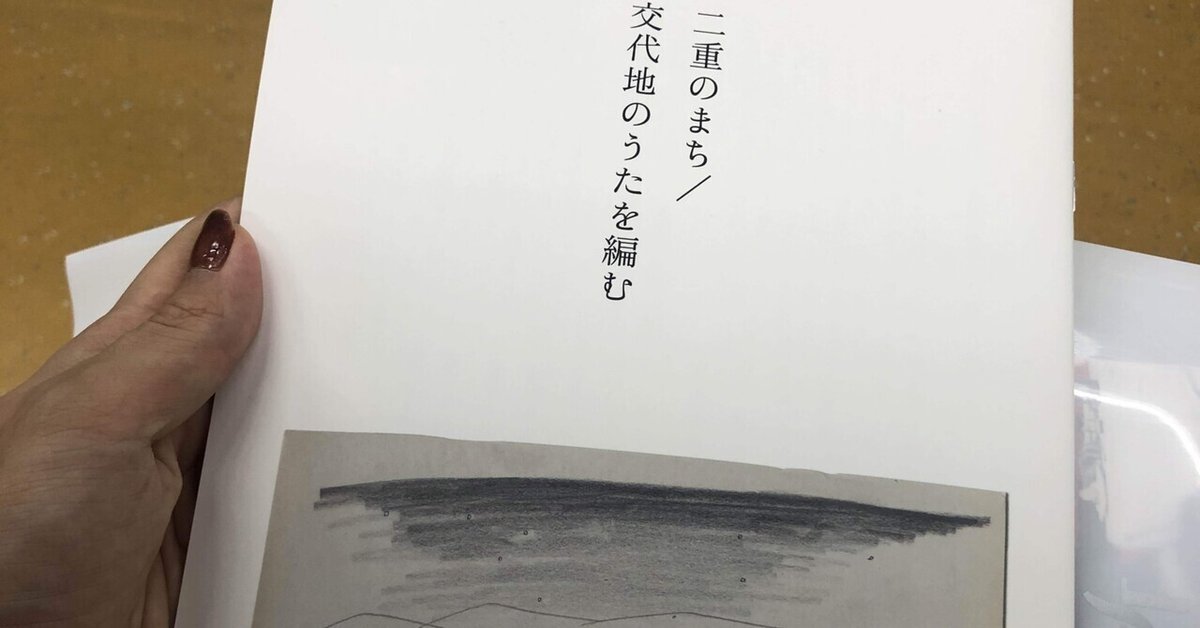
小森はるか、瀬尾夏美『二重のまち/交代地のうたを編む』を見ました。
(Facebookに書いた日記をやや加筆修正して転載)
いわゆる、「ワークショップ映画」と言えるこの作品では、ワークショップ参加者が震災の被災地に赴き、おもに親しい人を亡くした生存者の話を聞く。その生者の語りはほとんど直接映されることはなく、死者ー生者という二者関係に、外部から来た「第三者」として介入することとなるワークショップ参加者によって語り直される。 ワークショップ参加者は、自身の言葉で語れば語るほど残された生者があのとき語ってくれた言葉からは離れていくような気がすると躊躇いつつも、語り直そうとなんとか試みようとする。ここで奇妙なねじれが起きているような感覚にわたしは襲われた。それは、死者と生者という二者関係に、第三者として関わっているはずの女子高校生のワークショップ参加者が、子を亡くした母の語りを語り直すとき、「わたしは母親になったことは無いし、むしろ子供の気持ちで考えたい」と言って、死んだ子供の立場から、生者である母を思いやる言葉を紡ごうとする瞬間だ。ワークショップ参加者は被災地の人々に対しては第三者である。そこには距離がある。だからこそ、「理解しきれない」という思いがあるために、注意深く、被災地で接した生者の心中を気にかける。それが、むしろ、死者が残された生者に語っているような錯覚に襲われる。「あまり心配しないで」と。
無論、これはわたしの錯覚である。死者は語らない。ただ、わたしも日々、生きていて、ほとんど不可能かと思われるような、他者の「心中を察する」ということを、スクリーンのなかに目の当たりにするだけで、もう少し、この星に、この時代にいようと思える。
小森はるかの単独監督作である『息の跡』では、被写体となるタネ屋の佐藤さんが、震災後の思いを、母国語ではない言語で語らざるを得なかったように、今作でも、語りたいけど語りたくないことを語るための迂回が行われる。今回は、あえて第三者が介入することにより、語りえない何かの輪郭をおぼろげになぞっていく。
わたしたちは映像に、そして他者に、まぼろしを見る。『息の跡』におけるタネ屋の佐藤さんも、『空に聞く』におけるFMラジオ局の阿部さんも、語りたいけど語りたくないことを語るために、なんらかの迂回をしているように思えた。そんな彼ら彼女らの姿にわたしは自分の似姿を見る。しかしそれはまぼろしなのかもしれない。わたしは映像のなかに、あるいは他者に、自分の似姿を探そうとしている。しかしそんなものは永遠に見つからないのだ。 ただ、今作を見ると、語りたいけど語りたくないことを語るために迂回する人ではなく、 迂回の起きている状況そのものを見ることで、なにか微かな希望のようなものが見える。
わたしはこの映画を見ながら、なぜか別の映画のことを思い出していた。 ダグラス・サーク『悲しみは空の彼方に』で、自身に黒人の血が流れていることを隠しながら、白人として生きているサラ・ジェーンのことを。
キャバレーの控え室を、黒人である母が尋ねてきたとき、同僚の目を気にして、サラは母を「知り合い」だと言い、冷たい会話を続ける。ただ、母との別れ際、声にならない声で 「ママ」という言葉の形に彼女の唇が動いたときのことを、わたしは思い出していた。 語りたいけど語りたくないことを語るための迂回。その迂回そのものを見たいし、知りたい。そして、わたしも、そのようにしか語れないと思う。
まわりくどい、長い話になりました。
(鈴木史)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
