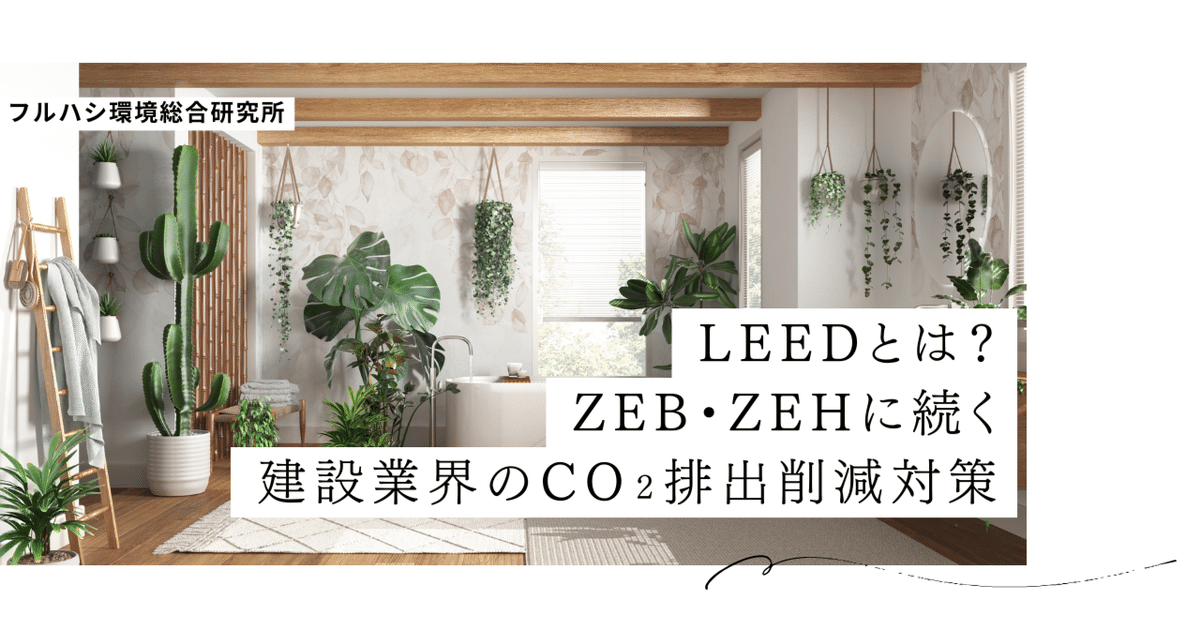
LEEDとは?ZEB・ZEHに続く建設業界のCO₂排出削減対策
はじめに
わたしたちの生活に欠かせない建物が環境にどのような影響を与えているのか、考えたことはあるでしょうか?
世界の産業別CO₂排出量の37%は建設関連といわれており¹⁾、建設や運営には大きな環境負荷が伴っています。設計から運用・廃棄までのすべてのプロセスにおける環境負荷低減・持続可能性が求められる中で、LEEDは環境にやさしい建物を評価する国際的な基準として注目されています。
1)2023 Global Status Report for Buildings and Construction, UNEP
本記事では、LEEDの基本的な概要を詳しく解説します!
(やや長文ですが、本記事1本でLEEDの全体像を把握いただけるよう丁寧に解説・まとめています。最後までお付き合いいただけると嬉しいです。)
LEEDの基本概要
LEED(Leadership in Energy & Environmental Design)は、建物の環境性能を評価し、認証するシステムです。米国グリーンビルディング協会(USGBC)が開発・運用し、GBCI(Green Business Certification Inc.)が認証審査を行っています。LEEDでは、環境負荷低減のみならず、運用コストの削減、入居者・利用者の幸福度や生産性の向上も求められていることが特徴で、以下の7つのゴールを掲げています。
1.気候変動の抑制
2.個人の健康やウェルビーイングの向上
3.水源の保護・涵養
4.生物多様性と生態系サービスの保護・回復・復元
5.持続可能で再生可能な材料製造サイクルの推進
6.環境により配慮した経済の構築
7.社会的公平性、環境正義、コミュニティの健全性、QOL(Quality of Life;生活の質)の向上
LEEDは、建物全体の企画・デザイン(設計)から調達、施工、運用管理まで、あらゆるフェーズにおいて適用されます。認証を受けることにより、建物の環境性能・持続可能性を客観的に示すことができます。
LEEDの認証システムの種類
LEEDにはプロジェクトに応じた異なる評価システムがあります。2025年1月時点の最新バージョンであるLEED v4.1²⁾では、以下の認証システムが提供されています。認証を受けるには、まずこの中から認証システムの種類と、そこに分類されたビルディングタイプを選択することになります。
2)LEED v5の開発が進んでおり、2024年5月にパブリックコメントの募集が締め切られるなど、リリースに向けた検討が行われています。

(「LEED v4.1, USGBC」をもとにフルハシ環境総合研究所が作成)
(1)BD+C(Building Design & Construction) - 建物の設計と建設
BD+Cは、建物の新築や、既存建物の大規模な改修工事における設計と建設が対象になります。設計段階から建設にかけての環境負荷の低減、エネルギー効率、材料の選定、資源のリサイクルなど、多岐にわたる要素が評価されます。
(2)ID+C(Interior Design & Construction) - インテリアの設計と建設
ID+Cは、内装がすべて完了した状態の空間が対象になります。室内空気、照明、温度、音環境など、内部空間の質を改善するための取組みが評価されます。
(3)O+M(Operations & Maintenance) - 既存ビルの運営と管理
O+Mは、少なくとも1年以上は使用されていて、運用・メンテナンスが実行されている建物が対象になります。建物が運営されている段階で、エネルギーや水の使用効率、メンテナンス方法、リサイクル活動などが評価されます。エネルギー消費の削減や、室内環境の改善、建物のライフサイクル全体にわたる環境負荷の低減が重視されます。
(4)Residential(HOMES) – 住宅
Residentialは、新築もしくは大規模改修の住宅のうち、戸建住宅・3階以下の低層住宅・4~8階の中層住宅が対象になります。BD+Cとほぼ一緒のように見えますが、「住宅」の場合はBD+Cを適用することはできません。エネルギーや水の効率的な使用(省エネ、節水)、快適性・耐久性・健康の改善、環境に配慮した素材の使用など、入居者が重視する要素が評価されます。
(5)Cities &Communities – 都市とコミュニティ
Cities & Communitiesは、人々のQOL向上を目的としたプログラムで、形態・規模・発展段階問わず、都市またはコミュニティが対象です。都道府県・市町村などの行政区画は「都市」、それ以外は「コミュニティ」に分類されます。計画段階(プラン&デザイン)か既存(再開発含む)か、都市かコミュニティかの組み合わせにより、4通りの認証システムが選択できます。社会的公平性・生活の質・生活水準の向上が評価の重点要素になります。
(6)ND(Neighborhood Development) - エリア開発
NDはLEED v4.1では含まれていませんが、NDを含むLEED v4は現在も適用継続できますので併せてご紹介します。
NDは、住宅用・非住宅用問わず、新規の土地開発または再開発が対象になります。複合的なエリア開発の計画段階から設計・建設までが評価され、計画段階か建設済み(完成間近~完成後3年以内)かによって評価システムが分岐します。交通利便性や歩行者にやさしいデザイン、省エネや節水など、持続可能で環境にやさしい街づくりとそこを利用する人々のQOL向上に関する要素が重視されます。
LEEDのクレジットカテゴリー(評価項目)
認証システムは、いくつかのクレジットカテゴリー(評価項目)で構成されています。評価システムごとに構成は異なりますが、全部で12のクレジットカテゴリーがあります。
統合的なプロセス(Integrative Process:IP)
計画の初期段階から環境保護(省エネや節水など)を視野に入れた設計に関する要件。立地と交通(Location & Transportation:LT)
用地選定にあたっての交通利便性や環境配慮(交通によるCO2排出削減、コンパクトな開発など)に関する要件。マテリアルと資源(Materials & Resources:MR)
建設材料の調達、再生材、地産地消、リサイクル、LCA(ライフサイクルアセスメント)に関する要件。水資源の保全と節水(Water Efficiency:WE)
建物内外における節水に関する要件。エネルギーと大気(Energy & Atmosphere:EA)
省エネとCO2排出量削減に関する要件。サステナブル・サイト(Sustainable Sites:SS)
用地利用にあたっての環境配慮(生物多様性・水資源保全、光害軽減など)に関する要件。室内環境品質(Indoor Environmental Quality:IEQ)
空気の質、日射と眺望を取り入れたデザインなど、室内環境の質の向上に資する要件。スマートな立地選択と周辺とのつながり(Smart Location & Linkage:SLL)
開発エリアの選択と敷地利用にあたっての、自然資源の保全やスプロール化(無秩序・無計画な開発)の回避、交通利便性などに関する要件。近隣街区のパターンとデザイン(Neighborhood Pattern & Design:NPD)
歩行者にとっての快適性(生活利便施設の充実度、周辺エリアとの接続性など)に関する要件。グリーンなインフラと建物(Green Infrastructure & Buildings:GBI)
建物およびインフラの建設と運用に係る環境性能に関する要件。革新性(Innovation:IN)
LEEDのクレジットカテゴリーで規定された要件を上回る性能や革新的なアイディアに関する要件。ボーナスカテゴリー。地域特性(Regional Priority:RP)
地理的・気候的条件の違う世界のさまざまな地域が、それぞれ優先すべき事項(環境、社会的公正、公衆衛生など)への配慮に関する要件。ボーナスカテゴリー。
それぞれのクレジットカテゴリーは、必須項目と選択項目で構成されています。必須項目はグリーンビルディングとして必ず達成しなければならない最低条件です。選択項目は、グリーンビルディングとしてのクオリティ・レベルがさらに高いと評価されるための条件で、選択項目で獲得したポイントに応じてLEEDの認証レベルが決定します。
各評価システムはボーナスカテゴリーを含め合計110ポイントで、獲得ポイント数と認証レベルの関係は次のとおりです。
• Certified(標準認証):40〜49ポイント
• Silver(シルバー):50〜59ポイント
• Gold(ゴールド):60〜79ポイント
• Platinum(プラチナ):80ポイント以上
ZEB・ZEHに続く、建設業界におけるCO₂排出削減に向けて
冒頭で「世界の産業別CO₂排出量の37%は建設関連」と書きましたが、これは日本においても同程度の割合であるといわれています³⁾。資材の製造~調達~建設~運用~解体に至る「建物の生涯」を通じて排出されるCO₂のことを「ホールライフカーボン」といい、このうち、建物の運用(冷暖房などのエネルギーや水の利用)に伴って排出されるCO₂を「オペレーショナルカーボン」、建物の建設(資材製造、調達、輸送、施工・建設、修繕、廃棄・リサイクル)に伴って排出されるCO₂を「エンボディドカーボン」といいます。
3)建築物のホールライフカーボン削減~これまでとこれからの取組み~(P2), 経済産業省

脱炭素の達成にはホールライフカーボンの削減が不可欠です。日本においては、オペレーショナルカーボンの削減はZEBやZEHの普及により進んでいる一方で、エンボディドカーボンの削減は欧米に比べて遅れています。そのような中で、LEEDはエンボディドカーボンの削減にも貢献する取組みとして注目を集めており、日本におけるLEED認証件数は毎年増加しています。

無料ESGウェビナー「環境ラベル(EPD)活用によるLEED対策」
フルハシ環境総合研究所ではLEED認証取得に寄与する環境ラベル(EPD)の取得もご支援しています。「EPDって何?」「LEEDとどのように関わっているの?」と思われた方もいらっしゃるかもしれません。詳細は今後の記事で取り上げたいと思いますが、「早く知りたい!」という方には当社の無料ESGウェビナーをご紹介します!
当社では、LEEDの基本から知りたい方や認証取得を目指されている方、建材メーカーの方向けに、無料ESGウェビナー「環境ラベル(EPD)活用によるLEED対策」を2025年1-2月にかけて開催しています!
ESGウェビナーアジェンダ
建設業界における脱炭素に向けた動向
LEED認証概要
EPD概要
LEEDとEPDの関係
建設業界における脱炭素の取組みとLEED認証に有利にはたらくEPDについて、わかりやすく解説しています。本記事を読んでから参加されると、より理解が深まること間違いなしです。ぜひこの機会にご参加ください!
無料ウェビナー「環境ラベル(EPD)活用によるLEED対策」のお申込みはこちらから。

さいごに
CO₂排出量割合の多い建設業界における環境に対する取組みは、これからの社会にとって非常に重要です。建物の設計から運用、廃棄に至るまでの全プロセスでの取組みが、わたしたちの生活環境の改善にもつながります。今後のさらなるLEEDの普及により、多くの企業や個人がこのような取組みに関心を持ち、実践することを願っています。そして、地球全体の環境保護と持続可能な発展への貢献につながることを期待しています。
最後まで読んでいただきありがとうございました!
