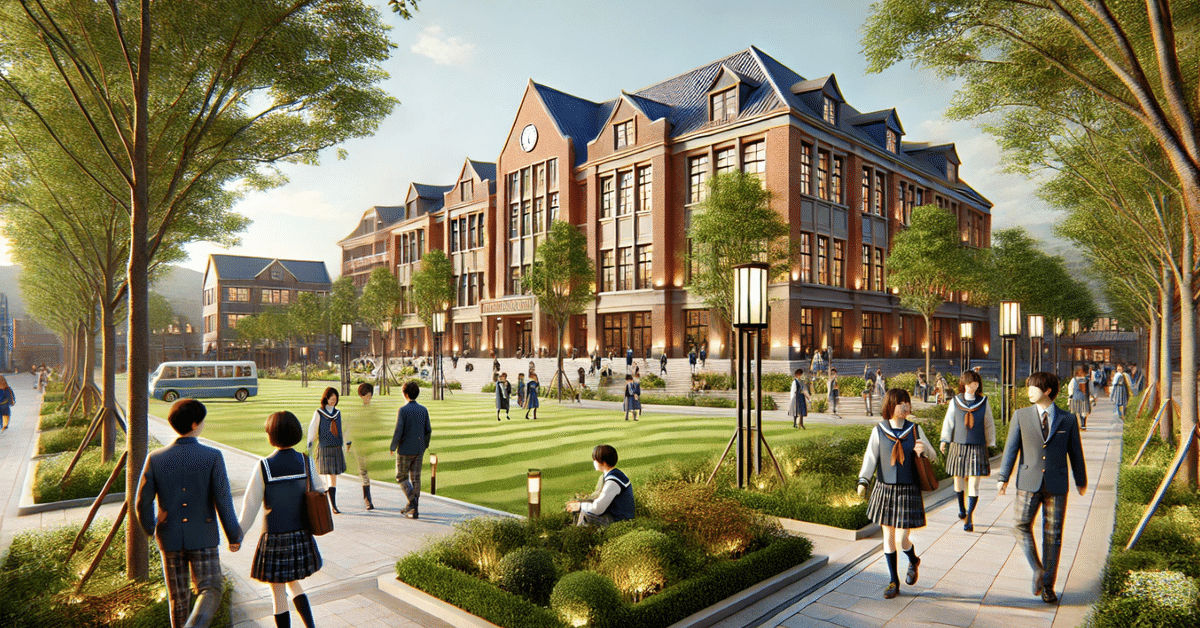
リアル!慶應幼稚舎生ってどこに進学するの?
慶應義塾幼稚舎は、幼稚園や小学校受験を考えるご家庭から注目を集める小学校のひとつです。
幼稚舎に入学すると、どのような進路が待っているのでしょうか?
幼稚舎から中学、高校、大学まで続く進学の流れや、大学卒業後の進路について、OBの目線でわかりやすく解説していきます。
幼稚舎から付属中へ
進学の割合
幼稚舎生は小学6年生を終えると、自動的に中学受験の必要がなく、慶應義塾の中学に進学する道が開かれます。ほぼ100%が付属中へ進学します。
男子の場合は「普通部」、「中等部」、「湘南藤沢中等部」、女子の場合は「中等部」もしくは「湘南藤沢中等部」から進学先を選ぶことができます。
幼稚舎からは、男子は64%が普通部、34%が中等部に、女子はほぼ全員が中等部に進学します。
私の在学時からしたら、男子の中等部への進学率が倍以上になっていて、私学全体の共学人気の影響を感じますね。
進学の理由
↑の通り、普通部は日吉にキャンパスがある男子校、中等部は三田にある共学のため、皆さん親御さんと相談の上、場所や男子校・共学、部活等によって進路を決めていました。
私の同級生で言えば、兄弟が先に進学している場合はその進学先を選ぶことが多かったです。
特に姉がいる男子が中等部に進学するパターンは多かったです。
また、年にもよりますが運動部で選ぶ子もいました。
当時は普通部のラグビー部が東日本代表になるほど強かったので、そのために普通部に進学するような体育会男子もかなりいました。
教育方針
この内部進学により、早い段階から一貫した教育を受けることができ、慶應義塾の伝統的な教育理念である「独立自尊の精神」を、さらに深く学ぶ機会が得られます。
普通部は、とにかく勉強に励める中学校です。
とくに有名なのが「理科のレポート」です。中学ながら理科の中でも生物・化学・物理など科目別に学ぶことはもちろん、それぞれの科目で週1回以上「実験」を行い、毎週手書きでレポートを作成します。
どのような実験で何を証明したか、そのうえで得られる示唆は何か、といった論理的思考力の基礎となるような内容を学ぶことができます。
湘南藤沢中等部では、先進的な教育プログラムが導入されており、特にICTを活用した授業が特徴です。
子どもたちは自分に合った環境で学びながら、次のステップへと進んでいきます。
付属高校への進学
進学の割合
中学を卒業すると、原則全員が自動的に付属高校に内部進学が可能です。
男子は「慶應義塾高等学校」、「慶應志木高等学校」、「慶應湘南藤沢高等部」、女子は「慶應女子高等学校」「慶應湘南藤沢高等部」へと進学します。
実際の進学先としては、アクセスで決めるパターンが多いと思います。
私の同級生は、男子はほとんど全員が日吉にある慶應義塾高校、女子は三田にある慶應女子高等学校に進学します。
それぞれの高校では、学問だけでなく部活動や生徒会活動などを通じて、より広い視野で自己の成長に取り組む環境が整えられています。
大学進学
慶應義塾の特徴は、大学までの一貫教育体制が整っていることです。
幼稚舎に入学すると、内部進学によって原則として慶應義塾大学への進学が保証されます。
東大受験、医学部受験する同級生も一定いますが、幼稚舎生の95%が慶應義塾大学へ進学します。
慶應義塾大学では、法学部、経済学部、医学部、商学部、理工学部、環境情報学部など、多彩な学部があり、生徒は自分の興味や適性に応じた学部へ進学します。
内部進学の場合、文系ならば経済学部、法学部への進学が人気です。
理系ならばもちろん医学部が圧倒的に人気理で、その席を狙って同級生がしのぎを削って争います。
当然毎年の学力や志望学部のバラつきにもよりますが、医学部志望者は3年間での10段階評価が最低8.5以上・法学部政治学科は7.2以上・経済学部(B: 経済史専攻)は7.0以上程度の成績を取れれば入れるかとは思います。
さらに、学部の学びに加えて、慶應義塾大学はサークル活動やインターンシップの機会も豊富です。
大学時代に幅広い経験を積むことで、卒業後には多様な進路が開かれるのが特徴です。
まとめ
幼稚舎から大学まで続く一貫教育のメリットは、学問を超えて、広く「人間力」を育てられる点にあります。
慶應義塾で培われる「独立自尊の精神」は、大学卒業後も生かされ、各界で活躍する原動力となっています。幼稚舎から大学までの道のりは、単なる進学ではなく、人格形成や将来の可能性を大きく広げるステージです。
慶應幼稚舎への入学を考えるご家庭にとって、未来の道筋をイメージすることで、教育の意義をより深く理解するきっかけになれば幸いです。
