
稙田優子 写真展 「分室」 を観た
仙台写真月間2022の最終週にSARP(仙台アーティストランプレイス)で行われた稙田優子さんの「分室」という写真展で、哲学者のジャック・デリダの差延という概念が可視化されたような刺激を受けたので、気が付いたことを書いておきます。

分室というガラスで囲まれた公共のコミュニティ・スペースが今回の主題。前半は分室に行くまでのプロムナードが続き、後半の横の距離がとれる壁面に、分室のガラスの映り込みをテーマにした写真が連続します。ビジュアル的に美しい写真群です。
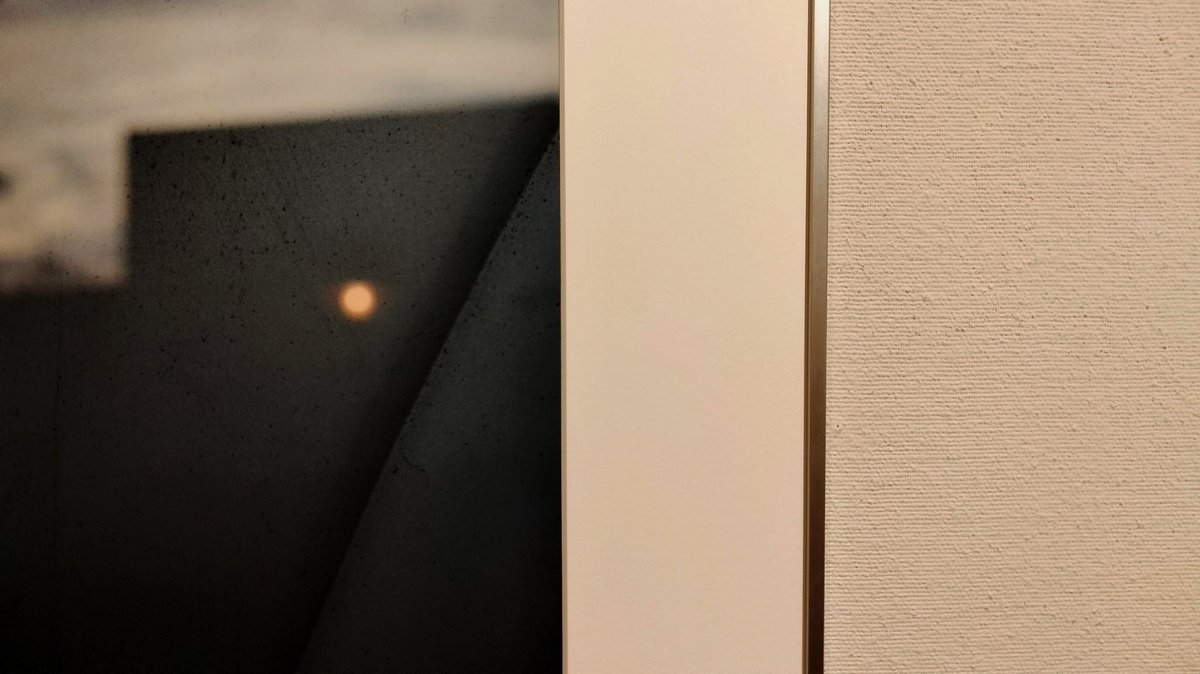
作家は「なぜ私は撮るのか」という問いが自己の作品の表層に現れていると考えているようで、写真家の坂本政十賜さんと合同で行ったギャラリートークでも、稙田さんは今回の写真展を「分室という空間を私の中に置く行為」という説明をしていました。この言葉は今回の写真展を考える場合非常に重要で、作家は今回の展示で、分室という空間に自己の同一性を定置しようと企図していることが容易に理解されます。

自己同一性について考えてみます。理論的に自己同一性は完全なる現前でなくてはなりません。完全なる現前は過去や未来といった時間的制約から解放されていて、つまり時間が止まっているブラックホールの特異点のようなものです。時間という制約から解放されたこの特異点は、「わたし」にとって居心地のよい空間かも知れません。しかし現実にはそんなものはあろうはずもなく、特に写真はそれを許してはくれないのです。なぜなら写真による表現においては、現前は常に先延ばしされているからです。写真というメディアはその特性上、差延たる運動から自由になる権利を与えられていないことがその理由です。写真は並べられることによって、またはテキストによって意味が組み替えられてしまうのです。

または、内部から外部が始まっている
今回の写真展で重要なのは、撮影者は分室の内部から外部を見ているのではなく、外部から内部を眺めている点です。「分室という空間を私の中に置く行為」という作家の発言からも明らかなように、作家にとって内部は自己同一性の特異点なのです。しかし作品では内部は容易に観察することはできず、鑑賞者が見るのはもっぱら外部の映り込みです。しかもその映り込みは、作家が分室に至るまでに歩いてきたであろう空間、風景なのです。分室の撮影を時間的現在とすれば、鑑賞者が見ている映り込みは撮影者が過去に経験した事象ということになるのです。
つまり写真表層に分室内部は現前することはなく、時間的差異たる過去の空間を鑑賞者はもっぱら見せられるわけです。ここに内部たる現前は永遠に先延ばしされるている、つまり差延が起こっているのです。

作家の自己同一性は、自己たる現前とは時間的にも空間的にも全く違ったもの=差異=他者によって浸食されていることに、鑑賞者は気が付きます。同時にその他者は遅れて現在に到来してくるのです。これが差延です。つまり差延の運動法則によって自己同一性の現前は永遠に先延ばしされるのですが、同時に自己は他者の到来なしには構成されえないのです。
今回、稙田さんは時間について語ることがなかったような気がします。ギャラリートークでも参加者から「空間には時間も含まれている?」という質問がでていました。前回の「雨包、粒子」でも同様ですが、稙田作品の魅力は時間的差異たる他者性だと思うのです。今回の写真展でその思いがますます強くなりました。
