
超危険!中東ドライブは「スリル満点」、またの名を「絶体絶命」
あらすじ
魅惑の本屋がヨルダンにあったので「ここで働かせてください!」とアタックし、いろんな国のスタッフと本屋に住み込みしていた連載。
●死海に行くはずだったのに

ヨルダンの本屋で働いていた日のこと。ヨルダン滞在中のほとんどが小雨か曇りだったのだが、珍しく天気がよい日があり、嬉しくなった。カラッとした晴天は本当にレアだったのだ。
私とラウラ(イタリア人スタッフ)は、店長とある約束をしていた。それは、「今度晴れた日があったら、死海に連れて行ってほしい」というものだ。なのでやっとの晴天に、女子たち2人はウキウキしていた。
【死海とは】塩分濃度が高すぎるあまり、勝手に浮いてしまうことで知られる海。中東にある観光地。
すぐに店長に駆け寄って、「死海に行こう!」と言うと…。
「そうだね。でもなんつーか、気分じゃないっつーか。むしろ『街歩きしたい』まである。だから、今日は街歩きするぞ!!」

ハア?!?!!?
私とラウラはもちろん抗議した。話が聞こえていたのか、姉的存在であるスタッフのアリスは「やれやれ」と呆れている。
「店長!?!?こんな天気、私がヨルダンにいる間に次あるのかも分かんないんだよ!?今日こそ死海日和でしょう!?」
「そうよそうよ、私たち、死海に行くの本当に楽しみにしてたんだけど!?!」
しかり、店長の眉はピクリとも動かない。「とりあえず2人とも、車乗ってー。街行くよー。」

もうだめだ。私たちは、店長の気まま具合に絶句した。そうして、「中東の地で、特に目的地も告げられないまま車に乗せられる女子2人」という、聞く限り最高に怪しげな状況が生まれてしまった。
●フロアをぶち上げるボンネット
ああ、こんないい天気なのに…。車に乗せられる私たち。
「ヨルダンではね、各国の環境基準でアウトになった古い車を輸入して使ってるんだよ」と店長。おいおい、アウトだからって輸出して手放せばその国はOKなのか?この星の空気は全て繋がっていることを知らないタイプの国なのか。
そうして世界中で「アウト」になった車たちが列をなす車道は排気ガスがものすごくて、窓を閉めていても車内までひどくガスの臭いがする。私は当然の如く体調が悪くなり、ずっと目を閉じていた。

しばらくブンブン進んでいると…
ギャあああああああああ!!!!
この車内で、めっちゃくちゃでっかい叫び声が聞こえた。私とラウラの声だった。
なんと、乗っている車のボンネットが突然垂直にバカッッ!と開き、車内の人間(運転手含む)は、前が完全に見えなくなってしまったのだ。だからと言って止まっても後ろの車に追突されるから、もう走り続けるしか無かった。
あまりにびっくりして、もうガスがどうとか言っている場合ではない。
「ギャアアアアアア!!!!あ、わかった♪ これ死ぬやつじゃん!」
その時の光景は脳に焼き付いているが、もちろん写真は持ち合わせていない。だいたい、こんな絶体絶命の時に「これも記録記録っと!」と呑気にパシャパシャ撮る人がいたら、そいつが犯人である。
私はボンネットに罠を仕込んだ犯人でもなければ、戦場カメラマンほど撮影に重きを置いているわけでもない。しがない書店員である(号泣)。リアル・ワイルドスピードの状況で、叫ぶ以外、何ができただろうか?
この状況で、私たちの命は店長のハンドルにかかっているが、視界が遮られているため、もうどこが前かも分からない。後部座席で叫ぶ女子たちをよそに、店長は「くそっ!くそっ!」といいながら、横の窓から腕を伸ばしてボンネットをボコボコ殴っている。
おいおい、これはどういう状況ですか?もしこのカオスを解説できる人がいたら、もうアラビア語でもいいから解説してほしかった。
しかしよく聞いてみると、店長は「くそっまたか!」と言っているではないか。「また…か??」おいおいヨルダン。運転中にボンネットが垂直に上がるなんて、何度あってもいいとでも思っているのか?
店長は、なぜ何にも衝突しなかったのか分からないまま無事に(?)道端に車を停め、力ずくでボンネットを閉じた。腰に手を当て、大きく頷いて「おし。じゃ、行くか」。何事もなかったかのように出発。
万が一、この車はもう大丈夫だとしても、なんだか"この国の感じ"だと、対向車のボンネットが突然上がって、パニックになってこっちに突っ込んでくる可能性もあるよな?ゾッとした。
ヨルダンで一番危ないのは、治安でも衛生面でもなく、ボンネットだったのだ….!
はは〜ん、なるほど。
だから中東の地で、空飛ぶ絨毯が発達したんだな。
だって、絨毯にはボンネットが無い。
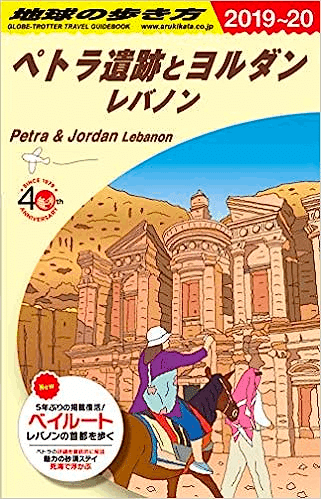
まったく!ヨルダンって、なんて危険な国なんだろう!(もしかして:周知の事実?)
(他の危なかった日はこちら↓)
●全てを素通りする街歩き
魂が抜けていると、いつの間にか街に着いた。いつも本屋にいるだけだから(それで十分幸せなのだが)、ヨルダン観光というのは心が踊った。いい天気だし。

と言っても、何かがおかしい。向こうに見える「あれ絶対世界遺産だろ」という感じの遺跡や、カラフルで美しい街並みを、店長は早足で素通りしていくのだ。
「あれ?私たちってさ、あの辺をじっくり見るべきなんじゃない?」「そうよね?なんか店長、『街歩き』って言っても、本当に歩いてるだけじゃない。…今度2人でゆっくり来ましょ。バスで。」私たちはそんな会話をしながら、ひたすら店長について行った。
●車道で久々の再会すな

ある程度街をぶらぶらしたら、また車に戻った。
今度はどこに行くのだろうということでまた、排気ガスのすごい車で走っていると…。
叫び声が聞こえた。「ウオオオオオオ!!!」
なんと、今回は店長の叫び声。
今度は一体なんなんだ。すると…
後ろの方を走っていた車が、私たちの車の横まで、現実と思うにはあり得ない状況で隙間を縫いながら割り込んできた。もう何が起きているのか分からないが、その運転手が「車線」の意味を知らないことだけは確かだった。
無数の車が団子状態で走っている状況でそんな運転ができるなんて、きっと彼はマリオのように命が何個もあるタイプの人間なのだろう。そのマリオの正体は、なんと「店長の従兄弟」だった。
なお、顔はどちらかといえばルイージだったが、それはどうでもいい。

店長は「いま偶然、バックミラー越しに目があって気付いてさ!こっち来いよ話そうぜ、ってアイコンタクトしたんだよ!」と、従兄弟と(車ごしに)久々の再会を果たし、先ほどのボンネットのごとく、テンション爆上がり。マリオカートのようにお互い運転しながら、後部座席で魂の抜けるピーチとデイジーをよそに、窓越しに何やら話している。
そして「おいガールズ!今からあいつの家に行くことになったぞ!」
「はあ?」
もういつものごとく意味がわからないが、私たちは観光そっちのけで店長の従兄弟の家に行った。私は結構ふてくされていた。店長、アンタだけで行ってくれないか。そんで私たちを街に降ろしてくれ。そしたらラウラと遺跡に行って、あとはバスで帰るからさ..と思ったが、いつの間にか私たちはアラブの魔力によって従兄弟の家に着いていた。
従兄弟の住居には驚いた。なんと、日本の家とほとんど変わらない、近代的な家だったのだ!!!ほんっとうに驚いた。へ〜、ヨルダンにも、こういう「直線や平面で構成された家」ってあったんだ〜!いつも暮らしている本屋はでこぼこした曲面のみで構成されていたため、ヨルダンの家って全部そういうものだと思っていたのだ。
そこで私は初めて、「私が暮らしているヨルダンの家は、ヨルダンのベーシックな家じゃなくて『ヨルダンの古民家』的な建物なんだな」と知った。もしこのルイージハウスを見ずに日本に帰っていたら、「ヨルダンの家ってどれも、岩でできてるんだよ!」と真剣に布教するところだった。
多分同じように、もし外国人が日本に来て古民家の集まる村でだけ暮らしたら、自国に帰って「日本の家ってどれも、木造の平家だったよ。床は畳」と周囲に語るであろう。そんな感じになるところだった。
従兄弟の家で、私とラウラは呆れきった。ヨルダン人たちが「アラビア語の親戚トーク」盛り上がっているなか、私とラウラは英語でもイタリア語でも日本語でもなく、世界共通である「女子特有アイコンタクト」で会話をした。
「チラ(え、今これどういう状況なわけ?)」
「チラ(フウ…落ち着いて。もう為す術はないのよ)」
店長の従姉妹ファミリーは私たちを、激辛ポテトチップでもてなしてくれた。「ああ、これを食べ切るまで帰れなさそうだし、食べきっても多分帰れないだろう」と、私はそのスナックをうつろに見つめる。一方で、いい子であるラウラは「でもせっかく出してくれたし…ね、元気出して」と私をヨシヨシなだめながら、辛い食べ物がすごく苦手なのに頑張ってパクパクと食べていて、なんて美しい心の持ち主なのかとしみじみ涙がでた。
やっと彼らのアラビア語会話が終わると、私たちは車に乗って、やっと帰れる …かと思ったら「せっかくこの辺まで来たんだし、本屋に多大な寄付をしてくださったマダムの家に挨拶に行こう」と言い出した。まあいいけれど、私は朝から死海で泳ぐ気満々だったことや、さっき死にそうになったこともあり、もう早く帰って寝たかった。でも車はそのマダムの家に着いた。
「せめて英語で話してくれれば相槌も打てるのに。どういうマインドでマダムの話を聞けというのか…。」と思ったが、いかんいかん。ここはヨルダン。アラビア語を話せない私の責任である。ただ晴れた空を窓から恨めしく眺めるしか、マダムの家でやることは無かった。
●やっと帰宅、なぜ全員生存しているか不明

マダムのお話をいろいろ聞いた後、やっっと本屋に帰った私たち女子は、我らの姉であるアリスの部屋に飛び込んで、今日あったことを全てぶちまけまくった。(アリスは長く本屋にいたので、本屋の中に空いた個室を見つけて、そこに住んでいた)
「ねえ!?本っっ当に、ありえなくない!?!?そもそもさ〜〜死海に行くはずだったのにさー!?」「私たち、死ぬとこだったんだよ!?」
世界中の女子は国籍関係なく、「本当にあり得なくない!?」という話をするとき、KEMIOのごとく早口になることが判明した。
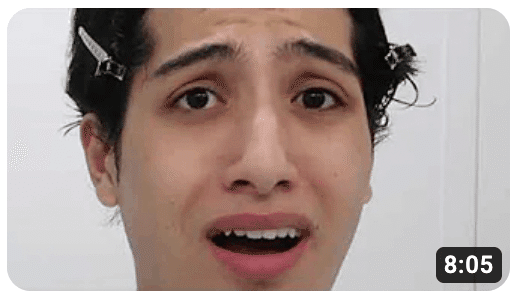
その後私たちは、今日のドライブや街歩きというより、今日のアラビア語リスニングに疲れ切って、爆睡したのだった。

つづく
●次の話:ヨルダンで一番号泣した日
●「ヨルダンの本屋に住んでみた」他の話
いいなと思ったら応援しよう!

