
ちっちゃな王子さま(超意訳版『星の王子さま』) vol.11
ⅩⅥ
そういうわけで、あの子が7番目におとずれたのがこの「地球」だったんだ。
地球ってのは、そんじょそこらの星とはわけがちがっていた。そこにはなんと、111人もの王様がいたし(もちろん、黒人の王様も入れて、ね)、7000人の地理学者に90万人のビジネスマン、それから750万人のよっぱらいに3億1100万人のナルシスト……合わせて、約20億人もの大人たちがいたんだ。
そうだ、この話をすれば君だって、地球がどれほど大きいのかイメージできると思うんだ。つまりさ、電灯が発明される前、この地球に6つある大陸をぜんぶ合わせるとなんと、46万2511人もの点灯夫が必要だった、っていう話をさ。
ちょっと離れたところから地球を見てみたら、それはそれはすばらしいながめなんだぜ。点灯夫たちの大群、その動きはちょうどオペラの舞台でのバレエの動きみたいに、きっちりと規則正しいものだからね。
プロローグは、ニュージーランドとオーストラリア。点灯夫はそれぞれ自分のところの街灯に火をつけて、それからベッドにもどっていく。すると次は、中国とシベリアの点灯夫が舞台に上がってくる。彼らも舞台袖に去っていくと、今度はロシアとインドの出番。その次はアフリカとヨーロッパだ。それから南アメリカ、その後に北アメリカ。点灯夫たちは、決して自分の出番をまちがえたりはしないんだ。あれは本当に感動的だったなあ。
ちなみに、北極にひとつだけある街灯と、南極にひとつだけある街灯。それぞれの点灯夫だけは、いつもなまけた生活を送っていたよ。だってふたりの出番は、一年に2回しかなかったからね。
ⅩⅦ
えっと、正直に白状すると、さっきの点灯夫の話、ちょっと気の利いたことを言おうとして話を盛りすぎちゃったかもしれない。地球のことをぜんぜん知らない人に話したら、地球に対してまちがったイメージをもっちゃうかもしれないから、ちゃんと訂正しておかなくちゃ。
さっきの話だと、まるで人間が地球の全体に広がっているみたいに聞こえちゃったかもしれないけど、本当のところ、人間っていうのは地球の上の、ほんのごくわずかな場所を占めているだけなんだ。たとえばもし、地球に住む20億人の人間全員で何かの集会をしよう、ってことになって一か所に集まって、おたがいにちょっと詰めて立って、きっちりと整列したとしたら、たかだか30キロメートル四方の広場にきっちり収まっちゃうくらいなんだ。太平洋でいちばん小さい島にだって、人間ぜんぶをつめこむことができちゃう。
まあもちろん、こんなこと、大人たちは絶対信じないだろうね。自分たちが地球上でもっと大きな場所を占めてると思ってるから。まるで自分たちが、バオバブみたいにでっかくて重大なものだと思いこんでる。だからさ、大人から「そんなことあるわけない」って言われたら「じゃあ、計算してみなよ」って言ってやればいい。ほら、大人って数字が大好きなんだからさ。あ、もちろん、君たちはそんなばからしい計算で時間を無駄づかいしちゃだめだぜ。そんなことより、君はぼくのことを信じてくれさえすればそれでいいんだ。
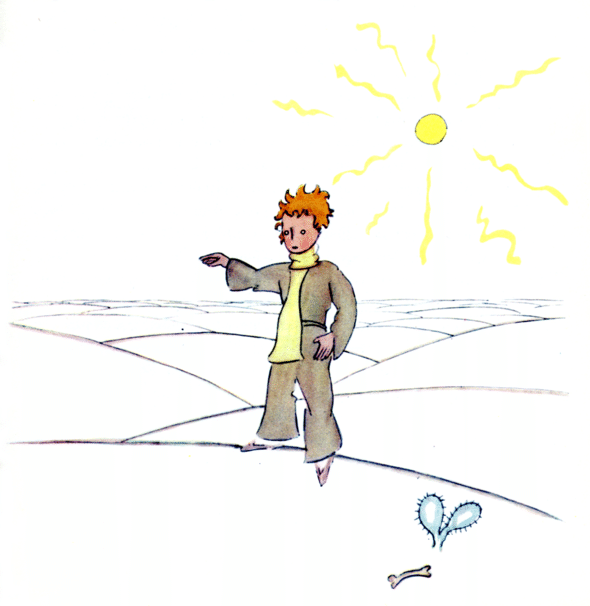
さて、王子さまは、地球にたどり着いて見渡す限りだれひとりいないことにびっくりしたんだ。いちめんの砂の中で、ほんの一瞬、月の色をした輪っかのようなものが動いたのが見えたとき、ちょうど、降りる星をまちがえたんじゃないかと考えていたところだった。
「こんばんは」
でもちっちゃな王子さまは念のため、動いたそれに声をかけてみたんだ。
「こんばんは」
王子さまの声に応えたのは、ヘビだった。
「ボクが落ちてきたここって、なんていう星?」
「地球だよ。地球の、アフリカ、というところさ」
ヘビはそう答えた。
「やっぱり合ってたんだ! ……ねえ、地球には、だれもいないの?」
「ここは砂漠だからな。砂漠にゃだれもいないよ。地球ってのは、でかいのさ」
ヘビはそう言った。
王子さまは近くにあった石に腰かけて、空を見上げた。
「ボクね、思うんだ、」
夜空を見上げながらつぶやくように言う。
「星が光っているのは、みんながいつか、自分の星を見つけるためなんじゃないか、って。ボクの星を見てごらん。ほら、ちょうどボクたちの真上にあるよ……。でも、ああ、なんて遠いんだろうな!」
「きれいじゃないか」
ヘビが言った。
「あんた、どうしてここに来たんだ?」
「ある花とさ、うまくいかなくなっちゃって」
王子さまは答えた。
「ありゃま」
それから、しばらくの沈黙があった。
「ねぇ、人間たちは、どこにいるの?」
しばらくして、ちっちゃな王子さまはまたたずねた。
「砂漠はちょっとさびしいんだ……」
「人間たちのところにいたって、さびしいもんさ」
ヘビはそう応えた。
ちっちゃな王子さまはおどろいて、長いことヘビのことを見つめていた。
「君はおかしな生きものだね」
やっと、あの子はそう言った。
「指みたいに細長くって……」
「だがオレ様は、王様の指よりも強い」
ヘビは言った。王子さまは笑った。
「君は強くなんかないよ……手も足もないじゃないか……旅行にだって行けやしない」
「オレ様はあんたを、船なんかよりもずっとずっと遠くまで、運んでいくことができるんだぜ」
ヘビはそう言って王子さまの足首に、まるで黄金のブレスレットみたいに巻きついた。
「オレ様はふれたやつを、そいつが元いた大地に返してやるんだ」
ヘビは続けて言った。
「だけど、あんたはピュアだからな。それに、星から来たときてる……」
王子さまは何も言えなかった。
「あんたが哀れだよ、あんたみたいなもろいやつが、こんな岩で固められた地球にいるなんて。なあ、もしあんたがあんたの星が恋しくてたまらなくなったら、オレ様があんたのこと救ってやれるだろう。オレ様なら……」
「わかった、もうよくわかったよ!」
ちっちゃな王子さまはヘビの言葉をさえぎって言った。
「ねえ、どうして君はぜんぶ謎かけみたいな言い方をするのさ?」
「オレ様が、すべての謎を解くのさ」
ヘビはそう言った。
そうしてふたりはまた、静かに黙りこんだ。
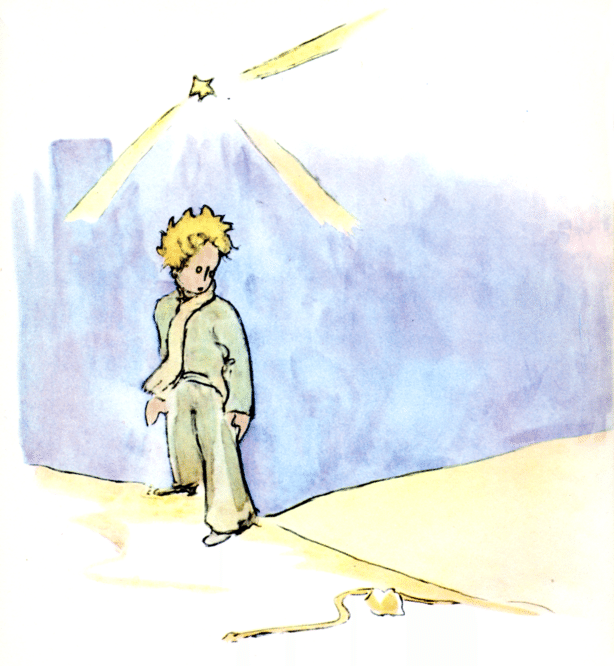
いいなと思ったら応援しよう!

