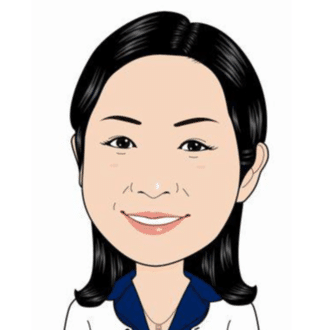リーディング・マラソン#9
本を読む→一定時間が来たら他の人に、読んで感じたことを語る、というのを繰り返すリーディングマラソン。今月で9回目。
朝、洗面所やシャワーを使う時間が家族みんなでぶつかって、後回しで待っていたら、時間がぎりぎりになってしまった。
今日読んだ本は写真の3冊。
限られた時間なので、もちろん最初の方しか読めていないけれど、その本を読む見通しみたいなものがたった。
1冊目の「はじめての哲学史」は、哲学史は日常からかけ離れたものではなく、現代に生きる私たちが利用できる貴重な原理をつかみだしてきた歴史であると捉え、時代のなかでどのような問いが生まれ、先人たちがどのようにその問いについて考えて答えようとしてきたか、そしてどのような原理をつかんだのかを丁寧に紐解いてくれている。
2冊目の「問いを問う」は、青学での哲学の授業を元に書籍化されているそうだけれど、解説が詳細なので「哲学的に考える」ということをじっくり学べそうだという手ごたえがあった。
3冊目の「子供とともに哲学する」は、タイトルに子供と入っているけれど、内容は全然大人向けで、多少哲学の知識がないと読みづらい。もともとはソクラティク・ダイアローグについての解説があるとのことだったので絶版になっているものを購入したのだけれど、どのように哲学が教育のなかで実践されているのか、丁寧に書かれているのでこれは今の自分に必要な本だなと思った。
今日3冊とも哲学にかんする入門書を選んだのは、哲学対話のファシリテーターに「哲学の知識は必要ない」という言説を真に受けて、そこをおろそかにしている人が案外多いのではないかという懸念から。知識はたしかにそんなに必要ないかもしれないけど、哲学的に考えるという考え方は、哲学対話を進行する上で間違いなく必要なものなので、そのあたりについて学べる講座を企画するためでもある。
試食で終わらせずにしっかり読み終えよう。
他の方が選ぶ本や、読んだあとの共有を聴くのも毎回とてもおもしろい。
自分が手に取らないであろう本を少しつまみ食いできるような感じ。
いいなと思ったら応援しよう!