
【非ロキノン史観】歴代邦楽アルバムランキング 100〜51位
○前回の記事に関する感謝
前回の記事がありがたいことに数多くの方々に読んでもらえてる。
当アカウントは当初フォロワー10人にも満たない極小アカウントであったし、ましてや4万文字を超えるランキングなんて誰も読まないだろな… なんて思ってた。
恐らくあの記事がここまで伸びたのは、Xの音楽界隈の中で紹介して頂いたおかげだろう。


しかも界隈の中でも私が普段から熱心に記事を読み続けてるライターの2人に紹介して頂けた。なんと光栄な!
三代目さんは界隈で見向きもされてなかったCHAGE and ASKAの魅力をnoteで熱弁していた記事を読んで、共感の嵐しかなかった。だって私も子供の頃からチャゲアスが好きだったから。
それにピエールさんも界隈であまり語られないボカロ文化・アニソン文化への敬意が感じられて好きだったし、ランキング記事だって何度も読み返した。
○ロキノン史観とは何ぞや?
このお二方の名前をわざわざ出したのは、記事を紹介してくれたことへの感謝はもちろんだが、それとは別に本記事の狙いを紹介しやすかったからだ。
この記事では、ロッキンオンジャパンを始めとする日本の音楽評論はかなりアングラ気質であり、一般層とオタク層の間で認知の差があまりにも生じている、と指摘している。
そして、それはいわゆる邦楽アルバムランキングを作るにしても起こりうる。
1位「風街ろまん」はっぴいえんど
2位「RHAPSODY」RCサクセション
3位「THE BLUE HEARTS」THE BLUE HEARTS
4位「Solid State Survivor」Yellow Magic Orchestra
5位「ゴールドラッシュ」矢沢永吉
6位「喜納昌吉&チャンプルーズ」喜納昌吉&チャンプルーズ
7位「A LONG VACATION」大滝詠一
8位「空中キャンプ」フィッシュマンズ
9位「黒船」サディスティック・ミカ・バンド
10位「FANTASMA」CORNELIUS
1位「COVERS」RCサクセション
2位「THE BLUE HEARTS」THE BLUE HEARTS
3位「無罪モラトリアム」椎名林檎
4位「空洞です」ゆらゆら帝国
5位「BEAT EMOTION」BOØWY
6位「軋轢」FRICTION
7位「Jealousy」X
8位「熱い胸さわぎ」サザンオールスターズ
9位「VISITORS」佐野元春
10位「SCHOOL GIRL DISTORTIONAL ADDICT」NUMBER GIRL
1位「風街ろまん」はっぴいえんど
2位「SONGS」シュガー・ベイブ
3位「黒船」サディスティック・ミカ・バンド
4位「火の玉ボーイ」 鈴木慶一とムーンライダーズ
5位「一触即発」四人囃子
6位「センチメンタル通り」はちみつぱい
7位「THE BLUE HEARTS」THE BLUE HEARTS
8位「BAND WAGON」鈴木茂
9位「Solid State Survivor」Yellow Magic Orchestra
10位「ひこうき雲」荒井由実
どれも名盤ではある。名盤ではあるのだが…
確かにユーミン、ブルーハーツ、矢沢永吉、サザン、YMO等の著名なアーティストのランクインは全然納得できる。が、問題はそれ以外の人たちだ。
彼らのアルバムは確かに誰にも真似できない個性を放っている。だが、残念ながらセールス・知名度は皆無だ。
そして、そういった認識のズレを指摘する者はあまりいないのが現状だ。
なぜか2ちゃんねらーだけが反応してるようだ…
それらの名盤は果たして名盤なのか?
誤解なきように言っておくが、俺はロキノンやXの音楽界隈含め、そういった世に埋もれてるいいアルバムやアーティストを発掘してくれる人々は大好きだ。
むしろ私はナンバーガールや、ゆらゆら帝国を日本が産んだ最高のロックバンドの1つだ思ってるし、彼らに出会えたのもいわばロキノン達のおかげである。
だがそれゆえに!
そういったアーティストを日本を代表するかのように取り上げてはいけないと思うのだ。
洋楽に当てはめると分かりやすい。
要はこういうことでしょ?

やっぱ違和感あるよね?
この違和感の正体って下世話な言い方だと歴史としての『格』だと思うんですよ。つまりビートルズやMJ達はしっかり売れて業界のトレンドを作り、それが今日に至る歴史として紡がれてるわけだ。
しかしそれ以外のアーティストはあくまで歴史の陰に隠れて支持を集めているといった具合だ。
はっきり言おう、この手の邦楽アルバムランキングは大幅な見直しが必要なのではないか?
裏の歴史ばかりに固執して、表の歴史が語られて無さすぎじゃないか?
そう思い、こうしてこの企画をやるに至った訳である。
ただ、これはともすればアングラなアーティスを完全に無視してしまう暴力的な行為に繋がりかねないし、どこまで基準を決めるべきか、かなり迷った。
そんなこんなでモタモタしてた矢先に、先程のピエールさんに先を越された。
結論から言うと、実に素晴らしいです。メジャーなアーティストとマイナーなアーティストとのバランスが絶妙で、いわゆる歴史の『取りこぼし』も極力防げてるような内容だったと思います。
おかげで、本記事のコンセプトはもっと突き抜けてみることが出来た。
つまり『もしもメジャーなアーティストのアルバムのみを選出したら?』というわけだ。
○注意
先に言っておこう。当ランキングは普段だったら絶対に入ってるはずの名盤をあえて除いてる。はっぴいえんど、SUGER BABE、フィッシュマンズ、ゆらゆら帝国、スーパーカー、ナンバーガール、くるり…全て登場しない。
ミッシェルも迷ったが、除外した。
さらにはTHA BLUE HERBやキングギドラやブッタブランドから連綿と続くアングラヒップホップのレジェンド達も無視した。
彼らの偉大さがあって今のヒップホップシーンがあるのはもちろん理解してるし、なんならTBHの1stは俺が生涯で1番衝撃を受けたアルバムだ。
でも、正直2015年辺りにMCバトルブームが来るまで、一般層からは『ラッパー=チェケラッチョ』とかいう雑な理解しかされてなかったと思うんですよ。評論家側からしても、正直HIPHOP受けいれられるのが遅かったと思います。だって大半はロックリスナーですし。
まあいわば選出されるアーティスト達は、普通の人に聞いても「ああ!この人ね!」となる人達、もしくはテレビで懐メロとして紹介される人達といった具合だろうか。
そしてもう1つ注意点、というか選出条件なのだがベストアルバム、ライブアルバム、コンピ盤も選出可にする事にした。
ニューミュージックが完全に台頭する前の歌謡シーンは明らかにシングル主体であり、アルバムによって芸術作品を作ろうとする意識が薄かったためである。
少し抵抗感がある読者もいるだろうが、事実ローリングストーン誌のアルバムランキングにはチャック・ベリーのベストアルバムだったりJBのコンピ盤が普通にランクインしているのでね。
とまあ、前置きが長くなったので、さっさと紹介に移りたいと思う。
100位 藤圭子『新宿の女』

藤圭子の登場を皮切りに、それまでジャズ、ブギ、ハワイアンなどそれぞれ微妙にルーツの違っていた流行歌に対し「演歌」と名づけたことで、流行歌自体がフォーマット化されることとなる。それもこれも藤圭子のオールラウンダーな歌唱力が成立させているのだろう。
奇しくも翌年の1971年以降から、筒美京平,阿久悠率いる昭和歌謡が黄金期を迎え、吉田拓郎,井上陽水率いるフォーク(ニューミュージック)も台頭していく。これをJ-POPの黎明期と考えると、このアルバムが邦楽のスタート地点と考えてもいいのかもしれない。
99位 KAN『ゆっくり風呂に浸かりたい』

些細な日常の些細な幸せを歌にする余りに日本人らしいソングライター KANの多幸感溢れるアルバム。どうしても「愛は勝つ」のようなピアノ弾き語り系のイメージが強いが、割と意匠を凝らしたプロダクションをする職人的な1面も垣間見える。「プロポーズ」「永遠」などもっと評価されるべき煌びやかな名曲で溢れてる。
98位 美空ひばり『オンステージ』

正直美空ひばりに関して残されてる資料はどれも音が古く、今のところレコード会社もそれを乱雑にコンピ盤などにして売り出しているため、可哀想になる。その中でもこのライブアルバムは他と比べて格段に音が良く、少しでも「歌謡界の女王」としての美空ひばりの歌唱力の凄まじさを味わえるだろう。
97位 スパイダース『スパイダース No.1』

60年代初頭のビートルズ達が与えたロックの初期衝動は日本にも伝播し、それを1番ダイレクトに表現してるアルバムがこれだ。
全体を通して、彼らの技術力の高さがひしひしと伝わってるだけでなく、フレッシュ溢れるビートと日本語の歌詞との融合がまだ難しかった時代で、その試行錯誤感が味わえる。
特に、複数のメンバーが交互にヴォーカルを担当するというアプローチは、他の日本のバンドには見られない独自のもので、バンドとしての一体感と多様性が光る。
この後GS(グループサウンズ)の人たちは歌謡秩序に飲み込まれていくが、本作はその前の刹那の衝動を切り取った傑作。
96位 サザンオールスターズ『タイニイバブルス』

サザンの3rdアルバムにあたる今作は、彼らのディスコグラフィーの中でも初期から中期にかけての過渡期の作品ではあるが、実験性と楽曲の強度がバランスよくまとまっていて、「コミックバンド」としてのサザンの側面が最も現れてる作品ではないだろうか。
このアルバムで、桑田佳祐の独特な歌い回しはさらに成熟し、さらにブルース、ビッグバンドジャズ、レゲエなど幅広い音楽的素養が色濃く反映されている。アレンジメントの観点からみても新田一郎と八木正生が加わったことで、アルバム全体の統一感が生まれた。
また、桑田ワンマンから脱却して、より民主的な制作スタイルを模索していたのもこの頃ならではのものであり、「私はピアノ」や「松田の子守唄」などメンバーがそれぞれリードヴォーカルを担当する愛らしい楽曲も収録されている。
95位 REBECCA『poison』

レベッカの最高傑作は一般的には「Mayby Tomorrow」とされてるが、彼らの集大成とも言うべき内容はこっちなんじゃないかな。事実上のラストアルバムであり、全編にわたってNOKKOの怒りと情念が表現されており、より内面に追求する作品となっている。
「MOON」では失われた少女時代を慰撫し、
「NERVOUS BUT GLAMOROUS」は女性の嫉妬に近いヤンデレ的な挑発を見せる彼女。NOKKOのキャリアの中でもまさにピークと言える表現力だ。
また、バックで演奏するバンドサウンドもこれまた絶妙で、デジタルレコーディングの全盛期の攻撃的で派手な音が聴ける。
94位 松任谷由実『U-miz』

松任谷由実の通算25枚目のオリジナルアルバム「U-miz」は、80年代後半のバブル期には時代を象徴するアーティストとして期待を一身に背負っていた彼女だったが、今作ではそれを一旦捨て、「90年代のユーミン像」にふさわしい自由な雰囲気に満ちてる。
エキゾチックな大ヒットチューン「真夏の夜の夢」はもちろん、アコースティックグルーヴとナバホ語が融合した「HOZHO GOH」や大胆なファンクチューン「只今最前線突破中」などキャリア屈指の異色作が入っており、40歳に差し掛かった彼女の創作意欲が感じられる。
かつてのデジタルな音色はなりを潜め、アコースティックな作りが施されていて当時はファンの間でも賛否両論だったらしいが、現代の耳で聴くとこのくらいのユーミンがいちばんしっくりくるし、聴き返すたびに新たな発見がある作品。
93位 美輪明宏『白呪』

スピリチュアルの人なのか、はたまた声優なのか美輪明宏という存在はミステリアスに包まれてるが、この人はそもそも歌手であり、作曲活動にも旺盛だった時期がある。「白呪」は数少ない彼のオリジナルアルバムであり、当時の彼の圧倒的な表現力と社会的なメッセージが詰まった問題作だ。本作には、紅白歌合戦での「ヨイトマケの唄」や、従軍慰安婦をテーマにした「祖国と女達(従軍慰安婦の唄)」など、他では聴けない戦前戦後の原風景を描いた貴重な曲が収録されており、やはり時代の生き証人なだけあって、ただの反戦歌に収まりそうもない文字通り呪詛のような戦争に対するメッセージが伝わってくる。
そしてその強烈すぎるメッセージに耐えうる彼の表現者としての実力を体現した一枚だ。
92位 misia 『Love is the message』

宇多田と共に、空前のR&Bディーバブームを巻き起こしたMISIA。2作目の本作で、彼女の歌唱力はより幅を広げる。
スウィート・ソウルな「Believe」や、アシッド・ジャズ風の「花/鳥/風/月」、ディスコ・ソウルの「One!」など、多彩なサウンドを難なく歌いこなす彼女は素晴らしいの一言に尽きる。
楽曲のプロデュースには、佐々木潤や松井寛、島野聡などの才能が結集しており、アルバムの構成力とMISIAの歌唱力とソウル・ミュージックへの深い理解がバランスよく組み合わさった秀作。
91位 嵐『how's it going?』
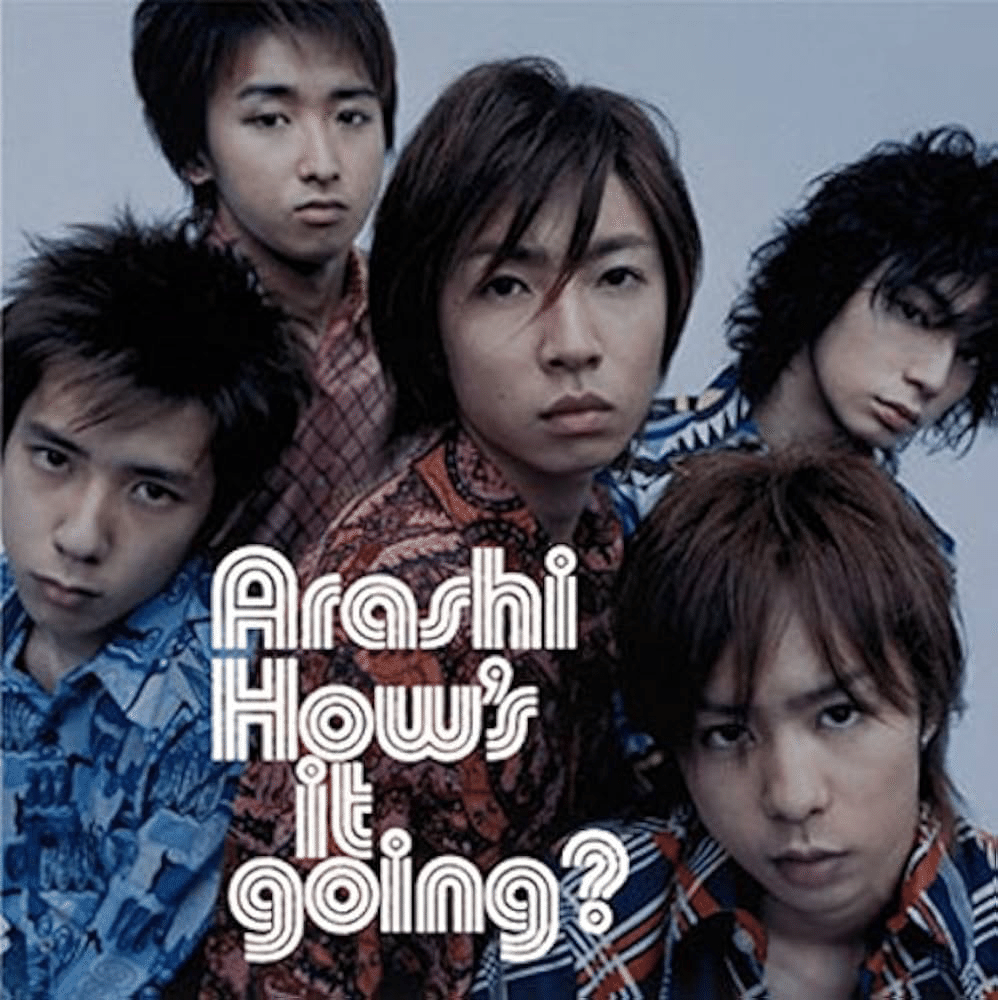
前作「HERE WE GO!」で独自のミクスチャー路線を切り拓いた嵐が、さらなる進化を遂げたサードアルバム。売上で見ると、この時期かなり苦戦したようだが、そういったものも気にしない吹っ切れたような挑戦意欲が伝わる。むしろメンバーの個性が溢れたこういうノリが今のような閉塞感が漂う時代に響くのではないだろうか。
ブラックミュージックに接近したファンキーでパワフルな歌とラップが今作の最大の特徴で、DJのスクラッチ音など細かなギミックも施されてる。
この時期は特に櫻井翔のラップや大野智のボーカルに対する称賛が多く、正に実力派アイドルといった具合だ。ハードなナンバーに加え、「Blue」や「Walking in the Rain」などファンの間でも隠れた人気を誇るバラードも収録されている。
90位 久保田利伸『Bonga wanga』

ジョージ・クリントン、ブーツィ・コリンズ、メイシオ・パーカーといった豪華ミュージシャンを迎えてニューヨークでレコーディングされた作品。彼の音楽的嗜好がこれまで以上にダイナミックに表現された意欲作で、ファンク、ゴーゴー、アフロなど多彩な要素が濃密に詰め込まれている。R&Bを極めるとやがてアフリカに行き着くのだ。「MAMA UDONGO」、LIVING COLOURのVernon Reidが参加した「MIXED NUTS」、レゲエテイストの「No More Rain」など、今までの彼にはなかった新境地を見いだしてる。
また、「大ボラ of LIFE」や「Love under the moon」など、多彩な楽曲を自在に歌いこなす久保田自身のボーカルが印象的であり、彼の音楽的な充実ぶりと実力を再確認させる作品となっている。
参加ミュージシャンの超一流の演奏に、久保田の圧倒的な歌唱力が加わり、非常に重層的で味わい深いアルバムに仕上がっており、久保田にとっても、日本のR&Bシーンにとっても重要な作品である。
89位 小泉今日子『N°17』

小泉今日子ほどクリエイティブを感じさせるアイドルはいないだろう。
前作『koizumi in the house』でのハウスミュージックへの接近に続き、本作ではさらにアバンギャルドな方向性を探求している。
アイドルポップとしては大胆すぎる表現や心理描写を盛り込み、全体的に彼女の内面が伝わるスリリングな作品だ。
藤原ヒロシや屋敷豪太、ASA-CHANGなど、当時のクラブミュージックに精通したプロデューサーたちを起用し、ダブやラヴァーズ・ロック、UKソウルなどの多彩な音楽性を取り入れているのもすごいところ。彼女のずば抜けたアンテナが捉えたこれらの才能が、『N°17』のエッジーな音楽性を支えているわけだ。
また、このアルバムは単に最先端を追い求めるだけでなく、1950年代や1960年代のポップミュージックへの愛情も感じられる内容となっており、単純な流行歌としての感覚と両立させているのも魅力。
88位 佐野元春『someday』

日本語ロックの歴史を振り返る上で、佐野元春ほど独創的な歌詞の乗っけ方をした人はいないんじゃないかな。英語を散りばめた散文詩のような歌詞は前の世代のビート感覚では絶対になし得なかったものである。そしてそのスタイルは本作をもって、ひとつの到達点に達する。
初のセルフプロデュースによる本作は、どの曲も日本語ロックの可能性を広げるものであり、小気味いいロックから「ロックンロールナイト」のような壮大なナンバーまで多種多様だ。
全体的には、当時大瀧詠一との交流もあってか、フィル・スペクターのような大味のアレンジがみられる。
ちなみに、このアルバムの発表した後に佐野はNYに拠点を移し、後世に語られるオルタナティブな問題作を作ることになるが、それは本記事ではあえて選出しなかった。
87位 安室奈美恵『Queen of Hip-Pop』

2000年の『break the rules』以降、プロデューサー小室哲哉の手を離れ、プライベートでも変動があった安室奈美恵。本来ならここで歌い手としてのキャリアは下降線を辿っていくはずなのだが、彼女は歩みを止めなかった。「SUITE CHIC」という当時最新鋭のR&Bのプロデューサーを制作陣に加えるプロジェクトによって、彼女は第2の黄金期を迎えることになる。
これまでのイメージを捨て、いかに素晴らしいダンスチューンを作るかというプロジェクトのプロデューサーとしての側面がますます磨かれてゆく過程でこの作品が生み出された。
ビート感覚からリリックまで当時の洋楽のタイムラインに忠実に沿っており、他のR&Bディーヴァと異なる手段で、J-POPと洋楽との真の和洋折衷ともいうべき独自のスタイルを確立している。「Want me,want me」で魅せるティンバランド風のトラックや「No」のような前半と後半で目まぐるしく変わる楽曲展開も何もかもが前衛的だ。
リリースから時間が経つ中で、本作は安室奈美恵の再評価を果たし、ファンからの信頼を再確認させる一枚となった。
86位 Dragon ash『viva la revolution』

1999年、日本語HIPHOPの歴史において、20歳の若者であった降谷建志が「革命」を成し遂げた。ミクスチャーロックを踏襲しつつ、日本人が苦戦しがちだったHIPHOPのビートとラップを軽々と吸収してみせたのだ。そしてそれがミリオンセラーを記録。DragonAshは単なる斬新な音楽性を作ったのではなく、言葉遊び程度の感覚でしか捉えられてなかったラップを硬派なものにしてみせたのだ。
もちろん彼らはそういったHIPHOPの普及を抜きにしても、ジャンルレスな感覚が持ち味のバンドであり、10代の心を的確に掴むカリスマ性すら持ち合わせている。この作品を聴いて改めて、そのパワーと影響力を再確認してみよう。
85位 ZARD『Today is another day』

ZARDはかなり迷ったがこの作品がやはりベストな気がした。
セルフカバー多めなことで、改めて坂井泉水のボーカルの魅力が再発見できる一作であり、原曲の世界観に加えてZARDらしい世界感の広がりを見せる。彼女が歌えばどこか夏の切なさやノスタルジックを感じてしまうのは俺だけだろうか。「DANDAN心ひかれていく」などの原曲との違いを聴き比べれば分かりやすい。
また、織田哲郎のプロダクションも商業ベースになりすぎず、落ち着いたアレンジが施されてる。
84位 Dream come true『The swinging star』

Dreams Come Trueの5枚目のオリジナルアルバムは、300万枚以上の売上を記録し、日本のアルバムセールス史に名を刻んだ一作。
アルバムの楽曲はどれも高品質で、当時のドリカムの勢いとクオリティが感じられる。
ディスコビートやラテン系サウンド、ジャジーなアレンジに加え、ラップを取り入れたファンキーな楽曲など、多彩なスタイルで聴きごたえがある。特に「決戦は金曜日」のディスコビートと「SAYONARA」のラテン系サウンドが見事に融合し、洋楽的なアプローチが光る。「眼鏡越しの空」は、ドリカム式バラードのひとつの到達点かもしれない。
またロンドンでのレコーディングを経て制作されたのもあってか、吉田美和の豊かな表現力が際立っている。
83位 Kiroro『長い間~キロロの森~』

個人的にJ-POPにありがちなピアノバラードのひとつの到達点がkiroroの楽曲だと思う今日この頃。派手さはないものの、その老若男女の心に残る優しいメロディと歌詞は、これからも確実に色褪せることはないだろう。
デビュー作なのに、ベスト盤といってもいい楽曲の強度で、嫌味のない純粋で素朴な愛が全編に染み渡ってる一作。
82位 いきものがかり『ハジマリノウタ』

いきものがかりがいきものがかりたる所以が詰まった作品。
YELLやジョイフルといった最強のシングル陣に加え、古風なメロディーの「秋桜」から芳醇なオーケストラを奏でる「明日へ向かう帰り道」など多彩でカラフルな作品が多い。
恐らく島田昌典や江口亮といったこれまでのプロデューサーに加え、松任谷正隆や本間昭光といったJPOPの手練とも言うべきベテラン職人が参加したのもでかいのだろう。
いつも通りで水野良樹の作曲能力はもちろん絶好調だが、山下穂尊の手がけた曲も駄曲なしなので入門者には持ってこいの1枚。
こうゆう純粋にいい曲が並ぶ作品はわざわざ評価する機会が少ないのだろうけど、僕はしっかり推していきたいです。
81位 和田アキ子『フリーソウル和田アキ子』

和田アキ子のデビュー35周年を記念して企画された本作は、生粋のレアグルーヴマニアである小西康陽が手がけたコンピ盤だ。
当時のソウル色の濃い貴重な初期シングルのB面曲やアルバム収録曲に光を当てており、通から見ても喜ばしい作品ではないだろうか。
何よりも特筆すべきなのは決してソウルフルなR&Bナンバーだけでは無いということだ。アルバム後半からはボサノヴァやバカラックサウンドっぽいナンバーにも手を広げており、彼女がいかに洋楽のグルーヴ感をものにしてるかが分かる。 また、収録曲のいくつかはモノミックスになってたり、現代版にリミックスしてたりと、彼女のダイナミックな歌唱を引き立ててるのも小西の見事な手腕といった所。
今ではもはやご意見番としての印象しかない彼女だが、日本のR&Bの草分けとして久保田利伸以前にゴッド姉ちゃんがいたことを絶対に忘れてはいけない。
80位 きくお『きくおミク6』

ボカロ文化は割とJPOPが下地となって成立しているが、数あるボカロPの中でもきくおのJPOP離れした音使いには元から定評があった。今作はそんな彼が最も長い制作期間をかけて完成させた一枚だ。これまでの作品でも見られた音響や調性、音階の実験はさらに進化し、シリーズ随一の実験性と完成度を誇る。
微分音や超低速BPMを用いた「わたあめ」、定位が上下左右に動く音響派ガムラン「闇祭」、VOCALOID5を駆使した「あなぐらぐらし」など、実験的で挑戦的な楽曲が多数収録されている。特に「昨日はすべて返される」は、ノイズを多分に含み、音の配置や減衰が精密に作り込まれた天才的な一曲だ。
聴けば聴くほどさらに新鮮なリスニング体験をもたらしてくれるこの作品はきくおの狂気を象徴するものだ。
そしてそこまで音世界を作り込む彼を生み出しただけでも、ボーカロイドという発明はやはり偉大なものなのだろう。
79位 B'z『LOOSE』
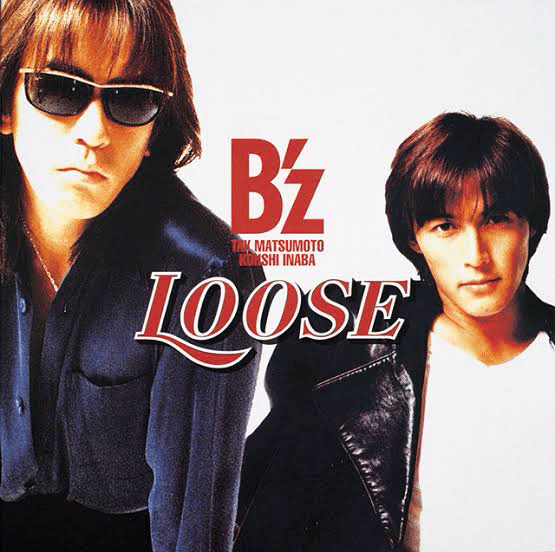
B'zの『LOOSE』は、前作『The 7th Blues』のブルージーな要素を継承しつつ、デジタルと生音を融合させたサウンドが特徴的で、至る所にB'z節が紛れる代表作だ。商業性と実験性が非常にバランス良く、その中にはアルバムタイトル通り、「ザ・ルーズ」や「消えない虹」など、リラックスした空気感が漂う曲も収録されている。
「Bad Communication」のアレンジバージョンもバンドとしての成熟が感じられる内容だ。
洋楽ハードロックを邦楽として翻訳する上でB'z以上に貢献したバンドはいないだろうし、そういう意味でもこの作品の存在感はもっと語ってもいいはず。
78位 小田和正『between the word & the heart』

優れたアーティストというのはこういった地味な作品でも聞き入ってしまえる人だと思うが、この作品が正にそうだと思う。
オフコース解散前に制作されたこともあってかことから、全体的に淡く儚い雰囲気が漂い、歌詞やメロディーにはしんみりとした感情が込められている。後に「ラブストーリーは突然に」を作ると思えないほど非常に素朴で内省的な印象が伝わる。「ためらわない、迷わない」や「静かな夜」などの楽曲は、ファンの中では隠れた名曲。
77位 サカナクション『sakanaction』

サカナクションの6作目にして、バンド名を冠した意欲作であり、自身の音楽性を徹底的に追求した作品。メンバーが集まり、山口一郎の自宅で4か月にわたって録音が行われたこのアルバムは、前半はダンサブルな楽曲、後半は深みのある表現へとシフトする構成が特徴的。
例えば「ミュージック」はネオ80年代を想起させるポジティブなナンバーだが、「映画」「mellow」など内向的でメランコリックナンバーもあり、より自由で前向きなアプローチが取られている。メンバーそれぞれの意向が反映されてるがゆえなのだろう。
肩肘張らずに聞けるサカナクションらしい一作。
76位 山崎まさよし『HOME』

非ロキノン史観ともなると、どこが中心になってくるのかというとやはり90年代のJPOPになってくる。今作もご多分に漏れず90'sのSSW作品の中で屈指の完成度を誇っている。
フォーキーでブルージーなアコースティックサウンドが持ち味の山崎まさよしの多彩な音楽性が存分に発揮され、その素朴なリリックと親しみやすいヴォーカルが印象的。「One more time, One more chance」や「セロリ」など、後に大ヒットとなる楽曲からライブ定番曲「Fat Mama」、元ちとせがカバーした「名前のない鳥」など、初心者にもおすすめできる1枚。
何より彼の高度なギターテクニックが柔らかく広がる音の空間を巧みにコントロールし、その職人技は独特の世界観を作り上げており、かのポール・マッカートニーを驚かせた逸話を持つほどの腕前が光る。
75位 ゆず『ゆず一家』
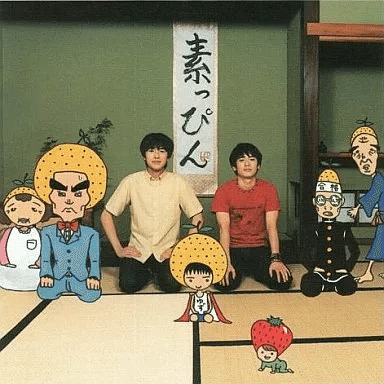
初期のゆずが嫌いな人っていないんじゃない。彼らのメジャーデビューアルバムである今作は路上ライブで鍛え上げたフォークデュオの勢いをそのまま詰め込んでる。名曲「夏色」や「少年」、そして感動的な「贈る詩」など、今でもライブで定番となっている楽曲が並んでおり、北川悠仁の少しダサいけど優しい歌い方、岩沢厚治の気持ち良い高音、そして二人の見事なハーモニーが、このアルバムを通じて心に響く。
特に、「夏色」は甘酸っぱい青春の瞬間を思い出させる一曲で、荒削りながらも勢いがあり、若さ故の直球な表現が逆に魅力となっている初期ゆずのエネルギーを感じることができる。
また、岩沢が作詞作曲を手掛けた「境界線」や「月曜日の週末」では、彼の強烈な叙情性が光り、二人の持ち味のコンビネーションがアルバムのフィナーレを飾る。
ゆずは、このアルバムで路上ライブからメジャーシーンへと飛躍し、後に「栄光の架橋」などで国民的な地位を確立するが、未だにこの作品が原点にして頂点だと思わせる傑作だ。
74位 沢田研二『架空のオペラ』

グループサウンズの貴公子、歌謡界の大スター、ニューウェーブの探求者…時代に応じていくつものペルソナを演じてきたジュリー。
エンターテイナーとしてあらゆる表現を追求し続けてきた彼が行き着いた究極の境地がこれである。
終わりなき表現の旅は、どこまでも耽美的で異国情緒の漂う怪しげな西洋への旅路となる。
それまではニューミュージックの人材らにプロデュースを任せることもあったが、今作では再び阿久-大野コンビを頼り、安定したソングライティングとハードボイルドな質感を呼び戻す。だがその楽曲群は、従来の歌謡曲と似ても似つかないものだ。その多面性は40代に差し掛かる沢田研二の成熟した哀愁と美学とマッチする。
特に1曲目の「指」はゆったりとしたメロディに優雅なAORのエッセンスが散りばめられた神秘的な美しさを内包している。セールスの面から見ても再び返り咲いたかと思われるほど好調な順位を記録した名曲だ。
この作品以降、沢田研二はCo-COLOというバンドを率いて商業性を無視したパーソナルで難解な曲を出し始めるのだが、そういう意味でも今作は彼のキャリアの最大のターニングポイントになってる。
73位 official髭男dism『Rejoice』

出てきた時はブラックミュージック版ミスチルのような認識でいたが、ここ最近の彼らの独自性のある活躍を見ると、その認識を改めなければならない。
米津玄師やking gnuにもいえることだが、音楽としてオルタナティブな試みをやりつつも、ポップスとして成立させようとする心意気にはプロフェッショナルでプログレッシブなものが感じられる。そういった最近の潮流を勝手に「プロポップ」と名付けているのだが、今作は彼ら流のプロポップが最も充実した形で聴けるのだ。
「ミックスナッツ」はとうに2年前からやばいと取り沙汰されてる訳だが、改めてその完成度の高さと独特さに唸る。
それでいて「Sharon」や「subtitle」のような素晴らしいバラードをかけるのもこのバンドのすごいところ。
「ホワイトノイズ」だって直球のロックナンバーに見えて結局しっかり趣向を凝らしてきてるなあと感じさるものばかり。
アルバムとしても非常にまとまった流れを感じさせる。
多くの困難を乗り越えた先にあるささいな喜びという今作のテーマは、声帯ポリープによる療養を経た藤原聡本人としても、コロナを経た我々としてもより心に突き刺さるのではないだろうか。
72位 中島みゆき『36.5°c』
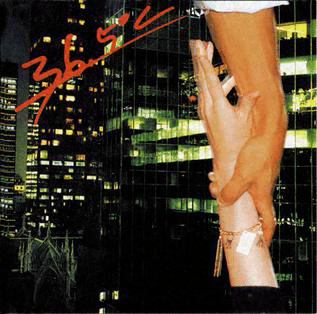
中島みゆきのキャリアを振り返ると、彼女ほどオルタナティブなアーティストはいないんじゃないか!と思わせられる瞬間がいくつもある。
それてそれは歌詞や楽曲の部分であったわけだが、『寒水魚』以降はとうとうそれがサウンドプロダクションにまで表れる。その結果、フォーク好きのファンはついていけず、本人も「ご乱心期」と自嘲するくらいセールスが低迷してしまったのだが、今作は正にご乱心を極めに極めた怪作だ。
プロデュースは甲斐よしひろ。ミキサーにラリー・アレキサンダー。レコーデイングはニューヨークはパワーステーション。 アレンジャーは後藤次利、船山基紀、萩田光雄、椎名和夫、久石譲と超一流どころのものすごい面子で、この頃の彼女の音楽的野心が伺える。
パワーステーションの打ち込みによるデジタルな感触と、情念溢れるみゆきの声は、ミスマッチに見えるが、これが今までには無い絶妙な世界観を確立してる。
いわゆる都会的なポップスといわれるものの多くは煌びやかで生活に余裕がある雰囲気だが、都会にはそうでない者の人も多く集まってくるわけで。
「あたいの夏休み」や「毒をんな」なんかはそういった本来言葉にすら残らないような地味で後ろめたい庶民の暮らしぶりすら映し出してる。彼らにとって都会とは実に冷ややかで殺伐としたものなのだ。「やまねこ」なんか女に生まれたこと自体が理不尽な業に嘆いてる。
つまりこれは、彼女の観察眼と挑戦心が結実した異形のシティポップである。
71位 井上陽水『Lion & pelican』

みゆきと同じく井上陽水もフォークの人でありながら、独自のサウンドを追求し続けたアーティストだ。かつての「氷の世界」とは全く別のアプローチで彼の世界観が確立したのが、こちらの作品である。70年代の作品と比べ物にならないくらい都会的でファンキーだ。
そしてシュールでユニークな歌詞はいっそう研ぎ澄まされ「リバーサイドホテル」や「とまどうペリカン」などキャリアを代表する迷歌詞が聴ける。「ワカンナイ」はなんと宮沢賢治へのアンサーソングらしい。
これと沢田研二のプロデューサーとして作り上げた「MISCAST」で陽水の第2の黄金期が幕を開ける。
70位 フリッパーズ・ギター『カメラトーク』

全国のギターポップ少年が憧れた至高の傑作。ネオアコースティックからソウル、フレンチポップ、ソフトロックまで多様なアレンジが施され、ロンドン録音の洗練されたサウンドがは当時の日本人からすると余りにお洒落すぎたのではないか。しかし、ただそこから漂う甘酸っぱい青春の香りが若者を熱狂させ、まさかの同年のレコード大賞では最優秀アルバム賞を受賞。最先端の街 渋谷としての新しいカルチャーが産まれる。
「恋とマシンガン」や「summer beauty 1990」はその後の日本のラウンジミュージックに多大なる影響を与えただろうが、意外と「Camera! Camera! Camera!」なんかの俗っぽい打ち込み曲も紛れていてなんか可愛い。。
69位 Speed『starting over』

平均年齢13.5歳という若さで登場した4人組の魅力を凝縮した衝撃のデビューアルバム。
TLCをロールモデルとしたソウルフルでダンサブルなR&Bサウンドは当時の日本にR&Bブームという新たなトレンドを巻き起こした。「body&soul」のようなナンバーから、「Starting Over」のようなバラードまで難なく歌いこなす完成度の高いヴォーカルワークは今でも惹き付けられる。
少女ゆえの刹那的な魅力とプロデューサーの本気度が融合した1stはやはり最も心を動かされる。
68位 BOØWY『BOØWY』

BOØWYの登場はそれまでのロック業界を根本から変えた。このアルバムは、そんな彼らがパンクロックからポップロックへと転換した際の音楽的な進化を示し、音質の変化やリズム隊の確立などなどその後の音楽性を決定づけた重要な作品だ。それまで日本では珍しかった縦ノリビートを上手く落とし込み、英国のニューウェーブの空気感を一気にシーンの中心に持ってきた。レコーディングはベルリンのハンザ・トン・スタジオで行われ、音のクリアさと独特の暗さ、硬質感が特徴。
軽快なシャッフルビートの「ホンキー・トンキー・クレイジー」、布袋寅泰のギターカッティングが印象的な「BAD FEELING」、名曲「DREAMIN'」など、ライブでも定番となる楽曲が揃っており、入門としても最適な1枚。
67位 ピンク・レディー『阿久悠 作品集』

昭和の歌謡史を振り返るとき、ピンク・レディーの存在は外せない。ミーとケイの二人組は、1976年の"ペッパー警部"でプロデビューし、瞬く間に大人気を博し、彼女たちのダンスと高速リズムは当時の音楽シーンに衝撃を与えた。
ブームの仕掛け人は阿久悠で、都倉俊一の親しみやすいメロディーに乗っけたコミカルな歌詞は歌謡曲の多様化に寄与したといっても過言では無い。今作品はいわゆる懐メロとしてただ聞くのもいいが、やはり阿久悠の3分間の中に描くドラマチックな歌詞を嗜むべきだ。「地球の男に飽きたところよ」と嘯く姿はラッパーもたじたじのパンチラインである。
66位 RCサクセション 『rhapsody』

1980年4月、久保講堂でのライブ録音を収めたこのアルバムは、前作「シングル・マン」から迫力満点のロックサウンドに変貌を遂げたRCサクセションの魅力を存分に発揮しており、ライブアルバムとして、演奏時の興奮をそのまま伝える形式で、ロック、ソウル、R&Bを日本語で独自に解釈した楽曲が次々と展開される。80年代日本ロックの幕開けを飾った一作である。
他のライブアルバムと比べると粗削りな部分も見受けられるが、RCサクセションが最も充実していた時期にリリースされた、忌野清志郎の安定した歌唱力が聴ける。
バンドの演奏技量の高さがパワフルなグルーヴと空間のうねりを生み出し、生気に充ちたエネルギーを感じさせる。
65位 TMN『expo』

小室哲哉は過小評価されすぎだと思う。彼がいなければ日本にクラブミュージックが根付くことは無かっただろうし、何より邦楽の歴史の中で彼ほど天下を取った人はいない。
もちろん小室プロデュースのシングルは過剰な派手なアレンジだが、ことアルバムに関してはクールなものばかりだ。
TM NETWORKのラストアルバムにして最大の問題作である『EXPO』は、彼の音楽的野心がバンドの枠に収まりきらなくなり、後に天下を取る布石すら感じさせる一作である。
いかんせん音質は緻密で、低音の響きが非常に強く、スピーカーやアンプによって音の聞こえ方が大きく変わる作品でもある。リスナーは音質の違いを体感しながら楽しむことができ、イヤホンで聴くと細かい音がより鮮明に聞こえることも特徴だ。
音の万国博覧会ともいわれるほど多彩な楽曲を展開しており、そしてそのどれもが海外仕様のビートを奏でてる。「We Love The Earth (Ooh, Ah, Ah, Mix)」のような開放的なナンバーから「Crazy For You」のような官能的なものまで様々だ。「月の河/I hate folk」はそのやりたい放題感が面白い。
シンクラビアを用いた録音技術やブルースペックCDの効果によって、音の奥行きがより一層感じられます。バブル期の日本文化を反映した、洗練されたサウンドとビジュアルが色褪せない魅力を放つ。
64位 ユニコーン『ケダモノの嵐』

ユニコーンの絶頂期に制作され、バンドの多様性と創造力が爆発した傑作。初のセルフプロデュースにより、メンバー全員がヴォーカルを担当するまでに自由な表現が可能になった。
アルバムは「命果てるまで」のような独特のスタイルで始まり、「CSA」のようなパンクナンバー、「スライムプリーズ」のような不穏なダブサウンドなど、ユニコーンならではのバラエティに富んだ楽曲が詰め込まれてる。
特に注目すべきは、ラブホテルの情景を描いた「命果てるまで」、死後の葬式を描写する「リンジューマーチ」、自転車泥棒をテーマにした爽やかな「自転車泥棒」など、奥田民生の天才的な作詞・作曲が光るところ。これらの楽曲は、当時のユニコーンが持つエネルギーと創造力を完全に表現しており、リスナーを楽しませる力が溢れている。
1990年の日本レコード大賞でアルバム大賞を受賞したこの作品は、正にユニコーンの人気と実力を裏付けるものだ。
63位 松田聖子『pinnapple』

今でこそ松田聖子といったら80年代アイドルの中でも別格の存在として語られるが、1981年当時の視点では河合美奈子や柏原芳恵なんかがライバルとして扱われていたし、ぶりっ子キャラのせいか歌唱力の正当な評価もなされてなかったそうだ。さらに、喉の酷使にハリのある歌声が出せなくなることも懸念点だった。
だがここからCBSソニー 一丸となって聖子プロジェクトはさらに巨大な「音楽性の投資」を果たしていく。
前作『風立ちぬ』の洗練された音像はそのままに、より松田聖子にふさわしい夏のコンセプトを追求し出来上がったのが今作だ。
ニューミュージック界のラスボスである松任谷由実が参戦したのもあって、松田聖子のさらなる一面を引き出した1枚だ。
それは単にアイドルソングの金字塔「赤いスイートピー」が収録されてるということだけでなく、「present」や「ピンクのスクーター」などで見られるハスキーボイスや、「ひまわりの丘」のような童謡的な歌唱が聴きどころ。
62位 三浦大知『球体』
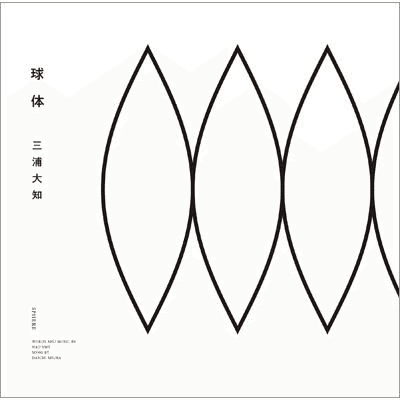
三浦大知と音楽家・プロデューサーのNao'ymtによる革新的なコラボレーションの結果生まれたアルバム。Nao'ymtが全曲の作詞、作曲、編曲、プロデュースを担当し、時空を超えた幻想的な物語を紡ぐ。三浦大知の繊細でダイナミックな歌声はもちろん健在。
断片的でありながらも一貫したテーマを持つ17曲がまるで群像劇のようにまとまっており、R&Bやダンスミュージックの要素に加え、アンビエントや和風テイストなどが融合した、複雑で神秘的な音像を確立してる。
さらに全編を通して日本語で綴られた歌詞は、文学的な要素が強く、海外の猿真似では無い日本人のミュージシャンとしての矜恃が伺える。
61位 矢沢永吉『ドアを開けろ』

キャロルでひたすらロックンロールを叫ぶ青年であった彼がわずか2年でここまで成熟する姿を誰が想像できたであろうか。
その圧倒的な貫禄とエネルギーはジャケットデザインからボーカル、サウンドに至るまで詰まっている。
いわゆるロックンロールに固執することなく、多様なアプローチを試みたこの作品は、ファンキーな演奏やジャンルを超えたアレンジが光る。
「黒く塗りつぶせ」のような矢沢のR&Rスタイルの完成系ともいえる楽曲から、「チャイナタウン」や「バーボン人生」のようなシックなバラードまで歌いこなす彼の姿は、まさにスターへの階段を駆け上がっていた勢いを感じさせる。
バッキングを務めたのは、日比谷野音でのライブアルバム『THE STAR IN HIBIYA』でも共演したサディスティックスで、特に後藤次利のベースラインが楽曲の骨太さを支えてる。ホーンやストリングスを効果的に使用したアレンジも、アルバム全体に深みを与えているといったところか。
60位 藤井風『help ever hurt never』

鮮やかなピアノの演奏力と、R&Bやヒップホップ、歌謡曲などの要素を融合させたモダンな音楽。藤井風の魅力が全て詰まった内容で、近年の音楽シーンの台風の目といっていい作品。特に「何なんw」や「帰ろう」などの楽曲は、彼の持つ独自の死生観や“解放”をテーマにしており、若者とは思えない達観した内容だ。
そこにある母音を重視した言葉遣いは、日本語の繊細な機微を捉え、自身のボーカルの強みすら活かしてる。
本来ならばこういう非常に日本的な楽曲なのに関わらずyaffleプロデュースによって海外すら見据えたサウンドに仕上がってるのは奇跡である。
今後もこの作品は宇多田ヒカルの『first love』などと共に日本のR&B作品の分水嶺として評価を上げてくに違いない。
59位 さだまさし『私花集』

「案山子」、「秋桜」など名曲ばかりで、さだまさしの豊かでほっこりした感性と才能が光る一作。
特にファンからも人気が高い「主人公」は正にさだまさし節とでもいうべき、彼の慈愛に満ちた人生観が感じられる。
またフォーク界隈の中では、かなりアレンジメントに趣向を凝らしていて、当時の邦楽のスタンダードから1段抜けた芳醇なサウンドが聞けるのも持ち味。
58位 薬師丸ひろ子『花図鑑』

なぜこれが有名じゃないのか全く不可解なくらいの名盤。
松本隆による花をテーマにしたプロデュースなのだが、薬師丸ひろ子の神秘的な声と松本隆の詞が見事に融合し、日本ポップス界の巨匠たちによる楽曲が並ぶ。なんと井上陽水、中田喜直、筒美京平、細野晴臣らが手掛けてる。やばすぎないかこれ。
そして、ここまでの面子も一目置くほど、薬師丸の歌声はあまりに神聖で美しい世界を描き出す。それはもはやただ上手いを超え、そこに女神がいるかのような錯覚さえ聴き手に抱かせる。特に、「花のささやき」、「紅い花青い花」、「かぐやの里」で見られる異界の風景は、極楽にいるかのよう。
この作品を生み出しただけでも80年代アイドルブームというのは偉大すぎるムーブメントだったといえよう。
57位 小沢健二 『life』

いわずとしれたオザケンの大名盤。ただこの手のランキングだとtop10に入るほどの評価を受けているが、そこまでかという気もする作品。
というのも小沢健二は次々に音楽性を変えるところが最大の魅力だと思っていて、そういう意味でこの作品=オザケンと見てしまうのは少し失礼なんじゃないかと考えてしまったのだ。
とはいえ、この作品は紛れもない傑作に違いない。
今作で彼のヘナヘナした歌い方と、それに反した歌詞の深さに惹かれた人はあまりに多いのではないだろうか。
ラブソングであり、日常讃歌でもある「ラブリー」や「おやすみなさい、仔猫ちゃん」は何度も聴くほどに味わいが増すし、「今夜はブギーバック」はいわゆる軟派なHIPHOPとして1つの到達点というべき名曲だ。
56位 trf 『dAnce to positive』

絶頂期にあったtrfがダブルミリオンを達成した5枚目のアルバム。生バンドによる力強い演奏を基盤に、華やかなブラスセクションやソウルフルなコーラスなど、ブラックコンテンポラリーの要素を大胆に取り入れ、従来のダンスミュージックからR&B/ソウルへと音楽性を広げた一作。
デジタルバキバキの音ではなく、各曲が生音で再構成されたことで、さらに力強いサウンドに仕上がってる日本のダンスミュージックの到達点のひとつといえるのでは無いか。
「1999 月が地球にKISSをする」は繊細なギターワークに加え、サウンドトラック的要素も含んでるかなりの異色作。「dAnce is my life系」は「DAYONE」の小室verともいうべきナンバーであり、当時の若者の肌感覚みたいなものが伝わる。
55位 aiko『時のシルエット』

前作から2年3か月のブランクを経てリリースされた10作目のアルバム。「恋のスーパーボール」や「クラスメイト」は、aikoらしい軽快さと切なさが見事に調和した、恋愛模様や複雑な人間関係が描れてる楽曲はもちろん、2011年に起きた東日本大震災の影響を受けたメッセージ性の強いものも見られる。「Aka」のサビに繰り返される「泣いてしまうなんて勿体ない」というフレーズがラブソングでは終わらないaikoの進化の姿勢が伺える。
メロディーはいつも通りキレッキレなのに加え、コーラスが多用されたアレンジが、アルバム全体に暖かみとメリハリをもたらしている。
54位 杏里 『timely!』

角松敏生が全面的にプロデュースを担当したシティポップの時代を象徴する名盤。
AORテイストのサウンドと、杏里の透明感のある歌声が絶妙にマッチし、"WINDY SUMMER"をはじめとする楽曲が、夏のリゾートや都会の洗練された風景を思わせる心地よいリズムを奏でる。
それに加えて杏里の感情豊かなボーカルが引き立つバラードも含まれており、そのバランスが秀逸。昭和とは思えないような洗練されたアレンジは、記憶にないはずの永遠の夏へと続く。そんな鮮烈な輝きを放つ作品。
53位 中島みゆき『愛していると云ってくれ』

本作は、「失恋の女王」としての地位を決定づけた重要作。ここでの失恋はいわゆる失恋バラードのような軟派なものではなく、孤独や疎外感といった負の感情を一緒くたにしたもの。「元気ですか」の朗読で見られる彼女の表現力はこの頃から凄まじく、ゾッとするような感覚すら覚える。そこから「怜子」の鋭い叫びに至り、「わかれうた」の悲哀を聞く頃にはもう頭から離れない。アルバム展開の流れも絶妙であり「化粧」のような絶叫バラードもあれば、「ミルク」のような聴き手に多層的な意味を抱かせるアコースティックな楽曲もあり、単純に楽曲の強度とバランスが絶妙だ。
そして今作のハイライトはなんといっても「世情」。ここまで溜まりに溜まった負の感情がここでさらにギアをあげる。
学生運動とかうんぬん抜きにしても、ここまでの怨念を感じさせる楽曲はやはり彼女しか作れない。
しかもここで満足せず『生きていてもいいですか』という最凶の怪作を作るのだから驚きだ。
52位 フィンガー5 『NEW BEST』

邦楽において沖縄県出身アーティストの存在は欠かせない。安室奈美恵、三浦大知、Begin、最近ではAwichなんかもそうだ。
恐らく一般的な評論誌は、ここで沖縄出身ミュージシャンのパイオニアである喜納昌吉の存在を挙げるだろうが、俺はあえてフィンガー5を推したい。まだ日本人がブラックミュージックの理解が薄かった70年代前半に、たった12歳でグルーヴを会得してしまった晃。そしてそれを上手く支える残りの兄弟とバックの演奏陣たち。当時のお茶の間はさぞビックリしただろう。
51位 吉田拓郎 『元気です』

フォークから日本のポップミュージックシーンへと進化を遂げる中で、吉田拓郎が持つ独自の音楽的ビジョンを鮮烈に表現した名盤。
ボブ・ディランはエレキギターを借りて現代の不平不満をぶっきらぼうに呟くことで、フォークとは違う表現を確立したが、拓郎はむしろ古くからの民謡にあるような日本の原風景であったり普遍的な心理を歌にした。
「春だったね」や「たどりついたらいつも雨降り」などのロック調の楽曲から、「夏休み」「旅の宿」「祭りのあと」といった日本の風情を感じさせる楽曲まで、どこを切り取っても時代の象徴としての力強さと自信が溢れている。
特筆すべきは、石川鷹彦によるアコースティックギターの演奏とアレンジメントで、ついつい吉田拓郎本人の腕前と勘違いされがちだ。
彼の存在によって歌謡曲とはまた別の方向性を指し示す拓郎流のフォークが完成したのだ。
作品を聴く度に、日常や恋心、個人の思いがどのように音楽に昇華されていくのか、その新しさと力強さを実感することができる。
とりあえず前編はこれで終了です!後編もお楽しみにしていて下さい!
