
質問攻めの現場見学でA4メモ10枚 - 課題解像度を極限まで高めるfindの現場主義
はじめに
find プロダクトマネジャーの白柳です。先日 COOの和田が1本の記事を公開しました。大変な反響の中で「現場主義を徹底しているのが良い」というコメントが多かったことが印象的です。findが大切にするものを褒めてもらえて嬉しくなりました。良い機会なので今回は find流の現場主義 についてお話ししようと思います。
落とし物業務の特異性
findに参画して間もない頃、私は落とし物業務を正直甘く見ていました。「落とし物なんて単なる捨てられたものと大差ないのでは?」なんて浅はかに思っていました。
ある日の打ち合わせで現場の方から「お忘れ物管理をする上で一覧をいろんな条件で分けて出したい」と言われました。当時の私は、同じ忘れ物なのにどうして分ける必要があるのかと思いました。ただでさえ件数が多いのに、いちいち分けていたらキリがないじゃないかと。
その意見をそのままぶつけてみると、実は落とし物は慎重な取り扱いが求められることが分かりました。例えば「権利主張の有無で分けたい」というものです。拾った人が所有権を主張した場合、3ヶ月以内に落とし主が見つからなければ拾った人のものになります。そういったものは「3ヶ月後にお客さまへお返しの必要があるものとして、紛失しないよう特に慎重に扱いたい」とのこと。他にも落とし物が貴重品だった場合は、盗難やなりすまし詐欺の危険があります。個人を特定できるものだった場合は、情報漏洩などにも気を遣いながら管理します。
話を聞く中で、現場の方々はとにかく丁寧に間違えないように扱うことで精一杯で、効率化することへの不安が大きいことに気づきました。単に効率化だけ唱えてもダメで、丁寧さの裏にある不安を払拭した上での効率化でなければ受け入れてもらえません。このとき私は「findは誰よりもお忘れ物について詳しくなければいけない」と思いました。

現場に行くことの大切さ
リモート会議で担当者から得られる情報と、直接現場で見る情報には大きな違いがあります。これは開発メンバー全員が最初から強く意識していた部分でした。
私が初めて現場見学をしたのはJR九州の博多駅です。大きな駅ですから、見学前は1人1台のPCとデスクがあって基本的には座って作業しつつ、たまに倉庫へ物を取りに行くような現場をイメージしていました。ところが実際は、紙と物であふれる空間に共有端末があり、複数のスタッフがそれを交互に使うのが日常でした。行ったことのない現場は想像と違うだろうと思っていても毎回驚かされます。
そして一度見たのと全く見ていないのとでは、想像力に雲泥の差がつくことも実感します。見学前に考えていた仕様はほぼすべて書き直しとなりました。

実証決定からMVP達成まで
最初の仕様検討はとにかく手探り状態でした。業務特有の用語はもちろん、なぜその作業が必要なのか理解できず、とにかく現場を見学し、質問を重ねることで業務を理解していきました。
findでは現場見学の際、徹底的な質問攻めを基本としています。「なぜそれをやっているのか?」「その操作は実際どうやる?」「こんなイレギュラー時はどうする?」など。今日からそこで一緒に働くんだ という気持ちで臨みます。最初のころは知らないことが多すぎて、1回訪問するだけでA4メモが10枚以上になりました。
仕様を作る時は、詳細が把握できていない状態で進めないよう心がけています。現場見学や質問を通じて業務パターンを洗い出し、そこから共通解を考えます。そして、仮説と検証を繰り返し、仕様やプロダクトデザインを現場の視点でシュミレーションし、対応できないケースがあれば書き直しを繰り返す。これがfind流です。
MVP(Minimum Viable Product)達成までは、4人のエンジニアのうち3人が工数の8割を現場理解に費やし、CTOの井上が一人でほとんど実装するという形でプロジェクトを進めました。また、エンジニア自身も「何かあればいつでも電話してください」と名刺を配りました。当然 現場からの電話は引っ切りなし。内容は操作に関する質問や不具合の報告など様々でしたが、いずれも真摯に対応することで現場スタッフとの信頼を築きました。その結果、検討中の仕様に関してこちらからも気軽に相談できたことは大変有り難かったです。
実証後の改善とPMF
実証成功後も改善を続け、真のプロダクトマーケットフィット(PMF)を目指しました。ここからは最速でPMFを達成するために「作らないという選択」も重要です。ワークアラウンドで対応できる範囲を見極め、本当に必要な機能にリソースを集中させます。CSの坂野井は毎日現場に通い、直接サポートを提供しました。日々スタッフから飛んでくる要望を一次受けして、Excelなどで対応できるものはその場で対応してくれました。現場理解が深まった後はあえて開発者を現場から離して、情報の整理と実装に集中させることも大切です。
以前、導入いただいたお客さまから「findは現場理解と汎用化のバランスがちょうど良い」とのお言葉をいただいたことがあります。当時CTO井上が「現場理解はとても大切だが、現場の人と同じになってはfindの価値がない」とよく言っていました。現場と同化したメンバーと俯瞰的に考えるメンバーの仕様バトルが社内で頻発しましたが、その過程はPMFに必要不可欠だったと感じます。
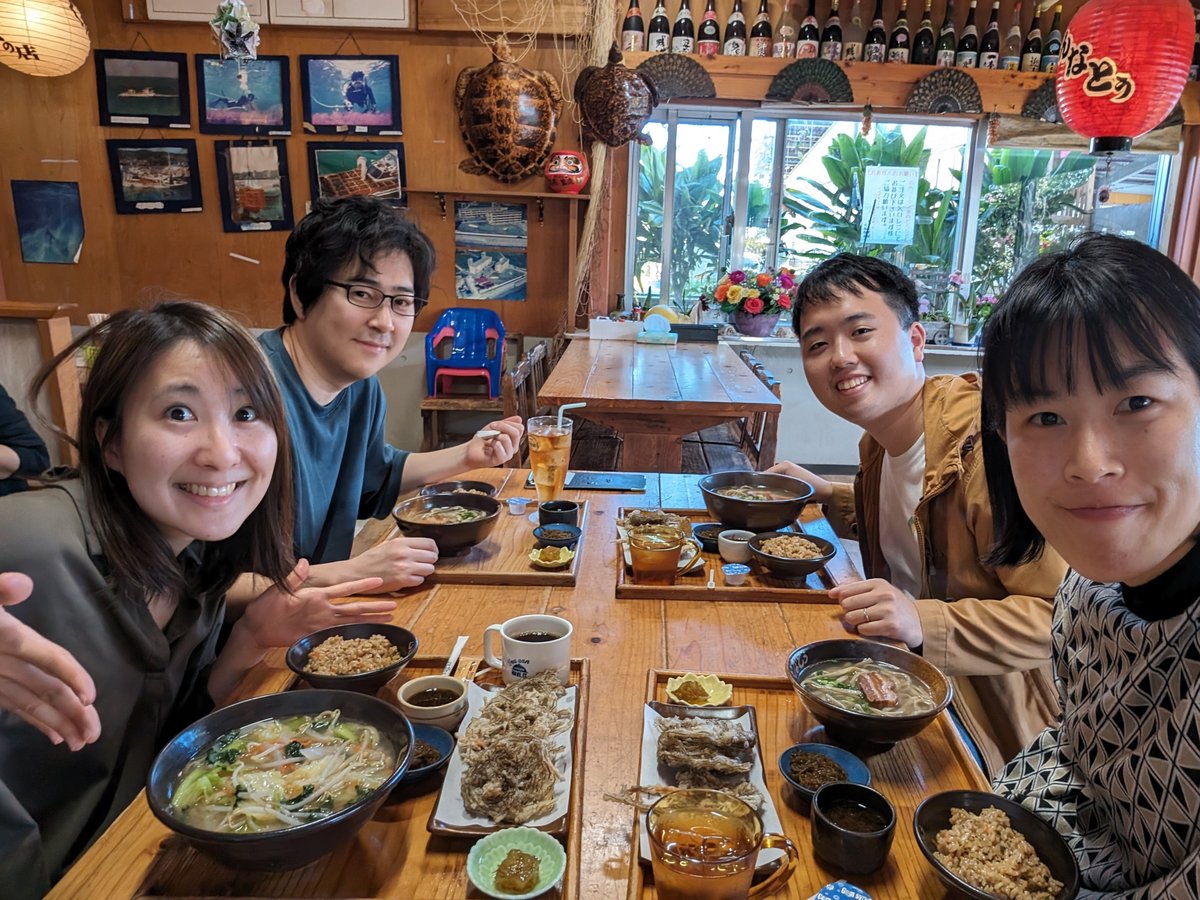
プロダクト作りで意識していること
プロダクト作りを行う上で今でも意識しているのは「解像度の高い話し合いをすること」です。例えば新機能を考える時、どんな要望か?どんな機能なら嬉しいか?ではなく、まずは「どんな会社の・誰の・どんな業務が・どう大変か」を深掘ります。これは開発メンバーだけでなく、直接お客さまと打ち合わせするカスタマーサクセスやフロント営業にも意識してもらっています。
社内で改善要求をあげてもらう際のフォーマットも一工夫しています。必須項目は「課題・現状の対応策・要求」の3つ。特に大事なのが「現状の対応策」です。これを聞くことによって具体的なエピソードを引き出せます。課題と要求は表裏一体なので、起案者自身も気づいていない課題を引き出すためにはエピソードが必要です。
最後に
findが掲げる現場主義は、課題の解像度にこだわって試行錯誤してきたプロセスそのものです。何か新たな視点を導入する際も、まずは現場を深く知り、そこから前進していく。これがfindの哲学であり、これからもその信念を持ち続けていきます。このストーリーが、読者の皆様にとって有意義なものとなれば幸いです。
