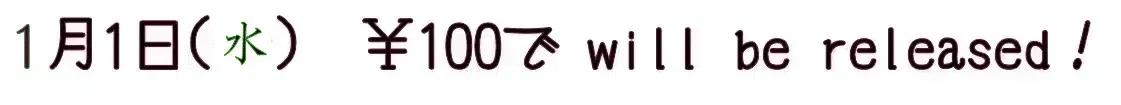鰤の野望「天下統一」
いよいよ暮れも押し詰まってきました。お正月の準備は万端でしょうか? 我が家は、年取り魚の到着を待つばかりです。近頃はあまり聞かなくなった「年取り魚」ですが、無いとなると物足りない気分になります。

年取り魚
年取り魚とは大晦日に食べる魚で、関西は塩鰤、関東は塩鮭が定番ですが、地方によって魚は変わります。塩鰤と塩鮭の境界は糸魚川静岡構造線と言われています。そして、この境界線は年取り魚に限らず、あらゆる食文化、生活文化の境界線でもあります。※糸魚川静岡構造線の境界線付近に位置する富山、長野、岐阜当たりは鰤と鮭が混在しています。
例えば、電気の周波数(西日本60Hz、東日本50Hz)、カップ麺の味付け、肉まん・豚まんの名称、面白いところでは灯油用のポリタンクは東が赤、西は青で、糸魚川では両方の色が使われています。また、ゲンジボタルの発光周期も糸魚川静岡構造線を境に、東日本は4秒に1回、西日本は2秒に1回です。律儀なことに、糸魚川周辺には3秒に1回の中間型がいるのですから面白いですね。
あまり知られていませんが、男性の髪型の横分けも、糸魚川静岡構造線を境として、西日本は右分け、東日本は左分けです。
どん兵衛
現在放送中のどん兵衛のCMで、吉高由里子さんが、どん兵衛の東西境界線は「関ケ原」だと明言しています。日清食品さんに確認したところ、開発担当者が新幹線こだまに乗り、一駅ごとに、駅や駅周辺のお店でうどんを片っ端から食べて、味の境界線を探したとのことでした。
日清食品さんが、自社の製品について説明しているのですから、部外者が横槍を入れる筋合いではありません。ですからブツブツと独り言を言うのですが、筆者も似たような調査をよくします。例えば、大阪うどんと京都うどんの境目調査など。その経験から言えば、新幹線の駅では、駅間が長すぎる! 駅周辺のうどん屋だけで、駅間の食文化すべてをカバーできるわけがありません。
この種の調査は、鉄道の駅そばや駅前の蕎麦(うどん)屋を対象にすると、簡単ですが結果は曖昧なものになりがちで、信憑性に欠けます。時間はかかりますが、主要街道沿いの民家を対象に調査をすれば信憑性が高いデータが得られます。
恐らく、日清食品さんもその程度のことは承知の上で、何らかの企業秘密を守るために「関ケ原」だと言っておられるのだと思います。

関西は塩鰤
関西の年取り魚が鰤なのは、西日本には鮭が遡上する河川が少ないからです。年取り魚は、旬が正月前で、大型、大量に捕れる、味と見栄えが良いという条件を満たしていなければなりません。西日本でそれに当てはまるのは鰤なのです。体長で言えばスズキも大型なのですが、スズキは群れで回遊しないので、一度に大量に捕れません。

関東は塩鮭
東日本~北日本には鮭が遡上する河川が多く、東京、千葉、神奈川を除く関東の年取り魚は昔から塩鮭でした。東京、千葉、神奈川は昔から転入者が多いので各地の文化が混在しています。したがって、年取り魚も様々です。
新巻鮭と塩引き鮭
年取り魚の塩鮭は、新巻鮭と塩引き鮭が有名です。
新巻鮭は、内臓をとったサケをまず塩漬けにします。一週間ほど漬けた後、水につけて塩抜きをしてから、天日と寒風にさらして水分を抜いていきます。近年の新巻鮭は最終的な塩分が比較的低く、塩鮭の塩分を表す用語で言えば「甘塩」です。さらに、天日干しではなく、冷蔵(冷凍)庫で水分を飛ばす製法もあります。
塩引き鮭も作り方は新巻鮭と大差ありません。ただ、乾燥具合が塩引き鮭の方が高く、身が締まっているので塩分濃度が高くなっています。こちらは「辛塩(辛口)」です。

正月魚(祝い魚)
年取り魚とは別に、「正月魚」あるいは「祝い魚」と呼ばれる魚もあります。関西では真鯛を塩焼きにした「にらみ鯛」を祝い魚、関東では「塩鰹」を正月魚といいます。
にらみ鯛は正月三が日は食卓の上、あるいは神棚にお供えして、4日に食べます。身をむしって食べる他に、茶わん蒸しに入れたり、鯛飯にしたり、各家庭で様々な料理に活用されました。大阪では最後の骨とアラでお吸い物を作るのが定番です。
塩鰹は房総半島や伊豆半島で作られたものが江戸まで運ばれていました。製法は塩引き鮭と同じですが、鰹は鮭に比べると小ぶりなので、比較的安価でした。また、江戸には独身者が多かったので、半身や切身の塩鰹も売っていて、重宝されたようです。こちらも正月三が日は神棚にお供えし、4日に焼いて食べました。
通常、年取り魚か正月魚(にらみ鯛)のどちらかを準備したのですが、関西、関東ともに、位の高い武家や大店など裕福な家庭は両方を用意することもありました。しかし、庶民は正月魚(祝い魚)が用意できれば御の字でした。

鮭の不漁
年取り魚、正月魚(祝い魚)ともに、受け継いでいきたい食文化ですが、近年、全国的に鮭が不漁です。中でも、今年は新潟県内の鮭の漁獲量が11月末時点で前年同期比37%減の約28500匹となっています。これは近年のピークだった2015年度の16分の1の漁獲量で、近年まれに見る不漁です。
水産研究・教育機構水産資源研究所(横浜市)によると、不漁の原因は海洋環境の変化で稚魚の餌となるプランクトンのほか、サバなど捕食者の分布が変わったことや、親鮭が回帰する際の海水温上昇などが考えられるそうです。

海水温の変化
日本生まれのサケの稚魚は、オホーツク海からアラスカ沿岸、ベーリング海を回遊しながら育ちますが、日本沿岸から初めて出る外洋がオホーツク海です。その時期のサケの稚魚には5℃~12℃の海水温が適しているのですが、1980年代からオホーツク海は低温が続き、日本生まれのサケの子どもには厳しい環境が続いていました。
進撃の鮭
しかし、2000年代からオホーツク海の海水温が徐々に上がり、2010年代には5℃~12℃と、サケにとっての適水温になりました。それを契機に日本やロシアでサケの漁獲量が急増し、空前の豊漁が続き、鮭の勢いは止まりませんでした。
鮭の三日天下
ところが、その後も海水温は上がり続け、今度はサケにとっては厳しい温水になってきました。日本海のサケは元々対馬暖流の影響を受けているので、太平洋のサケに比べると温水に強いのですが、その日本海のサケでさえ「そうそう、温泉は気持ちええわって、アホー! 熱いわ‼️」と言うほど日本周辺の海水温は上がり続け、かつての豊漁が嘘のように鮭は捕れなくなりました。
新潟県柏崎市の谷根川では2015年度には約2万匹の鮭が捕れ、豊漁に沸いたのですが、2023年度には約1400匹にまで減少し、伝統行事の「サケ豊漁まつり」は2023年、2024年と2年連続で中止に追い込まれました。
鰤の野望
東北、北陸、北海道で続く鮭の不漁とは逆に、今まで北海道ではあまり取れなかった鰤が2010年ごろから豊漁で、近年は北海道が都道府県別の鰤漁獲量のトップに躍り出ています。これは温水性の鰤の生息に適した温度の海水域が、冷水域を押し上げて北上しているためです。

天下統一
このまま温暖化がすすめば、日本で鮭は捕れなくなるかもしれません。その代わりに鰤は大漁です。いつの日か鰤が天下を取り、年取り魚は鰤で統一されるのかも知れません。

一筋の光明
しかし、まったく希望がないわけではありません。今月26日、JR四国の養殖サーモン、「ミルクサーモン」が東京で売り出されました。ミルクサーモンは、キングサーモンとニジマスを掛け合わせた品種で、乳児用の粉ミルクを餌に配合して育てたそうです。味に定評がある両親なので、大きさも十分、味も期待できそうです。
また、日本最大の淡水魚イトウ(陸封型サケ類)の養殖も一案です。同じく陸封型サケ類のヤマメやイワナは日本人が主に食べているシロザケほど大きくはありませんが、イトウなら十分代用品になると思います。

とは言え、ミルクサーモンが大量養殖になるかどうかは、これからの売れ行き次第ですし、イトウの養殖は、海のものとも山のものともつきません。なにせ川のものですから。
それまでに国産シロザケが、丹波産マツタケのような高級品にならないように願うばかりです。どうしますか、鮭のおにぎりがひとつ2千円だったりしたら!
あっ❗️ そうそう、男性の髪型の横分けが、糸魚川静岡構造線を境として、西日本は右分け、東日本は左分けってのは、冗談ですよ😅
良いお年をお迎え下さい。
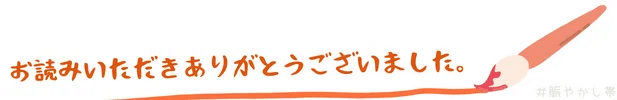

学校給食の誤解と嘘

給食の中の人だったから知っている給食の真実。
▶学校給食は教育の一環なのか?
▶給食費無料はいいことなのか?
▶民間委託の実情
▶東京都の現実
▶食育の現状
▶PTAは無関心
▶給食にファミチキはダメなのか?
お子さんが食べている給食のことを、どれぐらいご存じですか? 興味ないですか?