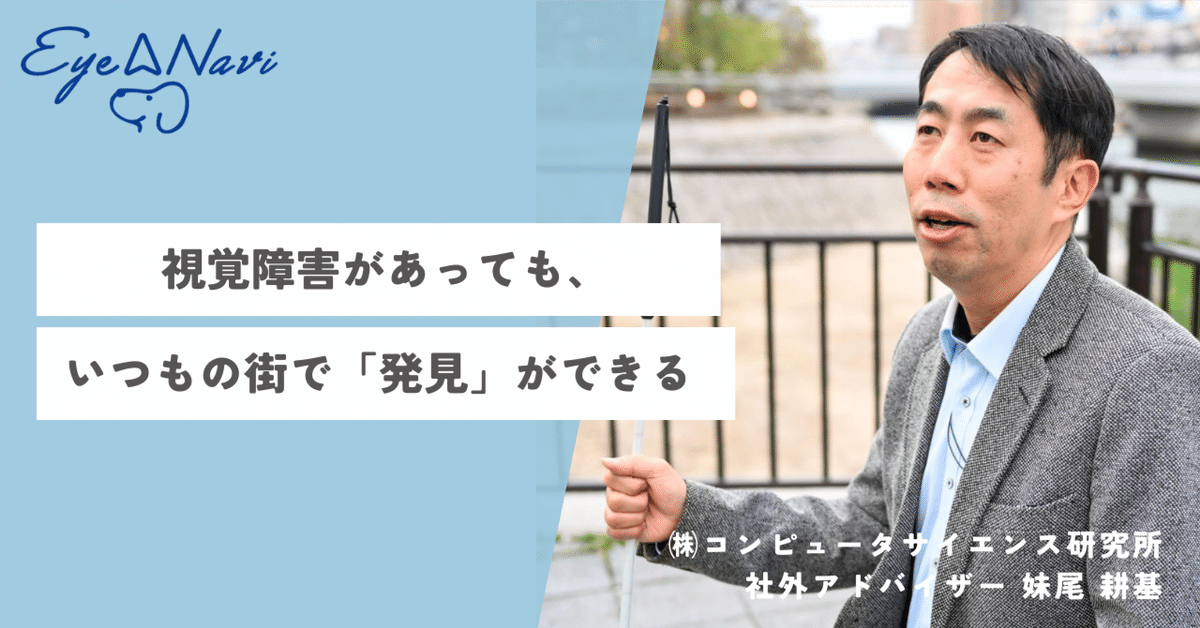
視覚障害があっても、いつもの街で「思いがけない発見」に出会える。中途視覚障がい者のアドバイザーが触れてきたEye Naviの成長
スマートフォンひとつで、道案内と障害物検出、歩行レコーダー機能を備えた歩行支援アプリ「Eye Navi」。
これまで、Eye Naviは視覚障がい者の方を中心に、「誰もがどこへでも、自由に楽しく移動できる社会の実現」を目指して、サービスを提供してきました。
そんなEye Naviを開発するメンバーに、サービスにかける想いを聞く「Eye Naviインタビュー」!
今回は、視覚障がい当事者として、Eye Naviの社外アドバイザーを務める妹尾耕基さんにお話を伺いました。耕基さんは妻である真由美さんと一緒に、ご夫婦でEye Naviの開発アドバイザーになっていただいています。
現在は製鉄所で働きながら、視覚障がいのある方々の声を開発に活かす架け橋として活躍している耕基さんに、4年間携わったEye Naviの成長や、耕基さん自身がEye Naviを使ってよかったことを教えてもらいました。
妹尾 耕基(せお・こうき)
製鉄所勤務。NPO法人ベーチェット病協会理事長。20代後半でベーチェット病により視覚障害を発症。現在も設備管理のエンジニアとして働きながら、2019年からEye Naviの社外アドバイザーに参画。妻の真由美さんと共に、視覚障害当事者としての経験を活かし、アプリの改善・進化に携わっている。
20代後半に難病を発症し、視力が低下。周囲からのサポートを受け、少しずつ新しい生き方を見出してきた

ーーまず、耕基さんの現在の見え方について教えてください。
耕基さん:
左目はほとんど見えない状態で、右目は一部分、視野が欠けている部分がありますが、0.1ぐらいは見えるので、明るいところであれば歩くことはできます。
体調や気候、周りの明るさによって見えにくさが変わるような状態ですね。普段は白杖を使って生活しています。
ーー見えにくくなったのは、いつごろからだったのでしょうか?
耕基さん:
20代後半のときに、ベーチェット病という難病を発症したことをきっかけに徐々に視力が下がっていき、2006年に身体障害者手帳を取得しました。
もともと新卒で入った製鉄所で電気設備エンジニアをやっていたのですが、視力が下がるに連れて、仕事もおぼつかなくなってしまって。正直「もうダメかもしれない」と落ち込んだ時期もありました。
でも、会社の産業医さんや上司、同僚がサポートをしてくれたおかげで、現在は大きな画面とパソコンの拡大機能を使って、整備の仕事を続けられているんです。

ーー困難がありながらも、それを乗り越えてお仕事を続けられているんですね。そんな耕基さんがEye Naviと出会ったきっかけは何でしたか?
耕基さん:
2019年くらいに、九州工業大学で視覚障害がい者用の新しいデバイスの実験参加者を募集していると聞いたんです。それが現在のEye Naviの元となる製品でした。
電気系の仕事をしていたので、技術的な部分に興味があって行ってみたのですが、最初は眼鏡にカメラをつけたり、パソコンを背負って歩いたりと、とても実用できるような様子じゃなくて...今から思うと、すごく大変でしたね(笑)
最初はダメ出しばかり。当事者の提案を取り入れつづけ、改良されていったEye Navi

ーーそんななか、どうしてEye Naviのアドバイザーになったのでしょうか?
耕基さん:
「盲導犬の代わりになるようなサービスを作りたいから、視覚障害の当事者に手伝ってほしい」という依頼を受けて、協力してみたいと思ったんです。現状は大変でも、どんなふうに成長していくのか同じ技術者として興味がありました。
でも、最初は正直「ダメ出し」ばかりしていたんですよ(笑)。開発者のみなさんは「あれもほしい、これもほしい」と欲張って、Eye Naviにさまざまな機能を付けすぎている印象があったんです。
ーーそんな時期もあったんですね。
耕基さん:
Eye Naviの前進となるデバイス型からアプリケーションの形になっても、やっぱりそれは変わらない。
でも、欲張ってもそれぞれの機能が中途半端になってしまうと、当事者側もうまく使えないんです。「とにかく、まずは信号機の色を正確に判断する機能を付けてほしい」と頼みました。
ーー信号機の識別にこだわった理由はなんですか?
耕基さん:
歩行支援をするアプリである以上、やっぱり安全が第一ですからね。私たち視覚障がい者が街で歩いていて、一番怖いのは横断歩道を渡るときなんです。
色の変化はわからないし、まっすぐ渡り切るのも一苦労。それで事故に遭ったり、危険な目に遭って外出が怖くなってしまう方も少なくありません。
夜や雨の日は特に見えづらいので、そういうときでも使えるようにしてほしいと意見をしつづけました。
ダメ出しばかりのなか、きっと落ち込むこともあっただろうに、開発チームの皆さんは一生懸命改良してくれて。現在は信号機の識別もかなり正確で、使いやすくなってきていると思います。

ーーEye Naviは、開発チームとアドバイザーの二人三脚で成長してきたんですね。Eye Naviのアドバイザーになってから、思い出に残っていることはありますか?
耕基さん:
2022年に岡山国際サーキットで開催されたEye Naviの実証実験に参加したことがいい思い出ですね。
Eye Naviが「Mobility for ALL」というトヨタのアイデアコンテストの一次選考を通過したことで実現したプロジェクトでした。
現地でEye Naviを使って1人でトイレまで行けることを実証したんです。豊田章男社長も見に来てくださって、「これからもっと便利になっていくんだな」って、本当にワクワクしましたね。
↓実証実験の詳細はこちら。
見えなくても街で「思いがけない発見」に出会えるようなった

ーー改良されてきたEye Naviを使ってみて、生活に変化はありましたか?
耕基さん:
外出するときの不安が随分減ったと感じています。以前は渡るのが怖かった信号のある交差点も、安心して渡れるようになりました。
それにこの前、嬉しい出会いがあったんですよ!いつもの道を歩いていたら、Eye Naviが道中で「ここに伊能忠敬の記念碑があります」と教えてくれたんです。何度も歩いたことがある道でしたが、そんなの知らなくて。
Eye Naviが案内してくれる音声ガイドのなかに、街の情報や周辺案内も少しずつ増えているのが、見えない情報には出会いにくい視覚障がい者にとっては、とても嬉しいです。
ーーこれからのEye Naviには、どんな進化を期待されていますか?
耕基さん:
まずは、商業施設やホテルなど屋内でも利用できるようになるといいなと思っています。大型のショッピングモールの中でカフェに行きたいときに、目的地まで案内してくれるような機能があれば、目が見えづらくても行動範囲を広げやすいと思うんです。
あとは、観光面での活用ももっと増えていってほしいですね。私がEye Naviのおかげで記念碑に気がつけたように、いつも通る道でも新しい発見があると嬉しいものです。
これが観光地でも使えるようになって、例えば観光地限定のEye Naviのガイドやマップがあれば、視覚障害がある人ももっと旅行を楽しめるようになると思います。

ーーEye Naviの観光地限定マップ、面白そうですね!夢が広がります。
耕基さん:
技術面では5Gの活用に期待しています。例えば、信号機から直接情報を受け取れるようになれば、画像認識に頼らなくても、より正確な情報が得られるようになる。
そういった新しい技術との連携で、もっと便利に、安全に使えるアプリになっていくんじゃないかと期待しています。
ーーありがとうございました。最後にEye Naviに興味がある方へメッセージをお願いします!
耕基さん:
まずは気軽に試してみてほしいなと思っています。基本機能は無料ですから、手軽につかえますし、信号を渡るときの不安も道に迷う心配も、Eye Naviと街の人たちが一緒になって助けてくれますから。
ヘルパーさんと一緒に使いはじめるのもいいと思います。きっと新しい発見があって、お出かけがもっと楽しくなるはずです。そんな「歩く楽しさ」を、たくさんの方と分かち合えたら嬉しいです。

(取材・執筆・撮影 目次ほたる (@kosyo0821))
視覚障がい者歩行支援アプリ「Eye Navi」について

Eye Naviは、スマートフォンひとつで、道案内と障害物検出、歩行レコーダー機能を備えた歩行支援アプリです。
2023年4月にリリースされ、リリース開始から4ヶ月ほどで1万ダウンロードを突破しました。
Eye Naviの特徴は、AIを活用した「障害物・目標物検出」と、視覚障がい者に寄り添った「道案内」が組み合わさっていること。
この2つを実現することで、目的地までの方向や経路、周辺施設、進路上の障害物、歩行者信号の色、点字ブロック等を音声でお知らせできるアプリになっています。
Eye Navi公式ページ
アプリのダウンロードはこちらから
株式会社コンピュータサイエンス研究所 ホームページ
お問い合わせ窓口
下記よりお問い合わせください。
info@eyenavi.jp
