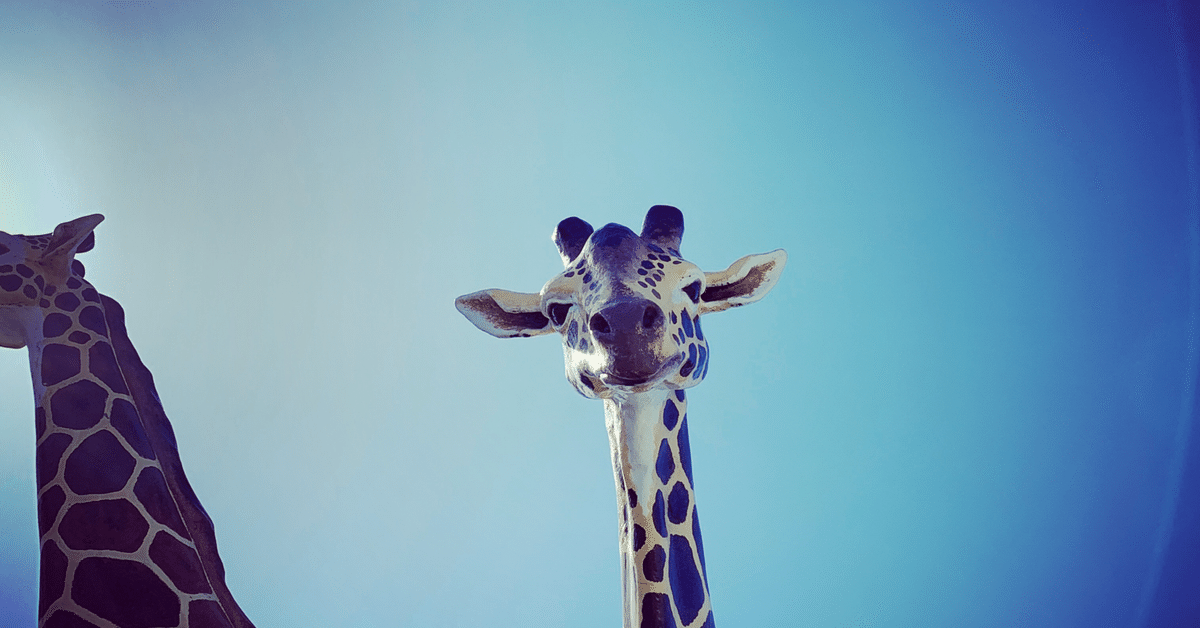
進化のしくみに関する誤概念
はじめに
進化のしくみに関する書籍は日本でも数多く出版されていますが、どのような誤概念が見られるかについては日本ではあまり紹介されていません。
そこで、進化のしくみに関する誤概念を下記の文献に基づき、紹介します。
Gregory (2009) Understanding Natural Selection: Essential Concepts and Common Misconceptions
Evolution: Education and Outreach volume 2, pages156–175
<補足>この論文は進化教育の分野ではよく知られており、現時点(2023.1.6)で約500の論文で引用されています。著者のGregory氏は教育に関する論文も書いておりますが、本業は進化学の研究者です。https://scholar.google.ca/citations?user=4NwGQS0AAAAJ&hl=en
「自然選択に関する知識がなければ、生物がどのようにして、あるいはなぜ、その多様性と複雑性を示すようになったかを理解することは不可能である(Gregory 2009)」と書かれているように、自然選択は進化の中心メカニズムであり、日本でも高校生物の教科書で扱われています(中学校理科の教科書でも発展として扱われているものもあります)。
ですが、残念なことに「自然選択による進化の概念はほとんどの生物学者が想像するよりも、生徒・学生にとって理解しにくいもの(Gregory 2009)」となっています。
この論文では下記の3つの内容が扱われていますが、この記事では「自然選択に関する誤概念」を中心に紹介したいと思います。
なお、これから紹介する誤概念は相互に排他的なものではありません。
つまり、一人が複数の誤概念を有していることもあるという点に注意してください。
自然選択の基礎
自然選択を理解することが困難な理由
自然選択に関する誤概念(←この記事はこの内容を紹介)
① 目的論(Teleology)
「石がとがっているのは動物が座らないようにするためだ」のように世界の物事を目的の観点から見ます。これを生物にも当てはめ、「鳥は飛ぶために翼を進化させた」のように考えます。自然選択による進化は目的や目標があるプロセスではありませんので、誤概念になります。
我々の身の回りのある物たちは用途・目的に合うようにデザインされています。人間は目的があって行動します。つまり、目的論的な考えは自然に育まれるものです。そのため、鳥が飛んでいる様子を見て、翼は飛ぶために進化した器官だと考えるのは自然なことであり、無理のないことだと思います。ある程度科学的な訓練を受けてきた人であっても「フィンチは生き残るために多様化した」などような目的論を含む表現を使うこともある程です。
もし、生物自身の目的に合うように進化が起こるとすると、どのようなしくみでそうなるのでしょうか。理由を尋ねると「必要だから変化した」のように回答することが多く、その形質が進化した「しくみ」が十分に考えられていないのです(なお、下記の書籍のNehm (2018) による分類では目的論(teleology)と必要性・目標(needs and goals)は1つのカテゴリにまとめられています)。
https://www.routledge.com/Teaching-Biology-in-Schools-Global-Research-Issues-and-Trends/Kampourakis-Reiss/p/book/9781138087989
この論文にも書かれているように「目的に基づく説明の傾向は非常に
根強く、中等教育以降も続く。関連の授業を行っても、目的論的思考は
少々抑制される程度であり、科学的に正しい考えに取って代わられることはない」ものです。
日本では詳しく調査されていないものの、我々が以前大学1年生を対象に調査した結果、やはり目的論に基づく進化の考えは根強い傾向が見られました(山野井ら2011、生物教育)。高校時代に『生物』を履修した大学生であっても「進化とは、生物の集団の形質が目的に応じて変化することである」に対して否定できた割合は22%であり、高校時代に『生物』を履修していない大学生と統計的な違いは見られませんでした(未履修者の否定率は16%)。https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjbe/52/1-2/52_28/_article/-char/ja/
② 擬人化と意図(Anthropomorphism and Intentionality)
自然選択の対象やプロセス自体に人間のような意識的意図があるとする考えです。Nehm(2018)では、意図(Intentionality)は「生物単位(個体、種)は、死や絶滅に直面しても、環境(生物的、非生物的)課題に取り組むために意識的な選択をする(学び、決断し、戦う)」と説明されています。
擬人化や意図の例として、アメリカのとあるHPの記事がが紹介されています。
「微生物が進化するにつれて、彼らは環境に適応していきます。もし、抗菌剤のような、成長や拡散を妨げるものがあれば、遺伝子構造を変えること
で、抗菌剤に抵抗する新しいメカニズムを進化させる。遺伝子構造を変化させることで、耐性を持った微生物の子孫も耐性を持つようになる。」
確かに、微生物が困難に立ち向かうべく、意識的に自らの遺伝子を変化させているように読めるので、擬人化や意図に該当すると思います。適応を「革新」「発明」「解決」のように表現することもこの誤概念に該当します。
本論文には、上記の例を科学的に正しく表現した場合の記述も掲載されています。
「病気を引き起こす微生物は大きな集団で存在し、すべての個体が同じではありません。もし、ある個体が抗生物質に対して耐性を持つ遺伝子を偶然持っていれば、その個体は治療後も生き残り、残りの個体は徐々に死滅していく。その結果、耐性個体は感受性個体よりも多くの子孫を残し、新しい世代が生まれるたびに耐性個体の割合が増加することになる。耐性個体の子孫だけが残ったとき(著者注:耐性個体の割合が有意に増加した時)、その細菌集団は抗生物質に対する耐性を進化させたと言える。」
科学的に正しい記述はこのように、「変異」「変異の遺伝」「変異に応じた適応度差」に関する内容が含まれていることが必要です。
なお、類似した誤概念として、進化を集団レベルのプロセスではなく、個々の生物が環境から課せられた課題に対応して進化するという考えがあり、前述のNehm (2018)では、この考えを「順応としての適応(Adaptation as acclimation)」として分類しています。
③ 用不用(Use and Disuse)
「形質の使用(または不使用)は、個体、集団、または種におけるこれらの形質の状態の増加、減少、獲得、または喪失を直接的に引き起こす」(Nehm 2018)という考えです。
ラマルクにより提唱された進化のしくみですが、獲得形質は遺伝しないため(④参照)、現在は正しくないとされています。高校生物の教科書にも長らく紹介されてきたものなので、進化のしくみに関する最も有名な誤概念と言えるでしょう。
要不要や用不要のように誤って表記されることがありますが、使うか使わないかなので「用不用」と書きます。
自然選択の考えを提唱したダーウィンも、形質の損失の過程については、一部、用不用を採用していたことが知られています。
「ダーウィン (1859) は、地中に住むげっ歯類が視力を失ったことを説明するために自然選択を持ち出したが、代わりに盲目の洞窟に住む動物が目を失ったことの説明として、不使用だけを支持したのである。「目は役に立たないが、暗闇の中で生活する動物に害を与えるとは考えにくいので、私は目の喪失は完全に不使用によるものと考える」(Gregory 2009)
近年の研究から、形質の損失の文脈では形質の獲得の文脈より、用不用の誤概念が見られることが報告されています(Ha & Nehm 2014, Science & Education)。
④ 後天的形質(獲得形質)の遺伝(Soft Inheritance)
「個体、集団、種が生きている間に獲得した形質が遺伝する」という考えです(Nehm 2018)。
現在では、遺伝は「ハード」なものであり、生物が生きている間に起こ
る物理的な変化は子孫に伝わらないことが分かっています。これは、生殖に関与する細胞(生殖細胞系列)とそれ以外の身体を構成する細胞(体細胞系列)が異なるためで、生殖細胞系列に影響を与える変化のみが受け継がれ
ます。新しい遺伝的変異は、複製中の突然変異と組換えによって生じ、多くの場合、子孫にのみその効果を及ぼし、他の細胞には影響を及ぼしません(Gregory 2009)。
<補足1>後天的な性質であっても、DNAの配列そのものの変化ではなく、DNAに生じた化学的な変化を介して、子孫に伝わることがあるようです。
<補足2>本論文の注には、後天的形質の遺伝についてはラマルクによって提唱されたものではなく、ラマルクの時代よりずっと昔(2000年以上に渡って)から一般に受け入れられていたことが記されています。
先述の山野井ら(2011)の調査によると、高校時代に『生物』を履修した大学生は、用不用や獲得形質の遺伝を否定できる傾向がみられました。
「ある器官を,一生の間に,他の器官に比べて頻繁に使用すると,遺伝子のその器官に影響を及ぼす部位が変化し,次世代の子ではその器官が発達するような進化が起こる」を否定できた割合は『生物履修者』が57%、『生物未履修者』が29%であり、統計的な差が見られました。
⑤ 選択主体としての自然(Nature as a Selecting Agent)
下記の例のように、自然選択における「自然」の役割を誇張しているものを指します。生徒や学生が持っている誤概念というより、生物学者や生物教員が進化のしくみを説明する際に用いやすい誤った表現という方が適切かもしれません。
Attenborough (1979)
「ダーウィンは、「適応」進化の原動力は、自然淘汰の厳しさによって選別された偶然の遺伝的変化の、無数の世代にわたる蓄積から生まれることを明らかにした。」(太字は著者による)
Darwin (1859)
「自然淘汰は、毎日、毎時間、世界中のあらゆる変異を、わずかなもので
あっても、綿密に調べ、悪いものは拒み、良いものはすべて保存し、積
み重ねているのだ。しかし、時間の針が長い年月の経過を示すまでは、
このようなゆっくりとした進行中の変化は何も見えない。」
同様に、自然淘汰を「好ましい」変異の中から「選択」したり、異なる選択肢を「実験」したり「探索」したりするプロセスであるとする記述(Gregory 2009)もこのカテゴリに該当します。
⑥ 変異の創出と選択の区別(Source Versus Sorting of Variation)
突然変異や減数分裂(組換えを含む)による変異の創出と、変異の選択は独立したプロセスですが、学生の多くは、この2段階のプロセスを区別できていないことが報告されています。このような学生は、突然変異は環境への応答として起こり、常に有益と考えてしまう場合があります。
⑦ 類型論的思考、本質論的思考、変容論的思考(Typological, Essentialist, and Transformationist Thinking)
類型論的思考(Typological Thinking)や本質論的思考(Essentialist Thinking)は個体間の変異の存在を無視あるいは軽視している誤概念で、「種は単一の「型」または共通の「本質」を示すものと考えられ、個体間の変異は型または本質からの異常でほとんど重要でない逸脱であるとされます」(Gregory 2009)。
自然選択が生じるには、変異の存在が不可欠であるため、これらの考えは自然選択と相容れないものです。これらの考えは、幼少期の早い時期に生じ、
大人になってもその考えを保持し続けている人が多いようです。
なお、これらの「種は一様である(つまり変異の存在を無視する)」という誤った考えは、適応が生じる際は「集団全体が変化して適応する」という変容論的思考(Transformationist Thinking)に繋がります。
⑧ イベントと絶対性、プロセスと確率性(Events and Absolutes Versus Processes and Probabilities)
・自然選択をプロセスではなく、イベントとして誤って捉えている。イベントには一般に始まりと終わりがあり、特定の順序で起こり、明確な行動からなり、目標が設定されていることもある。これに対して、自然選択は集団全体において継続的かつ同時に起こり、目標指向ではない。
選択をイベントとして誤解すると、適応的な変化が集団全体で同時に起こると考えられるため、変容論的思考(Transformationist Thinking)につながる可能性がある。また、自然選択を一つのイベントとしてとらえることは、複雑な適応的特徴が一世代で突然現れると想像してしまう。
・自然選択は、不適合な個体はすべて死に、適合する個体はすべて生き残るという、「all or nothing」であると誤って考えている。しかし、自然選択は確率的なプロセスであり、ある形質を持つ生物が繁殖に成功する可能性は高くなるが、それを保証するものではない。さらに、このプロセスの統計的
性質は、生殖成功率にわずかな差(たとえば1%)があっても、何世代にもわたって形質の頻度を徐々に増加させるのに十分である。
最後に
長文になってしまいましたが、お読みいただきありがとうございました。
進化を教える際、生徒や学生のレディネスを知る上での参考になれば幸いです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
