
天籟(てんらい)能の会 ワークショップ 川崎晶平さん(刀鍛冶)(1)
▼小鍛冶とは刀鍛冶のこと
安田:今回の天籟能の会では能『小鍛冶(こかじ)』を上演します。この能は、刀剣に関する能なので、刀鍛冶の川崎晶平さんをゲストとしてお招きしました(2018年6月14日@東江寺:広尾)。
川崎:刀鍛冶の川崎晶平でございます。よろしくお願いいたします。安田さんとこうやって対談させていただく機会を設けていただくのはこれで何回目かになるんですけれども、いつも打ち合わせがほとんどないんですよね。
いままで檻に入れられていた子犬か何かが、いきなりドアを開けられて「出て行け」と言われて、いきなり野に放たれたような感じで、どれくらい喋っていいのか、何を喋っていいのか、これから徐々に組み立てていこうかなと思ってるところなんですけども。
今回の能の演目が『小鍛冶(こかじ)』となっております。小鍛冶とは何かというと刀鍛冶のことなんです。皆さんのお手元に配られました私のリーフレットの一番後ろのページに私のメールアドレスがあると思うんですが、akihira.kokajiとなっております。
このように昔は刀鍛冶のことを小鍛冶と呼びました。能『小鍛冶』に出てくる役の名前が三条小鍛冶宗近(さんじょうの・こかじ・むねちか)。あまりにも有名な平安末期の刀鍛冶でございまして…。
▼宗近の打った「三日月宗近」
宗近はいつ頃の時代に生きた人なのか・・・。
東京国立博物館には「三日月宗近」という刀が所蔵されています。

▶リンク:e国宝「三日月宗近」
▶リンク:刀剣乱舞「三日月宗近」
日本刀というのは時代時代の要求によって姿が変化してきておりまして、皆さんがイメージされている反りのある日本刀の姿が完成したのが平安末期の頃だろうと言われています。
▼毛抜形太刀
宗近が生まれたのは、おそらく天慶(てんぎょう)の頃(938年から947年;平安中期)あたりといわれていますが、この頃日本に何があったかというと天慶の乱(939年)がありました。
皆さんご存じの平将門が坂東武者を率いて、関東一帯を暴れ回ったのが天慶の頃。
その将門を打ちとったのが藤原秀郷なのですが、彼が使った太刀が「毛抜形太刀」です。
皆さんがよくご存知の日本刀というのは刀身があって、柄に入れる茎(なかご)があって、柄に差し込むようになってるんですね。ところが毛抜形太刀というのは、刀身部分と茎(なかご)、握る所、グリップ部分が一体形成されてるんです。

それ以前の刀の形はどうだったかというと、中国大陸から渡ってきた刀のスタイルというのは真っすぐなんです。反りのない直刀であったり、両方に刃がついている剣のような形状であった。
ところが前九年の役、後三年の役で中央の武士たちが東北の方に遠征するのですが、東北の武士たち豪族たちは非常に馬に乗るのがうまくて、馬上で使う刀は反りがあるんです。
これは世界共通です。フランスの騎兵隊の刀も反りがあるし、アラブの兵たちも、アラビアのロレンスだって、刀が反っています。なぜ反ってるかというと馬上で振り回すには反りがあった方が刃筋が立てやすい。
もうひとつは、相手を斬りつけた時に力がうまく抜けてくれるんですね。真っすぐでは少々都合が悪い。馬上で取り回しが悪いわけです。
都から東北に攻めて行って見た人達がこれはいいぞということで、それを都に持ち帰ったのが反りのある日本刀の始まりくらいではないのかなと言われているわけです。そうするとだいたい1000年代前半くらいには反りのある刀ができたんじゃないかと。
▼童子切安綱
これも伝説めいた部分があるので本当か嘘かわからないんですが。
年号でいうと永延(987年~989年)ですかね、そのころのことなんですけれど、こんな話が残ってます。
皆さん「童子切安綱」という酒呑童子を斬った太刀のこともご存じかと思います。

これも国立博物館にあります。

▶リンク:e国宝「童子切安綱」
今の鳥取県の大原という所にいた安綱という刀鍛冶が、都の源頼光に太刀の制作を依頼されたらしい。
最初、都に太刀を持ってきたんだけれども、源頼光に会ってみるとなかなかの男なので、安綱はもうちょっといいのを作って治めたいなと思ったようなんです。なので頼光の部下だった渡辺綱に「これ、献上します」と言って、自分は一度帰ってもう一度作り直す。そして、一年後にもっといいのができて、それを源頼光に治めた。これが後の童子切安綱になったというわけです。
じゃあ渡辺綱に治めた太刀はどうなったかというと、一条戻橋で鬼の腕を切り落とした鬼切太刀がどうも最初に作った太刀であるらしい。
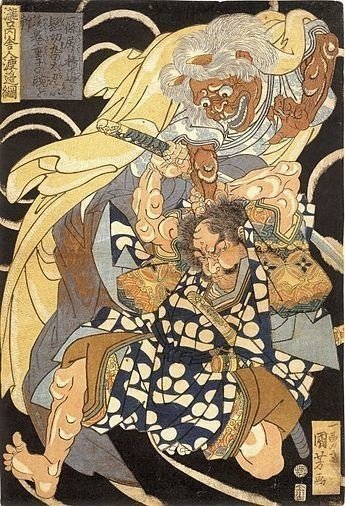
その後、頼光のものになった太刀は京都を荒らしまわっていた鬼童丸という盗賊を斬った、その話がだんだん大きくなって大江山の酒呑童子を斬った童子切になったという話ではないかなということなのです。
大江山で鬼を斬ったという話が出てくるのが室町時代の絵草子からなので、まあそんなところではないかなと。
時代的にいうと、1000年代前半、1100年までいかないくらいです。そのころに安綱が反りのある日本刀、「童子切安綱」を納めている。
▼宗近が刀鍛冶になる
だいたいそれと同じくらいの頃にやはり宗近も京の三条に居を構えて刀鍛冶を始めたのではないかと言われています。
宗近の出自については諸説あります。公家の子供である説。あるいは為吉(タメヨシ)という刀工の息子である説があるんですけども、今で言えばちょうど京都のウエスティンホテルの辺りに宗近は仕事場を構えていたらしいということになっております。
(続く)
