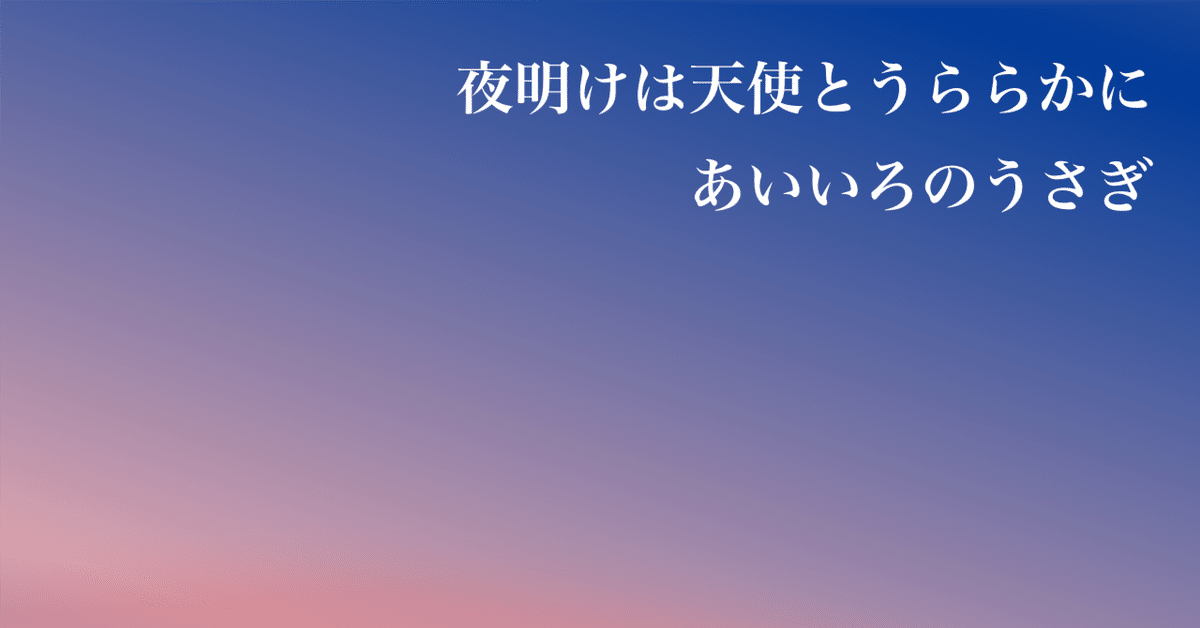
夜明けは天使とうららかに 2-3
〇 〇 〇
翌日、担任の先生に会えたのは昼休みのことだった。僕は先生が会ってすぐに江藤君の話をするんじゃないかと思ってた。だけど、挨拶をしたら、そんなことは無かったみたいに僕の体調とか、昨日帰った後何をしたかを聞いてきたから、少しビックリした。そして、江藤君のことを自分から切り出さないといけないんだ、と気づいて心の中が嫌な跳ね方をした。
昨日覚悟を決めたのに、僕の口は固められてしまったみたいに江藤君のことを言えない。言われて頷くのと、自分から言わないといけないのでは、こんなに感じ方が違うんだ。
でも、昨日、決めたから。
リセが「一緒に戦いましょう」って言ってくれたから。
今も隣にいてくれるから。
「あの、先生」
「ん、どうした?」
先生が僕の顔を見つめる。僕は目を逸らしそうになったけど、ちゃんと言えた。
「江藤君に会わせてください」
少し震え声で、カッコ悪いなと自分で思った。
江藤君とは放課後に顔を合わせることになった。
それまでの間、プリントを解いたり読書をしたりしていたけど、あんまり集中できなかった。頭の中は悪い想像でいっぱいだった。僕の言葉を聞いてくれなかったらどうしよう。馬鹿にされたらどうしよう。その場は聞いたふりをしておいて、後からネタにされたらどうしよう……。先生の前だからあり得ないだろうことまで想像して、不安でいっぱいになっていた。
でも、どんなに僕が不安でも、どんなにやっぱり逃げたい気持ちになっても、時間はどうしても進んでいって、放課後になった。
空き教室で待っていてくれ、と先生に言われてから嫌な緊張が全身を脈打つ。
「菖太さん、深呼吸です。一旦息を吐き切ってください。そうすれば自然と息を吸い込みます。それの繰り返しです」
リセに言われた通りに息を吐く。吐き切ったら確かに勝手に息を吸い込んでいて、今まで呼吸がとても浅かったことが分かった。しばらく深呼吸を繰り返すと、上手く呼吸ができたというだけで少し落ち着いてきた。
「ありがとう、リセ」
「どういたしまして」
リセは変わらずふわりと微笑んでいる。けれど少しその顔に緊張が見える気がした。リセも僕と同じように緊張してくれている。自分のことのように考えて、けれど僕の前ではいつも通りに笑ってみせてくれる。それが嬉しかった。
コンコン、とノックの音がして二人してビクッとドアの方を向いた。
先生と江藤君がドアを開けて入ってくる。
その顔を見た途端に、緊張が戻ってくる。呼吸を整えながら、必死で自分を説得する。
江藤君は謝りに来てるんだ。先生もリセもいる。だから大丈夫。
実際、江藤君は黙ったままで、僕に文句を言ってきたりはしなかった。
「まず、この時間を設けてくれてありがとう」
先生は僕の方を見てそう言った。僕はどうしていいか分からなくて、ただ頷いた。
「江藤、お前から話したいことがあるんだよな」
先生はそう言って江藤君に先を促す。
江藤君は僕を見て、頭を下げて、言った。
「色々ごめんなさい」
少し待ってみたけど、江藤君からの言葉は、それだけだった。そんなあっさりしたものだった。心の底では謝る気がないんだろうと感じた。後ろめたさなんて、全然なかった。
僕は、授業中に的当ての的にされたことも、体操着袋をトイレに隠されたことも、全部覚えている。クラスの子たちに気持ち悪がられたのも、その原因がたぶん江藤君なのであろうことも、分かってる。
それらの悪意が、怖かった。嫌だった。すごく悲しい気分になった。
江藤君は、それを全然、一ミリも分かってない。
「……もし、もう二度とこんなことは誰にもしないって約束してくれたら、いいよ」
先生が何か言おうとしていたのを遮って僕は声を振り絞った。
江藤君は一瞬、ぽかんとして、何を言われたのか理解すると「わかった」と言った。
もしも本当に言葉が葉っぱだったらそよ風で飛んでいきそうなくらい軽い『わかった』だった。
心の中から湧いてくる感情があった。
怒りだった。
「本当に約束してくれる?」
「分かったって言っただろ」
「今、早く終わりにしたいって思ってる。違う?」
江藤君はその顔を不機嫌に歪めた。
「君は、全然分かってない。僕がどうしてもうこんなことはしないって約束をしようとしているのか、考えようともしていない」
江藤君が少しだけ怯んだ。
「分かるよ。態度に出てる。どれだけ僕のことを蔑ろにしてるか、悲しいくらい分かる」
僕の声は少し震える。けれど、どんなに潤んでもこの目は離さない。
「その悲しさを考えて。僕に何をしたのかもう一度思い出して。そして約束して。もう二度とこんなことはしないって」
江藤君は怯えたような目で言った。
「……分かった。……ごめんなさい」
江藤君は逃げるように教室を出て行った。
「あ、こら! ……悪いな、ちょっと追いかけてくるからここで待っててくれ」
先生もそう言って教室から出て行った。
僕はすっかり力が抜けて座り込んだ。
「お疲れさまでした、菖太さん」
リセは僕の頭を撫でながら言った。
「ご自分の意見を、怖かった相手に伝えるのはとても勇気のいることだったでしょう。菖太さんは見事にそれをやり遂げました。誇って良いことです」
それに、と続けて悪戯っぽく笑う。
「先生も驚いてらっしゃいましたよ」
「そっか」
さっきのことを思い出すと、自分のことなのに僕もビックリしてしまう。あんな風に意見できるなんて、今まで考えたこともなかった。
「なんであんな風に言えたのかな」
「私も少し驚きましたが、でも、そうですね。あえて理由をつけようとするなら、菖太さんが強い人だからではないでしょうか」
僕は目を丸くしてしまった。
「強い? 僕が?」
「はい。正確には強くなった、ですかね。詳しく説明しようと思えばできますが……野暮なのでやめておきましょう」
「え、気になるよ。僕は自分が強いなんて思ったことないのに……」
「先ほどの勇ましさは菖太さんが強いことを証明するのに充分なものだったと思いますが?」
リセはその目を細めて僕に問いかけて来る。そう言われると、正直何も言えない。確かに僕は、江藤君に意見できない側だったはずで、それどころか学級会の時なんかも黙りっぱなしで、それなのに今日は自分の思ってることをハッキリ言えた。あんなに怖かったのが嘘みたいに。……涙目だったのは、すごくカッコ悪い気がするけど。
「本当にお疲れさまでした」
リセはそう言ってふわりと笑った。もうどこにも緊張のない、安心しきった表情を見て、僕も安心した。
戻ってきた先生は「待たせて悪かったな」と言った後、僕の頭をわしゃわしゃと撫でた。
「江藤がちゃんと謝ってない様子だったから、口を出そうとしたらちゃんと怒ってくれたから正直ビックリしたよ」
「ちゃんと、ですか?」
「ああ」
先生は屈んで僕と視線を合わせる。
「ちゃんと悪いことをしたって自覚することがあいつには必要だった。情けない話だが、俺がいくら言ってもあまり聞いてない様子でな。でも、今日のはきっと響いたんじゃないか?」
先生はニカッと笑った。変わらず僕の頭をわしゃわしゃしながら、
「よく言ってくれた。ありがとう」
と言ってくれて、僕は少し安心した。
