
7月の左手
7月の左手の練習風景です。
7月1日


毎月2回行う測定スケッチ。決まった人物画(45分)と1分間ひらがなです。
前頭葉が大きく剃り出てますね・・・
7月2日-5日

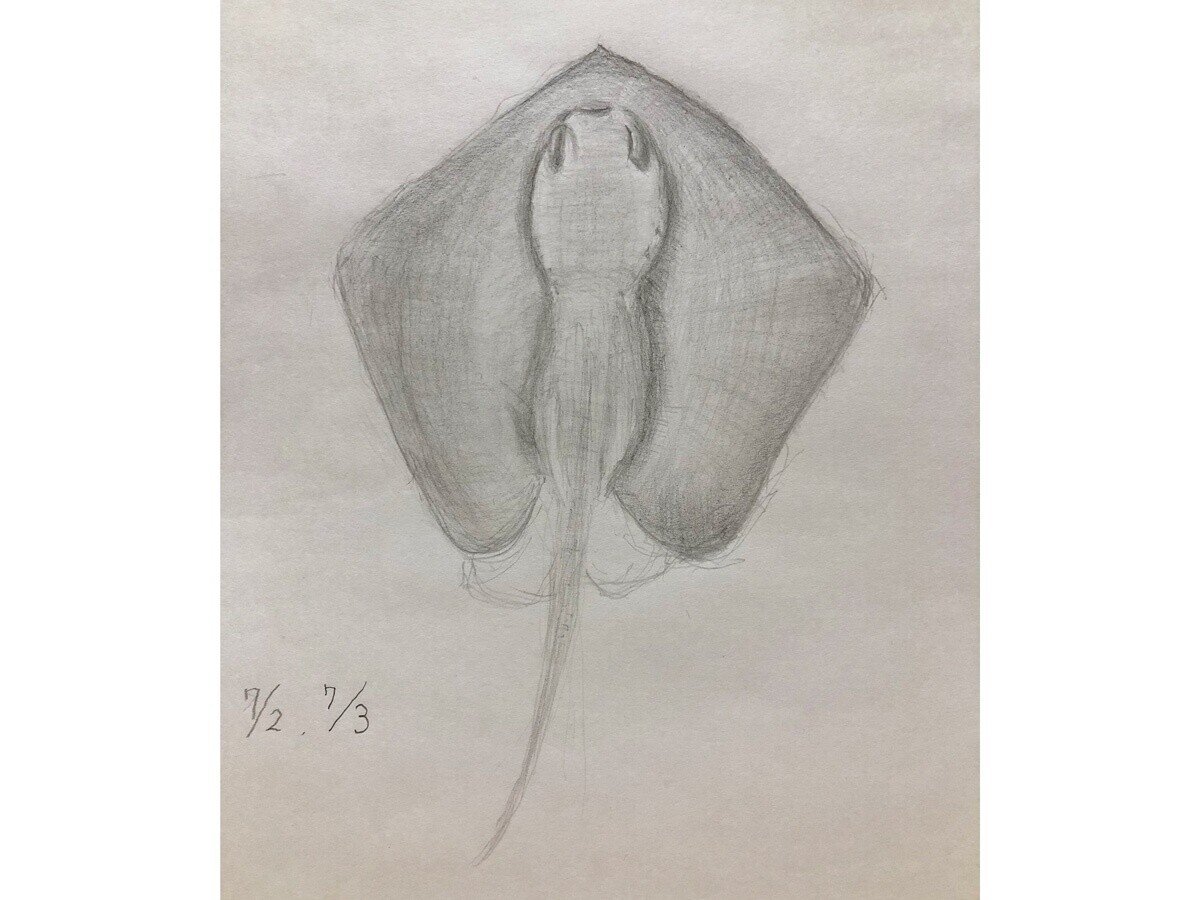

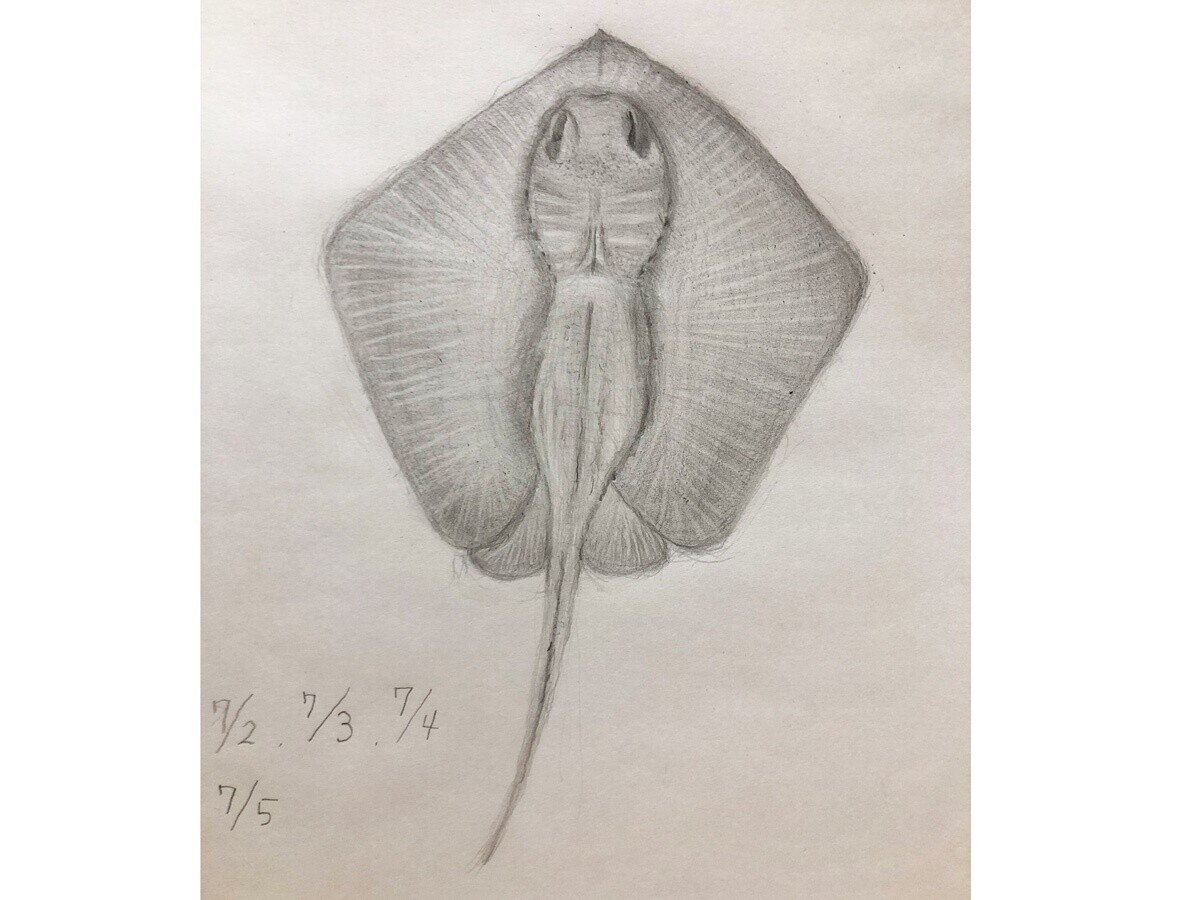
アカエイです。ぺったり、滑り感を出すって難しい。巨大おたまじゃくしがマントをつけたのがエイなんですね。
アカエイは波打ち際や入り江に潜んでいるので、踏んづけないように気をつけましょう。毒針に刺されて大変!!
7月6日- 9日




キハダです。図鑑に載っている魚が左向きなのは、右手で描く構図になっていたんですね。左手で描くまで気がつかなかった!
青白い光沢感を出すのが難しい。
背びれ、しりびれが黄色いことからキハダと呼ばれるそうです。特に関西で人気の魚だとか。ちょっと胸びれが小さかったな。
7月10日- 13日




ヤマメです。あどけない顔がなんとも言えません。ヤマメはイワナ、ニジマスと比べ警戒心がとても強いそうです。
右手で描いたものと比べると、左手はぼんやりと描くのが得意なようで、胸びれや下顎の境界線は柔らかに仕上がりました。
7月14日- 18日
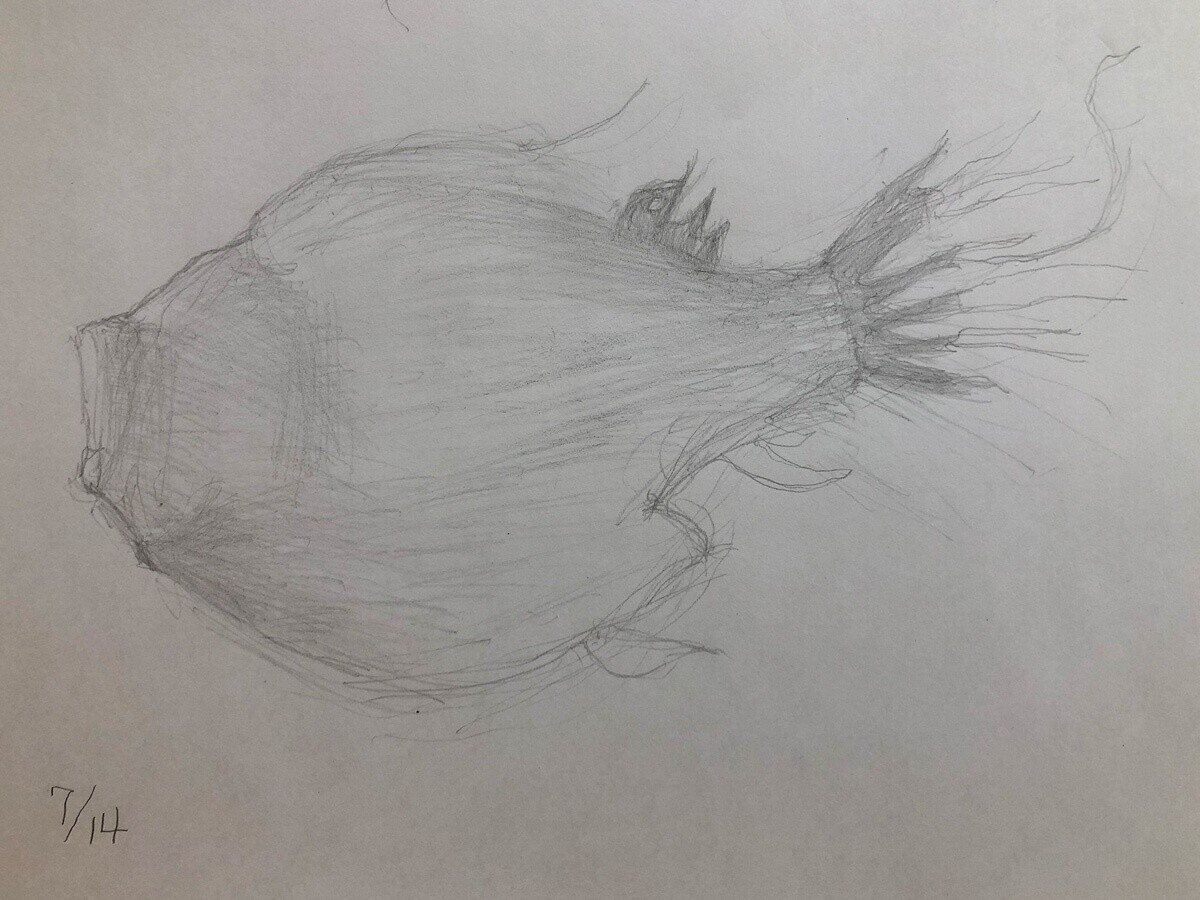



ビワアンコウです。複雑な形に挑戦!
この魚は水深200m〜400mの深海に暮らす魚で、雌は体長最大120cmになるのに対し、雄はなんと最大でも15cmにしかなりません。
これは雌のビワアンコウ。そしてお腹から、チョロっと出たヒレのようなもの。これはオスです。
歴然とした体格差のあるメスとオス。ちっちゃなオスはどう子孫を残すか?
それはメスを見つけたらしゃぶりつく。そしてオスはメスに噛み付いた口元からメスと同化し、子孫を残すそうです。
オスはメスと同化していく時、何かを思ったりするんですかね?
「神よ、なぜ貴方は生物をメスとオスに分けてたのですか?」とか。
さらに詳しく知りたい方はNational Geographicへ。
話をスケッチに戻して、今回、気がついたこと。左手は右手に比べ、手首が少し硬いようです。なので、手首をへし曲げて描く時、指先の動きも連動して動きが硬くなります。
7月17日

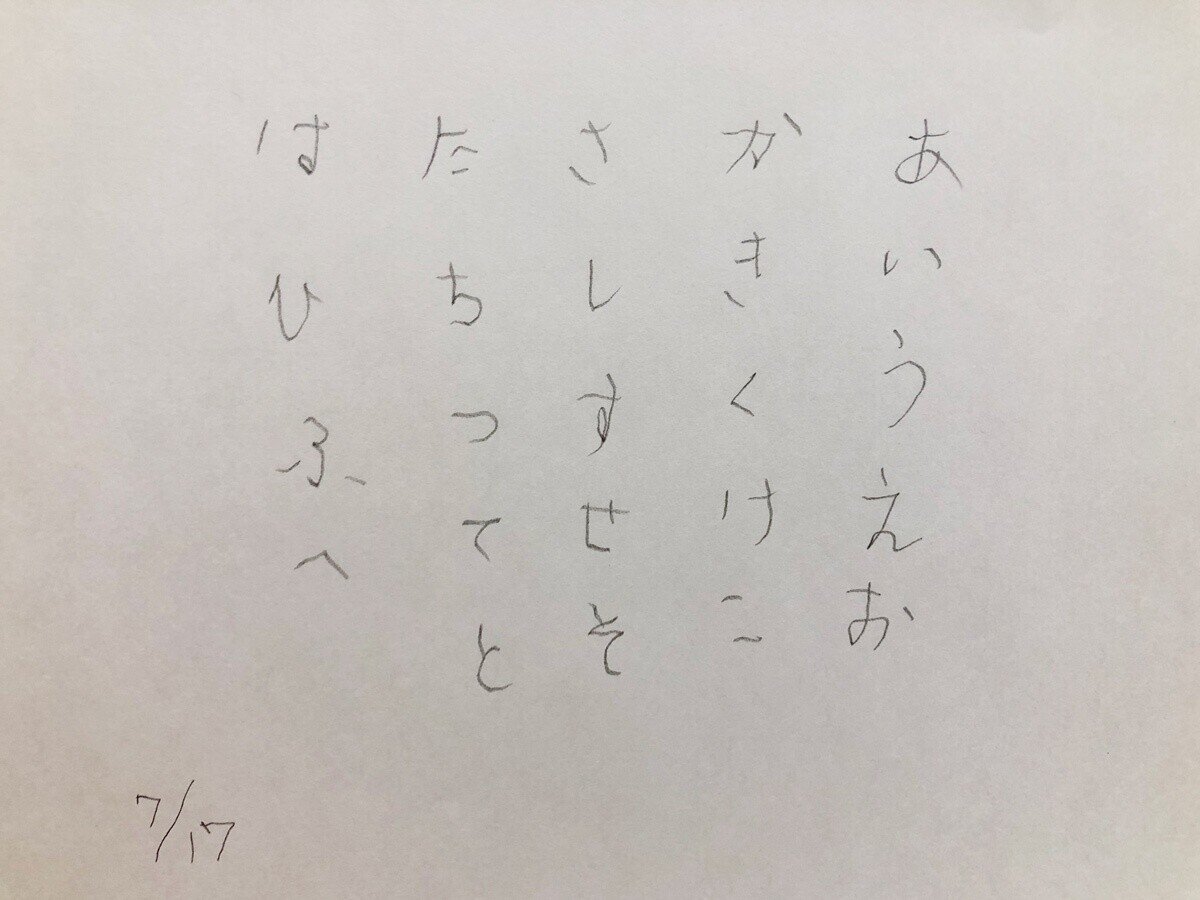
前頭葉のサイズに気をつけて描きました。
7月19日- 22日




シマゾイです。東京のスーパーでは見かけない魚ですが、煮付け、唐揚げ、塩焼きなどで食べるのが美味しいそうです。
背びれの形が恐竜っぽい魚なのですが、なんだかスーパーサイヤ人っぽくなってしまいました。スーパーシマゾイということにしましょう。
歯を食いしばって泳いでいます。泳げシマゾイくん!
7月23日- 26日




ツノダシです。黄・黒・白の3色で彩る魚です。カラフルな魚を見ると、南国へ行ってシュノーケリングしたくなりますね。
目が難しい。目をストライプの黒と同化させるのがポイントなのですが、目つきの悪い魚にも見えてしまう・・・
ツノダシのお味は?調べてみると「筋肉は少なく、水分多め、少し臭みがあり、旨味はない」
う〜ん。無理に食べることはないですね。和やかに鑑賞しましょう。
7月27日- 30日




魚図鑑を図書館へ返却したので、メガネを描きました。
特に細かい描写が苦手な左手。1日目を描き終えて、レンズの角度や大きさに修正が必要だと気がつく。修正は手間がかかるけれど、それをやっておかないと先へ進むほど気持ち悪くなるから、しっかりやっておこう。
パソコンでは修正前の画像を保存しておけるけれど、アナログはそうはいかない。
図鑑で写真を見て描くのも楽しいけれど、やっぱり実物を見て描くのはいいですね〜。
7月31日のスケッチは8月の左手に掲載します。
感想とまとめ
左手でのスケッチ練習を始めて2ヶ月、集中スイッチが入り易くなった気がします。そして、実験実施前と比べると、日常でも左手が使えるようになった!
例えば、お米を研ぐとき、お風呂掃除をするとき、左眉毛を描くとき(アイライナーはちょっと早いかな)など、非常に便利!!
今だったらベスト・キッド(Karate Kid)のミヤギ 先生の修行も難なくこなせます。
Wax on, right hand. Wax off, left hand.
Wax on, wax off.
