
デザインによる正義とデザインの罪
実は修士論文が間に合わず大学院を除籍になった。ので最終学歴は大学院中退だ。
最後のセメスターに、修士論文にはわたしはデジタルファイナンシャルインクルージョンについて書こうと思っている、というと指導教員の方が『Design Justice』という本を紹介してくれた。非常に面白い。
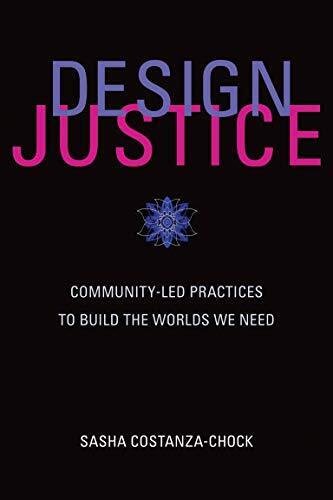
本書は、著者の空港での体験から始まる。この著者はノンバイナリーで見た目は女性だけれど生物学的には男性なのだそうだ。空港のボディスキャナは、男性か女性かしか選べない。見た目が女性なので担当者は女性を選ぶが、スキャンすると男性器のあたりが異物とされ、係員が触って確認することになる。そしてその時も、男性が検査するのか女性が検査するのか、ということが問題となる。中には、本人がどちらを希望するか聞かれることもあるものの、そうでないことも多い。
女性か男性かしか選択肢がない機械。ジャスティスとは何か。
話は変わるが、今年の夏、身近な人がアルツハイマーになった。短期記憶がなくなり、判断力も衰え、お金の管理ができなくなった。それにつけ込んでいらないものを売りつける近所の電気店のカモになった。高額な家電を買わされ、その売買契約書のサイン欄には「カタカナで署名」とある。認知症が進んで漢字を書けなくなった人でも、カタカナなら署名できたりする。
よく見ていると、明らかにカモにしてやろうとして近づいてくる人だけに注意すれば良いわけではないことがわかった。
新聞に入ってくるチラシ、定期的に届くカタログ、それらの「今だけ」「限定商品」「まとめ買いでお得」みたいなことにいちいち引っかかる。チラシの隅から隅まで目を通して、別に必要のないもの、すでにいくつも持っているものでも、そこに書かれている電話番号に電話して注文する。
この手のチラシやカタログを実際に作っているのは、若いデザイナーであろうと思う。私もその立場であったことがある。上からの指示で、ここに目立つように「今だけお得」と入れろといわれて、それを目につくようにデザインしているだけ、だ。コンテンツ自体にはほぼ関与できないし、それによって老人が騙されても責任もない。
本当に、デザイナーに責任はないのだろうか。もしも売り上げが上がらなかったら、売れない責任は問われるかもしれない。しかし、老人をうまく騙して売り上げが上がったら? 最後の一つ、と目立たせて不安を煽り、必要のないものを買わせる。「君のデザインのおかげでたくさんの老人から巻き上げられたよ、ありがとう」と言われることが、デザイナーのゴールなのだろうか。
私は違うと思う。デザインというのは問題解決のためのツールだ。デザイナーのゴールは、問題を解決してより良い社会、世界を作ることに参加することであるべきだ。ダークUXや小手先の問題解決風トリック(カタカナ署名もいい例)を駆使して人からお金を巻き上げることではない。
それに加担するデザインの仕事はBullshit jobsの典型だ(『ブルシット・ジョブ――クソどうでもいい仕事の理論』、首がもげそうになるおすすめの本!)。
最初にあげた空港のボディスキャンも、多くのテクノロジープロダクトでありがちな、デザイン手法による事前調査なしに、スポンサーと技術者だけで作り上げられたのではないかと思う。あるいは、「できるから」という理由だけで作られたもの。その技術を使うことが目的化していて、本来解決すべき問題やその問題を抱えた人々の存在感にすら気づかれない事態なんてよくある。
技術的にはなんでも可能な時代である今、物を作る人、デザイナー、技術者、そしてそれらの人を使って何かを成そうとする人それぞれが、倫理観、正義感を身につけるべきではないか、と思う。
正義というと白黒はっきりしたアメコミヒーローみたいに聞こえるかもしれない。そうじゃない。正義とは何か、今自分がやろうとしていることは倫理的か、立ち止まって考える癖をつけるということだ。
それをどうしたらできるのかな、と考えている。ビジネスパーソンやデザイナーよ、正義感を持て! と声高に叫ぶことは多分解決策ではないんだ、という感じはしている。これ、私の研究課題になるかもしれないな、と思っているところ。卒論間に合わなかったけど…
