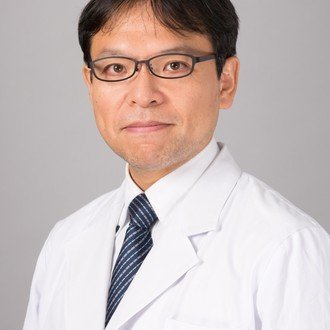赤穂市民病院についての覚え書き
赤穂市民病院で発生した医療事故に関して、この一週間ほど動きが相次いでいる。
事故を起こした脳外科医と思われるアカウントが出現した。
被害者ご家族、ご遺族を傷つけるような投稿をしたのち、いったん消えた。
こうした動きに呼応してか、赤穂市民病院の医療事故をモデルにしたと言われる漫画、「脳外科医竹田くん」の作者から、重大な発表があった。
私(漫画作者)は、赤穂市民病院 脳神経外科で2019年から2020年にかけて複数発生した医療事故のうち、2020年1月22日に起きた医療過誤の被害者の親族です。
この発表に大きな衝撃が広がった。
いったいどのような思いで漫画を描かれたのだろうと思うと心が痛む。こうしたご遺族の思いを、赤穂市民病院のもと常勤医師として、深く受け止めなければならないと思う。
初めて読まれる方に向けて書くと、赤穂市民病院は私の医師としての21年あまりの経歴のなかで大きな位置を占めている重要な病院だ。
今回は、この赤穂市民病院について、私との関わりを中心に書いていきたい。
赤穂市民病院と私との関わり
当時所属していた神戸大学病院病理診断科から打診され、常勤病理医として務めたのが、2009年8月から2011年7月まで。その後近畿大学医学部に異動したが、2019年4月から2020年3月まで再び勤務した。
そして、2008年の後半から常勤になるまでの1年足らずと、二度の常勤の間、さらに常勤を辞めた後はいまだに非常勤医として勤務している。
常勤医だったときは、病理医がたった一人、指導医も部下もいない、いわゆる「一人病理医」だった。
最初に赤穂市民病院に非常勤病理医として関わりはじめてから、実に16年以上、何らかの形で関わり続けてきた病院なのだ。
そういう意味で、この病院なくしては、私の医師人生はなかったと言えるくらい関わりが深い。
とくに、最初の常勤医としての2年間は、病理専門医取得前の期間であり、未熟な私を導いてもらったと言っても過言ではない。2010年に病理専門医試験に落ちたことも、思い出深い。
専門医試験に落ちたとき、流石に専門医がない状態で一人病理医は厳しかろう、と、神戸大学の教授などから異動も打診されたが、赤穂という街と、よくしてくれている職員の皆さんのことを思うと、ここで投げ出すわけにはいかん、と残留を決意した。
そのときは、病院側も激減していた病理解剖をがんばって増やしてくれた。実は病理専門医試験に落ちたのは、解剖の試験に2点足らなかったからだ。
その年の解剖の試験は、肺癌が出題された。
赤穂市民病院に来てから1年ほど解剖がほとんどなかったかつ、呼吸器科が撤退し、肺の診断をほとんどしていなかったことが影響したと自他ともに認める状態であり、そこを考慮してくれたのだ。
そういう意味で、恩義もある。本当はもっと長く務めたかったが、近畿大学からお誘いがあり、ずっと一人で診断していたら、病理医としての実力を伸ばすことができないのではないかと思ったこともあり、「他人の飯」を食うための武者修行の意味も込めて異動を決めた。
赤穂に常勤医として赴任したとき、2年の勤務という話だったこともあり、そのタイミングでの異動なら迷惑がかからないだろうと思ったからでもある。
ちなみに、赤穂市民在籍最終日が病理専門医試験の当日で、翌日から近畿大学に勤めた。合格発表は近大で受け取った。異動のはざまだった。
しかし、ずっと赤穂への思いが残り続けていた。
私が去ったのち、当初の話では、神戸大学病院が交代で常勤医を派遣するという話だったように聞いているが、神戸大学も神戸市内や近隣への医師派遣で手一杯で、兵庫県の最西端にあり、神戸から2時間程度かかる赤穂に常勤医師を送れなくなった。ただ、非常勤は重点的に派遣し、教授自らが診断に行っており、見捨てたというわけではなかったが。
とはいえ、私が常勤を去ったのち、非常勤主体になってしまったことに罪の意識を感じるようになり、非常勤を神戸大に任せたのちも、月一でカンファレンスを行うという名目で赤穂に通い続けた。
のちに神戸大学から打診されて、非常勤医に復帰。いつの日か赤穂に戻ろうという思いを抱き続けた。
そして、いろいろな思いがあって近畿大学を辞める決意をし、2019年4月から、常勤医として復帰したのだ。
こうして赤穂市民病院に再び勤務して数ヶ月後。今回話題になっている医師の方が赴任した。
赤穂を1年で辞めた理由
赤穂に勤務しはじめたときは、やる気に満ち溢れていた。当時の記事には、そんな前向きな姿勢がうかがわれる。
しかし、そんな病院をたった1年、2000年3月末で退職した。その理由は、病理医にも成果主義が導入されたことだ。
そのあたり、このnoteで何度も書いているので、ここでは赤穂民報のロングインタビューを紹介するに留める。そのインタビューに概要は書いている。
病理診断という、基本的に自ら診療報酬を獲得できない、いわば「稼げない」診療科に成果主義を導入する病院の姿勢に怒りを感じ、このままこの病院にいては危ないと感じた。
私たち病理医は、医療のチェック機構でもある。病理解剖を通じて死因を明らかにし、よりよい医療のための情報を提供する、あるいは普段の診断を通じて、治療のための情報を提供するといったように。
なお、病理解剖は死亡後であるため、診療報酬からお金が出ず、病院の持ち出しになる。やればやるほど病院の赤字になるので、病理解剖に熱心な病院というのは、基本的に医療安全などに前向きな病院と考えていいだろう。
病理解剖のコストをどうするかは、日本病理学会が何度も提言を出しているが、いまだ実現していない。
病理解剖は、診療の相互検証、向上のために必要不可欠であり、以前より一定数の実施が望まれてきた。とくに先進医療の普及がめざましい現在の日本では、高度な医療の最終評価として、病変の広がり、治療効果の判定など、臨床面へフィードバックすべき事項が増加しており、「病理解剖は診療の延長上」である。 しかし平成12 年(西暦2000年)以降、病理解剖数は減少傾向が著しく、さらに今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、病理解剖数は激減(注5)し、研修医および病理専攻医の教育面からも危惧すべき状況となっている。 日本の医療の質をしっかりと担保し相互検証の医療文化を形成していくため、病理解剖に対する保険診療上、財政的裏付けを明確にするよう継続して働きかけるとともに、病理学会からも病理学会内はもちろん、全診療科に対して、病理解剖の重要性、患者に施した診療の相互検証を行うよう、積極的に発信していく所存である。
https://www.pathology.or.jp/jigyou/2023.html
こうしたチェックの医師を軽視し、「売り上げ」に走る病院の姿勢に強い違和感を感じたのだ。
そのころ書いた記事だ。
おかげで病理診断も10年前に比べて数百件減少。病理診断で僻地医療に貢献するぞと意気込んできましたが、病理診断の需要そのものが減っていたという状態です。
そのため、時間外勤務もほとんどない、極めて健全な働き方ができて、心身ともにリフレッシュできました。地元の飲み会などにも参加し、楽しい日々を過ごしています。
それはそれでよかったのですが、あまり地域医療や病院に貢献できていないという後ろめたさも感じたりしています。
略
というわけで、8ヶ月という短い在野生活ですが、いろいろな気づきがありました。思ったことと違ったことも、期待以上のこともあります。
地域医療に貢献する充実した生活を送らさせていただいていますが、フリーランスや他のやり方がより人々や地域に貢献できるのであるならば、考慮していきたいと思っています。
このときの記事では、「後ろめたさ」と書いているが、内心は病理診断数で成果を評価するとは何事か、と怒りで書いていたのだ。そして、この記事で書いた通り、フリーランスでやっていくことを決意した。
当時は知らなかったが、この時期に医療事故が院内で発生していた。
死亡退院も発生していたのに、病理解剖の依頼が一切なかった。これもこの事故を知らなかった理由であるが、こうしたことからも、赤穂市民病院が医療安全を重視していたのか、振り返って疑問に思うところだ。
赤穂市民病院の置かれた状況
今回、漫画の作者が被害者のご親族であることが分かり、大きな話題になったが、そのなかで、これは赤穂市民だけの問題ではない、という声が聞かれるようになった。
竹田くん問題、竹田くん個人より
— 篠沢教授に全部 (@allbetshinozawa) February 6, 2025
・事故が隠蔽された
・インシデントレポートが無視された
・「医師の倫理・技術の不足」をチェックする機構が国にも医師会にもどこにもない
このへんがよっぽどヤバいんだけどあんまり伝わって無い感あるな https://t.co/Sb1eT9ZFXr
なんとなく、竹田くんが現れて全てをメチャクチャにした、というより、すでに崩壊しかかった地域に竹田くんくらいしか来てくれる人がおらず、実際来させてみたら死んだ、という経緯が透けて見えるというか。竹田くんは原因というより「結果」な感じがしてくる…
— チー (@cheetaro3) February 5, 2025
ようやく構造の問題に光があったかという感じだ。
一つは、これまで何度も書いてきたように、医療事故調査制度が責任追及と原因調査に分けられていないことだ。
もと脳外科医の問題ばかりに注目が集まり、その背景にある原因究明がまったくなされていない状態では、同じようなことは繰り返す。
そしてもう一つは、地方の病院が置かれた厳しい状況だ。
このあたり、内部にいたのでよく知っています。京大がどんどん撤退して、関西のいろいろな大学に掛け合って人を派遣してもらっていましたが(病理の私は神戸大からの派遣扱い)、なかなか人が来ず、ほぼ毎日のように院長、事務長、ときに市長が同行し各地に医師派遣をお願い行脚し続けていました。… https://t.co/Ne8weGQQyC
— 榎木英介 独立系病理医(学士編入) (@enodon) February 6, 2025
私自身の投稿がプチバズっているが、それも含め以下にまとめられている。
だいたい投稿に書いた通りなのだが、もうちょっとだけ深掘りしてみたい。
深掘り部分は有料記事にさせていたき、文末に回す。
自分ごととして考える
このように、赤穂市民病院の医療事故は、病院が巨額赤字をかかえるなか、隠蔽に走り、まともな調査を行わなかったことが発端にある。
だからこそ、事故被害者ご親族が漫画を描き、世に知らしめた。この漫画が世論を喚起した功績は大きい。もちろん、地元紙赤穂民報や、ネットには出ていないが、赤穂新聞も熱心にこの問題を追い、問題点を明らかにしてきた。ローカルジャーナリズムも大きな役割を果たしていると思う。
竹田くんのモデルも、自分が「スケープゴート」にされたと不満を持ち、Xのアカウントを作ったりしたわけだ。
現在そのアカウントは復活し、また投稿を始めている。リンクはしない。
全て赤穂市民病院の医療事故への向き合い方が、医療事故調査制度の基準に満たなかったことに始まる。そして、その医療事故調査制度そのものが、責任追及と責任者探しに傾いているという問題点もある。
さらにいえば、公立病院が生き残りをかけて赤穂市内のみならず近隣の患者を集めるといった状況は、日本の医療制度が作り出した大きな歪みだ。
わが街に病院があり、24時間365日いつでも高水準の医療が提供できる、という医療体制はとても素晴らしい。しかし、コスト、アクセス、クオリティの3つのうち2つまでしか満たせないという「オレゴンルール」がある。
もっとくだけた言い方をすれば、早い、安い、うまいの3つが満たせるのは牛丼だけだということだ。
これが難しいことは、おなじ兵庫県にある三田市民病院と済生会兵庫県病院の合併をめぐる問題をみれば分かる。
そして、はやり同じ兵庫県内で起こった、若い医師の自死の問題は、24時間365日の医療提供が、医師の尋常ではない過重労働にささえられていたことをあらわにした。
医療関係者、そして何より、患者さんや地域住民も含め、少子高齢化や人口減少などもふまえ、これからの医療体制をどうしていくべきかを考えていかなければ、医療も国も持たないところまで来ている。
赤穂市民病院で起こったことは、こうした医療体制の歪み、矛盾とつながっているということも考えなければならない。
もちろん、「一億総懺悔」みたいに、みんな罪人みたいなことにして、当事者を免責するというつもりはない。そこは勘違いしないでほしい。
このように、さまざまな構造の歪みをあらわにした赤穂市民病院。
もと常勤職員として、私自身この問題と向かい合い、発言を続けていく。これは決してお世話になった赤穂を裏切る行為ではない。理解されないかもしれないが、よりより病院、よりよい医療を作るために行動しているつもりだ。
これが、退職直前で知らなかったとはいえ、事故が起こったときに常勤職員であった自分自身の責任だと思っている。
有料限定 人口減少、新臨床研修制度、僻地、ライバル病院
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?