
「こうち冒険がっかい」キックオフイベントでファシグラを書きまくって見えたもの
2月8日のMyミッション=ファシグラ
2月8日に開催した「安斎勇樹『冒険する組織のつくりかた』出版記念・こうち冒険がっかいキックオフイベント」での私の主な役割は、ファシリテーション・グラフィック(以下、ファシグラ)を書くことでした。役割といっても、「やりたいです!」と自ら手を挙げたんですが。
ファシグラとは、「意見のありようを視覚的に確認するための手法」(出典:『つぶやきの育て方』畠中智子)です。「あー! グラレコですね!」と言われることが多いのですが、グラレコよりも文字がメインで、後から見返すためというより場づくりのための記録手法だと思っていただけたら。
ここまで読んで、「ん?でも、今回は後から見返す記録だったのでは?」と違和感を持った方、鋭いですね。その話はまた後ほど!
準備からすでにテンションUP♪
事前に難波さんが安斎さんに許可を取ってくださっていたので、当日は模造紙を壁に貼れるだけ貼りまくりました。会場のKSBの壁は少し凹凸がありましたが、模造紙が映える色だったので、それだけでもテンション爆上がり!
実は、こんなに大量の模造紙を貼ったのは初めてで、「これからここを埋めるのは自分」という現実をすっかり忘れてはしゃいでいましたw
が、貼っているうちにどんどん右下がりになってって…
のざたんがくすくす笑いながら教えてくれて、あわてて貼り直したのも良い思い出。
今回使った道具
・模造紙:説明は不要ですね。
・透明の養生テープ:模造紙を貼る用。
ガムテープは粘着力が強いので、NGな会場が多いです。
・ラムネ:ブドウ糖補給用。今回、長丁場なので、今回初めて用意。
・プロッキー(太字):メインで書く用の黒と補足用のグレーの2種類。
一応、赤や青も持っていましたが、使う(気持ちの)余裕がありませんでした。
・ミニサコッシュ:予備のプロッキー入れ
付箋は安斎さんがCCMについてお話されたときにスペルをド忘れして焦らないためのカンペです。
本来であれば、これに白の布ガムテープが加わるはずだったのですが、当日持って行くのを忘れちゃいました。おかげで誤字が修正できず。。

いざ本番!ファシグラ開始
安斎さんの講演が始まり、書き始めて最初に思ったのは、「毎日Voicyを聴きながら書いていてよかった!」ということ。話のテンポや流れに慣れていたので、めちゃくちゃ書きやすい!

とはいえ、講演は90分。安斎さんも途中で「Voicy 7本分くらいしゃべった」とおっしゃっていましたが、ラムネを食べてエネルギーチャージしながらなんとか書き上げました。
CULTIBASELabのときは90分の授業をファシグラしてたのになぁと思うと…ファシグラ筋の衰えを実感。これは過去の放送を見返しながら、週一でトレーニングしないと!
気づけば11枚! でも、枚数じゃない達成感
講演の後も、公開1on1や「冒険的質疑応答」の記録を続け、最終的に合計11枚。
いや、ほんとによく頑張ったよ。新品のプロッキー黒1本を使い切ったのも初めてだったし!完走できてほんと良かった!
公開1on1で書いたファシグラは、3人の発表者にプレゼント。それを持って記念撮影に参加してくださる方もいて、「あぁ、書いてよかったなぁ」と。

それ以外のファシグラは、イベント終了まで壁に貼ったままにしてました。写真を撮ってくださる方も多かったのですが、第2部のネットワーキングの際に見返している方がいて。そんな様子を見て、「これこれ♪ このために書いたんだよ」と密かに嬉しくなってました。
安斎さんのお話は具体的でとてもわかりやすく、ためになるぞ!ポイントだらけで、質疑応答やネットワーキングの際に「どれにしたら…あり過ぎて迷う」「詳細を忘れた…けど、気になる。なんだったっけ?」と迷ってしまうかも知れない。もし、そんな人がいたら、思い出すための助けになればと思ったのが今回ファシグラをしたかった理由の大半です(残りはガチで自分が書きたいから)。
今回得た新たな気づき
書いたこと、書けることをほめられることは、これまでもあったのですが、今回、書く意味について対話してくださった参加者の方がいらっしゃって、めちゃくちゃ気づきをいただきました。自分の中にあるふわっとしたものを伝わるように言葉にしながら、自分でも「そっか!そんな意味づけしてたんだ!」と。
このことが無かったら、このnoteも書いてなかったです、たぶん。
私が影響を受けた方の本3選!
ここまで読んでくださって、もし、話し合いの場を可視化したい方へのおすすめ本を3冊選んでみました。
『つぶやきの育て方【改訂版】』
ファシグラに出会ったきっかけでもあるMy師匠畠中 智子さんの書かれたテキスト。
ファシグラだけでなく、ファシリテーションについても説明されており、入門書に最適。
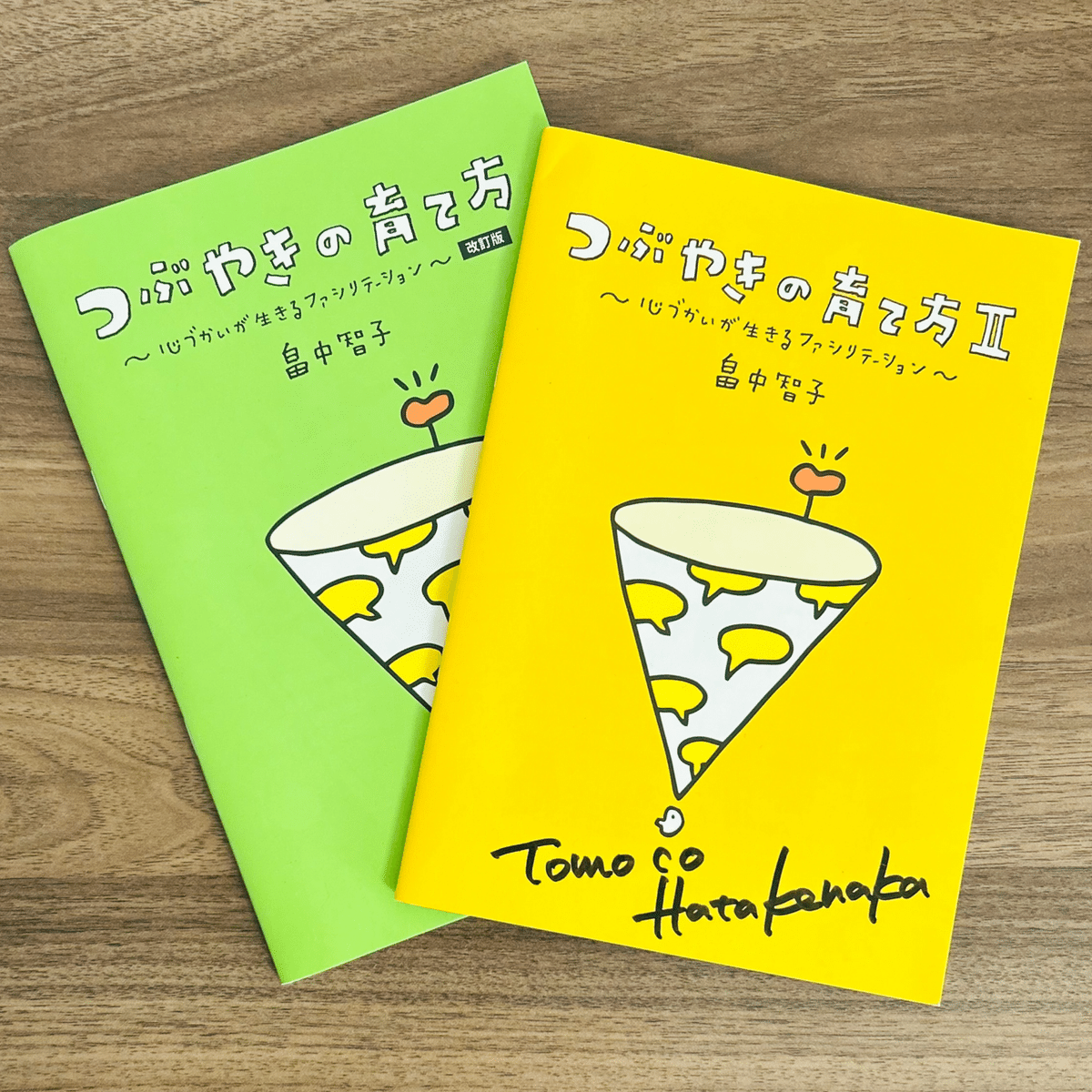
『なんでも図解絵心ゼロでもできる! 爆速アウトプット術 』
WASEDA NEO主催のオンライン講座で、えんま先生こと日高 由美子さんに優しくビシバシと鍛えていただいたことが血肉になっています。
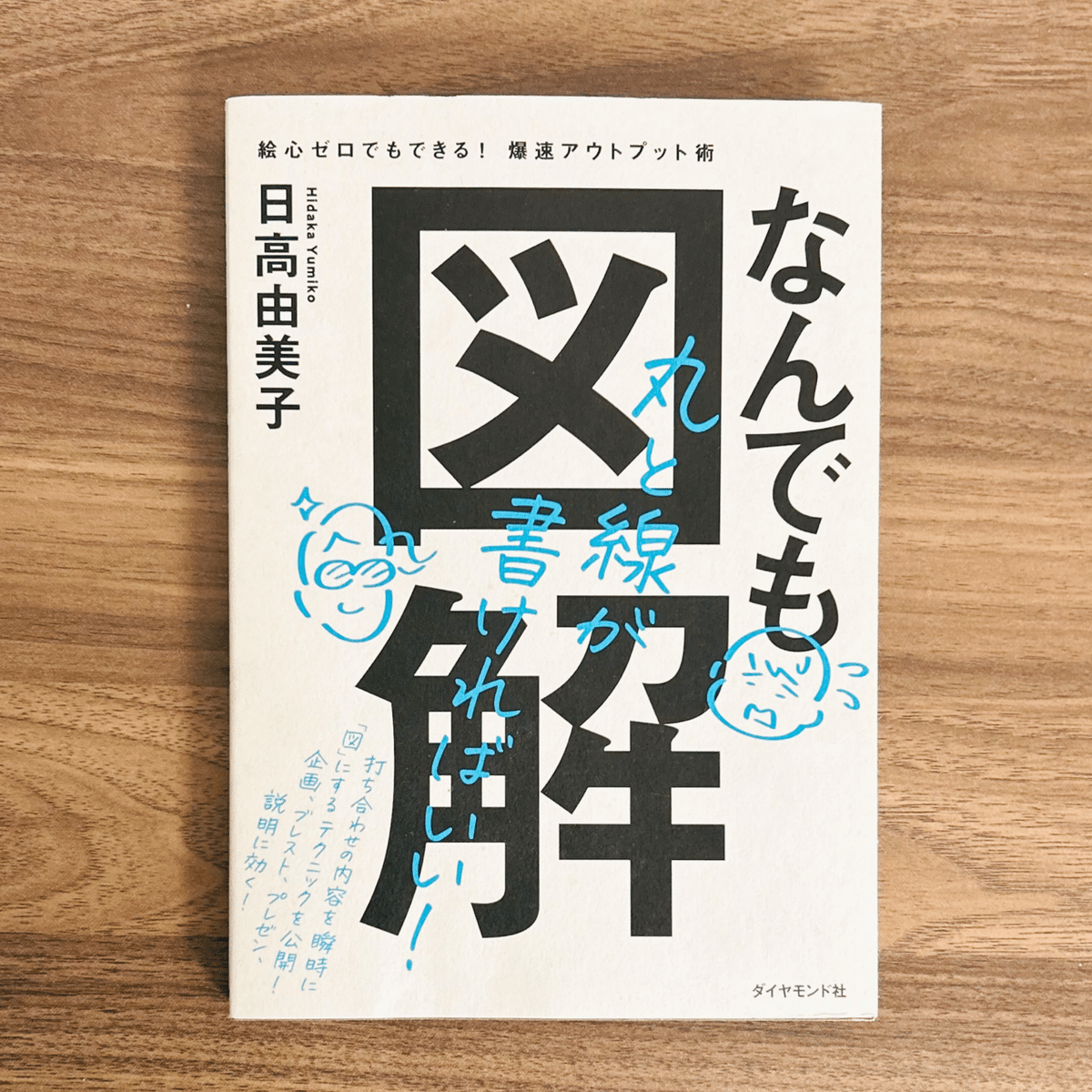
『グラレコの基本』
ファシグラでなくグラレコですが、本園先生には大人たちがずっと学び続ける生放送コミュニティ「Schoo」で本当にたくさんのことを教えていただきました。特に「ネガポジ変換」や「最終奥義」といった場を描くときの姿勢からめちゃくちゃ影響を受けています。
なお、Schooのプレミアム会員になれば、過去の動画で学べます。

