
- 運営しているクリエイター
#ブラジル音楽

column is a diary:ミルトン・ナシメント & エスペランサ・スポルディング - Milton + esperanza(11,000字)
エスペランサ・スポルディングとミルトン・ナシメントの共作を聴いたときに僕は「バランスがいい」と思った。 つまり、よく考えられているアルバムだと思った。インタビューで何度聞いてもその辺の意図に関してはエスペランサは話してくれなかったが、深く考えてやったのだろうし、深く考えて様々なプランをたてて臨んだが、81歳のミルトンからダメ出しもされたし、変更も余儀なくされたのではないかと思う。随分ラフな仕上がりになっている曲もあるし、エスペランサっぽくないところも沢山あるのはそんな現場の

interview Antonio Loureiro:エレクトロニカ、アマゾン先住民、北東部のダンス音楽などの影響を反映する初期2作
2010年ごろ、アントニオ・ロウレイロという才能が発見されたときのことはよく覚えている。2010年に1stを高橋健太郎が紹介したことで彼のことが日本でも知られるようになったのだが、僕が聴き始めたのはセカンドアルバムの『So』からだった。 ブラジルのミルトン・ナシメント周辺コミュニティのサウンドに通じるもの、もしくは当時日本で話題になっていたアルゼンチンの新しい世代によるフォルクローレの作品群とも共通するものを感じただけでなく、2000年以降のアメリカのジャズを思わせる作編曲
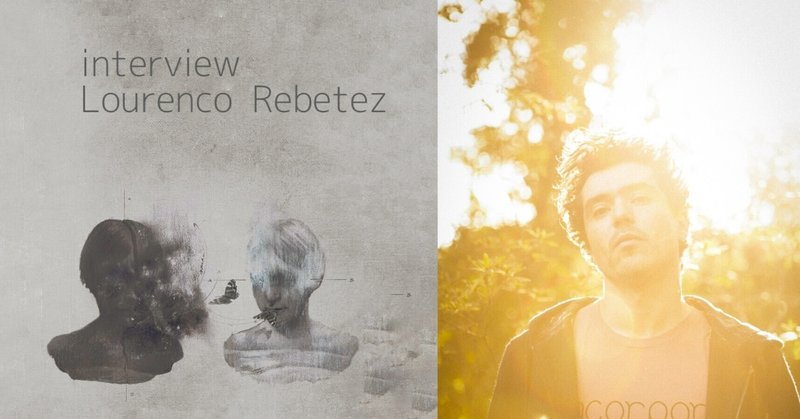
interview Lourenco Rebetez:レチエレスの音楽ではオーケストラの中でリズムが爆発するように多くの音と交わる
僕がブラジルの音楽の中でもアフロブラジレイロの音楽へ関心を強く持ったきっかけは、2016年にロウレンソ・ヘベッチスという作曲家でギタリストが発表したアルバム『O Corpo de Dentro』だった。 ギタリストとしてはカート・ローゼンウィンケル以降の現代ジャズのスタイルもあれば、アイザイア・シャーキー的なネオソウルのギターも聴こえていた。つまり、2010年代におけるギタリストの必修科目と言えるスタイルを兼ね備えていると感じられた。また作曲の面ではギター・カルテットを核に
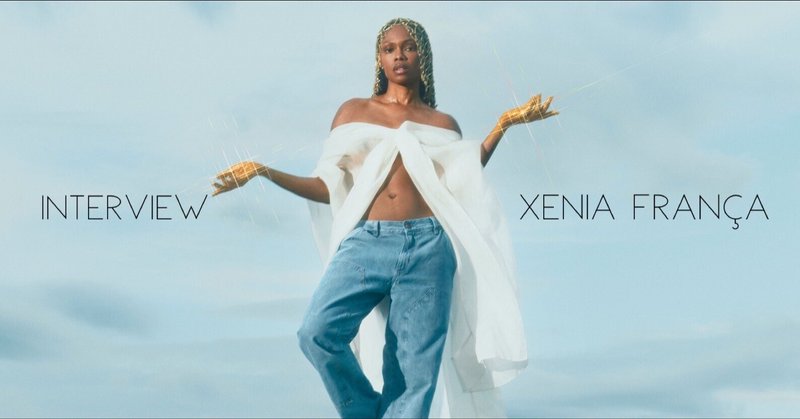
Interview Xenia França:アフロブラジレイロとしての誇り、ステレオタイプからの超克を込めたスピリチュアルな傑作を語る
シェニア・フランサの1作目『Xenia』は鮮烈だった。ロバート・グラスパーやホセ・ジェイムズに端を発し、そこに追随するかのようにハイエイタス・カイヨーテやジ・インターネット、ムーンチャイルドらがジャズ×ネオソウルの再解釈を行っていた2010年代。ブラジルの北東部、アフリカ系ブラジル人=アフロブラジレイロの人口がブラジルで最も多く、その文化の中にもアフリカ系の影響が色濃く残っているバイーア州に生まれたシェニア・フランサは、そんなジャズ×ネオソウルの流れにアフロブラジレイロの音楽
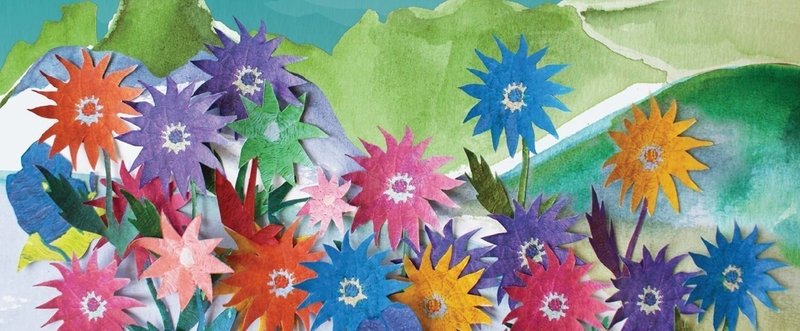
interview Pedro Martins & Antonio Loureiro:Talks about 『Caipi』Jazz The New Chapter 4 OutTakes
カート・ローゼンウィンケルにインタビューした時に、「次のアルバム『Caipi』にはペドロ・マルチンスとアントニオ・ロウレイロというブラジルの若いミュージシャンが参加している」という話を聞いた。立ち話してる時にカートは「なんでアントニオやペドロをすでに知ってるの?」という感じだったが、僕の友人の音楽評論家がアントニオの1stを発見したんだというような話をしたりした。 あとから、ペドロ・マルチンスのアルバム『SONHANDO ALTO』を聞いて驚いた。ディスクユニオンのサイトに
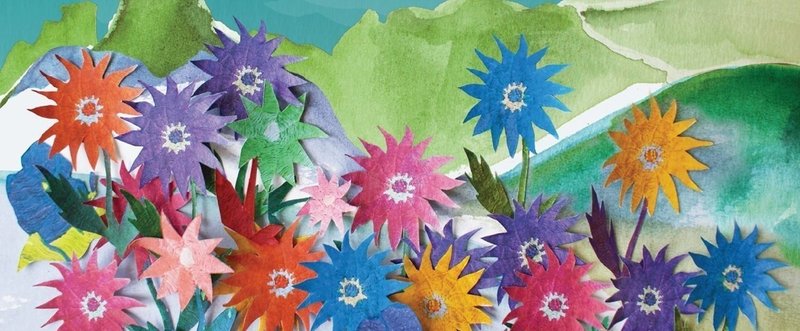
Review:Kurt Rosenwinkel - Caipi:メロディーと演奏がコネクトするカートの脳内で鳴っていた理想のサウンド
現代ジャズ最重要ギタリスト、カート・ローゼンウィンケルの新作はこれまでの彼のコンテクストとは少し異なる異色作だ。ペドロ・マルチンスとアントニオ・ロウレイロというブラジルの新星や、マーク・ターナーやベン・ストリートといった旧知の仲間、更にはエリック・クラプトンなどがクレジットされてはいるものの、ほとんどの楽器をカート自身で演奏し、自ら丹念に重ねた多重録音で生み出した架空のバンドサウンドだ。 僕はこれを最高傑作だと言い切ってしまうことに躊躇はしない。『Remdy』でコンテンポラ

interview Kurt Rosenwinkel - Caipi:Jazz The New Chapter 4 OutTake
2013年の11月にカート・ローゼンウィンケルがバッド・プラスと来日公演を行った時のことだ。カートとバッドプラスのインタビューの司会をして、帰ろうとしていたら、カートがギターショップにギターを観に行くから、一緒に来てもいいよってことになって、ついていった。なぜか移動は電車だったので、カートと電車に乗って、雑談しながら移動をした。その時に、「今、3枚のアルバムを作っている。そのうちの最初に出るのはブラジル音楽のアルバムだと思う。タイトルは『Caipi』だよ」って教えてくれて、「






