
歴史の中で馬がいたという事の意義 〜秀吉の大返しから江戸の日常まで〜
イントロダクション:馬の速度の驚異
馬の速度に関しては、常歩(なみあし)で時速約6.6 km、速歩(そくほ)で時速約13.2 km、駈歩(かけあし)で時速約20.4 kmと、それぞれ異なる速度で移動できます。そして、一瞬ではありますが、襲歩(しゅうほ)では驚異的な時速約69 kmで走ることができ、これは車よりも速い速度です。

速度とスタミナの関係
例えば、駈歩(約20.4 km/h)であれば、トレーニングを積んだ馬は1〜2時間の連続走行が可能です。一方で、襲歩(約69 km/h)は短距離のスプリントで、通常2〜3分程度しか持続できません。
馬の回復力
適切なケアを施せば、馬は30分〜1時間の休憩で心拍数や呼吸を正常に戻すことができます。これにより、1日の間に複数回の長距離移動が可能となります。
色んな歴史の検証:馬の速度と歴史的な検証
1.中国大返しの検証
本能寺の変が起きた1日半後、豊臣秀吉はその情報を毛利方の斥候を捕らえて把握したとされています。本能寺からの距離は約200kmで、通常の行軍では7〜10日かかる距離です。このため、秀吉が明智光秀を唆して信長を殺して天下を狙ったという「秀吉黒幕説」が一部で支持されています。

しかし、当時、斥候たちは伝馬制度を利用していたとされ、伝馬制度を使うと不可能とは言えません。
伝馬制度とは、馬をリレー形式で乗り継ぐ方法です。具体的な移動距離や時間は不明ですが、もし馬をすぐに乗り換えて移動したとすれば、最短で10時間前後で達成可能だったと考えられます。

実際には、情報の引き継ぎや道の整備状況なども影響するでしょうが6月2日の午前中に状況が把握され、翌日の夕方から午後までの1.5日あれば十分に到達可能だったでしょう。
2.美濃の大返しの検証
岐阜城の織田信孝を攻めるために向かっていた秀吉は、大垣に留まっていた際、柴田勝家が大岩山砦を攻めたという情報を得て急いで現場に向かいました。この距離は約52kmで、秀吉が情報を入手したのは14時の段階でした。
・佐久間盛政の推論と行動の妥当性
この距離は単純な行軍であれば2〜3日はかかります。また、それに合わせて少し早足気味に移動したとして馬を常歩で移動した速さと同じくらいになりますがその時間は8時間戦後となります。そこに休憩時間を1〜2時間取るとしたら翌日以降になると推論出来る。
佐久間盛政がその様な形でその様に計算して推論を行ったかは不明ですが、長年の経験で凡その行軍時間に関する情報を佐久間盛政が把握していたならば秀吉が来るならば数日で早く来れても翌日という推論は理にかなってると言えるでしょう。
なので、砦を壊したらすぐに戻れという柴田勝家の命令を聞かずに大岩山でそのまま野営していました。

・実際の秀吉の行動とその後
しかしながら、秀吉は移動を駈歩で行ったとします。そうすると、到着まで約2.5時間前後となります。馬の体力も考えて、途中で1時間休憩を2回程入れても4.5時間で現場に着く事が出来ます。実際、秀吉は現場には5時間で着いていました。
その様な不測の事態により柴田軍は敗退してしまいます。この様に馬というのをどう扱って行軍するのかという認識のズレがまさしく歴史的な大きな転換点を作るきっかけとなったのです。
余談:「大返し」の実態とは
余談ですが、当時、馬を扱った武将は全体の約1割程度でした。中国大返しと併せて考えると、秀吉とその側近たちが現場に早く到達したという形だったのが後の世の中で拡大解釈されたというのが「大返し」の実態だったのかもしれません。
3.弘道館と偕楽園の距離
「弘道館」は水戸藩の9代藩主・徳川斉昭が設立した藩校で、「偕楽園」はその学びの場の人々の憩いの場所として造られました。両者の距離は約2.8kmで、徒歩では約40分かかります。朝の勉学後、午後に実学として剣術稽古等を行い、その後に憩いの場所として歩くには少々厳しい距離です。さらに、弘道館は偕楽園よりも高い場所にあるため、帰り道は坂を登る必要があります。
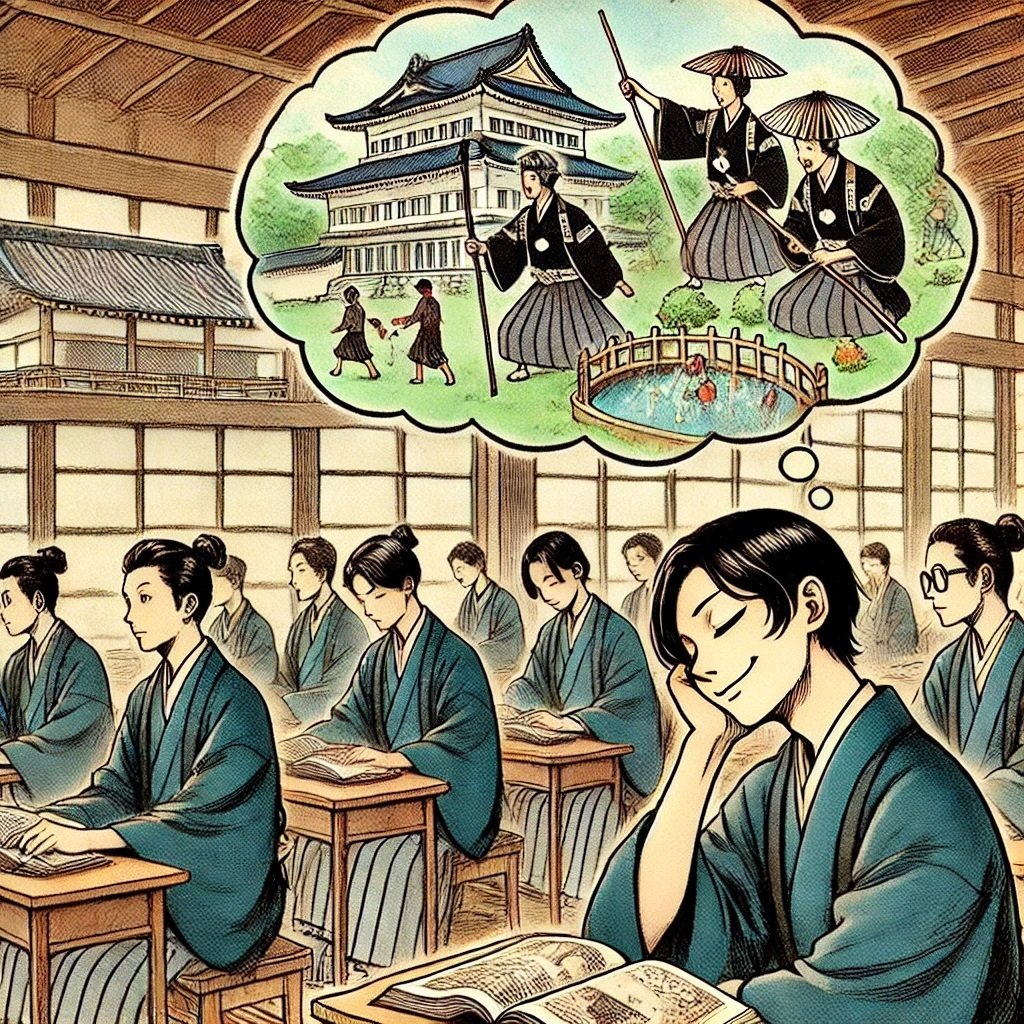
しかし、馬を使った場合、駈歩ならば移動時間は8〜10分ほどに短縮され、襲歩ならわずか2〜3分で移動可能です。これなら、現実的に偕楽園が憩いの場として機能していたことが理解できます。毎年2〜3月に偕楽園で梅祭りが開かれる際、馬術の得意な人が授業後すぐに祭りを楽しんでいる姿が目に浮かびます。
結論
馬の驚異的な速度と持久力は、歴史の重要な転換点で大きな役割を果たしました。秀吉の大返しや日常生活における移動手段として、馬は当時の武士にとって現代の自動車に匹敵する存在でした。この視点から見ると、歴史的遺物や事件の捉え方が変わるのではないでしょうか。
