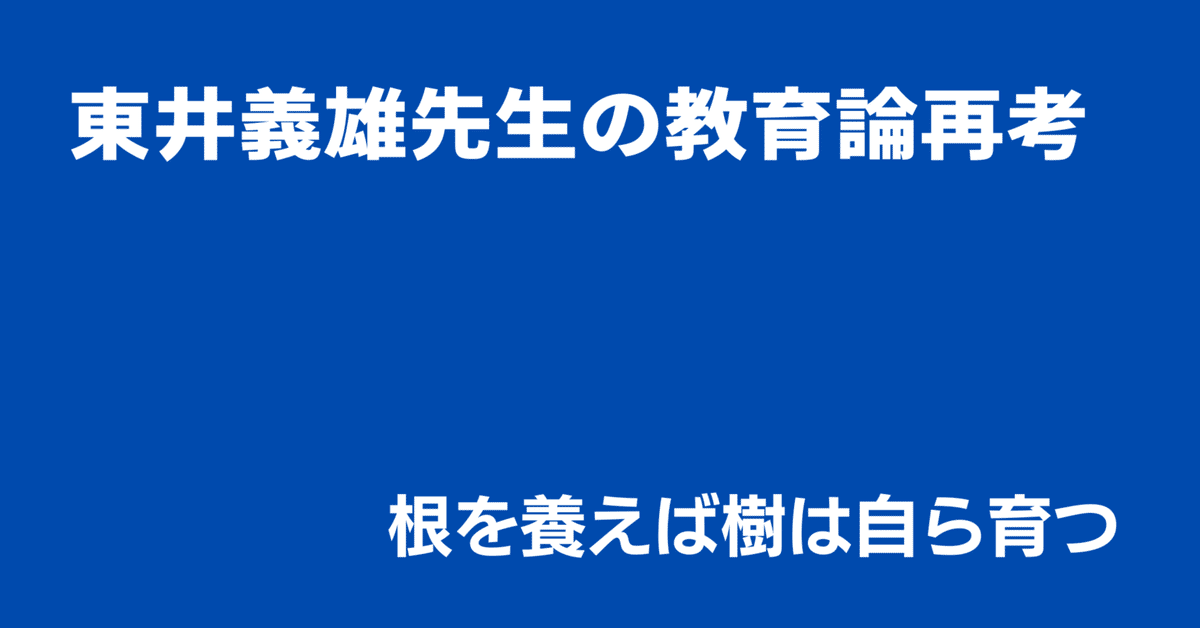
No.3 「ほんものの学力」は「人間」とともに育つ-東井義雄『いのちの根を育てる学力』国土社-
2025年2月9日(日)
今回は,こちらの書籍から東井先生の教育論を明らかにしてみよう。
東井義雄『いのちの根を育てる学力-人間の回復-』国土社
東井先生を代表する「村を育てる学力」ということばがある。
経緯としては,
当時の調査において,農山村・漁村の子どもの学力が低いという結果が発表された。東井先生のいた兵庫県でも教育課題として取り上げられ,教育研究所によって次の対策が打ち出されたそうである。
農山村・漁村の子どもの学力が低いのは,地域に希望がないためである。希望を育てるためには,農山村・漁村も,その空は都市につながっていることを自覚させ,都市に雄飛する青少年を育てるようにすることによって希望を育て,進学指導を強化すれば,学習意欲を育てることにより,学力を高めることができる
戦後の貧しさの残る時代において,都市に生きる希望を見いだすしかなかったのだろう。
これに対し,東井先生は次のような主張をしている。
それでは「村を捨てる学力」になってしまうではないか。しかも,それは,入学試験用の学力であり,点とり学力であり,ほんものの学力とはいえない。村に希望がないことは事実であるが,希望のもてないその村を,何とか希望のもてるような村に育てようということに希望を育てる道を考えたい。そういう中で,ただ特典につながればいいという,点とり学力,入学試験用の学力ではなく,人間そのものを育てる学力をこそ目指すべきである
東井先生は,「村を捨てる学力」ではなく「村を育てる学力」を育てようと日々の教育活動を行ってきたわけである。
現代においても,点とり学力や入学試験用の学力を育てているところはあるだろう。いい大学に行って,いい会社に入ってなどという思考から抜け出せない親も多いはずである。
現在は,入試改革によって,変わりつつあるし,学力主義で就職が決まるような時代ではない。
最近では,本当の能力を見極められるようなリクルートを行っている企業も増えている。コロナをきっかけとして在宅ワークが推奨される場合もあり,必ずしも,都市部で働く必要はなくなっている。
つまり,働き方の価値観が大きく変容している。
これを踏まえると,東井先生の主張する「ほんものの学力」を育てることが重要となる。
東井先生のいう「村を育てる学力」とは,ほんとうに生きて働く知恵・学力のことである。
それを育てるために,東井先生は,「生活の論理」と「教科の論理」という言葉を用いて語られている。
東井先生は,両者の関係を次にように述べている。
子どものものの感じ方・思い方・考え方・行い方のすじ道を,私は「子どもの生活の論理」といってきたのであるが,ほんものの学力とにせものの学力のちがいは,これを大切にするかどうかに決まるといっていいように思う。(中略)
しかし,ここで警戒しなければならないことは,子どものものの感じ方・思い方・考え方・行い方にとらわれ,これにふりまわされてしまうことになると,これは「はいまわり児童中心主義」と批判されても仕方がないということになる。
そういうことにならないためにも子どもの論理を客観性のあるものに育てあげていくためにも,入学試験であろうが,就職試験であろうが,へっちゃらでのりこえていくことのできるような確かな学力を育てるにしても,常に大切にしなければならぬのが「教科の論理」である。
算数には算数の,国語には国語の,理科には理科の,どうしても子どものものにしてやらなければならない学問のすじ道というものがある。
著書では,教科の論理を粗末にしたエピソードが語られている。
そして,最後に,次のようにまとめている。
ほんとうの「学力」というのは,この「生活の論理」が「教科の論理」を完全消化して,「生活の論理」そのものが変革され,客観化され,生きて働く力となったものということになるだろう
東井先生が考えているものこそが「学力」である。
多くの授業では,教科の論理が優先される。
校種があがれば,余計にその傾向は強いだろう。
子どもたちのものの感じ方・思い方・考え方・行い方のすじ道は意識していないことはないだろうが,生かされていないのが現状である。
東井先生自身も,校長として中学校に配属になった際,
中学校の授業に衝撃を受けたようである。
ある子どもの日記の表現を借りて,
「猛烈なキカンジュウ式授業」と表現している。
つまり,先生が一方的にしゃべり続けているということであろう。
東井先生は,この授業を見て次のように感じている。
これでは「人間破壊」の授業であると思った。教えた,ということにはなっても,学んだということにはならないと感じた。
「人間破壊」という強烈な表現ではあるものの,これではダメだという危機感が伝わってくる。
この著著の副題にもなっている「人間の回復」という表現にもつながっているのだろう。
東井先生は,「生活の論理と教科の論理の止揚統一を目指す」と表現している部分がある。
気になったのは「止揚」である。調べてみると次のような意味だとわかった。
止揚(しよう)<アウフヘーベン>
ヘーゲル弁証法の根本概念。あるものをそのものとしては否定するが,契機として保存し,より高い段階で生かすこと。
矛盾する諸要素を,対立と闘争の過程を通じて発展的に統一すること。
つまり,古いものが否定されて新しいものが現れる際、古いものが全面的に捨て去られるのでなく、古いものが持っている内容のうち積極的な要素が新しく高い段階として保持される。
当然,授業において,子どもの生活の論理と教科の論理の対立が生まれる。もしくは,生まれるように授業を仕組んでいく。
その生活の論理と教科の論理の対立を経て,より高次の新しいもの(生きて働く知恵・力)が生まれるのだろう。
