
α(アルファ)世代とは?特徴やZ世代との違い、家庭の教育方針までα世代の研究組織「α世代ラボ」独自の研究結果から解説!
こんにちは、α世代ラボ主任研究員の喜藤です。
近年、「Z世代」という言葉を目にする機会が増えましたが、その次の世代である「α(アルファ)世代」はご存知でしょうか。現在、消費の中心を担っているのはZ世代ですが、数年後にはその主役が「α世代」へと移り変わると予想されています。
このコラムでは、α世代の定義や特徴をはじめ、マーケティング研究組織「α世代ラボ」がアンケートやインタビュー調査で明らかにした新しいα世代像や、彼らを取り巻く環境について分かりやすく解説します。
α世代とは?
α世代とは、Z世代の次に続く世代であり、おおよそ2010〜2024年ごろに生まれた世代を指します。2025年時点では中学生以下の世代になります。
これまでの世代は、X世代(1960~1980年代前半ごろ)、Y世代=ミレニアル世代(1980年代前半〜1996年ごろ)、Z世代(1996年〜2010年ごろ)、α世代(2010~2024年ごろ)と区分されています。

α世代は注目を集めている
α世代は多くの企業からマーケティングのターゲットとされている、Z世代に次ぐ世代として注目を集めています。メディアでも徐々に取り上げられることが増えています。
2024年12月7日公開日本経済新聞:
α世代ラボのコメントも掲載されています!
このように、α世代が注目される理由は、現代に育つ最大ボリューム世代であることです。日本では少子高齢化が嘆かれていますが、若者人口が増加している世界では毎週280万人以上のα世代が生まれています。2025年の総人口数は25億人規模が予測され、 今後のグローバル経済に大きな影響を及ぼす最大ボリューム世代として注目されています。

一方、日本ではα世代は少ない層ではありますが、いずれはZ世代同様に消費の中心、トレンドとなる世代です。企業が今後もビジネスチャンスを獲得していくには、α世代および親であるミレニアル世代の行動パターンや需要に応じた戦略を策定する必要があります。
一般的にいわれるα世代の特徴
では、そんなα世代はどのような特徴があるのでしょうか。従来いわれているα世代の特徴を紹介します。
1.高いデジタルユーティリティ
α世代は、デジタル技術が普及している時代に産まれ、真のデジタルネイティブな世代といえます。
小学校では既にICT教育が導入され、新たな学習指導要領ではプログラミング教育が必修となりました。実際に教員へインタビューをした際に、小学校では、プログラミング教育のほかにも授業の一環で小学生がPowerPointで資料を作成し、学年全員の前でプレゼンをするという機会もあるそうです。

参考記事はこちら!
このように、教育現場では早い段階から本格的にデジタルツールを活用する機会が増えてきています。また小学校5、6年生になると、8割程度がスマホを所持しています。スマホの所持が増えていることに合わせてSNSの利用も盛んであり、中でもTikTok、YouTubeといった動画SNSが人気。α世代は動画で情報収集することに馴染んでいます。
2.タイムパフォーマンス思考
α世代は「タイムパフォーマンス」を重視する傾向にあるといわれています。タイムパフォーマンスとは、時間対効果という意味です。「タイパ」と略されるタイムパフォーマンスの例を紹介します。
YouTubeやNetflixなどの動画を倍速で再生
自分好みのものを提案してくれるSNSの機能を利用
TikTokやinstagramのリールなど、ショート動画を好む
このように、日常的にタイパを意識する行動をとっているのです。この傾向は共働き率が高いことから、「タイパ」を重視する親の影響も大きいといえます。
3.自己肯定感が高く、多様性を受け入れられる世代
α世代は自己肯定感が高く、ゆえに他の世代に比べて自分に対しても、他人に対しても多様性を受け入れやすい世代です。
現代人の自己肯定感の低さは度々話題になりますが、α世代は自己肯定感が高いといわれています。実際に、α世代ラボが実施した「α世代の親子関係・将来観に関する調査」では、α世代を対象に「自分のことが好きですか?」と質問したところ、9割以上が「自分のことが好き」だと回答しました。

調査結果をまとめた記事はこちら!
また、調査だけではなくα世代ラボの活動で行っているインタビューを通しても、家庭や教育機関の教育方針は「褒める教育」であることが多く、ゆえにα世代は自己肯定感が高い傾向にあることが分かっています。また、LGBTQの認知向上など、世の中の多様性を受け入れる動きも相まっているのではないでしょうか。
このような自己肯定感の高さによって、α世代はどのような自分にも自信を持つことができ、合わせて他人も受容できるパーソナリティに成長しやすいのです。
今後もα世代の多様性を尊重する意識は強まっていくのではないでしょうか。
α世代ラボの活動で明らかになったα世代の特徴
ここまで、一般的に言われているα世代の特徴を紹介しました。次は、α世代を研究するマーケティング組織「α世代ラボ」の活動より明らかになったα世代の特徴を紹介します。
1.AIネイティブ
α世代は幼いころから、知らず知らずAIと触れている世代です。α世代が良く使用するSNSであるYouTube、TikTokなどは、AIのアルゴリズムによってコンテンツが提示され、抵抗感なく選択し消費しています。今後のさらなるAIの発展により、よりAIが身近になってくる世代だといえます。
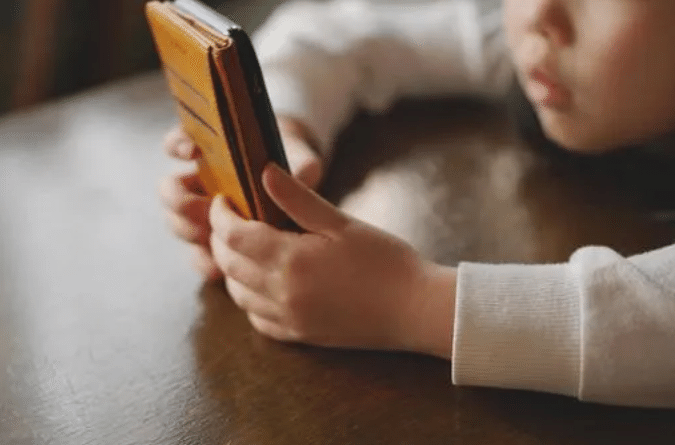
2.「オンライン世界」は生活圏の一部
ここでいう「オンライン世界」とは、バーチャル空間のことを指します。
バーチャル空間
バーチャル空間とは、コンピューターシステムによって生成され、ユーザーがその中で回遊できる仮想空間のことを指します。バーチャル空間は、物理的な空間に拘束されることなく、時間や場所から解放された体験を可能にします。
α世代の生活圏はリアルにとどまらず、インターネット上にまで拡大しているのです。α世代へのインタビューでは、学校ではリアルで友達と出会い、放課後はオンラインゲームで友達と集まるということが一般的に行われていることが分かりました。

また、オンライン世界の使い方も「みんなでゲームに集中する」というよりも、「学校の話など日常的な雑談を中心にしている」といったα世代特有の用途となっており、彼らにとってオンラインゲームは生活圏の一部であり、公園のような存在になっているのです。
同時に、α世代はオンラインゲームやSNSで知らない人たちとコミュニケーションをとることに抵抗感がありません。オンラインゲームをするα世代の親御さんは、時々「はじめまして!」という話し声が部屋から聞こえるとか。
彼らは「リア友」(リアルな友達)と「ネッ友」(インターネット上の友達)の両方を持っており、どちらとの関係性も大事にしています。
参考記事はこちら!
3.α世代=総クリエイター時代
α世代は幼いころからSNSに触れていることもあり、コンテンツを制作・発信することが定着しています。Z世代の兄姉の影響や、SNS上のインフルエンサーを見て憧れを持ち、早いうちから自分をオシャレに見せたいという欲求を持つα世代も多いように思います。
他の世代と比べ、特に動画制作(編集)に長けている傾向があり、テキストを書くように動画を撮って発信します。実際にα世代を対象としたSNS「4kiz(フォーキッズ)」では、多くのα世代がTikTokのようなショート動画を毎日上げています。
彼らはインフルエンサーになろうとしているわけではなく、コンテンツのクリエイト/アウトプットが日常的な活動(習慣)になっているのです。
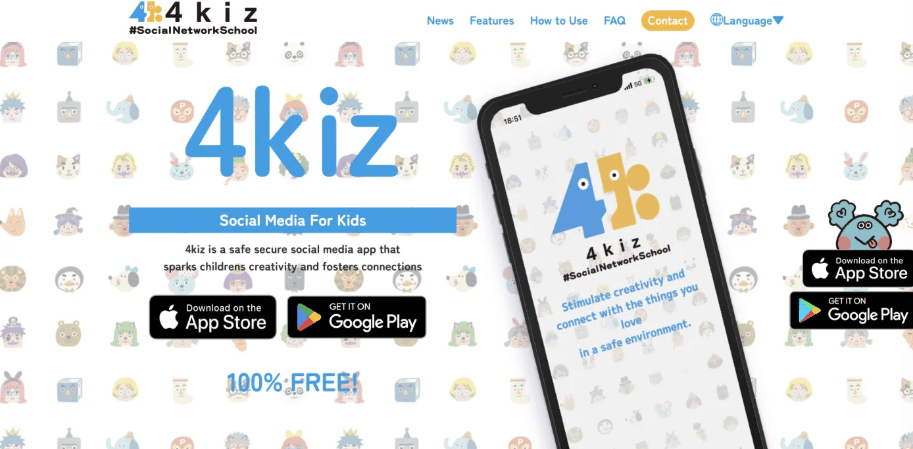
α世代向けSNSアプリ「フォーキッズ」とは
FacebookやInstagram、TikTok、Twitterなどは利用規約上、13歳以上しか使えず、12歳以下の子どもはSNSが利用できない状況です。また、規約違反して利用している小学生も多く、決して安全ではない状況です。そこで、親子で一緒に管理投稿する安心・安全な15歳以下の子ども向けSNSアプリサービスを無料で提供しています。
参考記事はこちら!
4.育つ「社会参画意識」
α世代間で大人気のゲーム「Minecraft(マインクラフト)」などを通して、α世代はバーチャルで自分の世界を創造することに慣れています。その影響からか、現実世界でも「自分たちが過ごす世界は、自分たちで変えていくことができる」というマインドを持つ傾向があり、「社会参画意識」が育っていることが分かっています。
実際に、α世代を対象としたSNS「4kiz(フォーキッズ)」では、好きなコンテンツを持つ人たちで集まる「コミュニティ」をつくり、チャットで会話をします。その中でコミュニティのルールを策定するなど、自然と社会を作っていく動きが見られます。
α世代と他世代の違い
ここまで、α世代の特徴について説明しました。では、Z世代との違いはどのような点にあるのでしょうか?一見、デジタルネイティブやSNSの活用など近しい部分が多いように見えますが、少しずつ違いが表れ始めています。

1.α世代はバーチャル空間、Z世代はSNS空間により親和性が高い
世界で最初にバーチャル空間(メタバース)が注目されたのは2000年代から。2006年頃に起こった「メタバース的」な仮想世界サービスの先駆けと言えるSecond Lifeのブームがきっかけとなり、2021年頃に流行したコロナ禍の影響で一般的に使用されるようになりました。
Z世代にとって、バーチャル空間は新たに誕生した文化ですが、α世代にとっては生まれながら当たり前の存在です。実際には、友達と公園で集まるような感覚でバーチャル空間を使用していたり、授業でも使用されているそう。
また、Z世代はmixiやXなど、SNSによるコンテンツが提供されていた期間も量も多いですが、α世代はマインクラフトなどのオンラインゲーム・Vtuberコンテンツなど、バーチャル空間を活用したコンテンツ提供が増えています。
そのためα世代はよりメタバースなどのバーチャル空間に対して親和性が高く、Z世代はSNSに対しての親和性が高いと考えられます。
2.α世代はSDGsの意識が当たり前に
SDGsが日本で急激に普及したのは2018年頃。レジ袋の撤廃や、学校の制服の選択が自由化したことなど、Z世代は世の中がSDGs意識の高まっていく様子を見てきた世代です。
一方、α世代は物心ついた時には、SDGsの意識を持っていることが当たり前の世界に生きています。そのため、必然的に環境保全、人間としての多様性、働き方(ライフワークバランス)などの意識が高い傾向にあります。α世代ラボで実施した調査では、夏休みの宿題として「SDGsな取組みをして発表する」ことがあるほどだそう。
また、多様性を受け入れる傾向がZ世代に比べて強いと考えられます。その理由はSDGsの浸透と合わせて、後述にもある家庭や教育機関の「褒める教育」の取り入れがあります。
個を尊重される教育のもとで育つα世代は、自己肯定感が高い分、他人の受容もしやすくなるのです。
α世代の親(ミレニアル世代)の特徴とは
ここまでα世代について紹介してきました。幼いα世代は、親の影響が強く影響しています。では、α世代の親のボリューム層であるミレニアル世代はどのような教育方針の特徴があるのでしょうか。
1.褒める教育が当たり前に
昨今「子どもはたくさんほめて伸ばしましょう」という子育て法をよく耳にすると思います。α世代の教育方針では、このような「褒める教育」をとっている家庭がほとんどです。
「褒める教育」は1900年代後半から提示された教育方針。ちょうどミレニアル世代の方々が子どもを育てる年代と重なっています。
実際に、α世代ラボの調査でも、α世代の親を対象に「子供へは褒めることと叱ることどちらが多いですか?」と聞いたところ、70.5%が「褒めることが多い」と回答しました。

このような「褒める教育」は親御さんはもちろん、教育機関にも浸透しているといいます。
α世代ラボのインタビューでは、保育園でお昼寝の時間があったとしても、「寝たくない子は寝なくても良い」と言われます。お昼寝に限らず、極力子どもたちの意見を尊重するような関わり方をするそうです。
2.子どもの「体験」に価値をおいている
従来は子どもに与えるおもちゃなどの「モノ消費」が重視されていましたが、現在は子どもの体験、つまり「コト消費」が重視されはじめています。
「コト消費」とは、「購入することで、どのような体験を経験することができるか」を重視する消費傾向のこと。現代は少しずつ「学歴」よりも、「どのような体験をしてきたか」が重視されるようになってきています。このような動きに合わせ、α世代の親世代も意識が変化しているのです。インタビューでは、「自分の好きなものを見つけてほしい」「好きなものを見つけ、それがスキルとなることが理想」という親御さんがほとんど。
また、親だけではなく、α世代自身もSNSで世の中のカルチャーや出来事に触れる機会が多いことから、自分のやりたいことに積極的に投資し、自分の好みや強みを見つけるために自己投資を惜しまない傾向が強くなると予測できます。
最後に
ここまで、α世代について紹介してきました。記事の中のポイントは以下です。
■α世代の特徴
デジタルユーティリティが高い
タイムパフォーマンス思考
多様性が尊重される世代
AIネイティブ
総クリエイター世代
社会参画意識が高い
「オンライン世界」が生活圏の一部
■α世代とZ世代の違い
α世代はバーチャル空間、Z世代はSNS空間により親和性が高い
α世代はSDGsの意識を持っていることが当たり前の世代に
■α世代の親の特徴
褒める教育
子どもの「体験」に価値をおいている
α世代ラボではα世代の情報を集め発信していくマーケティング組織です。
現段階では、α世代の特徴に注視していますが、今後は消費傾向の調査も実施していきます!
α世代ラボでは、ほかにもα世代に関するコラム記事が多数ございます。
こちらの記事もお読みください!
調査に基づいた取材のご依頼や情報の活用についてのご相談は、下記お問い合わせフォームよりご連絡ください!
