
五味川純平『人間の條件』
『ぼくの命は言葉とともにある』の中で福島智さんが、「光と音のない世界」で生きるご自身の状態を、「戦場などのある種の極限状態におかれた人間がそこででどう生きるかということと共通する部分がある」として、戦争に関連する本をよく読まれているというくだりの中で紹介されていたのが本書でした。
日本の戦争小説で最も感動したのは、五味川純平の『人間の條件』です、これは大学一年生のときに読みふけり、睡眠不足の日が続いて体調不良になったほど没頭したことを思い出します。
『人間の條件』は中国大陸に出征した良心的な一人の男が、軍人としてどう戦い、生き、死んだかを描いた長編です。そこに妻との関係、上官や部下との関係、そして中国人捕虜との関係などが絡んできます。そうしたものも含めて、一人の人間が戦争という状況をどう生きたかが描かれています。
福島さんが体調不良になるほど没頭したというこの小説が気になり、手に取りました。六部からなる大長編でしたが、『人間の條件』というタイトルそのままに、「人間であるということ」が問われるような作品でした。
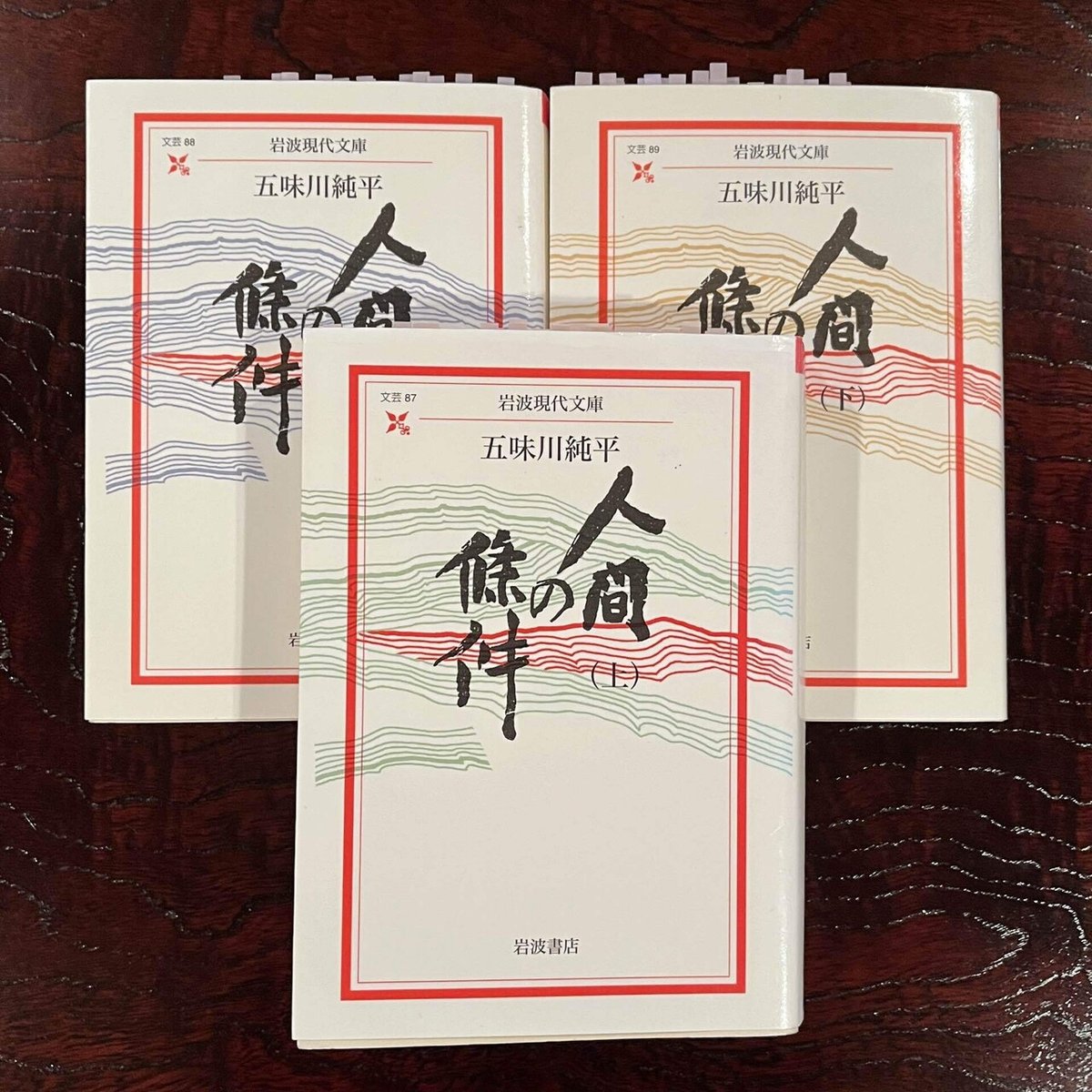
小説の中では、知識人である主人公・梶のおかれる立場がどんどん変わっていきます。植民地の労働者の管理者から、召集免除を取り消され軍隊へ。上官からの一方的な暴力への抵抗、戦闘後の曠野の彷徨、捕虜からの脱走と、凄まじい展開が梶を待っていました。
・人間は誰でも幸福になる権利があるんだからな。(略)逃しちゃ駄目だぞ。摑むんだ。誰に遠慮が要るもんか。
・僕は、ただ、工人の状態を改善して、人間を、人間として扱おうと心がけているだけなんだ
・まあ君は、ぎりぎりいっぱいのところで正しい生き方というのを見せてくれ。罪を犯してしまった人間の正しい生き方という奴をな
・人間を蒙昧の状態に据置いて、生命ぐるみ一切の価値を搾り上げる。それが植民地政策の根本精神だ。
・動物カラ人間ヘノ進化ニハ数十万年カカリマシタ。人間カラ動物ヘノ退化ニハ、長クテモ一年、短ケレバ数カ月デ充分デス。
・人間ハ、イクラ疲労シ、空腹ニナッテモ、モウ一ツ決シテ無クナルコトノナイ恐怖トカ虚シイ希望トカガアルタメニ、コノママデハ死ンデシマウトワカッテイテモ、働キツヅケルノデス。ココニ着眼シテ使役シタ日本人ハ、マコトニ賢明ト申サナケレバナリマセン。
・彼自身の存在が人間として危うく失格しかけているのだ。(略)自分自身への絶望的な戦を宣する合図かもしれなかった。
・いままで彼は檻の外から檻の中の人間に接して来た。今度は彼自身が檻の中に入れられて、到底人間のものではあり得ない世界に、人間を求めることになるだろう。
・そこにはそこなりの、息づまる悩みと苦しみと迫害さえもありはしたけれども、人間が自分の意志で生きる試みをする場所があった。(略)ここは氷雪に鎖された国境地帯。人間がただ戦いのために用意されている。
・人間のそばには、いつでも、必ず、人間がいるらしい。
・この非人間の世界を人間らしく生き抜いてやるのだ。俺は俺自身の可能性を、それが何であれ、最大限に発揮して戦うのだ。
・人間を放棄して、兵営の習性と妥協するのだ。被害者から加害者へ、もしくはその傍観者へ変貌することを、自分の意志にではなく、専ら時間に委ねるのである。「皇軍」数百万の実体は、時間に劫掠された人間の残骸に過ぎない。
・今度の戦闘で死ぬのは、犬死だよ。(略)自分を生かすためだけに戦え。奮戦しろよ。怯じ気づいたら、おそらくおしまいだ
・人間の独立の最小限度が、或は人間そのものの最小限度が、この非人間秩序の上に認められれば、それで満足であった。
・お前は生きたか? お前は働いたか? お前は愛したか?(略)体の奥底から揺り上げて来るおののきがあった。まだ存分に生ききった憶えはなかった。生きたしるしを遺すほどの、何もしてはいなかった。
・梶は胸が痛んだ。すすり泣きに似た喘ぎが起った。豊富な未来、あらゆる欲望、すべての夢を容れるに足りる莫大な未来が、正にこの瞬間から消え去ろうとしている。ここで死ぬ、それでは何のために生きていたか!
・梶は生きた人間に向ってはじめて照準した。(略)これが戦争なのだ、と、心にはっきり云った。怨みも憎しみもなしに、これから人間を殺すのである。何の正当な理由もない。また、同時に、何の良心の呵責もない。単に、これが戦争なのだ。
・果たしてあれが唯一の方法であったか。(略)生きるためには何事も許されているのかどうか。何がどうあろうとも、梶はもう紛れもない殺人者であった。常に人間であろうと念願した男が、だ。そのためにこそ、どのような苦痛とも戦おうと決意していた男がである。人間の中で、いつか、何かが、狂いはじめている。
・彼は心身の力を出し切って逃避行をやり遂げることを決意していたに過ぎない。戦場からの、敵からの、死からの、逃避であるだけでなく、彼を苦しめ続けた非人間的な不自由から逃避するためには、いままでどのように非生物的な不自由にも耐えねばならぬと覚悟しているだけである。
・戦争が終わるとしたら、終戦処理は、どんな勢力の手によって、どんなふうに行われるのですか? 私達が人間として生きることが約束されますか? 私達が戻って行こうとしている社会は、私達を容れてくれますか?
・戦争は俺の意志の外で起った。俺はその中でなんらかの程度に戦争責任を負わねばならんようなことをすることはしたがね。(略)戦争は俺の意志の外で終った。俺はもう沢山なんだよ、自分の意志以外の力で、あっちへひっぱられ、こっちへ動かされて、自分の生活を台無しにされることはね。
・助かろう。いのちをながらえて必ず帰り着こう。決して死ぬまい。殺されまい。絶対に捕虜になるまい。必ず自分の意志で、自分の欲望と願望を貫こう。明け暮れそう思いつめ、自分自身を鞭打って来たことが、梶を動物化していたのは否めない。いや、動物よりも悪かった。智慧や技術もその一点に集中され、鍛えられたという意味では、(略)「殺人技術の名手」に自分自身を作り変えてしまったのだ。
・美千子よ、俺はまだ君にさよならは云うまい俺はまだ、ともかくも生きている。人間が何処まで耐えられるか、バカげた実験だが、やってみようと思う。戦争が俺をそういう実験用モルモットにしてしまったのだ。
・犯罪は終った。すべてが終ったのかもしれなかった。罪悪感など完全に欠落していた。虚しかった。現在から、この場から、前も後ろも断絶してしまったようであった。
長い引用となってしまいましたが、これらの引用だけでも、ヒューマニストの象徴のようであった梶が、「戦争という非人間的な現実」の中で変貌さざるを得なかった様が手に取るように分かります。しかも、その変貌が、梶自身が「人間」であろうする故に起こってしまうという皮肉な現実に、なんとも理不尽さを感じずにはいられませんでした。
生き延びて、生活へ戻らなければならなかった。戻って、そこから出直しさえすれば、過去の全てを、自分自身に説明することも、清算することも出来るはずであった。
「人間」であることを取り戻すべく、ひたすら美千子を目指して歩き続ける梶。梶がどのような変貌を遂げようとも、彼の生き方は、「罪を犯してしまった人間の正しい生き方」を示しているように思わずにいられませんでした。梶にとっては、常に「自分の意志」を保ち続けることが「人間の條件」であり、また、「人間」であり続けることだったのでしょう。
ラストで梶に降り積もる雪は、冒頭で梶と美千子を「ふんわりと柔らかく包」んでいた棉のような雪を思わせるものでした。もしかすると、雪も梶が見ている幻想も、なんら変化していない梶を象徴しているのかもしれません。(八塚秀美)
