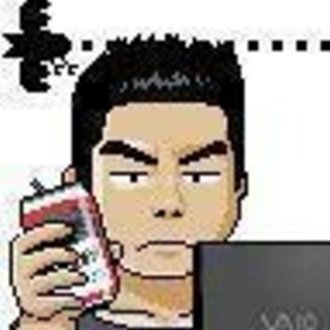お金を稼ぐか、信用を稼ぐか?・「新世界」を読む
ようこそ「新世界」の世界へ。
この記事はお笑いコンビキングコングの西野亮廣さんの著書「新世界」をその章立てごとに読み解くことで、より「新世界」という作品をあんたに楽しんでもらうための記事だ。
今回は6回目。「お金を稼ぐか、信用を稼ぐか?」の章を読み解いていこう。
目次はこちらね。
お金が進化してきた道
お金ってやつはそのニーズに合わせて進化をしてきた。
まずは物々交換に始まった。
「俺は今日撮った魚があるからよ、おまえんところの木の実と交換しくれよ」
ってなもんで、自分が持っているものと相手が持っているものを交換する。
考えてみると、この頃のマーケティングってやつは命がけだよな。昨日は肉だったらいくらでも交換してもらえたのに、今日は魚じゃないと交換してもらえない。
毎日命がけで物々交換。こりゃぁ大変だ。
考えてみたら、物々交換しか出来なかった世界ほど「信用」ってのに価値がある世界もないよな。
「あいつのところでは、毎日肉がある。」
「あいつは毎日木の実がたくさんある。」
そんな信頼感がなければ、安定した物々交換なんてままなるはずもないもんな。
で、流石に不便だろってもんで、物品貨幣ってのが登場した。
(1)誰もが欲しがるもの
(2)収集・分配できて、誰もが納得できる値打ちの大きさを表現できるもの
(3)持ち運びやすく、保存できるもの
これが物品貨幣の条件だ。
結構その条件を満たすのは難しくって、そのモノはある程度限定的になった。
・穀物
・貝殻
・砂金
などなど。
で、この物品貨幣ってやつは(3)持ち運びやすく、保存できるものって条件がものすごく意味が大きくなってくる。
何故かって?
取引の量を増やせるからだな。
持ち運びが便利じゃないと、大量の商品をやり取りするために、大量の物品貨幣が必要になっちまう。
肉100kgをもらうのに魚100kgが必要だったら、大変だよな。
保存できるものじゃないと、せっかく交換して手に入れたものが腐っちまったら目も当てられない。
ものすごい富が1ヶ月後にはゴミの山なんて願い下げだもんな。
なので、この物品貨幣ってやつはどんどん小さく、そして変質しないものが重宝されていくことになった。
変質しないもの。つまりはものとして「信用」できるものをお金として選んだわけだな。
で、次に来るのが、貨幣だ。
貨幣ってのは、物品貨幣に比べて、その価値ってのがより明確化される。
「これが100円分の貨幣だ」ってみんなが認識することによって、その貨幣の価値を確認する手間を省いたわけだな。
それまでは金が何グラムだからどれだけの価値とか、いちいち確認する必要があったわけだが、みんながその「価値」を共有する、すなわち「信用」することで、経済が効率化されたわけだ。
次に出てくるのが紙幣だ。
ここまで来ると、「信用」ってものそのものに対して価値が生じてくる。
紙幣は金本位制という「この紙幣をもってくれば○○円分の金をあげますよ~」って制度から始まった。
つまりは紙幣ってのは金との交換券だったわけだな。
紙幣はその名の通り紙だからな。ものすごく持ち運びが便利だ。
加えて腐らない。だもんで、それに伴って経済規模ってやつがものすごく拡大した。
この金本位制の基本は「この紙を持っていけば金に変えてくれる」っていう「信用」だった。
そして、次に来たのが信用経済。
こうなると、もはや金に変えてくれるっていうものすらない。
「俺がこれは1000円だっちゅーとんじゃ。1000円にしとき」ってなもんだ。
これを言っているのがジャイアンだと限りなく1000円にはならない気がするが、日本という国がその千円札に1000円という価値を認めているよって事実が、多くの人をその紙切れに対して1000円だって認めるようになる。
つまり、日本はその紙切れが1000円だってことを認めさせるような「信用」を世界から得ているってわけだな。
さて、ここまで物品交換から信用経済まで見てきたが、そのいずれにも「信用」ってのが関わっていることがあんたにも伝わったと思う。
つまり、「お金」ってやつはいつだって「信用」と共にあったわけだな。
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?