
ちば在宅医療ことはじめ~まなぶ、つながる、うごく~ 第8回:10月21日(月)
2024年10月21日(月)にオンラインにて、ちば在宅医療ことはじめ第8回目の講義を行いました!
①在宅医療の質評価と組織マネジメント
〜データとナッジで人の意識や行動は変えられるのか?〜:石井洋介先生

自身が潰瘍性大腸炎のため19歳で大腸を失ったことをきっかけに医師を志す。高知大学医学部卒後、消化器外科医として手術をこなす中で、大腸癌などの知識普及を目的としたスマホゲーム「うんコレ」の開発・監修、「日本うんこ学会」の設立を行う。厚生労働省医系技官等を経て、病院の外の医療の充実に力を入れ、在宅医療診療所グループを展開している。おうちの診療所 中野院長、株式会社omniheal代表取締役、高知大学デジタルヘルス学特任准教授など兼任。
石井先生には①在宅医療の質評価と②組織マネジメントについてお話いただきました。
1. 在宅医療の質の評価
石井先生は、複数医師で診療所を開業しようとした際、人によって「いい在宅医療」の考え方が違うことに気づきました。そこで、「患者、診療所、国にとって良い在宅医療とは何か」を開業メンバーで話し合い、8項目(①症例の非選別率向上 ②対応可能疾患数向上 ③イベント数低下 ④緊急コール率低下 ⑤緊急往診率低下 ⑥搬送後入院率向上 ⑦自宅看取り率向上 ⑧在宅医療からの卒業患者数向上)を設定。数値を上げること、下げることそのものにはとらわれず、項目のバランスを見て「外れ値」が出てきたら異常が起きていると察知して対策するよう、院内に浸透させました。
また、石井先生が訪問診療を始めてわかったことは、患者さんの具合が悪くなりきってから出会う病院での医療と、具合が悪いときもいいときも2週に1回会う在宅医療とでは、後者の方が患者さんの「普通」や経過について分かることがはるかに多く、打ち手も増えるということでした。そして、急性期医療では救命率や生存率がゴールになることが多いのに対し、在宅医療は明確なゴール指標がなく、意思統一を図りにくい点が課題だと思い、プロセスも大切にしたQI-8を考案したとのことです。

2. 組織マネジメントについて
開業から約5年でスタッフ数が35人、非常勤を合わせると70人ほどに拡大したおうちの診療所。マネージャーは、組織の規模に応じてマネジメントスタイルを変える必要があることを理解するのが大切だと感じたそうです。経験を通じて分かったのは、20人くらいまでの小規模組織であれば経営者(リーダー)も一人ひとりと話ができる距離なのでフラットなワンチームでいられる。30人以上の中規模組織になってくると、全員と丁寧にコミュニケーションをリーダー一人で取ることは難しく、細かいキャリアの方向性や業務の悩みまでは拾いきれなくなってくるため、リーダーとスタッフの間にミドルマネージャーが必要になるとのことでした。石井先生も、診療所が大きくなるにつれ自分だけでマネジメントをしていくことに困難を覚えたそうですが、大事だと感じたのは、組織全員の目指す方向性を合わせ、文化として浸透させ続ける工夫をすることだったそうです。全てをリーダーが決めなくても、ミドルマネージャーやスタッフが判断できるよう、行動指針やコミュニケーション方法などについて組織の原理原則を作り、現場判断がしやすいようにすることを進めているそうです。こうして作成した原理原則は、今後も組織でアップデートを続けていくと言います。
石井先生の疑問に感じたことはすぐ検証してみる姿勢がとても勉強になりました。それを実行に移され在宅医療の指標を開発されたり、学会を作ったりされているお姿を拝見し、石井先生のご活躍はそのような好奇心から生まれているということがよくわかりました。
②在宅医療の働き方とハイブリッド生活:望月崇紘先生
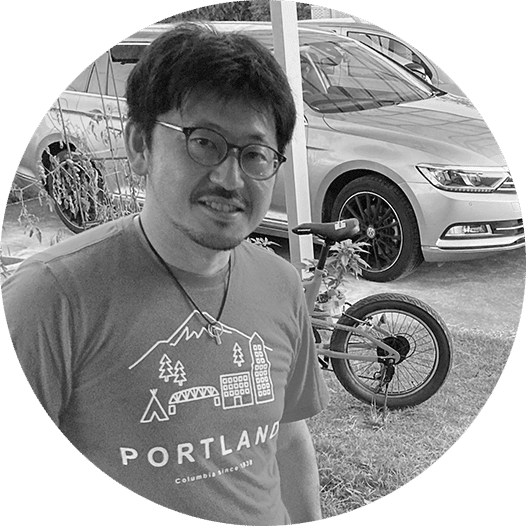
平成18年千葉大学医学部卒。地域医療6割、救急3割、研究1割の医師人生。自宅は都内、職場は君津市で、都会と地方のハイブリッド生活。2017-2019年オレゴン健康科学大学留学を機に地域医療振興協会(JADECOM)内にPBRN(Practice Based Research Network)を設立し代表を務める。地域医療の最前線で看取りを含む在宅医療をしつつ、地域診療所にACPを実装する研究を行っている。また、東京ではラーメン食べ歩き、君津ではBBQやゴルフ、ドライブなどを楽しんでいる。
望月先生には①在宅医療の働き方と②Tipsについてお話いただきました。
1. 在宅医療の働き方
望月先生の診療所では在宅医療で緊急往診が必要なケースはそれほど多くないとのことです。予期せぬ出来事が発生した場合,そもそも電話診療で済む軽症例か,急いで医師が患者宅に駆けつけてもその場で解決できずに搬送になることが多いからです.必要に応じ看護師に訪問してもらい病院調整をして搬送するということもあるそうです.また、望月先生は緊急往診をすることよりも、むしろ、緊急事態になる前のちょっとした症状のうちに連絡をするように患者さんに声をかけているそうです。緊急事態になる前の軽いうちに声をかけてもらったり、病状に対し不安なことの説明をしたりすることで、医師が緊急に呼ばれるという状況が少なくなるそうです。普段から少しでも気になったことを聞ける環境を築き、信頼関係を形成することが在宅医療では何よりも大切とのことでした。
②在宅医療におけるTips
2-1. 患者宅で主治医意見書を作成する
外来患者さんの主治医意見書を作成する際は、患者宅に訪問した方が普段の生活が見えたり、段差や手すりなどのリスク要因も確認できるのでおすすめとのことでした。また、一度敷居をまたぐとその後の定期訪問診療をお願いされるケースも多くなるとのことです。
2-2. 患者宅でACP(アドバンス・ケア・プランニング)をする
患者宅でACPをすると、患者さんの普段の生活や大切にしていることを知ることができ、話が膨らみやすいそうです。会議室では表情もかたくなりますが、自宅ではリラックスして話せるためだそうです。
東京と千葉のハイブリッド生活をどのように実現されているのかに大変関心がありました。千葉にいるときにできるだけ患者さんのフォローや不安の解消に努めることで、東京にいながら千葉県での在宅医療診療所の責任者としての生活が実践できているのだとわかりました。
最後に先生方におすすめ頂いた本はこちら。
石井先生:
緩和ケア・コミュニケーションのエビデンス ああいうとこういうはなぜ違うのか?
望月先生:
いずれくる死にそなえない
石井先生、望月先生、充実した講義をありがとうございました!
ちば在宅医療ことはじめ
公式HPはこちらです!
