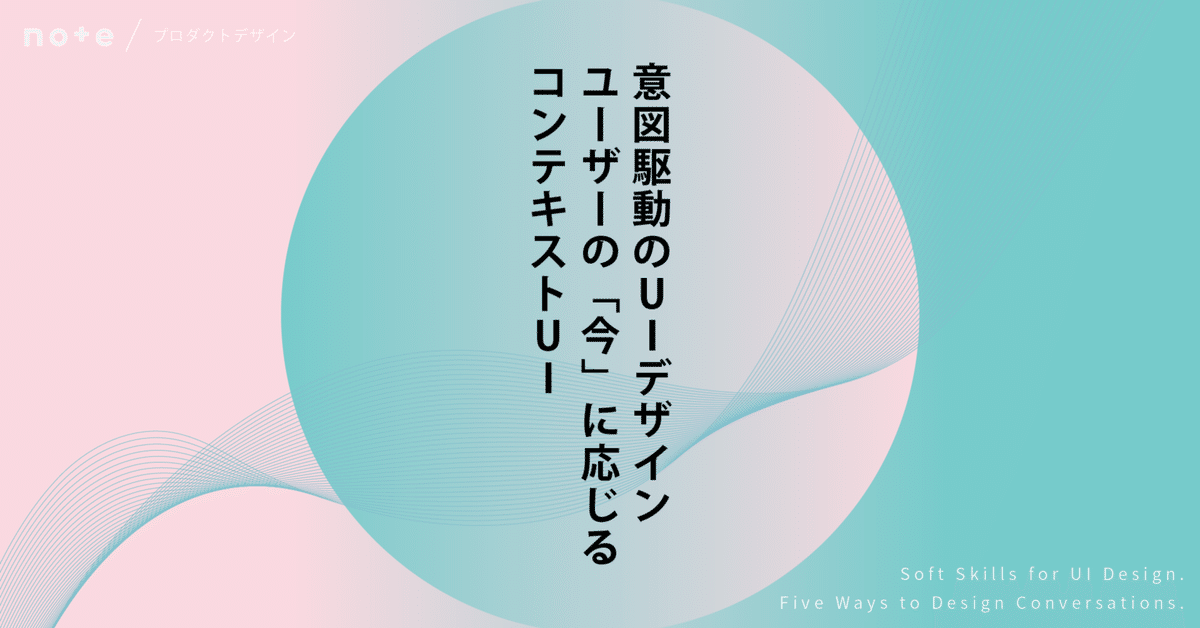
意図駆動のUIデザイン、ユーザーの「今」に応じるコンテキストUI
意図を汲み取るUIデザイン、ユーザー中心のアプローチ
コンテキストUIってご存知でしょうか? 日本語で検索してもほとんどヒットしないんですが(私は知らなかった、不勉強でした)、海外のテックブログで見かけたのでご紹介します。
コンテキストUIは、「ユーザーが今やっていること」に合わせて、ちょうどいい情報や操作オプションを出してくれるインターフェースの総称です。
例えば、Google検索で検索結果以外に情報が表示されることがありますよね。人の名前を検索したらWikipediaが表示され、商品名を検索したらECサイトへのリンクが表示されたり。 要は、ユーザーがやりたいこと(意図)を起点にインターフェースが変わるわけです。それがコンテキストUIです。
これがあると、「あれ、これどこにあるんだっけ?」みたいな手間が減って、サクッと使えるようになる、って感じです。
今のデジタルプロダクトって、とにかく情報が多すぎる。だからこそ、「必要なものだけ、いいタイミングで出す」っていうのがめちゃくちゃ大事なんですよね。
コンテキストUIがうまく機能すると、ユーザーが欲しい情報をさりげなく出せるので、使いやすさがグッと上がります。 しかも、この考え方ってUXデザインの基本である「ユーザー中心」ともすごく相性がいいんですよね。
コンテキストUIのメリット
コンテキストUIの大きなポイントのひとつは、「ユーザーの認知負荷を減らせる」ことです。
情報が多すぎると、どれを選べばいいのか迷ってしまって、結果的に決断が遅れることもあります。だからこそ、必要な情報をちょうどいいタイミングで出してあげると、スムーズに使いやすくなる、っていう話です。
たとえば、旅行アプリでフライトを予約したあとに、関連するホテルやレンタカーの情報が自然に表示されたら、「あ、次これやればいいのか!」ってなって、めちゃくちゃ楽になりますよね。
あと、Google Docsなんかも、テキストを選択したときにフォーマットやリンク挿入のオプションが出てきますよね。 いちいちメニューを探しにいかなくていいので、作業の流れを止めずに進められるわけです。こういう工夫があると、直感的で効率的な体験につながると思います。
コンテキストUIの事例
具体例としてわかりやすいのが、Googleの検索結果です。検索キーワードに合わせて、関連性の高い情報が最適な順序で表示されるだけでなく、画像検索やショッピング情報など、ユーザーの意図に合ったコンテンツにもすぐアクセスできるようになっています。これもコンテキストUIの一種と言えます。
Spotifyの「あなたへのおすすめ」機能も、かなり優秀な例ですね。過去のリスニング履歴やプレイリストの傾向をもとに、新しい音楽を提案してくれるので、「あ、これ好きかも!」みたいな発見がしやすくなります。そのままワンタップで再生や保存もできるので、自然な流れで音楽を楽しめるのがポイントです。
さらに、オンラインショッピングサイトでも、この仕組みはよく使われています。たとえばAmazonでは、購入履歴や閲覧履歴をもとに、「この商品を買った人は、こんなのも買ってます」みたいな関連アイテムを提案してくれますよね。買い物かごに追加した商品のレビューや、よく一緒に購入されるアイテムが表示されるのも、次のアクションをスムーズにするための工夫です。こういう流れがあると、ユーザーは「次に何をすればいいか」を考えなくても、自然と最適な選択ができるようになります。
コンテキストUIの課題
もちろん、コンテキストUIには課題もあると思います。
たとえば、開発コストが高くなりやすいという点です。ユーザーの行動を予測するにはデータ分析が必要だし、シチュエーションごとに異なるUI設計をするとなると、開発の手間も増えてきます。結果的に、作るのがけっこう大変になってしまうんですよね。
それに、適切なタイミングで適切な情報を出すには、かなり細かいユーザーリサーチやテストが欠かせまん。ちょっとでもズレると、「余計なお世話」になってしまったり、「情報が多すぎて逆に迷う…」みたいなことにもなりかねない。だからこそ、どれくらいの情報量を、どんなタイミングで出すのがベストなのか、うまくバランスを取ることがめちゃくちゃ大事なんですよね。
選択肢としてのコンテキストUI
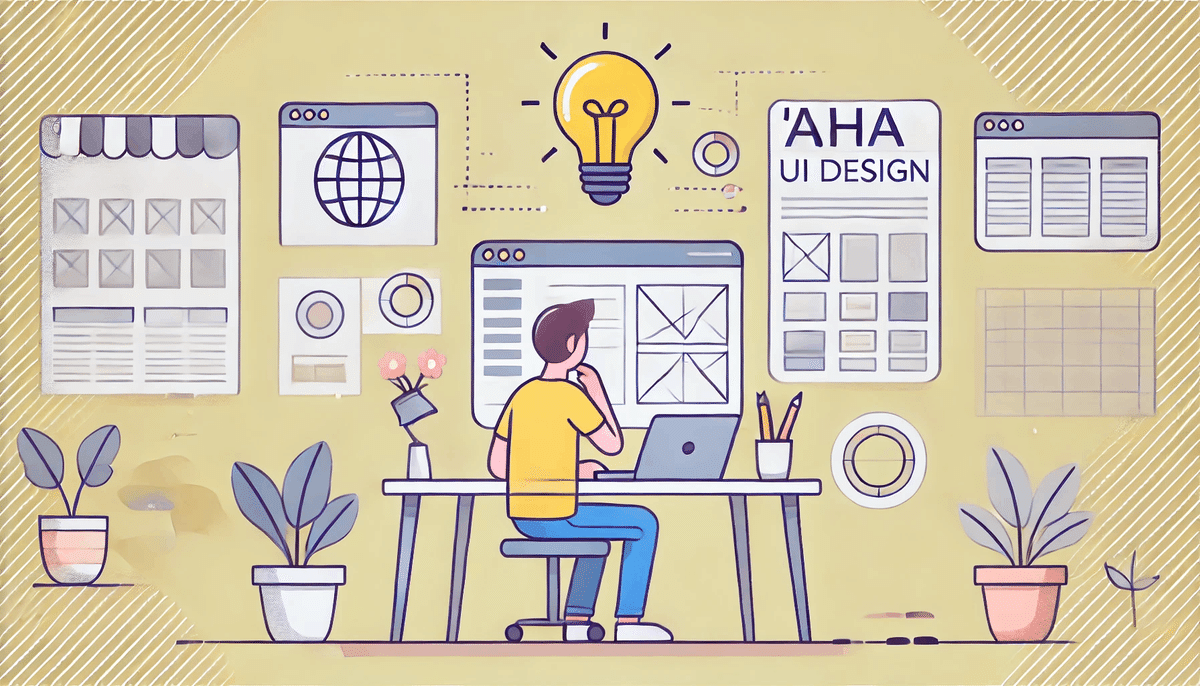
コンテキストを意識する
コンテキストUIをうまく取り入れると、ユーザー体験が向上するだけじゃなく、プロダクト自体の価値も上げられるんですよね。
そのためには、データを集めたり、プロトタイプを何度もテストしたりして、「ユーザーが本当に求めているものは何か?」を見極めることが大事になってきます。さらに、AIや機械学習を活用すれば、より精度の高いコンテキストUIが実現できるかもしれません。
あと、コンテキストUIってOOUI(オブジェクト指向UI)と共存できるのも面白いポイントです。このnoteを読んでいる方の中にも、OOUIに興味がある人は多いんじゃないでしょうか? 近年、UIをオブジェクトベースで設計する考え方が注目されていますよね。私自身も、UIをオブジェクト中心に捉えることが多かったので、「とりあえずOOUIの要件を満たせていればOK」と思いがちでした。でも、そこにコンテキストUIの視点を加えると、新しい発見があるかもしれません。
例えば、ある特定のロールのユーザーが、決まった時間にログインして特定の作業をするというケースを考えてみましょう。この場合、ダッシュボードにその作業へのショートカットを出してあげるだけでも、かなりスムーズに操作できるようになりますよね。
こういう細かい工夫の積み重ねが、結果的にユーザーの認知負荷を下げることにつながるんじゃないかな、と思います。
まとめ
コンテキストUIは、ユーザーの負担を減らし、より直感的で快適な操作体験を実現してくれます。大事なのは、「ユーザーが今、何を求めているのか?」を深く理解し、それに自然に応えられるデザインを作ること。そうすることで、プロダクトの価値もぐっと高まるはずです。
これからのデザインに、コンテキストUIの考え方を取り入れてみると、「あ、こうすればもっと使いやすくなるのか!」みたいな新しい発見があるかもしれません!
プロモーション
iCAREでは、共に成長し、新たなチャレンジに挑む仲間を募集しています。詳細は採用ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております。
XでもUIデザインやプロダクト開発に関する投稿をしています。ご興味がありましたら、ぜひフォローしていただけると嬉しいです。
いいなと思ったら応援しよう!

