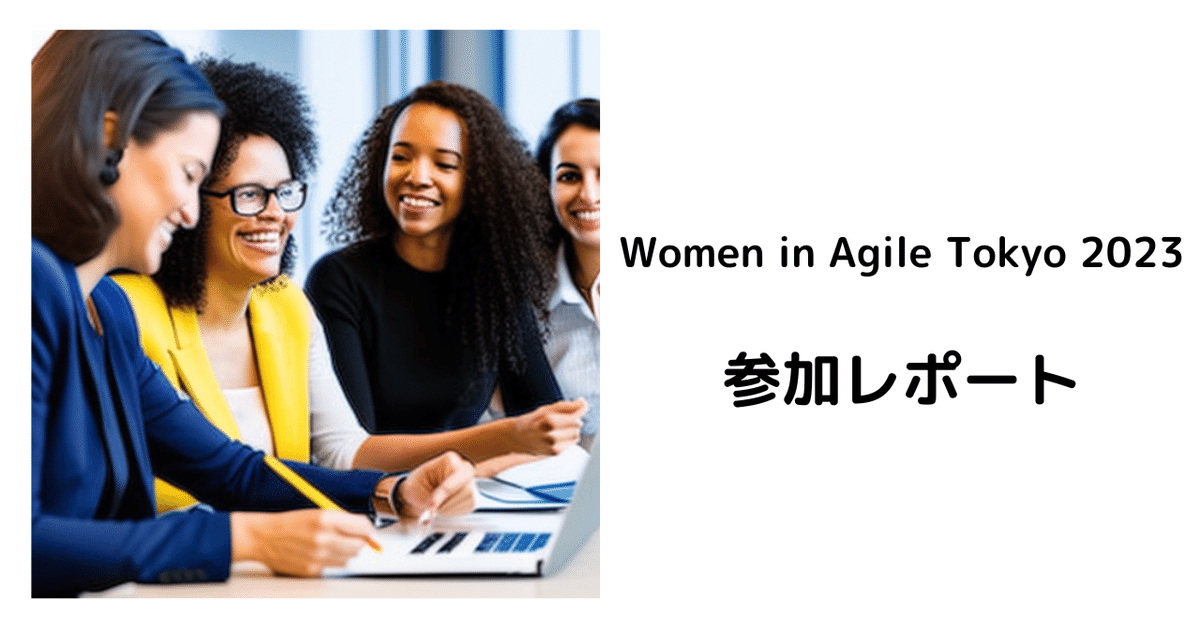
Women in Agile Tokyo 2023に見たOSTの真髄 #wiaj
はじめに
2023/2/17に「Women in Agile Tokyo 2023」が開催されました。本稿はその参加レポートになります。
カンファレンス名からもわかるように、本イベントは女性が参加することを歓迎するものでした。ではなぜ私が参加しているのかというと、女性「にしか」参加してもらいたくないわけではなく、普段こういったイベントに対して参加しづらさを感じている女性「にも」参加してもらいたいもので、女性じゃなくても参加してよいということを事前に伺っていたからです。実際、普段のカンファレンスに比べて女性比率が圧倒的に高かったものの、男性陣も少なからずいました。
キーノート
午前中はREALs理事、武力紛争を防ぐNPO法人の瀬谷さんによるキーノートでした。
武装解除は加害者の更生であるという難しさ。
現場の裁量がないために動けず、失敗から学べない日本。
対話を諦めていた人々。
思わず耳をふさぎたくなるようなそれは、けれどもこの地球の上で確かに起こっていること。感情がないまぜにされていきます。
争いは、規模の大小はあるにせよどこにでもあるものです。諦めもそう。瀬谷さんは、私たちが日頃向き合う争いや諦めの何十倍ものスケールのそれと戦っている。前へ進む確固たる意思を持ち、行動する。
アジャイルカンファレンスなのに、アジャイルの話は出てこない。それなのにアジャイル者たちの心に確実に火を付けるキーノートでした。
OSTに次ぐOST
午後は、なんとまるっとOST。一コマがだいたい一時間くらいで、RSGT等と比べるとかなり潤沢な時間を与えられていました。
私が参加したテーマは「対話」、「目上の人との接し方」、「安定してきたチームが次に進むためには」、そして「変わらないというあきらめを超える」。最後のテーマは自分が出したものなので、後で詳しく書きます。
このOSTの体験が非常によかったです。時間がたっぷりあるから、あわてて結論を出そうとすることなく十分に掘り下げられる。テーマを出した人は自分が話したいテーマだし、集まってきている人はそのテーマに共鳴している人だしで、ファシリテーターが頑張りすぎなくてもちゃんと盛り上がる。
今回、私は二人の同僚を連れて参加しました。初めて参加するカンファレンスがOST主体のもので、期待したように学びを得られるのか少し不安でしたが、全くの杞憂でした。
むしろOSTだったからこそ主体的にテーマを出し(2人とも、カンファレンス初参加なのにテーマ出ししたんですよ!すごくないですか!)、興味があるテーマに参加し、最大限学べたように思えます。
「変わらない」というあきらめを超える
前述の通り、私は「変わらない」というあきらめを超える、というテーマを出しました。もともと参加する前には別のテーマを考えていたのですが、瀬谷さんの講演に感銘を受け、急遽この新しいテーマを考案するに至りました。

誰でも「変わらない」と判断し、諦めているものがある。そしてそれは、自分自身は変わらないと判断しているがゆえにそこを変えることは難しい。
じゃあ、他の人から見たらどうだろう。その変わらないと考えている理由をともに分かち合い、異なる視点でまなざすことで、「こういう見方をしたらどうでしょう」という変化へのヒントを得られるかもしれない。そういった思いから、このテーマを提示しました。
ありがたいことに多くの方に興味をもっていただき、16名もの参加者が集まってくださいました。全員に自己紹介をしてもらいながら悩んでいたのが、進め方。4−5人くらいを想定していたのでどうファシリテーションしようか迷った末に、以下のように決めました。
私は話には参加せず全体のファシリテーション・タイムキープに徹する
四人一組で話し合ってもらう
一定時間ごとにその話し合いの内容を共有する
このとき、「こういう進め方ではいかがでしょうか」と問いかけると、ノーリアクションではなくしっかりリアクションしてくださる方ばかりで本当にありがたかったです。

「変わらない」と諦めたことを共有しているフェーズでは、どのチームも少し沈んだような表情が見られました。辛かった経験と向き合っているのだから、それは無理からぬことです。
それが後半、周囲からヒントをもらうフェーズに入ると、徐々に明るい表情が見られるようになっていったのが実に印象的でした。
真正面から反対しないこと。「こうやりましょう」ではなく「こうなりました」で共有していくこと。
この「小さく結果を出し、そこを見てもらう」というのは実にアジャイル的で、その解が自然に出てきたところに語り尽くす対話の素晴らしさを見ました。

ワークの最後にはハピネスドアによるふりかえりも実施。かなりポジティブなフィードバックがいただけて、こんなにうれしいことはない…ってなりました。

私たちの一歩は私たちが作り出す
アジャイル「ではない」キーノート。セッションではなく、OST。これまで経験してきたどのカンファレンスとも違う手触りの、いってしまえば異質なカンファレンス。けれども、しっかりとアジャイルを体現している。本当にOSTの体験がよくて、他のカンファレンスでもOSTの比率を高めると学びの質が更にあがっていきそうだな、なんて思いました。
勝手な憶測になりますが、こういった慣例にはないやり方をやるにはそれなりの議論があったのではないか、と思います。けれども、Women in Agile Tokyo 2023のWebのトップに掲げられた言葉「始めなければ、何も始まらない 私たちの一歩は私たちが作り出す」は伊達じゃない。この言葉を体現したことが、この開催形態につながり、それが結果として他ではないような学びの渦を巻き起こしたのだと私は捉えています。
素晴らしい場を、ありがとうございました。
