
【禍話リライト】「赤い本の親子」
Oさんは、学生時代に地元の図書館で1週間アルバイトをした経験がある。
主に蔵書の整理や移動をする仕事で、その中でも殆ど人が来ない百科事典などが並ぶ区画を担当していたそうだ。
知らぬ間に汗が流れ落ちてしまう程の重労働ではあったが、それにも徐々に慣れ始めていた。
そんなある日のこと。
その日も蔵書の入れ替えの作業で、本棚と倉庫を往復していた。
その最中に、背後から「すみません」と声が聞こえてきたそうだ。
振り向くとそこには、二人の女性が立っていた。
一方は20代位の若い女性で、もう一方は似た顔立ちでやや小皺の目立つ40代位の女性だったそうだ。
二人は揃って『これからピアノの発表会があるんです』と言わんばかりのやけに着飾った服装で、その出で立ちからOさんは(この二人は親子なんだな・・・)と思い至った。
「何でしょう?」と言葉を返すと、母親らしき女性が「すみません、誰も係員の人がいないのでこっち来たんですけど」と、そう話してきたという。
(そんなことあるかなぁ・・・ここ結構奥の方なのに、ここに来るまで誰一人会わないとか・・・)
そのような疑問がOさんにはあったものの、今更無視をする訳にはいかない為「自分は、司書でも何でもないアルバイトで来てるだけなんで──」と、力になれないと説明したのだそうだ。
しかし、Oさんの言い分を聞き入れることなく、母親らしき女性は「いやでも、人がいないので──」と、同じようなことを繰り返し口にしてきたのだという。
(あー聞いてくんないタイプの人なんだなぁ・・・早く司書の人見つけて、引き継いでもらうか・・・)
自分の話は馬耳東風なのだと早々に悟ったOさんは、後のことは司書に対応してもらおうと、取り合えず二人の話を聞くことにした。
すると母親らしき女性に促されて、「〇〇の棚にあった、赤い本を探しているんです」と娘らしき女性が、そう話したのだという。
話にあったその棚というのは、文庫本が置かれている区画だった。
自分たちの今いる場所から比較的近かったこともあり、Oさんは探してみることにしたそうだが、彼女たちが求めている本は無かった。
そもそも大まかに【赤い本】としか聞いていなかった為、Oさんは改めて本の詳細を訊ねてみたそうだが、出版社・著者・本の内容・表紙のデザインといった詳しい情報は「分からない」との返答だった。
困り果てたOさんが、「内容が分からないなら、調べようがないですよ」と半笑いで話しながらこれ以上の捜索を断ろうとするが、親子は頑なに「でも絶対にここにあった!」「あったんならずっとあるでしょ!」と、全く引き下がろうとしない。
(あ、ヤベェ親子だ・・・)
終始こちらの言い分に耳を貸すことなく、自分たちの主張を押し付けてくる二人にOさんは辟易としていたが、そんなことはお構いなしに娘らしき女性は話を続ける。
「いい本だったから読みたいの!ここの棚にあるのと同じ位の大きさの本!そんな本だったってことしか覚えてないけど、ここにあった!」
「・・・それ、どれ位前にあったんです?」
「5~6か月前位にあったの!」
「そん位経ってたら、本の入れ替えなり誰かに借りられてたり、とかはあると思いますよ?」
「でも!誰も読みそうにないボロボロの本だったから!パッと開いたページがすごい良かったから、もう一回探してるんだ!」
「悪いですけど、それじゃ探せないですよ・・・」
そんな問答をしていると、母親らしき女性が苛立った口調で、「なんで分かんないのよ!」と再び口を開き詰め寄って来た。
流石に埒が明かないと思ったOさんは、「司書の人を連れてくるので、ちょっと待ってて下さい!」とその場を離れ、図書館受付まで向かった。
すると親子の話と打って変わって、明らかにすぐに見つけられる位置に司書が三名程いたのだという。
誰がどう見ても胸元にはちゃんと名札があり、パッと見て話し掛けにくそうな雰囲気の人たちでもない。
それを見て、(めっちゃいるやん・・・なんやねん・・・)などと内心思いながら、Oさんはその中の司書の一人に、今あったことを話した。
その司書の方は「あー大変ですね・・・時々いるんですそういう人、大丈夫です、代わりますから──」と快く親子の対応を引き受けてくれた。
しかし、どこを探してもその親子の姿はなかったのだという。
Oさんも混じって館内を一通り回ったのだが、それらしき人影すら見当たらなかった。
本人たちがいなければ対応のしようもない為、元の持ち場に戻ろうという話になり、Oさんは腑に落ちない心境のまま図書館の奥に戻っていった。
また別れ際「一応皆に把握させておきます」と司書の方は言っていたが、その後親子がその司書の方を始めとする、職員の前に現れたという話は結局無かったそうだ。
持ち場に戻って、先程同様に本棚と倉庫間を往復していたOさんも、再びあの親子と遭遇することは無かった。
そして、そうこうしている内に休憩の時間に入った。
(なんだったんだろう・・・)と思いつつ休息を得ていると、別の区画で働いている知り合いに声を掛けれた。
「聞いたぞ、大変だったなぁ」
「あぁ、面倒な親子連れでしたよ」
「でも、偶にいるらしいぞ。お前程酷くないんだけど、物凄いざっくりと『猫が出てくる話ってどこにある?』とか」
「それ『吾輩が~』以降いっぱいあるでしょ・・・」
「そうなんだよ。あと『最後が嫌な感じに終わるミステリーってあるか?』とか」
「ミステリーって大体そうでしょうに。アハハ!そうなんですかぁ~」
知り合いが気を遣って、笑い飛ばそうと話を振ってきてくれたお陰で、Oさんは幾らか気分が落ち着いた。
そして親子の対応で遅れていた作業を再開しようと、休憩を少し早く切り上げて、自分の持ち場に戻ろうとしたという。
しかし、その考えはすぐに改めることになった。
遠巻きに目撃してしまったのだ。
自分の担当の区画に、またあの親子がいるのを。
二人は付かず離れずの距離を保ち、忙しなく通路や本棚の間をちらちらと確認しながら、区画を歩き回ってる。
(ウワッ!キッツ!!)
その様を見てOさんは、一目散でその場から逃げ出した。
親子は明らかに、受付で作業をしている司書の存在をも確認出来た位置にもいた。
しかしそれを無視して未だに誰かを探しているということは、即ち自分を再び捕まえようとしているのだと、そう直感したからであった。
興奮と恐怖に苛まれ若干ぎこちない動きで、Oさんは再び休憩場所に戻っていったそうだ。
そして休憩場所の入口付近で、知り合いから「おいどうしたんだ?まだ時間あるぞ」と怪訝そうに話しかけられ、咄嗟に「そうですよねぇ・・・?」と生返事をした。
助けを求めることも出来たであろうが、(まぁここにいる人たちと一緒に戻れば、さっきみたいなことにはならないか・・・)と、そんな考えが頭に浮かんだこともあり、結局誰にも伝えずにそのまま休憩をし続けたという。
そして休憩明け。
内心ビクビクとしながら自分の持ち場に戻ったが、そこにあの親子の姿は無かった。
(いない!?まぁいなけりゃいいか・・・)
肩透かしを食らったOさんであったが、一先ず元凶たるあの二人がいないことに安堵し仕事を再開した。
それからというもの、あの親子を警戒しながら業務にあたっていたそうだが、結局再び親子と相見えることは終ぞ無かったのだという。
アルバイトの期間も終了して暫く経った頃に、知り合いにさりげなく訊いてみたところ、「いや、あれ以来一切来てないみたいだな。諦めたんじゃないか?」との返答だった。
(他のところに行ってくれたなら、まぁいいか。他のところ気の毒だけど・・・)と、そんな感想をOさんは抱いていたとのことだった。
それから数年後。
社会人になっていたOさんは住んでいたその地域を離れて暮らしていたが、ある日同じ地域に住んでいたというE君と飲みの席で一緒になった。
自分よりも年下のE君は、まだその地域を出て日が浅かったこともあり、Oさんは「どこの高校だ?」「あの店まだあるの?」などと質問しつつ、E君と郷里の思い出話に花を咲かせていたそうだ。
楽しく語らう中で、偶々地元のネガティブな噂についての話題になったのだという。
「あー嫌な噂ってその土地とか建物とかであるよねぇ~。でもあんま無いよね俺らの地域って」
「まぁそうっすね。でもあったとしたら、俺らの世代だと、【赤い本】の話っすかね?」
「え・・・何それ?」
「俺は見たこと無いんすけど。でもね、俺の直接の友達が見てるんで、これは本当っすよ」
不意にE君の口から発せられた【赤い本】という言葉。
それを聞き、Oさんは数年前にあった奇妙な体験を想起してしまう。
内心は動揺しながらも、E君に話を促した。
「公園のゴミ箱あるじゃないすか。そこの燃えるゴミのところに、文庫本が捨てられていることが何度かあったんすよ。
捨てられている本のジャンルはバラバラだったんすけど、決まって元々のカバーが外されてあって、代わりに赤い折り紙みたいなので作ったブックカバーが掛けられてあって、【赤い本】になってたんすって」
「お・・おう・・・・・・そうなんだ・・・・・・」
「そうなんすよ。で、そのブックカバーと同じような紙で作った感じに、赤い栞みたいなのも作ってあって、それが挟んであるページを開くと、鉛筆かシャーペンかなんかで『死ぬ』とか『殺す』とか書かれているところに【〇】が付けられてあるんすって」
「えぇ・・・何それ・・・」
「ラノベのバトル物だったりしたら、『殺すぞ』とか『死んでしまう』とかあるすけど、『死ぬ程──』とかのそういう表現にも【〇】がされてあって。
それで、これ完全にヤベェなって話になったんすよ。だから近所にヤベェ奴が住んでて、そういうことやってんだって──」
「うん・・・それは・・・・・・ヤバいな・・・」
「それも一つの公園じゃなくて、街中のあちこちであって。
✖✖ってカフェあるじゃないすか。あそこのテラス席にも、いつの間にか置かれてるってことがあって。
で、一時期本当に酷かったから警察も動いたらしいんすよ。公園とかなら未だしも、店だったら業務妨害ってなっちゃうからって。
でも結局『ゴミが捨てられてたと思ったら、調べてみてもよく分かんない状態の本だけだったから──』って有耶無耶にされて、いつの間にか収束したって感じっす」
E君に相槌を打ちつつ話を聞いていたOさんは、自身のあの体験とは無関係なのだと無理矢理思い込みながら、怖がるリアクションを取っていた。
そして「でも、誰やってたとかは分かんなかったんだぁ~」と、何気なく口に出した。
するとE君は「一部の説っすけど──」と、再び話し始めた。
「『一応分かったけど、これ以上追及しちゃいけないよね?』って感じになっちゃったとか。やってた奴がどっかのお金持ちと関係があって、『もう言わないでくれ!』ってなったとか。色々とそんな噂があるんすよ、怖いでしょ?」
「怖いねぇ・・・それは怖いなぁ・・・」
「で、俺の友達が本当に見たって話なんすけど、そいつ本の赤いカバーを外したんすって、完全に。
他に見たって奴は、やってもちょっとカバー外す位ですぐに戻したって話なんすけど。
そいつの話だと、完全に外したら名前が書いてあったって言うんすよ。
女性の名前が、著者の名前の横に鉛筆みたいなので書いてあったって。
字の感じからして多分大人の字だったらしくて、それ見てそいつも(気持ち悪!)ってなってすぐに戻して捨てたんすって。
だから、全部の本に書いてあったらなら特定は出来る筈なんすよね、本当の名前なら。
で、そっから警察なりがそれで調べて、最終的に家族とかが『もう二度とこんな事させないようにします──』ってなったって説もあって、俺はそっちなんかなって思ってんすよ。
どうしたんすか?チョー青ざめてますよ?」
Oさんは途中から恐怖で完全に固まっていた。
E君の口から出てきた様々な単語の端々から、どうしてもあの体験を思い起こしてしまう。
考えまいとしていても彼の脳はそれを許さず、話に関連させようと思考を巡らせてしまっていた。
【お金持ち】と聞いた時には不自然なまでに着飾ったあの親子の装いを、【大人の字】と聞いた時にはあの娘らしき女性を。
そうしている内に、E君の話に相槌を打つことすらも出来なくなっていた。
そんな状態のOさんを見て、E君は気を遣ってなのか、或いは単純にそう思っただけなのか、「あれ?この酒合ってなかったんすか?」と水を向けてくれたそうだ。
それに対し、Oさんも「お、おぉーん。全然飲まない種類の酒だったからかなぁ~?」と、何とか道化た調子の声を捻り出して別の話題へと移したのだという。
そんな話を聞いて暫くして、Oさんは夏季休暇を利用し地元に戻っていた。
その際両親に【赤い本】の話について尋ねてみると、「あー、なんかちょっとあった気がする」との答えが返ってきた。
Oさんは、例のアルバイトであったことについて両親に伝えていなかった。
故に、両親にとって【赤い本】の話というのは、昔に近所であった変な出来事の一件のことなのであった。
その場であの体験について語るという選択肢もOさんにはあったが、折角の一家団欒をぶち壊しにしたくはないと考えて、結局両親には黙っておくことにしたのだそうだ。
そして両親に詳しく話を聞いてみたものの、概ねE君が語っていたものと同様の話で、やはり本を捨てていた犯人は分かっていないとのことだった。
余談だが、話の終わり際に父親が「だから今も、同じ空気を吸ってるかもしれないな!アッハッハッ!」と上機嫌にそんな冗談を口にしたのだという。
無論それを聞いたOさんは「ハハァ・・・」と、苦笑いを浮かべる他なかった。
その後Oさんは、【赤い本】に関する一件を気にすることなく街中を散策し過ごしていた。
不気味な話ではあるが、既に終わった事件だからと己を納得させて、特段怯える必要はないという結論に至っていたからであった。
歩きなれた街並みの風景を横目に散策を続けていると、一軒の古本屋に行き着いた。
(久しぶりにここでも覗くかぁ・・・)
自分が子供の頃から営業しているその古本屋の存在に、懐かしさと感動を覚えていたOさんはそのまま店内に入っていった。
店先にある週刊誌や新刊めいた単行本は、幾らか手に取られた形跡があったが、店の奥に足を踏み入れると、見慣れた色合いと形の書籍たちが所狭しとひしめき合っているのが見て取れた。
(懐かしいなぁ・・・変わってねぇなぁ・・・昔を思い出すなぁ・・・)と思いながら、Oさんは感慨深く埃の被った本棚を見渡していた。
(この奥行くと、もう誰も買わねぇ奴しかねぇんだよなぁ・・・
ここ昔と変わってねぇなぁ・・・
ん?)
不意にOさんは歩みを止めた。
自分の目の前。
ここは恐らく古本屋の店主すらも、普段足を踏み入れることのない場所だ。
そんな場所にある本棚のその一台。
見覚えのある年季の入った古本の数々の中。
そこに全く見覚えのない本が一冊あった。

埃を殆ど被っていない赤いカバーの本がそこに・・・
(ウェッ!!?)
途端にOさんの背筋に冷たいものが走る。
そして無意識のうちに呼吸が早くなり、体の内から「ドッドッ」と激しく心臓の鼓動が響いてきているのに気付いく。
恐怖で逃げ出したい気持ちでいっぱいだ。
しかし、ほんの僅か好奇心が勝ってしまった。
虫や小動物を捕まえる時の如く、ゆっくりと手を伸ばす。
そして、その本に手を掛けた。
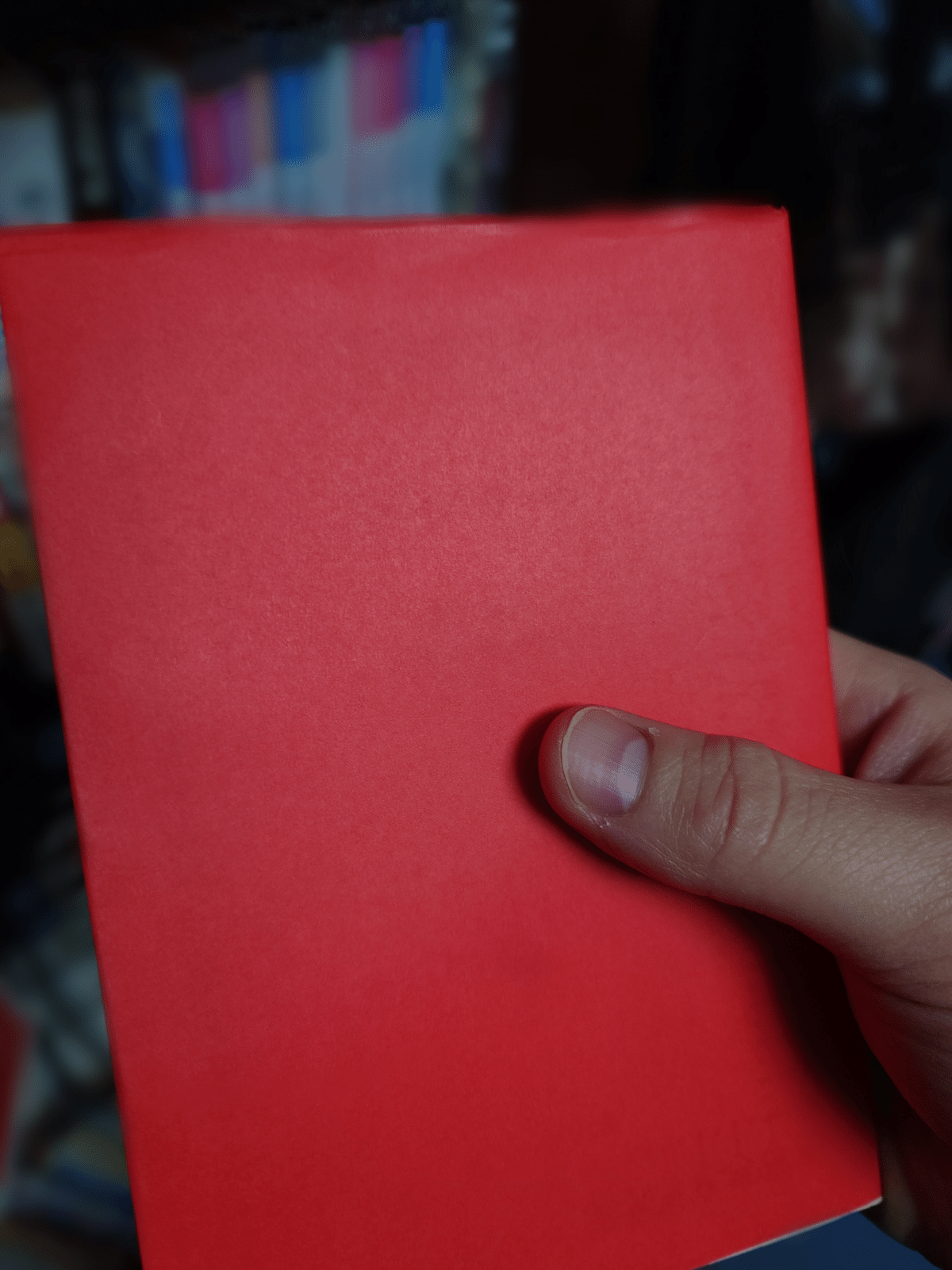
(ア・・・これ・・・折り紙・・・・・・赤い折り紙だ・・・・・・・・)
触れた本の表紙の触感。
紛れもなく、それは折り紙のそれだった。
何処にでもあるような文庫本に、折り紙で作ったお手製のブックカバーを掛けてあった。
E君や両親の話していた、あの【赤い本】そのものが、今自分の目の前にあるのだとOさんは認めざるを得なかった。
「ウワッ!!!」
一瞬茫然自失になりながらも、小さく悲鳴を漏らしながらOさんは正気へと戻った。
そして、手元にある禍々しいその本を元あった場所に戻すと、足早にその古本屋を後にしたのだという。
曰く、本を戻す時に僅かではあったが本の上部から、赤い栞の様なものが飛び出していたのが見えたとのことだ。
それはやはり、ブックカバーと同じ質感をしていたという。
恐らくは栞の様に、細長い形に切った折り紙を目的のページに挟んでいるのだろうと・・・
* * *
【禍話】の語り手かぁなっき氏は、上記のお話を随分昔にOさんから頂いていた。
そしていざ【禍話】で語るに際し、改めてOさんに連絡を取ったとのこと。
話の要点を幾らか確認した後に、さりげなくその後に何か進展があったのかを訊ねてみたそうだ。
すると・・・
O「—―いや、開いてないですよ・・・栞あるところ捲った時に『死ね』とか『殺す』とかに【〇】付いてたら嫌だから、見ないですぐ戻しましたよ。
でも分かっちゃいましたね、『いる』って・・・同じ街にいるんだって・・・
もしかしたらまだいるかもしれないって、バレない場所でまだやってるかもしれないって思って、それであんまり実家に帰れなくなっちゃって・・・」
かぁ「いやでも、そろそろないでしょ?その話から随分経ってるんだし。
年齢的にも、そのお母さんも娘さんもいい歳になってるだろうし、流石にないんじゃない?」
O「いやぁそれが、かぁなっきさんねぇ・・・例えば、【面倒見てくれてた人がいなくなった可能性】もあるんですよ・・・」
かぁ「ん?どうゆうこと?」
曰く、最近Oさんの地元で、夜中に徘徊している二人組の姿が目撃されているのだという。
詳しい年齢や性別はOさんは把握していなかったが、唯一聞いたその二人組の特徴というのが、【二人揃って、年齢に似つかわしくない服を無理に着て、変に着飾っている】ということだった。
あるコンビニではそんな二人組が店内に入ってきて、『存在するかも分からない聞き覚えのない変なジャンルの本を、しきりに店員に尋ねていた』との話もあったそうだ。
そんなトラブルが起こっていた為、『もしその二人を見かけたら保護するように──』と、その地域で呼びかけがされているとのことだった。
そして・・・
O「詳しいことは分かりませんよ!?でも、それが【赤い文庫本】だったら、もう詰みじゃないですか!?
それに!そういう人たちを捜そうと思って、突き止められないっておかしいじゃないですか・・・徒歩で街中を徘徊してて、そんな目立つ二人組を・・・
それで、消息が分かんなくって、『見かけたら言いましょう』ってなってるってことは・・・・・・
もうこの世のモノじゃないのかもしれない・・・・・・
そしたらかぁなっきさん・・・
俺、もういよいよ戻れないですよ・・・
だって俺・・・
顔は覚えられてますからね・・・・・・・・・」
怯え切った様子で声を震わせながら、Oさんは最後にそんな言葉を残したのであった。
出典:【禍話フロムビヨンド 第16夜】
(2024/10/26)(48:24~) より
本記事は【猟奇ユニットFEAR飯】が、提供するツイキャス【禍話】にて語られた怖い話を一部抜粋し、【禍話 二次創作に関して】に準じリライト・投稿しています。
題名はドント氏(https://twitter.com/dontbetrue)の命名の題名に準じています。
隣の叩く音/赤い本の親子/直球の映画を待つ!/「?」なお知らせは来週に延期です pic.twitter.com/2ApafEz9DW
— ドント (@dontbetrue) October 26, 2024
【禍話】の過去の配信や告知情報については、【禍話 簡易まとめWiki】をご覧ください。
使用した画像はこちらです。
