
わたし、人には恵まれるの!《第2話》
「こちらが浴室になっております。脱いだお洋服は籠に入れておいていただければこちらでお洗濯させていただきます」
「は、はい……」
案内された浴室。
の直前の脱衣所。
ここは銭湯ですか?ってくらい広い脱衣所だけど、隅々まで掃除が行き届いており、埃一つ、水滴一つも見当たらない。
「お着替えはこちらにご用意させていただきました」
メイド長の人の合図でハンガーラックが運び込まれてくる。
そのラックには大量の服がかけられており、こちらに選択を委ねるためか種類はバラバラだ。
「アルノ様のサイズでしたらこのサイズでしょうかというお洋服を十点ほど選ばさせていただきました。もしサイズが合わないなどございましたら何なりとお申し付けください」
「は、はぁ……」
見るからに高そうな服。
びしょびしょのプリントTシャツで立ってる私が情けなく見える。
「下着もこちらに……」
「い、いや……!下着はそのまま使うので……!」
「左様でございますか。お風呂はお時間気にせずにご利用していただいて構いません。お着替え終わりましたら、そちらのボタンを押してお呼びください」
メイドさんが脱衣所と廊下を仕切る扉のほうを指さす。
インターホンのようなものが見えた。
「そうしましたらお洗濯のほうさせていただきますので。では、ごゆっくりと」
「あ、ありがとうございます……」
メイドさんが脱衣所から出て、私一人取り残される。
冷静に見渡してみたら、本当にこの先がお風呂なのかってくらい豪華で大きな扉。
洋服を入れておくための木製の棚もなんかつやが違う。
こんな、ドラマとかの中でしか見たことないような場所、ゆっくりできるはずもないよ……
「さっさと入っちゃお……待たせるのもよくないし……」
服も下着も丁寧に籠の中に入れて、浴室の扉を開けると、真っ白な湯気に襲われるようだった。
・・・
「はぁ……あったかい……」
冷えた体をシャワーのお湯が溶かしていく。
雨の汚れも、湿気の汗も、全部排水溝に流れていく。
体を洗い、私は湯船に体を沈める。
シャワーの時とは違い、身体の芯まで温められるような感覚。
「はぁ……」
私の口からは思わずため息がこぼれる。
湯船につかるのは久しぶりだ。
一人暮らしの時にお湯を溜めるなんてことはない。
水道代ももったいないし、お風呂に給湯機能なんてついてないし。
「てか、広すぎる……」
ぽろっとこぼれた私のつぶやきも、ライブハウスかってくらいに反射して、浴室中に響き渡る。
「私とは文字通り住む世界が違う……か……」
ずっと、貧乏だった私とは……
「……もうちょっとだけ浸かってよっと」
結局、私は十分ほど浸かってからお風呂を出た。
そしてお風呂を出た先、十着の洋服が掛かったハンガーラックが目に入る。
「どれにしようかな……」
ワンピース、パンツスタイル。
迷う……
迷うけど……
私は直感で水色のワンピースを選び、着替えを終えてから髪を乾かす。
「着替え終わったらって言ってたよね……」
絶対に言っていたけれど、本当にこのボタンを押してしまっていいのか……
でも、押さなかったらきっとこのまま私は脱衣所に放置だ。
恐る恐るボタンを押し込む。
・・・
あの後すぐにやってきたメイドさんに連れられて、私は長い廊下を歩いていた。
メイドさんが持ってきてくれたスリッパ。
もこもこ、ふかふかが私の足を包む。
「リビングでお坊ちゃんがお待ちです」
「○○くんが……」
しばらく歩き、メイドさんが扉を開けた先。
リビングと思しき大きな部屋。
「アルノさん、こっちこっち」
長机を中心に、それを囲むように置かれたソファ。
一人掛けのものには○○くんが座っており、彩ちゃんはカーペットに寝転がってテレビを見ていた。
「こっち、座っていいよ」
○○くんが指をさしたのは何人掛け……?ってくらい大きいソファ。
皮の質とか、サイズ感とか、もう私の知ってるソファじゃない。
「こ、ここ……?」
「遠慮しないで」
するよ。
こんな高級ソファ、座ったことなんてあるはずもないし。
「し、失礼します……」
でも、座らずに立ってるだけっていうのも変な奴に思われちゃうし、私は覚悟を決めてソファに腰を下ろした。
「わぁ……」
思わず、感嘆の声が漏れる。
普段、自分の部屋では椅子なんか使わないで地べたに座っているし、大学の席だって座面は固い。
なのにこのソファはなんだ。
腰から包み込まれるような柔らかさ。
絶対、長時間座っててもお尻痛くならないやつだ。
「アルノさんの服乾いたら呼びに来てもらえる?」
「かしこまりました。では、失礼いたします」
メイドさんが部屋を後にして、それと入れ替わるように”爺や”がリビングに入ってきた。
「紅茶をお持ちいたしました」
テーブルにカップが三つ並べられる。
これ、もしかして私の分も……?
「爺や、ありがとう」
「デザートはあるの~?」
彩ちゃんが飛び起き、目を輝かせる。
「もちろんございますよ、お嬢様。何になされますか?」
「ん~……わたしはアイス!」
「お坊ちゃまはどうなされますか?」
「僕もアイスをお願い」
「アルノ様はいかがいたしましょう?」
「わ、私もですか……!?」
「もちろんでございます。アルノ様はお客様ですから、おもてなしをするのは当然のことでございます」
やっぱり、この紅茶も私の分だった……!
いかにも高そうなソファに、いかにも高そうなカップ。
緊張で手が震えて、ソファにこぼしたらどうしよう……!
「じゃあ、ア、アイスで……」
「かしこまりました」
”爺や”も部屋を後にして、○○くんは紅茶に口をつける。
「美味しい……。アルノさんも、飲んでみてよ。爺やが淹れた紅茶は絶品なんだ」
「う、うん。いただきマス……」
○○くんに促されて、私も一口、口に含む。
「…………」
「どう?」
「お、美味しい……!」
「でしょ」
今までに味わったことのないくらい深い香りが口いっぱいに広がり、さわやかな甘さと、心地の良い渋み。
きっと、使われている茶葉も最高級のものなんだろうけど、こんなにもその美味しさを引き出す”爺や”の腕もまた最高級だ。
「気に入ってくれてうれしいな。……そうだ、気になってたことがあるんだけどさ」
「なに?」
「アルノさんって、乃木坂大学には一般入試できたの?」
「え、うん……」
「すごっ!めっちゃ頭いいんだ!」
「そうでもないよ……。それに、○○くんだって同じ大学じゃん」
「僕は、アルノさんとは違って小学校から大学まで、ずっと内部進学だから」
「なるほど……」
そりゃあ、こんなお金持ちなら小学校から私立に通ってるのも当然か……
「内部進学って言っても、お兄ちゃんは受験しても受かるくらい頭いいんですからね!ほかの内部進学の人と一緒にしないでください!」
「う、うん……」
兄の沽券に関わることだからか、彩ちゃんの迫力がすごい。
私は思わずその迫力に圧倒されてしまう。
「彩、余計なこと言わなくていいってば」
「だって、お兄ちゃんがほかの人と同じように思われるの嫌だったんだもん……」
「そんなこと、思わないよ」
「……ほんとですか?」
「だって○○くんは、傘ももたず、転んでた私を助けてくれて、こんなにも良くしてくれるんだから、絶対良い人だって信じてる」
「お兄ちゃん、そういう流れでアルノさんのこと連れてきたんだ」
「ま、まあ……恥ずかしいな……」
「お兄ちゃんやるねぇ~」
○○くんは、彩ちゃんに肘で小突かれて、照れくさそうにはにかみながら眉の上を指で掻く。
ほんのり耳も赤みがかっているから、本当に照れを隠しているんだろう。
「失礼いたします。アイスをお持ちいたしました」
「わ、おいしそう!」
「爺や、ナイスタイミング……!」
彩ちゃんが”爺や”の持ってきたアイスに意識を持っていかれ、○○くんへのいじりが止まる。
「たべよたべよ~」
彩ちゃんの私に対する警戒はすっかり溶けたようで、普通にコミュニケーションも取れるようになって、いろんな話ができた。
彩ちゃんは乃木坂大学付属の女子校に通っていること。
○○くんの家は世界有数の大企業の創業家で、○○くんのお父さんは尾の企業の社長さん。
私でも知ってる会社だったから、ビックリして声が出ちゃった。
「アルノさんはサークル入ってたりする?うちの大学、愛好会も含めたら結構いろんなのあるじゃん」
「……バイト、忙しくて。時間が取れないから入ってないんだ……」
「そっか。じゃあ、バイトは何してるの?」
「個別塾の講師と、コンビニの夜勤だよ」
「バイトって、大変?僕、やったことないからわからなくて……」
「それなりに大変……かな」
片方ずつならそれなりだけど、掛け持ってるから大変になってる。
っていうのが正しいかも。
「アルノ様、お時間よろしいでしょうか」
私たちが話していると、再び爺やがリビングにやってきた。
用事があるのは○○くんや彩ちゃんじゃなくて私らしい。
「あ、はい……!」
「予報では、この先も雨脚が強くなるようなので、今夜は当家にお泊りになるのはいかがでしょうか」
「お気持ちはうれしいです……。でも、この後アルバイトがあって……」
「左様でございましたか。承知いたしました。では、お帰りになられる時間になりましたらお呼びください」
”爺や”は一礼してリビングを出た。
「これから夜勤?」
「うん」
「生活リズム、おかしくなるんじゃ……」
「おかしくはなるけど、夜勤のほうが時給いいから」
「そうなんだ……」
「洗濯物が乾いたら、私帰るよ。長居するのも悪いし」
「……わかった。じゃあ、それまでいろんなこと教えてよ」
「わ、私が……!?」
「バイトの話とか教えてよ!」
服が乾くまで、私は○○くんといろんな話をした。
○○くんは特に、アルバイトのことについて興味をもったらしい。
塾講師はどんなことをするのか。
コンビニバイトはどんなことをするのか。
接客って大変?
やっぱり、変なお客さんってくるものなの?
○○くんのリアクションは新鮮で、話をするのが楽しくて、時間はあっという間に過ぎていった。

・・・
洗濯物も乾き、私は慣れ親しんだ自分のTシャツに着替えて、借りていたワンピースを返した。
もらっていっても良いって言ってくれたけど、それはさすがに申し訳なさが勝った。
それにこんな高級な服、貰っても自分がちゃんと扱える自信もなかったから。
「それではアルノ様、お家までお送りします」
「僕も行くよ」
”爺や”のエスコートで、門の外に停まっている車まで案内される。
停まっていた車も高級車。
つくづく、住む世界が違うなぁと思わされる。
”爺や”の運転で、車は私の住むアパートへ。
普段通っている道も、こんな高級な車で通るとまるで別の道みたいに感じる。
「ここら辺で大丈夫です!」
車を止めてもらい、私が降りようとすると、○○くんも傘を手にもって降車準備を整えていた。
「部屋まで傘、差してくよ」
「ありがと」
○○くんが先に降りて傘を広げ、私はその中に入れてもらいながら車を降りる。
アパートは歩いて一分もかかるかどうかってくらいの距離に止めてもらったので、わざわざ○○くんの手を煩わせてしまったことに申し訳なさも感じる。
「アパートここだから、もう大丈夫だよ」
「一人暮らし?」
「うん。だから、いっぱいバイトしないと生活できなくて……頼れる人も、いないから」
「そう、なんだ…..」
「今日は、本当にありがと」
「いいよ、お礼なんて。僕なんかでよかったらいつでも頼って」
「ありがとう。○○くんは、ほんとに優しいね」
私が○○くんの傘から出て、部屋の鍵を開けていると、
「おや、アルノちゃん。おかえり」
「大家さん。ただいまです」
たまたま外に出ていた大家さんに遭遇した。
「そっちの男の子は?」
「小川○○くんです。友達……で、いいのかな?」
「はい。アルノさんの友達の○○です」
「そうかい、友達だったのかい。てっきりアルノちゃんの恋人かと思ったよ」
「こ、恋人……!?ち、ちがいますよ……!」
私は慌てて否定する。
いきなり大家さんが変なこと言うから、顔が熱い。
「わ、わたし夜勤の準備しないと!○○くん、ほんとにありがとう!」
「う、うん……」
どうにも恥ずかしさが拭えなくなってしまった私は、その場から逃げるように部屋に駆け込んだ。
・・・
アルノさんが部屋に戻って、僕と大家さんが残された。
「お似合いだと思ったんだけどねぇ」
「そんな。僕ら、今日話したばかりなんですよ」
「おや、そうだったのかい。まあ、ともかくアルノちゃんと今後も仲良くしてあげておくれ。あの子、会うたびに挨拶もしてくれるし、アルバイトも毎日頑張っているようだし、家賃もちゃんと納めてくれる。あの子は、本当にいい子だから」
大家さんの声色、まなざし、滲みだす空気からも、この人はアルノさんのことを親のように見守っているんだろうなと伝わってくる。
「最近、アルノちゃんはちょっと大変そうでなぁ……」
「アルバイトが忙しいんですかね」
「そうだろうなぁ。あの子、幼いころに両親を亡くしてて、一人で頑張らなきゃって気持ちが人よりも強いのかもしれんなぁ」
「………..」
そんな理由があったんだ。
アルノさんがあんなにアルバイトをする理由。
きっと、乃木坂大学を目指すに至った理由にも繋がるんだろう。
「友達も少ないみたいだから、ぜひ仲良くしてやっておくれ」
「はい、もちろんです」
「今日は花壇の手入れでもしようと思ったんだがのぉ。この雨では……。○○くんも、気を付けて帰ってな」
「はい。大家さんもお気をつけて」
大家さんに一礼して、僕は爺やの待つ車に戻った。
「随分と長かったですね」
「大家さんと話してて」
「左様でございましたか。このまま、お家に戻ってもよろしいですか?どこか、寄りたい場所などございましたらお申し付けください」
「寄りたいところは特にないかな。こんな天気だしね」
「かしこまりました」
爺やが車を発進させ、アルノさんのアパートから家へと戻る。
「…………ねえ、爺や」
「はい、なんでしょう」
「今日、父さんと母さん、何時に帰ってくる?」
「本日は会食などの予定もなく、お食事は家でと伺っているので二十時にはお帰りになられると思いますよ」
「そう……。なら、その時に話そっかな」
「どんなお話をするのですか?」
「爺やにはまだ内緒」
「ふふっ。左様でございますか。お坊ちゃま、何か企んでいるようなお顔をされていますな」
爺やの観察眼はすごいや。
なんでもお見通しなのかも知れないな。
・・・
冷蔵庫からカット野菜の袋を取り出し、一つまみお皿に乗せる。
湧いたお湯でインスタントの味噌汁を作り、電気代節約のために焼いていない食パンを二枚。
小さなテーブルの上に並べて、今日の夕飯の完成。
「いただきます」
夜勤前ではちょっと物足りなさも感じるけど、節約第一。
栄養は……まあ、ね。
お味噌汁をのんで、私は薄暗い部屋を見て思う。
「ほんとに、住む世界が違ったな……」
どうしても、さっき見た○○くんの家と自分の部屋を比べてしまう。
「いや……」
私は変なことを考えるのはやめにして、夜勤の準備を始めた。
・・・
久しぶりに父さんと母さんも含めて、家族で囲む食卓。
「やはり、うちのシェフが作る料理はどこの高級レストランにも勝るかもしれないな」
「そうね」
普段は両親ともに会食が多く、彩と二人でご飯を食べることが多かったけれど、やっぱり家族そろってというのはいいものだ。
「彩、最近はどうだ」
「どうって、特に変わらないよ。普通に過ごしてる」
「まあ、普通が一番だもんな。○○のほうはどうなんだ」
「僕は夏休みで、特に何もないなぁ……」
「そうか、夏休みだもんなぁ」
父さんは、ちょっと悲しそうな顔をした。
多分、子供の時みたいにあれしたんだ、これしたんだっていうのを期待していたのかもしれないけど、それをするにはちょっとばかしタイミングが悪かった。
会話の切れ目。
次の話題への転換点。
僕は、ここしかないと思い口を開く。
「……あのさ、父さんと母さんに頼みたいことと言うか、お願いがあるんだ」
「お願い?」
「○○がそんなこと言うなんて珍しいな」
「お兄ちゃん……?」
「実は……」
・・・
「眠い……」
夜勤明けの朝六時。
眩しい朝日が染みる。
早く帰って寝よう。
いや、シャワーは浴びてからか……
面倒だし、起きてからでもいいかな……
「ふわぁ……。ん……?」
私があくびをしながらアパートにたどり着くと、大家さんともう一人、見覚えのある人影があった。
「掃除手伝ってくれて助かるよ」
「いえ、これくらい手伝わせてくださいよ」
すっごいなじんでるけど、間違いなく○○くんだ。
たった一日で大家さんと仲良くなりすぎじゃない?
「○○くん……?なに、してるの?」
「アルノさん、おかえり」
「おかえり。アルバイトおつかれさま」
「た、ただいまです。……で、○○くんはこんな朝も早くから何してるの?」
「何って、掃除の手伝いだよ」
何が不思議なのかが不思議といった顔の○○くん。
「そうじゃなくて……」
こんな朝早くからなんでこんなとこにいるんだろうってところが気になってるんだけどな……
「実は、アルノさんに話したいことがあってきたんだよね。あ、大家さん、箒お返ししますね」
「手伝ってくれて助かったよ。ありがとね」
掃除を終えて、大家さんは道具をしまって自分の部屋に戻っていった。
私は○○くんと二人、取り残される。
「私に、話……?」
「そうなんだ。まあ、回りくどくいってもだから、単刀直入に言うね」
「うん」
「アルノさん、僕の家に住まない?」
「……………………ぇ?」
・・・
「ふふふ~ん、ふふふふふ~ん」
かわいらしい家具に彩られた部屋。
ベッドに寝ころぶ少女の鼻歌が響く。
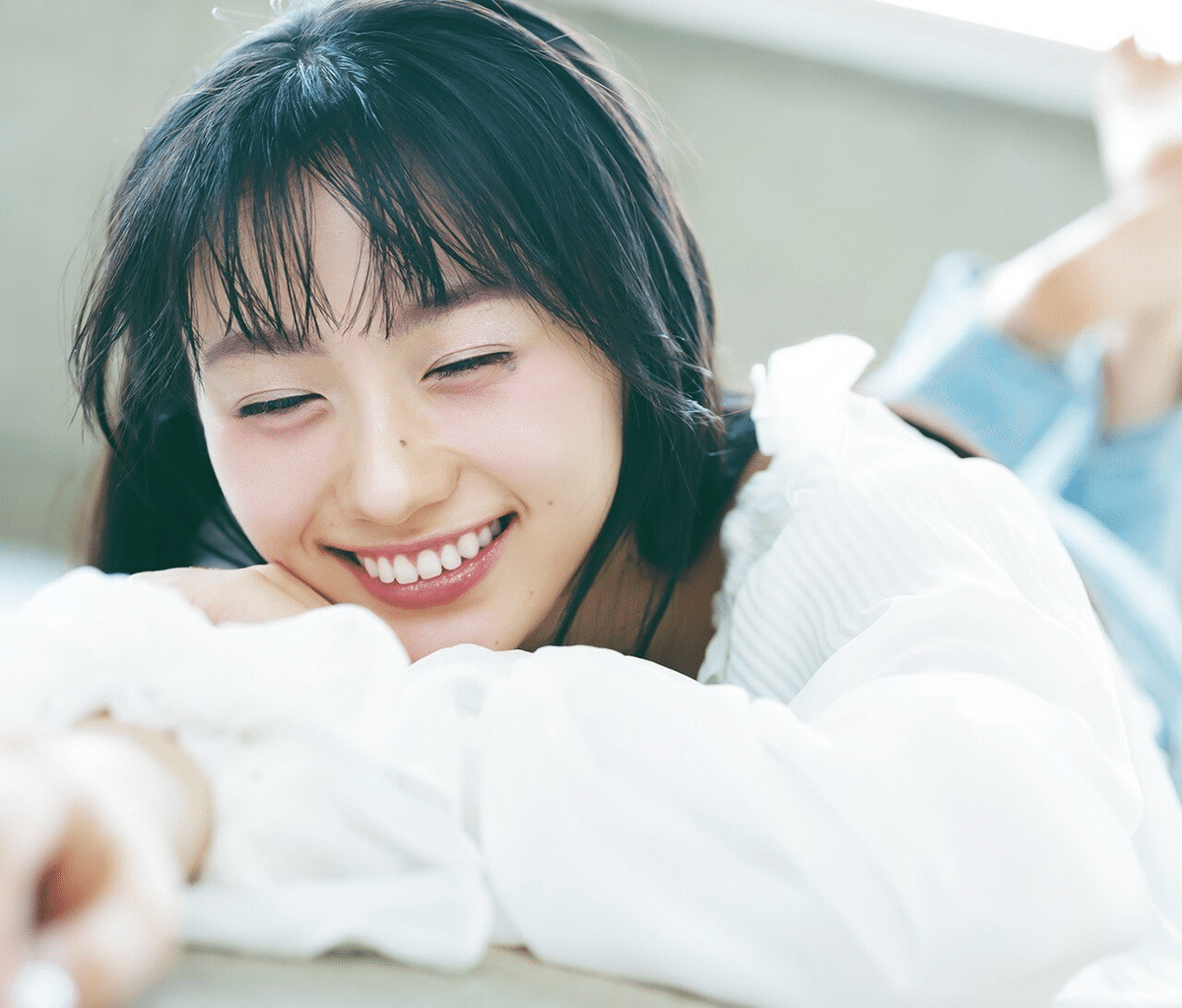
「○○、今日暇だったりするかなぁ。お家、いっちゃおっかな~」
少女はそう呟いて、また鼻歌を歌い始めた。
………つづく
