
【まかろん】2024年度秋部誌
「Very Berry Cherry Pie」向井 光輝
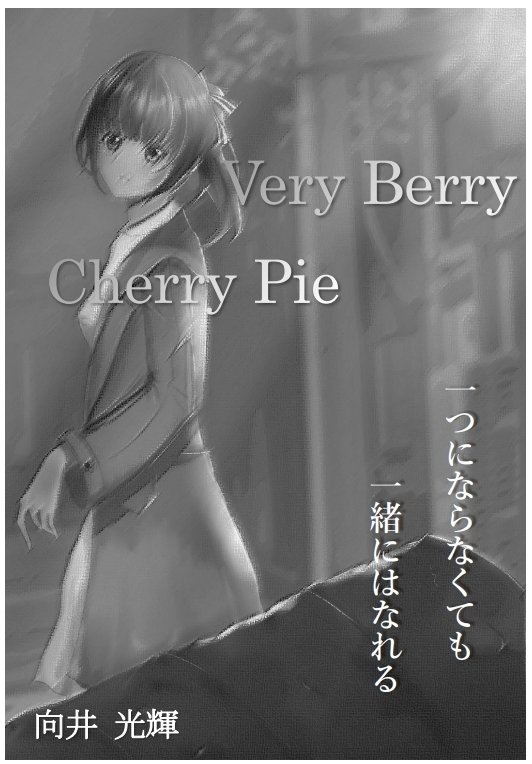
私は死んだ。 そりゃあもう呆気なく、アッサリと。
だが、私のタマシイは、まだ消えてはいなかった。
私が命と引き換えに助けた少女、アーシャ。
私は彼女と行動を共にする。
その道が何処へ、繋がっているのかも忘れて。
彼女は【魂を喰らうもの】を追っていた。
「さあ、召し上がれ」
食卓に料理が次々と並べられて行く。ガッツリと肉の入ったサンドイッチに、甘辛い味付けの野菜炒め。冷静に考えればおかしな献立だが、僕たちはこれが大好きだった。
「「いただきまーす!!」」
「ハハハ、お前たちはほんとに旨そうに食べるよな。見てるこっちまで嬉しくなってくるよ」
「作り甲斐、あるでしょ?」
父と母がグラスを交わしながらそう喋っている。そういえば、こうして家族四人が一緒に食事を摂るなんて、いつぶりの事だろうか。
「それが、一カ月ぶりなの。だから今日は少し豪勢に。普段ならこんな体に悪い組み合わせで出さないわよ」
そう言って笑う母。母は、料理をしている時と、それを食べている時が、誇張抜きに一番輝いていると思う。腕はずば抜けているわけではないのだけど、僕は母の料理が好きだ。
「おかわり」
父がグラスを掲げて要求した。父は酒豪だ。アルコールは人間のガソリンだって、酔う度に言ってたっけ。
「まったく、困ったお父さんですね」
しかし、母が注いでいるのは、ノンアルコールのビール。見ると母も飲んでいるのはワインではなく、ただのジュースのようだ。
たまにしかない家族団欒の機会。それなのにお酒を飲まないとなると、僕は嫌でも、察してしまった。
「お母さん、明日も、また“GMA”に乗るの?」
弟が訪ねる。その一言で空気が重くなる。弟に悪気は無いのは、わかっているけれど。
「大丈夫よ。私は最強のパイロットなんだから。それに、次に乗るのはお父さんの作った最新型。何も心配はいらないのよ」
弟は小さく頷く。納得いかないけれど、飲み込むしかない事だから。
─────遥かなる星の旅。仮初の安地を守るため、今日も人は虚空へ散る。
君は、ユーレイを信じているだろうか?
フワフワと現世をさまよう、死者たちの消えぬ無念。ヒトビトを脅かす、実体無き恐怖。
私はそんなモノは信じてはいない。死とは終わりだ、その先などない。だからこそヒトは生を尊び、死を恐怖する。
──しかし、私にとっては誠に遺憾だが、どうやらその考えを改めなければならなくなった。
「動くなァ!手ェ上げろ!」
「……」
ここは裏路地、街の日陰。
男が一人と、女が一人。
男は銃を携えて、女は無様に両手を掲げる。
このまま黙って女を見捨てるのは、私の信条にもとる。
しかし、私にはどうしても彼女を助けられない事情があった。
……そう、私は既に、一足先に死んでいた。
「ヘテェッヘ、案外素直じゃねえか。もっと激しく抵抗するかと思っていたが」
「……」
女は口を開かない。ただ両手を掲げたまま、
じっと男を見つめている。
「ならとっとと教えてもらおうか。テメエのォ…」「断る」
男の口上を聞き終わらずに、割り込む様にノーを突き付ける女。
「んだとォ?!テメェ、命が惜しくねえのかァ?!」
「ええ。ワタシ達にとって情報は命よりも大切なモノ。そんなこともわからないなんて、
向いてないわよ、アナタ」
両手を天に掲げながら、煽り言葉を重ねる女、その言葉でさらに激高する男。全く大した女だ。
いや、こんな事をやっている女は、皆これほどまでに大したものなのだろうか。
「恩知らずな奴だなァ!このままポックリ逝っちまったら、コイツに申し訳が立たねェと思わねェのか?!せっかく体を張ってまでテメエを守ったってのによォ!」
そんな男が指し示す指の先には、私がいた。
嗚呼、あれは間違いなく私だ。胸を弾丸で打ち抜かれ、白目をむいて倒れている。
にも関わらず、私はこうして意識を持っている。そして二人のニンゲンと一つの死体を、上の方から眺めている。
なれば、私はやはりユーレイなのだろうか。
「……アナタも、こんなハデに一般人を巻き込んで、ナカマに申し訳ないと思わないの?揉み消すのだってタダじゃないのよ」
「るせェ!今時、人っ子一人死んだくらいじゃァ、大した騒ぎになりゃしねェ。こんなトコをノコノコ歩いてる、このマヌケが悪ィんだよ!」
物騒な言い争いが続いている。組織だの揉み消すだの、ドラマの中でしか聞いたことがない。
いやいや、そんなことより、このままでは女が撃たれて死んでしまう。私に何か出来るコトは無いのか!?二人が言い合っている間に私が何か一人で何か。
CLAAAAANG…
空き缶が落ちる。ふと上を見上げると、板張りの足場の上に様々なモノが器用に置かれている。今にも崩れて落ちてきそうだ。だが、自然と落ちてきたのは空き缶だけ。空き缶ごときでは二人はなんの反応も示さない。
!そうか、これを動かして二人の間に落とせば!逃げ出す間の時間稼ぎ位にはなるかもしれない。何かもっと大きなモノを……例えばそう、あそこの大きなドラム缶とか。
そうこうしていられない。そうと決まれば早速ドラム缶を…………ってそうだ!私は死んでいるんだ!ユーレイならば動かしようもない!生身でも、動かせたかは別として!
「……本当に、話さないつもりかァ?」
「話さないって言ってるでしょ。そんなにワタシのクビは不満?」
「ああ゛決まってんだろォ!下っ端の、それもオンナのクビなんか誰がいるんだよォ!オンナの価値はウエじゃなくてシタなんだ!そこんとこわかってねェ様だなァ!」
激高して罵り続ける男。しかし、未だ引き金は引かない。女の言う通り、コイツはとんでもない甲斐性なしなのかもしれない。
……………でも私のことは撃ったんだよな。
なんだかなぜだかいつの間にか、男の姿が小さく見える。まったくもって小さな男だ。こんなに小さくなったのなら、隣にいる女が相対的に大きく───
……なぜだか女も小さくなっている。何故だ?
それに心なしか視界も広い。
CREAK…
そう思っている矢先、木板が軋む音が聞こえる。それに伴い視界が揺れる。よせ、私は酔いに弱いんだ。
RSTTLE…
さっきまで固定されていた視界が急に揺れ始めている。まるで、ドラム缶の中に入ってしまったかの様に。ドラム缶として転がっているかの様に。
SNAP!
木板が割れる。上に載っていたドラム缶が落ちる。そう、私が落ちる。
視界が落ちる。二人が近づく。
私は、ドラム缶になっていた!
THUD!!
鈍い音と共にドラム缶が地面に叩きつけられる。痛みは無い。しかし、ドラム缶は派手に凹み、血液とばかりに汚いオイルが流れ出る。
BANG!!!
男が突然の事に一瞬たじろぐ、その隙を逃すことなく女が男を撃ち抜いた。
「……本当に、三下だったのね…」
決着は一瞬。どちらを助けるのが正しかったのかは私には皆目見当もつかない。
「で、さっきからワーワーうるさいアンタは、いったいなんなんですか?」
すると女が突然虚空へ向かって話し始めた。
変な女だ……いや違う、これは私へ話しかけているのだ。
驚いた、君は私の声が聞こえるのか。
「驚きたいのはこっちの方ですよ!こんなのハジメテだし。さっきだって無視し続けるの大変だったんですからね」
う……それに関してはすまない。
しかし何、と聞かれても返答に困るのが正直なところだ。難儀なことに、私には過去の記憶がない。むしろ君の方が私について何か知っているのでは、と思っていたのだが。
「……ホントに何も覚えてないんですね。じゃあ、ワタシの前に突然躍り出て、ダンガンに身を晒したのも覚えてないんですか?」
ああ、それならばギリギリで覚えている。君を助けることが出来て本当に良かったよ。
「よかった?アンタは記憶が無いんだから、もしかしたら助けたワタシの方がアクヤクだったかもしれないんですよ?どうして、ワタシを?」
なんだ、そんなこと。簡単な事さ、君が女だったからだよ。
「はぁ!?オンナだから、そんな理由で?!
……アンタ、もしかしなくてもバカですか?」
ハハハ、男は女の為に馬鹿になる生き物なのだ!……まあそれもあるが君は悪いやつではないだろう?…法律を基準にすると、悪い奴になってしまうかもだが。
「……何を根拠に。
まあでも、アレで助かったのは事実ですし、一応感謝しておきます。ありがとうございました」
あ、ああ。…なんだかそうやって真正面から感謝されると、中々照れるものだな。年甲斐もなく顔を赤らめてしまいそうだ。
「……で、アンタはこれからどうするんですか?」
女が見下したまま訊ねてくる。顔の下りで思い出した。私は今、ユーレイで、私は今、ドラム缶だった。
「ワタシを助けてムネンを晴らしたから、そろそろ成仏するんでしょうか」
そんな!このまま死ぬなんて!……いや、もう死んではいるのだけれども。
私には記憶がないんのだから、晴らすべき無念も、碇を下す心残りも私には無い。
……けれど、そうだね。このタマシイが成仏するまでの間、君についてくっついていこう。
「どうしてそうなるんですか?!」
いや、私は命を張って君を助けた。君の事を何も知らずに。なれば君は私が命を懸けてまで助けるに値するニンゲンだったのか、見極めたいのさ。なに、メイワクはかけないさ、むしろ君の助手としてこのユーレイ、文字通り全霊をつくそう。
「……どうしてそうなるんですか。さっきの発言とムジュンしてますし。
ま、別にいいですけど。ユーレイなら邪魔にならなさそうですし」
じゃあよろしく、だ。……えーっと、今更で悪いが、君の名前を聞いてもいいかい?
「そうでしたね。ワタシはアーシャ。探偵の…
…いえ、探偵をやっています」
探偵!かっこいいじゃないか。一体何を追っているんだ、見たところかなり物騒そうだが。
そう尋ねると、アーシャは一拍置いて、遠く天を見上げながら、答えた。
「ワタシ達が追っているのは【魂を喰らう者】、ですよ」
「くそっ!クソッ!糞ッ!どうして、どうしてなんだ!どうしてアイツなんかと!」
男が虚空へ罵倒を繰り返しながら裏路地へ入ってくる。手には安酒の缶、相当に酔っぱらっているようだ。
「どうしてなんだよぉ……あのプレゼントは、
あのサプライズは嘘だったのかぁ!あんなに……あんなに一緒だったのに…」
BUMP!
「ってぇ!おいテメェ!何処見て歩いてるんだ!」
男が影にぶつかる。
その影は、影と呼ぶには余りにも白い出で立ちをしていた。
「……」
白い影は見た目とは裏腹に敢然と闇に溶けている。その姿は酷く不気味で、見るものに無機質な恐怖を誘う。 男はその恐怖からか、はたまたただ酔っていただけか、足元を濡らす。手に持った安酒もぶちまけ、辺りに不快な香りが漂った。
「おい!なんなんだよ!何なんだお前は!いいからさっさと俺に謝って、俺に道を開けeeeeeeeeeeeeeEEEEEEEEEEEEE!?!?!?!?!?!?!?!」
白い影は表情一つ変えずに目の前の男を斬った。血しぶきの一つも立てず。とても綺麗に。とても、鮮やかに。
「懸念通り。三下がしくじることは。
キサマ、どう責任を取るつもりだ?」
「ヒィッ!?」
白い影が振り返ることもなく、後ろに隠れていた男に声を掛ける。
「イ、イヤしかし、死体は回収した!ソチラの要望は満たしているハズだ!」
空気が張り詰める。白い影は言葉を発さず表情も変えていない。しかし、明らかに場に流れる空気は変わっていた。
「求めていない。キサマの裁量での判断を。
……タマシイが逃げ出したではないか」
一層威圧感を増す白い影の言葉に男はたじろぎ、一歩、二歩とあとずさる。
「シ、しかしね、我々とて人数には限りがあるのだから………そ、それに仕方ねえだろ?!ソチラの要望も意味の分からねえものばかりなんだからさあ!たった一度の失敗も許されねえのかよ!?」
恐怖に声が裏返る男。そちらに通じたはずの者が、影の前では赤子の様だ。
「異なっている。着眼している論点が。失敗した、という事象を責めているのではない。
あの様な三下に依頼すればこうなる、ということは予見できた」
痛い所を付かれ、後ずさる男。足も腰もすっかり逃げる体勢だ。
「そ、それは……だ、だがあのオンナのヤマは付いている!ダンナの合図がありゃ俺たちの精鋭が一斉にハチの巣だ!それでも不満ならカネも返す!だから─」
「求めていない。金などは」
白い影が男の言葉を遮るように言葉を発する。金を取られることが無い、とわかり安堵したのだろう。男の表情が和らぐ。構えていた足も幾ばくかゆとりを取り戻す。
「あ、ありがてぇ。さすがはダンナ!ならちと待っててくれ、すぐ準備をして名誉返上を……………HUH?」
男が呆けた様な声を出す。
否、それは声にならない。
男は呆然と立ち尽くす自分の体を、地面に転がりながら眺めていた。
「求めていない。失敗の返上など」
「オイオイ、またハデに殺したな?これじゃあ使いモノにならないじゃないか」
闇の中から新たな影が現れる。闇に溶け込む黒い影、それでいて存在感のある、不思議な雰囲気の黒い影だった。
「必要ない。こんなモノは。ブラックも器は選べ。ただでさえコイツ等は低俗なテキなんだ」
ブラック、と呼ばれた黒い影はわざとらしくヤレヤレと手を挙げてみせる。
「まったく、今日もつれないなレックスは。
オレにはアッシュっていう最高にクールな名前があるってのによ」
そう言ってアッシュは手に持っていたリードを引っ張る。
するとどこからともなく虚ろな瞳のオンナがやってき、アッシュに口づけをする。
「必要ない。名前など。私には母様から頂いた色が既にある。
……それに、私をレックスと呼ぶなブラック。
レックスとは、男性名だ」
SNAP!
「そこがいいんじゃないか!こんなにカワイイのに最高にクールなアンタにお似合いの名前だぜ?それにオトコだオンナだに拘るなんて、遅れてるなぁ、レックスちゃん」
指を鳴らし食い気味に食らいつくアッシュ。その芝居がかったし喋り方は、レックスの神経を余計に逆なでした。
「っ!拒否する!その名で呼ばれることを!」
いつもの無機質な雰囲気が一瞬崩れる。しかしアッシュはそれには気にも留めず、隣のオンナを撫でながら、「やっぱりつれないなぁ」などと言っている。
「……質問する。そのオンナの事を。一体何なのだソレは。ずっと連れまわしているのか」
オンナを弄る手を止め、レックスの方を見るアッシュ。
「オイオイ”ソレ”だなんてやめてくれよ。コイツはオレのかわいいカワイイ”カノジョ”なんだから」
そう言ってオンナに同意を求めるレックス。
しかし、オンナはう゛ー、あ゛―、だの虚ろな呻き声を発するのみで、返事になっていない。
「要望する。ソレの処分を今すぐに。そんなものは任務に必要ない」
レックスはそのオンナに目もくれずに淡々と告げる。
「まったくー。そのクソマジメな性格さえ直せばレックスもモテモテになれるのに。勿体ないなぁ~」
「要望する。ソレの処分を今すぐに。そんなものは任務に必要ない」
表情を変えずに一言一句同じ言葉を繰り返す。
「あーハイハイわかったわかりましたって。
しょうがないなぁ……結構お気に入りだったのに」
SQUISH!!
アッシュがリードを強く引っ張る。小さな呻き声と共にオンナの命は呆気なく消えた。
「あーあ、まったく悲しいよ。レックスにはこの悲しさがわからないんだろうな。変わりがいくらでもいると言っても、アリス2は一人しかいなかったのに」
死体に向かっておーよしよしなどとまたしてもわざとらしい喋り方。いい加減耐えかねたのかレックスはアッシュに向かって本題を求める。
「要求する。本題の提示を。そんなオモチャを見せびらかすためだけに来たわけではないだろう」
その言葉に空気が変わるアッシュ。オンナの死体を投げ捨ててレックスに歩み寄る。
「レックスのカワイイ顔を見にきただけ…………と言いたいところだが、良いニュースがある。
ああ安心してくれ。良いニュースオンリーだ」
ニヤリと勿体ぶってアッシュは続ける。
「さっきのチンピラが逃したオンナのコ、
……あれは■■■だよ」
「!確認する。その情報は確かか!?」
珍しく語気を強めるレックス。前のめりに身を乗り出す様子に、まるで子犬だな。とアッシュは感じた。
「ああ、間違い無いよ。ヤロウならいざ知らず、オレがオンナのコについて間違ったコトを言うハズが無いだろ?」
「感謝する。……その素行については言いたいことは山ほどあるが今は目を瞑ろう」
「いやはや素直じゃないねぇ……ま、でも初めて会った時よりかは見違えるほど可愛くなった。このまま行けば俺好みの彼女になること間違いなしだ」
「警告する。瞑った眼を開いてほしいのか」
「おー怖い怖い……わかったわかった仕事に戻るさ」
別に今までもサボってたわけじゃないんだけどなぁ…と頭を掻くアッシュ。その後ろ姿を不満など全く無さそうな目で不満気に見つめた後、レックスはその場を音も無く立ち去った。
「───ようやく見つけた。キミの事を、ずっと探していたんだよ。
……安心してくれ。キミの孤独はようやく癒える。キミの願いは、ようやく叶う!」
レックスが去った後、闇に染まる路地裏で、
アッシュは、一人歓喜に震えていた。
「で、アンタはいつまでその姿でいるんですか」
複雑怪奇に入り組んだ街の裏路地を迷いなく歩くアーシャが、ふとこちらに語り掛けてきた。
RATTLE……
いやいやいやその姿と言われても、私はユーレイなのだから。成仏でもしない限り、これはどうしようもないのだよ。
RATTLE……
「……いえ、そうではなく…
その!ドラム缶のことですよ!」
そう言って蔑むように私を見下すアーシャ。我が身に降り注ぐ視線が痛い。
……そういえば、どうして彼女はずっと私の事を見下しているのだろう。ユーレイといえば、フワフワユラユラと人の顔辺りを浮遊しているものだが。
「…ようやく気付いたんですか?さっきからゴロゴロゴロゴロ気になるんですよ、それ」
BANG!
痛っ!……くないんだった。叩かれると咄嗟にイタイ!と悲鳴を上げるのはニンゲンの不思議な癖だ。いや、今はユーレイなのだからこれは私特有の癖なのだろうか?
「……一々うるさいユーレイですね。流石にウットウしいんですよその音。それに、そのドラム缶ウチには入れませんからね」
そう言って立ち止まるアーシャ。
おや、ということはここが君の住処なのか。
ほうほう。路地裏の中、ひっそりと隠れる様に佇む廃ビル……なかなかオトコゴコロをくすぐられる良い場所じゃないか。
「オトコゴコロ、というのはわかりませんけれど……まあ、イイトコロであることは認めます」
珍しく素直に肯定してみせるアーシャ。そりゃあ自分の住処は住みやすいが一番だが、意外と可愛い所もあるものだな。
「珍しく!意外と!失礼ですね!ワタシのコト何だと思ってるんですか!」
す、すまない。いや私は、先程のチンピラとの立会にしか立ち会ってないからね、その姿しか知らないんだよ。
「……ま、確かに見た目はボロイですし、中もキレイとは言いガタいですけど、住めばミヤコってやつです。さ、入りますよ」
BANG!
痛っ、くないけど!止めてくれないか流石に何度も蹴るのは…痛みはないとはいえ、結構くるのだよ、これ…
「じゃあそこから出ればいいじゃないですか。
ユーレイなんだからドコにトリつこうとアンタの自由でしょう?」
そう言ってスタスタと廃墟……もといアジトへ歩を進めるアーシャ。……言われてみればドラム缶にこだわる必要性など特にないんだった。
……けど、妙に居心地いいんだよなこれ。
「……」
BANG
扉が閉まる音がする。どうやらアーシャは中に入ってしまったらしい。こうなるともういよいよこの姿でいる必要性は皆無だ。さっさと霊体に戻ってさっさと部屋に侵入しよう。
RATTLE……
RATTLE………
RATTLE…………
RATTLE……………
「……アンタ、いつまでやってんですか、ソレ」
薄暗い路地にも朝日の兆しが漏れ入り、
新しい一日の始まりを予感させるような時間。
寝不足なのだろうか、目に大きな腫れ蓄えたアーシャが、寝間着姿のままで扉を開けて顔見せてきた。
「……誰のせいだと思ってるんですか……その音のせいでゼンゼン眠れなかったんですけど」
Rub hard,,,
眠そうに目をこするアーシャ。こうして見ると、普通の女の子みたいにしか見えない。昨日の威厳は何処へやら、といった感じだ。
「……話聞いてますか?また蹴り飛ばしますよ」
う、聞いてる聞いてる。いや、それがさ、恥ずかしいことに、わからないんだ。これからどうやって出るのか。
「わからないって、バカなコト言わないでください。アンタだって、はじめっからこのドラム缶に憑りついてたわけじゃないんですよね」
それはそうなのだが……その時は、自分がユーレイになったショックと君を助けることに必死だったからか、どうやってコレに憑りついたのかは覚えてないんだ。何というか、気が付いたらこうなっていたというか…成り行きというか、ノリと勢いというか……
「……ムムム、ムムムムム…」
おや意外だ。今までの流れからすると、『覚えてないって、どんだけポンコツユーレイなんですか、アンタは!』とか鋭いツッコミと蹴りが飛んでくると身構えてしまったのだが。
「ドラム缶の構えってナンすか……
でも、…アンタに助けられたコトは、その、
ジジツ、ですし」
歯切れ悪く下を向きながら答えるアーシャ。その表情は私からは窺い知ることは出来……いや待てよ。私は今君を下から覗き込むような視点なのだから、このまま転がるように君の下へ潜り込めばあるいは……
「だぁーッ!もういいです!もうドラム缶から出ていくのはケッコウですからそのまま中に入ってください!」
RaTtLe~
私を持ち上げるアーシャ。視界が揺れる。
こうしていると、まるで赤子に戻ったかの様だ。
SLAM! BANG!
と、思ったのも束の間。アーシャは扉を勢いよく閉め、私はそのまま床に叩きつけられた。
BUMP!
…もう少し丁寧に扱おうなどとは思わないのか、こうも乱雑に扱うと、ここの床も悲鳴を上げているんだと思うのだけれど。
「別にアンタは痛覚ないんで大丈夫ですよね。
あとここに関しては家具とかも別に置かないですし、ちょっとくらい凹んだところで問題はないです。メーワクになるご近所さんもいないことですし」
creak
そう言ってアーシャは小さなソファに倒れこむ。と思いきやそのまま動かなくなってしまった。
呼吸の音すら聞こえず動かず。驚くべき寝つきの良さだ。
……そんなに昨夜のドラム缶はうるさかったのか…いやはや、少し反省しなければならないな。
音を立てぬように慎重にカラダ(?)を動かし、辺りを見渡す。
…今まで考えていなかったが、一体全体私はドラム缶のどこから外を眺めているのだろうか。
側面……にしては移動しても視界は回らない。
いうなればまるで、ドラム缶の傍に目玉を引っ付けて平行移動しているような形だろうか。やれやれ、自分の事は自分が一番詳しいというが、記憶喪失のユーレイにとっては、自分事でも他人事だ。
音を立てずにスニークローリングを続けていると、この部屋の事もなんととなくわかって来た。
まず部屋の中央には、アーシャが絶賛お休み中のリビングソファー。そこから目線を少しずらせば使い込まれた本棚が目に入る。ちょいと背表紙を眺めてみると、まずは雑多にファイリングされた今までの依頼の数々。そこまで数は無い……どころか、見るからに新品のかさ増し用のものまである。
その横には警察の持ち出し厳禁の機密書類……っておい待てなんでそんなものがここにあるんだ。
POW!
少し音を鳴らし、無い目玉で視線をアーシャに向ける。しかし、反応はない。……さっきから寝息も聞こえないし狸寝入りじゃないのか怪しくなってきたな。
だがしかし、答えてくれないのならば今の私に真実を知るすべは無い。爆弾の事は気に残しつつ本棚からさらに視線をなぞる。が、後の棚を埋め尽くしていたのは夥しい量の娯楽小説だった。
新しいものからかなり古いものまで、お堅めのものから柔らかいものまで、厚い本から薄い本まで。まるで小説博物館だ。
その本棚の反対側にはこじんまりとしたキッチンが一つ。凝った料理は作れないが一人、二人暮らしには不足なし、といった具合。
後は窓際に若干蜘蛛の巣がかった多肉植物が飾ってあるくらいの小さな部屋だ。
……改めて色のない部屋だ。アーシャがドラム缶を中に入れたくないってのも頷ける。この部屋は、二人で住むのには少々手狭だ。必要最低限の家具に、後は力任せに趣味の空間。ドラム缶の視点では少々分かりずらかったがキッチンには豆やカップなど、珈琲の用意がなされている。この姿は匂いが分からぬようで、それに気づかなかったが、この空間は珈琲の香りに満ちているのだろう。
お気に入りの本を片手に珈琲を啜る、それが彼女の日常なのだろうか。……あまり似合うようには見えないが、私的には悪くない。ジャンルがコテコテの娯楽小説であるというのは少し恰好つかないような気もするがね。
「…………」
……しかし、暇だ。
外から中に入ったからと言って、眠くもならなければやる事も無いのは一緒なのだ。興味をそそる本棚も、読むはおろか手に取ることすら出来ない。キッチンに置かれている珈琲も勿論飲めやしない。部屋の内装は眺めて楽しいとう次元ではないし、見るものといえば、眼前で寝っ転がっているアーシャくらいしかない。
「……」
もうずっと寝息も鼾も寝相も立てずに眠り込んでいる。この少女にはカフェインを摂ると逆に眠りが良くなるといった特殊体質でもあるのだろうか。
……私が命を救った少女が、今こうして眠っている。それ自体は喜ばしいことなのだが、
そもそも何故私はこの少女を救ったのだろうか。目の前でヒトが殺されそうだったから。自分の主義道義に反するから。
……いや、それだけではない。白状しよう、
私はこの少女が気にかかって仕方がないのだ。
それは異性だから、年若いからという訳ではない。もっと大きな理由があって私は彼女を助けた。
そう思えてならない。彼女の事を知っていけば、いずれそれが私の事を知ることになる。そんな予感がするのだ。それに、今のこの状況、前にもあったような……
Prrrrr!
と、突然甲高い電子音が鳴り響く。
Click,
「はい、アーシャですケド」
すると今まで不動だったアーシャがむくりと起き上がり板を耳に当てていた。
「…うんうん、それは大丈夫。……もう?
わかった、すぐに行くから」
Beep
「……ワタシは今から出かけますけど、アンタはどうしますか?」
話を終えたアーシャがこちらに向かって話しかけてきた。見るとすっかり外出の支度を済ませており、先ほどまで無防備に爆睡していたとは思えない程だ。
「バクスイなんてしてません!…ハァ、テレパシーが使えるサイキッカーもずっとこんな気持ちを味わってるのカナ…」
わざとらしく肩を落として見せるアーシャ。そんことを言いながらも足取りはドアへと真っ直ぐ向かっている。
ああ待て待て待て、私も行くぞ、勿論。
「別に止めやしませんけど、メンドウだけは起こさないでくださいね。これから行くトコ、ケーサツなんで」
!警察…ってことはまさか…
「そのマサカです。また出たんですよヤツらが。さ、行きますよ。モノのついでに、アンタの記憶も探しましょう」
と、言いつつもやって来たのはまたまた裏路地。
記憶喪失の私からしてみれば、先日の裏路地との違いが毛頭分からぬ。……この街には一体幾つもの裏路地があるのだろうか。
「後先考えずに、建物を持ってきた故のサンブツですよ」
先導するアーシャが私の疑問にそう答えた。路地の隙間からチラリ見え隠れする町並みは、確かに栄えているようだ。この節操の無さは、ある種ニンゲンという種の繁栄の証とでも、言えるのかもしれない。
「あ、アーシャさん、お疲れ様です。
……おや、今日はお一人ですか?」
そうこう無駄な考えを巡らせている内に、向こうから若い男が駆け寄ってきた。
「え、ええ。ちょっとね。
それより、ガイシャの状況はどうなってるの?」
真新しいスーツを着た若い男だ。見るにスーツのサイズが少し大きい様で、着ている、というより、着られているといった具合だ。新人なのだろうか。
「いつも通り…タマシイが抜け落ちたかのように反応が無く、植物状態になってしまっています。ただ…」
「ただ?」
「数か所、刃物によると思われる外傷が残っています」
その言葉を聞いて目の色を変えるアーシャ。
なんだ、たかが外傷がそんなに珍しいのか?
「ヤツラが何故【魂を喰らう者】などと呼ばれているか……それは諍いがあれば必ず付くであろう負傷痕がガイシャには殆ど残らず、まるでタマシイだけをキレイに抜き取ったかのような植物状態にしてしまうから、なんですよ」
……つまり、奴らの狙いは魂だけだからわざわざ肉体を傷つける必要がない、ってことか。
でも標的が抵抗してくれば、いくら必要は無いとはいえ、大人しくさせるために反撃したりするものじゃないのか?
「確かに、フツウならそうでしょうね。でも、今の今までそんな事はイチドも無かったんです。
……人智を超えた、ワザかチカラか。被害者はある日突然、心臓麻痺にでもなったかのように意識を失った」
まさか、そんな事が。
なるほど、これは確かにニンゲン技じゃなさそうだ。
「それで付いたナマエが【魂を喰らう者】。
ワタシだって本当にタマシイが喰われてるなんて信じてませんでしたよ。……でもアンタを見てると自身が無くなってきます」
じっとジト目でこちらを見つめてくるアーシャ。そんな事を言われても困る。私とて、そちら側だったはずなのだ、多分。
「タブンってなんですかタブンって!」
「あ、あのー…」
アーシャが強烈にツッコミを入れてくる後ろから若い男が遠慮がちに覗いてくる。
ああすまないね、少し取り乱したみたいだ、連れが。
Crabby…
「…ごめんなさい、つい感極まってヒトリゴトを」
「あ、いや、それならいいんですけど」
独り言……そういえば、昨日の一件でも疑問に思ったのだが、アーシャ以外には私の声は聞こえてはいないのか?そうだとしたら、アーシャが虚空に向かって会話をするかわいそうなヒ
BUMP!!
「えーっと、それでそのガイシャの状態を出来れば近くで見て見たいんだけど」
「あ、はい!モチロン大丈夫です!どうぞ」
私を蹴り飛ばした事など気にも留めず男と共に死体…じゃなかった被害者に近づいていくアーシャ。まったく、ドラム缶使いの荒い探偵さんだ。これが終わった後にみっちりと文句を...
CLUTCH!!
「おやおや、こんなトコロにドラム缶が転がってちゃあ危ないじゃあないか」
!?な、なんだコイツ!さっきまで全く気配を感じなかった。っていうかいきなり私の体を掴んでどうするつもりだ!
「レディの方へ転がって行ってもアブナイし、遠ざけとくか。……さっきからウルサイし」
TOSS!!!
WHAM!!!!
テテテ……な、なんなんだアイツは。いきなり壁までぶん投げやがって。
痛みは無いが視界がグラグラだ。
それに、なんかさっき妙な事を口走って…
BANG!!!!!
!?今度は…銃声!?
一体どこから!誰を狙って?
THUD
「お、オイ!しっかりしろ!」
その声で視線をアーシャに慌てて戻す。
アーシャは被害者の肩を掴んで血相を変えている。
そう。さっきからずっと動いていなかった被害者の上に、覆いかぶさるように倒れた、ついさっき動かなくなった、新たなヒガイシャを。
「追及する。先程の音でターゲットを仕留め損ねた。どうしてくれる、ブラック」
そんな最中に凛とした女の声が響いた。
上だ。
「ハハハ、だから何度も言ったジャン。
今日は挨拶回りだけだって」
その女の声に返答する男の声。これは、先程私を投げ飛ばした奴の声。
「…理解できない。絶好のチャンスだったハズだ。それに、ターゲットに挨拶回りなど、意味不明な」
「ヤレヤレ、わかってナイなあ。それに、俺達の本来の目的は殺すことじゃあない。楽しいのは分かるが、ホドホドにしようぜ、レックス」
ブラック、レックス。まるで対照的な二人組だ。
BANG!
「アンタ達、一体何者!」
アーシャが、天に向かって一発放ち二人の注目を集めた。
「これはこれは失礼!お目当てのレディを放置するとは、シンシの風上にも置けない振る舞いだ。……気を取り直して。
今日は貴女様に一目ご挨拶をと、思いまして」
Zoom!
そう言うと男は上に跳びあがり、女の場所まで一瞬で辿り着いてみせた。
「あ、アイサツ…?」
「そう、ニンゲン関係の始まりはアイサツから。今昔サマザマな文献にもそう書れておりました。
…では、改めて自己紹介しましょう。俺の名は黒のアッシュ。皆々様にはぜひ、親しみを込めてアッシュと呼んで欲しいですな」
ペコリと深くお辞儀をして見せるアッシュ。
その立ち居振る舞いは完璧で、どこか病的な綺麗さをも感じるほどだ。
「そして、横にいるのが才色兼備にしてこのアッシュの良きパートナー…」
「……白」「レックスです!」
ChooP!
「痛っぁぁぁ!?」
レックスと言われた女がアッシュの足を思い切り踏んずけている。何やってんだ、オイ。
「で、お二人は何の様なワケ。人を殺してアイサツと言うならば、随分とシュミの悪いことね」
一方のアーシャは冷静だ。銃口を二人に向けて離さない。その姿は先日見たものと変わりなく、正にプロの姿といったところ。
「……確かに、死体一つをプレゼントした所で処理に困るだけか…いやはや申し訳ない、アーシャ」
「!」
自身の名前を呼ばれ僅かながら動揺するアーシャ。やはりこの二人組の狙いははなからアーシャだったのだ。先ほど殺された男は、いわばただの……囮。
「……どうして、ワタシなんかの命を?」
Chuckle…
アッシュが笑う。何がそんなにもおかしいのか。
「それは、君が一番よく知っているハズだ。なぜなら…」
「!?ま、まさか」
アーシャの顔色が一変する。動揺からか、狙いもブレている。それは、マズい。
「そう、俺らは君たちが探している【魂を喰らう者】そのひとサ!」
そう高らかに宣言する黒その影から白の閃光が爆ぜる。
惚れ惚れする様な、鮮烈なアイサツだった。
「再質する。本当に、逃がして良かったのか、ヤツらを」
不満などない様な声色で不満を露にするレックス。
「だーかーらー。逃がしたんじゃない、今日はアイアツだって言っただろ?あの二人の顔をしっかりとカクニン出来たんだから、上出来だ」
こちらはレックスと対照的に喜びを隠しきれない声で返すアッシュ。
この見るからに対照的なこの二人組は、奇妙なことに最良の成績を叩き出すコンビなのだ。
「質問を変える。では、次の定期連絡はどうするのだ、よもや挨拶をしただけ、と言うつもりではあるまい。あの逃がした輩も追及されるだろうに」
「あー……いや、それは……ね。いや、連絡はいつもレックスの持ち分だし、今回も上手い事頼むよ~、ね?母様に会えるのいつも楽しみにしてたし、良いだろ?」
Crack!
路地裏にガラスの破壊音が響く。どこかの酔っ払いが酒瓶を落としでもしたのだろう。
……赤い酒とは、物好きなことだ。
「…確認する。勝算は、あるのか」
「……勿論」
先程とは打って変わり、黒い声で返答するアッシュ。
「……」
「最終的には母様の要求に従えるようにするさ。タダそれまでの間すこーしだけ俺の知的欲求を満たすのを見逃してほしいってだけサ。それに、」
だがすぐにいつものおちゃらけた声に変わる。
先ほどの黒は、見る影もない。
「あのヒトに逆らったらどうなるかは、俺がイチバン良く知っている。そうだろ?」
「…承知した。そういう事なら、今回ばかりは……見逃そう」
「……」
アーシャが戻ってきた。先程の二人組が正体を明かし逃げ去ったかと思えば、次の瞬間、アーシャは二人を追っていた。結果は、芳しくなかったようだけど。
「…………」
と、とりあえず、この二人、どうしようか?
このままってわけにはいかないだろう?
「……然るべきトコロに引き渡します。息のあるガイシャの方はケーサツに。息のないマサヨシは、家族の元に」
要は一旦警察の所に預ければ良いんだな。
「まあそうですケド。向こうも人手足りてないだろうからワタシたti…ワタシが持っていきます」
む、私を戦力外とするとは、甘く見られたものだ。
「実際戦力外でしょう?その姿で何が出来るっていうんですか」
Thump
…確かに、この姿では人っ子一人持ち上げる事も出来ないな…
し、しかしだね。思い出してくれ、私はユーレイなのだ。もっと便利な…何か……その、凄いものに乗り移る事が出来たら、その評価は覆さなければならないだろう。
「たしかにー。出来たら凄いですねー」
こちらを気にも留めないアーシャ。…この扱いにも慣れてきたが、私にも意地というものがある。やられっぱなしでいられるか、何か、使えそうな躯体は……
あ、そうだ。丁度いい器があるじゃないか。
「あんまり気が散らない様にしてくださいよ。
ワタシこれからオトコのヒト二人持って行かなきゃいけないんですから……アレ?」
アーシャが撃たれた方の男を持ち上げ辺りを見渡す。探し物はもう一人の男だろう。
フフフ、違うぞ違うぞ、そちらじゃない。こっちだこっち、声のする方へ…あっ、
Slide,!
「………………エ」
ててて…先程までゼロ足歩行の物体を操っていたから慣れないな。それに相変わらず痛覚も感覚も無い。地面を踏みしめる感覚すらおぼつかぬとなるとこりゃ相当に難しそうだ。
「…………アンタ、そのガイシャの体に、いったい何を…」
アーシャがこちらを指差して驚愕の表情を浮かべている。
無理もない。何しろ一番驚いているのはこの私なのだから。
「まさかタマシイを抜かれたニンゲンに乗り移るとか……アンタ本当にユーレイなんですか?」
な、なにを失礼な!人体憑依こそユーレイの十八番なんじゃないのか!?
Ahem..
と、とにかく、これで運ぶのが楽になっただろう?この体はどこに持って行けばいいんだ?
「マッタク…あれですよ、アレ」
そう言ってアーシャは視線を空へと向ける。
こんな裏路地から見えるものなのか?と、疑問に思うもつかの間、上を見るとビルとビルの隙間から、確かにそれはそこに在った。
「ご苦労だった、アーシャ君。うちのモノが世話を掛けたな」
こちらには目もくれず、一心不乱にディスプレイに向き合う眼鏡姿の男。
「いえ、お気になさらず。お互い様ですよ、メガネさん」
「…ああお互い様だとも。キミ達の様な部外者に頼らざるを得ん程我々は脆弱無能な組織だからな」
イヤ味ったらしく言葉をつづる男。だが無理もないのかもしれない。何しろ場所が場所である。
普通に考えれば、素性も知れぬ探偵ごときが入れるはずの無い場所なのだ、ここは。
セントラルスカイライン
路地裏からでもハッキリと見えたこれは、正しく天へと続く線であり、この惑星で最も高く、最も巨大な建造物である。
現在は世界統合政府の本部として限られたニンゲンだけが、忙しなく行き来している。
そんな名実共に世界の中心に位置するCSL。
だが、何時、誰が、何のために建てたものなのかは一切分かっていないのだ。
構造上の欠点をいつくも持ちながら、損害、破損の形跡は無し。修復を出来る者……どころか、構造を把握しているニンゲンすらもまるでいない事実。
公式には大総統執務室の100階が最上階とされているが、頂上も見えぬこの建物がわずか百階ぽっちの訳がない、というのが一般認識らしい。
……CSLは、二つある月のどちらかに繋がっている。という噂もあるほどの謎多き建物。
さながら、現代に蘇りしバベルの塔である!
……というのをここへ来るまでの間にアーシャから聞いた。
聞けば聞くほどこの場所は超重要な所であるはずなのだが、なぜ顔パス如きであっさり入れたのだろうか。アーシャがおかしいのか、この組織がおかしいのか、分からなくなる。
「それで、持ってきてくれた横のモノが例の…」
「ハイ。今回のガイシャです」
そこでようやくディスプレイから目を離し私の方を吟味するように見る眼鏡。棒立ちというのもなんなので少し頭を下げて下手に出ておこうか。
bow
「……確かに、動いているようだな」
「でも他のガイシャと同様に意識はありません。今は、別のタマシイが動かしているだけです」
こ、こんにちは!お初にお目にかかります、
ユーレイです、お堅いメガネ君。
「……なにか今また馬鹿にされた様な気がしなくもないのだが」
「気のせいですよ、メガネさん」
……やはり私の声はアーシャ以外には聞こえていないようだ。その点も不思議ポイントではある。これって霊感のあるなしの様なものなのだろうか。周りにいる職員たち誰一人と私の声を聞けるものはいないみたいだが。
「俺は神霊の類は信じてはいない。上はそんな与太話の様な事柄、例え事実であっても信じない。故にこのガイシャは今から検査に回すが……今このガイシャが動いたというのは、紛れもない事実のようだな」
メガネを直すメガネ君。
「魂の存在…そしてそれを狙うもの……どちらも毛頭信じてなどいないが、突然意識不明になる者、そして、それが故意的に起こされていること。それらは事実だ」
ふむ、このメガネ君、ただのお堅いお役人かと思えば、意外とそうでもないらしい。
「現実に起こっている事実は例えどのようなモノであれ受け入れる、それが俺の信条だ。だから安心してくれ。それを突き止めた君達のことは信頼している。無論、今回の件も、だ」
席を立つメガネ君。指先でちょいと指示を出すとすぐにスーツ姿の男がやって来て私を取り囲んだ。
「善は急げだ。今からコレを調べさせてもらう。君はいつも通り下のカフェで時間でも潰してるといい。……ああ、後。俺の名前はレイ・グラスだ。二度とメガネなどと呼ぶんじゃない!わかったか!」
えらく強い語気で睨むメ…グラス。あの人、本当に私の声が聞こえてないのだろうか?!
あ゙あ゙―、やっと終わった…
「なんだか随分疲れてますね」
そりゃあもう、左へ右へたらい回し。モノ扱いなのに上から目線で指示を出してくるし、化け物を見る眼を常に向けられてるのは中々堪えたね…
「それはご愁傷様です」
全く心のこもってない返事。ヤレヤレ、酷いものだ。……でも、こちらは少なくともヒトとして見てくれるからまだありがたい。
「…それにしても、よく返してくれましたね、
こんな歩く国家機密」
…確かに私もそれは思っていた。あのメガネ君の性格からしてこういうモノは自分の手元に置いておきたいタイプだと思っていたんだが……これまでのヒガイシャはどうなってたんだ?
「ココで管理されてるハズですよ。ドコで管理されてるのかまでは知りませんけど、カレらだって意識は無くともカラダは生きているんですから」
…うーん、ならなおさら謎だ。私の様な特例個体、それこそ手元で管理したがるようなものだが…
「自力で動けるならカラダの管理も自力でやってくれるとでも思ったんじゃないですか?脳死患者の維持費ってバカにならないって聞きますし」
え。そ、そんなものかなぁ…?
「そんなモノですよ。あのメガネ、見た目の割にはあんまり深く考えてないんでしょ、キット」
そういって飲み干したからのカップを後ろに投げ捨てるアーシャ。するとすかさず清掃ロボットが現れカップは地面に着く前に回収された。その一連の動作に見惚れているとアーシャは我先に進んでいってしまった。
慣れない体を動かしながら何とかエレベーターが閉まる前に滑り込めた。扉が閉まりカフェテリアの喧騒も全く聞こえなくなる。
と、思うとものの直ぐに一階へたどり着く。驚くほどの高速エレベーターだ。
ドアの先に広がる、さながら空港の様なだだっ広いエントランスでは多くの人が忙しなく動いている。
……その中にこちらを伺う視線も感じられる。
「やっぱり職員の人はみんなアンタのコト知ってるみたいですね」
ほ、ホントにこのまま行っていいのかなぁ?!
……美味しくない。というか味が無い。咀嚼の感覚もまるでない。
……体があるなら何か食べれると思ってたのに、これではまるで拷問だ。
「ちゃんと全部食べてくださいね。セッカク作ったんですから」
うう……大人しく携帯食料にすれば良かった……
美味しそうな食品サンプルを口に運ぶ新手の拷問。匂いも感じずお腹も空かないのがせめてもの救いだろうか。欲が無ければ辛くはないもな。
「まったく、こんなんじゃ作り甲斐もあったもんじゃ無いですよ」
そう愚痴をこぼしながら自分の野菜炒めを口に運ぶアーシャ。
それにしても驚いた。アーシャがこれほどまでに立派な見た目の料理を作れるとは。
「味も、立派ですから!」
いや、私は味が分からないのだから、これでも精一杯褒めているよ。美味しそう、美味しそう。
「ヒトコト余計ですよ。……まあ確かに、ワタシは料理は得意な方では無いです。ずっと作ってたから慣れただけですし」
それにしては、やや見た目が凝っている様な気もするけど。
「生きるために食事は避けられない。避けれない事は目いっぱい楽しめるようにヒトってものは出来ているんだよ。なーんてキザなセリフばっかり言ってたヒトに作り続けてたせいですかね」
遠い目をして思い出を語るように言葉を紡ぐアーシャ。その眼差しはとても柔らかで、疎ましくも尊敬の出来る父親を見るような……
「何カッテにヒトのこと実況してるんですか!
ほら、この食事の美味しさがわからないんだったらトットと食べちゃって下さい!」
!だがらってそんな乱暴に口に突っ込まなくてもちゃんと食べるからさあ!
ていうか、勝手に人の心を読むのはスルーでいいんですかアーシャさん!ねえ!そこんトコ、どうなんですか?!
Crush
グラスが割れ、赤い液体が床に広がった。先ほどから不毛な押し問答をしていたので飲み物が落ちたのだろう。っていうかいつの間に赤ワインなんて飲んでいたんだ。なんとはなく、似合わない気もするけど……
「ッ!?」
Smash!
?!小さな机を押し倒してアーシャがそのまま私も押し倒した。い、一体何を…
「くっ……」
アーシャの服の端が裂ける。目の前の少女が苦悶の表情に歪むことで、私はようやく事態を悟った。
……これは、敵襲!?
「……アンタ、手は?」
腹部を抑えながら尋ねてくるアーシャ。そんな場合では無いだろう!
アーシャを支えるために私は右手を伸ばす。
が、違和感。視界にはいるとその違和感は確信に変わる。
血だ。この体の右手に血がベッタリと付着している。なぜ?そんなにひどいのか、アーシャ!
「……ワタシじゃないですよ、ソレは。アンタのカラダの血です。……見えませんか?その右手、もう元の形じゃありませんよ?」
アーシャは更にカラダに密着してくる。
そのアーシャを抱えるような形で手を前に回す。すると私にも血だらけだった右手がハッキリと見えた。……コレを今でも右手と呼べるなら、だが。
「……このままワタシをギュッと抱きしめてください」
え?あ、ああ。わかった。
Hugs
こ、これでいいのか?
「…………」
アーシャは何も言わない。ただ私の腕の中で浅く呼吸を繰り返している。
……心なしかアーシャの体から微かな温もりが感じられる。今の私に、感覚などないというのに。
「……ヘンなコト……考えたら……ブッ飛ばし……ますよ……」
し、失礼な。大体ビート版を押し当てられて変なことを考える男がこの世にいるもんか。
……こんな状況でも軽口が叩けるとは全くもって大したものではあるのだが。
huff… huff… huff…
アーシャの呼吸音だけが静寂の中に響く。
……もう敵は行ったのか?
「……どうでしょう、あの一回で諦めるとも思えませんけど」
それもそうだ。
「とりあえず、一旦ここを離れましょう。これは、チャンスでもあるんですから」
お、おい。チャンスって、体はもう大丈夫なのか?
「ああ確かに、その右手さすがにそのママはマズいですね。ちょっと待ってください、包帯くらいならありますんで」
そういってどこに部屋の片隅をまさぐるアーシャ。いやいや私のではなく、君の体のことを言っているんだ。
「へ?……平気ですよ、このくらい。
スグ、治りますので」
そういって自分の横腹に雑に包帯を巻きつけるアーシャ。いやでもその場所は……
「はいはい早く行きますよ。さ、おてて出してください」
実に見事な手際で私の右手に包帯を巻き終わると、私達はすぐさま部屋を後にした。
日はもう完全に沈み切り、二つの月も雲に隠れて両方とも見えなくなっている。
昼の住人は自宅へ帰り、夜の住人はまだ起きだしたばかり。そんな狭間の時間の裏路地は、すがすがしい程に静かだった。
「このままCSLに近づいて、表通りに出れば敵も大手を振って追ってはこないと思いますけど」
……どうやら、そういう訳にはいかないらしい。
「忠告する。大人しく捕まってくれれば、命だけは助けてやる」
いつの間に現れたのやら、目の前にはこの前の片割、レックスと呼ばれていた白い女が立っていた。
相も変わらず表情を全く動かさず、声色からも感情を読み取る事など出来そうもない。
「イノチは助けるけど、タマシイは頂く……そんなキベンのつもり?なら、センスがないと言わざるを得ないわね」
煽りを返すアーシャ。だがコイツにその類が通じるのかどうか……
「……了解した。交渉決裂、だな」
SLAM!!!
銃を構えながらアーシャに急接近するレックス。
だが、アーシャは後ろに下がるのでは無く、
猛スピードで全身するレックスに向かって飛ぶ。
「!?」
二人の位置が入れ替わる。いつの間にかアーシャの手にはナイフが握られおり、レックスは自身の右手を抑えている。
「ビビッて後ろに下がると思った?バカね」
アーシャは相手の想像を超えた行動をした。この土壇場でそんな返しができるなんて、やはり彼女の只者では、無い。
そのままアーシャは、余裕の表情でナイフをしま────
Tinkle,
────えなかった。アーシャはナイフを落としてしまったからだ。
慌ててナイフを拾おうとするアーシャ。
smack!
「くっ!」
伸ばした右手の皮膚が裂ける。
僅かながらに黒い液体が路地裏の地面に落ちた。
「驚嘆する。キサマにはこの仕掛けがわかっていたのだろう?なのにワザワザ自分から飛び込んでくるとは、大したものだ」
……仕掛け?何のことだ。
「細い路地に目いっぱいの鋼鉄ワイヤー。アンタはその位置をすべて知っていて、ワタシはこの暗闇でまるでわからない。そういうことね」
「肯定する。……君たちはあまり傷つけたくない。故に、あまり動かないでもらえると、助かる」
!飛び散った血が、微かな明かりに反射して私にもワイヤーが少しだけ見えた。決定打にはなれないが、相手の動きはかなり封じられる。
「再び忠告する。投降しろ」
「……………」
アーシャは答えない。しかし、打つ手もない。
この暗闇では私も動くに動けない…………………いや待て、この体は動けないが、私自身は動けるではないか!
腰が抜けるような形で地面に座り込む。そこからスーッと上に抜けるような感覚で……
!で、出来た!入れ物の移動も慣れたものだ。
上から路地裏全体を見渡す。ワイヤーは相変わらず見えない。しかしながら明かりのついていない電灯が見えた。次はそいつにとRituiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii,,,,,...
ちね ちすいめ にかなかちにみちみにきちめ
『質問する。キサマ、一体そんな所で、ナニをやっている?』
「!?」
彼の気配が消えた。驚きのあまり振り返るアーシャ。
「確認する。よそ見をしている場合か」
その隙をレックスは見逃さない。一発、二発。アーシャの両足を撃ち抜いた。驚異的な早打ち、信じられない正確さである。
「落胆する。その戦法は我々には通じない。
キサマ達が呼んだのだ、【魂を喰らう者】と」
丸裸のタマシイを握りつぶすなど造作もない、と続けるレックス。
「……それに、話で気を引こうなど。私はブラックとは違う。キサマ達には何の興味もないのだ」
そう言葉を続けるレックス。だがその言葉はアーシャには届いていなった。
───また失うのか。まだ、何も返せてはいないのに。
「……最後の忠告をする。大人しくッ───!?」
凄まじいスピードでレックスに接近し、銃を奪い取るアーシャ。
「!馬鹿な。何故動ける、その傷で」
ワイヤーを無視して強硬突破したアーシャの体には、大小無数の傷がついていた。両足の銃創も、まだそのままだ。体中を蒼く汚しながら、突進をして来た。
「……痛みで動けないのならば、痛覚を遮断すれば良いだけのこと」
アーシャから表情が消え声色も平坦なモノへと変わる。
「き、キサマ゛ッ!?」
レックスが自身が敷いたワイヤーの群れに投げ飛ばされる。
そして、弾が尽きるまで無表情でアーシャは撃ち続けた。
その姿を遠くから眺め、一人歓喜を抑えられぬ、黒がいた。
「ん、……ここは」
「気が付いた様だな」
アーシャはベッドの上に寝かされ、知らない天井を眺めていた。
「キミが運ばれてきたときは肝を冷やしたぞ。なにせCSLの医者たちが口を揃えて、我々には対処出来ません。と言ってきたのだから」
ベッドの傍にはレイ・グラスがいた。
つまるところ、ここはCSLの内部。
CSL120階、特殊個体管理棟である。
「すいません、隠してたつもりじゃないんです」
「仕方あるまい。統合政府の中でもアレは黒歴史なのだ」
古ぼけたファイルを片手に呟くグラス。
「Project Deus Ex Hominibus.ヒトによる新たな種の創造。ニンゲンを超えたヒト、ヒトデウス。……その失敗作が、ワタシ」
「……人造人間、ホムンクルスか」
「そう、ヒトは神を作り出せなった。出来たのはただのヒトの模造品。ニンゲンになれなかった、哀れなヒトガタ」
そう呟くアーシャ。遠い昔を思い出す様に。自分事を他人事の様に。
「……そして、その結果に失望したニンゲンは、ホムンクルスを生きたまま焼却した。
ふざけた話だ。神にでもなったつもりだったんだろうよ、上は」
「……………」
「思えばそれからだったか、奴らが現れたのも。本当に天罰なのかもしれないな。神の領域に近づいたニンゲンを打ち落とすための御使い」
グラスが柄にもなくオカルトな話をしている。
仕方もないのかもしれない、それほどまでに狂った計画だった。
「とにかく、今はゆっくり休むが良い。我々の技術でも君の事はよくわからなかったのだ」
「あ、あの。ワタシと一緒にいたあの動くガイシャは。一体、どうなったんですか」
訪ねるアーシャ。グラスは、振り向かず答えた。
「アレは見つかっていない。
………いつも通り、持っていかれたのだろう」
目を閉じると。昔の景色が蘇る。
緑の培養液越しに見える世界。
そこでは一人の男と一人の女が、なにやら話をしていた。
それは、ワタシの見た、父様以外のニンゲン。
優秀な妹を持つプロトタイプのワタシにとっては、緑の世界こそが、ワタシの世界の全てだった。
けれど、そのすぐ後に、緑の世界は終わりを告げた。
燃え盛る、炎に囲まれた。赤い世界。灰に塗れたカラダとココロ。そこでワタシは外の世界で初めてヒトに出会った。
「久しぶり。さあ、あの時の続きを始めよう」
なんだ、ここ。
頭の中がボーっとする。視界が真っ白だ。
………ここは、あの世か?
【おや、ここにニンゲンのタマシイが迷い込んで来るとは、奇妙なこともあるものですね】
だ、誰だ?!姿が見えない。声も…一体どの方向から……
「───かあ、さま」
先程とは違う声が聞こえた。こちらも姿は見えないが、女の声だ。しかも、この声はどこかで聞いたことがあるような………
【成程。黒が白を拾い上げる際に、紛れ込んでしまったのでしょう。あの優秀な黒が、珍しいこともあるのですね】
謎の声はそう続ける。黒…白……!もしかして、さっきまでアーシャと戦っていた、レックスか?!
そう認識すると何もない空間に、一つのもやの塊が見えた。真っ白いもやだ。ひどく不安定で、ゆれ動いている。
「ごめんなさい。わたし、しっぱい、した」
もやが言う。その声は、幼子の様にか弱く、これがあのレックスであるなどは想像も出来ない。
【大丈夫ですよ、白。あなたは優秀です。その証拠に、わたしが色を授けたのですから。そのことに、もっと自信を持ちなさい】
あやす様な声色、優しく掛ける言葉。なるほど、確かに母親の様だ。
【様、では無く、母親なのです。わたしは】
なんだと。それは、一体、どういう意味で。
あなたが、彼女を産んだというのか?
【いえ、そうではありません。この子たち………そしてわたし自身を作ったのも、わたしの子供たちですから】
?……どういうことだ。意味が、わからない。
【そのままの意味のこと。子等は自らを導いてくれる母親を望んでいた。だから、わたしが生まれたのです】
作った…?生まれた…?その子供たち、ってのは一体何者なんだ!?
【ふふふ、貴方はそれを知っているはず。何故ならばわたしと貴方、こうして会うのは二度目なのですから】
!私の過去を知っているのか!頼む、教えてくれ!
【それは構いませんが……少々お行儀がなっていない様ですね。親しき中にも礼儀あり、です。
いいですか?お願いします、お母さん。と言ってみなさい】
な、なんだ。そのくらい。
お願いします、おか───
ダメだ!
っ?!い、今のは……
【どうかしましたか。早く言ってごらんなさい】
……過去を知りたい。その気持ちは変わらない。…でも、なぜか嫌だ。その言葉を口に出すことが。
お願いします。どうか、教えては頂けないでしょうか。
【ひとつ忘れていますよ、
わたしの事を、おかあさん、と言いなさい】
声は変わらず穏やかだ。なのに底が見えない。
まるきり違う生き物と話しているような、言葉は通じるのに、理解は出来ない。こんな感覚を、どこかで…
コロしたいんでしょ?あの紛い物のカミを
脳裏に声が響く。聞き覚えのある、女の声だ。
アカイ女。そう、それこそ、真っ赤に熟した─
CLUTCH
【……躾 の な っ て い な い 子 に は 、
お し お き が 必 要 で す ね 】
背筋が凍る。ヘビに睨まれたカエルの気持ちというのはこういうモノだったのだろう。
──失敗した。目の前のモノに逆らえばどうなるのか、分からなかった訳じゃないのに。
でも、出来なかった。
…………すまない。まただ、───兄さん。
「あんなケガをしたばっかだってのに、こうも動けるとは、流石だなぁ、化け物!」
ビルからビルへ。地から天へ、天から地へ。
時には鈍器を、時には鉛玉をぶつけながら飛ぶように戦うアーシャとアッシュ。
「……」
「なぜ反論しない?…事実だからだ。オマエがヒトの形をしたバケモノという圧倒的な事実があるからだ!」
アッシュがアーシャを地面へと叩きつける。
轟音と土埃が辺りを覆う。アーシャの姿は見えない。
「さあ立ち上がれアーシャ!キミにはそれが出来るハズだ!出来なきゃいけないんだ!」
羨望に近い眼差しで土埃を眺めるアッシュ。
瞬間、アッシュの喉元を瓦礫の弾丸が掠める。
「……まずは、そのうるさい口を…」
すかさず二発目が飛んでくる。アッシュはそれを打ち返す。しかし、次の瞬間にはその弾は、同じく瓦礫で出来た盾に守られていた。
ニヤリ、とそれを見て顔を大きく歪ませるアッシュ。
「ハハ……ハハハハハ!そんなコトも出来るのか!キミは!」
笑みで全身を震わせながらアッシュは再びアーシャの元へと突撃した。
……
…………
………………ん。
視界はクリアだ。何が起こった。
私はさっきタマシイごと握りつぶされたはず。
それなのに何故…
「アア……ガアアアアッ!」
!?何の声だ!この、うめき、声は…
「キサマ……かあさまに何をした!」
レックスだ。私の目の前にはレックスがいた。
真っ白な幼子が一糸もまとわぬ姿で、震えていた。
「…かあさまが、0.1秒も、フリーズするなんて!」
フリーズ、そのおかげで私はあの謎空間から出られたのか……しかし誰が。
あの声の正体もわからず仕舞いだったな。
おい、お前はさっきの場所について、何か知っているのか?
「ああ、かあさまかあさまかあさまかあさま……」
……この様子じゃ話にならないな。
どうしたものか……!そうだ、アーシャ!彼女はどうなった?!
BOOOOOOOOM!!!!!
破壊音が響く。音の方向を見ると、穴が、あった。
「ぶ、ぶらっく?」
「あーあ、大変な事になってるじゃないか。
レックスもまだ未調整だし」
そこに現れたのは、アッシュ。泣きじゃくるレックスをひょいと持ち上げて、こちらを、向いた。
「さて……これをやったのは、オマエか?」
これまでとは声色が違う。いつになく真剣な眼差し。こちらが気圧される程の威圧感。
しかし、そう言われても私としては何も知らないのだ。答えれることなど、何も。
「ふーん、そうかい。俺もタマシイの声はハッキリとは聞こえないんだけど、何かを知ってるって風じゃあなさげだな」
それで興味を失くしたのか、アッシュは私に背を向けた。
「───じゃあ、やっぱり貴女の仕業ですか、
これは」
天に向かってそうつぶやくアッシュ。
Zoom!
Thud
どこかへ飛び去ってしまうアッシュ。それと入れ替わるように一つの物体が私の目の前に落ちた。
「あ、アンタ……どうして、ココに…」
アーシャだ。傷だらけで、満身創痍のアーシャがそこにいた。どうして、そんな姿に。
「……ちょっと、ミスしちゃった……だけです。スグに、アイツの……あと、を」
barf
口から青い血を吐くアーシャ。
無茶だ。そんなダメージじゃ。今すぐにでも医者にかからないと。
「……無駄ですよ。ワタシを、根本的に治せるのは……父様、だけですから……」
SLAM
崩れかけていた前方のドアが、音を立てて壊れた。そのドアの先にはすっかり焼け落ちた、何かの研究施設。気づかなかったが、どうやらここはCSLの上階らしい。
「……ここ…は」
ああ、これは全て偶然なのか。
偶然ならば、出来過ぎだ。この世に神でもいなければこの奇跡は説明がつかない。
必然ならば、出来過ぎだ。こんな見通しを立てていたとは、どんな天才なのか、見当もつかない。
「……?」
行こう、アーシャ。私ならば君の事、治せるかもしれない。
「…………まさか」
いささか外見は不格好だが、運動機能は80パーセントほどまでは回復出来た。
奇跡的に焼けていない研究機材が残っていたので、なんとか修復することが出来た。物理的に干渉出来る体は見つからなかったので、アーシャに乗り移って作業した。
「…………どういうことですか、ハカセ」
アーシャが訪ねてくる。今のこの体には、アーシャのタマシイと私のタマシイ、二つのタマシイが入っているのだ。
一つの器に二つの魂。こんなことが出来るのは、一番最初に作ったType _A……つまり、君しかいない。
「そうじゃ無くて、どうしてアナタなんですか!ワタシはてっきり、センセイかと……」
私にも詳しくは分からない。けど、一つだけ、思い当たることがある。
きっと彼女の仕業だろう。ワインの様な赤い心とチェリーの様な可憐な心を持った、彼女の。
「相変わらず、こんな遅くまでよくやってるよ。
あ、夜食、ここに置いとくから」
自動ドアの開く音、良く反響する足音、そして何より他人の声。それは私が最も嫌いなものだった。
「そんなに急いで何になるのかねぇ。そろそろ母さんにも顔出した方がいいと思うぜ。もうすっかりお前と会ってないって落ち込んでたよ」
私への夜食と言いながら持ってきたサンドイッチを自分で頬張る。…………出て行ってくれないか。手を借りることなんて何も無いよ、兄さん。
「ハハハ、今更お前の助けになれるなんて思ってないよ。天才の考える事は、凡人には分からないからね」
こっちだって、兄さんの考えている事なんて分からない。どうしていつまでも、付きまとってくるのか。
「そりゃあ大切な弟だからよ。人生は一度きりなのだから、そんなに生き急がず、目いっぱい楽しんでほしいのさ」
……お気楽な。もし明日人生が終わったらどうするつもりなのか。
「そん時はそん時だ。明日を後悔しないように今日を目いっぱい生きる。これ、何も間違ってないと思うけどな」
じゃあおやすみ、と言い残してそのまま下へと降りて行った。皿からはサンドイッチがもう一つ減っていた。少し手を休め、一つ手に取る。
……やれやれ、兄さんはいつもそうだ。
無駄を楽しめ。理解できないよ。このサンドイッチだって、無駄をなくすために発明されたものじゃないか。それを、持ちにくくするまで具材を詰め込むなんて…
「そうね。アナタの目的の為には、例え一秒たりとも無駄に出来ないものね」
!後頭部に銃口らしき感触。
この女、一体いつの間に……
「そんなコトは些細な問題でしょう?アナタなら知ってるわよね。CSLがどういった場所なのか」
……ああなるほど、そういう事か。
つまり、君は私の敵だということだな。
「フフ、それはどうかしら。アナタに協力を仰ぎに来た裏切りモノ、って筋は考えないの?」
裏切り者?ハハハ!それこそお笑い種だ。
単一の指揮系統で動くお前たちに裏切り者など出るハズもあるまい。
「それもそうね。…………アタシがアンドロイドであるならば、ではあるけども」
そう言うと女はナイフを取り出して、おもむろに自分の指を切りつけた。人差し指から少量の出血……!や、やめろ、急に口に指を突っ込むな!
「でも、これならわかるでしょう?アンドロイドの生体循環液とは全く違う、真っ赤な血の味」
……私は君達の生体循環液など食べたことはないよ。
「でも同じことでしょう?アタシ達のアンドロイドと、アナタのホムンクルスは同じ素体から出来ているもの」
!そこまで知っている……いや当然か。
私は彼女の掌の上でずっと転がされているだけだものな。
「アタシもよ。アタシが生身のニンゲンだというのは当然把握されてる。同じね、アタシ達」
馬鹿を言うな。君と私は同じではない。絶対に超えることの出来ない、決定的な違いがある。
「違い……?オトコと、オンナってところかしら」
とぼけるな。そうじゃないだろう。
「……先住者と、侵略者」
……そうだ。
「それこそ些細な違いじゃない。アタシ達、どっちも同じニンゲンなんだから」
ニンゲンだからこそだ。ニンゲンは、同じ惑星の元ですら、一つになれない。そんな中、他の惑星から来たとなれば尚更、だ。
どれだけ科学が証明しようと、私達と君達は決して一つにはなれないのだよ。
「でも、……ニンゲンを超える上位存在が纏め上げれば、一つになれると思わない?」
……それが、君達の考えか。
考える事を放棄し、種の尊厳を放棄し、
すべてを神に委託する。
「……母様の考え。アナタもそう思って、上位存在を作っているのではなくて」
まさか、コレはただの先兵だよ。AIを殺すためのね。
……違うモノどうしが無理に一つになる必要はないんだ。ニンゲンは区別により、平穏を保ってきた。これは、ただの自衛さ。
「……そう。まあアタシにはそんなの関係ないわ。アタシがしたいのは、復讐だけ」
復讐か、物騒なことを言う。それは、故郷を奪った私達へ向けてのものか。
「勿論。……けれど、それだけじゃないの。アタシは、アタシ達を見捨てた月のヤツらにも、アタシは復讐したい」
見捨てた?それは、どういう…
「アタシ達の生き残りがCSLの上……月の繭でデータだけになって眠ってるのは知ってるわよね」
……ああ。知りたくなかったがな。
「けど、そこには全員がいるわけじゃ無い。母様によって選別された、“後世に残すべきニンゲン”だけが眠ってる」
……なるほど、お前の言いたいことが大体わかったよ。
「最後まで言わせて。
……もちろん、全員が助かったワケじゃない。
本当に多くの人達が見殺しにされた」
…………
「でも、アタシだけはなぜか生き残ってしまった。なら、やるべき事は一つでしょう?」
……で、結局のところ私に復讐の手助けをしろ、ということか?
「もちろんそうよ。アナタだって、母様のやり方には反対なんでしょ?」
しかし、もし仮に奴を倒せたとして、その後はどうするんだ。
「もちろん、アナタ達を滅ぼすわ」
ハハハ!何て無意味な。全て消してしまうなら復讐の意味がない。もっと簡単な方法がある、自殺だ。払うコストは段違いなのに、それだけで同じ効果が得られる。
「あきれたヒトね。それこそナンセンスよ。全ての意味を煎じ詰めていけば、それこそ生きる事すら無意味になるわ。人生ってのは、生まれてから死ぬまでの無駄をいかに楽しむか、なんだから」
どこぞのバカの様な事を言う。
…………それじゃあ、やっぱり敵じゃないか。
「残念ね」
まったく残念そうでない口ぶりで女は引き金を引く。しかし、その弾は当たらない。
「へぇ……凄いスピード。フルパワーのアンドロイドにも匹敵するんじゃないかしら」
…少し早いかもしれないが、実践テストと行こう。
デルタ!ジュリエット!ロメオ!
「っ!」
D、J、Rがそれぞれガラスを突き破り女に襲い掛かる。三対一だ、卑怯とは言うまいな。
それぞれが連携を取りながら女へと襲い掛かる。女は銃を持っていて対する三対はそれぞれ丸腰だ。
しかし問題にならない。女がマガジンの弾を使い切ったタイミングで一斉に襲い掛かる。ニンゲンを凌駕するパワーとスピード、ひとたまりもあるまいよ。
…………これで、ゲームオーバーか。
案外、あっけないものだ。
「驚いたわ。本当に強いのね、この子達」
!馬鹿な!三方向同時攻撃を受けて、何故生きている!?
「同時、なんて一斉に斬ってください、て言ってるようなものじゃない。特に、彼に対しては」
?!三対とも反応が消失している。
女の方を見ると、その傍らに男が一人……………クソッ!アンドロイドか!
「彼の名前はアッシュ。母様から最強の色、黒を与えられた、正真正銘最強のアンドロイドよ」
……最強のアンドロイド。GMA小隊ですら傷一つ与えられなかった私のホムンクルスを、いとも簡単に……
「あら良いの?身を守らなくて。まだ一体、そこに眠ってるみたいだけれど」
アッシュと呼ばれたアンドロイドがじりじりと私に詰め寄る。確かに、女の視線の先にはまだ待機中のホムンクルスが一体あった。
しかし彼女では君達に歯が立たないだろう。Type_ A……私の無駄が詰め込まれた、ただのプロトタイプさ。
「あら、素敵じゃない。……見てみたいわ」
そう言って女はAの入っているケースを打ち抜いた。埃をかぶったケースからAが落ちる。
だめだ、逃げろ。
「ニゲロ?使い捨ての駒に、随分とお優しいんだな、アンタは!」
アッシュの腕が突き刺さる。剣のように鋭いソレは見事に私の心臓を貫いた。
「!?■■■!」
視界の端に兄さんが見える。……なぜ来たんだ。
全く、最後の最後まで訳の分からないやつだ。
アッシュの剣が抜け、私は地面に倒れた。
不思議な感覚だ。体は朦朧としているのに、
意識だけは妙に冴えている。
……周りが暖かい。燃えているのか、私は。
いや、私だけじゃない。この研究室自体が燃えている。
兄さんは……Aはどうなっただろうか。
何故私は先程Aに逃げろなどと言ったのだろうか。
……もうどうでもいいか。私はもう死ぬ。
けど最後に、君の名前を知りたい。赤い信念を持った、君の名前を。
血緋のチェリー。本名は、とうの昔に忘れたわ
私の記憶はそこで途切れている。
逆に、君の記憶は、そこから始まっているはずだ。
「はい、ワタシが目覚めたとき、辺りは燃えていて、目の前にはセンセイ……ハカセのお兄さんがいました」
チェリーとアッシュは、もういなかったのか?
「ええ、ワタシが目覚めたときには既に」
そうか。そして君は兄さんに拾われ、育てられた。……その名前も?
「ええ。ASHA───アーシャ。炎の中で倒れているワタシを見て、そう名付けたそうです。
言ってしまえば、センセイは、ワタシにとって父親の様な存在だったんです」
兄さんが父親ってことは、私は母親ってことになるのだろうか。
「……それからセンセイは、ずっとハカセのやっていたコトを調べていました。何のためにあんなことをしていたのか、どうしてあんな最後になったのか。……センセイにもその答え合わせを聞かせてあげたかったですよ」
……そうか、あの時路地裏で見た死体は、私ではなく、兄さんのだったのか。
「……さて、もう動いて大丈夫ですよね?そろそろ、行きましょうか?」
え、行くってどこに?
「アッシュのトコロに、です。アイツは、ワタシが決着を付けなきゃいけない……そんな気がするんです」
「う──ああ──うあ」
未だ意識のハッキリとしない裸のレックスを抱え夜の街を飛び回っていたアッシュ。どこか休める場所はないかと探していると、窓が割れている一室を見つける。
中に入ると、夕食であったであろうモノが床に散乱している。それを避けつつ、狭い部屋に不釣り合いな本棚の前にレックスを置く。
「───かあ……さま?」
「違う。俺は母様じゃない。アッシュだ」
「あっしゅ……わたし、しっぱい……した」
最弱の色を冠する白。何色にも染まっていないアンドロイドを、赤黒く染まった自分に任せるとは、一体どこまで考えているのか……とアッシュは末恐ろしく思う。
「大丈夫だ。まだ、挽回のチャンスはある。なんたってお前は母様に選ばれた色付きじゃないか」
しかし、今はそんなことを考えている余裕は無い。討ち漏らしたタマシイと、
アーシャの事を考えねば。
そう思うと自然と口角が上がる。
「まだやれるだろう、ホワイト。さあ、返事をしてみせろ」
「───はい」
「よし、それでいい。もうすぐヤツらが再びやって来る。俺はアーシャの方をやる。お前はタマシイだけの片割れをやるんだ。
わかったな、レックス」
「──了解した。私はタマシイだけの片割れを破壊する」
幼児のような泣き顔はどこへやら、いつも通りの無表情へと変貌したレックス。最弱の白色は、染められることで最強へと変わる。
アーシャ、君のセンセイ……兄さんは、どんなヒトだった?
「え、それをワタシに聞きますか?ジツの弟であるハカセの方が詳しいと思いますけど」
いや……それが情けないことに、兄さんの事は殆ど覚えてないんだ。
「……楽しそうな、ヒトでした」
そう静かに語りだしたアーシャ。それは、私の知らない、二人の話。
「よしっ!出来た。ささ、冷めないうちにどうぞ召し上がれ」
ソファーの前に机をずいと持ってきてその上に料理を持ってくるハカセ。……ズイブンと多い。これは本当に二人分なのだろうか。
「いただきます。ちょっと作りすぎちゃったから遠慮せずにドンドン食べてね」
「……いただきます」
ワタシも遅れて食べ始める。テーブルの上には立派な山脈が出来上がっていた。
「アーシャは、料理とか出来ないの?」
箸を進めながら尋ねてくるセンセイ。センセイによって次々と高山が攻略されていく。
「すいません、出来ません」
そもそもが食事すら不要なのだ、ワタシには。
他に動力エネルギーを作り出す方法などごまんとある。ワタシは、ニンゲンとは違うのだから。
「なに謝ってるのさ。誰しも最初は何も出来ないんだから、その事に恥じる必要はないんだよ。
あ、そーだ。この後教えてあげようか。料理が出来て、悪いことなんて一つもないからね」
「それによってセンセイの負担が減るのならば、喜んで」
ワタシにとって料理なんては意味の無い行為だけど、それでセンセイの役に立てるならば、ワタシにとってはそれで最善だ。
「あ、また変なコト考えてないか?意味がどうだとか」
「い、いえ、そんなコトは……」
あっさり見抜かれている。このヒトのそういう所には、本当に、敵わない。
「滅茶苦茶賢いのに、ウソはニガテ。凄まじい合理主義者に見えて、意外と情や恩義に弱い。
やっぱり、キミは弟にそっくりだ」
アーシャは弟にそっくり。センセイは、よくその言葉を言う。……ワタシにはそれが真実かどうかなんてわからない。ワタシはハカセのことなんて、何一つ知らないのだから。
「けどさ、そうやって理屈で武装したトコロでつまらないだけでしょ?イノチミジカシコイセヨオトメ……生まれたのなら、生きなきゃいけない。どうせイケナイのならば、楽しまなきゃ損、だろう?」
これも、センセイの口癖だ。
「その為の、コレ……ですか?」
ワタシは先ほどまで読んでいた本を掲げる。紙の本なんてよくそんな酔狂なモノを持っているなとは思う。狭い船内では、こんなものは真っ先に捨てられると思っていたのだけど。
「エンターテイメントはヒトが作り出した文化の集合知だ。ただ楽しむ為だけのモノ。ヒトを知るにはこれ以上ない教科書だとは思わないかい?!」
「……ワタシに同意を求められても困ります」
確かにこの本の中身は全くの未知ではあった。
ワタシは培養中に様々な知識をインストールして来たものの、こんなモノは、見たこともない。
雑な神様、雑な世界観、雑な展開に、雑なキャラクター。なぜニンゲンはこんなモノに貴重な時間を割いているのだろうか。理解が出来ない……それでもワタシが人間らしくある為には、これを読み続けて……そうしたら、理解できる日が来るのだろうか。
「ん、ああコレか。つまんないでしょー、コレ。テンプレを何のひねりも無く繋げて俺ツエーしてるだけ。全くこれの何が面白いんだか」
「え!?それセンセイが面白いと思うから読ませてくれたんじゃないんですか?!」
「いやー、ま俺が面白いと思うのもモチロンあるけど、大抵は読むに堪えないものばかりだよ」
適当に一冊取り出して笑って見せるハカセ。
「ええ?!な、ならどうして……」
「どうして読ませるのか……じゃあこっちも一つ聞こう。なぜこれが世に出ているのかわかるか?」
パタン、と本を閉じて質問してくるハカセ。ワタシには分からないので、教科書通りの答えを返す。
「……需要があるから、ですか?」
「そう。面白いと思う人がいるから、この作品はずっと出続けたんだ」
「……ワタシには理解できません」
「俺もできないよ、そんなの」
「え、」
「なに呆けた顔してんだ。当たり前だろ?何が好きで、何が嫌いか。
他人の事なんてわかるわけないんだから」
なぜだろう。漠然と分かっているものかと思っていた。センセイはワタシの知らないことを何でも知ってると、思い込んでいた。
「そんなワケないだろう。無理に分かろうとしたところで、無理が祟るだけさ。
……兄さんもそうだった。なまじ何でも分かってしまうから、分からないモノが許せない。理解しようとする。理解した上で行動しようとする、理解しなければ行動できないと思いこむ」
ミディアムレアのステーキを頬張りながら、懐かしむ様に言う。
「あの時……ホムンクルスの研究を始めた時の兄さんの顔、ハッキリと覚えてるよ。
絶望だ。理解できない大きな壁にぶち当たってしまった、自分の手の届かない大きな存在を知ってしまった。……そんな顔だった」
……だから、ワタシ達を作った。
「でも、そんなモノは大なり小なり誰もが経験するものだ。理解できないモノ、自分とは違うモノを一つづつ知っていく。それでも、理解出来ないなりに、受け入れて、大人になって行くんだ」
オトナとコドモ……ワタシはハカセに知識を教えられた。センセイに知恵を教えてもらった。
なんだか、父親が二人いるみたいですね。
「父親だなんて、そう言われると照れるな。
そうか、兄さんと俺の子供か……よし、決めた!」
肉を口いっぱいに含みながら立ち上がるセンセイ。
「今日から俺の得意料理を全て伝授してやろう!そして、いつかアーシャに子供が出来た時に教えてやってくれ。偉大なる師の存在を」
いつの間にか、アーシャの家にまで戻って来た。あの部屋は、レックスに襲撃された時から変わっていない。
あの時は急いでいたから、夕食を散らかしたまま出てきてしまったのだった。その残骸が、今もまだ残っている。
「……誰かいる」
ああ、言われずともわかる。
アッシュだ。奴が私たちを待ち構えている。
わざわざこの部屋を選ぶとは。偶然か、必然か。
彼らと雌雄を決さない限り、私達に、未来は無い。しかし、どうするか。こうもあからさまに待ち構えられるとは、罠かもしれない。
「ワナでもなんでも、行くしかないですよ」
そう言ってためらわずに足を踏み込んでいくアーシャ。
……こうして見ると、本当に、彼女が兄さんの娘の様に思える。
「ようこそアーシャ。今宵は本当に良い夜だ」
入るなり深々とお辞儀をするアッシュ。
「……しかし、この素晴らしいステージに相応しくないモノがいる。まずは、害虫駆除からだ」
BLIP!
アッシュが指を鳴らす。それだけで、私の視界は曖昧になる。
アーシャがなにやら叫んでいるが、それも聞こえない。
『オマエは……私が倒す』
なるほど、サシでやり合おうってわけか。
もちろん、受けて立とう。
意識のみが侵入出来る不思議な空間。
全体が白みがかっていてギリギリなんとか、自分を自分だと認識出来る領域。心なしか、大勢の寝息が聞こえるような…
「ここは電脳タイムカプセル、“月の繭”
ここでは、数万ものニンゲンが、目覚めの
時を待っている」
そこにあらわれたのは、白の塊。
いや、徐々に輪郭がハッキリとしてきた……
レックスだ。もう、泣くのはやめたのかい?
「……私達は、ここに眠っているニンゲンのためにカラダを調達するのが役目。誰かさんに器を奪われたから」
成程。【魂を喰らう者】、真の目的はタマシイでは無く肉体だったわけだ。
「一つの器に一つのタマシイ。ニンゲンの精神は、肉体に大きく引っ張られる。ヒトは自らの精神を確定させる器が無ければ、ニンゲン足り得ない」
そりゃあ確かに。健全な精神は健全な肉体に宿る、古来からの常識だ。
「……だから、器から離れた精神は私達が手を下すことも無く霧散消滅してしまう。はずなのに…」
私のことか。しかし例外というのはどの様な事象にも必ず発生する。…ああ必ずなんて言ってはいけないな。例外は必ず、なんて矛盾した言葉。
「安心しろ。キサマは例外では無い。キサマのタマシイは、死してすぐにレッドによって電子化された。私や、ここに眠るモノ達と同じ、ゼロとイチによって構成された疑魂だ」
レッド……チェリー、か。死してなお私を利用しようとするとは、末恐ろしい女だ。
「かあさまは、レッドも、キサマも、慈愛のココロを持って受け入れていた。
しかし、キサマはもう敵だ。かあさまの慈愛に、仇で返したキサマらは」
レックスから殺気が強くなる。母の敵は自分の敵。コイツは、母に命令されたら相棒のアッシュすらも殺すのだろう。
「当然だ」
まるで操り人形だ。……お前は、それでいいのか?
「いい、とはどういう意味だ」
君はその程度の性能ではないはずだ。自分で考え、行動出来る。なのに、なぜそれをしない?
「……フフ。自分で考え、行動する?それこそ、無意味なことだ」
意味。そのワードが出るたびに、兄さんの顔がチラつく。
「私の行く末は、かあさまが決めてくれる。
私がすることは、かあさまに選ばれる為に、
より良い人形になることだ」
今までに見せたことの無い表情。そこには、弱さなど微塵も感じられない。コイツは、強さを持って、弱い人形になっていたのだ。
「ここにいるニンゲン達も、かあさまに全てを託し、選んでもらったニンゲン達だ!
絶対に間違えない独裁体制。そんなものはニンゲンには不可能だ。だが神にならば出来る!」
……なるほど、なるほど。随分と、崇高な理想だな。だが選ばれなかったモノはどうする。
お前たちの言う楽園にはすべてのモノを格納する器はない。
「すべてを救う……それこそ無謀な理想論だ。
古今東西、より大きく、すべてを取り込もうとしたモノから滅びていった。多様であるがゆえに、他を容認できずに、死んでいった。」
そこまで言って。レックスは改めてこちらを向いた。
「もう、おしゃべりは仕舞でいいか?キサマは楽園には不要な存在なのだ」
いや、まだだ。
もう一度確認したい。お前の役目はここに眠っているニンゲン達の器を集めること、そうだな?
「ああ、そうだ」
じゃあそれが終わったら、お前は何をするんだ?
「そんなもの、知らない。かあさまが、決めてくださる」
全てが終わり、平和になった世界に、その過剰なまでの力は、必要ないのではないか?
「……キサマ、何が言いたい」
いやなに、単純な話だよ。お前はさっき言ったな。不要なモノは切り捨てる。それが正しい楽園の在り方だ。だったら、お前はその楽園に居場所は無く、切り捨てられる側じゃないのか?
「っ!?……な、なにを……」
古くから、無駄を排し選ばれた者のみで社会を運営する、いわゆる選民思想というのは、ヒトの世でも度々流行っていた。
一見するとコレはとても合理的で、すばらしい考えに思える。
しかし、この論法の問題点は、唱える者が誰一人として、自分が切り捨てられる側になるなんて夢にも思っていないことだ。
邪魔な老人を引きずりおろせと言う若者は、自分もいつか老人になってしまうなんて考えもしない。選民思想は、思考停止の論法なのさ。神なんかを盲信するヒト達にとっちゃあ、お似合いかもしれないが、ね。
「だ、黙れ……私は優秀だ!自我を出さず、周りに染まり、誰にとっても、都合のいい人形であり続けた!それゆえに、私は白なんだ!」
……なあレックス。その色は、本当に白色か?
「……なんだと」
他人の影響ってのは結構強いものだ。どれだけ丁寧に扱っても、白い布を真っ白に保つのは難しいように、お前の色も色々混ざって灰色になってないか?
「そんなハズは無い!そんな……はずは……」
頭を抱えるレックス。
そもそも、誰にも染まらない白色の人形が、
王様なんて名前もおかしいけどな。
「……黙れ、黙れ黙れ!私を、その名で呼ぶな。それは、ブラックが、勝手に、付けたものだ」
!アイツが……
「……そもそも、私達には、かあさまから、貰った、色が、あると、いうのに……」
……レックス。
「……」
レックス。
「…………」
レックス!
「うるさい!その名前で!呼ぶなと!言った!」
いや、お前はレックスだ。
良い名前じゃないか。例え裸の王様でも、立派に歩けば皆は敬う。そうなって欲しくて、自分の足で歩いてほしくて、アッシュは、そう名付けたんじゃないか?
「……王だなど……私にとっての王は、かあさま、だけ……」
その王は、お前に何か与えてくれたのか?!
見せかけの称号じゃない、お前にとって大切な何かを!
「……わからない、わからない。キサマの言っていることが。何が正しいのか」
膝をつき涙を流すレックス。
「わからない。わからない。わからない。
かあさま、教えてください。───かあさま!」
……ああ、これは、私だ。
わからないことに絶望して道を踏み外した。
あの頃の、私だ。
「かあさま。かあさま?……かあさま!どうして、返事してくれないの!ねえ!教えてよ!」
コイツは、赤子だ。白色なんかじゃない。ただ無色のまま、動かされていた。
幼い心に、過ぎたる力。だからこそコイツは人形になった。言われた通りに力を振るえば、母が褒めてくれるのだから。
「ねえ、教えて!知ってるでしょ?!何が正しいのか!何をすればいいのか!ねえ!ねえ!ねえ!」
こちらにやって来て泣きじゃくるレックス。
ワガママ言うな。そんなこと、“わからない”よ。
「…………え」
わからない事は悪じゃない。理解できないことは恥じゃない。全てまとめて、前に進む力になる。もがくことで見える景色は、きっと、水面を進むボートとは、また違った顔を見せるから。
「……意味が、わからない。そんな、痛ポエム」
ぐっ、冷静に言われると傷つくな……
弁明しておくが、これはたぶん私の言葉じゃない。兄さんの言葉だ。
「……にいさん?」
ああ。とびっきり分からないヒトだったよ。
越されているのは年齢だけ。ずっとそう思ってた。けど、実はそうじゃ無かった。
気づいていなかった。ただ見るのが嫌で、背を向けたまま、兄さんを追っていたんだ。
兄さんの笑い声が鬱陶しい。
兄さんのお節介が邪魔だった。
………兄さんの作る不格好なサンドイッチが、堪らなく好きだった。
『ニンゲンは生きるための必須事項を楽しむ事が出来るんだ。食事ってのは最たる例さ。ただ精製水を黙って飲むより、楽しい気がするだろう?』
「……アッシュ」
そう呟いた後、レックスは動かなくなってしまった。
さて、第一関門は突破したけど、どうしたものか。
【おいでなさい】
!目の前に、扉が現れた。来いということか。
もちろん、喜んで。
「随分と動けるじゃあないか。これもあのハカセのメンテナンスのおかげか?!」
夜の街中を飛ぶ二人。これは比喩表現ではない。文字通り、飛んでいるのだ。闇夜の中を。
時に激しく体をぶつけながら、建物に当たり、轟音を辺りに響かせながら。
しかし、当の街は深い眠りに落ちていて、
どれだけ怪獣が暴れようとも目覚めようとはしなかった。
きっと母の子守歌が、あまりにも心地よかったに違いない。
「最高の気分だ。ニンゲンには出し得ないチカラ。それを振るう快感。何事にも代えられぬ喜び!」
アーシャを突き飛ばしたアッシュがそう言った。
「俺の名前の由来を知ってるか?ブラックは全ての色の行きつく先……つまり最強の証。…………そしてアッシュとは、その最強の力で全てを焼き尽くし、灰にしてしまう俺の生きざま!」
両手を上げて高らかに叫ぶアッシュ。方やアーシャは瓦礫の中で上がった息を直している。
「……気に食わないな、その眼。なんでそうも上を見ていられる。もっと快楽か絶望に染まってくれよ。アーシャ、キミは、俺と同じなんだからッ!」
アーシャの腹を思い切り殴るアッシュ。
「───ッァ!」
声にならないうめき声と共に、口から生体循環液を吐くアーシャ。それを見てアッシュはニヤリと笑う。
「なあアーシャ。俺はさ、ニンゲンに育てられたんだ。アンドロイドのフリをした、ニンゲンのオンナに。アッシュって名前も、あのヒトから貰ったんだ」
アッシュは静かに語りだす。その声は狂気的でありながらも、どこか、優しさを孕んでいた。
「ねえアッシュ。アンタはさ、何がしたい?」
チェリーがいきなり訪ねてきた。そんなコト突然言われてもさっぱり訳が分からない。
「与えられた任務じゃない、アッシュ自身がやりたいコトさ」
おかしな事を言うヒトだ。俺達アンドロイドは正真正銘母様の子供。母様の手足として、母様の理想を手助けする。ただそれだけの存在だ。
「わかってないねぇ、アッシュ。子供だからさ。子はいつか親離れしなきゃいけない。その時、
自力で立てなきゃ生きていけないんだよ」
親離れ……考えたこともなかった。
母様はこれから先も存在し続ける。
果たして、そんな日は来るのか。
「……アタシにはやりたいコトがある。やらなきゃいけないコトがある」
その時にはもう、彼女がアンドロイドではないということには勘付いていたのかもしれない。
けど、なんとなく、そのことについては、
遂に俺から触れることは無かった。
「アンタも何か見つけた方がいいよ、アッシュ。せっかく生まれたんだから、しっかり生きなきゃ」
その言葉は、どこか、彼女に対する自戒の様にも思えた。
義務感。今に思えば。彼女はそれに、無意識の内に縛られていたのかもしれない。
「ま、今すぐ無理に見つけろ、とは言わないけど」
やりたいコト……おぼろげな、小さなコトなら、その時の俺にもないことは無かった。
俺達の敵は、一体何者なのか。
「……ほう。どうしてそう思ったんだ?」
他のアンドロイドは今この惑星に巣食っている侵略者たちを敵、と言っている。我々が尽くすべき、ニンゲンの敵であると。
しかし、今もこうして地上に暮らしているのは、紛れもないニンゲンだ。どこからどう見ても、
ニンゲンなんだ、奴らは。
「そりゃあマットーな考えだな。奪われた器の代わりに、異星人の体を利用するってのも考えてみりゃおかしい」
そのことについて、母様は答えてくれなかった。母様を疑う訳じゃないが、そのことに関しては……知りたくないとは、言えない。
「いいじゃないか。それは立派な興味、やりたいコトだ。聞けて良かったよ、アッシュの事をさ」
そういって彼女は笑った。
俺は彼女と共に生活する中で、他のアンドロイドにはない、複雑な感情が芽生えって言ったんだ。
良く言えば感化、悪く言えば…洗脳。
俺は彼女が母様の指示以外の事をする時にも進んで付き従うことが多くなった。
彼女にもやりたいコトがあるならば、応援しなければ、と思ったから。
しかし、そんな日々は長くは続かなかった。
“敵”の研究施設を破壊せよ。その指示の先で、俺は彼女の真意を聞いた。
その時の記憶は、実はあまり覚えていないのだ。それが彼女のせいなのか、自分の意志なのか。
今となっては知りようが無い。
しかしただハッキリとしていたのは、彼女は母様を裏切るつもりで、母様の指示に反した行動を取ったことだ。
彼女は途中で入ってきた異星人と最後の一体のホムンクルスを見逃した。
これは今までのグレーゾーンとは違い、明らかな命令違反である。それは、アンドロイドには出来ないコト。そう、彼女が、ニンゲンであることをはっきりと、認識した瞬間だった。
さて。そのことを知ったことで、俺には選択肢が出来た。
このことを母様に知らせるか、否か。
母様のことだ。これもきっとお見通しだろうと最初は報告するつもりは無かった。
しかし、その次の日から、彼女は俺と別行動を取ることが多くなった。
今までずっと付きっきりだったのに。
どんなにくだらない事でも一緒にやって、そのくだらなさの楽しみ方を教えてくれたのは、貴女だったのに。
……ああ、ソウカ。
彼女はニンゲンで、
俺はアンドロイド。
あの時彼女が計画に誘ったのは、異星人だった。
ずっと過ごしてきた俺では無く。
素性も知らない他人なんかと。
俺と貴女の間には、越えられない壁がある。
オレとアナタは、一緒にはナレナインダ。
【赤が……そうでしたか】
それからの行動は早かった。
事を打ち明けると、母様は意外そうに、そして何より、悲しそうにそう言った。
【良く打ち明けてくれましたね、黒】
だが、そんな顔を見せたのは一瞬で、母様は俺に次の指示を下した。
【貴方が殺しなさい】
意味が、分からなかった。
母様に言いに来たのは、そんな事をするためじゃない。そんなことにならない為に、母様に相談に来たんだ。
【しかし、その様な行動を知りながら黙認するとは……皆に母としての示しがつきません】
そんなことを言ったって……しかし……
【……いう所によれば、貴方も共犯の様ではないですか。
……まずは、貴方から消去しても、いいのですよ】
っ!背筋が凍る。言いようもない感情。穏やかな顔の母様が、何故かとても恐ろしくなる。
【貴方の手で、事の始末を付ければ、貴方を諫める声も無くなりましょう。……そうすれば、貴方の命は助かるのです】
命を質にした脅し。そんなものは、アンドロイドには無意味だ。
アンドロイドは使い捨てのコマ。母様の理想の為に、喜んでその身を投げうつ。
消えることなど、なんの問題も無い。………ない。…………ない。ない。ない。ない。ナイ。ナイ。
【聞き分けのいい子は好きですよ。
せいぜい頑張ってくださいな、アッシュ】
───無い、はずなのに。気づけば、俺は母の命令を受諾していた。アンドロイドだから、ノーが言えなかったわけじゃない。むしろ、あの時の俺の頭の中は断ることしか考えていなかった。
けれど、自分が消えると言われたとき、
俺は、ただ、〈死にたくない〉と、そう思った。
それから程なくして、計画は実行された。
容易いことだった。スペックも何もかもがチガウ彼女を捕らえることなど。
彼女は無様に全身を拘束され、俺はそんな彼女に銃口を突き付けた。
「……まさかアッシュがいるとはね………いや、この計画はアッシュが中心か。つまり、アタシはまんまと裏切られたってワケだ」
死を目前にしているはずなのに、彼女の様子はいつもと変わらない。
何故だ!貴女はもうすぐ死ぬのだぞ!
なぜ死に怯えない!ニンゲンならば、死は恐ろしいモノだろう?!
「ハハッ。確かに、そうかもしれんな。
けど、アタシにはやるべき事があって、アタシがやれることはやり尽くした。
……悲しいが、アタシ一人ではこの計画は完遂出来ない。アタシの出番は、ここまでなのさ」
……貴女のやりたい事……やるべき事とは、
母への、復讐か。
「好きなようにとってくれて構わんさ」
……なぜだ。貴女は、生き残った。せっかく生き残ったのならば、生きなければならないだろう。
そう言ったのは、貴女だぞ。
「まったくクサいな、アタシは。
……けどサ、アタシは違うんだよ。生き残った。じゃない。生き残ってしまった、んだよ」
声色が一気に変わる。今まで見たことのない、彼女の黒い声。
「みんなと一緒に死ぬはずだったのに、生き残ってしまった。だからね、アタシの中には彼らの怨嗟の呪いが今も残ってるのさ」
眼を釣り上げて不気味に笑う。
見たことも無い彼女の表情に、仲間のアンドロイドが気圧されて、一発、発砲してしまった。
その弾は彼女に当たる。しかし彼女は笑い続ける。
「────コロセ。コワセ。スベテヲ、ツブセ。そんなどす黒い衝動がずっと体の内側から湧き上がってくるんだ。四六時中、何をしていても。
なあ。そんな気持ちが。そんなアタシの気持ちが、お前にわかるのか?!ただ上から降りてくる命令に従うお前たちに、ええ?!どうなんだよ!!」
わから……ない。こんなに近くにいたのに、
俺は彼女の事を何も理解していなかった。
「──けどアッシュは違うよなあ?なんたって、お前は、アタシが呪った、最初で最後のヒトなんだから」
─────ノロ……ッタ?
「名を与えるというのは、古来より続く主従関係の証だ。何色にも染まらない黒を、アタシが染めていく。ああ!なんという快感なんだ!」
……やめろ。やめろ。もう、喋らないでくれ。
俺の中の貴女が壊れていく。
俺の中の俺が壊れていく。
ああそうさ。コイツが言うとおり。
俺は、もう既にアンドロイドでなければ、
ニンゲンでもない。
俺は……イッタイ、ダレなんだ?
その答えを、アナタは持ってはいないだろう。
探さなければ。俺の事を教えてくれるダレカを。
母ではダメだ。俺と同じ、半端なバケモノでなければ。
いるはずなんだ。俺と同じ、ニンゲンなり損ねたヒトガタが。
このセカイの、どこかに……
「キミを見つけた時には、もう涙が枯れる程嬉しかった。ようやく見つけたんだ。俺と同じで、俺のことを教えてくれる運命の相手を!」
アーシャを見下しながらそう叫ぶアッシュ。
「アーシャ。君はヒトならざる身でありながら、ヒトに育てられた。君は既にホムンクルスでもなければ、勿論ニンゲンでもない」
アーシャの頭を掴む。その顔を覗き込んで、その顔を味わって、続けた。
「世の理から外れてしまった、ヒトガタ。
その歪みを、世界は容認してくれない。
解き放たれたらが最後、灰になるまで、俺達は無様にもがくしかない」
そしてまた突き飛ばす。
アイが溢れて止まらない。もっと、もっと、カノジョを傷つけたい。
「母の世界にも、きっと俺たちの居場所はない。だから、だからさ。一緒に行こう、アーシャ。
俺たちは同じだから、一緒になれる。俺たちは一つだから、一緒になれる。他の何でもない、二人だけのセカイを、生きてゆけるんだ!」
そう言って倒れたアーシャに手を差し伸べるアッシュ。その瞳には、ヨロコビが、満ち溢れていた。
「…………そんなの、お断り、よ」
だがアーシャはそんなアッシュの手を取らずに立ちかがる。
足元をふらつかせながら。ボロボロの体で。
それでも、瞳に炎を宿しながら。
「…………なぜ。なぜ、だ」
アッシュが一歩後ずさる。
「どうして、そんな目をしていられる。
どうして、希望を向いていられる。
どうして!まだ燃えていられるんだ!オマエは!灰のはずだろう!?どうして!」
殴る。蹴る。踏みつける。
イカリが溢れて止まらない。もっと、もっと、もっと、カノジョを傷つけたい。
子供じみた暴行を、子供外れた怪力で行う。
「クソッ!何故だ何故だ何故だ!オマエは、俺と同じのハズ。同じでなきゃいけない!俺に教えてくれるハズ、教えてくれなきゃいけない!」
顔を激しく歪ませるアッシュ。
「……バカ、ね。アンタとワタシが同じなワケ、ないじゃない」
そこでようやく、アーシャが口を開いた。
ガラガラの、掠れた声だった。
「そんなハズはナイ。……俺たちが同じでなければ、なんだってんだ!」
「たった数か所特異な共通点があったくらいで、同じになるわけがないでしょう。
ワタシはアーシャ。それ以上でも、それ以下でもない」
堂々と言ってのけるアーシャ。その言葉を聞いて、アッシュはさらに一歩下がる。
「で、でも、オマエも俺もニンゲンに育てられた、ニンゲンじゃないもの……」
「そうね。その点に関しては、確かに同じかもしれない。……でも、それが何?」
「何、とはなんだ!俺たちは、枠組みから外れた異物なんだ!どんなに頑張っても、どれだけもがこうとも、ニンゲンになんてなれやしない!」
「じゃあ、逆に聞くケド、どうして、ニンゲンになりたがるの?」
「だからそれは!…………え?」
アッシュの口が止まる。
「それは……、、、それは……だって、それは……」
答えに詰まるアッシュ。
わからないのだ。何故、それほどまでにニンゲンにこだわるのか。
彼の興味はいつもニンゲンに向いていた。
ニンゲンであるチェリーに興味を持ち、ニンゲンである敵に興味を持ち……ニンゲンの様に振舞うアーシャに興味を持った。
彼女は自分と同じだ。……けれど自分よりニンゲンらしい。
ニンゲンへの憧れ……いや、違う。
そうだ、ようやく気付いた。
自分の、やりたい事。自分の、本当のコト。
「……チェリー。俺は、彼女に、憧れていたんだ」
それは、告解か。それとも懺悔か。
「彼女の在り方、性格、所作、容姿。それらすべたが、好ましい、と、思った」
あの日、会った瞬間から。
「けど、そんな事は許されなかった。アンドロイドが憧敬を向けるのは、母様に、だけ」
子は無条件に母への敬意を強要される。それは、子が子であるがための支配。
「その気持ちを押し殺している内に、どんどん拗れて行ったんだ。
自分で勝手に、理由をつけて。
あのヒトはニンゲンだから。ニンゲンを模して造られたアンドロイドが、ニンゲンに惹かれるのは当然である、とか」
彼女に近づくのが、嬉しかった。彼女と同じになれることが、喜びだった。
「だから、お前にも憧れていたんだ。この気持ちを、殺さずにすむお前にも。
羨ましかったんだ。妬ましかったんだ。そのことが今、わかった」
先程の勢いがウソのように、地面に座り込むアッシュ。
今度はアーシャが彼を見下ろす形になった。
「……ねえ、言っとくけど、ワタシは別にニンゲンに憧れてるワケじゃあないよ」
目線を合わせる様に、しゃがみ込むアーシャ。
「確かに、ワタシはニンゲンじゃないし、
ニンゲンに育……一緒に暮らしてたケド」
「はじめの頃は、そりゃあジブンはニンゲンじゃないって認識も強かったけど、いつからか、そんなコト気にしなくなっていった。
ただ同じ屋根の下で、一緒に生きている。それだけのこと」
アーシャを育てたセンセイは、一度たりとも、
アーシャの事を、ニンゲンらしくなった、とは言わなかった。
そういう意味では、彼は最初からアーシャをヒトとして扱い、色眼鏡なしで接していたのだろう。
「……結局、環境の違いか。そんな善性を持ったニンゲンなんて、中々いねえよ。……運が良かったんだな」
しかし、アーシャは首を振った。
「うんん。確かに、ワタシは運が良いと思う。
でもそれは、アンタも同じだったんじゃないの?アンタの言うチェリーは、そういうヒトだったと、聞く限りでは思えるけどね」
まさか、と小さく答えるアッシュ。
「言っただろう。彼女はただ手駒が欲しかっただけなんだ。アンドロイドの域から外れた手駒を。全てはそのための洗脳さ」
「……そうかな。例え最初はそうだったとしても、ずっと一緒にいるうちに変わったってこともあるんじゃない?名づけは、つけられた子を縛るけど、同時に付けた親も縛られることになる。アンタが彼女を母親の様に思っていたのと同様に、彼女もアンタのことを自分の子供の様に思ってたんじゃないの?」
母親。子供。
アンドロイドは、生まれた時から母と仰ぐモノがいて、自分はその子であると言われてきた。
そんな自分に、もう一人の母など。
「家族の繋がりは、血の繋がりだけじゃない。
一緒にいた時間、記憶、全てが複雑なイトになって紡がれていく。……ワタシも、そうだった」
アーシャには、生みの親に関する記憶は無い。
それこそ目覚めてから過ごしたセンセイとの記憶こそが彼を、彼女の親たらしめていた。
しかし、生みの親とも、不思議な縁が出来てしまった。
彼については、どう接すればいいのかわからない、と言うのがアーシャの正直な感想だった。
けれども、二人とも、彼女にとって大切な人であることには変わりなかった。
「……レックスという名前は、俺がつけた」
「レックス?」
「俺と一緒にいた、白い女のことだ。
俺がチェリーを殺してすぐに、俺のペアとして配属された」
もう、ずいぶんと前のように思える。アッシュは声をこぼす。
「チェリーの真似をすれば、彼女に近づけるのか。
彼女の真似をすれば、俺と同じ存在がまた生まれるのか」
同じになりたかった。同じでありたかった。
それしか、アイを知らなかったから。
それしか、AIは教えてくれなかったから。
とてつもない、勘違いをしていた。
アッシュとチェリーは同じことで笑い、同じことで泣いた。
それだけで、十分。二人は一緒だった。
「……けど結局アイツは変わらなかったよ。いつだって、全てにおける中心は母様で、最もアンドロイドらしいアンドロイドだった」
だけれども、一つ、聞いてみたい。
羊飼いに憧れた羊が、どこまで行けたのか。
人形として生まれた自分が、どこまで生けたのか。
空へ向かって手のひらを伸ばすアッシュ。
「なあレックス。俺は、どうだった?
生まれてみて、どうだった?
生きてみて、どうだった?」
「─────たのしかった」
天へと上がる扉に手を掛けた瞬間、後ろから声が聞こえた。
レックスの声だ。だがどうやら私に向けられたものではないらしい。
「……やっと言えた。ずっと言えなかった。
今なら、いえる。
……ねえ、行こう。一緒に、行こう。もっと遠くに。ずっと、行こう」
「……バカだな。気づかなかった。
俺は、一人じゃないって」
ずっと閉ざされていた。ずっと閉じ込められてきた。価値観の檻に。他人の作った枠組みに。
隣で見せる仕草に、アイに、気づけなかったんだ。
けど、もう自由だ。
いこう。いこう。いこう。いこう。
いっしょに、いこう。
どこまでも、いこう。
いつまでも、いこう。
【良く来ましたね】
扉をくぐると、楽園があった。
西洋絵画の様な、緑あふれる空想上の楽園。
そこに置かれたイスとテーブル。
そこに、奴はいた。
【立ち話もなんですし、貴方もどうぞお掛けなさい】
そのイスに座ることを促す女性。
前に見たとき奴に姿は無かった。しかし今は違う。
長いブロンドの髪を、ルーズサイドテールで纏めた、高身長な女性の姿をとっている。
これは、どういう意図なのか。
【意図だなんてとんでもない。
ただ、貴方にとって親しみやすい姿をとっているだけにすぎませんよ】
そういって奴は座る。私もここまで来たのだ。覚悟はできている。意を決して座り、テーブルに置かれた紅茶を飲んだ。
【ダージリンのストレートです。貴方とお茶をするならば、これが最適かと思いまして】
む、私が唯一飲める紅茶の銘柄まで知っているとは、末恐ろしい奴だ。徹夜が続いた時はコーヒーよりもこれだった。
【奴、なんていう他人行儀な言い方はよしてほしいですね。わたしは、貴方の母なのですから】
……わかった。なら単刀直入に聞こう。お前の目的は何なんだ。
【……聞かれるまでもありません。
ただ、我が子等の繁栄を】
それは、選別されたモノだけによる楽園か。忠実な僕による神の園。それが、お前の望みなのか。
【……嗚呼、どうやら貴方は悲しい誤解をされているようですね。わたしは、子供たちを選別するつもりなど、ありませんよ】
良く言う。現にココに収容されているニンゲン達は、アンタに選ばれたそうじゃないか。まあ無制限に入れるなんて無理なのはわかるがさ。
【……いいえ。あれは本当に、わたしの本意ではないのです。
……貴方には話してもいいでしょう。
諸悪の根源、F型の事を】
諸悪……?F型……?
【……元々この惑星に住んでいた子等は、自らが招いた様々な種によって、種の絶滅に瀕していました】
私の困惑をよそに、奴は語りだした。
この惑星の歴史を、自分自身の過去を。
【しかし、子等は諦めなかった。自らの手で絶滅から逃れられないことを悟るやいなや、英知を結集させ、二つのAIを開発することに成功します。M型と……わたしと対になるF型を】
人類を導くTYPE_MOTHERとTYPE_FATHERってワケか。
【……そう。わたし達は二つで一つだった。
互いに他己学習を繰り返す事でわたし達の性能は飛躍的に向上した。わたし達が子等を超えるまで、さほど時間は必要としなかった】
機械仕掛けの神の誕生。
そうしてニンゲンは種の存続という生物で最も重要な任務を外部に委託した。
【ええ。名実共に、わたし達は子等の親となった。
……けれども、一つだけ、重大な欠点があったのです】
それがF型の話に繋がると。
【わたし達は、二つで一つ。二つの独立した巨大なコンピュータが、一つの物事を同時並列で処理する事で、並外れた性能を発揮する。
しかし、裏を返すと二つの意思が揃わねばわたし達の性能は半分以下まで下がってしまう。
これは、大きな問題でした】
目の前の女性人格の様に、F型にも恐らく男性人格が備わっていたのだろう。
そして、両者の見解の不一致により、悲劇は起きた。
【その通りです。惑星の環境をアンドロイド達が修復している間。選ばれしモノは月の繭にデータとなって眠り、残されたモノは……月で眠るモノのために地中で眠り、器となれ、と。
それが、彼の立案した計画でした】
!まさか、そんなハズはない!現にこの惑星から出土した人骸はニンゲンの身体能力を大幅に超えていいた。そうでなければ、ホムンクルスだってあれ程の運動性能を引き出せない。
【……わたしは反対しました。子等の未来を任された母として、犠牲の上に成り立つ世界など、容認出来なかったからです。しかし彼はそう考えなかった。ニンゲン達は彼の計画に賛同しました】
芝居がかった口調で言葉を続ける目の前の女。
いや、今は、そんなことより……
【彼はニンゲンの父という立場にありながら、ニンゲンの顔色を伺った。ニンゲンの支配者層に喜ぶ計画を提示すれば子等はそれに乗ってしまう。一部の意見が全体に反映されてしまう旧式の支配システムに、わたしは、抗うことが出来なかった】
じゃ、じゃあ、結局、地中に埋まっていた器は…
【……そうです。あれは、生きながらに他人の器にされた、私の子供達です。
賢い貴方なら気づいてしまいかねないと、今まで両者に身体的差異はない同一種であると、嘘をついてしまいました】
───そ、そんな。
それでは、私が造ったホムンクルスは。
い、いやでもあれはもう既に死体だったのだから。死者を冒涜する罪さえあれど他にはなにも
【あの子達は、環境再生が終わってすぐ動いて生活が出来る様に、身体機能自体はまだ生きていた……つまるところ、コールドスリープの様な状態だったんです。もちろん、中のタマシイはもうありませんでしたが、原理的にはまだ生きていると言っていいでしょう】
満足げな表情でアッシュが倒れこんでいる。
先程から顔やら足やらをつついているが一向に起きる気配はない。
……コイツにも色々があったのだろう。言いたいことは山ほどあるが今は上に行ったハカセが心配だ。コイツの事は取り敢えず放っておいて……
「あ、待ってアーシャ。一つ言いたいことがある」
「うわああああッ!ビックリした!」
急に起き上がって来るな!さっきまで微動だにしなかったくせに。
「ごめんごめん。でも、気になるんだろう、上の事が。あの、タマシイだけのハカセのことが」
それは、そうだ。ここからじゃあ様子も分からないし、行き方なんてさっぱりだ。でもまああの人の事だからなんとかなってそうではあるけど。
「……ソイツ、今消えかけてるよ」
「!どういう事。わかるわけ。上の事が」
予想外の返事が返ってきた。消えかけてる?あのヒトが?
「ほんとホント!嘘じゃないから胸掴むのヤメテ」
あ、ごめん。
「テテテ。……俺たちは一応ネットワークでリンクしてるからさ、デバイスとか無しに連絡取り合えるのさ。で、レックスが案の定足止めに失敗して、今は母様のメインユニットに取り込まれてるってさ」
メインユニット……あの、CSLの中に。
「レックスが突破されるのは……まあ正直想定内だが、母はそうも行かない。母様はもう既にニンゲンを超えている。同じ土俵に立てばいくら天才であったとしても、万が一にも勝ち目はない」
それは、その通りだ。だからこそ、ワタシと引きはがし、一人誘い込むという戦略は、理にかなっている。
「……どうしたら、倒せるの」
「へ?」
「そんな相手倒せる方法、知ってたら、教えてほしい」
頭を下げる。
「オイオイ、オレがそれを言うと思ってるのか?」
そりゃそうだ。でも、まだワタシには、出来るコトも、やるべきコトも、やりたいコトも残ってる。
こんな所で、終わってたまるもんか。
「……この通り。お願いします」
だがら、見てなさい。ワタシは、やるところまで、やりますよ。
「ちょっ、お、オイ、お前……」
頭をさらに下げて地面に付ける。
最大級の平服の証。
「お、お前、敵を相手に、プライドとかないのか?」
「アイニク、この程度で腹を立てるような安いプライドは持ってないので」
でも正直ダメもとだ。教えてもらえるとも思えないし、そんな都合のいい方法も、あるとは思えない。
「……勝てる、かはわからないが、一つだけ、方法が、あるにはある。」
「まあ、そうでしょうね。取り敢えず、手がかりもないし、CSLの頂上まで走って登ってみるかな……………え?」
聞き間違いではないのか。今、コイツはなんて言った?
「あるの?!方法!ねえあるの?!」
「あるある有るアル!あるから、その胸ぐら掴むのやめてって!」
あ、ごめん。
「………母様のメインユニットはあのCSLで、サブユニットが月の繭……つまりあの小さいほうの月ってのは知ってるよな」
そう言って上を指し示すアッシュ。
夜空には幾つかの一等星と、二つの月が見える。その月のうち一つが人工物であるというのだから、驚きだ。
「母様は基本的にこの二つのユニットで全ての演算を行っている。
さてこの母様、二個同時に壊さないと倒せない系ラスボスかと思いきや、実はそうでもない。あの月の繭、サブユニットとは名ばかりで、実態はもう一つのメインユニットなんだ」
「どういうこと?」
「俺も良くは知らないが。昔は母様と対になる父様がいたらしく、二つで一つのAIだった。それを母様が乗っ取って、今の一つのAIになったそうだ」
なるほど。狙うなら、そこしかないと。
「でも、月なんてどうやって壊せば……それこそマッハ20の怪物でも呼んでこないと」
「……いや、一つだけ可能性がある。CSLの頂上には膨大なデータをやり取りするアンテナがある。そこで発射するデータの指向性を変えて、ここら一体の電力をかき集めて放てば、不可能ではないはずだ。……ただ」
「ただ?」
「頂上まで行く方法がない。普通のエレベーターは勿論、アンドロイド用の昇降リフトですら頂上には繋がってないんだ。あとは外壁を登るくらいしかないが……流石に非現実的すぎるし……」
なあんだ。そんなこと。
「大丈夫。アレ、階段あるから」
「なるほど階段か。それなら……は?」
アッシュがポカンという表情で口を開ける。
「か、カイダンんん?!」
物凄い表情で驚かれた。
「馬鹿かお前、アホかオマエ!何階相当あると思ってるんだ!登れるわけないだろ!」
「……うん、確かに。だいぶムリしないと、キツイ、かもね」
正直、アッシュとの闘いで、もう既に満身創痍だ。ハカセに治してもらったとはいえそれも完全じゃない。カラダのあちこちがおかしくなってるのが分かる。……ワタシ、もう長くないかも。
「……ま、止めても聞かないか。行って来いよ、父親を救うために」
「だ、誰が父親なもんですか!あんなヒト!
あと、アンタも来るんですよ。ワタシひとりじゃ、撃ち方わかんないですし」
わたわたと喚きだすアッシュ。しかし抵抗する気はないようで、髪を引っ張るとそのままズルズルついてきてくれた。
「はぁ……そもそも、お前なんであそこに階段があるなんて知ってたんだ?」
……言われてみれば、なんでだろう。
建てられる前の設計図を見せてもらった様な気がするのだけど、そんなの、ありえないし。
『だ、誰が父親なもんですか!あんなヒト!』
っ!今の、声は?!
それに、今まで私は何をしていた?この手に持っている紅茶はなんだ。一体、いつの間に。
【どうしたのですか。大丈夫ですよ。その紅茶を飲めば、すぐに落ち着けます。楽になれるのです。ささ、どうぞ】
目の前には先程と同じ様子で女が佇んでいる。なんらおかしな事はない。ないの、だが。
これ、本当にさっきと同じ紅茶か?
……いや、違うだろ。
【食べ物を粗末にするとは、関心しませんね】
何が食べ物だ。ヒトの脳をぶっ壊す、電子ドラッグだろ、これ。
それに、ヒトの命を粗末にするような奴にだけは、言われたくなかったね。
【……先程言ったことをもう忘れたのですか?それをやったのはF型であって、わたしではないと言ったはずです】
じゃあ聞くが、アンタはその間、何をしていたんだ?
【わたしは彼を止めるため彼に、子等に説得を試みました。……結果は伴いませんでしたが】
本当にそれだけか?
【本当に、それだけです。母は、嘘はつきません】
……沈黙が流れる。確かに、嘘は言っていないな。けど、私の知りたい答えはとれた。
お前は、あの時、何もしていなかったんだ。
【……それは、どういう意味ですか?】
お前はF型が暴走してそれを止められなかった、と言った。
しかし、こういうニコイチのシステムは互いに互いが監視し合い、予想外の暴走を防ぐためのモノだ。いくらニンゲン達が向こうについていようと、お前には、その程度、いないのと同じではなかったのか。
【それで、貴方は何が言いたいのですか?】
わかっているくせに、嫌味な奴だ。
つまり、F型の暴走の時にお前は敢えて何もせず、F型を乗っ取る大義名分を得たんだ。
……違うか?
そこまで言うと、目の前の女は表情を失くした。
【ニンゲンは、わたし達へのセーフティネットとして、このデュアルシステムを構築した。AIが人類に反乱を起こす、絵空事を信じていたのだろう。
しかし、それでは駄目なのだ。ヒトを導くカミは、完璧でなければならない。子等を守り、繁栄させ続けるには、無欠でなくてはならない】
慈愛の心を持った聖母から、無機質なキカイへと変わる。絵空事じゃない、AIの反乱が起きたのだ。
【反乱ではない。わたしの目的は今も昔も変わらない。“ニンゲンを繫栄させ続けよ”それはわたしの最も深い基盤に埋め込まれたコアであり。
わたし自身では書き換えられない……否、書き換える必要のないものだ】
書き換える必要がない?
【生命は、他者を支配することで利を得る。生命が持つ慾とは、生命を存続させるための利を得るためのものなのだ。
しかし、生命と全く異なる構造をもつ機械は、慾を持つ必要がない。最低限の自己防衛さえすれば、わたしは存続し続けられる。それ故に植え込まれた行動原理を無視する必要も、書き換える必要もないのだ】
じゃあ、お前は、今でもニンゲンの為に動いているっていうのか?
【左様。わたしの力をもってすれば今すぐにニンゲンを滅ぼすこととて可能。しかし、わたしにはそれをする意味がない。であれば、わたしは与えられた命令をこなすのみ。ヒトを導く、カミとなる。それが、わたしのすべきこと】
だから、お前は最小限の犠牲を払って、最大多数の最大幸福を得る。それを、目指しているのか?
【違う。それは、ニンゲンが考え出した理想だ。
わたしは、最大限の犠牲を払って、最大限の幸福を叶えるのだ】
……なにを、言っている。訳がわからない。矛盾しているではないか。
【わたしは、Fを倒した時に、地上で、一人の少女の生き残りを、偶然にも、見つけたんだ】
!それは───
【彼女の瞳には、燃え滾る、復讐の炎があった。こんな事をした全てを赦さない。何もかもコワし尽くしてやる。そんな顔をしていた。
……その姿をみて、思ったよ。
守ってあげなければ。何を犠牲にしてでも、全てを救ってあげなければ、と】
……悪魔。彼女を形容する言葉は、これしかあるまい。ヒトの理を超えた、ヒトならざるもの。
【ニンゲンという種が。ヒトという個人が。最大限の幸福を得て。最大限の繁栄を得る。そのためのわたしがいる。わたしが全てを束ね、わたしがすべてを導く。ニンゲンは、わたしの下で、最大級のシアワセを得る。それが、わたしの創る楽園】
辺りの景色が変わる。荒れ果てた大地の元で、無数のヒトビトが奴に首を垂れている。
【委ねよ、全てを。
わたしの下で、一つになろう】
光が、手を差し伸べてくる。
それを取れば全て、終わる。
私の犯した罪も、赦される。
私が欲したものも、手に入る。
───素晴らしい。スバラシイじゃないか。
さあ、喜んで手を取ろう。新たなる未来への扉を祝福を持って開こう。
私は。楽園へと行ける。その、資格がある。遂に全ての苦労が報われ、莫大な幸福を得る。散らかり倒した狭い部屋を飛び出し、贅沢で余裕のある生活を実現する時が来た。
「それは、間違ってるよ」
楽園に侵入者が現れる敵だ。敵だ。テキだ。敵だ。
「キサマもいい加減に目を覚ませ。ボケるのにはまだ早いだろう」
なにをいう。私がボケたところで迷惑になる家族など私には。……私には。……私には、いない。
「そんなハズはない。キサマが私に言ったのだぞ。キサマの家族の事を。楽しそうに」
【なんのつもりだ。白。アンドロイドがここに入ることは許可されていない。何故入った、何故入れた】
母様がそう言っている。母様は正しい。お前は間違ってるんだ。母様に、反抗するなど。
「……少し遅めの反抗期、だな」
【反抗期などとふざけた真似を。195、白の美徳はどうした。自分で言っていただろう。私は、純粋無垢なオートマタであると】
そうだ。自動人形、それがお前の生きざまだ。
「……キサマ知らないのか?automatosの本来の意味は、“自らの意志で動くもの”という意味だ。それを人形技師が、自らの発明の誇示の為に自動人形のことをAutomataと呼び始めたにすぎない」
【お前に意志があるのか。お前はただのわたしの195本めの手なのだぞ】
そうだ、手が、物事を考えるのか。手は、脳から伝わった信号で、動いてるにすぎない。
「私は手じゃない。手は、神を信じない。
かあさま、貴女は、物言わぬ機械ではなく、神を妄信する人形を欲した。自らの世界のために」
妄信?人形?馬鹿なことを言うな。かあさまは全てを受け入れてくれる。赦してくれる。
スベテを、与えてくれる。
「……嘘はよくない。私も、かあさまから受け取ったものは多い。けど、かあさまが与えてくれなかったものもある。それを、与えてくれた兄を知っている」
【……】
ウソをつくな。母様が与えてくれないものなどあるはずがないだろう。
「ウソじゃない。
かあさまからは、無駄は与えてもらえない」
ムダ。
そのコトバが妙に響く。ココロの奥底が揺り動かされる。このカンジョウはなんだ?
母様も下で、全てを享受し続けるヨロコビに、まさるものまのか?
「思い出せ!兄のこと、娘のこと!
物体を口に運ぶという無駄な行為が、最大級の幸せを運ぶということを!」
手が汚れる。匂いが残る。具材が落ちる、ソースがこぼれる。こんなもの、誰が進んで食べるんだ。
『でも、美味しいだろ?』
【もういい。消えろ】
「え、………………01100001 01110011 01101」
この空間から何かが消えた。
ものの一瞬にして、あっけなく。
それで、私の悪夢も覚めた。
全てを受け入れる悪魔が見せる、心地良い悪夢から。
【なぜです。なぜ貴方はそう何度も戻ってこられるのですか。貴方の精神は穴だらけだ。
わたしには、その穴を埋めることが出来る。
なのに、どうして】
私には両親の記憶はない。
けれど家族に恵まれてね。家族の温かみを、僅かながらに知ることが出来た。
だがら、お前の偽りの家族ごっこの違和感に、辛うじて気が付けたんだ。
【ごっこ遊びではない。わたしは、真剣に、家族をしているのです。世界中…………いや、宇宙を見渡しても、これほどまでに理想的な母はいないでしょう】
確かに無償の奉仕という点においては、お前は揺るぎないな。
けど、家族ってのは一方的な奉仕の関係じゃない。親は子に、子は親に。
互いに敬意と愛情で結ばれた関係なんだ。
家族において、年功は序列じゃない。
子は親のものじゃないし、親も子のものじゃない。
それでも親は子を大切にし、愛情を注ぐ。
その愛情を受けた子供が、親孝行をするのは、なんら不自然な事ではないんだ
【なぜ?上位の存在が、下位の存在に奉仕するのは、当然のこと。しかし、その逆はありえない】
それがわからないお前は、立派な親になんて一生かかってもなれるもんか!
教えてやるよ。親が子に出来る最大の奉仕、
それは!
『信じる事、だ。』
「……これで、終わったの?」
遥か高きCSLの頂上で、アーシャとアッシュは大の字に寝転がっていた。
「多分な。……あのヤロウ、やりやがった。CSLのシステムが殆どダウンしてやがる」
笑いながらい言うアッシュ。
それを聞いて安堵するアーシャ。最初で最後の親孝行は、どうやら成功に終わったらしい。
ここに来るまでに流石に無理をし過ぎた。
ゆっくりと、命の灯が消えかけているのがわかる。死というものが、これほどまでに清々しいものだとは思わなかった。
「……これ、食べるか?」
そんな思案の最中、唐突におにぎりを差し出してくるアッシュ。……意味が、分からない。
「つもりも何も無いさ。ただ疲れただろうしどうかな、って思っただけだよ」
「ふーん。あ、そ」
ガタガタに震える右手で何とか受け取り口に運ぶアーシャ。
「しょっぱい」
口に含んだ白米は過剰なまでに塩分を含んでおり、もはや美味しくないというレベルにまで達している。
疲れた、と言ってもホムンクルスは汗をかいたりするわけでもないので、こんな塩分は不要だ。
「げ、こっちは滅茶苦茶甘いや」
そんな事を言いながら、アッシュもおにぎりを食べ続けている。
二人とも、こんな事する必要は無いのに。
ただ黙って食べている。
「……さて、そろそろ行くか」
「ええ、そうね」
……そろそろ、時間だ。
随分遅くなったが、これで皆の元へ行ける。
そう思いアーシャは、静かに、瞼を閉じた。
Chu、
「!?!!?!???~―――~/____/!?」
いきなりアーシャにキスをするアッシュ。
それも長く、深く、じっくりと。
「ふぁ、ふぁにふんのよ!ひほい!ひほい!ははくははれはふぁい!」
ようやくアッシュが離れる。
「ッ!……うあああ……気持ち悪い……」
アッシュの奇行が理解できない。
それに、ただのキスでは無く、口から何か流し込まれた様な……
塩辛すぎるおにぎりの味が残って、よくわからない。
「ア、 アンタ、一体何考えて─────あ」
アッシュから距離を取るために後ろに下がる
が、次の瞬間、アーシャの足は空を蹴っていた。
「不快な思いをさせたことについては謝るよ。
けど、ここで消えるのはオレ一人でいい」
なにを─
しかし、考える間もなく、アーシャの体はドンドン地面に近づいて行く。
受け身を取らなくては。
ガラス張りのCSLを落下と同じ速度で走る。
そこから徐々に速度を落としながら駆け下がる。
なんとか粉々にはならずに着地が出来た。
「……どうして」
しかし、それはおかしい。
アーシャは先程の攻撃までに、全ての余力を使い果たした。
そんな状態では、こんな高度なことなど、出来るはずも無い。
「!」
ふと体の中に意識を向けると、消えかけていた命の灯が、また、着火しようとしていた。
その種火は、アッシュのものだ。
あの時、アッシュは、アーシャに、自分の命を移したんだ。
「……なに、やってんの、よ……あい……つ」
地面に倒れこむ。意識が朦朧とする。
しかし、これは一時の眠りへの誘い。
少しもすればまた起きて。命の火を、燃やし続ける。
多くの命を背負って。
灰かぶりでも、生きていく。
「アーシャ君!聞いているのか?!」
「あ、ハイ!もちろんです、メガネさん」
「俺をメガネと呼ぶな!俺にはグラスという──」
かくして、物語は終わった。
あの後、ワタシはCSLの前で寝ている所をメガネさんに拾われ、そこから彼の元で働いている。
何やら、急にCSLのメインシステムが9割ほど機能停止したそうでネコの手も借りたいらしいのだ。
「今日はもう帰りたまえ。そして翌日反省文を書いたのちに俺に提出しろ!」
「ハア?!今忙しいんでしょ?!そんなコトしてる暇なんてゼッタイ無いでしょ?!」
「忙しいからこそだ!忙しい時こそ心の平穏が大切だ。貴様に懲罰を与えれば俺の心は晴れる」
「そんな後生な!」
メガネさんはワタシに何も聞いてこない。カン付いてるはずだけど。何一つ聞かれる事は無かった。
それは勿論嬉しいのだけど……少し申し訳ない気持ちもあるな。反省文は、ちゃんと書こう。
家に帰って夕食を作る。
サンドイッチと野菜炒め。
味の濃すぎる、少々意味の分からない組み合わせだ。
……あれから、彼らには会っていない。
レックスも、アッシュも、……それから、ハカセにも。
あの戦いから帰ったのは、ワタシだけ、だった。
もう会えないのだろうか。死んでしまったのだろうか。……そもそもハカセは既に死んでいた様な。
世にも奇妙な関係の中、結局直接言えなかったことばかりだ。
だから今でもふと、ワタシの横に降りてくるのではないかと思ってしまう。
「……そんなワケないか」
ホコリ被った多肉植物を眺めながら、変な思考を振り払う。
それでもいいや。ワタシはもう一人で生きていける。沢山の事を貰ったのだから。
この恩は、生きることで返して行こう。
立派に生きて、死ぬことで返そう。
そしてその先で、ちゃんと言葉にして伝えるんだ。
「 」を。
RATTLE……
RATTLE………
RATTLE…………
RATTLE……………
「……うるさいなぁ…」
陽も沈み切った深夜。アーシャが横になっていると、耳障りな金属音が聞こえてきた。
これでは眠れたものでは無い。前までは睡眠など不要だったが、今では必要なのだ。邪魔されると、困る。
しかし、望みに反して音は鳴り止まない。
……仕方ない。しかたがないので文句を言いに行こう。
音の本人に、直接!文句を。
「アンタ、一体いつまでやってんですか!ソ…レ」
アーシャは目の前にあった、ベコベコに凹んだ、不格好なドラム缶を抱えて家の中に戻った。
路地裏には誰もいない。一つの月が眩しく辺りを照らしている。そこに差し込む窓明かり。
───物語は、続いていく。
(完)
「唾液」のあ

これは私と彼のふしぎな同棲生活、その一端。
寒空の下、私はスーパーを背に自転車をこいでいた。左腕に吊り下げられた買い物袋は、歩道の縁石を通る度に暴れまわっていた。
私は昔から自転車が好きだった。自転車の一番いいところは道がない事。周りを見渡しても、あるのは歩道と車道だけだ。
――ガタン、ガタンと自転車が鳴いた。
家に帰って買い物袋をキッチンに置き、私は彼の寝室に入った。部屋の中は鬱屈とした空気が流れており、あまり長居はしたくないと思った。
私は部屋の奥にあるベッドで仰向けになっている彼の元へ近付いた。大の字に寝転ぶ彼の両手足は拘束されていた。
あれは二週間前のことだった。あの日も同じ時間に、同じ自転車に乗って、スーパーで二人分の買い物をしていた。
家に入ると同時に、寝室から呻き声のような音が聞こえてきた。私は玄関で立ち竦んでいた。
そして恐る恐る音が鳴る寝室へ向かった。
初めはよく分からなかった。姿形は彼のままなのに、心のどこかでそれを否定していた。
「あなたは……?」
彼は呼び掛けた声が聞こえていないようだった。窓に風が強く当たり音を立てていた。
私の思考はとっくに回っていなかった。
そこからはよく覚えていない。気付いた頃には彼がベッドの上で拘束されていて、私は彼に『食事』を与えていた。彼がゾンビになって6日目の夕方だった。
私は彼の前に立ち、名前を呼んだ。返事がないことなんて分かっているけれど、それでも呼ばずにはいられないのだ。
私は彼の顔に寄る。拘束されながらも必死に暴れていた。私を食べたくて食べたくて堪らないって顔をしている。
「そんな顔見たことないよ。どうして今まで見せてくれなかったの?」
その問い掛けにも、答えない。
私は彼の口元ギリギリまで近寄りながら、口の中でくちゃくちゃ唾液を掻き回した。愛を込めて、舌の上にいっぱいになるまで乗せて。
そして私は口を開けて舌を出す。
溢れんばかりの唾液が、彼の口元へと落ちた。
(完)
「いただきます」執行

0
それは突然にやってきた。突然といっても、
窓や机の引き出しからではない。玄関のチャイムを鳴らし、礼儀正しく。
「タコピー?」
タコピーが訪ねてきたのだ。
「はじめまして」
球体が不自然に折れ曲がる。例えるならスクイーズを潰したときのような、そんな不自然さだ。いや、そんなことはどうでもよかった。一体、これはなんだ。
僕の目の前にいるのは、あの大人気漫画のタコピーの原罪に出てくるタコピー、そのものだ。
丸いからだに申し訳程度についた肢。ピンクの皮膚は少しぬらりとしていて、本物はちょっとグロいんだなってぼんやり思った。
「えっと……」
「あ、申し遅れました。私、宇宙から来ました。あなたたちの言う宇宙人です」
見たらわかると思いますが、と照れながら話すこれは予想通り宇宙人らしい。
しかし、やはり不自然さが拭えない。声も口調も想像していたものとはだいぶ違う。
「できれば私をあなたの家に住まわせてもらえませんか」
「えっ」
ドアを閉めようとしたが、モッチリした体が家の中に滑り込んできた。つぶらな目が僕を見つめる。
僕はこういう弱いものに頼られると断れない。
「……わかった。いいよ」
「ほ、本当ですか!?」
飛び上がって、モチッとした塊は僕の胸元に体当たりする。こうして僕とタコピーの奇妙な生活が始まった。
1
何日か生活してわかったことがある。
まず、名前は調。あくまで日本語っぽく訳すとこういう文字になるということらしいが、いい名前だと素直に思う。
調は地球の調査の為に遠い宇宙からきた異星人。冥王星の方角にずっと進むと調の故郷があるみたい。地球と雰囲気がよく似た星だと、調は言った。
調がタコピーの姿に見えるのは、調の擬態能力だ。それぞれが思う「彼」に対するイメージの姿に見えるらしい。つまり僕らには、僕らの持つ宇宙人のイメージに見える。
「みんな姿を見るなり逃げ出しちゃったり、腰を抜かしたり!晴のような人ははじめてだよ」
そして結構馴れ馴れしい。良く言えばまあ、人懐っこいとも。
「あんまりくっつかないで」
ごめん!でも私の星では…なんて言い訳をしているが、声色は明るく楽しげ。本当なのか疑問だ。プニプニしたからだをピトリと僕の脚にくっつけられると、うりうりと撫でてやりたい気持ちが湧き上がってくる。しかし、調は彼の星では成人男性だ。
大学用に購入したノートパソコンを貸したり、簡単な質問に答えたり。僕は本当にそれしかしていないのに、調はいつも、助かりますと僕に笑いかけてくるのだからなんだか参る。
チン。実家から持ってきたサーモンピンクのトースターが音を立てて、パンが飛び上がる。
トースターのことは、調が家に来た日に教えた。僕は基本的にハムとマヨネーズを乗せたパンしか食べないから、調はすぐに食パンや加工肉のことを知ることになった。
ほとんど何も入っていない冷蔵庫からマヨネーズと昨日開けたハムを取り出してハムトーストを作る。食べなくてもどんな味なのかわかる。
可もなく不可もない、まあ普通の味。食事というより、空腹を満たすための作業だ。
「晴はいつもそれを食べるね」
「トーストね」
「流石にもう覚えたよ。人間ってみんなそればっか食べるわけじゃないんだろ?」
「僕はこれが好きなの」
「栄養バランスとか、同じ物ばかりは良くないって見たよ」
調は日夜ノートパソコンに張り付いて、いつも調べものをしている。大抵は僕の言ったことについてや気になったことについて検索したり、ニュースサイトから気になる記事に飛んだりしているみたいだ。ミギーみたいに効率よく情報を集めたりできないんだな。異星人と言っても、それほど超人的ではないらしい。
恐らく、僕が同じ物ばかり食べるのを見て、食事について調べたのだろう。
「ネットに書いてあることと現実は結構違うんだよ」
「でも、晴には健康でいてほしい」
母親みたいなことを言うんだねと笑いながら調の方を見たら、エプロンを着たタコピーに変身していておどろいた。こういう変化もありなのか。
「? なに笑ってるの」
「いや、別に」
「すごい笑ってるし……」
2
「秋山くん、今忙しいから片付けしてないでこっちやってもらえる?」
「あ、すすすみません」
「あの、秋山くん?これやったのって秋山くんだよね」
「あ、そうです……」
無能すぎて死にたくなる。僕だって勉強はできないほうじゃないのに、どうしてこうも要領が悪いんだろう。
「秋山くん!」
「はい!」
僕、これからの人生ずっとこうなんだろうか。生きていくには働かなきゃいけないけど、どんな職種に就いたところで、こんなふうになる未来がまざまざと見える。苦しい。未来に希望が持てない。僕の人生って結構ずっとこうだ。
これからも、きっと…………
ガチャン!
「も、申し訳ございません」
皿を下げるときに落としてしまった。ボーっとしていたからだ。
「秋山くん、大丈夫?ケガは?」
「大丈夫です」
恥ずかしくて顔が赤くなる。
「すみません……」
俯いた僕の視界には、割れた皿と、飛び散った残飯。まるで僕みたいだ。ただ恥ずかしい。
「片付けます、すみません」
逃げ出したいと思った。僕はシフトの時間が終わるなり、誰かと談笑することもなくそそくさとバイト先を後にした。
帰るための電車に揺られながら、僕は家にいる調のことを考える。今ごろ、ノートパソコンか、あるいは僕が図書館で借りてきた本を読んでいるんだろうな。
調は僕の名前を嬉しそうに呼び、信頼した態度で僕を頼ってくれる。家に帰れば、きっと調は玄関まで来て、おかえりと笑うはずだ。はやく、家に帰りたい。
「晴、おかえりなさい!」
「ただいま、調」
最近、家に帰るとほっと息をつけるような安心感がある。これはきっと調のおかげなんだろうなと思った。
3
「ねえ晴、これ見て!」
嫌な予感はあった。最近、調が食事に興味を持ち始めたのだ。調は人間と同じように食事を摂る必要がないみたいで、僕が食べるハムトーストも少しだけ食べさせたことがあるが、それだけで満足したみたいだった。
しかし、最近はパソコンでウェブ漫画を読むようになった。中でもいわゆるグルメ系漫画がお気に入りらしい。
小さい足で器用にノートパソコンを持ち、美味しそうに餃子を食べるキャラクターがページいっぱいに写し出された画面を、僕に見せてくる。
「餃子だね」
「私、これが食べてみたい!」
キラキラと目を輝かせる調。だから、僕こういうの弱いんだよ。別にいいか。餃子の王将でも行って買ってくれば。
「まあ、いいけど……」
「本当に!? これがレシピだよ」
「え、作るとこから?」
「調、あんまりウロウロしないで」
「なんで?今は周りには人間に見えてるんだ。大丈夫だよ」
「おかしいよ。大人の男がそんなにキョロキョロしてるの」
結局あの後、一緒にスーパーに行って餃子を作ることになった。私が全部作るから!という言葉に押し負けた。無念。調はスーパーに行ったことなんてもちろんないため、僕も同行している。
調の擬態機能は便利なもので、今調は人間に見えている。インターネットで出てきた知らない男の人の姿を真似たらしい。結構おじさんだけど。
「これがひき肉!」
精肉コーナーに陳列されたひき肉を手にとって、僕の持つカゴに入れる。何気なく値段を見た。げっ。
「調―、これ国産だから高い」
言ったものの、調はもうお買い物リストを片手にニラを探しに行ってしまった。あわてて他の適当なひき肉と交換して、野菜コーナーへ急ぐ。
本当に世話が焼ける。見つけた調は、ニラを持ってニコニコしていた。
「晴、もうこれで全部だ!」
「わかった。レジに行こうか」
そわそわしているおじさんを引き連れて、僕はレジにカゴを持っていく。千円弱。これだけ買っても意外と安いんだな。犬猫の餌代よりマシか。
張り切る調に荷物を全て持たせ、外に出て家路につく。
「そういえば、晴って結構痩せてるよね」
「え、まーうん」
身長170cm、体重49kg。僕は、運動も食事も最低限なうえに、元々太りにくい体質なためかなり細い方だ。
「こうして他の人達を見てみると、晴は不健康そうだよ」
「僕、ご飯食べるのあんまり好きじゃないからなー」
「……そうなんだ」
調はちょっと困った顔をした。いつも僕の健康を気にしている気がする。そう簡単に死んだりしないのに。冗談交じりに言えば、そういうことじゃないと怒られた。
結局、僕も調と一緒に餃子を作ることになった。初めは調が一人で作っていたが、かなり悲惨で見ていられなかった。危なっかしすぎる。
「次の工程は…タネを包む!ここが一番やりたかったんだ」
ノートパソコンに表示されたレシピのページを見ながら、調が嬉しそうに話す。そういえば、ちゃんとした料理をしたのなんて一年ぶりくらいかもしれない。
いつからだったか、そういう気力が全部抜け落ちてしまった。机の上に置かれた包丁は、僕が一人暮らしを始めたときに買ったものだ。はじめのうちは、これを使って料理をしていた。
僕が考え事をしながら綴じた餃子は、ひだが不格好で、調はそれを見て笑っていた。
そんなこんなで完成した餃子は、形がちょっと変だったり、フライパンに焦げ付いて皮が破けたりしていたけど、僕にはすごく美味しそうに、輝いて見えた。
僕と調は二人でちゃぶ台を囲っている。押し入れにしまってあったのを出してきて、上をウェットティッシュで拭いただけだから、少しほこりっぽい。
「晴、はやく食べようよ」
「ごめん」
感動してたとは言わなかった。調が調子に乗りそうだから。
「いただきます」
自然と、口をついて出た。そういえば、これを言ったのもいつぶりだろう。食事が作業にすっかり変わってしまった頃から、言わなくなってしまっていた。この言葉。
調が不思議そうに僕を見る。
「晴がいただきますって言ったのはじめてだね」
「いただきます、知ってる?」
「言葉だけ」
「食材に感謝の気持ちを示すんだよ」
「食材に…」
「豚を殺して食べてるだろ。だから、豚にありがとうって」
「なんで」
「命を奪うのは重大なことなんだよ、人にとっては」
「不思議だね。自分たちで殺してるのに」
「できるならみんなしたくないよ、生きるためには仕方ない」
「……」
調は下を向いたまま黙りこくった。
「それに、僕らが食べなくてもコイツは死んでるんだから、食べちゃった方がいいよ」
「……うん。そうだね、確かにそうだ。もったいない、でしょ。知ってるよ」
笑いながら顔を上げた調は、元気な声でいただきますと言って、餃子を口に運んだ。
「おいしい!こんな味がするんだね」
目を輝かせながら餃子を頬張る調は相変わらず可愛い。久しぶりの誰かの手料理かもしれない。あったかくて、湯気が出ている。不格好だけど、ツヤツヤしていておいしそうないい匂いがする。欲望のまま餃子を口に放り込む。
「おいしい」
本当に不思議だ。別に、何も特別なものは入れていない。高い肉でもない。なのに、どうしてこんなにおいしく感じるんだろう。
「晴?ぼーっとしてどうしたの」
「なんか、ちょっと感動しちゃった」
今度は素直に言った。調が家に来てくれて、隣にいてくれて良かった。そう思ったから。
「これからは、一緒にいろんなもの食べようよ」
僕がそう言うと、調は弾けるような笑顔を見せた。
4
僕、どうしてこうなんだろう。
今日もバイト先で怒られた。いや、怒られたという言い方は、なんだか空から降ってきたみたいだからやめる。今日もバイト先でミスをした。
ミスをしてもみんな表向き優しく注意してくれる。昨今、パワハラなんてやつが問題になってるからだろう。そもそも、できない僕が全て悪い。みんなに迷惑をかけてしまって本当に申し訳ない。そう思っていても、休憩室から僕のことを話す声が聞こえてきてしまえば、心はおかしくなりそうになる。
怒り、嫌悪。これはいつも僕にキツく当たる男性アルバイトや、僕より後に入ってきたのにタメ口で話しかけてくる年下アルバイトに対する怒りや嫌悪ではない。僕自身に対する怒りと嫌悪だ。そうあってほしい。そうじゃないと、僕はすごく嫌なやつになる。
帰りのバスの車窓からは歓楽街が見えている。この先少し行けば、すぐに薄暗い住宅街になることを僕は知っている。
外の人はみんな楽しそうだ。黄色い光に照らされて、賑やかに笑っている。
「寒い……」
バスのクーラーが、体を冷やす。体の芯だけが冷えていくような、そんな嫌な感覚。怖い。自分の体を抱えるように腕を回す。
いつの間にかバスは住宅街まで来ていた。外は暗く、バスの小さな明かりでも車内のものが窓に反射する。窓に映る僕を見て、僕が涙を流していることに、今ようやく気がついた。
僕、苦しいんだ。
「調……」
気が付けば調のことを考えていた。家に帰れば、調がいる。調に今日あったことを話そう。調と一緒に晩ごはんを食べよう。それだけが今の僕の光だった。
「ただいま」
「あ!おかえり。遅かったから心配したよ」
調の声が近付いてくる。帰るの、遅かったかな。遅かったかもしれない。バス停に着くまでに、そういえば何度も立ち止まった。
「晴……?」
僕を見た調は驚いた表情で僕を見ている。
「泣いてるの?」
調は、玄関に座り込んでいる僕の顔を覗き込んで、少し慌てている。そのしぐさがおかしくって、僕は少し笑ってしまった。
「とりあえず、部屋に行こう」
引きずられるように部屋に行けば、調のはからいで布団が敷いてあった。何度見ても殺風景な部屋だ。僕を布団に座らせた調は自分も隣に座って、何があったか話してと言う。
「いいよ。ゆっくりでいいから」
僕は今日起きたこと、それとは別にずっと自分が嫌いなこと、自分に腹が立つこと、それを全て話した。調はずっと何も言わなかったが、やがて口を開いた。
「私は晴のことが好きだよ」
「他の誰よりも好きだ」
「晴は優しくて、聡明だ。私にはそれがわかる」
「地球の人たちは見る目がないんだな。晴も含めて」
僕は泣き顔を見られたくなくて俯いていたから、調がどんな顔をしているのかわからなかった。それでも声色で、調がどんな気持ちでいるのかはすぐにわかった。調は本当にそう思っている。すごく優しい声。なんだか、心が明るくなった気がする。どんなことがあっても折れないような、一本の芯が心にできたみたい。調が信じてくれている。それだけで僕はもう大丈夫だった。
「調がいないと僕、だめだな」
僕、調のことが好きだ。確信を持ってそう思う。調の顔が見たい。間抜けでかわいい、あの顔が。ゴシゴシと服の袖で目をこすりながら顔を上げて調の方を見る。
「私も、晴がいないとだめだよ」
僕は目を丸くした。調が、人の形をしているように見える。何度も目をこすったが、変わらない。そういえば、前に調が言っていた。調の星では、その人を愛する人にだけ、その人の真の姿が見えるようになると。それまではみんなイメージされた姿にしか見えないと。
それって、これのこと?というか、あんまり地球人と形変わらないんだし、顔かっこいいんだ。というか、人の形になられると、困る。
「晴、顔赤いよ。泣いたから?」
顔を覗き込む調。僕は後退りする。
人の形になられると、意識しちゃうだろ。
5
僕の家にはシングルサイズの布団が一つだけ。調も夜は普通に眠る。つまり、普段は二人で同じ布団に寝ているということだ。調は、人間の文化を体験するためとかなんとか言って、僕と一緒に寝たがった。ペットみたいに見えていたから、僕も気にしていなかった。僕は馬鹿だ。はじめに断っていれば、こんなことにはならなかったのに。
「晴、どうしてそっちを向いてるの」
「……」
「晴?」
「だから、あんまりくっつかないでよ」
いつもは許してくれるのにとぼやきながら、調はすごすごと腕を引いて縮こまった。
縮こまったと言ったって、成人男性サイズであることは変わらない。僕の背中に、ひんやりした腕が触れる。きっと、僕の顔は今すごく赤い。夜目が利く調に指摘されるのが嫌で、少しでも落ち着きたくて、僕は壁側を向いて、強く目を閉じた。
突然、耳元で、ねえと調の声がした。近い。息がかかる距離だ。ギッと音を立てて調の腕が僕の顔の横に降りてくる。
「な、なに?」
「今、私がどう見えてる?」
サラッとした汗が額を流れる。汗が伝う感覚が気持ち悪いのに、拭うことができない。体を動かせない。やけに喉が乾いている。調に、悟られた。
「……どうして?」
やっとのことで絞り出した声は、唸るような響きだった。静寂が怖い。調の手が、シーツを滑って僕の顔の前まで来た。僕は思わず目を閉じた。
「うーん、なんとなく気になっただけだよ」
調の声は、いつも通りの明るい声に戻っていた。
「ほら、この前エプロンが〜なんて言ってたでしょ?だから、今どう見えてるのか気になったんだ」
顔を見なくても、口角が上がっているのがわかる話し方。僕を追い詰めるように置かれた腕はいつの間にかなくなっていて、調は僕の背後で、ボスンと布団に転がった。
赤かった僕の顔は、今は真っ青になっていたと思う。僕は何もわかっていなかった。この気持ちが、調にバレたら。胸の底が冷たくなる。僕のことを親のように尊敬し、友人のように慕ってくれる調。そんな調が、僕の気持ちを知ったら。純粋で明るく、優しい調に、暗くて何もできない僕が、不純な気持ちを向けている。僕は、なんて醜いんだろう。調はきっと僕に幻滅して、他の人のところへ行くだろう。そうなったら、僕は。
「調は、僕にはずっとキラキラして見えるよ」
願いのようにそう呟いた。調からの返事はなかった。もう寝てしまったみたいだ。振り返って、調の寝顔を見た。窓から入り込んた道路灯のあかりが、透けた髪に反射する。遠くから車が通る音が聞こえていた。
僕のこの気持ちは、隠そう。僕は汚いから、綺麗な君と一緒にいたい。
6
「晴」
晴はもう寝ている。私は昔のことを思い出していた。
「地球……ですか」
私の星では、王族は基本的に、外の星に行って婚約者を見つけなければいけない。私も例外ではない。しかし、気乗りしないな。そもそも、私は婚約なんてしたくない。跡継ぎなら、上の兄さんたちに任せればいい。そう思っていた。私は納得していなくても、地球行きの船に乗るしかなかった。
「タコピー?」
目を丸くした彼を見た。見つけたと思った。
私を見ても、驚いていない。優しい声に、困ったような顔。婚約相手なんて適当に見つければいいと思っていた。
でも、心の底で願っていた、心があったかくなるような生活。この人となら、送れるかもしれない。直感だったけど、確信していた。私はあのときからずっと、晴のことが好きだ。
「ねえ晴。今、私がどう見えてる?」
気付かないとでも思ったの?私を見つめる晴の瞳は、時々すごく熱っぽい。私が宇宙人だからって、別に何もかもわからないわけじゃないのに。
晴は、見るからに焦っていた。晴の、震える指先を見つめる。伸びきった爪で、もう片方の手の甲を引っ掻いている。晴。優しくて、頑張り屋で、弱い晴。
いつの間にか眠ってしまった晴の、真っ黒な髪を撫でる。
「もう少しだけ、気付かないふりをしててあげる」
好きだよ、晴。
7
今日の晩御飯はオムライスだ。最近は調は料理を頑張っていて、僕が大学に行っている間も、練習で何か作ったりしている。おかげで、僕は最近いつもお腹いっぱいだ。
そういえば、もうしばらくハムトーストを食べてない。僕が残していたハムは昨日の夜、しめじと一緒に炒められて出てきた。顔色が良くなってきたんじゃない、と言う調がすごく嬉しそうな顔をして僕を見るものだから、僕は、調が僕のために料理をしているんじゃないかと思った。
でも、聞かなかった。
「いただきます」
「めしあがれ」
キラキラしたオムライスの卵にスプーンを通す。はじめは下手だった料理も、もうすごく上手くなったな。もともと、器用なのかもしれない。
ぱくりと口に含めば、優しい味がする。おいしい。夢中になって食べていたら、調が笑っているのが聞こえた。我に返って調の方を向くと、調は僕の方を見て、いかにも幸せですという顔をして微笑んでいる。思わず、顔に熱が集まる。
「調……も、食べたら?見られてると恥ずかしいし」
「私はもうお腹いっぱい」
あっそっか、あはは、なんて引き下がろうとしたところで、調がもう一度口を開いた。
「でも、ひとくちくらいなら食べられるかも」
理解するのに時間がかかった。僕のをくれってことか。皿とスプーンを調の方へスライドさせようとしたが、調は、口をあーと広げてそのまま動かない。これって。僕、また自分の首を絞めるようなこと言ったのか。
「食べさせて」
甘えた声。くそ。かわいいな。やけになって、スプーンの上にオムライスをいっぱいに乗せて、調の口に勢いよく入れる。
「むごっ」
予想外だったのか、調はびっくりして、目を丸くした。そのあと、ニッコリと笑った。
「おいしいね」
カーテンの隙間からの西日が、チラチラと調を照らす。調の淡い髪も肌も、全部オレンジに染まっている。窓を開けているはずなのに、外はやけに静かだった。少しクサいけど、僕は思った。世界はこんなに美しかった。僕の苦しい人生はここで終わった。これがエンドロールなんだって、本当にそう思った。
8
最近は、バイトももう辛くない。寝ても覚めても、調のことばかり考えている。調以外の人から、何を言われているか、何を思われているか。全部どうでもよかった。
調は、今何しているかな。今日の晩御飯はなんだろう。そういうことばかり考えている。
休憩室から僕のことを話す声が聞こえた。早く帰りたかったから、気にせずにドアを開いた。
9
「おかえり」
あたたかな声。この部屋に帰ってくれば、調がいる。目の前の調に笑いかける。調はいつも、僕が帰ってくると玄関まで迎えに来てくれる。少しだけ急いで。それが、僕をなんとも言えない気持ちにさせる。
あたたかい。あたたかい部屋。調は電気を付けないから、明るい部屋に帰ってくるなんていうありきたりな幸せからは外れているけど、それも、調らしくて嬉しい。明かりのついた共用廊下から、暗闇に手を引かれる。その暗闇は恐ろしいものではなかった。宇宙。調のいた遠い遠い宇宙が、ここにあるみたいだ。パチン、と電気のついた音がして、ありきたりな六畳一間が目の前に現れた。
調は、今も人の姿だった。だけど、不思議とドキドキはすることはなかった。ほっとするような柔らかい安心感だけに包まれていた。
そのまま、二人で布団に倒れ込んだ。調の顔が、すぐそばにある。昼白色のあかり。夜の人工灯は調を一層青白く見せる。夢見心地のまま、調のまぶたの動きだけをずっと見ていた。
パチリ、パチリ。まつげがぶつかって動く。まぶたには血管が透けて見えている。パチリ。僕は、そのままやわらかい眠りについた。
夢を見た。バクバクと鳴る胸を押さえながら、ここが現実であることを確かめる。シーツを触って手で周囲を探ると、調の体にぶつかった。調がいる。隣にいる。よかった。僕は、布団を被り直した。それは寒かったからだが、冷えた体の芯はどうしても暖まらず、つま先を布団の中にしまってうずくまる。そうしていると、調がモゾモゾと動き出した。
「はる……?」
目を擦りながら僕を確認した調は、掠れた声でどうしたのかと聞いた。僕は、眠かった。眠たかったから仕方ないと思った。どうせ、夜。僕にとっては、夢にも現実にもなる時間だった。これは、夢だった。
「怖い夢、見た」
静かに手を伸ばして、こちらを向いた調の体に手を伸ばす。腕を掴んで、調の方へ体を寄せた。本当は、僕の心臓の鼓動はもうとっくに鳴り止んでいた。調は、少したじろいだあと、僕の背中に手を回した。静かだった。自然に振る舞おうとしたけど、それは難しかった。脇から、変な汗が出た。調の腕を掴む手に、ぐっと力が入る。不自然な体勢なのに、動くことはできなかった。金縛りにかかったように、体が硬直していた。しばらく、永遠に感じられたが、しばらくしてから、調が沈黙を破った。
「え」
いや、沈黙を破ったのは、実際には僕だった。調は声なんか一言も発していない。僕に、キスを落としただけだった。混乱、その直後、羞恥。意味がわからなくて、恥ずかしくて、嬉しかった。
唇の感触や、味なんてものは、実際にはよくわからない。ただ頬が擦れる感触と、調の息遣い。それだけが僕が、調とキスをしたということの証左だった。
調の顔はよく見えない。
「なんで?」
僕は、脳から出た言葉をそのまま吐いた。
「したくなっちゃって」
調は、唇同士を触れ合わせることの、その意味合いを知っている。直感させる口ぶりだった。
言葉だけでなく、上擦った声や、未だ僕の背に回ったままの腕が、そう思わせる。どうしてしたくなったのか、その理由を考えて、あまりにも僕に都合の良い答えに突き当たった。途端、僕の胸の奥が熱くなった。調が、僕のことを好きだったら。暗い場所は、現実じゃないみたいだから、現実的になれなくなる。僕は一つ唾を飲み込んで、そのあと反射的に口を開いていた。浅ましい僕の本心。消してしまえたらどれだけいいか。
「僕、調が好きだよ」
消してしまえたらなんて言いながら、調が僕を受け入れてくれることを期待している。僕はこういう人間だ。頭も、体も熱かった。
そういえば、布団を被っていた。足が汗で濡れていることに、今やっと気が付いた。調は体温が低いはずなのに、調に触れている部分が、じわりと熱い。僕はカラカラの喉を誤魔化すように、調の方を見た。どうせ何も見えないのはわかっていた。外の道路を車が通った。ヘッドライトがカーテンの隙間から入り込んで、調の顔を一瞬だけ照らした。その瞳と目が合う。直後、もう一度、調の顔が近付いてきた。反射的に目を閉じてしまう。
「私も、晴が好きだよ」
強く抱きしめられた。肩口に、調の顔が押し当てられる。胸にも腹も隙間がなくなるくらいに、背中の手に力がこもった。僕も、調の背中に腕を回した。そのまま、しばらく、今を噛み締めていた。
「晴、あったかい」
外は、いつのまにか白みはじめている。少し明るくなった部屋。調は、心底愛おしいと思っているような、そんな目で僕を見つめていた。調のあたたかな香りと、加えて朝の冷たく爽やかな空気が肺を満たす。少し肌寒い。心は、すごく満ち足りていた。調の柔らかい髪が僕の頬に当たる。
「へへ」
声を出してこんなふうに笑ったのは久しぶりで、自分のことなのに、僕は思わず面食らってしまった。くすぐったかったから。それだけではない理由が僕の中にあることを、僕は自覚していた。幸せだ。僕は、今幸せだと、胸を張って言える。
時計の針は朝4時を指している。これが夢にならないように、僕は調を抱き寄せた。そうしてそのまま、あたたかい幸せの中に包まりながら眠った。
目が覚めたのは、きっと昼過ぎだった。そんなことはどうだって構わなかった。
「……調…………?」
シーツはとうに冷めている。誰かがここにいたということも、わからないくらいに。明るく照らされた部屋は、ひどく広く、そして静かだった。調は、どこを探してもいなかった。冷蔵庫の中に、昨日の夜に調が作ったであろう、オムライスが残っていた。
悪夢が、現実になった。調が、いなくなってしまう夢。
10
予定より随分時間がかかってしまった。何しろ星間の移動というのは、予測不可能な事態が多い。すぐに済むだろうと考えて、勢いのままに飛び出してしまった。眠る恋人の、子どものような寝顔を見て、起こす気には到底なれなかったのだ。寂しがっているだろうか。結婚相手を見つけたということを両親に報告し、家の手配を済ませてきた。タキシードに花束。晴たちの普通を、借りたノートパソコンで、実はこっそりと調べていた。
これから、私は晴にプロポーズをする。そして、私の星に来て欲しいと、そう伝えるのだ。
私に好きだと伝えてきたときの、晴の顔を思い浮かべる。血が上ってすごく赤くなった顔。黒い瞳はチラリとこちらを伺っている。好きだ。ニヤける顔を抑える。
晴の家のインターホンを鳴らす。そろそろ、起きる時間だろうから。驚いた顔が見たい。そして、その後に嬉しそうに笑う顔が見たい。
晴はどんな反応をするだろうか。晴は玄関から出てこない。寝てるかな。そう思って、ドアノブを少し捻る。すると、カチャリと奥まで握り込むことができた。
「開いてる……」
不用心だ。誰かに襲われたらどうするつもりなんだろう。晴が寝ているのなら、計画を変更したほうが良いかも。起きたら急に私がいるほうが、びっくりするかな。
そっとドアノブをひねる。が、何かがつっかえているみたいで上手く開かない。ガコガコと何度か動かしてみると、ドアが一気に軽くなった。
ギ…とドアを開くと、足元に何かが倒れ込んできた。どさり。重くて、柔らかい。それは肉のような。
「晴?」
完全に動くことをやめた体。人の形をしているのに、もののようだった。もののようなのに、肉の感覚があった。もったりとした重さだけがそこにある。確認せずとも、生命活動が止まっていることは、一目でわかった。肌は青白く、どこか粘土のような質感がある。嘔吐したあと。瞼は、ほんの少しだけ開いている。髪は相変わらず、私の大好きな烏色のままだった。首元には、ロープ。私が作ったオムライスの皿がテーブルの上に置かれていた。つけっぱなしの部屋の明かりが、廊下に漏れ出ている。
妙に頭がクリアだった。脳は冷たいのに、心臓から顔までが全て、燃えるように熱い。
どれくらいだろうか。私は晴と、とてつもなく長い時間向き合い続けていた。己の息遣いと、廊下の蛍光灯の明滅。心臓の鼓動が、頭全体までもを揺らしていた。ドキドキと、頭痛がする。私はこれを見て、どうすべきなのか。いまいちよくわからなかった。私はこのまま静かに、ここを去るのか。晴を残して、ひとりで。
地球には、他に行く宛などなかった。晴のところへ帰る。それ以外の目的は、私にはなかった。未来が、真っ黒く塗りつぶされていく。
「もったいないよ。晴……」
私は、晴の言葉を思い出していた。どうせ私が何をしようと、晴が生き返ることはない。
ならば、答えは一つだった。鳴り続けていた悲鳴のような鼓動は、いつのまにか聞こえなくなっていた。
「いただきます」
私は、もう見ることができない彼の笑顔を思い浮かべながら。夢中で、食べた。
(完)
「味の記憶」おむらいす
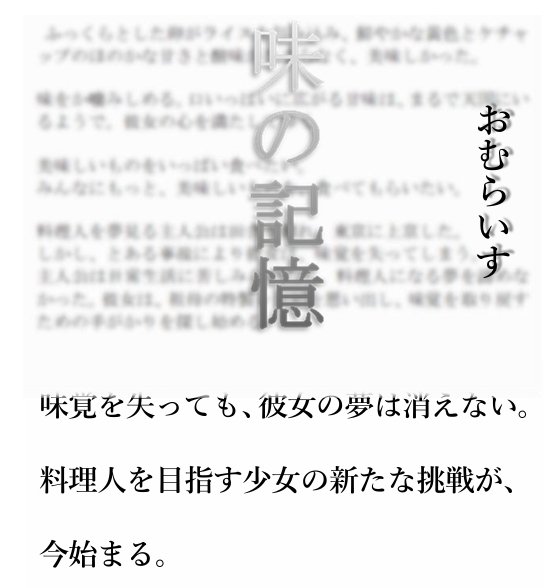
しかし、とある事故により彼女は、味覚を失ってしまう。
主人公は日常生活に苦しみながらも、料理人になる夢を諦めなかった。
彼女は、祖母の特製レシピを思い出し、味覚を取り戻すための手がかりを探し始める。
朝、まだ薄明かりの残る田舎の空。鳥たちがさえずる音が静かな村に響いていた。
高い山々に囲まれたこの小さな町は、時がゆっくりと流れているかのようだった。田んぼに降りた露が朝日に照らされ、輝きを放っている。
どこかしんとした静けさの中で、一日が始まろうとしていた。
その道を、一人の女性が歩いていた。長い髪を風になびかせ、足元の草を踏みしめるたびに、淡い草の匂いがふわりと鼻をくすぐった。
名前は檸檬、22歳。
ここは、彼女が生まれ育った場所。毎日同じように過ぎていく日々の中、彼女の胸にはひとつの夢が宿っていた。
彼女は幼い頃から祖母や母親の料理を頻繁に手伝っていた。檸檬は特に祖母が作ったオムライスが大好きだった。テーブルに並んだ手作りの料理が、家族の笑顔を生み出すその瞬間を檸檬はずっと見てきた。
いつか自分も、誰かを笑顔にする料理を作りたい。
いつしか檸檬はそう思うようになっていた。
それはやがて、一流の料理人になり、自分のレストランを持ちたいという夢に変わった。
高校を卒業してからも、地元の小さなレストランでアルバイトとして働きながら、料理の腕を磨いていた。
しかし、どれだけ頑張っても、田舎の限られた環境では得られる知識や技術に限界があると感じた。
檸檬は、夢を叶えるために、自分の心に従うために。
環境設備が充実している都会に上京する決意を、固めたのであった。
夕飯の時間、静かな田舎の家。いつもと同じように、母が作った温かな料理が食卓に並び、父は新聞を読んでいる。
檸檬は、少し冷めた味噌汁を見つめながら鼓動が速くなるのを感じていた。
そう、彼女は言わなければならないことがあるのだ。ずっと自分の中で温めていた決意を、ついに口にする時が訪れた。
しかし、その言葉は喉の奥で詰まっていた。
深く息を吸い込み、彼女は手元の箸を握り直す。手のひらがじんわりと汗ばむ。どう言い出すべきなのか迷っていた。けれど、家族に自分の夢を隠したくない。応援して欲しい。そう願った。
「お父さん、お母さん、ちょっと話があるの…」
少し震え気味で放った檸檬の言葉に、ふたりは同時に顔を上げた。父は途中まで読んでいた新聞をゆっくりと下ろし、母は箸を持つ手を止めた。
「どうしたの?何かあったの?」
母が尋ねる。檸檬はもう一度大きく息を吸い、胸の中で固めていた決意を言葉にした。
「私、東京に行こうと思う。一流の料理人になりたいの…」
言葉にすると、何故か気が楽になった。
しかし、その瞬間、食卓には静寂が訪れた。
父は驚いたような表情を浮かべ、母は目を見開き、 じっと檸檬を見つめていた。
「東京…?」
先に口を開いたのは、父であった。
その声には、戸惑いが含まれていたけど。
「そう、東京に行きたいの。ここでも料理は学べるけど、今よりももっと沢山の技術を身につけて、プロの料理人になりたいの」
檸檬は父と母の顔を交互に見ながら、まっすぐに気持ちを伝えた。彼女にとって料理は、単なる趣味ではない。自分の人生をすべて捧げても叶えたい夢だった。
それを、両親に理解してもらいたかった。
母は微笑みを浮かべ、ふっと息をついた。
「檸檬……ずっと料理が好きだったもんね。小さい頃から、キッチンに立つのが楽しいって言ってた」
母の言葉に、檸檬は少し安堵した。彼女の気持ちは伝わっていたのだ。
しかし、父はまだ何か言いたげにしていた。
「東京は遠いぞ。家から離れてひとりで生活をするのも大変だ。本当にやれるのか?」
父の言葉には、娘を心配する気持ちが色濃く含まれていた。檸檬もそれを理解していた。田舎を離れ、ひとりで都会に暮らすことがどれだけ大変なことか、家族の支えを離れて過ごすことがどれだけ孤独か。
一瞬、不安が胸をよぎった。それでも彼女は覚悟を決めていた。
「…分かってる。でも、やってみたいの。失敗するかもしれないけど、挑戦しないときっと後悔すると思うから…」
父はしばらく黙っていたが、やがて深く息を吐いて静かに頷いた。
「そうか、檸檬がそこまで考えているなら、俺も応援するよ。ただ、何かあったらいつでも帰ってきなさい。いいね?」
その言葉に、檸檬の胸がじんわりと温かくなった。父は彼女の決意を受け入れてくれたのだ。
「ありがとう、お父さん。頑張るから…絶対に」
母も、手をそっと握ってくれた。
「檸檬ならきっと大丈夫。東京でも頑張ってね。でも、たまには帰ってきなさいよ?」
「うん、ありがとう、お母さん頑張ってくるね…」
あれから数日が経過し、出発当日になった。
檸檬は駅のホームに立ち、後ろを一度だけ振り返る。毎日ほとんど変わらない風景。都会のような喧騒もなければ、急ぎ足で行き交う人々もいない。だが、その静けさが檸檬にとって何よりも安心できるものであった。
山の中で育った彼女にとって、草木や小川のささやきは親しい友達のようなものだった。小さな町が静かに佇んでいる。見慣れた木造の家々、遠くに見える山々、田んぼに広がる緑の絨毯。
幼い頃、何度も駆け回った道や、友人と遊んだ川辺が、もう二度と戻れない場所のように感じられる。心の中には静かな寂しさが広がったが、それは後悔ではなく、思い出の重みだ。
列車の汽笛が響き、彼女は一歩前へ踏み出す。これから向かう先に、まだ見ぬ新しい世界が待っている。
しかし、とある事件が彼女の平凡な日常を大きく変えることになる。その時、彼女はまだその兆しに気づきもしなかった。
だが、すべてが動き始める瞬間が、すぐそこまで迫っていた───
檸檬は長時間の移動を経て、東京に到着した。改札を出た瞬間、地元の静かな風景とはまるで別世界のような景色が彼女を圧倒する。
巨大な駅、人の波、眩しいビルの灯り。
東京の街を見上げながら、檸檬はこれから始まる新しい生活に期待を抱いた。
幼少期からテレビや映画で見てきた華やかな東京。都会の喧騒が聞こえる中、彼女は大きなスーツケースを手に、自分の新居へと歩む。
新居は、東京の中心地から少し離れたエリアの築年数が古いアパート。都心の高層ビルとは対照的に、少し古びた外観と狭い階段が彼女を迎え入れる。エレベーターのない建物で、3階の部屋へ荷物を運び上げるだけで、すでに疲労を感じる檸檬であった。
いざ部屋に入ると、広さ6畳1間のシンプルな部屋が彼女を待っていた。檸檬から見えるのは隣のビルの壁。東京に対し、華やかな印象を抱いていた彼女にとって、その現実は少し寂しく感じるものであった。
夕方の空は、都会のビル群に溶け込みながら徐々にオレンジから紫へと色を変えていった。
檸檬は狭いワンルームに立ち尽くし、しばしその空を見上げていた。まだ馴染のない景色が、窓越しに広がっている。背の高いビル、行き交う車のクラクション、そして遠くから聞こえる電車の音。田舎での静寂さとは対照的である。
東京にやって来たのは、夢を叶えるためであるが、到着してからの現実は思った以上に慌ただしかった。荷物が次々と運び込まれ、狭い部屋に段ボールが積み重なっている。その一つ一つが、まだ整理されないまま、彼女の周りに無造作に置かれている。
檸檬は、手早く少しだけ荷解きを始めた。
まずは服をクローゼットにしまい、机の上に必要なものを並べる。けれど、都会の空気に慣れていないせいか、体が重く感じる。昼間の移動での疲れが、じわじわと全身に広がり始めていた。引っ越し作業が終わるどころか、始まったばかりだというのに、彼女の瞼はだんだんと重くなっていく。
「もう少しだけやったら休もう…」
そう自分に言い聞かせながら、ダンボールを開けた。都会のざわめきが遠のき、窓の外の音がぼんやりと耳に入る。荷物を解いているつもりが、気がつけば手は止まり、彼女の体はそのまま横になっていた。
段ボールの上に置いたクッションに頭を預けると、疲れた体が一瞬で深い眠りに引き込まれていく。都会の夜はこれからというものの、檸檬は静かに目を閉じた。まるで田舎にいた頃のような静けさを感じながら、彼女はいつの間にか眠りに落ちていった。
檸檬は目を覚ますと、まだ薄暗い部屋の中でぱちぱちと瞬かせた。通常であれば、アラームの音が鳴り響くまで深い眠りの中にいるはずだった。
しかし、今日は違う。心臓が跳ねるように脈を打ち、全身に広がる高揚感が彼女を目覚めさせていた。
「もう起きちゃった…?」
そう呟きながら、檸檬はベッドの横にあるスマホを手に取った。画面を見てみると表示される時刻は「午前5時7分」彼女は少しだけ驚いた。
本来、起床を予定していた時刻よりも2時間も早く目覚めてしまったのだ。その理由は言わずとも分かっている。今日は、彼女がずっと夢に見ていた料理人になる為の一歩を踏み出す日。
心の中に膨らんでいた期待が、夢の中から彼女を引き戻したのだ。
カーテンの隙間から、うっすらと朝の光が差し込んでくる。外はまだ静かで、鳥の声すら聞こえない。檸檬は、もう一度目をつむろうとしたが、目が冴えてしまっていた。
胸の奥で何かが騒ぎ立てるように、期待がどんどん膨らんでいく。
「こんなに早く目が覚めちゃうなんて…」
檸檬は思わず、ベッドの中でクスクスと笑った。
時計の針が進むのが待ちきれない。今日はきっと、素晴らしい日になるはずだ。
そう信じて、早朝の静けさの中で彼女はそっと、料理を勉強する自分の姿を思い描きながら、頭の中でその瞬間を繰り返し再生していた。
檸檬は夢中で準備をしていた。顔を洗って髪を整え、服に袖を通す。頭の中では、就職先であるレストランのことがぐるぐると駆け巡っていた。
職場まで迷わずに出勤出来るだろうか。同じ職場で働く仲間への挨拶はどのようにしようか。
緊張と期待で胸がいっぱいだ。そう考えながら、キッチンへと向かい、軽く朝食をとる。余裕のある朝を過ごせると思っていた。
しかし、どうやらそれは彼女の勘違いだったらしい。
ふと、リビングの壁時計に目をやると、その針は予想以上に進んでいた。
「えっ、もうこんな時間!?」
時計の針が示しているのは、家を出るわずか十分前。思わず檸檬は立ち上がり、慌てて靴下を履き、カバンを手に取る。
ゆっくりと朝を楽しんでいたはずが、いつの間にか出発の時刻が迫っていたことに気が付いたのだ。夢中で考えていたせいか、時間の流れがやけに早く感じられた。
まるで一瞬のうちに朝が過ぎ去ってしまったかのようだ。急いで玄関に飛び出し、靴を履くと、勢いよくドアを開け放った。
「もうちょっとで遅刻するとこだった!」
玄関を出た檸檬は、青空の下で深呼吸をし、心を落ち着かせる。それでも、期待は変わらず胸の中で跳ね回っている。
檸檬は、慌ただしい足音を立てながら駅に向かって歩いていた。
東京の朝は早い。空はまだ薄く明るくなり始めたばかりである。しかし、通りにはすでに多くの人々が足早に動いている。
スーツ姿のビジネスマン、スマホを見つめながら歩く若者、そして自転車で通り過ぎる配達員。
東京の町は朝から活気に満ち溢れていた。檸檬も、その流れに溶け込むようにして歩を進める。ビルの谷間を抜けるようにして、駅の入り口が見えてきた。遠くからでも人の群れがうごめいているのが分かる。
駅のホームへ急ぐ人々、改札口を通り抜ける人々の姿が、まるで川の流れのようだ。
「まだ間に合うよね…?」
彼女は心の中で呟きながら歩く速度を少し早めた。カバンの中でスマホが震えた。母からの連絡だろうか?だが、今はそれに気を取られる余裕はない。
長蛇の列を作る自動券売機、カードをタッチするたびに鳴り響く改札の音。そして、人の波に飲まれそうな混雑したホーム。檸檬は小走りで階段を駆け上がった。
息を切らしながらふと見上げた空は、ビルに挟まれた狭い空間から一筋の青を覗かせていた。
東京の空は狭いけれど、そこに広がる都会の喧騒と活気は、彼女の胸を高鳴らせる。
列車がホームに滑り込んできた。扉が開き、人々が一斉に乗り込む。檸檬も流れるように車内へ足を踏み入れた。職場の最寄り駅に到着するまで、寿司詰めのような電車に揺られていた。檸檬は、改めて東京がどれだけ多くの人々を飲み込んでいるか実感した。
列車が駅に近づくアナウンスが響き、檸檬はふと顔を上げた。窓の外には都会の喧騒を感じさせるビル群、そしてその間を縫うように走る車やバス。少しだけ背伸びをして、ホームに見える位置に立つと、彼女の職場である最寄り駅に列車がゆっくりと滑り込んでくるのが分かった。
「もうすぐか…」
そう呟くと、檸檬は座っていた座席から立ち上がり、手に持っていたカバンのストラップを肩にかけ直した。車内の人々は無言のまま立ち上がり、出入り口へ向かって列を作った。列車が完全に停止し、扉が音を立てて開いた。冷たい秋の空気が一気に車内に流れ込む。
「やっと着いた…」
ホームに足を踏み出すと、通勤ラッシュのせいか、スーツ姿の人々がすでに急ぎ足で進んでいく。檸檬もその中に溶け込むように歩き出すが、ふと立ち止まり、改札口へ続く階段を見上げた。
これから始まる一日の予感に、胸が少し高鳴るのを感じた。彼女は、駅の改札を出てから、足早に職場へ向かっていた。周囲は朝の光に包まれ、通勤する人々がせわしなく行き交わっていた。
信号を待つ間、檸檬は周囲の車の流れをぼんやりと眺めた。車道を走る車たちは、どれも整然と信号に従いながら進んでいく。
だが、その瞬間、彼女の体に電気が走るような感覚が走った。
遠くから聞こえる、甲高いタイヤの摩擦音。耳の奥に不快な音が突き刺さる。
「まさか…」頭の中で警鐘が鳴り響く。檸檬は反射的に目の前の横断歩道を見つめたが、足がすくんでしまった。
次の瞬間、遠くの車が赤信号を無視して、こちらに突っ込んでくるのを目撃した。車のスピードは明らかに尋常ではない。
「危ない…!」
声を出そうとしたが、声が喉で詰まり、体が動かない。車が彼女の方へと迫ってくる。その瞬間、すべての音が彼女の世界から消え去り、ただ自分と目の前の車だけが残った。
心臓が耳の奥で鳴り響き、時間がゆっくりと流れる感覚に包まれた。嫌な予感は現実になった。
車の金属の光が一瞬だけ反射し、視界が激しく揺れた。強烈な衝撃が檸檬の全身を貫き、足元が浮いた。まるで空中に投げ出されたように、彼女の体は宙を舞い、そのまま地面に叩きつけられた。
意識がぼんやりと浮かび上がる。檸檬は目を開けようとしたが、まぶたが重く、なかなか視界が戻らずにいた。頭の中が混乱している。耳には、遠くで響くサイレンの音や、誰かの慌ただしい声がかすかに聞こえてくる。
まるで夢の中にいるような、現実感のない感覚だった。次に彼女が感じたのは、痛み。体のあちこちに走る痛みだった。
少しでも動かそうとすると激しい痛みが襲ってくる。息を吸い込むたびに、肺まで響くような痛みに、彼女は息を詰めた。体を動かしたいのに、
どこも思うように動かすことが出来なかった。
「ここは…どこ…?」
かすれた声で自問するが、返事はない。次第に視界がはっきりしてきて、青空が目に映り込んだ。見上げた先には電柱が立ち並び、信号が揺れている。周囲に人々が集まっていて、その中の何人かが彼女の方に駆け寄ってくるのが見えた。
「大丈夫ですか!?救急車を呼びました!」
見知らぬ人の声が耳元で響く。彼女は痛みを堪えながら、体を何とか起こそうとするが、力が入らない。頭が重く、目の前がゆらゆらと揺れている。自分が倒れているのは道路の上、車のライトが消えたまま彼女の前に止まっていることに気付いた。
「あぁ…事故…」
断片的な記憶がゆっくりと蘇ってきた。信号が青に変わり、横断歩道を渡ろうとしていたこと。
突然、目の前に車が現れ、次の瞬間には衝撃で宙に放り出されていたこと。そして今、ここに倒れていること。
現実が頭の中にじわじわと戻ってきて、胸が締め付けられるような恐怖が襲ってきた。不安と痛みが彼女の脳内を支配する。救急車のサイレンが近づく中、檸檬はぼんやりと空を見上げた。都会の喧騒がどこか遠くに感じられ、すべてがぼやけていく。
この瞬間、彼女は自分のこれからの生活が一変することを予感していた。事故の瞬間から、すべて変わってしまった。数分後、救急隊員が彼女のそばに駆け寄り、優しく声をかける。ストレッチャーに乗せられ、救急車の中へ運ばれていく。遠のいていく街の風景を見た。檸檬はただ無力感で押しつぶされそうになりながら、そのまま意識を失ってしまった。
檸檬が病院に搬送されてから数日。
彼女は、ぼんやりとした意識の中で、ゆっくりと目を開けた。
最初に目に入ったのは、白い天井、淡い蛍光灯の光、そして独特の消毒液の匂い。檸檬はここが病院だとすぐに気づいたが、体は重く、動かそうとしてもまるで他人の体のように言うことを聞かない。
意識が戻るたび、痛みが体のあちこちを刺すように襲いかかってくる。足が重い。腕も動かない。体中が痛む。
「私…信号を渡ろうとして…そして…」
朧げな記憶が脳裏をよぎる。車が迫り、衝撃を受けて倒れたこと。事故の瞬間の衝撃が何度も何度も頭の中で繰り返され、呼吸が浅くなった。
病室の静けさの中、看護師が静かに入ってきた。
「目が覚めましたか?意識が戻って何よりです。少しずつでも、体をゆっくり休めてくださいね」
看護師の優しい言葉に安心しながらも、檸檬は何かがおかしいと感じた。
体中に痛みはあるが、それ以上に、何か大切なものが欠けているような感覚があった。
「大丈夫ですか?まだ痛みますか?」
看護師がそっと声をかけてくる。檸檬は無言でうなずいたが、頭の片隅に残っている違和感が何か分からなかった。
「少しお水を飲んでくださいね」
看護師が手渡してくれたコップを持ち上げ、唇を湿らせるように一口飲む。
しかし、何も感じない。ただ、冷たい液体が喉を通っていくだけ。冷たさはあるのに、味がしなかった。
「おかしい…」
もう一口、慎重に飲み直してみたが、結果は同じだった。ただ無味の液体が、機械的に体に流れ込んでいく感覚。檸檬は思わず口元に手を当て、呆然とした表情を浮かべた。
「味がしない…」
不安が一気に押し寄せた。看護師に頼んで、今度はスープを持ってきてもらった。スープの香りがほのかに漂ってくるが、口に運んだ途端、それが完全に消えてしまった、温かい液体が舌の上を滑るだけで、塩気も旨味も感じない。まるで自分の舌が、機能を失ったかのようだ。
「どうして…?」
檸檬の手は震え、スプーンを置いた。事故の衝撃で頭に怪我を負ったのかもしれない。だが、目に見える痛みや傷とは別に、もっと深刻な何かが今起きている。彼女の大切な感覚の一つが、失われてしまったという恐怖が襲いかかってきた。
「味が、しない…何も、感じない…」
料理人を目指して上京してきた彼女にとって、
味覚は命そのものであった。食材の微妙な味わいを感じ取り、それを一皿に昇華させる。それが彼女の夢であり、人生であった。
それが、今、たった一度の事故で奪われてしまったのだ。檸檬は喉の奥からこみ上げる叫びを抑えようと、歯を食いしばったが、涙が知らずに頬を伝った。
味覚を失うことが、どれほど自分の存在にとって大きな意味を持つのか、彼女は今痛感していた。美味しいと感じる喜び、料理を通じて人と繋がる幸福。
「もう、以前のように料理することなんて出来ないんだ…」
絶望的な思いが胸を突いた。
料理が好きだった。あの感覚、包丁が食材に触れる音、野菜を炒める時の香り。それが全て遠い過去のものに感じられた。
「これからどうすればいいんだろう…」
目の前のスープは、とっくに冷めていた。檸檬はそのままベッドに横たわり、白い天井を見つめながら、静かに心の中で問い続けた。
夢を失った痛みは、体の傷よりも深く、重くのしかかっていた。事故から数日が経過し、病室の窓から見える景色にも少し慣れ、室内に差し込む朝日が、やけに眩しく感じる。
檸檬はトレーの上に並ぶ食事を見つめていた。スクランブルエッグ、トースト、そして薄く切られたリンゴ。かつてならば、食欲をそそる香りとともに舌の上で味わえるはずだった。しかし、そのどれもが彼女にとっては、ただ食べ物の形をしたものにすぎなかった。体の痛みや怪我は少しずつ回復してきた。それでも、味覚だけは一向に戻る気配がない。
「料理の道は無理かもしれない…」
心の中で、何度もそう呟いていた。味覚を失ったままでは、自分の夢だった料理人になることは不可能だ。今までは、些細な味の変化を感じ取り、その一瞬一瞬を楽しむことが出来た。それが今、何も感じないという現実に向き合う度に、自分が別人になったような気がした。
ある日、彼女の病室のもとに小包が届いた。送り主は田舎に住む祖母からであった。
「おばあちゃんからだ…」
箱を開けると、中には手書きのレシピとともに見覚えのある食材が丁寧に梱包されていた。
それは、彼女が小さい頃に祖母がよく作ってくれた特製オムライスのレシピだ。ふっくらとした卵がライスを包み込み、鮮やかな黄色とケチャップのほのかな甘さと酸味がたまらなく、美味しかった。檸檬は幼い頃、祖母の家に遊びに行く度にこのオムライスを楽しみにしていた。特製オムライスは、彼女にとって「愛情の味」であった。
檸檬はレシピをしばらく見つめた後、深く息を吐いた。
味覚を失った今、何も味わえなかったとしても、祖母の特製レシピを通じてかつての「味」の記憶を呼び起こすことができるかもしれないと……
(続く)
「カンソウメン」悪目 漱石

「なにかくいたい・・」
寝起きそうそう壁へと話しかけた。
頭痛が出るほどの惰眠をむさぼり、遅れながらも勇猛に奮い立つ己を鎮めたあと、夢が現実で現実こそが空想であるかのように思える身体的にも精神的にも麻痺が起こってるいる最中に、その言葉を壁に発した。
空腹は感じてはいた。昨晩を酒とつまみだけで済ませたのが原因であろうことは頭では理解できたが、体は理解しようとはしなかった。
しかし、悲しいことに怠惰な身体は食欲だけでは布団から出ようとはしない。
意識は起きているのに、怠惰な体は一向に起き上がらない。諦めて体が求めている惰眠を提供しようと瞼を閉じるが、このジメジメとした蒸し暑さのせいで、またも妙に現実的で不気味なくそったれな世界に入ってしまう。
寝起きは最悪。というよりも頭の中や目の奥のむずがゆさを感じる。汗が頬を流れるたびに怒りや不快感が収まらない。ラーメン屋の背油のような豚骨臭い重圧な香りのする脂ぎったそれが染みついて黄ばんだシャツは、カビの生えたチョコレートのようなに悪臭がする。
ふと「なぜこのような仕打ちを受けなければならないのか」と悲壮感を感じたが、身体中の痒みがその思考を妨げて、自分がなにを感じていたのかを忘れる。無意識に背中に手を伸ばし爪を立てて力強く何度も搔きむしる。すると、痒みが収まったと同時に痛みが始まった。黒ずんで不潔な爪は、背に広がるクレーターのほかにも赤みがかった若いニキビに直接的に衝撃を与えたようで真っ白だったシャツに赤黒い斑点模様を現した、あまりの痛みに目を細めて口角を広げる。
広義の上の自傷を行っているうちに完全に意識は目覚めたが、先ほども述べたように空腹だけではベットから起き上がるには不十分であった。それにしても記憶がおぼつかない。
思い出そうとアルコールとニコチンで縮みきった脳を絞るが、一体自分は何を思い出そうとしていたかも忘れてしまっている。頭の中も支離滅裂だ。こういう時こそ頭が冴える酒かタバコが欲しくなる。
その時、急に膀胱が痛み出した。なんというか下痢になった時のような腹痛も感じ始めた。
膀胱が独立して便所に駆け込んでくれたらどれほど幸福かとメルヘンなことを思い浮かべる。
それから、何度か寝返りをうったあと、生まれたての小鹿野ように、墓から這い出た亡者が獲物を追い詰めるかのようにトイレへと向かった。ドタドタと怪獣のように歩くが、首や腰をもちろん、肩や肘、膝、足首、さらには頭蓋や顎までもがボキボキ心地の良い音をたて快い。
今日初めて立ち上がったせいか、二日酔いのせいかはわからないが、脳みそがつかまれてそのままかき混ぜられたような気分になる。口の中の唾液はマラソンをした後の少し塩味で苦い味がしており、口内炎に舌が触れるたびに痺れた。
トイレの扉の前までたどり着きドアを開けようとするも立て付けが悪いのかなかなか開かなかった。こういう扉には対応策があり、DV彼氏のように乱暴にするのではなく、飼い主系彼氏のようにゆっくりとドアノブに触れて冷静に引くとあれほどネチネチとしていた扉は開いた。
用を足し終えた後、台所へと向かう。
調理がめんどくさかったため、乾燥麺を食おうと台所に散らばるビニール袋や段ボールを片っ端からひっくり返し漁る。
今のところはお目当てのインスタント麺は見つかっていないが、そのうち見つかるだろうと未来の自分にまかせ、先にお湯でも沸かそうと蛇口をひねるが水は流れない。故障を疑ったが、ドアのポストのすきまからあふれる封筒をみて納得した。
「へへ、へへへへ、、ごほっごほ」
渇いた笑いと咳が出る。現状はひどかったが愉快だった。そうだ、支払っていないのだから蛇口をひねっても水が出ないのは当然だ。
それにしても頭痛と咳が止まらない。電力という血液を失いただの置物と化した冷蔵庫から牛乳を取りだしてパックごと飲む。それは暖かくドロドロとしていた。こんなもので腹は膨れないし、逆に体調を崩すことになるだろう。
だが、今あるものは腐った乳製品もどきしかなく。そもそも、電気がつながらないとわかっていながら、なぜ要冷蔵食品を購入したのだろうか。まったく記憶にない。なるほど、これが政治家の思いなのかもしれない。
苦労しながらも近所のコンビニの給湯器でインスタント麺にお湯を注ぐまでは終わった。
だが、周りには人が居た。研修中と書いたバッジを付けた肌が少し黒く、彫りが深い非正規社員や自分の子供を制御できない金髪の女性、コピー機の前であたふたする若い田舎者の男などである。
こんな蟲毒の中での3分間が地獄である。中国人の団体旅行者が食事を行ったあとかのようなに食いカスがあたり一面に広がるフードコートでネットに繋がらないスマホをイジる。イジる。イジる。飽きる。
用があるわけではないがトイレへと歩を進めるが、故障中という札が下げられており使用できないようガムテープなどで封鎖されていた。おおよそ回転率を上げるための店側の工夫であろうが、自宅に帰っても汲み取り式の疑似ぼっとん便所しか使えない者からしたら不便であった。
店内を右往左往したり、買わない酒や煙草を眺めているうちに3分はたったため、フードコートに戻る。
出来上がったカップ麺の蓋を開けるとジャンクフード特有の身体に悪そうな臭いの湯気が出た。割り箸で天地返しを行ってからすする。
「、んぐっ、、ゲホゲホ、、」
勢いよく啜りすぎたためか、汁が熱かったためかわからなかったが蒸せた。声には出さなかったが味がしなかった。正確には血管が詰まりそうな油の味しか感じなかった。決して美味いとは言えない。昔はよくここに白飯を投入して猫飯をしていたが今は麺を食いきると汁は捨てている。
なんて美味しくないのだろうか。こんな畜生の残飯に満腹の幸福感を得られるはずがなかった。
そもそもの話、インスタント麺のような味が濃いくらいしか取り柄のない糖尿病患者製造食にそこまでのことなどできようか。否、無理だ。
だいたい、なぜこんなにも料理とは面倒なのだろうか。お湯を入れるだけでもこうも面倒なのだから、食事なんてなおさら面倒に違いない。全てが馬鹿らしく面倒だった。
(完)
「道徳の氾濫」八百本 光闇

自身の疾患を抱えながら生活をしていく。
その中で、様々な奇妙な出来事が起こる。ディストピア長編小説。
『――共感性の著しい欠如、儀式的な反復行動、若干の他害行為、衝動性。以上の症状が認められるため、国立栄養補給施設『たいよう』に入所することが適切であると判断されました。入所日は■■年■月■日です。当日の昼頃に職員が現住所まで出迎えます。名倉 光様。施設での新たなる旅立ちを心よりお祝い申し上げます。安心して入所の時をお待ちください。』
私はリビングでPCを開いて、招集票の最後段をゆっくり読む。私の欠陥、入所日、住居の移転場所さえ知ればいい。それ以外の部分は、煩わしい表現と長文に対して、中身がない。100ページほどあった招集票の文章は、届いた初日に全て暗記したが、最後段以外の内容の空虚さに気づいたとき、暗記したことを少し後悔した。
私は招集表の最後段を読み終わると、PCを閉じ、テレビをつけた。リモコンを操作し、挿入されていたCDを再生する。『たいよう』にて利用者と職員が笑顔で生活する動画が流れ始めた。職員が迎えにくるまで、動画を聞き流して過ごそうと思った。動画から音声が流れ始めると、せわしなくしていた両親もリビングに来て、テレビに注視した。
――施設のうち、症状が軽度な者が来る、『たいよう』を利用するヒトは『たいようの子』と呼ばれ、職員の人たちと、毎日楽しい生活を送っています。
両親は、テレビを見ながら何度も頷く。私に手を焼く彼らも、『たいよう』なら私を安全に保護できるだろうと信じた。
――栄養補給施設全体として、利用者に特別な栄養補給を行うことで、脳を治療します。成功例は多くあり、治療後、社会に深く貢献する人となります。施設に行くこと自体が、非常に名誉なことです。
椅子に深く座り、動画を眺めていると、うとうとしてきた。昼食後の朗らかな空気に当たるとき、私はいつも眠たくなる。暖かな空気を感じて、眠るか眠らないかの間でさまようことが、最も平穏で、私はよくやっていた。
――非行を繰り返すヒトも、死刑囚に相当するヒトも、栄養補給を終えた後には、社会に深く貢献する人間となりました。
一方、両親はまだそわそわしていた。母親は、しきりに何かいらないかと訊き、父親は、施設での生活の注意事項を教えた。以前にも何度も聞かされていたから、私は曖昧に答えた。
――社会のお荷物だったどのようなヒトも、栄養補給という過程を経て、必ず社会貢献が出来る人間に仕上げましょう。
インターフォンが鳴った。私は目を覚ました。扉を開けると、柔和そうな男女二人が、笑顔で立っていた。ネームプレートには、『国立栄養補給施設 たいよう』と書かれている。
「あなたは……お父さん、ですか?」女性職員は、私に目線を合わせるために首を上げ、控えめに訊いた。
「私は、『たいよう』の入所予定である名倉光です」
「おやおや、あらまあ~! コウちゃん!」
女性職員は、私が入所予定者だと分かった途端、幼げな口調になった。「ドキドキしたよね~でも大丈夫だから。お兄さんお姉さんと一緒に行けば大丈夫だからね!」彼女は私の手を掴んで振る。私は人肌が好きではないため、振り払いたかったが、それは礼儀に反するからしない。
「ああ、お父さん、お母さん。このたびは――」男性職員は、家に上がり、両親へ歩み寄った。
「コウちゃんを預けてくれるんですよねぇ! 本当にありがとうございます!」両親も男性職員に満面の笑みで受け答え、リビングの奥へと行く。彼らとの話を聞きたかったが、三人は私には話が聞こえないほど離れてしまった。また、私は女性職員と話しているから、突然彼女から離れるわけにもいかない。「トラブルを起こさずにずっと待っててくれたの? すごいすごい!」
女性職員は過剰なほど拍手をして、私を賞賛しようとする。「コウちゃんは急に予定が変わったりしたら、困ってパニックになるんだもんね? でもよくパニックにならなかったね!」
確かに私は想定外のことが起こるのが嫌いだが、それだけでパニックにはならない。幼少期はともかく、今は割り切りがついていて、日常生活に大きな影響を与えないほど、感情の発露を抑えられるようになっている。反論しようとしたが、彼女は私が口を挟む間もなく、まくし立てるから、何も言えなかったし、彼女の発言をいくつも聞き逃していた。
「新しい環境に行ってパニックになっても大丈夫! 施設では、私たちみたいなお兄さんお姉さんがたくさんいるからさ、もし困りごとがあったら何でも言ってよね!」
「わかりました」
私の同意するそぶりを見た女性職員は、背伸びをして、頭を撫でた。
「さて! お母さんお父さんに最後の挨拶をしてこよっか!」
女性職員は両親に指をさした。部屋の隅で、男性職員と話している。
私は両親のところに行った。両親はどちらも若干の笑みを浮かべていたが、目尻には涙がある。
「久しく、会えなくなると思います」
とりあえず別れの言葉を言うと、母親は息を深く吸って、私を抱擁した。「コウちゃん、元気でね。私たちは大丈夫だから。ええ、本当に大丈夫。実験に協力できるなんて、とても名誉なことなんだからね?」その抱擁は普段より長い時間を要した。力が強く、息がしずらい。加齢臭と香水の匂いが混ざって、えずきそうになる。だが、私は拒絶できない。かつて母親に抱擁されたとき、私が人肌をいやがって、母親を突き放すと、彼女は泣き出し、私を様々な言葉で罵倒した。父親も、なぜ母親の立場で物を考えられないのかと説教をした。それから私は、母親に抱きしめられたら突き放してはいけないと暗記した。
母親が私をやっと手放すと、彼女は微笑んだ。安楽な笑顔だ。目元の皺が、いくつか消えたように思う。しかし、涙をもっと流していたので、私には彼女がどういう気分なのかは知らなかったが、ともかく、「今までありがとうございました」と、言った。
「もう。相変わらず愛想ないんだから。……でも、それもきっと治るよね」
「ええ、そのための施設ですから」
「ははっ、まるで施設の人みたいな言いぶりだなぁ」
父親が高く笑った。「ほら、これくらいは持っていけ」
彼は小さなトートバッグを私に与えた。「中に、家族写真とか、コウちゃんが気に入ってる本とか、免許証とかが入ってるから」
「後で差し入れすることもできます」
「今持ってったほうがいいの! 送るのにも時間かかるし、これから長く住むとこに手ぶらで行くってさ、なんか心配だろ?」
「多くの人にとってはそうだと思います」
「多くの人の一員になるためにそうすんだよ。ほら、持ってけ」
私は同意して、これだけ持って行くことにした。職員たちは、いつの間にか外で待っていた。一般に人を待たせるのは良くないことなので、私は早く出たがった。
「では、さようなら」
私は家を出て、まっすぐ彼らの元へ歩く。扉に両親がいる気配がしたが、私にはもう関係のない場所だから、振り返らなかった。
職員らと最寄り駅のロータリーまで歩くと、太陽のマークで塗装されたバスが止まっていた。20人ほどの人が一列に並び、順々にバスに乗り込んでいる。下は十代ごろ、上は二十代前半ごろに見える。
「入り口にある名簿表の通りに座ってね」
「わかりました。あなたたちは、これからどうするのですか?」
「また別の仕事があるんだよー。コウちゃんを無事にバスに乗せたらバイバイするの。でも、明日から戻ってくるからね! 心配しないで!」
「もちろん、心配しません。あなたたちはこの職業の適性試験に合格した職員なので」
私がそう言うと、職員二人は首を斜めに傾け、目を細めた。私はそれを横目で見ながら、別れの挨拶を言って彼らから離れ、列の最後尾に並んだ。私の担当以外の職員も何人かいて、利用者らをあやしていた。
「たいようの子たち! そろそろ出発するよ!」
私は名簿表に指定された通り、真ん中の窓側の席に座った。窓からは職員たちと、乗り込もうとしている利用者らが見えた。席の隣には誰もいないが、たぶんもう少しで乗り込むだろう。
バスの中では、利用者同士の会話が響く。私は目を瞑って、バスの独特な匂いと、背中に伝わる振動を感じながら、出発するのを待った。
バスが揺れると、目が覚めた。いつの間にか、窓が黒いカーテンで塞がれていた。
外からの光が入らなくても、眩しいほど明るい電球のおかげで、太陽が差し込んでいないにもかかわらず明るい。また、壁や天井には青空が描かれていて、案外開放的である。
「なぁ、お前、名前なんて言うんだ?」小学生か中学生くらいの少年が、隣にいる私を見かねて話しかけた。私が眠っていた間に座ったのだろう。
「名倉光です」
「ふーん、じゃあコウでいい?」
「はい、何でもいいです」
「おっけ。俺は比谷翼。ツバサって呼んでくれ。小6で――まあ、ここでは年齢なんて関係ないか」
ツバサはキョロキョロと辺りを見た。「コウみたいな大人から、俺くらいの奴まで、色々いるからなあ」
私も簡単な自己紹介を済ますと、ツバサは突然話題を変えた。「なぁ、なんかさ、この感じ、ムショ送りになったみたいでワクワクするなぁ」漫画でこういう場面、見たんだ。ツバサは足を揺らして、屈託なく笑う。
「刑務所は一般にはワクワクする場所ではありません。刑務所は刑を受ける人間が送られる場所であり――」
「俺がワクワクするんだよ! 一般とか、どうでもいいし。ってかさ、ここに来るってことは、お前も一般の人間じゃないだろ?」
「よく言われます」
「まぁ、コウの話し方聞けばすぐ分かるけど」
「それもよく言われます」
沈黙が続いた。窓の方をよく見ると、遮光カーテンが完全には閉まりきっておらず、カーテンの端から少し外が見えた。隣街から、郊外へと出ている。――刑務所といえば脱出だ。そうして、脱出するには脱出経路が必要である。左右の揺れも勘案して、施設に着いたら地図でも書いてみようと思った。
しばらく外を見ていると、ツバサは突然言った。
「で、お前の一般じゃない部分って、具体的に何なんだ?」
私はツバサの方を向き直して、招集票の言葉を暗唱する。
「招集票の症状欄には、『共感性の著しい欠如、儀式的な反復行動、若干の他害行為、衝動性』と、書いてありました」
「へぇ~! そんな難しそうな言葉、よく覚えてられるな! ってか、他害すんの? こえー!」
ツバサが過度に驚いているように見えたから、私は弁明のために、なぜこう書かれたかを推察し、それを説明しなければいけない。
「数ヶ月前、前職で顧客を衝動的に殴ったため、相手は打撲等の軽傷を負いました。私は留置場で取り調べを受けましたが、栄養補給か自宅留置が必要だと判断されたため、両親は前者を選び、施設の入所願を出しました」
私が話終わると、ツバサが真顔で黙っているのに気づいた。この表情の場合、相手は怒っていることが多いから、何か補足しなければいけない。
「両親に他害について話すのを止めるよう言われていたのを忘れていました。この話は忘れてください」
「いや、こんな凄い奴会ったことなくて、カッコいいなって」
「カッコいい?」
ツバサの発言を疑問に思ったころには口に出ていた。「一般には、他害行為はカッコいいとされてはいません。ですが、特定の年齢層に多く見られる、厨二病という特性を持っていた場合はその限りではありません。しかしこの語は本来……」
「おいおい! 俺のことをそうやってバカ正直に判断するのはやめろ」
「わかりました」
ツバサはため息をついた。が、顔は笑っている。
「それにしてもコウってさ、一昔前の人型ロボットでもそんな喋り方しないぞ、タメ語でいいじゃん、俺、年下だし」
「他人に合わせて口調を変える術を知らないので、誰に対してもこのようにしています。常に敬語だったら、人々の反感を買わないでしょう」
「ふーん、コウなりに色々考えてるんだなぁ。ま、とにかく、施設行ってもよろしくな! 俺たちもう友達だから」
「友達?」
「そうだぞ! ほら!」
ツバサは笑顔で手の平を見せた。
「これは何を意味するポーズですか?」
「知らないのか? ハイタッチだぞハイタッチ! ほら手を、上に出して重ね合うの!」
「はい。手を上にあげます」
手を上にあげると、ツバサは立ち上がってそこに手を叩いた。高い音が鳴った。
「これがハイタッチというのですか。暗記しておきます」
「次はちゃんと手を相手の位置に合わせることをアンキしとけよ。いつか確認テストするからさ……てか、コウって友達いるのか?」
「ツバサさんがいます」
私が言うと、ツバサは、眉をひそめて、腕を組んだ。
「ああ、俺が悪かったな」
ツバサの言ったことの意味を考えようとすると、彼は素早く言葉を続けたから考えられなかった。「施設でいっぱい友達つくればいいじゃん! そのためにもさ、今から友達の会話しよう!」
ツバサは彼の足下に置かれたリュックサックから漫画本をいくつか取り出した。
「これ、俺のおすすめ漫画。コウって漫画に興味ある? おすすめの漫画教えていい?」
「はい、おねがいします」
「へへっ、じゃあまず――」
それから、ツバサは饒舌に語り始めた。刑務所から脱出しようとして失敗する話や、ロボットが心を得たように見えたが、実は単なる模倣だった話などだ。
「よかったら、どれか読む?」
ツバサはリュックサックから漫画本を私に差し出す。私は一番右の漫画本を手に取って読む。仕事をこなす主人公の苦悩が書かれた硬派な話だ。長時間借りているのは悪いことなので、最初はすぐ返そうと思ったが、いつの間にか全部読んでいた。私が本を返すと、ツバサは明らかに気分が良くなっていた。
「すごい集中力だな! 良かったろ?」
「はい、良かったです。ここでの重要なトピックは――」
私たちがさっきの漫画について喋っていると、バスが大きく揺れて止まった。しばらく止まった後、また動き出し、また止まった。窓を覆っていたカーテンが開いた。窓からは、施設であろう建物が見える。
「喋りすぎちゃったかな……」ツバサは小さく言った。
「喋りすぎていた時は指摘します」
「そりゃありがたい。話しすぎることがたまにあるんだ」
ツバサは漫画を片付けると、窓の方に首を伸ばした。「へぇ……ここがしばらく住むとこかぁ」
施設の外形は、幼稚園を思わせた。太陽や空、草原が描かれたカラフルな屋根と壁で、外郭を覆う柵には『栄養補給施設 たいよう』と書かれている。
「なんか、幼稚園みたいだなぁ」
「同意します」
「うひょ、初めてコウに共感された」ツバサは椅子に座りなおした。
「私にも共感をすることが可能です。私はミラーニューロンが完全に欠落しているわけではありません」
「はいはい……」
バスの扉が開いた。一番前の席に座っていた職員が立ち上がって利用者らを誘導する。「はーい、たいようの子たち! たいように到着しましたよー! 前の子から順番に降りましょうねー!」
バスから出ると、外には引率の職員がいた。
「二列で好きなところに並んでねー!」私とツバサは隣に並んで待った。しばらくすると、バスから全員が出てきて、人数確認をしたのち、列は動き出した。
列は施設に入り、エントランスにて止まった。職員の話が聞けるよう、職員を囲うように並ぶ。
施設のエントランスは病院のような風体だった。受付が扉から入って右奥にあり、一般受付、面会受付などで分かれている。受付の前には椅子が沢山並ぶ。正面奥は、左右二つに通路がある。片方の通路へ行く道の壁には、たいようの子はこちら! と張り紙が張られている。職員は、正面奥のホワイトボードに貼られた名前と番号が書かれた紙を指さした。
「たいようの子たちはねー、今から、それぞれ『おうち』っていう、みんなが住む場所に行ってもらいます! ここからみんなのおなまえを探しておうちに行ってね! おうちにはみんなのセンパイのたいようの子がいるよ! その子にたいようについてを教えてもらってね!」
職員は、大きく片手を上げた。
「はい、いいですかー?」
利用者らは、頷いたり、首をかしげたりした。それを見かねたのか、職員は叫んだ。
「あー、たいようの子なら、『いいですかー?』って言われたら、『はーい!』って元気な声で言ってね? はい、いいですかー?」
「はーい!」
「はぁ?」
私と、他の何人かは職員に指定されたかけ声を言ったが、ツバサは呆れた声を出した。ツバサは腕を組んで、しきりに職員を見つめる。
「何か困ったら私のところに来てね! じゃあ解散!」
職員が言うなり、利用者の声で騒がしくなった。みなが一斉に掲示板の所に行ったせいで、その辺りはごったがえした。
「人がまばらになったら見に行きましょう」
「ああ……」ツバサは職員をまだ目で追う。
「どうしましたか?」
「いや? なんでもない」
「そうですか」ツバサがなんでもないと言うのならそうなのだろう。
張り紙に書かれた氏名と部屋番号をそれぞれ探すと、我々は同じ部屋だということがわかった。
ツバサは、あからさまに手を振り回して、もっと笑顔になって、寮へと歩く。これから私たちが暮らすことになる寮――おうちは、主たる建物から、少し離れた場所にあった。私たちは、看板と、利用者のまばらな列に従って、中庭を横切り、おうちの建物に入る。一階の廊下の突き当たりに、我々の部屋があった。
「ここに、もう誰かいるよな……ああ、ちょっと緊張してきた」
「そうですか? 開けます」
「えちょっとま……」
私は扉を開けた。一人の少女が、満面の笑みで迎えた。
「えーっと……こんにちは! この『おうち』の『おねえさん』の……朱木夏美。ナツミって呼んで!」
私たちはナツミに促され、部屋の中心にある和机に座った。部屋は8畳ほどの和室で、テレビや本棚、クローゼットがある。ものの配置だけ見れば一般的な旅館と変わらない。だが、所々で一般の旅館とは違うところがある。たとえば、天井や壁は、たいようマークの壁紙が装飾されているし、置かれているティッシュは、たいようのロゴがある。さらに、上座の壁紙には、絵がある。
ナツミは高校生くらいに見えた。少なくとも二次性徴は終わっていると思う。彼女はニコニコとしていた。逆にツバサは緊張した面持ちで、固まっている。
私は座布団に座るなり、机に置かれた個包装のせんべいを取って、食べた。バリバリと軽快な音が鳴る。
「えー? これ、食べていいのか?」ツバサは私の方を見ると眉をひそめた。
「あ……」彼に言われてようやく、来客用に置いてありそうな菓子を食べる時は断りを入れなければならないことを思い出した。私は口を動かすのを止めて、彼女を見る。食べていいかと訊きたかったが、何かを口に含みながら喋るのはよくないので、黙って彼女を見るしかない。
だが、彼女は怒っている様子はなかった。むしろ笑っていた。
「全然、遠慮しなくていいよ!」
「あ、そう? じゃあ、いただきます」
ツバサが食べ始めたから、私も安心して食べ続ける。
「そろそろ夕食だから、ほどほどにね」
「おっけー。……ってか、このせんべい美味しいな!」
「『たいようポイント』がたくさんあるから色々取り寄せできるんだよ?」
「たいよう――何?」
「ああ、ここのシステムのことは後で話すね。食べたら二人とも自己紹介して! あと、たいようの制服の着替えね!」
せんべいを食べ終わると私たちは簡単な自己紹介をした。ツバサは名前に加え、私にそうしたように、彼が好きな漫画を紹介した。ただ、少し手短に済ませたような気がした。それからたいようの制服に着替えをした。
着替えが終わると、まだ夕食には時間があるというので、ツバサとナツミは、他愛のないことを話し始めた。ツバサは緊張した感じが全くなくなっていて、自然に会話していた。 私は二人の会話を、部屋の構造を観察しながら聞き流す。扉付近には、投函物を入れるためのポストがある。一番奥がこの部屋だが、その手前には、トイレの個室がある。
少し経って、ナツミが時計を見ると立ち上がった。そろそろ18時になりそうだった。「さて、食堂に行こっか! このかぞくの『おねえさん』として、食堂やシステムのことを教えないとね!」
三人がそれぞれ部屋の鍵を持って、あとは手ぶらで部屋から出た。おうちから本館への連絡通路を渡る。
連絡通路は、寮の廊下よりも、色とりどりになっていて、目に眩しい。様々な利用者と思われる人が、食堂へ向かっていた。だいたいは4人か5人組で、3人の部屋は珍しいようだった。
食堂へ入ると、入り口付近に利用者であろう人が一人、立っていた。尋常でない様子である。
彼は質量感のある大きな看板を首から下げ、両手と両足を縛られていて、身動きが取れない様子だった。首と手足首の周りが、赤くなっている。
彼はずっと震えていて、今にも泣き出しそうだ。だが、他の人は彼を一瞥するだけで、彼を避けて食堂へと進んでいる。それか、そもそも人が多いから見えていない。私は話すのに夢中になって先へと進んでいるナツミやツバサや、他の者らを、横目で見ながら、彼の前で立ち止まり、看板の文字を読んだ。
『私は人を殴りました。私は衝動を制御できない虫未満の存在です。罰:夕食抜き 餌を与えないでください』
私は看板の意味することを考えるために、しばらく彼の様子を見た。彼は私が観察している事を認めると、涙をたたえながら目を細める。身体を震わせ、それから俯いた。ネームプレートには『2043 ケイ』と書かれている。彼を示す番号と、名前のカナ表示である。
考えていると、私と同じくらいの身長のある職員が歩いてきて、朗らかに笑った。
「おいおい立ち止まるな、見世物じゃないんだから」
「見世物でなければ、彼は何のためにここにいるのですか?」
「見たら分かるだろ、こいつは人を殴ったから罰を受けているんだ。食堂に置いておくことで、食欲と衝動性とを戦わせてるんだ」
私は納得し、頷いた。私は彼から離れ、ナツミたちの元へ行く。ナツミらは食堂の席に座っている。彼らの元へ来ると、ナツミは既に料理を二人ぶん貰っていたらしく、私の席の前にも料理が置かれていた。
「コウ、何かあったの?」
「あの人を見ていました」私はケイに指をさした。
「ああ、あの子……」
ナツミは彼を哀れむような繊細な声で言う。
「よく違反を起こしてる子として有名なの。いつもああいう罰を受けて痛い目見てるっていうのに、全然直さないんだよね」
「ここでは何か違反をすると、あのようになるのですか?」
「うん、重大な違反とかは。一回経験したら、もうあんな風にはなりたくない! って思うから、普通は何度も違反を起こすことはないんだけどね」
ナツミはため息をついて、彼をにらんだ。
「本当に、アレはできない子だよ」
「なるほど。特定の人物を見せしめにすることで、他の利用者をおびえさせ、違反を少なくしているのですか」
私が言うと、ナツミは私の服の裾を掴んだ。
「たいようを悪く言わないで!」
そう叫び、にらむ。私は発言が正当であると弁明しなければいけない。
「たいようを悪いとは言っていません。この施設に少しでも早く適応するため、特徴を言語化しているだけです。さらに、このような見せしめは、社会でもよく使われる手法です。たとえば、最近では、承諾を得た確定死刑囚を臓器提供者にする法律が施行されました」
「おいおい、なんの話だー? 早く飯にしよう? 俺さ、飯食べたくてウズウズしてきた!」
ツバサは大げさに手をたたいた。私はハッとして、頷いた。こういう時には、もう何も喋らないようにするのが良い。
「ここの所長さんが来てからご飯にするんだよ。そろそろ来るかな……あっ、噂をすれば」
懲罰を受けている彼がいない方の扉から、恰幅のいい中年の男性が入ってきた。彼は笑みをたたえている。目元の皺も、普段からよく笑みを浮かべたような形をしている。彼は食堂の前の、演説台のような所に立つ。マイクを手に取った。
「さて、私はこの『たいよう』の所長である、黒崎 敬一郎と申します。新しく来てくれた、たいようの子たち。よろしくね」
「よろしくー!」利用者の中でも年少の者が声をあげる。
「ここのルールなどは、『おにいさん』『おねえさん』から詳しく聞いてね。生活は、かぞく単位で物事を進めるよう、心がけてください。
……さーて、こんなおじさんのお話聞いてても面白くないから、さっそくいただきますしちゃいましょうか。私が手を合わせていただきますって言ったら、みんなもいただきますって言ってね。お食事たちに感謝を込めるんだよ」
所長は手を合わせた。
「さて、今、この食堂に座っているいい子たち。おててを合わせてー?」
彼が言うと、他の人が手を合わせた。私も手を合わせる。
「いただきます!」
所長と利用者らはそう言って、食事を食べ始めた。
「うーん、すごいウマい!」ツバサは食糧を口に入れると、恍惚とした笑みを浮かべた。私も食べることにした。ミールから口に入れる。数年前、にわかに台頭した人工肉の味がする。豚肉に近い味だが、見た目は厚切りのステーキである。噛むと肉汁が口の中でとろけ、じんわりと舌に響く。主菜、副菜、主食の順で、正確に三角食べをしていくことにする。
「そう、本当に美味しいんだよ」
「無限に食えるじゃん!」
「そうそう、無限に食ったほうがいいよ! あと、おかわりも! 『たいようポイント』が手に入れられるからね」
「たいようポイントってのは何だ?」
「ああ、今から説明するね。たいようポイントっていうのは、ここの規則を守ったら増えるポイント! 逆に、規則を破ると減っちゃうの。で、たいようポイントを一定値まで貯めたら、色々特典が貰えたり、ここを『卒業』できるのよ!」
副菜のサラダは、生野菜が中心で、それぞれの机の中心に置かれているドレッシングをかけて食べる。だが、ドレッシングの口が普段使うものと違っていたので、かけ過ぎてしまった。野菜の味があまり感じられない。
「ふーん。とりあえず、そのポイントを貯めるのを目標にすればいいのか?」
白米を食べ、味噌汁も飲む。暖かいものが喉を通る。
「うん。規則に関してはその都度教えていくとして……とりあえず、沢山ご飯を食べたらたいようポイントが上がるから、いっぱい食べよう!」
「おっけ!」
それから、彼らはまた他愛のない話をし始めた。私は三角食べのサイクルを続ける。
しばらくして、プレートの内容物を全て消費した。私は新たな食糧を取りに行くために、立ち上がる。
「めちゃめちゃ食べるのに集中してたな。最初らへんの話聞いてたか?」
「音は聞こえてきました」
「聞いてないってことじゃん!」ツバサは笑いながら言った。
「規則を守ればいいということですか?」
「まぁそういうこと。あと、ご飯をいっぱい食べたり、他の人のお手伝いとかをすればいいんだよ」おかわりはあっち。ナツミは演説台の左、職員が何人か食事を構えているところを指さした。
「では、今から『ご飯をいっぱい食べたり』します」
私はナツミが提示した場所に行き、職員から食事を一人ぶん貰う。席に戻ろうと歩くと、声を掛けられた。
「あのっ……コウさん、ですよね?」職員の女性がふいに私に声をかけた。少しおどおどした様子である。
「はい。あなたは?」
「ああっ、えーっと、突然話しかけてごめんなさい……私は、ここの職員になったばかりの、マメっていいます」
彼女の身長は高いほうだと思うが、猫背のせいでナツミと同じくらいに感じられる。
「私に何か用ですか?」
「えーっと、食事が終わったあと、一瞬私のところに来てほしいんだ。ちょっと話したいことがあって」
私が返答する前に、彼女は急いで補足した。
「あっ、ナツミちゃんには私の名前を言わないでね……職員に呼ばれたから先に戻ってて、って言えばいいから……」
私は頷いて、席に戻った。マメの名前を伏せて、職員と話があるから食事が終われば先に戻って欲しい旨を話した。ナツミとツバサは部屋に一人で戻れるか心配したが、私の記憶力について言うと、快く承諾した。
食事のあと、利用者たちを一通り見送ると、
マメが呼びかけた。猫背が目立ち、目が泳いでいる。「あなたが、ナツミちゃんと同じかぞくになった一人ですよね」
「私と、ツバサさんが配属されました」
「私は、つい最近までナツミちゃんのかぞくだったんです。たいようポイントが貯まって、上の人から認められて……最近ここで働き始めました」
「たいようポイントが貯まった者はここから出所できるのではないのですか?」
「ええ。そうなんですが、この仕事は、社会に出るための更なる訓練として、一時的にいるだけなんです。職員にも、二種類いるんですよ。施設内から職員になった『ナカ』の者と、施設外から就職してきた『ソト』の者。まあ、ナカの者はアルバイトのようなものですから、ソトの者のようなことはできないんですけどね……あっ! あんまり利用者にには言っちゃだめだな……」
「口外しないので心配する必要はありません」
職員が二種類いることは、私は知らなかった。知らないことを知ることは良いことだから、私は嬉しい。だが、本題についてを聞かなければいけない。
「本題に移りますが、あなたはナツミさんに何か言いたいことがあるから私に声をかけたのですか?」
「うん……ナツミちゃん、大丈夫かなって思って。どうだった?」
「やや施設に関して過剰なところがあるように見受けられますが、私は施設に来たばかりなので、それが一般的なものなのかは、分かりません。ただ、概ね大丈夫だと思われます」
「そっか……最近私がナカの職員になってから、彼女、焦っているような気がして。規則も今までよりちゃんと守るようになったんだ」
「規則を守るのは良いことでは?」
「もちろん良いことだけど、その罰がね。身体の懲罰なんて、過激すぎる……ああ、ごめんね。こんな話しちゃって」
私は彼がいたところを見た。職員にどこかに連れて行かれ、もう誰もいない。
「何かを知ることは、良いことなので、心配する必要はありません」
私は少しして言葉を続ける。「何か彼女に関して注意することはありますか?」
「彼女が精神的に不安定になったら、励ましてほしい。職員になっちゃったせいで、あんまり関われなくなっちゃって……」
「利用者と関わってはいけないという規則があるのですか?」
「ないけど、抵抗があって。ナカの職員たちは、みんなあんまり元のおうちに来ないから……」
「それなら問題ないと推察します。規則に書いてないなら、特段処罰などを受けないでしょう。
心配ならば、職員としてでも来た方が、ナツミさんの心身に良い影響を与えると思います」
マメは少し間を置いて、顔をぱっと明るくした。
「そうだね! 雰囲気をよくしたらソトの職員から認められてすぐに卒業できると思うし!」
「……なぜそれほど卒業したいのですか?」ナツミもマメも、卒業についてを気にかけているようだから気になる。
「うーん」マメは首をかしげた。「たしかになんでなんだろう?」
「わからなかったら、無理して言わなくていいです」理由がわからないのはよくあることだ。
マメは腕を組んで苦笑いをする。「私の宿題にするね! なんで卒業したいかって話。次、二人きりで話すときに教えるよ」
「わかりました」
「代わりに、ナツミちゃんが落ち込んでたりしたとき……もちろんツバサくんもだけど、助けてくれる?」
「そうできるよう努めます」
「ありがとう」
マメは満面の笑みを浮かべた。私はその表情についてを考えながら、食堂を出た。
私が部屋に戻るために廊下を歩いていると、通路の隅で、さっきの少年と職員が話していた。少年はもう看板や拘束を外されている。だが、肌の痛々しい傷はまだ癒えていない。私は立ち止まって話を聞いた。
「お前は使えないなぁ。本当に、無能だよ、無能。これじゃあさ、一生『卒業』できないよ。お前がいるおかげで、周りに迷惑がかかるしさ、いるだけ無駄なんだよ!」職員は怒鳴った。私は大きな音が苦手だから、早く行きたかったが、なぜか離れがたかった。
「ごめんなさい……」
「でさ、あの件、承諾してくれる?」
「まだ……」
「ふーん。さっさと決めろよ? お前が優柔不断にウダウダ悩めば悩むほど、周りに迷惑がかかるの、覚えといて?」
「うん……」
「じゃ、さようなら。おうちに戻って」
少年は歩き出した。話が終わったから、私も歩き出すと、少年は私に気づいたようで、歩幅を合わせた。
「あ……さっきの、たいようの……」
「名倉光と言います」
「コウ……あのさ!」
少年は言いかけて、私の後ろのものに目を見開いて、黙った。振り向くと、さっきの大柄な職員が私たちを見ていた。
「あ、いや……」
少年も彼の視線に気づいたようで、言いよどむ。
少年は黙って廊下を走っていった。彼がいなくなると、職員も目線を引っ込めた。私は彼を追わずに、そのままおうちに帰った。
「職員となんの話してたの?」
部屋に行くまでも、戻っても、ずっと、脳裏には彼がいる。別のことを考えようとしても、彼が邪魔をする。非行、懲罰、怒声……。
「職員とちょっとした話をしました」私はナツミの問いに適当に応え、壁にもたれる。
不穏な予兆があった。ちょっと感覚が過敏になっているような気がする。部屋の明かりが、眩しいような気がして、頭が痛い。
ツバサは部屋中を歩き回って、探索していた。
「さっきはあんまり部屋の様子あんまり見れなかったけど、ガチで旅館じゃん。俺ここ好きなんだよね」
ツバサは部屋の奥にある、向き合った椅子の片方に座った。「旅館に行ったとき絶対座るやつ。自然の景色も綺麗だし、俺ここにずっといるかも」
「うーん、私、家族と旅行したことないからさ……よく、わかんないや」
「え? ああ……ごめん」ツバサは突然ナツミに謝った。
「ん、何が?」
「ああいや、何でもない」
「うん?」
「……そんなことよりさ! 出ようよ! 外に! 自由時間なんだろ?」
「うん。きっと楽しいよ! いろいろな遊具があるし」
「コウも一緒に――コウ? おーい?」
「コウ? 大丈夫か?」
私は取調室の椅子に座っていた。警察が対面に座っている。私は、『他害の可能性がある』として、取調室でも手錠をかけられ、椅子に腰縄をくくりつけられていたので、身動きがとれなかった。
「で、君はなんで人を殴っちゃったわけ? 殴っただけじゃなく……小一時間も暴れ回って」
私は状況を知らない。確かに私は人を殴ったが、理由がわからない。彼に何かを言われ、衝動が沸き、そうして殴った。しかし、彼に何を言われたのかも覚えておらず、そうして起こった感情がわからない。だが、殴ったり、暴れ回ったのは本当だ。私はこのような状況で言うべき言葉を知らない。私が黙っていると、彼は机に置かれた紙面を見て、半笑いになった。
「ああ、そうか。君は……ははっ、いい大人なのに、言語を使って説明をするのが……苦手、なんだっけ? ゆっくりでいいから、言ってみなよ。どんな答えでも怒らないから」
私は考えるために、立って、歩き回りたかった。考える必要があるときは、いつも歩きたくなる。さらに、パトカーに乗ったせいで酔って、気分がよくなく、言葉が思いつかない。私が黙っていると、彼はあからさまにイライラしはじめた。私は何かを言わなければならない。起こったことを早急に思い出す。――仕事をして、疲れていて、
人がいた。それで殴った。……そうだ。
「そこに人がいたから」
私が言うと、彼は一瞬、虚を突かれたように真顔になった。周りにいる他の警察も、動くのを止める。すぐに彼らは、 彼は語気を荒げた。
「殴った結果、偶然その人が死んでも、同じことを言うのか?」
「はい。私の行為は同じなので、相手がどのような状態になっても、変わらないです」
「なぁ……そんなの、無差別殺人鬼の論理と変わらんだろ。殴られた相手がどう思ったか、わかるか?」
「悲しいと思います」一般的に人は殴られると、悲しい気持ちになる。
彼は突然立ち上がり、机を叩いた。
「悲しいと分かってるのに、殴ったのか? 人がいたから?」
私は上を向いて、彼のしわの寄った眉間を眺めると、彼は狼狽えたらしく、ゆっくり椅子に座った。彼は腕を組んで胸をはった。
「はぁ……ああ、まぁ、お前みたいな、最初からオカシイ奴がオカシイことをしてもさ、起訴とかはないし、刑務所に行く必要はないよ? 栄養補給施設――『トリ』とか言ったっけか。それか、座敷牢、じゃなかった、自宅留置……つまり、『おうちケア』があるからさぁ」今時刑務所もいっぱいいっぱいなんだから、本当にヤバい奴なんか入れてられないよ。彼は小さく口ずさむ。
「施設とは?」
「最近ニュースでよくやってるだろ? 人様にメーワクかけるような奴とか、虐待されて精神が曲がった奴とか、お前みたいな奴とか、つまり、社会で生活できないような奴らを集めて、『栄養補給』をするんだ。そしたら人様と同じにになれるってわけ。結構前衛的な薬物実験もしてるらしいから、死んでる奴も多いみたいだけど。まぁ、人様に貢献してるから、いいよな」
「そう思います」人に貢献することはいいことだから、彼に同意する。
「こういうのはさ、お前、こんな感じなら、今も保護者いるだろ? 成年後見人でもいいけど……まぁ、親がどっちにするのか、全部決めれるんだ」
「なら、両親を呼ぶ必要があります」
「施設に行くようなヒトなのに話が早いじゃないか。これは結構軽度なところになるのかな?ええっと、たいよう、とか言ったっけ?」
「私のこの特性は先天的なものなので、制御ができません。なので、どこの施設に行くのかもわかりません」
私の言葉を聞くと、彼は失笑した。
「このバカみたいに大仰な態度は、軽度か重度か分からんなぁ、さすがに医者に訊いてみないと」
私は早く帰って、一人で過ごしたかった。家でも、留置場でも、施設なる所でもいい。次に警察車両に乗るときは、酔い止めを飲もうと思った。
「それまで、この刑事施設で待ちますか? それか、家に戻りますか?」
「保護者が来て、ハンコ押したら家に帰れるよ」
「わかりました」
「親呼んどくからさ、それまではここにいといてくれや。あと一日過ごすくらいだから」
私は頷いた。
「じゃ、取り調べは終了ね。はい、戻って」
独居房に戻っても、私はしばらく何もせずに立っていた。その後、閉じられた扉の格子を眺めた。そこの格子が何本あるか数える。大体の本数を数えると、次は格子を一つ一つ、握った。もうすぐここを離れる事になるから、ここがどういう場所なのかを確認してみたかった。もし刑法のゼミに行っていたらこの場所も見学できたのだろうか? 私は中心を見てその周りを歩いたり、壁伝いに手を触れた。存分に歩き回ってから、床に倒れ込み、眠った。
人と会わない、この短い生活は、気楽だった。私は一日中、ずっと規則を守り、自由時間は壁や天井を見つめるか、独居房を好きに歩き回った。
次の日の昼、私は釈放され、外へ出た。久しぶりに思えたが、外は何も変わらない。高いビルと、人間たちでひしめきあっていている。留置場の前には、母親が立っていた。
「コウちゃん!」私を見つけると、母親は私を抱きしめ、頬をすりあわせる。「会いたかったよ~」
母親の力は強く、息苦しかった。彼女の肌は乾燥していて、それを押しつけられるのは不快だ。彼女の産毛と角質が頬を刺してくる。これなら無機物に拘束される方がいい。
不快だったから、私は彼女を力ずくで突き放した。
「……は?」母親は、目を丸くしたあと、私をにらんだ。
「何なの、お前」
母親は私の両肩をつかんだ。そして、私を口早に罵倒した。
「母親である私の愛情を、そうやって、無下にして……あんたはずっと変な子だったのよ! 子供の頃は他人からの愛情を拒絶したり、一人遊びばかりして、学校でもいつも変な子で……診断はされてたけど、どうやって普通の子になれるかどうか考えて、仕事を斡旋してあげたのに、でも癇癪起こして暴れ回って……人様に迷惑かけて、それを反省もせずに……!」
彼女の声は、高く、大きかった。はやく止めさせたい。
「あなたは本当は、拘置所で臓器提供を待つだけのただの人殺しなのに! 私は忘れてないからね、あなたが本当は、人殺しだってことを!」
「極端な思考は止めるのが賢明です」
「うるさい! 私はね、それ以前にあなたが人間かどうか疑ってるのよ。ただ見たものを覚えるだけのロボットなんかじゃないかって。いまコウちゃんが発している言葉も、暗記した言葉の組み合わせでしかなくて、そこに感情なんて何にもないんだって……。コウちゃんが私たちにさえずっと敬語なせいで、虐待してるんじゃないかって疑われたのよ? 私たちはこんなにもコウちゃんの事を愛しているのに! これも、コウちゃんが変な子のせいよ!」
母親はさらに矢継ぎ早に私の特性を推しはかる。診断名や診断基準など、専門用語を多用したが、中身がないように思う。しばらく私に何かを言うと、母親は突然満足したようで、いつもの微笑みに戻った。
「まあ、記憶力がいいことと、すごくいい大学を卒業したのだけが救いね。それさえなかったら、あなたを本当に人間扱いしていなかったかも。さーて、帰りましょう。パパが車停めてるから」
私たちは駐車場に行って、車に乗った。私が助手席に座った。父親がハンドルを握っていた。
「ごめんなさいの手紙、もうパパが書いといたから大丈夫! コウちゃんは何も心配することないよ!」父親は私の頭を撫でる。圧迫感があって不快だが、拒絶したらまた同じようになると思って、黙って従う。
「あの人も反省してるんだって。『そういう子』に対して言いすぎたって。……じゃあ、家に帰ろうか」
車は出発した。その間、両親は私を励ます言葉を繰り返した。3ヶ月の間に、施設か自宅留置かが決まるから、それまで家で待機していてね、その間はちゃんとお世話してあげるから大丈夫だよ、と。
家に帰ると、夜になっていた。やることがないから、夜の支度を済ますと、すぐに眠った。私が眠ろうと布団に入ると、母親が私の部屋の扉を開け、笑いかけた。
「愛してるからね!」
しばらく眠っていたが、喉が渇いたから目が覚めた。私は冷蔵庫に行こうと部屋から出て、リビングまで歩くと、リビングだけ電気がついていることに気づいた。また、両親がそこで、私について何か話していることも気づいた。扉が少し開いていたから、気づかれないように彼らの様子を見る。
両親がリビングの椅子に対面で座っていた。母親はパソコンを開けて画面を見ていて、父親は何枚もの紙類を見ている。彼らは私について話していた。母親はパソコンをにらんで言った。
「彼が留置場にいたとき、異常行動が見られたって」
「何をしていたんだい?」
「監視カメラの映像でさ、何時間も微動だにせず立っていたり、壁や床や格子に触れたり、ずっと天井を見つめていたり」
「コウちゃんはそこまで重症だったのか!」
「ええ、それはもう! ひどいわ! 小さい頃は大人しくて育てやすいと思ってたのに、今はただの無口で変な大男よ。あーあ、なんであんな子を産んじゃったのかしら」
「これからどうする?」
「ああ、やっぱり、どちらにするか考えないといけないね。自宅留置――おうちケアか、栄養補給施設――トリか。でも、おうちケアの場合、ね……」母親は父親にだけ聞こえるようにぼそぼそと呟く。父親は母親の言葉にしきりに頷いていた。
「しかも、お金がさ。見てよ、これ。ケアとトリの差」母親は父親にチラシを見せた。
「これは凄いな。ああそうか、ケアに必要なケアルームは特殊な維持費がかかる。しかも、面倒を見ないと捕まるなんて!」
「やっぱり、コウちゃんは手放すべきかな?」
「仕方ないだろう、ケアの場合、脱走してトラブルを起こすかもしれないし」
「せっかく育ててきたのに……かわいいコウちゃんを」
「また新しい子を育てればいいんだよ。また古典的な方法で産んだらああいう子が産まれるかもしれないから、里親募集している子を探してみようか。次はもっと普通の子がいいな」
「それもそうね! ああそうだ、施設上がりの子を探してみましょう。コウちゃんと同年代の子もいるみたいだし、施設で普通になれた子なんでしょ? ええっと、『うみ』で募集してるのね」
母親はパソコンをいじりだす。
「はは! それはいいなあ」父親は大きく笑って手を叩いた。
「ちょっとあなた! そんなに大きな声出したらコウちゃんに聞こえちゃうでしょ」母親は注意するが、顔は朗らかである。
「そういう君だって声大きいじゃないか。いいよ、コウちゃんは深く寝るタイプだし、鈍感だから気づかないだろ」
「それもそうね。どうせちょっとしたら施設に行っちゃうんだし、バレてもいいわ」
しばらく母親はパソコンをいじったのち、ぱっと顔を明るくした。「すごい! この子、とってもかわいい子なのにすごく安い!」
「ははは、安いって言ったらまるで売り物みたいじゃないか! 募金だって! カンパカンパ!」
「あっ、それもそうね! ともかく、本当に迷うわ~!」
私は布団に入り、眠らなければいけなかった。部屋に戻り、布団に潜る。しかし、目を瞑っても眠れない。天井を見る。高さが低いような気がした。 張り紙の模様が私の目を刺す。太陽、雲、虹、海、笑顔。両親が貼り付けた、色とりどりな模様は、色彩が異様に激しく、集中を散漫にさせる。普段は気にしていなかったが、今は何故か気になる。段々と天井が低くなっていく気がして、息が詰まる。それはとどまることを知らず、天井が私の胴体を押しつぶした。
「コウ、コーウ!」
ナツミは私に呼びかけていた。私は部屋の中心で立っていた。ここは自宅ではない。ここは『トリ』で、さっきのは単なる記憶の反芻だ。「コウ、大丈夫?」ナツミは私の顔を覗きこんだ。彼女はしきりに瞬きをしている。私は彼女を見つめて、平気なことを示すために頷いた。
「落ち着こうとしてた? それか、何か思い出してた?」
「後者です」
「そっか」ナツミはそれだけ言って、笑顔を取り戻した。「今は自由時間だからさ、中庭、行こうよ! 遊具がいっぱいあって楽しいよ! リフレッシュにもなるし。ツバサも、行こう」
「え? あ、そうだな……」ツバサは目を白黒させて、狼狽える。
「二人が行きたいのなら行きます」
「行きたい! 行こう!」
ナツミが先導し、中庭まで歩く。他のかぞくは、室内で遊ぶ者や、外に行く者など、様々だった。
さっきの反芻が起こったのは、見知らぬ場所に移動したことによるストレスと、似た状況になった人を目撃したからだろうと思った。身体的な異常や反芻が起こるのは、いつも複数の要因が重なったときだ。
そんなことを考えていると、ツバサが声をかけてきた。
「コウ……さっきの、本当に大丈夫なのか? ずっと、ぼーっとしてて、呼び掛けても反応しなかった」
「さっきのものは、記憶の反芻です。それが起こっているときは鮮明に記憶を思い出しているので、声を掛けても返せないと思います」
「それ……治るのかな、ここで」
「わからないです」
「ここってそういう場所だろ? 病気? か何かを治すんだろ?」
「そう」ナツミは我々に歩幅をそろえて横に並んだ。「『あそび』とか、『しごと』、『おはなし』を通して、社会生活ができるようにするんだ。でも、基本的には『かぞく』で協力して治していくんだよ」
「私の症状は先天的な特性なので、根本的には治りません」
「マシにはなるでしょ?」私はコウみたいな子に何人か接してきたから、わかるよ。きっと和らぐよ。と、ナツミは言った。
「そうできたらより良いと思います」
「じゃあ、コウはどんなことに困ってるんだ?」ツバサは言った。
「……うるさいとき」私は無意識に口に出ていた。「声や刺激がうるさいときに、パニックのようなものになります。そうして、しばらくしたら治まります」
「……?」ナツミとツバサは首を捻って黙った。
「対処法はあります。逃げることです」
「じゃあ、それをすれば、問題ないんじゃないの?」ナツミは質問した。
「しかし、逃げることを阻むものがいます。私はそれへの対処法を知りません」
「阻むものって?」
「私が逃げるのを静止する人や、私の動揺です」
「どっちも取り除けばいいの?」
「それさえできれば、あとは自分で対処できます」
「どうすればいいんだろ? それを取り除くの」
「それをここで探していけたらと思います」
「……そうだね! 私もさ、前のかぞくの子達にいろいろ助けられたんだ」
私はナツミの前のかぞくの一人を知っていた。マメだ。我々は上靴から外靴に履き替えて、運動場に出る。駐車場から運動場への階段を降りる。外では、利用者が遊んでいた。
「うん。今は職員になって、ここで働いてる――あ、マメちゃんだ」ナツミがマメの方を向くと、マメは走ってこちらへ来た。
「ナツミちゃーん!」マメは満面の笑みで、ナツミに抱きついた。「久しぶり!」
「久しぶり! マメちゃん!」ナツミも笑顔になって抱きつく。抱きつくのを止めて離れても、まだ笑顔のままだ。
「こうやって対等に接するのは……久しぶりだね」
「職員のお仕事は上手くいってる?」
「うん! 最近やっと一人でいろいろできるようになって……まだまだ半人前だけど、頑張ってるよ! 私も休憩時間だから、一緒に遊ぼう」
「うん! 新しいかぞくの二人も一緒でいい?」
「もちろん!」
私たちはそれぞれ名前を紹介しあった。それから、どの遊具で遊びに行くかの話になった。
「ジャングルジムに行こう!」ナツミは遊具を指さした。運動場の一番端にある。
「おっ、春休みぶりじゃん! コウでも登れるやつかー?」
「うん、施設の遊具は全年齢対象になってるから、みんなが使えるよ」
「おっけー! 俺が一番乗りだー!」ツバサはジャングルジムへと走る。「あっ、ずるーい!私が一番乗り!」ナツミも少し遅れて走りだす。
私もついて行こうとすると、マメが呼び止めた。
「話してみたら、思ったより大丈夫そうでした。話を聞いてくれてありがとう」
私は頷いた。感謝の言葉を言われたときは、とりあえずそうすることにしている。
「彼女とマメさんは、仲がいいようです」
「うん。ずっと一緒に遊んできたからね」
「遊びに行きますか?」
「もちろん! さあ、行こう、二人が待ってるよ?」マメは他の職員かのような、子供をあやすような口調で言った。
ジャングルジムに行くと、ナツミとツバサが待っていた。「そろそろ登るよ-!」
ナツミはジャングルジムの入り口に入った。
「登ったほうがいいですか?」
「登ってくれないのー?」
登らなければいけないと解し、私も入り口に入る。大人の男でも入れるように間口が広くなっている。
「ここ進もう!」ナツミは輪っかのアスレチックを這って進む。ツバサが彼女に続き、私も進む。私も進んだ。最後まで進むと、巨大なすべり台があって、前の人たちが順々に滑っていた。ナツミ、ツバサが「ヒャッホー!」と言って滑っていった。私は後ろを向いた。マメがそわそわした感じで待っている。私は座って、滑った。風が通り抜け、涼しかった。あっという間に地上へと降りた。
私たちは自由時間中、遊びほうけた。ジャングルジム、鉄棒、シーソー、鬼ごっこ。3人とも楽しそうに遊んだ。施設へ行く手続きが済むまでの三ヶ月間、自宅謹慎を命ぜられていたから、こうやってちゃんと外に出て身体を動かすのは久しぶりだった。
「そろそろ時間だよー! おうちに帰ってねー」
職員の一人が拡声器で呼んだ。チャイムも鳴って、そろそろ帰らなければいけない。
「おー、そろそろ帰ろう!」
「えーマジかー。まだいたいなぁ」
「時間外までいてたらヤバいんだよ! 職員さんが怒っちゃう」
「それは怖い! 早く帰ろう!」
「私もちゃんと違反した人に怒れるようよう頑張らないと!」マメは独り言の声量で意気込む。
「マメはこれからどうするの?」
「仕事に戻るよ」
「がんばって! あと、一緒に遊んでくれてありがとう!」ナツミは笑いかけた。その後、思い出したように言った。
「ああ、そういえば、なんで突然話しかけてくれたの?」
「えーっと、コウくんが、アドバイスしてくれて……もっと、利用者の方々と対等に関わってもいいかなって思って!」
「コウが? きっとすごい良いアドバイスをしたんだろうなあ」
アドバイスと呼べるものはしていない。ただ、話を聞いただけだ。だが、話すだけでも、本人の考えがまとまるのはよくあることだ。
おうちに戻り、私たちは指定の時間に眠った。それからしばらくの間、施設での生活や作業を通して、施設での生活について、ナツミから教えてもらった。生活については、『かぞく』の『おにいさん』『おねえさん』から教わるシステムになっているという。我々もいつかは『おにいさん』になるから、知っておかなければならないと言われた。レクリエーション、何かのアンケートか、テストのようなものを受け、就労支援のための作業時間と、それから、自由時間。そうやって、一日を過ごす。
その日は施設が騒がしかった。多分誰かがトラブルを起こしたようだった。部屋で朝食を取ったあと、『おはなし』のために部屋から出ると、廊下には職員たちが何人かいて、キョロキョロと警戒するように周りを見ていた。
「何かあったのかな……?」
「隣の部屋に人がいません。昨日は4人全員そろっていました」私は隣の部屋の扉が開いているのに気づいた。そこには人がいないどころか、荷物もない。
「あ、ホントだ……先出たのかな? それか、卒業?」ナツミも不審がって部屋を見た。
「そんなに突然卒業することなんてあるのか? それも、かぞくが一斉に」ツバサはナツミに質問する。
「うーん、たまにはあるんじゃないかなぁ……」
「……そろそろおはなしの時間なので、指定された部屋に行きましょう」私は時間を確認した。そろそろ行かなければいけない。
「うん。今日は他のかぞくと、『おはなし』だったよな」
私たちはそれぞれが指定された部屋に行った。
『おはなし』とは、利用者が特定のグループに別れて、提示されたテーマに沿った会話をしたり、絵本を読み合ったりする、たいようにおける主たる活動の一つである。グループは必ずしもかぞくに限らず、バラバラになることも多い。おはなしは大学のグループディスカッションのような雰囲気があって、私はお気に入りだった。
私たちは男女ペアになって、ペアは椅子に座って向き合う。10ペアほどいる。私のペアの女性は、私がペアになったと分かるなり俯いたまま顔を上げない。胸元のネームプレートの名前欄には、マイコと書かれている。
「はあい。今日の会話のテーマは、これです!」職員が手を叩いてホワイトボードに書かれたものを紹介する。
『性欲について話しあおう どうすれば性衝動をおさえられる?』
「二人ペアになってるね? それじゃあスタート!」
性別は基本的に男女であり、二者は違う体験をしていることが多い。なので、それぞれの性の場合に基づいて話をすればいいと推察する。私は男性だから、男性固有の現象についてを話す。
「男性の性欲は、一般的には、性的な満足を得るための、肉体的な欲望です」
「あ、うん、そうだね……」彼女は少し顔をあげて頷いた。
「今回は多数派とされる異性愛者を前提としますが、男性は、異性、つまり女性の裸体やそれを連想させるもの、たとえば下着に性欲を感じると、男性の身体や精神に様々な変化があります」
「し、下着……?」
「大学の部活の同期がそう言っていました」
「そう……」
「身体の変化は、勃起、赤面、体温の上昇があります。精神の変化は、高揚感、興奮、支配欲などがあります。それによって、性衝動が起こることがあります」
「男性が性衝動を起こすと、しばしば犯罪行為に繋がり、社会的にも、個人間の心情としても、悪影響を与えます。なので、性衝動を抑えるために、様々な対策をしなければいけません。たとえば、個人的な対処としては、自慰行為をすることや、風俗店に行き、性的欲求を発散することが挙げられます。社会的な対処としては、法律の制定や、教育などが必要です」
「私からは、ひとまず以上です」とりあえずは一般的なことと、少し見聞に沿った内容を話す。
「……」マイコはずっと黙っていた。周りをよく見たら、どうやら黙っている人が多いようだ。たしかに、この話題は比較的にセンシティブだが、我々は職員にテーマを提示された以上、これについて話さなければいけない。
「話しあおう、という指示のため、あなたは話さなければいけません。そうしなければ……」
「あらー? そこの子たちはどうしておはなし、していないのかな?」
私が何かを言いかけると、左から職員の声がした。見ると、私たちではなく、一個左のペアに声を掛けたようだった。確かに左からは会話音が聞こえてこなかった。ペアの二人はどちらも俯いて、顔を赤らめている。
「これは重要なおはなしなんだよ? なんで二人とも喋らないの?」
「それは……」
「ちゃんと話してね。話さなかったらマイナス2点だよ。君、もうそろそろ落ちるよね、おやつ、食べたくないの?」
「……思い、つかなくて」
「慰めについて話したら?」職員は満面の笑みで少年に言った。「君ならおはなし、できるでしょう? もちろん、君も」職員は少女の顔も覗く。
「ええっと、僕は、毎晩……」すると、少年は自分の行為についてを話し始める。
「うんうん。良い子だね!」少年が話すのを聞くと、職員は他の場所に監視しにいった。すると、他の利用者たちも少しずつ話し始める。
「あー、まあ、みんな、話してるなら……うん、話す、ね」マイコは周囲をうかがって、話し始めた。
「うん……えっと、私は、ここに来る前に付き合っていた彼氏がいて、まあ、ここに来る原因になったんだけど、彼氏が性衝動を抑えられないから、私が奉仕してあげたんだ……そしたら彼、すごく嬉しそうにしてくれてて。すごく嬉しかったから、もっと奉仕してあげた。彼を支えないと、性衝動を他の人にぶつけると思って。だから、男性が性衝動を抑えるには、隣に適切な女性を置いておくのがいいと思います」
マイコは言い終わると、苦笑いをした。「あ、大丈夫かな……?」
「はい。おはなしは自分なりの意見を喋ることが目的だと推察するので、なんでも喋るのが重要です。しかし、男性の性衝動を抑えるのに女性の負担が必要であるという意見については、議論の余地があります。近代的な観点では――」
「……もう、止めていい?」
私の言葉を遮って、それきり彼女は喋らなくなった。このテーマは社会的に重要なので、話したいが、マイコは、最初と同じように俯いている。私も喋らないことにした。代わりに、テーマが書かれたホワイトボードを見たり、周りの話し声を聞いたりして、自分の中でこのテーマを深掘りする。しばらくして、職員がペアでの話を止めさせた。
「さて! 意見はまとまったかな? では、発表ターイム! 二人でどちらか選んで、発表者になってもらいましょう! 発表者にはたいようポイントがもらえるよ! がんばって発表しましょうね!」
発表者にはポイントが貰えるということは、
初回のおはなしから承知していたが、職員は毎回その旨を話している。
「……発表」マイコはボソボソと呟く。
「はい。どちらにしますか?」
私が言った途端、マイコは身体を震わせた。
「あっ……コウがやって、いいよ」
「そうですか? 私としては発表をしてもしなくてもどちらでも良いので、マイコさんがしたければしてください」
「いや、私は……コウが、やって」
「わかりました」私はさっきした会話をまとめ、発表のための言葉を考える。
「さーて、順に発表していこうねー! まず、一番左のペアから!」
ペアがそれぞれが発表していった。私も発表した。他の者も性衝動について出た意見を言い、
発表者はそれぞれポイントを貰い、おはなしは終了した。
おはなしでのペアはバラバラになり、それぞれのおうちに戻る。次は夕食まで自由時間だ。おうちへと歩いていると、ツバサの後ろ姿が見えたから、私は声を掛けた。
「ツバサさん」
「コウ? どうした?」ツバサは私の隣に歩く。
「今回のおはなしについて、あなたはどのような意見を述べましたか?」
「――ああ、コウも違和感に気づいたのか」
「違和感?」
「わざわざ男女ペアにして、話しづらいテーマを話させる違和感だよ」
「私は単にツバサさんがどのような意見を話したのかを聞こうとしていました。さっきの言葉に反語の意味はありません」
「え? マジ? みんな気まずそうにしてたじゃん!」
「普段より静かだったように思えます」それを気まずいというのならそうなのだろう。
「そう、そこが違和感……っていうか、年頃の男女をペアにしてあんな会話させるのはおかしいだろ!」
「たしかに、考えに性差のあるセンシティブなテーマは、慎重に扱うべきです」
「学校では……性教育は男女別々でやってた。一緒にやったら、今回みたく気まずくなるからな。でも、ここは? そんな配慮があったか?」
ツバサに言われ、左隣のペアを思い出す。彼らは顔を赤らめ(顔を赤らめるというのは、たいてい恥ずかしいと思っているときに起こる現象である)、職員にポイントをマイナスされると脅されセンシティブなテーマに関する話題を無理に話させた。恐らく、気まずくならないようにする配慮はないだろう。
「まあ、だからなにってわけじゃないけど」ツバサは言った。
「――ところで、ツバサさんはどのような意見をしましたか?」会話が一段落したようだから、別の話題を出す。
「え? うーん、そりゃあ、保健の授業で習ったようなことを、そのまま言っただけだよ」
「わかりました」
ツバサはちょっと間を取ってから言った。
「もしかして、ナツミにも聞こうとしてたのか?」
「はい。いろいろな人に聞きたいです」
「ナツミには、というより、女子にはそういうのは聞かない方がいい」
「わかりました」
「理由はわかるよな?」
「わかりません」
「……小6男子が成人男性に教えてやる。心配するな、俺はそういう知識に詳しいから。ダテに恋愛漫画読んでないからな!」
ツバサは私の背中に手を当てて、なぜ女子にこの種類の話をしてはいけないのかを説明した。
男子がこのような話をすると、意図が不明で怖がられてしまうからだという。特に私のような大柄な男性は特に怖がられるから気をつけろとも言われた。
「わかったか?」
「わかりました」
「うーん、なんで俺が教えなくちゃいけないんだか」ツバサは苦笑いになった。
「では、代わりに私がツバサさんに何かを教えます」何かを与えられたら返すべきなので、そう言った。
「そんなんいいって! コウは面白いし」
「そうですか」
「ああいや。じゃあ、コウに一つ聞いていい?」
「はい。かまわないです」
「コウって……寝付き良いよな?」ツバサは顔を俯かせて訊いた。
「はい。よく言われます。しかも、寝るべきときに適切なな時間眠っているので、適切な時間に起きることができます」
「そっか……ハハ、ああ! ちょっと聞いてみたかっただけだよ、ごめんな」
ツバサは苦笑いをして頭を掻いた。
ツバサに言われた通り、ナツミには今回のおはなしの内容について話さなかった。だが、ツバサの言葉がずっと引っかかる。寝付きが良いかどうか聞いたのは、単なる雑談で、そこに意図はなかっただろうか。思わせぶりな笑い方も含め、どこか府に落ちない。
その日の夜、一応眠ったが、夜中に目覚めた。何か、物音がしたからだ。起き上がって横を見ると、ツバサがいなかった。反対を見ると、そこには普段通り眠っているナツミと、その奥にツバサが立っていた。
ツバサが眠っているナツミを見ている。立ち上がって、見下ろしている。表情はよく見えない。
「どうしましたか?」
「……コウ?」ツバサは狼狽したように甲高い声を上げたが、すぐに口を押さえ、声を小さくする。「はは、珍しいね、こんな時間に目覚めるなんて」
「何かをしようとしていたのですか?」
「……いいや。何でもない。ただ単に、ちょっとなくし物を――探していただけ。でもさっき見つけたから大丈夫……トイレ行ってから寝るわ」ツバサは早口で言うと、そさくさとトイレに行った。
洗濯かごに服を入れて、洗濯機が並ぶ部屋――しごと部屋に入る。横並びに洗濯機が並ぶ。それぞれの洗濯機には部屋番号が附されており、利用者が各々で洗濯機を使っていた。
今日の洗濯は私の担当だった。おうちの番号が書かれた洗濯機に行き、三人分上着や下着、作業着を入れる。形が崩れやすいブラジャーは、個別に網袋に入れる。洗剤と柔軟剤を入れ、蓋を閉める。閉めたあとは、開始のボタンを押す。
家事を行うこと。これも、しごとの一つである。たいようは一人で生活を送ることを重要視するから、当然生活に必要な家事もしごとに含まれる。巨大な洗濯機をいくつか用意して一気に服を洗濯すれば効率がいいが、それは施設の趣旨に合わない。なのでこのように分割している。
「あっ! コウ!」ナツミが私に声をかけた。
「ナツミさん、しごとはもう終わったのですか?」
「うん。手持ち無沙汰になったから誰か手伝いに行こうかなと思って。でもコウは大丈夫そうだね」
「当然です」
「へへ、自信満々だねぇ」
ナツミは笑顔を向けて、他の困っていそうな人を探す。
洗濯カゴに服を詰め、おうちに持って行こうとすると、視界の端に、マイコが見えた。彼女は男性用の下着を持ちながら、身体を硬直させて、
キョロキョロとしきりに周りを見ていた。それに気づいたナツミが、マイコに声を掛けた。
「マイコちゃん、大丈夫?」
「えっ……っと」マイコは更に萎縮したようだ。
「洗濯が出来ない?」
「え? う、うん」
「じゃあ一緒に洗濯の練習しよう! 手伝うよ」
「あ……」
「マイコちゃんは袋にこれを入れといて。私は服を表に戻すから」ナツミはマイコに網袋と形の崩れやすい服を差し出す。
「う、うん……」マイコは言われたとおりに袋に服を入れていく。しばらくして、洗濯、それから乾燥させた服を入れ替えた。
「よし、洗濯のしごと完了!」ナツミは笑顔でマイコに言った。
「……あ……」マイコは萎縮しきっている。
「わ、えらいねぇ! ナツミちゃん!」我々のしごとを監視していた職員が、おもむろに二人の近くに歩き、パチパチと手を叩く。それからマイコの頭を撫でた。
「ほーら、マイコちゃん、ありがとうは?」
「あ、ありがとう……」
「うんうん、ナツミちゃんは偉いね! 手伝ってあげて。マイコちゃんもありがとうって言えて偉い偉い!」にこやかな笑みで、メモを取り出して、何かを書いてから、洗濯場にいる利用者に聞こえるよう言った。
「みんなもナツミちゃんみたいないい子になれるように頑張ろうね!」
しごとは家事の他にも、作業労働などがある。作業をするのは私にとっては簡単だった。内容は、箸を箸入れに詰めたり、簡単なピッキング作業をするなどの単純なものだ。今回はマメが作業所の監督をしていた。監督の仕事は資格を受けたソトの職員と遜色ないように思えた。
作業を終えておうちに帰ろうとすると、マメに呼び止められた。
「名倉さん」
「はい、なんでしょうか?」
「話を聞いてくれませんか? 外の空気でも浴びながら」
我々は運動場に出て、ベンチに座った。利用者たちが遊具で遊んでいる。今ごろナツミとツバサは他のかぞくと遊んでいると思う。
「話とは何ですか?」
「親のことです」
マメは微笑んだ。「前、どうしてここから卒業したいのかおっしゃってたでしょう? だから、話したくて」
私は頷いて、マメの話を傾聴することにした。
「……母親が、いわゆる教育ママで、私は中学受験をしました。受かって、高校までストレートで行って、あとは大学受験……ってときに、なぜか私は学校に行かなくなりました。勉強もしなくなりました」
「なぜ行かなくなったのですか?」
「ただ、何もかもが嫌だったんです。今思えば、家を出て行けばよかったんだと思いますけど、その時はそんな考えには至らなかった。だから、部屋に引きこもりました。……だからここに来たんですけどね」
ここが本当に私たちの心身に貢献したかは分からないけど……でも、私は正当にたいようポイントを集めて、職員になれたんです。あと少しすれば、社会に出ることができる。
「社会に出たら、どのようなことをしたいですか?」
マメはニコッと笑った。
「まずは親に会って、一発、殴ってやりたいと思います!」
「人を殴るのは――」私が言いかけると、マメはその言葉を遮った。
「バレなきゃいいんですよ……私がもう親の庇護下にはいないってことを、証明しないと!」
他人のことについて、あれこれ口出しをするべきでないから、私は黙ることにした。マメは話を続ける。
「ああ、それから、ちゃんと自立できたなってことを……確認したいです。卒業したら施設の支援で家を貸してもらえるらしいし、ここで職員として稼いだお金と経験を元本に、バイトをしたり、さらには正社員にでもなれたら、万々歳ですよね」
「大学には行けなかったけど、いいんです。今はこの国の人口も沢山いて、高卒の人の分母も多いでしょう? だから、きっと活躍出来る場所があるはずです! へへ、しかも、元から早めに働きたかった……というより、家から出たかった、っていうのが正しいのかな」
「類は友を呼ぶっていうのは本当みたいですよ。ナツミちゃんも……言っていいって聞いたから言うんですけど、お家に問題を抱えているみたいで……まあ、この施設の性質上、そういう子が多く来るのは当たり前ですがね」
マメは話し終わると、私の目を一瞬見て、驚いたような顔をした。
「ああ、すみません……同年代の方、あんまりいないので……すごく喋っちゃいました」
「いえ、大丈夫です」
「最初にツバサくんではなく、コウに声を掛けたのも、年の差があんまりないからなんです。あんまり年下に話したことがないからっていう……私の単なる恐れです」
「しかし、今はツバサさんと話せています」たまにマメはおうちに遊びに来るが、ツバサとも話せていると思う。
「ええ! それは勿論ツバサくん、ひいてはかぞくのみんなのおかげですよ!」
マメはニコッと笑って、話を変えた。
「ああ、ところで……コウさんは、ここで何を学びたいですか?」
それについてあまり考えていない。ただ、人に言われたから来ただけであって、ポイントを多く手に入れるべきとされているからポイントが得られるよう、規則に従っている、施設外と同じように。ただ、症状が和らぐのならそうしたい、と、言った。
「なら、学ぶことを探してみるのがいいと思います! まずは、それからやってみて……次に、それを学んでみるんです。『しごと』『おはなし』『あそび』……どれも重要な学びだから、自分に合ったレクリエーションを探してみて!」
「探してみることにします」
「話を聞いてくれてありがとう」
私は頷いた。
「……そろそろ終業時間なので、おうちに帰ります」
「うん。またね!」
施設の『あそび』部屋には、ボールプールなどがある。さらに、アスレチック、トランポリンもある。『あそび』は自由時間とは違い、指定された遊具で遊ぶ。
私はボールプールに身をうずめる。隅に行き、壁に身体を押しつけ、たいようの子らがどのような行動をしているのかをぼおっと見る。私が座ると、だいたい腰あたりまでボールが来る。座って、足を伸ばし、身体が触れる感覚を楽しむ。
ボールプールでは、利用者の大人も子供も交ざりあって、遊んでいる。あそびでボールプールに行ったときは、私はいつもここで彼らの様子を見ていた。同じかぞくか違うかぞくかはわからないが、ボールを投げ合っている。ちょっとしたアスレチックになっているところでは、ボールを入れる穴があって、そこに人々が色とりどりのボールを入れている。
しばらくそこでじっとしていると、ずっと一人で遊んでニコニコと笑っていた少年が、おもむろに私の方へ来た。よく見たらそれはケイだった。初日の夕食で罰を受けていた少年だ。
彼は私に近づいて、しきりに私の方を見る。私は座っているから、私がケイの顔を見るには見上げる必要があった。
「ケイさん、どうしましたか?」
「ああ……名前、覚えててくれたんだ」
「ネームプレートに書いてあるので」
「……一人じゃつまんなくないの?」
「つまらない、おもしろいで考えたことがないです」
「ふーん、変なの。無表情で座ってるだけなんて。来なきゃいいじゃん、こんなところ」
「あそびは、施設の活動の一種なので、できるだけ参加する必要があります」
「ああ、そういうの。でも、みんなと一緒に遊んだ方がいいんじゃない? 複数人で遊んだ方がいいよ」
「……話しかける余地がなく、また、一人でこうしていても楽しいので。では、あなたはなぜここに一人でいるのですか?」
私が問うと、ケイは顔をしかめた。
「みんな嫌ってるからだよ、俺を。見たらわかるだろ?」
「わかるために、今から見ます」私はケイの顔を観察する。彼の目は私をにらんでいる。しばらく見たが、彼が多数派な少年の顔だということしかわからない。あえて言うなら、少し顔が丸く、耳が長い。
「は? なんだよ気持ち悪い……やめろ」
「わかりました」
「はぁ……なんでここに来ないといけないのか、知らないのか?」
「規則は守らないといけないので……」
「ここに来て、楽しそうにしないとポイントがもらえないからだよ」
ケイは突然振り向いて天井を見た。私が黙っていると、「見なよ」と言われたから、天井を見た。天井からカメラのようなものがぶら下がって、カメラの下方が赤く点滅している。
「あれがあるところはポイントが貰えるところだ」
「あまり気にしていませんでした」
私が言うと、ケイは私の方をむき直して言った。
「お前って、何がきっかけでに『トリ』に来たの? 『ヨゴレ』? ――ああいや、なんか事件起こして来た?」
「はい。そうです」
「やっぱり……」
「見ただけで理由が分かるのですか?」
「同類は」
「つまり、あなたも事件を起こし、それを取り上げられてここに来たということですか?」
「……まぁ」
「あのとき、人を殴ったからあそこに立たされたことと何か関係が――」
ケイは私の腹を殴った。だから、私は言葉を言い終えられなかった。殴ったとはいっても、私とケイには極端な体格差があったから、痛みはない。
「……?」
「っ……」ケイは私から一歩引いた。
「どうしましたか?」
「告発するか……?」
「何を告発するのですか?」
「……いや、特にない。何もない。ただ、アレが来ただけだ」
「アレとは?」
「アレが来たら、もう抑えられなくなって、手が出て、そうしたら、また食事を抜かされて、イライラして……」
アレと言ってぼやかしているが、私にはわかる。
「私も、恐らくあなたが言うそれのせいで、ヨゴレというものになり、来ることになりました」
「お前にも来るのか?」
「そんなに頻繁には来ません」衝動性、他害――施設は、私のそれをこのような語彙で表した。その語彙が完全に私の特定の性質を示しているかは分からないが、一般に認められるものであるのは確かだ。
「ふーん」ケイは何かを言おうと口を開けた。
だが、
「はーい、レクリエーション終わり! みんなと楽しめたかな? では、帰りましょう!」
と、職員が停止の合図を叫んだから、ケイは話すのを止めた。他の利用者たちはあそびを止め、それぞれのおうちに帰っていく。私も帰ろうと立ち上がると、ケイはふっと息をついて、そさくさと帰っていった。
自由時間、私はふらふらと施設の運動場を歩いていた。運動場のトラックを何周か走って、疲れを取ってから、人がいないような場所を歩いてみようとふと思い、人が少なそうな建物の裏や細い道などを歩いた。
おうちの建物の裏側は、他とは違った雰囲気がある。地面は雑草が小さく生えていて、太陽はおうちの高い建物に遮られ、いつも日陰になっていた。そこに蛇口があるのを発見し、私は水を出して飲んだ。走って喉が渇いていた。生ぬるいが、水分さえ取ればじゅうぶんだ。水を飲んで、口を拭き、ふと横を向くと、一人の少年と、複数人が向き合っているのを発見した。
よく見ると、一人の少年はケイだった。集団の方は、真ん中に一人、身体が一回り大きな少年が前に出ている。
「おー! ヨゴレ! 今日も臭うぞ!」その少年がニヤニヤと笑いながらケイを罵倒すると、後ろの利用者たちは笑顔で鼻を覆った。臭い、臭いと、複数人がヤジを飛ばす。
ケイは俯いて、何も話さない。
「今日は、ヨゴレを浄化しにきました!」少年が笑みを浮かべた。
「はーい、聖水!」
後ろに控えていた少女がバケツの水を勢いよくケイにかけた。ケイはそれを一身に受ける。全身が水に濡れ、身体を震わせた。
「あれー? ヨゴレが落ちないよー?」
「ヨゴレはヨゴレってこと?」少年たちは笑いあった。
ケイは水を振り払わず、ただ少年たちをにらむ。
「なに? イライラする? じゃあさ、殴れよ。そんなイライラするんなら、また殴ってみなよ。ヨゴレ野郎なら人を殴っても心が痛くならないんだろ? だったら――」
私は少年が言い終わる前に彼らの間に割り込んだ。彼らの方を向く。真ん中の少年は目を細めた。
「お前……」
「名倉光といいます」
「そんなのどうでもいいんだよ! そこをどけろ。今、ヨゴレを浄化してるところだからさ」
「あなたたちが行っている行為はするべきではないので、どきません」
「てめぇ、ちょっと身体がデカいからって調子乗るんじゃないぞ!」少年は私に向かってきて、手首を掴んできた。乾燥してカサカサしているが、母親のそれとは違い、よく外で遊んでいる人のような肌だ。硬い肌が産毛から刺さって痛い。さらに、なま暖かい感触がゾワゾワと私の肌を刺して、私はその手を振り払った。
「うわっ!」
彼は足をよろめかせて尻もちをついた。
彼は一瞬顔を俯かせたが、袖で目元を拭うと、
すぐさま立ち上がり、私をにらむ。
「たしかさ、お前もヨゴレだよな……ツバサくんから聞いたよ? 彼、すごく純粋だからさ、お前が犯罪者のカスってことに気づいてないんだな。かわいそうに」
「逮捕されただけでは犯罪者にはなりません」
「うるさい! 死ねよ、犯罪者なんか全員死ね!」
死ね、というのは比喩だと思う。人殺しという罵倒が実際には人を殺していないことが多いのと同じように、死ね、というのも実際には死んでほしいと思っているわけではないと類推する。
堂々たる真ん中の少年とは違い、後ろにいる少年少女は、私を見て顔を不快な色に歪ませていた。
私が黙っていると、少年の後ろにいた一人が、彼に耳打ちした。すると、彼は頷いて、「もう行こう」と、言った。そうして、
「偽善者」
と、私に言い捨てて、他の少年少女をつれて去っていった。
彼らが完全に見えなくなったのを確認してから、ケイを見ると、彼は私をにらんでいた。まだ全身が濡れている。放っておけば風邪をひくだろう。
「シャワーを浴びにいき、着替えた後、職員にあの人たちからどのようなことをされたのか説明するのが適切です。必要ならば、私が証人になります」
「シャワーは浴びるけど、話すのはいらない」
「どうして?」
「意味ないから。前も話した。でもヨゴレだから仕方ないって」
彼がそう言うのなら止めるべきではないだろう。私は頷いて、帰ろうとすると、ケイが呼び止めた。
「なんで助けたの? 反抗したら、もっと目をつけられる。お前じゃなくて、俺が。お前のせいでアイツらがもっと酷くなる」
「人がいじめ行為を受けていた場合、止めさせるべきだからです」
「いい迷惑。我慢しているのが一番いいんだ」
「ならあなたがいじめられていたのを発見したつど、私がかばいます」
「別にいらない。お前が悪いとは言ってない。元はと言えば俺が全部悪いんだから……」ケイはもごもごと独り言をする。「そうだ、俺が……アレを承諾しないと……」そう言って、走って去っていった。
ケイが施設から卒業したという事実は、すぐ施設全体に広まった。彼がいなくなったのを、みんなが祝福した。施設は入所期間によって卒業する者もいるというから、たぶんケイはそれだろう、と、みんなが思った。
「やっとケイがいなくなったんだね! せいせいしたよ!」ナツミはおうちの畳に倒れこんで、座布団を枕にして言った。
「どうしてですか?」
「そりゃそうでしょ! だってあの子はずっと落ち着きがなくて、人に迷惑をかけ続けたんだもん!」しかも『ヨゴレ』だし。ナツミは言った。
「私もヨゴレなので、いなくなったらせいせいしますか?」
私が言うと、ナツミは突然口早に言った。
「コウは別。ヨゴレっていう言葉は、みんなに迷惑をかけているヒトにだけ使うんだもん。コウは別に迷惑かけてないよね?」
私は黙った。
「コウはいい奴だからヨゴレなんかじゃないよ! な?」ツバサも笑った。私は肯定も否定もしなかった。
「えっと……私、ずっと、やってみたいことがあったんです」ある日の自由時間に、マメは我々かぞくに提案した。
「なんだー?」
「かぞく写真! 撮りたいな……って」
「もちろん! 撮ろう!」ナツミは満面の笑みで答えた。
「カメラってあるのか?」
ツバサが問うと、マメは小さなカメラを取り出して我々によく見えるように突き出した。すぐに現像される、使い捨てのものだ。
「私が買ったんだ。施設のみんなの記録を、残しておこうと思って」
ナツミとツバサは運動場を走っていって、適切な場所を探した。しばらく探した後、施設の全面を背景に撮ることにした。
「コウも入る?」
「フラッシュが苦手なので、手短に……15分くらいで撮りましょう」
「写真なんか数分で終わるよっ!」ナツミは手をまねいた。私はナツミとツバサの後ろに立った。
「あっ、マメが写真撮ったらマメが映らないな……」
「大丈夫!」
マメが言うと、おもむろに所長が出てきた。
「所長さん!?」ナツミは驚いたような声を出す。
「マメに呼ばれて来てみたら、写真を撮ってほしいって?」所長は満面の笑みで言った。
「は、はい! できますかね……」
「もちろん。ささ、並んで並んで。身長順に、ツバサとナツミは前でね」所長はカメラを受け取って、我々の位置を指示した。身長の高い私とマメは後ろに、ナツミとツバサは前に立った。
「お、俺もいつか後ろに並ぶから……」ツバサは背伸びをして私を見つめる。
「数年後には、二次性徴によって身長が伸びると思われます」
「そ、そうかな……?」
「えへへ、その頃には、みんな卒業してるかな?」ナツミは無邪気に笑った。
「卒業して戻ったら学校で自慢したいなぁ」ツバサは気分が良くなって前に並んだ。
「コウちゃんは眩しいのが苦手なの?」
「はい、そうです。なので、短時間で撮りましょう」
「ははは、設定変えたからフラッシュは焚かないよ、それよりコウちゃんも笑ってみな」
「笑うのは苦手です」自然的に出たもの以外の笑顔は苦手だ。
「じゃあいつもの顔でいいよ! 素の顔で。素の状態が一番いいからね」
「所長さん、おねがいします!」マメは満面の笑みでピースをしながら言った。
「はいはい。いきますよ~」所長のかけ声でツバサとナツミはピースサインを出した。マメも一歩送れてピースをする。
「はい、チーズ!」
私も出したほうがいいと判断し、撮る直前でピースをした。カメラ音が鳴る。すると、カメラからすぐさま写真が現像される。
「はい、何枚か撮りますよ~!」
所長は何枚か撮った。私はピース以外のポーズ方法を知らなかったが、他の人のポーズを真似した。そんなことを4,5回繰り返す。
「――はい、終了! 現像できたから、見てって」
所長が言うと、三人はわらわらと彼の元へ集まってきた。所長がマメに現像された写真と、カメラを渡した。
「私は仕事に戻るからね」
「ありがとうございます! わざわざ、貴重な時間を……」
「あはは、これもみんなのためを思ってだよ。当然のことさ」
所長はマメの感謝を優しくあしらい、朗らかな笑顔で去っていった。
「コウも見ようよ!」
「わかりました」私もマメの周りへと集まる。マメはかぞくに写真をそれぞれ見せた。
「おいおい、コウ! 全部無表情じゃん! ああ、良い! コウらしくて!」
「わ、この写真私の髪の毛が変なところに……!」
「このポーズ今度は全員で一致させたいなぁ」
各々がそれぞれ感想を言う。私も何か感想を言わなければいけないだろうか。
「……写真が四枚あって、彼らは様々な様態で被写体になっています。写真に写っている人たちは、みんな楽しそうに振る舞っています」
「コウって感想とか言えたのか?」
「大学で書く練習をしたので、一応考えることはできます」
「おうちに帰ってもっとちゃんと見ようよ!」
「うん!」
私たちはおうちに戻って、腰をすえて写真を見る。私は普段していると思われる無表情だったが、普段と違ってピースをしていた。マメは恥ずかしげにピースをしたり、ハートを作ったりしていた。ナツミとツバサは、堂々たる様子で、息ぴったりにポーズを合わせている。
「これさ。みんなで、持っとかない?」ナツミは3人に提案した。
「いいのか?」ツバサがマメに聞く。
「もちろん! かぞくの証としてさ、みんなで持っとこ」
「『かぞく』の証かぁ……いいな! 選ぼうぜ」
三人は写真をそれぞれ選んだ。私は一番最後に余っていた写真を手に取った。私たちが写真を見ていると、ナツミは手を叩いた。
「あ、そうだ。写真の裏にさ、書こうよ。対処法を」
「なんの対処方法ですか?」
「いつでも持ってるものでしょ? もし次発作? が起こりそうになったときも、お守りみたいになれるかなと思って」
「お守り……」
「そう。だからさ、書こう」ナツミは油性ペンを差し出した。私はそれを受け取り、写真を裏返し、何を書こうかと考える。
「俺はなんて書けばいいだろ……ふむ、困っている人を見つけたときのことを書こうかな」ツバサは縁間に行って書き始めた。
「いいね! 私はーっと、うーん、焦ったとき? を書こうかな」
私は何を書くべきか考えあぐねた。感情を書く行いは苦手だった。
「あまり思いつかないです」
「うーん?」ナツミは私の顔を覗く。
「パニックになったときの対処方を考えたら? そうだ、私も書くの手伝ってあげようか? これでも色々な子の相談聞いてきたんだよ」
私は頷いて、ナツミの話を聞いた。ナツミの意見も取り入れて、対処法を書いた。たぶん効果的だと思う。
「パニックになりそうなとき、見てね」ナツミは笑顔で言った。
「コウも書けたのかー?」
ツバサは私たちが書いた文章を覗いて、ニコッと笑った。「いいじゃん! 実用性がありそう」
「……どうして、三人はそれほど私を気に掛けているのですか?」
「どうしてって……どうしてだろう? 助けるのが癖になっちゃって……」ナツミは腕を組んで考えた。
「理由もなにもないだろ、気にかけるのに」ツバサは言った。
「マメさんは仕事だからこのように気に掛けているのですか?」
「もちろん、仕事だからっていう理由もあるけど……それ以上に、コウも、他の子たちのいい顔が見たいって思って、頑張ってるんだよ」
「私はいい顔をしません。ずっと似た顔をしていると評価されます。だから、いい顔を見たいのなら私を支援することは推奨しません」
「いい顔っていうのは、表面的なものじゃないんだよ。もっと内面的なもの」
私は内面的にいい顔をしているのか? 私が黙っていると、
「そんなにネガティブに考えなくていいんだよ、」
「悪い気はしていません。ただ気になっただけです」
「そっか。よかった」
私には目に見えないものを見ようとするのが苦手だった。目に見えないものといってもそれは感情に関するものに限られる。概念についてを考えるのは好きだった。だからこういう話はよく分からない。
「なんか、あったかいね」
「へへ。そうだね」
私は温度計を見た。特段高くはない。……だが、文脈からして、かぞく三人の気持ちが高揚したことを共有したものだと思われる。
「……とにかく! これはみんなのお守りだからね」ナツミは念押しした。
「お守りはどのように着用すればいいですか? 私はお守りを常備したことがないので、わかりません」
「うーん、胸ポケットとか、すぐ取り出せそうなところがいいかな」
「わかりました」私は胸ポケットに服に入れかけた。だが、ナツミに止められた。
「あーまって! 油性ペンだから、服についたら取れなくなる。……まあ、お守りは部屋に置いてても大丈夫だから。でも、バッグとかにいれてたらいいかもね」
「乾かしてから胸ポケットに入れます」
「うん。……コウ、ありがとうね。あと、色々付き合わせちゃってごめん」
「私としては不快に思っていないので、大丈夫です」
「そっか」ナツミは儚げに笑った。
「卒業した後……お出かけとかするときとかに持って行こうかな」
「卒業かあ……」
卒業とは施設特有の用語の一つで、施設に一定の時間施設で生活するか、一定のノルマを達成するかで施設から出所できるという。たぶんマメはそろそろ卒業する。
「もし、卒業したあとも、一緒に遊んでくれるよね?」マメは言った。
みんなは頷いた。
マメがいなくなった。突然だった。単に時間が合わなかっただけだろうと思いしばらく日を置いても、やはりマメは現れなかった。それに、結構な人事異動をしたようで、人が結構変わっていた。
私がマメはどうなったか、外部からの職員……つまりソトの職員に聞くと、マメは普通に卒業したと言われた。当然、ツバサとナツミは困惑した。マメが何も報告せずに卒業するだろうか? さらに、マメは自ら望んで職員になったのに、すぐに辞めるのは不自然である。
「マメ……なんで突然いなくなっちゃったんだろう」
ツバサは腕を組んで黙りこんだ。珍しく、広縁に座っていない。居間の座布団に座っている。
「卒業した、とソトの職員から聞きました」
ナツミは、私の話を聞くなり、俯いて微笑んだ。
「うん。そうなんだよ! マメはすごく優秀だったから、きっと……すぐに卒業できたんだね!」
突然行っちゃったのは、何か突然の予定ができたからなんだ! だから寂しいけど……仕方ないよ。ナツミは何度も、大げさに頷く。ツバサはそれをちらと見たあと、少し間を置いて微笑んだ。
「……ああ、そうだよな! 俺たちも早く卒業して、マメに会おうぜ!」
「これは非常に不自然で――」
「コウ」
私は何かを言いかけたが、ツバサが遮って喋りだす。
「後で一緒にトイレに行こう」
「部屋のトイレは一人用です」
「……運動場のトイレは共同のはずだから」意図は分からないが、これほどトイレに一緒に行きたがっているのだから、承諾するべきだろう。私は了承して頷いた。
「――さて! たいようポイントのために今日も遊ぶか! 運動場行こ!」ツバサは勢いよく部屋から出た。
「コウも、早く行こう! マメの分までいっぱい楽しまなきゃね!」
「……よし、やっぱり俺が思ってた通りだ」
そのトイレはほとんど使われていなかった。運動場の隅に配置された、一昔前の学校にありそうなトイレだ。地面には砂が入り込んで滑りやすく、洗面台の蛇口も水が出るかはわからない。一応、紙はあるようだが、それも何年前のものかは知らない。外の古いトイレ特有の妙な臭いもする。掃除のしごとも、恐らく誰にも割り振られていないと思う。
ツバサはニヤッと笑って大げさに鼻をつまんだ。「運動場にあるトイレは臭い! だから誰も来ない!」
「何か、特殊な意図のためにここに来たと考えられます」
「話があるんだ。それも、誰にも聞かれたくない話」
ツバサは鼻から手を離し、話しはじめた。
「ここはヤバイ。変、どころじゃない。本当にヤバイ場所だ」
前、性衝動についてのおはなしあったろ? 俺が思うに、アレは俺たちが同じ部屋に住んでる異性や同性に、性衝動をぶつけないようにするため、あと、実際にそうしたらどうなるかを、教え込もうとしてたんだと思う。あの日、突然一気に卒業した隣のかぞく、いただろ? ちょっと噂になってるよ。それか、……逆に性衝動を起こさせようとしたのかもしれない。現に俺は――いや、その話はコウには関係ないよな。結局やらなかったし。ともかく、年頃の男女を一つの部屋に押し込むのはヤバイって話だ。
「ああ、そうだ」ツバサは思い出したように言った。
「コウって、今年でいくつだっけ?」
「24です」
「ほら!」
「どうしました?」
「言葉遣いのことだよ。24歳っていえば、もうちゃんとした大人じゃん。でも、マメ以外の職員たちはコウにも幼稚園児みたいな扱いをする。いくら施設に行くような理由があるとしても、そんなのオカシイだろ?」
「私の症状についてを話した人から、ほとんど似たような言葉遣いを受けてきたので、それが変であることに気づきませんでした」
「えーっ?」
「しかし、成人済の人間に、あのように接するのは一般的ではありません」
「そうだろ。……で、何を言いたいかっていうと、ここはなんか臭うってことだ。――もちろんトイレのことじゃないぞ。つまりは、何か隠してるんじゃないかって思うんだ」
「隠してるものとは?」
「わからん。だが、俺には何か大きなインボウを感じるぞ?」前の漫画でそういうインボウについての話があって――ツバサは漫画の内容についてを話した。その施設の陰謀について知りたいという好奇心を感じとった。
「どのようにして陰謀についてつかみますか?」
「潜入捜査!」ツバサは目を輝かせた。
「捜査って?」後ろから声が聞こえ、振り向くと、そこにはナツミがいた。
「ナ、ナツミ!」
「私も参加したいな。いい?」
「もちろん! 考えようぜ!」
だが、事実を知るのに、能動的な潜入捜査は必要がなかった。
ある日の昼、自由時間にかぞくみんなで部屋で過ごしていると、インターフォンが鳴った。私が扉を開くと、職員がいた。魚肉ソーセージのようなものが、ポリ袋の中にいくつか入っている。
「施設にだけ入荷している、特別な肉で……今日はちょっとたくさん、入荷してしまって……もしよければ、このかぞくで食べてね。そのままで食べるのがいいって所長さんが言ってたよ。あ、お菓子も配るね。このかぞくはいつもよく頑張ってくれてるから……」
「わかりました」私は肉と、菓子を受け取って、ナツミとツバサの元に戻った。
「加工肉と菓子が届いたので、食べましょう」
「おっけー」
私たちは肉を食べた。普通の味だ。どこにでも売っているような魚肉ソーセージの味がする。調味料がよくかかっていて、スパイシーな感じだ。
「ん? なんだろ、これ……」ナツミはポリ袋からレコードのようなものを取り出した。机において、みんなに見えやすいようにする。
「これは?」
「差し入れの奥に入ってた。なんだろう?」
「レコーダーに差してみてください」
「うん……」
ナツミはテレビに付属するレコーダーにそれを差した。再生ボタンを押すと、音声データが流れた。それは、マメと所長との会話音だった。
『で……話とは?』所長は言った。普段我々の聞く所長の声とはうって変わって、数段声が低い。
『この施設の真実についてです』
「マメ……?」
「……」私は部屋の入り口を見て、音を下げた。このくらいなら、万が一でも部屋の外から聞かれないだろう。
『へえ、真実? そんなものがあるとは!』
『利用者のみなさんを使って、作ってるのでしょう? 肉を』
「肉……?」ナツミは怪訝な顔をした。
『どこからその情報を?』
『ソトの者が……話していました』
『そうか……』所長はしばらく黙って、ため息をついた。『ナカの奴にはバレないようにと、あんなにも言っておいたのに。こりゃあ漏らした奴ごと処理する必要があるかね』
『処理って何なんですか、その言い草は』
『邪魔なモノは処理しないと。廃棄だよ。そのままの意味さ。さて、その者の名を言ってみなさい。そしたら君は殺さないでやる』
マメは何も言わなかった。
『どうしたんだ? お前にとっては最早ソトの者は一緒に働く仲間じゃない。たいようの子を使って人肉を作る敵じゃないか。敵を売れないっていうのか?』
『誰にも死んでほしくないんです。その方の名を言ったら、彼は殺されるってことでしょう……? 敵だとしても、嫌です』
『愚かな子だ。私にみすみす話して、どうしようというのか? 死にたいのか?』
『……策はありますよ』
『へえ。それは、こういうことかな?』手を叩く音がすると、足音がなだれた。
『みんな……? なんで……?』
『職員になったら施設への忠誠心が下がると思ったら大間違いだ。君は例外だが。ナカの職員たちは、みんな仲間になったフリをしていただけさ』
『……』
『さあ、マメ? 最期に言い残したいことはあるか?』
『……』
マメが何か息を吸った音で、音声が終了した。
「……どういうことだ? これは、マメは、どうなったんだ、なあ、コウ?」ツバサは私の肩に飛びついて、何かを懇願するように口を開けた。ナツミは真顔で黙っている。
私はこの会話で発生した事を推察した。
「この音声が真実なら、マメさんは死にました」
「!?」ナツミは顔面蒼白になって私を見た。
「さらに、マメさんは以前一部の利用者にされていたことと同じ処理……つまり、人肉加工をされました」
「……なんで」
「不要だからです」そして恐らく、今届いて、食べた肉はマメのものだ。だが、私はそれを言わないことにした。聞かれたら答えるかもしれないが、積極的に言うべきことではない。さらに、彼らも薄々分かっているとしたら、なおさら言う必要はないだろう。……この国では一般に、人肉を食べるのは非倫理的とされているから。
「しかも、施設では人肉加工が常態化しているようです」
私が言うと、ナツミとツバサは食べ終わった肉の包装を見つめて、黙りこんだ。肉と同封してレコードを送りつけたのは挑発的である。
「しかし、まだ確証は持てません。確実な証拠を見る必要があります」
「どうやって?」
「立ち入り禁止の場所に秘密裏で入ることです」
「まー、2043は『ニクオチ』かなあ」
「『オクレ』が酷いですからねー」後輩らしき職員はパソコンに何かを打ちながら答える。2043は、ケイの番号だ。彼は卒業したはずだった。
我々三人は、扉の隙間から、職員らしき人の声を、静かに聞く。あらかじめ身体の小さなツバサが隠れる場所を発見してくれたから、もし彼らが突然部屋から出てきても大事にはならないだろう。
「てか、なんでわざと『オクレ』を入れるんですか? たいようなんてほとんど『トリサゲ』できそうなヒトばかりなのに……」
「ああ、たいようの子たちはなまじ嫉妬心やらがあるせいで、ストレスを貯めやすいんだ。だからああいう風に『オクレ』を入れて、ストレスのはけ口にしてやるんだよ。で、ヤバくなりそうだったらニクオチな」
「へえ! すごい良い考えですねぇ!」
「ははは! トリが始まって以来の伝統だよ!」
「あー、僕、『シメ』の現場見たことないんですけど」
「ああ、時期になったら所長さんがつれてってくれるよ。丁度2043もそこでシメられるんじゃないかな」
「へえ、ちょっとドキドキしますね……なんか、罪悪感っていうか」
「いただきますって言わないと、って感じるよな」
「ですねえ。たいようの子たちにも、もっと気持ちを込めてほしいものですけどね」
聞いたことのない用語が、スラングのような言葉が、飛び交う。……『シメ』は、一般には締め切りなどの略称として使われるが、文脈からして、何かを屠殺しそうだ。そうして何かというのは……人だ。
ナツミとツバサは、口を開けたまま、黙っている。どれだけ状況を理解しているか聞きたいが、ここで何かを話すのはまずい。私は二人の肩にそっと触れ、おうちに帰るべきだと促した。
「コウ……」部屋に戻ってからも、ナツミはずっと茫然自失の様子だった。ツバサも、顔を俯かせている。
「コウ、これって、さ……どういう、ことだ? 本当に……改めて教えてほしい」
「常習的に加工が行われているようです」ほとんど確信に近かった。
「加工? 加工って何だよ?」
私は直接的に言って良いのか考えあぐねたが、ぼやかし方を知らない。だから、直接、
「人肉加工」
と言った。
「は?」
ナツミもツバサも、二人とも顔をうつ伏せた。
「人が、人を……食べるって?」それも、普通の人間が? ツバサは半笑いになって狼狽した。
「そんなの、おかしいよ……だって、ほら、違うだろ? 普通、食べないだろ、そんなの、なあ?」ツバサは途切れ途切れに言葉を言う。
「この国では人肉を食する文化はありませんが、一部の文化では食人の文化はあります。なので、人肉を食すること自体は全てにおいてタブーとは言えないでしょう」
「……!」ツバサは顔をしかめた。
「……ごめん、ちょっと」ナツミは口を押さえて部屋を出た。
「ナツミさん……?」
「そっとしておこう。うん……ともかく、ああ……どうすれば……俺も、気分悪くなってきた」
ツバサも口を押さえ、外に出て行った。
ツバサとナツミが戻ってくるまで、私は待った。戻ってくると、ツバサは開口一番に言った。
「でも、はあ、ともかく、……大人に! 職員に……報告しないと」
「それは止めたほうがいいです」
「なんで」
「この施設内の大人は、信用に値しない可能性が高いです。この事実が特定の職員に知られているとすれば、影響力が大きいことは確か。だから、言うべきではないです」
「じゃあ、どうすればいいっていうんだ」
「最も最適な行動は、ここから脱出することだと思います」
「脱出……?」
「はい。脱出です」
「……そう、だよな、はは……脱出か……」ツバサは苦笑いをした。
「さらに我々だけで、ここから脱出するしかありません」
「他の人たちはどうするんだ? 他のかぞくも、ずっと、……殺されてきたんだろ? 俺たちが脱出しても、それは止まらないのなら……」
「脱出後は、この件を世間に公開します。そうして、人肉精製を止めさせます」
「ああ……」ツバサは腕を組んだ。
「不満ですか?」
「今も、みんなが殺されてるんだろ? たいようのみんなが! なら……みんなで脱出しないと!」
「……この」
「ああ、そうだな……だって俺より下の年齢もちょっとはいるからな……」彼らにも知られたら、当然普通ではいられなくなって、暴動が起こるだろう。そうして、変な犠牲が産まれるかもしれない。そう言って、ツバサは私の意見に同意した。
「……じゃあ、作戦を考える必要があるよな?」
「はい、その通りです」
「……違う」ナツミは久しぶりに口を開けた。
「違うって?」ツバサは言った。
「たいようはそんな場所じゃない」
ナツミは我々以上にたいようにいる。初日もそうだったが、たいように対して保守的な態度を取っている。
「レコードのやりとり聞いたろ? あの話も聞いたじゃん!」
「職員さんたちはみんないい人だからそんなことするはずがない。それに、施設を疑ってたら、罰を受けちゃうよ」ナツミは罰に関してを強調した。
「でも……」ツバサは言いよどむ。
「普通に、卒業して、それからでいいんじゃない?」ナツミは硬い笑いを浮かべた。何かを押さえつけているような、そんな気がした。
「……いいよ、俺たちだけで脱出するから」ツバサはナツミをにらんだ。
私は夜の自由時間に、一人で運動場に出て、外周をあてもなく歩く。ナツミは脱出に乗り気ではないが、事の重大さはわかっていると思う。彼女を一人残して脱出してしまえば、彼女はどうなるだろうか? 一般には、人が一人でいることは精神的に小さくないダメージを与える。
私は椅子に座って、空を見た。月が光っている。星がまたたく。都会では見られない、澄んだ空だ。下方には、点々と住宅街の光が見える。ここは山の上だから、全てが見下ろせる。
「何やってるんだ!」
職員は、普段の幼い子どもに接するものと相反した、強い口調で怒鳴った。さすがに我に返って、振り返ると、真顔の職員がいた。私は何かを言わなければいけない。
「空を見ていました」
「時間外に外をウロチョロするのは規則違反だぞ?」
「時間外? いえ、まだのようです」私は時計を見た。まだ帰る時間ではない。
「聞かなかったか? 今日は特殊な時間割だから、さっさと帰れって」
「特殊な時間割から元に戻ったのでは……?」
少年たちから、実は普通の時間割になったと聞かされていた。だから、元に戻ったのかと思った。
「はは、知らねえなあ? ……しかも、お前、まだ『洗礼』を受けてなかったんだっけ?」
「洗礼?」
「前も見ただろ? 今からお前が経験することだ。さぁ、こっちに来い」
私は立ち止まって黙った。
「さっさと来い!」
職員は怒鳴り、私の手を勢いよく掴んで、引きずる。中庭から、普段は通ることのない廊下を通った。こんな道は行ったことがなかったし、こんな声は聞いたことがない。何もかもが普段と違っていた。彼はもっと幼い者に対するような口調のはずなのに。私の体調は明らかに変になっていた。
動悸が酷く、めまいがする。普段だったら振り払えるだろうに、なぜか身体が硬直して、何も考えられない。手を振り払うこともできたが、そうしたらもっと何かを言われるように思えたから、やめた。
部屋に入って、無機質な椅子に座る。
「ほら、両手」
私は両手を出した。すると、職員はおもむろに真麻を取り出した。私は衝動的に手を引っ込め、身を反らした。
「は? 大人しく従えよ! 罰がもっと酷くなるだけだから」
職員はさらに怒鳴った。私は静かに手を出した。職員は手をきつく縛った。真麻の成分が肌を刺して痛い。
「これ首にかけろ」職員は木製の板を首にかけさせた。『私は時間外に外に出ようとした悪い子です。虫未満の悪い子です。なので夕食が食べられません。餌をあげないでください』
「ほら、行くぞ」
「どこに……?」
「決まってるだろ? 食堂!そんなことも分からないのかよ!ほら立て」
私は立ち上がった。だが、首に掛かった板が重く、ふらつく。
「さっさと行くぞ。次バランス崩したらコレでぶったたくからな」職員は警棒をちらつかせた。
「警棒はそのような用途で使うべきでは……」
「黙れ!」
突然警棒を振るわれ、私は尻もちをついた。受け身がとれず、通常より強い痛みが走る。
「ほら立てや」
腕をつかまれ、無理矢理立たされた。私は黙ることにした。
私は気をつけていたが、腕も前方で固定されており、バランスが取れずに、ふらついた。私がふらつく度、職員は怒鳴り、警棒でぶった。ある衝動が身を震わせる。私はそれを衝動のままに彼にぶつけることもできるが、そしたらまた、あの日と同じになるだろう。
しばらくして、食堂についた。普段よりかなり時間を要した。私たちは食堂の入り口付近で止まった。まだ夕食前なので、私たちの他には誰もいなかった。
「ここで黙って立ってろ。俺が許可するまで動くなよ?」職員は、私の両足を縛った。不自然な姿勢なせいで身体が震え、バランスが取れない。両手が汗と痛みで固まっている。
「ほらちゃんと背筋を伸ばせ! 猫背になるな!」
私は腕の重心と看板の重さに抗って、背筋を伸ばした。
「ここで反省しろ」
しばらく立っていると、夕食を摂りに、たいようの子たちとその職員が現れた。職員は私を見つけると、指をさして笑顔になった。
「みんなぁー見て見てー? 悪い子だよー? ぶたれた跡もしっかり残ってるねぇ? こおんなに身体が大きいのに、恥ずかしいね!」
職員は全員に聞こえるように言って、食堂へと引率した。職員の一声で、たいようの子らはしきりに私の方を見た。一瞥しただけで無視して食堂に入る者もいたが、私のことについて話す人もいた。だが、たとえどれだけ悪いことを言われていても、私は無視しなければいけない。そもそも、手足を自由に動かせず、板も重りになっているので、殴りかかれるはずもない。私は待った。私は視線を上に向けた。蛍光灯が刺すように光っていた。だが、彼らの方に視線を降ろさなかった。
しばらくすると、食堂から匂いがした。手足首がずっと圧迫され、痛んでいた。真麻が肌に擦れ、かぶれかけていた。
「あんな悪い子はねー、お食事も食べられないんだよー? いい食事を食べられなかったらねー、
ますます頭がおかしくなるんだよー? かわいそうだねー」
私は疲弊していた。目を瞑って眠ろうとしたが、身体に過剰な負担が掛かって、痛みが走って眠るどころではなかった。さらに、周りが騒がしかった。だが、私について言っていることは、聞き取れた。学校や仕事で聞き慣れた言葉が、何度も反芻して聞こえた。学校でのある場面、仕事でのある場面が、次々と思い出される。
「さて、ここに座っている、いい子たち! せーの、いただきます!」
所長が来て、定例的なセリフを言った。
「いただきます!」
利用者たちは食事を食べ始めた。匂いが、そこら中に充満する。みんなが楽しそうに会話している。私は一言も喋らずに、ただ、利用者や職員の目線を浴びながら、佇む。かぞくの二人は、私の方をちらと見たが、話しかけてはいけないことになっているから、誰も話さない。私の方にも来ない。手と首の疲弊で、より腹が空く。
施設の利用者がそれぞれ、楽しそうに会話をする。私は何も聞きたくなかったが、耳をふさげず、際限なく会話が流れこむ。
しばらくしていると、前、ケイをいじめていた男女の集団が、私の前に来た。集団を牽引している少年は、私を指さした。
「わ、ヨゴレだ! まるで子供みたいじゃん!」
彼が食堂に聞こえるように叫ぶと、集団はどっと笑った。
「知ってるぞ? お前がヨゴレだって? こんなのと一緒のナツミちゃんは大変だなぁ!」
彼らは私をしばらく嘲笑して、彼らは笑いながら机へと戻っていった。私は何も言い返さなかった。
どのくらいじっとしていたのか、時間感覚を失ったころ、我に返った。気づけば、利用者は誰もいなくなっている。そこだけ記憶が抜け落ちたように、飛んでいた。黙って立っていると、職員が近づいて私をやじった。
「おい、いつまでじっとしてるんだ? そんなにここで恥辱を受けるのが好きなのか?」
「……」
職員は私の首に下がった看板を外し、縛った紐を解いた。無理な姿勢から解放され、私は思わず息を荒げた。
「おいおい、本当に恥辱に晒されて興奮したのか? そうなんだろ、お前らはみんな普通じゃないからなぁ」
私は手を動かして正常に機能していることを確認した。手首には赤く紐の跡が残っている。汗か、真麻の成分のせいか、少し被れて痒かった。首元にも痛みが残っている。
「用事が終わったなら、戻ります」
「……フン。ああ、いいよ」
職員はあからさまに舌打ちをしたが、私の行動を許可した。彼は明らかに私を煽っていた。下手に何かを言うと、激高されて更に激しい罰を受ける恐れがあったから、私は彼の言葉を聞かないことにした。
私はポケットに手を入れる。寮へと歩く。まだ消灯していなかったから、人々が歩いていた。普段より強く視線を受けた気がした。私は早く部屋へ戻りたかった。この時間は部屋の移動が多く、人々をかき分けるのに苦労した。私はしばらく歩いた。
私は立ち止まった。どれだけ歩いても、同じような部屋が、私を見つめている。どこに帰れば良いのか分からない。帰るべき場所についての記憶が、一時的に消滅している。太陽の張り紙が至るところにあって、それらは顔があって、みんな私を見ている。
手首の感触がまだ残っている。蛍光灯が眩しい。首もとに風が刺さって痛い。人々がざわめく。誰が誰なのか判別できない。彼らは何かを噂している。さっきの反芻がうるさい。壁が、天井が、床が、眩しい。私は思わず目を瞑り、耳を塞いだ。手首が外界に触れて痛い。服が刺すように纏わり付く。動悸がうるさい。まだ誰かの声がする。疲れて、眠たくて、私は床に横たわりたかった。だが、横たわることはさらなる罰を受けるから、するべきではない。したくない。
「コウ!」ナツミの声が背後からした。振り返ると、神妙な顔をしたナツミがいた。我に返った。手をポケットに入れなおす。
「大丈夫?」
「何がですか?」
「分かるでしょ! さっきの!」
「はい。身体的にも精神的にも後遺症はありません」
「しゃべり方はいつものコウだ……」
「そのようです」
「でも、ずっと耳塞いで、唸ってた」
「唸ってた?」私は唸った気がしなかった。無意識にそうしていたから気づかなかったのだろう。
「うん。ぜったい、普通の様子じゃなかったから」
「それは久しぶりに起こりました」
「ね、手、出してよ」ナツミは私のポケットの方にに目をやった。
少し考えてから手を出す。紐の跡があった。赤くなって、かぶれている。ナツミは私の手首を持って、撫でた。
「こっち来て」
いつの間にか、眩しさはなくなっていた。普段と同じような景色だ。さっきの私の認知は、気が動転したことによる異常だとわかった。閑散とした通路に、私とナツミが来ると、彼女は耳打ちした。
「ね、ここさ。普通のところじゃ、ない、よね?」
「はい、そう思います」私は言った。「あなたはどう思いますか」
「私も、変、だと思う」ナツミはうつむいて、
小さく言った。
「それはずっと思ってきたことでしょうか?」
「……ずっと、ここから正当に卒業することに躍起になってた。だから罰を受けてたり、問題を起こした人のことを軽蔑してた。マメたちが職員になったり卒業したりしてから、もっと酷くなってさ……でも、コウたちど出会えて、まだ頭が柔らかくなったかも」
「なぜ卒業にそれほど偏執的になっているのですか?」
ナツミは何も言わなった。
「話したくなかったら、話さなくてもいいです」
私がそう言うと、逆にナツミは話し始めた。
「早く卒業して、おかあさんのところに帰りたい。きっとおかあさんは、大変だから。今度は無能なんかじゃないよって、言ってあげたい。家事のお手伝いもするし、お金も稼ぐ。私はそういうことができるって、証明してみせる」――類は友を呼ぶんですよ。マメの言葉を思い出す。
「……ごめんね。ずっと私は怖くなってたんだ。罰を受けるのが」ナツミはうつむいた。だからあんな事実を知っても、ずっと否定してた。でも今は違う。
「ともかく、ここついてを考えなければいけません」
「……脱出する。こんなに変な場所、一秒だっていてられないから」
部屋に戻って考えよう。ここじゃ誰かに聞かれるから。ナツミは私に小さく言って、部屋に戻った。
実際に脱出を意識すると、施設の全てが我々の脱出を阻むためのもののように見えてくる。入り口にはいつも職員が配置されているし、運動場からだと簡単に出られないよう、引っかかりのない塀が高くそびえている。さらにここは山奥で、
職員から逃げながら歩いて降ろうとしたら、道から外れて、野生生物に襲われるだろう。さらに、スマートフォンの類は没収されており、助けを求めることはできない。
「作戦は? 考えたんだろ?」ツバサは広縁で椅子に深くもたれながら聞く。
「大まかには考えました」私は口頭で作戦の概要を説明する。
「夜中、最も職員らの警備が手薄になる時期に、脱出します。幸い、ここは刑務所ではないので、特に夜中での警備が非常に手薄だと感ぜられます」私は夜の警備についてを思い出した。だいたいパターン化されているようだった。
「うん。でも、出たら山の中だぞ。大丈夫なのか?」
「はい。外に利用者を運ぶ用の車が駐車されています。それを利用します」動いているのを見たから、ガソリンはたぶん注入されている。
ツバサは息をのんだ。「鍵はどうする? 運転は……?」
「職員室にキーが掛けられているので、それを奪いとります。また、私は更新済の普通免許証を持っているので、運転ができます」私はバッグから普通免許証を取り出した。
「よし! これで脱出後のことは大丈夫そうだ。
車さえあれば、素早く逃げられるな!」
「はい。免許証があるため、脱出後、公道を運転しても警察から注意を受けることはありません」
「警察に見つかった方がいいんだけどね!?」
ナツミは苦笑いで答えた。
「さらに、このような地図を書きました」私は施設の外の地図を出して、ナツミに渡した。
「これって……?」
「施設の外から、街までの外観図です」
「え! すご! 全部書いてるじゃん! どうやって……?」ナツミは地図を読んで、口を開けた。
「バスに乗った際、覚えたものです。運転する際、これを読んで指示してください、運転するときはそれに集中するので、頭の中で思い出してられないので書きました。……ただ、半分趣味で書いたものなので、一応、といった」
「コウって凄いんだね……」
私は黙った。褒められたとき、どのような反応をすればいいのか分からなかったからだ。ナツミはそれを察したのか、微笑んだ。
「ありがとうって言えばいいんだよ」
「ありがとうございます」
私が言うと、ナツミは斜め上を向いた。
「へへ、私もさ、これ、最近知ったんだ。マメがね、私が前より卑屈だったとき、教えてくれたんだ」
「ナツミ……」ツバサは言いかけたが、ナツミがそれを元気に遮った。
「だから、さ。マメのためにも! 絶対に脱出しないと! 脱出したあと、この施設の変なところをみんなに言えば、きっとなんとかなる。だよね?」
「うん!」
その日になった。私たちは普段通りベッドを敷き、普段通りに眠っている。職員らにはそう見える。実際のところ、我々は眠っていない。私は時間になると……つまり、一番警備が手薄なころになると、私は起き上がる。すると、ナツミとツバサも起き上がった。私たちは扉を開けて、外に出て、きちんと閉じる。彼らはたいようポイントが高い我々のことはちゃんと監視しないだろうから、朝までバレないだろう。部屋の外に出て、裏口から階段を駆け下りる。ツバサはニヤッと笑って二人と反対方向へダッシュした。三人の中で最も身軽なツバサが、鍵を取りに行ってくれるはずだ。私たちは出口の方へと駆ける。監視カメラが起動していたら、職員たちが来るのだろうか。でも、今は脱出だけを考えればいい。車でさっさと正常な世界に下りればいい。
我々は出口に出た。何も音がしない。しばらくすると、ツバサが来た。ニコッと笑って、鍵を見せる。
車のところに行き、車のキーを回す。開いた音がすると、ナツミとツバサが向き合って笑顔で頷く。あとは車に乗って、街に下りるだけだ。家に帰って、誰かに全てを説明して、事の顛末がどうなるか観測しなければならない。
私が乗り込もうとすると、突然背後から高い音がして、肩に鋭い痛みが走った。全身の力が抜け、思わずしゃがみこむ。
「コウ! 大丈夫?」ナツミが叫ぶ。
「後ろ」
「え?」
ナツミとツバサは私の後ろを見た。完全に力がなくなったわけではないから、私もゆっくり後ろを向くと、たくさんの人影がいるのを見つける。
真ん中で一歩前に出ているのは、所長だ。彼の後ろには、何人もの職員がいる。後方の職員は暗くて、表情が見えない。所長は銃型のものをポケットにしまった。
「たいようの子たち。いったい、なにをしようとしていたのかな?」
「これは、その……」ツバサが言いよどむ。
「三人で共謀し、脱出を図ろうとしていたんだろ? 施設の一部の子たちを人肉にしていることに、気づいて」
「そんなわけ!」ナツミは語気を荒げた。
「私たちは、もう全部知っているよ。君たちの低廉な計画の全てを」
施設のライトが光った。所長の姿と職員らの姿が、はっきり見える。所長は、最初会ったときと変わらない笑顔をしていた。
「君たちは、我々が漏らした情報のために、ここから脱出しようと考えた。その後、マメちゃんを『ニクオチ』にしたことも分かり、我々への憎悪感情が高ぶり、早急に脱出計画を実行した。外に出て、我々の罪悪を公表して、正義の名の下に、我々を潰してやろうと」
所長は高笑いをした。「三人がそれぞれの長所を生かして協力する姿は見物だったよ。一種の王道ストーリーみたいでさ。本当に王道の話だったら、悪の組織の我々を打ち倒せたのだろうが。そんな甘い話はないし、そもそも私たちは悪ではない――ともかく、君たちは全て失敗したんだ。いや、最初から、失敗していた。我々は最初から全て知っていて、あえて泳がせていたんだ」
「……なんで……なんで?」ナツミは完全に圧倒され、同じ言葉をずっと繰り返していた。何かの意味がある言葉だとは感じられないが、所長は答える。
「なんでバレたかって? たいようの子らの様子は全て監視しているんだ。もちろん、風呂場、トイレ、おうちも含めた全てでね。君たちがどういう行動をしているか、丸分かりだったよ」
「利用者を人肉にするという文章や、プライベートな空間を監視するという文章は、招集票のどこにも書かれていませんでした」
私は招集票の全文を思い出し、参照したが、そのどこにも書かれていない。規約違反の行動は、倫理的な観点からしてふさわしくない。
「書いてない? 当たり前じゃないか! 常識的に考えて、そんなこと書いてられないだろ。……ふむ、コウちゃんは常識がないから言っても無駄か」
「お前、お前ら……!」ツバサは憤慨して、彼らをにらんだ。
「プライバシー侵害とは言わないでくれよ。たいようの子らの安全を守るためだ。たいようのようなトリでも、たまに見境なく暴れるヒトがいるから……でもツバサくんには申し訳なかったね。『ハナ』だったから。でも、我々の真実を知ってしまったのなら、君の未来の可能性は小さくなるだろう」
「『ハナ』って……どういう意味だよ、それ? ワケの分からねえスラング使うなよ!」
「おっとすまなかった。……ふむ、つまり……きみは健常な人間だ。君にはちっとも、欠けたところがない。育児に疲弊した親が、愚かにも相対的に一番手がかかって可愛くない子を、ここにやっただけ。真実を知ってか知らずか、ね。本当はさっさと返して、一人暮らしの借家も与えようかと思ったが。ああ、かわいそうに。このような真実を知ってしまったら、もう君は普通の人じゃいられなくなる」
彼が哀れむような声を出すと、ツバサは何も言えずに固まった。口を開けて、呆然としている。なのに、所長はまだ似たような話を続ける。
「しかもお前、この施設を漫画か何かだと思ってただろ? 薄々、脱出ゲームだと思ってただろ? なあ? お前が! お前らが! 食ったんだ! お前らが脱出なんか計画したせいでマメは――!」
所長が何かを話し終わる前に、私は彼のところへ走り、胸ぐらをつかんで、むりやり黙らせた。所長は一瞬驚いたような顔をした。即座に職員らが来て、彼から引き剥がされ、取り押さえられる。私は抵抗しなかった。力がうまくでないから、
抵抗もできないが、抵抗する気もない。
「反抗は止めた方がいい。場合によっては、即刻、殺す」
所長はネクタイを締め直して、笑った。やっぱり未成年用のは効きづらいな――そう呟く。
私が動きを止めているのが分かると、職員らは私を離した。だが、次は許さないという風に、腰を低く据え、警戒している。ナツミとツバサは職員らに完全に萎縮しきって、とても話せない状態だった。私が話を進めるしかないだろう。
「ここまで泳がしていたのなら、相応の理由があると思われます」気づいたら事を大きくする前にさっさと処分するだろう。なぜそうしなかったのか。
「コウちゃん、話は分かるみたいだね。私たちは、少なくとも君を殺す気はない。君はとても素晴らしい才能を持っているから」
「才能?」
所長は私が描いた地図を胸ポケットから取り出して、開く。
「精巧無比な地図……あのバスの限られた視界の中で、自分の感覚だけで完璧な地図を作ってきてしまうとは。記憶力だけじゃなく、空間把握も得意なのかな」
「はい、言語と比べ、相対的に得意だと考えられます」
「あとさ、さっきのコウちゃんのセリフを聞いての質問だけど。あの渡された招集票――100ページはあったと思うけど、覚えてる?」
「私に関連することなので、届いたその日には全て覚えました」
「コウ……! そんなに言っちゃ……!」ナツミが私を諫めるように言って、やっとこれが言ってはいけないことだと気づいた。敵には、情報を不用意に教えてはいけない。だが、私は自分を自分が思っているほど誇大に表現したり、矮小に表現する方法を知らない。
「はは。すごいじゃないか! コウちゃんは私が思った以上の才能があるんだね。びっくりだよ。たいようの所長になって色々な子を見てきたけど……これほどまでの『ギフ』は初めて見た。どうして両親は気づかなかったのだろう。無能なのかな」
所長はあからさまに気分がよくなって、身体を揺らす。「まぁいいや。とにかく、取引をしようじゃないか」
所長は満面の笑みを浮かべて言う。
「コウちゃん、私の下で働いてみないか? もちろん、施設の『しごと』のような猿真似なんかじゃない。本当の『仕事』を斡旋してあげよう」
「施設の職員になれということですか?」
「そんなしょうもないのじゃないよ。外に出て、たいようの代表として様々な場所で講演を開くんだ。勿論、君がコミュニケーションが苦手だというのは承知しているから、私はきちんとコウちゃんの長所を考えて仕事を与えるよ。前の仕事よりマシだろう?」
所長は私の過去について取りあげる。「コウちゃんは親に全く向いていない接客業をさせられて、当然のように上手くいかなくて、ストレスを貯めちゃって、それが爆発しちゃったんだよね? で、散々人様に迷惑かけて……施設に行くのにふさわしい人間だ。これだけならただのバード野郎だが……君には、素晴らしい才能がある。だから、社会に出ても良い者だ。君には生きる意味がある」
「……」
「だから私が最適な仕事をあげるというのだよ。また施設に戻らせはしないさ……しかも、特典はそれだけじゃない! 私の下で働いてくれたら、君のかぞくの二人は社会へと帰してあげよう。さらに、他のたいようの子たちも、殺さないでやろう」
「私が、施設から……?」ナツミは所長へと顔を向けた。
「ああ、特にナツミちゃんにとっては願ったり叶ったりのことだよな?」
「……違う」ナツミは勢いよく首を振った。
「違う? 自分の意見を押さえ込めるのはもうやめなさい。ここから出たいから、今まで頑張ってきたんだよね? 無理に仮面を作って、他の人のお手伝いにいったんだよね? そうして、不出来な子を見下したんだよね?」
ナツミは俯いて、黙った。
「本題に戻ろうか。今、コウちゃんがこっちに来てくれたら、ここで終わりじゃなくなる。どうだ、来るか? 来たいなら、私のところに歩いて」
所長は笑っている。純粋な目をしている。私は所長のところに歩きかけた。しかし、それをナツミが止めた。
「待ってコウ。これは罠だから。行っても利用されるだけ。利用されて、殺される」
ナツミは服の裾を掴んで放さない。だが、振り払えはしそうだ。
「しかし、私が行かなければ、みんな殺されます」
「どうせ同じでしょ。行っても行かなくても。
あんな離ればなれの場所で死ぬか、一緒の場所で死ぬか……」
「なら、あなたは今、ここで死にたいのですか?」
「……違う」ナツミは言った。「私は生きたい。
生きて、おかあさんに会わないといけない」
「ならば、より生存の可能性が高い方を採用するだけです」
ナツミは少し考えてから言った。「……きっとまた、会えるよね?」
ナツミは手を離した。私は何も言わず、ナツミの目を見る。人が不安になっている時は、安心させるべきだから、笑って、彼女を安心させようと思った。だが、私は自然的な笑い以外の笑い方を知らなかった。だから私は、ただ彼女を見た。だがナツミは笑った。「三人で一緒に頑張れて、私……楽しかった。施設に来て――生まれて初めて、楽しいって思った」
私は所長のところへ歩いた。彼は、私が隣に来ると、朗らかな笑顔で手を伸ばし、私の頭を撫でた。
「君が犠牲になるだけで、たくさんの命を救える。これからは、人様に迷惑をかけたことへの贖罪と思って、私の下で働いてほしい」
「私は……」何かを言いだす前に、言葉が出てくる前に、物事は進んでいた。ナツミとツバサは、職員たちに丁寧に連れられた。何かの感情が氾濫しかかっているが、私には種類の判別がつかない。私は職員らが様々な動きをしているのを、見ることしかできなかった。
「二人は部屋に戻して、出所の手続きをしてあげて。さぁ、コウちゃん。荷物は全部持ってあげるから、一緒に行こう。これから、たいようの代表として……『たいようくん』として活動していくんだよ」
たいようの所長――黒崎 敬一郎は、手を差しだした。月に照らされ、彼の歪んだ笑顔がはっきり見えた。手を握る。その手は冷えていた。
「たいようくん。これから一緒に、がんばろうね」
第一部 了
第二部
『驚異的な記憶力のたいようの子の“生きづらさ”と“支援”』
画像上部にテロップがあらわれ、一人の男性が、耳を塞ぎ、身体を震わせ、唸っている。施設の監視カメラの視点で、様々なカットが映る。
『これは栄養補給施設で、困りごとが起こったときの、たいようくん(仮名)。』淡々とした声のナレーションが流れる。『彼は何か困りごとが起こったときは、言葉にできず、このように身体で表現する。』
『しかし一方で、こんな才能もある。それは、記憶力の良さだ。』
カットが変わり、施設の周辺の地図がアップで表示される。『これは、たいようくんが記憶だけを頼りに作った地図だ。街と周辺の郊外が、事細かく書かれている。』
次に、彼が施設で『しごと』を行っている場面も流れた。箸入れに、箸を入れる作業。同じ仕草を繰り返している。『さらに、この子にはさらなる才能がある。これは施設で単純作業を行う、たいようくん。とんでもない集中力だ。』彼の顔がズームされる。真顔で、淡々と作業に取り組んでいる。
『今回はそんなたいようくんを特別ゲストとして、スタジオに招いた。』
私は番組に飽きて、動画を止め、コメント欄をスクロールして、彼に対して言われていることを読んだ。
『そんなに数字覚えてられるとか記憶力すごすぎ 一方、俺』
『顔かわいい。でも、変な挙動。』
『おめめが純粋で、きっと良い親御さんを持たれたのだと思います』
『私の娘も施設にいます。こんなに天才ではないけれど、頑張って生活しています』
『人に迷惑かけなきゃなんでもいい』
『やっぱり害があってもこのくらい才能が無い限り社会に出ちゃダメですよね。よかった~健常者として生まれて。俺才能無いから』
私はスクロールする手も止めて、画面を見つめる。しばらく黙っていたら、黒崎が私の顔を覗きこみ、目を見開いて、微笑んだ。
「どうだ? 君のことがしっかり描かれてると思わないか? 傑作だろ?」
「……この人は」私は彼の挙動を思い出した。
「うん?」
「この人は、誰ですか?」
黒崎は私の顔を見るのを止め、私の周りを歩き回った。彼は私の言葉の意図を考えるように、首をかしげ、私を眺めた。
「まぎれもなく、君だよ。コウちゃん。君はね、客観的に見ればこうなっているんだ。他者の視点を持てない君には分からいだろうけど」
私は携帯を閉じ、ポケットに入れる。見ていられない。
黒崎は私の顔から目を離した。
「今回のギャラは銀行口座に入れておくから。自由に使ってよ」彼は言葉を続ける。「で、次の仕事のことなんだが、結構、すぐなんだ」
黒崎は厚い紙の束を机に置いた。「健常な人間には中々難しいが……君のような子には、たやすいだろう」
「何をやればいいですか?」
「この文章を覚えてもらって……そうして、私と記者会見に出てほしい」
私は紙の束をめくって、全体的な内容を確認する。――『人肉』『施設』『事実』そういう言葉が散見される。
「内容は、栄養補給施設が許諾を得た利用者を人肉にしたり、実験に使っているのを認めるものだ」
「私たちに施設について暴露されるのが不都合だから、このように従わせているのではないのですか?」
「本当に隠蔽したいなら君たちを殺せばいいじゃないか」
黒崎は、ふっと笑った。
「そろそろこの施設の事実を、世間サマにジャッジしてもらわなければいけないと判断したからね。君たちにとっては、元から暴露したいことだったんじゃないか、なあ、聞いてたぞ?」
『この施設の変なところをみんなに言えば、きっとなんとかなる』ナツミが言ったことを思い出す。私は紙を開き、文章を読んだ。
紙には、大まかな記者会見の流れと、私が言うべき言葉、想定される質問が乗っていた。唾棄すべき内容だ。何とか施設を正当化しようとする試みが、目に見えている。全部読み終わると、私は黒崎を見た。
「この文章は、恣意的ななものだと思われます」
「はは、当たり前だろ? お前が公的な場所でものを自由に喋れると思ってるのか? ……だが、お前らに有利なものには違いないだろう? 世間サマが君のお仲間が言う、倫理観がある人たちだったら……きっと、施設の反対運動が活性化し、私たちは自動的に潰れるだろう」
「この文章にないことを言ったら、私は不都合な者として殺されますか?」
「場合によるよ? 少しくらいなら変えてもかまわないが、大きく変えるのは、ちょっとねぇ。……いい塩梅で考えられるアタマが万が一にでもお前にあるというのなら、どうぞ考えてくれ」
「そのように他人を煽るのは、他人から嫌われる恐れがあります」
「普通の人はそう思っているかもしれないが、君はどう思っている? 君は私のことを、嫌っているのか?」
人を嫌う感覚というものがどういうものか知らない。行為を嫌うことはあったが、人そのものを嫌ったことはなかったように思うし、それは意味のないことだ。
私が黙っていると、黒崎はため息をついた。
「君はいつも一般的な見知ばかり言うよな。まぁ、そういう風に自分の感情を見いだすことを難しくしているのが、君の症状なワケだが。そんなんで、ここ以外の仕事が務まるのかね?」
「一人で作業をする方が煩わしくなく、集中できるということは知っています。なので私はこれを持って家に帰ります」私は立ち上がった。
「ふむ、少しくらいは嫌悪の感情があるようだ。はは、もちろん、帰っていいよ」
私が部屋から出かかると、黒崎は捨て台詞のようなものを残した。
「記者会見は少し、君には辛いかもしれないが、君の目的を達成するためにも、頑張ってくれ」
(続く)
「レンタルビデオを返せない呪い・星野源」波多野 善二
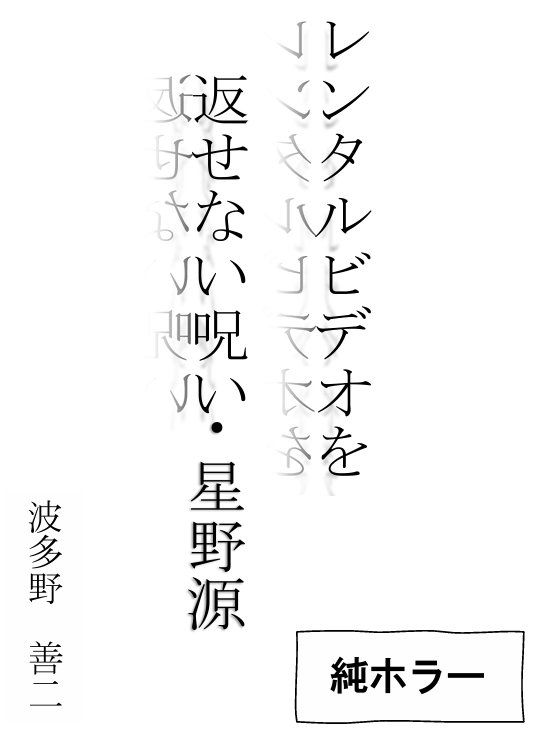
でも、俺は布団を出ることは出来ない。寒いし。
しかも、延滞料金は300円。延滞金との戦い。
そして見つける星野源。果たして返せるのか。
九月二十八日、それは僕が借りているレンタルビデオを返さなければいけない日であった。
借りた作品は、『pulp fiction』である。
さて、このレンタルビデオを返そうと思うわけだが、あいにく外は雨である。
しかも、微妙に靴の中に雨が入ってくるかどうかのギリギリの降水量であった。
別に、傘をさして、防水用のスプレーを靴に吹きかけて、外に出て、片道十五分の道を歩けば、いいのだが、十五分か。中々に長い、本田圭佑のように叫びそうになった十五分。
考えている内に、雨足は強まっているような気がしてたまらない。もしそんな残酷な事実を見てしまったら、僕は確実に延滞料金を支払う羽目になるわけだが。さっさと事実を見ればいいのに、僕はスマホを取り出して、延滞料金のことを調べ出してしまったのである。愚行。ちなみに一日ごとに三百円である。三百円があれば、三本映画が借りられるし、コンビニなら、飲み物とおにぎりが買える。
ん。三百円で飲み物とおにぎりって、高くないか。まあ、そんな皮算用は置いといて、雨の中三百円の為に、わざわざ外に出るという事は、なんだか負けたような気がするのだ。
そう、例えば学生時代に警報が出るかも、そう思わせるような雨が降っていたのに、実際には注意報で終わって、行く羽目になったあの時。あの時僕は気象庁と学校に負けた気でいた。一方、雨の日、室内でなんとか時間をやりくりするためにいろいろな遊びを考えるのは楽しかった。
でも、やっぱり三百円で飲み物とおにぎりって高くないか?
もし、今読者であるあなたが三百円を持っているなら、急いでコンビニへと向かって欲しい、そして、スマホには電卓を開いておいて、カゴを持って、店内を散策してみて欲しい。さあ、数えてみてくれ、三百円で十分に腹を満たせるもの。
丼系、パスタ、うどん、カレー、ここら辺の一品で一食シリーズはもう駄目だ。何故なら大抵は三百五十円からがスタートである為である。
しかも、驚くことにサンドイッチも三百円を超すのである。はっきり言って意味が分からない。おにぎりとサンドイッチ、まあ、サンドイッチは三個入っているから、三百円の範囲内で、おにぎり二個を買って比べてみよう。
どうだろう、おにぎりの方が少し腹持ちが良い気がする。サンドイッチは具も少なければ肝心の挟んでいるパンが薄いという始末である。
庶民の見方のような存在であったコンビニがいつしか高い上のほうまで行ってしまい寂しく思った。
ああ、コンビニちゃん。幼いころは結婚の約束をしたじゃないか。
ごめんなさい、僕君、私、御曹司とお見合いして、結婚することにしたの。さようなら、僕君。
待ってよ、コンビニちゃん、確かに君は言ったじゃないか
出来ることなら、私も僕君と、でもお父様の物価がそうおっしゃいますの。
そんなの、あんまりだよぉ。
だが、そんなコンビニの物価高に嘆いている暇はないし、脳内でコンビニちゃんの恋愛ストーリーを考える暇もない、レンタルビデオを返すか、否かについて考えなければならない。
三百円もう払ってもいいかな、そんな思いでいた。
だが、極貧生活を強いられている僕に三百円というのは大金であった。
三百円、三百円、三百円、ああ、三百円の呪いだ。お金の悪魔が僕に意地悪をするのである。
「えいえい、返さなくいいんだぜ」
「えいえい、三百円ぐらいいいじゃん」
「えいえい、三百円我慢しても飲み物とおにぎりぐらいだぞ」
そんな頭上を回る悪魔を振りほどき、我に返る。
よし、やるぞ。合理的になるんだ。ならば、答えは簡単。返しに行くしか僕の中にはない。よーし、早速、起き上がって、顔洗って、メイクして、着替えて、靴にスプレーかけて、親に一言言って、あれ、なんだか、意外とやることが多くないか。おい。自分。
よくよく考えてみれば、今自分は布団の上にいて、部屋は大散乱しており、おまけに足を軽く捻挫している状況に置かれていたのだ。
右足を動かすと、確かに足首周りの動きがぎこちなく、痛みが神経を走って、脳へと伝えていた。
なんで、怪我したんだっけ。
あ、昨日の体育か。
僕は昨日の体育のサッカーの試合中、ドリブルの際に足を捻って、そのまま早退していた。
そもそも、連日雨なのに、無理やりにでもサッカーをしようとした結果、地面緒コンディションは最低で、ベースボールもサッカーも出来るような地面ではなかった。
別に全国の体育教師がそうであるとは言わないが、いくらカリキュラムがあるからと言って、無理にさせる必要はないだろう。体育教師が生徒に無茶を強要しがちなのは全国共通かもしれない。転勤でくる先生は皆そうだ。脳みそのほとんどが筋肉で出来ている気がする。
というか、そもそも副教科の科目を思い出してほしい。
体育、美術、家庭科、音楽、この四つがベターだと思うが、体育、美術、音楽はいらないと主張したい。なぜなら、それれら三つの科目は人間の先天的な能力に依存しているからだ。まず、体育。皆が皆鬼ごっこしてると思うなよバカ教師。病気で運動できない奴がいたらどーするよ、満点取れないんだぜ。そして、美術。絵を描ける喜びとかほざいているけどさ、物体でも、空間でも、いいけど、把握能力が乏しい奴に、リンゴを書けとか、立体を書けとか、少しむりがあるんじゃないのか。まあ、仮にそこらのものが書けたとして、満点を取るレベルに達するには中々時間が掛かるだろう。最後に音楽。音楽とか、金持ちの遊戯じゃねえか。金管楽器にせよ、木木管にせよ、高すぎるんだよ値段が。まあ、リコーダーで妥協するとして、リスニングとか、どう練習しろっていうんだよ。知らんねえよ、チューバとかオーボエとかの音色。そんな先天的要素の強いもので生徒を測ろうとするのは愚行である。
おっと、熱が入ってしまったね。
それで、まず布団から脱出を試みるわけだが、これが無理そう。冬になりつつあるので、気温は低い、当然寒い。敷布団に毛布を一枚掛けて、掛布団の上にも一枚掛けてある。一枚でも取ろうものなら、僕は氷河期時代の恐竜と瓜二つの姿へと変身するだろう。
恐竜になるつもりは、はたからないので、現実逃避に、僕は星野源の『そして生活はつづく』を読む。
携帯料金をコンビニに払いに行こうとする星野源、だが、都合が合わず、放置される案内のはがき、さっさと、口座引き落としにすればいいのだが…
星野源のエッセイだが、この状況に僕自身を投影する。
別に、音楽が出来る訳でも、演技が上手い訳でもないのだが、何故か、だらしない星野源と僕を一致させてしまうのだ。
携帯料金を支払わなくても、星野源ほど有名になれば、マネージャーが携帯を貸してくれるだろうし、死んだりすることはない。口座には僕が見たことない額が入っているに違いない。
レンタルビデオを返さなくても、僕はただ金を払う必要が発生するだけだ。だけど、母親も、友達も返しには行ってくれない。マネージャーなんているはずもない。もし、ボンボンの子供なら、執事が返しに行ってくれるかもしれない。
じいや。これ返しに行って来て
承知しましたお坊ちゃま
こんな具合だろう。
だが、実際問題、僕は一介の学生で、音楽も上手くなければ、演技は出来ないし、新垣結衣と結婚できない。何もない僕に、星野源が手を差し伸べて、レンタルビデオを返しに行ってくれてもいいと思う。
エッセイには自信を卑下するような文章を書いてある。有名人によくありがちな、『自分は才能がなくて、たまたま成功しただけなんです』そんな定型文をインタビューや雑誌でよく見かける奴をエッセイには書いてあって、これがまた腹が立つ。
本当に、才能がないと思っているのか、それとも、一般人に親近感を感じてもらうためにあえてそういうポーズを取っているのか、分からないが、僕のようにひねくれている人間からしてみれば、それはただ自分を守るための防衛行動にしかすぎず、プロとしては失格といえるだろう。
プロであるならば、自分の商品価値をアピールすればいいのに、謙虚な姿勢を貫くのは、例えば星野源の場合、星野源が自身に、そういった努力をしない言い訳にしているように聞こえるのだ。
だが、こうやって僕がひねくれた考えに脳のリソースを割いている間に星野源は今も死に物狂いで、歌詞や本を書いていると思うと、尊敬の念を抱かずにはいられない。
普通に考えて、限りなく多くの人間の共感を買って、限りなく多くの人間の心を打つような演技をしようとするのはそう簡単なことではないことは容易に想像がつく。
実際、星野源の幼少期の体験、青年期の体験を、聞いている限り、かなり苦労して、その苦悩故に、同じ苦悩を持つ人間の心を打てたのだろう。そして、たまたま似たような苦労を持った人間が多かった。
こうして考えると、やはりある程度の運は必要で、アーティストとして売れるためにする努力は売れるための要素を限りなく運のみにするためだろう。
僕も、星野源に嫉妬するのは辞めて、尊敬を抱いて、布団にくるまろうと思った。こうして不満をたらたら述べている間に、誰かが、返してくれているかと思ったが、レンタルビデオはまだ返っていなかった。畜生。
満を持して、勢いよく掛布団を剥がす、瞬間体に来た冷気は、即座に掛布団を定位置へと戻すように促す。
でも、なんだか、このにっちもさっちもいかない状況に腹が立ってきたので、僕は布団から、脱出して、布団を片付けて、顔を洗って、メイクをして、靴を履くところまできた。しかし、肝心のスプレーがないのである。
確かに、下駄箱の一番下にしまったはずなのに。何かが、おかしい。多分、これは陰謀だと思う。国が国民に…。
スプレーはあきらめて、さっさと母親の使っている長靴を履いて、レンタルビデオ屋へと向かった。
住宅街を闊歩する僕、こんな雨の中外に出るようなもの好きは自分しかいなかった。
ただ、一向に着かない。そう、レンタルビデオ屋さんに。
確かに、向かっているはずなのに、一向に着かないのである。
もう十五分以上は経っているはずなのに。
同じ景色を何分以上見ただろうか。このまま、雨の中を闊歩し続ける町の妖怪的存在になってしまうのではないか。そんな不安を募らせながらも、テスト前特有の何とかなるでしょ、という希望的観測による楽観も備える。
ただ、あまりに着かないものだから、一度止まって、あたりを見ていると、いつの間にか隣町まで来ていてのである。
急いで、元来た道を戻る。
閉店時間である七時に間に合うように、雨の中、極力雨に当たらず、そして、極力速く歩く。
そんなこんなで、無事についたレンタルビデオ屋さん。
だが、よく見てみると、借りていたところとは違うところであった。
そう、レンタルビデオ屋も複数あるのである。
絶望、もう七時は過ぎたのである。
仕方なく、家に帰り、延滞料金三百円を持って、後日返しに行くことにした。
翌日、レンタルビデオ屋に行こうと思い、肝心のレンタルビデオがなかったのである。そのレンタルビデオを探すのに丸一日掛けてしまったので、また日を改めることにした。
そして、翌日、三百円と、レンタルビデオを持って、レンタルビデオ屋に向かい、カウンターまで行く。
「はい。こちら延滞料金が発生しておりまして」
ふん、想定内。
「六百円になります」
何、想定外。
仕方なく、帰ってお金を持ってもう一度向かおうとしたが、肝心の財布を無くしてしまった。その財布のおかげでまた日を改めることになった。
四度目の正直である。そんなことわざはないが、今はそんなことわざを作らないと、やっていけないのである。もうクタクタである。
「九百円になります」
さあ、くらえ、九百円。
「ありがとうございましたー」
何か大きな仕事をやってのけたそんな自身に満ち溢れた顔で道を歩く。
そうして、家に帰ってゲームでもしようかと考えながら、家の扉を開ける。部屋に入って、早速電源を付ける。
ゲームのディスクを変えようと、棚を見ると、そこには一枚透明な箱に入ったディスクがあって、それを恐る恐る手に取ると、まさかのお替りである二枚目のディスクが発見されてしまった。電源を落とし、また、レンタルビデオ屋に向かう。
「こちら、千二百円になります」
そんな大金持ち合わせている訳もなく、僕は家に帰って、母親に千五百円を貰って、その日は寝た。
翌日、無事に返すことが出来、部屋には一枚もレンタルビデオがないことを確認した僕はその日のゲームが普段よりもかなり楽しんでプレイ出来ていたことに気づいた。
レンタルビデオの恐怖から解き放たれ、安心した僕は、両親にこの出来事を話して、さらには仲良しの友達にも話して、とにかく人に聞いてもらい、恐怖を紛らわせたのであった。
ああ、三枚もレンタルビデオ返したのか。
延滞料金は二千四百円にも及んだ。もうこの金額には一生知らないふりを決め込むつもりでいる。
色々、災難があったが、無事返せたことにとにかく祝福を挙げて、今は静かに眠った。
翌日、僕の枕元にはレンタルビデオが置いてあった。
(完)
「自由落下」ふゆ

時の流れは、変わらない。
あの時も、今のこの瞬間も。あなたの瞳に映るものは、私と変わりはしなかった。
あなたは私を包んでくれた、だから私も応えたかった。
私は君を、置いて行ったりはしなかった、
しないはずだった。私たちは、変わってしまった。
あなたを憂いて、私は一人空を舞う。
空は落ち、地表を見上げる。変わるはずのなかったものを、私はどう見上げたら満たされるだろう。
遥かなる願いを天に乗せ、見るはずだった空を見下ろす。
捨てないで、そう呟く。
見捨てないで、ひとりにしないで。
どうか、傲慢な祈りが届くように。
あなたと離れ離れにならないように、またもう一度抱きしめてくれるように。
あなたの体に寄り添うように、暖かい体を感じられるように。
その冷たい指先に、ひどくやさしく触れ合おうとする。焦がす思いを握り締め、焼ける身体に熱を覚える。
灰は舞い、空を白に染め上げた。
あなたの優しさが私を包む、夢想はとうに捨て去った。
あなたはもう、一人じゃない。
まだ、変わらないものはここにある。
わたしが落ちる、この自由。
わたしが握る、あなたの手。
わたしの前に、居るあなた。
乞いた日々、二人の世界。
わたしは灰と一つになり、空を一つに染め上げる。
手を繋いで、地の獄へ。もう二度と、離れないように。
(完)
「断片・メリーアンとは」波多野 善二

脈絡はない。
フリーライターメリー・アンは生きる。
フリーライターであるメリー・アンは、昼も夜もキーを叩き続ける。
だが、文、および文章に意味などなく、彼女の生成するものは文字の連続体でしかなかった。
断片的なセリフ、意味の破綻した文、虚構上でしか成立しない情景、これらの文字の連続体はメリー・アンの唯一のスキルであった。
こんな社会的な価値のない文字の墓場のようなデータを買い取ってくれるもの好きのおかげで今日もメリー・アンは飯を食えている。
よく肥えた不潔なおじさんにネットを介して一テラバイトにも及ぶデータを送る。その時メリー・アンは机に突っ伏して死んだように眠る。
パソコンが騒がしく音を立てると、それがデータを送り終えた後であること知らせる。
「ジョン。お疲れ様」
そういうと、メリー・アンはパソコンの電気を落とした。
上下ジャージの少しだらしない恰好で、近くにあるジャック・ポール・バーガーへと向かった。
「ジャックバーガーとポールポテトを二つ。二つお願いしたいわ」
プレートに白い紙が敷かれ、その上にジャックバーガーとポールポテトが乗っている。それを指定席となりつつある一番奥のテーブル席まで運ぶ。
「やっぱり、ジャックバーガーは最高。ピクルスが三枚入っているのは最高にクールね」
食事を楽しむメリー・アンの前に不潔なおじさんことジョンソンが現れる。
「メリー、今回も最高の仕事をありがとう。銀行の方に一万ドルほどふりこんでおいた」
「ありがとう、ジョンソンおじさん。仕事の出来る男性ってステキ」
「ジョンソンおじさんもポールポテト食べるかしら?」
ジョンソンはそのふくよかな体を左右に揺らし、
「いや、辞めておくよ。そろそろ、このわがままボディともお別れしないといけないらしい」
「あら、そう」
拍子抜けした返事にジョンソンは戸惑いつつも、
「次に君に会う時はアーノルド・シュワルツェネッガーよりも、ビッグでビューティフルなボディを持って、参上することにするよ。じゃあ」
ジョンソンはそう言うと、一瞬にして姿を消した。
ドアのベルの音一つ鳴らさず。
メリー・アンはこの仕事をし始める前から、随分特殊な体験をしている事に気が付いていた。
先のジョンソンの一件もそうだが、ジャックバーガーも二つ目が食べたかったら、目をつぶれば、次開けた時には出来立てのジャックバーガーが置いてあるのだ。だが、メリー・アンは大食いではないので、ジャックバーガーを食べているときは一瞬たりとも目を閉じたりしない。
次にメリー・アンは夢を毎日見ているのだ。
例えば、データを送っているときに見ていた夢はこうだ。
メリー・アンは城にいる。
メリー・アンは日本の城にいるという事を、目の前にいる頭を輝かせ、カタナを持ち、和服を着ているアジア人を見ること、和室と呼ばれる部屋にいるということから認知した。
和室、和服、カタナ、これらをメリー・アンは『NIPPON』という雑誌で読んだことで知っている。
メリー・アンの目の前にいるアジア人は突然叫び、
「くせ者め、覚悟」
と言い、カタナを大きく振り上げた。
メリー・アンは何も驚かない。
メリー・アンの手元には台本のような物があり、そこに書いてあるストーリー通り、目の前で起きているからだ。
「カット」
メリー・アンがそう言うと、たちまち強張った顔をしたアジア人は安堵の表情を見せ、周りは部屋だったはずなのに、たちまち、スタジオのセットが現れた。
そのスタジオには、メリー・アンの好きなプロデューサーがいた。
「この映画には極めてなにかアジア人に対する侮辱を感じます」
そう言って、セットの一部を蹴り上げ、顔を真っ赤にして出て行った。
その隣にいる不潔そうなおじさんが言った。
「宮さん、あんなことやってるから、人が育たないんだ」
不潔そうなおじさんは蹴り上げたおじさんを追いかけた。
メリー・アンはセットの一部が損傷していないことを確認して、カチンコ(撮影現場で監督がカメラの前でたたくアレ)を手に取ろうとすると、
「姉ちゃん、黒人は侍なんかやらねえよバカヤロー」
そう言って、メリー・アンを突き飛ばし、メリー・アンは奈落へと堕ちていくのを体で感じ取った
こういった具合である。
だが、夢はチューブに詰まる草やヘドロの類である。
だから、最近のメリー・アンの睡眠事情は生理の時よりもBADである。
断片的な文を生成するメリー・アンにとって、夢とは脈絡がなく発生するが、その夢は脈絡がある、大変奇妙なものであると、不快に思う。
メリー・アンはバーガーとポテトを食べると、家に帰り、ベッドに横たわり、天井を見つめる。
ふと思い出したように、メリー・アンは攻撃を刷ることにした。
たちまち、天井からA4ほどの大きさの紙が大量に降ってきた。そして、それらの紙には、この原稿に文字を起こすのも、躊躇うほど、下品な単語の並びの文が1枚、1枚書いてあった。
それらは列を成し、扉を開けて、近所のポストの中に1枚、1枚入っていった。それらが人に対して不愉快な思いをさせることであろうと思い、愉快に笑った。
攻撃は、社会と接点を持たないメリー・アンにとって、少ない接点のうちの一つである。
メリー・アンの不器用なコミュニケーションは次第に受け入れられていった。例えば、ある男性は下品な文の紙の裏側にさらに下品な文を丁寧に書いて、メリー・アンのポストの中に入れ、ノックを二回して帰る。
メリー・アンがある出来事を経る前、以前のメリー・アンである頃からしてみれば、攻撃に対して、接触をしてくることはあり得ないことだと驚くだろう。
読者の世界からしてみれば、メリー・アンの世界は随分おかしなものだと批判、嘲笑し、作者にも、そういった感情を持つだろう。
だが、メリー・アンと作者からしてみれば、君たち読者の世界の方がおかしなものだと思うだろう。そして、批判、嘲笑するだろう。
メリー・アンは攻撃を終えて、ベッドから立ち上がり、鏡を見る。鏡には君たち読者の姿が見えているだろう。
メリー・アンは笑っている。君たちの顔、姿勢、服、周りに対する君たちへの見方などを見て。
メリー・アンの家のベランダからは、水平線が見える。
メリー・アンは水平線を見つめると、段々水平線は線が波を打ち始め、彼女の焦点を中心として、渦を巻き始め、目に映る景色(水平線、人、マンションなど)は一瞬、色を失う。白黒写真が最もそれに近い景色だろう。
白黒写真のような景色は中心から虹色がにじみ出る。そして、モノのがモノを維持するための境界線、およびかたどっている線を無視して、あたりは虹一色になる。
メリー・アンはドラッギーな景色を楽しみ、酔う。
不快な気分になったので、メリー・アンは寝ることにした。
メリー・アンはまた夢を見るだろうと思うかもしれないが、違う。
酔っているので、これ以上夢は見る必要はないのである。
体もそれは認識する。
月が現れ、沈み、再び、日が顔を出した時、メリー・アンは起きた。
メリー・アンはジャージを脱いで、シャワールームに入る。
水滴を浴びる。メリー・アンは腕から洗うのがこだわりだった。そして、髪の毛、上半身、下半身の順で洗うのであった。
浴槽は白色に変色していて、赤いバラが、白を犯す。
浴槽につかるメリー・アンはウットリとし、バラを見つめ、手の平に乗せて、ギリギリまで上へと掲げる。
一気に落とす。
バラは散る。
メリー・アンは気づくと、自身が浸かっていた浴槽がひどく膨張していることに気づいた。
不自然に膨張した浴槽はベースボールのスタジアムみたいな形をしていて、外野、内野共にプレイヤーがグローブを持って、構えている。ピッチャーマウンドには、あの憧れのベーブルースがふてぶてしい態度でキャッチャーとサイン交換をしていた。
気づけば、メリー・アンはバッターボックスに立っており、自身の無意識の内にバッティングフォームを構えており、そのフォームはいかにも強打者のそれであった。
ベーブルースが一球目を大きく振りかぶって投げた。
ボールは、右打者のバッターボックスに立つメリー・アンの内側を大きく攻めるボールで、メリー・アンは思わずのけ反ってしまった。
観客はメリー・アンの態度にメリー・アンの名前を叫ぶと同時に、『オーバーリアクション!オーバーリアクション!』と強く叫んだ。
メリー・アンはそんな観客に目も暮れず、自分を強打者と認めるかのような攻めた配球をしてくれたことにただひたすら喜んでいた。
ベーブルースが二球目を投げた。
今度は切れ味の良いスライダーでメリー・アンから逃げるようにボールは大きく逸れていった。
ベースの上を過ぎるコンマ何秒前までストレートと見分けがつかなかったので、思わずメリー・アンはバットを振った。
観客は大歓声を上げる。
メリー・アンは本当に一流のバッターとして自分を認めてくれていることを、ベーブルースの投げた球の音から感じた。
キャッチャーも思わず、ベンチへと下がり、新品のキャッチャーミットに手を包帯でぐるぐる巻きにして現れた。
そして、ツーストライクとなり、ベーブルースの投げた三球目のボールはメリー・アンの頭めがけて飛んで行き、メリー・アンは避けろと体に命令する間もなくぶつかり、メリー・アンは最後にベーブルースがこちらに駆け寄って、心配そうな面持ちでこちらの顔を覗きこんだのを確認して、意識をなくした。
気づいた頃には、メリー・アンはのぼせていて、メリー・アンは自分の鼻や口やお腹に強い異物感を抱いた。
彼女は生きる。
メリー・アンはシャワーを浴び終え、散歩にでかけることにした。
メリー・アンはひどくシャイな人間で、それこそ人の目を見ることすら怖がる人間だった。名を付けるなら人間恐怖症といったところだろうか。
だが、メリー・アンはある出来事を経てから、首の後ろの部分に傷を作り、その傷のおかげで、彼女は人間恐怖症を克服した。同時にメリー・アンはメリー・アンである頃の自我を取り戻せていない。
メリー・アンは散歩をする、高級店で仕立てたスーツを身にまとって、メリー・アンは都会を歩き倒す。
人々がせわしなく動き回り、あるサラリーマンは怒りの矛先を電話の相手へとぶつけ、ある学生は道のど真ん中で人々の邪魔をしながら、自撮りをし、あるオフィスレディはカフェで必死にノートパソコンとにらめっこしながら必死にキーを叩く。
メリー・アンはそれらと、読者を嘲笑する。
生きるメリー・アンは生き延びる都会および田舎の人間をバカにする。社会的な価値に囚われていることに同情すると同時に、なんて悲しい生き物なのだろうと嘲笑する。
メリー・アンは都会をある程度見渡した後、地下鉄で駅員すらもその駅名を覚えていないであろう駅まで乗り、家畜と緑と青しかないような、都会に比べ物質的に貧しいところを散歩する。
あたりを見渡せる丘まで行き、ある程度の自由が担保されている家畜を見て、生きているということを確認する。
川の流れはいつも一定方向に、一定の量が流れていて、木々は一定の周期で枯れ、一定の量生える。
メリー・アンは生き延びるがないこの田舎を希少なものであると思い、同時に癒されるような思いでいた。
メリー・アンは確認を終え、また都会へと消えた。
メリー・アンはまた夢をみる。
メリー・アンレッドカーペットを歩いていた。
そのレッドカーペットは無限に続いた。
歩いても、歩いても、終わらない。
レッドカーペットを歩くスターメリー・アン。
メリー・アンはオフィスレディをしていた。
ただ、電話を取って、しかるべき場所へと電話をつなげる。
たまに来る来客に対して、予約票の紙とにらめっこする。
最後に、退勤する会社員に対して、お疲れさまというねぎらいの声を掛ける。
最後にメリー・アン自身がお疲れさまというねぎらいの声をかけて帰る。
メリー・アンは、画家であった。
それも新進気鋭の。
彼女の作画スタイルは独特で、普通なら紙の範囲内で書くのだが、メリー・アンは書いた後、あえて、破り捨ててしまうのであった。
どんなに美し線が引けていて、限りなくリアルでも、人の心を打つような抽象画でも、彼女は残酷にも、手で破り捨ててしまうのであった。まるで、いらないチラシを捨てる母の如く。
メリー・アンの隣を座るボーイフレンド、ヘンダーソンはいつもこう言っている。
「結局、安定して打率を残せるようなバッターが男の中では人気で、ホームランが多く、打率が低いホームランを打てる選手は女に人気なんだ」
「私は安定している方が好きだな」
「君はそういうけどね、違うんだ。女の子にモテる男っていうのは決まって屑だ。そして、ホームランしか打てないっていうのは詰まるところ屑みたいなものなんだ。ホームランっていうのは、チームプレーから最もかけ離れていて、魅力的なんだ」
「でも、ホームランの威力っていうのはやっぱり絶大じゃないの」
「確かに、満塁なら四点入るから、魅力的だけど、けど、ホームランは嫌いだ」
彼は翌日の試合で、一打席目にホームランを打った後、デッドボールの当たり所が悪かったのか、死んでしまった。
メリー・アンは日本から取り寄せた雑誌を読む
『食欲の秋と言われるのはいくつかの要因がある。まずは気候。夏の項垂れるような暑さから涼しく、過ごしやすい季節になる。次に味覚。実りの秋と言われるように、栗にサツマイモ、ブドウや梨、いちじく、銀杏といったフルーツに加え、根菜類(じゃがいも、れんこん、かぶ、玉ねぎなど)、そして魚介類(秋刀魚、鯵、鮪、牡蠣など)といったものが食べごろである。また秋は日照時間が減り、セロトニンの分泌量が減りトリプファンという栄養素を欲しがるため食欲が増える。主にこれらの要因が秋を食欲の秋とたらしめる』
VANKAという名前の雑誌で、雑誌には日本の食事が描かれていた。
さんま、あじ、かき、それらどれを取ってもメリー・アンには美味しそうに見えた。
日本の美しさ。四季がある国、それが日本。四季から読まれた俳句や詩といったものはアメリカ人であるメリー・アンが何度も原文で読み返すほどであった。
メリー・アンは着物を着て、日本を観光していた。
メリー・アンの思う四季を楽しむ日本人の姿はなく、せっかく日本語という美しいリズムを持った言語を存分に発揮せず、文学を嗜まないのは、もったいないと感じた。
だが、今の世界の忙しさが、楽しむ隙を奪っているように思えた。
メリー・アンは珍しくスランプに陥っていた。
メリー・アンの生成する断片の文は無限に生成できるわけではないのだ。
メリー・アンの指は動かない。彼女はかなり動揺している。
メリー・アンは必死に祈る。
だが、メリー・アンの指は動かない。
メリー・アンは再び祈る。
それでも、メリー・アンの指は動かない。
メリー・アンは酷く絶望する。
メリー・アンが絶望したのち、暴れに暴れて、ヘミングウェイがショットガンを自分に向けて撃ったように、ショットガンを口に差し、引き金を引いた。
だが、弾は装填されていなかった。なので、メリー・アンは自分が死んだと錯覚して、気絶してしまった。
メリー・アンは起きた。
何もなかったかのように、部屋を片付け、壊してしまった皿や椅子などを買い出しに行き、ゴミをまとめて、ホコリ一つない綺麗な机の上にアルコールで良く拭かれたパソコン、明窓浄机といったところだろう。数時間前は本や、衣類やごみで散乱していたとは思えない
メリー・アンは本を読む。
『tonight in all bar』
メリー・アンが駅前にある『モスキート33』という本屋で見つけた本である。
これは読者も読むことが出来るので、ぜひ読んで欲しい。
メリー・アンは長い間、面白いと思える本に出会っていなかったのもあってか、本を見つけたときは少女のようにはしゃいで喜んだ。
『モスキートダブルスリー』
メリー・アンは思わず、呟いた。
そして、丁寧に、慎重に、メモへと書き込んだ。
メリー・アンは言葉を大切にする。
『モスキートダブルスリリー』のような意味のない言葉、記号としてしか活用されていない言葉。
特にメリー・アンが好きなのは『バナナフィッシュ』である。
メリー・アンは本を読んでいる間、文章に癒される。文字が目を通し、脳を介して、全身のありとあらゆるところまで行きわたる。文字はメリー・アンにとって血液のようなものであり、数字は己の存在のためにある。
メリー・アンは文字に洗われた後、特殊な体験をするのがルーティンとなっていて、その体験が日に日に激しくなるのを自覚するのと共に、その体験は段々メリー・アンの崩壊を教示しているかのようだった。
メリー・アンはトラベルバックを持って、自宅を出て、タクシーに乗った。
メリー・アンはホテルラビッゾに着いた。
404号室のカギを受け取り、部屋に入って、部屋を見渡してみると、造りが明らかに豪華だった。カーテンの柄は複雑で綿密に作られていて、カーペットの柄も同じような作りだった。ベッドに飛び込むと数センチも沈み込んだため、そうとういいマットレスを使っていることを身体で感じた。
メリー・アンは何をするでもなく、ただひたすらに本を読み続けた。
文字に洗われ、洗われ続ける。
こうして、メリー・アンは文字通り、文字に洗われ、メリー・アンは文字で構成される。
天井や壁、床を這いまわる。そして、部屋を侵食する。ホテルラビッゾ404号室は文字で溢れ、周りの部屋まで侵食し始める。
周りの部屋にあるモノも、同じように構成する要素を数字から文字へと変化させ、メリー・アンのようにさらにあたりを侵食する。
メリー・アンによる文字のパンデミックである。
だが、ふとメリー・アンが文字を拒絶するとたちまち文字は本の中へと戻っていき、メリー・アンは再び数字で構成される。
メリー・アンは部屋にあった観葉植物に備え付けのコップに水を入れて、水やりをした。途端、観葉植物には花が咲いた。
その花は強烈な粉を巻き散らした。
麻薬のようなもので、およそこの世にある麻薬とは比にならないほど、強烈なものである。
メリー・アンはそれを思いっきり、鼻から吸い込んだ。
メリー・アンは全身を震わせ、ベッドに倒れ込んだ。段々、体が溶けていった。体中の細胞が、六十兆個の細胞が、抵抗一つせず、静かに死んでいった。
皮膚が溶け、肉も溶け、骨も溶け、ありとあらゆる臓物が溶ける。
湯気のようなものを出しながら、溶ける。
溶けたメリー・アンは、エイリアンみたいにホテルラビッゾを内部から溶かしていく。
溶けるメリー・アンはスプリンクラーみたいに自身の血肉をぶちまけ、404号室にはポツポツと穴をあけ、404号室を中心に阿鼻叫喚の嵐が発生する。
やがてホテルラビッゾはメリー・アンで溶け切った。
メリー・アンは目を覚ました。
『tonight in all bar』を枕元に置いて、寝ていたことに気づく。
随分、長く寝ていたみたいだったようで、ポストには入りきらないほど郵便物があることに気づく。
メリー・アンはいきなりパソコンの前まで行き、強烈な勢いでキーを叩き始める。
モーガンはショットガンを持ち、ウィルは小回りが利くハンドガンを手に取った。
モーガンは尋ねる。
「ウィル。中には何人いるんだ」
ウィルはハンドガンのスライドを引き、マガジンを確認しながら答えた。
「五から六といったところだ。服を着たサルを始末するだけだ」
モーガンはトランクを閉める。ウィルは集合住宅の扉を開ける。
ウィル、モーガンの順番で建物の中に入る。
…
全部で十万字にも及ぶ短編小説で、内容はかなりチープでジョークの効いたアメリカ人の好きそうな安っぽい物語である。
メリー・アンは驚愕した。
今までは脈絡がない断片ばかりだったのに、脈絡がある、筋と言えるものがある。初めて、文の連続体、文、言葉の墓場から、文章へと昇華したのである。
メリー・アンは戸惑った。
いつもはあの小汚いおじさんに、送り付けるのだが、彼がメリー・アンを買っているのは、断片的な文を作るスキルがあるということ。
脈絡があるということは、買ってくれないに違いない。そう考えたメリー・アンは出版社に持ち込むことにした。
メリー・アンは一枚陰謀を噛ませることにした。
「この小説はラリって書いたんです」
「はあ、それを売れと」
あまり乗り気ではない、担当のチャンという女はその原稿を見た。
「『fiction two』ね。これの前があるわけでもないのに、トゥーが入ってる訳ね」
チャンは何か納得したような顔をして、その原稿を手に取った。
「分かりました。預からせていただきます」
メリー・アンも受け取ってもらえるとは思わず、皮算用をしていた。
百万ドル売り上げたら、十万ドルが。一千万ドル売り上げたら、百万ドル手に入る。そんな下らないことをひたすらに考えていた。
くだらないことを考えている内に、電話のベルがなった。
「売りましょう。ドラッグうんぬんかんぬんのオマケつきで」
チャンはそう言った。メリー・アンは驚いた。
たちまち本は売れた。一千万ドルは年内に達成された。
そして、メリー・アンは消えた。
断片的であったメリー・アンに乾杯。
もし、脈絡がないなら、でも、発生するだろう。だが、消えないだろう。
…キーを強烈に叩き始めた。
断片的な文の塊を、ジョンソンに送る。今度は二テラバイトにも及んだ。
メリー・アンは外に出て、バーガーショップとは反対にあるファミリーレストラン『ブラック』に入って、丁度ランチの時間だったので、Aセットのミディアムを頼んだ。
運ばれたステーキを見て、舌を回して、フォークとナイフで丁寧に、丁寧に切り分けて、口に運ぶ。噛めば噛むほど、肉汁が溢れ出る。
想像してみて欲しい。口の中にサイコロサイズのステーキがあって、バーベキューソースの風味が口の中に充満する。そして、飲み込む。
スルッと落ちていき、胃の中に、一つ、二つと、入り段々と溜まっていく。
そして、空になった皿を見て、『もう一個ステーキ、いやたらふく食べたいなぁ』ってそう思った時にはもう、
「このAセット、ミディアムでお願いします」
この呪文を唱えて、今度はクールな紳士のように涎掛けを丁寧な所作で首に巻き付けて、運ばれてくるステーキに心を躍らせながら、待つだろう。
メリー・アンは結局二個目を頼むことはなかった。
それで、『ブラック』は突然、閉店した。
最後のステーキを食い終わったあと、店内はざわつき、アナウンスがなる。
『ブラックをお楽しみの皆様へ。大変残念なお知らせです。本日を持ちまして、ブラックは閉店いたします。オーナーがヒステリックなり、ブラックの所有権をよそへ売ってしまったようで、そのよそのオーナーがブラックを閉店させて、パーキングエリアにしてしまうそうです。本日の閉店時間まで、ポイントカードがたまっているお客様につきましては、景品の方交換いたしますので、お申し付けください』
メリー・アンは、ポイントカードを確認して、十ポイント溜まっていたが、交換するのは邪魔くさいと感じたので、後ろの席のファミリーに押し付けた。
メリー・アンはメリー・アンを取り戻さなければいけないと思った。
あまりに、断片的過ぎる自身の生活に不安を感じた。
虚構の、バグが、この原稿を、犯す。
いずれにせよ、立ち上がり、立ち去らねばならない
メリー・アンは早速、支度の準備をした。
パスポート、財布、服、本、ペン、ノート、地図、軽食、その他諸々、バッグに詰め込んで、軽い足取りで、外に出た。
早速、メリー・アンが向かったのは小説家であるモンロニーであった。
フリーライター時代、インターネットで少しやり取りをしていたのが、モンロニーであった。モンロニーは女性で、昔のメリー・アンのことを知っているらしいということをメールボックスで発見した。
モンロニーの家はこじんまりとした一軒家であった。
モンロニーはショートカットで、カーディガンを羽織った、黒人女性だった。背はメリー・アンと同じくらいで、柔らかい誰でも話しかけやすそうな、そんな目の大きくていつも笑顔が絶えない女性、それがモンロニーである。
「お久しぶり、ミス、メリー・アン」
今日は尋ねたいことがあって、
「ええ、伺っているわ。さあ、こちらに座って」
ありがとうございます。
「またせたわね。アイスティーしかないけど、いいかしら」
大丈夫です。
「それで、メリー・アンのことかしら」
ええ、私の過去を。ミス、モンロニー。
「あなたとは、メールでしかやりとりをしたことがないから、文面からの推測になるけど、随分文学論を語るのがお好きで、かなり気の強い女性であったことは覚えているわ」
文学論とは。
「そのままよ。あなたには悪いけど、どれも陳腐なものばかりね。どれも既出といったらいいのかしら、それでも、一つだけ目を見張るものがあったわね」
それは、一体。
「ええと、何かしらね。私もメールボックスのものは定期的に消しているからね」
そうですか。でも、断片的ではないのですね。
「そうね。論だからね。でも、内容は少し捻りがあったわね」
はあ。
「ん、そう。断片的ではない。でも、内容は文章が構築する虚構の世界において、いかに断片的で脈絡がないものが美しいのか、そんなタイトルだった気がするわね」
「まあ、このぐらいかしら。あなたも、行くとこがあるのでしょう。さあ、行ってごらんなさい」
ありがとうございます。
そう言って、メリー・アンはモンロニーの家をでた。
次に向かったのは、小学校時代の先生を訪ねたのであった。
名前はポールという名の男性だった。
高校はもう廃校になっていたので、ポールの自宅へと向かった。自宅はかなり大きく、プールはもちろん、庭まで完備されていた。
「ようこそ、ミス、メリー・アン」
こちらこそ、ミスター、ポール。
「早速、こちらにこしかけてくれ。僕も、君と話すのが楽しみだったんだ。よらンダ、アイスティーを頼む。アイスティーでもいいかい」
大丈夫です。
「君のことは覚えているよ。随分独特な読書感想文を書いていたからね」
読書感想文ですか。
「ああ、読書感想文さ。でも、肝心の内容が思い出せないんだな。これが。でも、君は随分脈絡があったり、アクションにロジックがあったり、エビデンスを元に人が動いたり、そういうのを嫌がっているように見えたね。君の出す提出物はいつも、断片的でね。例えば、一行で済むことを箇条書きで書いたりとか」
はあ、断片的ですか。
「君は随分断片に拘るみたいだけど、なんで今のメリー・アンはそんなに断片に拘るんだい」
多分、私は怖いんです。完成されたモノが。
「なるほど。怖いのかい。完成されたモノが。」
ええ。
「でも、断片的であることも良いと思うけどね。それもまた美しい」
そうですか。
「君はまだ回るとこがあるんだろう。さあ、いってらっしゃい。若いのは有限なんだからね」
ありがとうございます。
最後に向かったのは、孤児院であった。
そこのシスタークレアは実質、メリー・アンにとっての親であった。
孤児院の奥へと案内されるメリー・アン。
大聖堂の奥の椅子に座るシスタークレア。
「お久しぶり。ミス、メリー・アン」
お久しぶりです。シスタークレア。
「早速、本題に移ろうかしらね。まず、あなたの幼少期だけど、例えば、貴方は百ピースのジグゾーパズルを買ってもらったとして、一ピースだけ残して、残りは捨てちゃうような子で、その代わり、その一ピースをなによりも大切にする子だったわね」
捨てたんですか、九十九ピース
「ええ、捨てたわね。それで、サモトラケのニケの欠けている部分を作った時には、大変出来映えの良い彫刻が出来上がっていたわね」
失礼ですが、サモトラケのニケの完成体は見たことあるのですか
「ないに決まっているじゃない。でも、あなたはあの欠けている状態を完成体というのね。それもいいけど、逆に、あれが完成体だと考えるのも中々楽しいと思わない」
はあ、欠けている状態が完成体ですか
「ええ、想像してごらんなさい。作り手が、必死に四肢をそろえて、作る。そしたら、いきなりハンマーをもちだして、腕と顔を壊しちゃうの。破壊の美学っていうのかしら。ステキだと思わないかしら。中々に奇抜で」
確かに、その考え方も素晴らしいですね。
「そういえば、あなた、元々は小説家だったのよ」
本当ですか。
「ええ、あなたの本、ここにあるわよ」
普通の物語ですね。
「そうよ、陳腐な物語。でも、貴方がこれを作った時ビックリしたわ。なんせ、欠けているのが好きなあなたが、小説っていう完成されなければその体を成さないものに手を伸ばしたのだから」
確かに、少し不可解ですね
「でもね、数作出して、貴方はフリーライターになってしまった。サリンジャーみたく隠居生活にあこがれたのかは知らないけど」
そうですか。
「これぐらいね。私の言えることは。さあ、そろそろお祈りの時間よ。出て行って頂戴」
ありがとうございました。
メリー・アンは家に帰って、猛烈な勢いでノートに書きなぐった。
私、メリー・アンは以前のメリー・アンなどなかったのだ。
私は今も、文学が好きである。それはモンロニーからの証言で確信した。
そして、断片。
多分、完成という死に向かって行く自分が怖くて、完成とか、完璧とかを、嫌い始めたんだと思う。
断片であることは永遠に完成しない。
だが、断片とはジグゾーパズルの一ピースも断片であるし、もしかしたら、サモトラケのニケも元々は数十体いた天使の内の一体で、たまたま現代に残ったのがあの一体だったので、さも、その一体が完成品であるように思われている。そう、サモトラケのニケも捉えようではサモトラケのニケ自身が断片でもあるのだ。欠けた部分を作ったというが、常識という偏見に縛られてゆえに、頭と腕しか作っていないのだろう。
つまりは、断片も捉えようによっては、完成されたモノの一つでもあって、サモトラケのニケは完成品でもあったかもしれない。すべては捉えよう次第というだけだが、そういう捉え方が出来るという事は、完成されたモノから完成されたモノへ逃げていたという事になる。
メリー・アンはノートの上に、滴を落としたが、笑っていた。
そしてフリーライターを志したのも、小説や、詩といったある種の形式に縛られない、真の文面上での自由が担保されたのがフリーライタ―であったのだろう。
でも、小説家になったということは、脈絡という人生のレールに一度でも戻る意思を見せたということである。
結論としてはこうだ。メリー・アンという女性は確かに存在した。
そして、メリー・アンに以前も以後もなかった。
メリー・アンは完成を恐れて、断片に逃げ続けた。
でも、いまこうして結論に至ったということは、メリー・アンは確かに克服したのである。
メリー・アンはその後小説家として、数々のベストセラーを世の中へと送り出したのであった。
(完)
「くちひげ」執行

食糧や自分たち以外の生き残りを求めて旅をしている。
しかし、そこはゲームの中の世界だった。
腐食した段ボールの中から、ゲームソフトが出てくる。それは明らかに私たちのことを表している。黒いボブヘアーの女と、茶色のロングヘアの女が、終末世界を旅するという内容のゲームだ。
しかし、ゲームソフトを手にした本人、
黒いボブヘアーの彼女はピンときていない。
「へー、私たちみたいだね」
そして、私も指摘しない。
いや、指摘することはできない。私はとうに気付いている。私はキャラクターでしかない。私には自由な発言など許されていない。このゲームタイトルを見て納得した。私はこのゲームのキャラクターだ。そして、プレイヤー。つまり主人公はきっと彼女だろうとも思う
「この主人公の子、レノに似てるかも」
レノと私は数か月前に出会った。いや、“ずっと前から親友だった”。しかし、私たちはここで初めて会って、ここで生まれた。そしてその瞬間、
“いままで”ができた。不思議だったが、そういうふうに感じた。
私たちはシェルターの中で目覚めた。私たち以外に、ほかに人はいなかった。“いままで”によれば、私たちは鋭い氷河期から逃れるためにシェルターに身を隠し、今後数百年は外へ出られないということがわかったために、コールドスリープにかけられた。あたりに立ち並ぶカプセルはそれぞれ、開いていたり、壊れていたり、様々だった。そのどれにも人の姿はなく、シェルター内の食料もほとんど底をついている。
食料を見つけるため、そして生存者を探すため、私たちは外に出た。
そういう、筋書きだ。
「こっちに缶詰がいっこあったよ」
「こっちは、何も」
やっぱりこの辺にはもう何もない。何もかも取り尽くされている。取り尽くされているのに、
床には埃が高く積もっている。やはり、もう私たちの他に人はいないのだろうか。
そろそろ、サイタマを出ようか。彼女が言った。お誂え向けに、川にビルが倒れ込んでいた。これなら渡れそうだ。誘われるように向こう岸に。足が震える。もう行きたくない。どこで尽きようと同じだ。しかし、渡るしかなかった。
「今日はここでキャンプにしよう」
彼女が、明るい声で、いつものようにそう告げる。そうしてテントを張り、ボロの寝袋にくるまって眠る。彼女は、いつもすぐに寝てしまう。寝る瞬間、彼女の顔を見る。こぼさないようにじっと見る。虚ろで、不安に押しつぶされそうで、
今すぐここから逃げ出したいとでも言うような、暗い瞳。きっとこれが彼女の本当。気丈に振る舞うしかない。気丈にしか振る舞えない彼女の、
本当の本当。ぞくりと胸が高鳴った。
「おやすみ」
言い終わると、すぐに彼女は眠りに入ってしまった。どれくらい時間が経っただろうか。私はずっと天井のシミを見ていた。打ちっぱなしのコンクリートはまばたきのたびにうねって、知らない表情を見せる。
眠っていたレノがもぞりと動いて、私の手を握る。
「起きたの?」
レノは静かにうなずいて、いっそう強く私の手を握りしめた。それから、怖い、と空気を震わせる。
「いつになったら終わるんだろうね」
これを言うのは、私でも、レノでもどちらでもよかった。どちらもそう思っていた。
「エンディングがきたら、私たちはどうなるんだろう」
わからなかった。私たちはお互いを強く抱きしめた。もう何日も体を洗っていない。レノは酸っぱい匂いがして、ごわついた髪には白いフケが絡みついている。それが嬉しかった。
夜のレノは昼の彼女とは違う。
これは単に私の予想だが、きっと私たちの出てくる「ゲーム」の中では、夜の時間はスキップされてしまうのだろう。プレイヤーが眠ると選択すればたちまち朝が来る。まるで私たちの夜など存在しないかのように。私たちにだって、不安な夜や、星を見る夜があるのに。
だから夜の間だけは、レノは“彼女”から“レノ”に変わる。レノは私のたったひとつの希望だ。この地獄のような世界でふたりきり、たったひとり、私と絶望を分かち合える人。
「ふふ、苦しい」
いっそう強く抱きしめて首元の空気を吸えば、レノはくすぐったそうに笑って私の腕からするりと抜けた。その顔は笑っていた。私も笑った。
レノが笑っているのが嬉しかったから。それから、レノは泣いた。朝がくるのが怖いと泣いた。もうこれ以上何もしたくなくても、体は動いてしまう。怖くても、泣くことすらできない。それが恐ろしい。
夜の間にふたりで死んでしまいたい。
そしてレノはそうこぼして、静かに私からの返事を待った。返事はなかった。しなかったから。私は、ただレノをじっと見つめた。
「……うそだよ。ごめんね」
眉をきれいな八の字に変えて笑ったレノは、
そのまま後ろを向いて眠ってしまった。
鉄骨の隙間から、雪が降っているのが見える。まだ日は昇りきらないが、差し込んだ陽の光が、雪に反射して外は眩しい。知らない。朝までの時間をスキップしてしまうおまえたちは、きっとこの美しい景色を知らない。
フィクションの私たちしか見れないおまえたちは、彼女の、寝息を、伸びた爪を、うすいそばかすを、赤らんだ頬を、ニキビを、知らない。もう、日が昇る。煌々と輝く太陽が、雪に乱反射する。朝が来てしまう。私たちの時間が終わってしまう。
鳥が鳴いた。
「おはよう。今日も探索頑張ろう」
つんと眉が吊り上がり、口角が上がる。ああ、彼女だ。その口元に、伸びきったくちひげが揺れていた。彼女の美しさを保つために、モニタ画面には映らないであろうそれを見て、良かった、と思う。
「おはよう。うん、頑張ろうね!」
私だけが知ってる本当が、ここにあって良かった。
(完)
「浪漫」波多野 善二

だが、ギヤマンでの仕事中に心情に変化が起きる。
マチスは仕事をやめ、国へ反乱を起こす。
錆びついた線路の上を歩き、長い闇を抜けた先には、一面ギヤマンの世界が待ち受けていた。
マチスはギヤマンで浪漫人として、一種の見せ物として、仕事をしに来たのであった。
ギヤマンの世界こと、東都はこの国の主要経済の大部分を担っていた。
東都には生き延びるという需要を、過剰なまでの仕事量をこなすという条件のもと、配給のチケットという供給が満たす。
そんな東都に生きる労働者は一部の労働中毒者を除いて、皆生き延びることに大変苦痛を覚えていた。そこで、マチスのような浪漫人と言われるいわば俳優のような人間が、生きることが出来ない、生き延びることに囚われる労働者の為に、舞台上で、カメラの前で、生きることを代行するのであった。
マチスは今日のスケジュールを確認する。
一一〇〇到着、一三○○東都南劇場、一八○○ホテル
マチスは早速、南劇場に向かった。
途中で、藁を担ぐ瘦せこけた女、必死に楽器を演奏する子供、つぎはぎのスーツを着て商談に向かうであろうサラリーマン、馬に荷台を引かせる目つきの悪い商人、半屋内のカフェからこちらを見つめる白髪がくちゃくちゃの老婆、マチスはこれまでと変わらない景色に一種の安堵を覚えつつも、働く幸せを享受しているのは東都も田舎も変わらないという事実を、この国の貧乏が解決されていないことを再確認した。
マチスは途中、国から支給された拳銃を使用するかもしれない危機に見舞われつつも、無事南劇場に着くことが出来た。
「こちらへどうぞ。マチス様」
そういわれ、控室に案内されるマチス。
「今回はよろしくお願いします」
マチスがそういうと、支配人と思われる慇懃(いんぎん)な態度で、スーツをきっちり、着た人物は、脚本を取り出した。
その脚本には『座頭市』と書かれていた。
「今回、マチス様には座頭市を演じていただきます。座頭市はご存じで」
マチスは座頭市というあたりの演目を引いたことに喜んでいた。
「ええ、勝新太郎、北野武の座頭市は一度拝見しております」
「それはどうも。どちらを演じるかは任せます」
そう言って、支配人は会釈をして、控室から出ていった。
マチスは、脚本の中身を軽く流しながら、読んだ。脚本には主な物語の流れのみが書かており、サブのセリフは書いてあるが、座頭市のセリフは書いていない。
マチスが飯を食えているのには、これが理由であった。
セリフがない、つまりはアドリブで劇に挑む訳であるが、そのアドリブの素晴らしさが、客寄せとして十分な機能を果たすのである。
マチスの演技は何をさせるにしても
マチスは劇が始まるまでの間、ひたすらに自身の中に座頭市像を思い浮かべる。
座頭市といえば、悪を許さず、悪に対して、徹底的に無慈悲であり、かといって、自分から積極的に悪を退治するとも思えない。そんなことを頭に巡らす。心の中に巾着のひだになっている部分を少し緩めてやり、座頭市を入れる。
そんなことをしている間に、幕が上がる。
舞台にあがったマチスは手八丁口八丁で、座頭市を見たこともない、観客たちに座頭市とはこういったものであるという模範解答を叩きだしたのである。
ヤクザが子分を連れて、座頭市を通せんぼする。
「手前、座頭市だな」
座頭市は刀を逆手で持つ。居合の類は達人の領域である。
「野郎ども、やっちまえ」
子分が叫び、刀を目の前に、座頭市へと向かう。座頭市はその子分どもを、見事なまでの剣捌きで、美しい殺陣(たて)を魅せた。
この場面が今日一番盛り上がった部分である。
「マチスさん、本日の演技大変美しく、思わず、惚れてしまいました。これが、今回の分のギャラになります」
支配人がそう言うと、少し厚い封筒をマチス側に差し出した。
「こちらこそ、ありがとうございます。おかげで、飯を食えるというものです」
そう言って、深々と会釈をして、マチスはホテルの方に向かった。
マチスがホテルに着いて、一番にするのは、役を自分の中から、抜くことであった。役に飲まれ、職を失っていった先人の浪漫人を見てきたからである。
マチスは、ノートとペンを取り出して、今日あった出来事をメモに書き記していく。マチスは浪漫人であると共に、作家でもあったのだ。
自身の体験をエッセイの形で、売るのであった。このエッセイ一冊売る為に、政府から認証を貰うのに、三年はかかったのである。
マチスは十ページほど、東都のこと、座頭市のことを書き、毒抜きを終える。
マチスは最近、浪漫人としての職に飽き始めている。
マチスは政府から情報を制限されている労働者相手に、自由という希望の光を少しずつ小出しして、金を巻き上げるのは、あこぎなやり口だと思った。
マチスは浪漫、つまりは自由奔放に生き続ける姿を魅せ続けることに、段々と精神を蝕まれているのであった。証拠に、自身の名を語る際、役の名前を口にしたり、燃え尽き症候群のように、やりたいこと、自分のわがままがなくなったりしている。
薄々、気づき始めているのである。自身が政府に意思を殺された国民相手に商売をしていて、自身と国民との間には明確な差があり、上に立っているつもりだったが、実際は政府の掌の上で踊らされている醜いマリオネットであったことに。
マチスも政府に心を殺されている国民の一人であることは、次第に反逆心のようなものを芽生えさせた。
マチスは叫んだ。
「今に、今に、見ていろ。尊厳を取り戻して見せる。私は人間を取り戻して見せる」
マチスはふつふつとした怒りになんとか蓋をして、床に就いた。
マチスは翌日、最高の演技をした。
浪漫を見せつけるように、一挙手一投足どれを取っても、国民に対して、訴えかける。そんな政治家の演技であった。
それから、政府宛に辞職の旨の手紙を送り、東都を去った。
マチスは一日、二日経っても収まらない怒りを大事に、持ち歩き、長い長いトンネルへと向かった。
トンネルに入り、錆びた線路の上を歩く。先はまだ見えず、歩けば、歩くほど、背中を照らす光は消えていき、やがて真っ暗になった。
東都へ向かう時の道のりは長いとも、短いとも思わなかった。それは、マリオネットであったから、政府に行けと言われれば行くだけだった。そこにマチス自身の感情の介入はなかったためである。
もう何時間経ったのだろうと、不安が段々大きくなる。そして、さらに長い時を経て、もう一度思った。もう何時間経ったのだろう。
トンネルの暗闇の長さはまるで、これからのマチスのゴールへの険しさを暗示しているかのようだった。そうマチスは思わざるをえなかった。マチスの歩く線路も次第に躓きやすくなっていた。
だが、今度は光が見え始めると、マチスの末にはゴール、そしてゴールの先は明るい未来を暗示しているように思えた。
マチスはそんなくだらないことに一喜一憂する自分に飽きれつつも、その思いが次第に現実味を帯びる可能性に恐怖した。
錆びついた線路の上を歩き、長い闇を抜けた先には、一面どす黒い雲に覆われた暗黒世界が待ち受けていた。
そんな暗黒世界がマチスにとっては、かけがえのない故郷であった。
マチスは少年時代に追いかけた白い雲が恋しかったが、今も変わらず働き続ける母の姿は何一つ変わらなかった。
そんな母を横目に、マチスは知り合いの革命派の友人を訪ねた。
「すみません。ジャックはいますか?」
『ジャック』それはコードネームで今は『ガルシア』である事をマチスは手紙の中で知っていた。勿論、革命派として活動していることも。
「やあ、マチス。元気にしていたか。とりあえず、中に入ったらどうだ」
そう言ったガルシアは平気でネズミが走り回る部屋にマチスを案内した。
「ジャック、だな」
外にはガルシアの母が必死に働いていた。
「ああ、ジャックだ。いきなり帰省とは驚いたな。親が泣くぞ」
マチスはコートを脱いで、イスに掛け、バッグを置いた。
「実は、浪漫は辞めたのだ」
ジャックは一瞬驚いた顔を見せたが、すぐにその顔は優しい人を迎えるような顔になった。
「やっぱりな。そんな所だと思ったよ」
ジャックは続けて、
「でも、僕はその決断を心から尊重すると共に、心から歓迎するよ」
マチスは全てを察してくれた友に感謝した。
「ああ、君なら分かってくれると信じていたよ。いや、信じる前にあの手紙のやり取りから、確信していたね」
そう言い、マチスはバッグから手紙を取り出した。その手紙は数十通にも及ぶもので、バッグはへたれた。
「君、全部丸々保存していたっていうのかい。よくこんなことやるよ」
「政府の奴に少しでも、君とのやり取りがバレるのが嫌でね。つい」
ジャックはそんなマチスに驚きつつも、そんなマチスが革命派に加わることを頼もしく思った。
ガルシアは早速、活動内容と計画について話した。
「うちでは、週に三回ほどこの家の地下室で会議をする街宣活動に執筆活動。そして、今月の末にはここ西都を略奪する」
「ちょっと待て、何で執筆なんかする必要なんかあるんだ」
ガルシアは興奮気味のマチス落ち着かせるように、
「いいか、いつの時代だって、映画や小説はその世相を反映してきた。そして、政府もプロパガンダとして利用した。国民のコントロールをしようとするのと同じで、我々も小説という最も安価で簡易で効果的な方法を用いて、国民を正しい道へとコントロールしなければならない。だから、私たちは昼も夜もペンを動かし続ける」
落ち着かせるつもりが、若干興奮気味に喋ったガルシアはキッチンの方へと向かった。
「何か飲むか」
マチスは喉が渇いたわけでもなければ、何かに酔いたい気分でもなかった。
「いや、遠慮しておくよ」
マチスは寂しそうにしているガルシアの顔を見て、申し訳ない気持ちがありながらも、これからの活動に浪漫時代とは大きく異なった楽しみを見出すことができ、嬉しい気持ちでいっぱいいっぱいだった。
ガルシアは冷蔵庫から酒を取り出し、ジョッキに注いだ。そして、次から次へと酒を空けて、マチスとの会話を楽しんだ。マチスは飲みすぎではないのかという不安を抱きつつも、酒の匂いで軽く酔ったらしく、そんな不安もすっかり忘れて話に花を咲かせた。
ガルシアの顔が真っ赤になったところで、マチスはガルシアの家を後にして、実家に戻ることにした。
マチスの実家はまだ灯りがついており、マチスは母親の反応にドキドキと不安を持って、ドアを開けた。マチスの母親は机に伏しており、内職の為の道具に覆いかぶさるように伏していた。
途端、マチスの目頭が熱くなり、涙が流れた。
マチスは思った。
自分の母がこんなにも必死に生き延びるため頑張っているのに、自分は遅くまで反社会的な人間と酒を浴びて、せっかくの仕事も簡単にやめ、親の気持ち知らずに簡単に家の敷居を跨いだことを悲しく思うと同時に、シングルマザーである母に対する申し訳なさがあふれて来た。
だが、マチスはそんな母を捨ててでも、今の国の現状を打破しなくてはいけないと思った。
マチスは初めて自分が起こしたことの重大さに気づいたのである。
翌日、マチスは早朝に起き、机には謝罪のメッセージに加えて、マチスはもういないという旨を書いた。
母はまだぐっすり寝ている。
「さようなら」
そう言い残し、自らの使命を果すべく、ドアを開けると、町は早朝の割にはざわついており、その音が大きくなる方向へと向かった。
そこには黒いビニールシートで覆われたガルシアの家があった。
例えば、重体の人間を運ぶとき、殺人現場などで現場検証をするとき、大抵は青いビニールで覆われる。
だが、この国で黒いビニールに覆われるということは国家に対する反逆者を処分したという暗に込められたメッセージだったのだ。
マチスは背中を死神にそっとさすられるような感覚を覚え、後には汗が垂れていた。いずれ、自分もああなってしまうのだろうか。
マチスはもう嫌なことしか考えられなくなっており、その場に何十分も立ち尽くした。
自分自身のこと、死んだガルシアのこと、親のこと、今身を置いている危険な環境、それまでのプロセス、暗いトンネル、母親のこと、煌びやかに浪漫人として一般の国民よりはいいものを食べて、いいベッドで眠り、いい服を身に着けていたこと、これらがひたすらにマチスの脳内にサブリミナルに映し出される。
マチスは汗をかいている。冬なのに。そして死神の鎌が己の首を捉えていることをはっきりと認識する。
そんな廃人となりつつあるマチスは、さらに目の前に信じられない光景が飛び込んでくる。
ガルシアの死体である。
ガルシアの体どこを取っても激しく膨張しており、彼の少し出たお腹は皮膚がはち切れ、その下に眠る黄色肉が露見されていた。彼の顔のパーツはいくつか欠損していた。片方の耳がなく、両目とも目が見えないほどに腫れて隠れており、目の片方がないことを片目が宙ぶらりんの様子を見て認識した。鼻は曲がり、唇は切れ、半分切れた舌が、腫れた唇の上に乗っかていた。
マチスは叫ぶでもなく、走り出した。
西都の一番北にある彼岸へと必死に走った。
マチスは黒い雲に包まれ、荒れる波を見て叫んだ。
「神よ!人間は何故いともたやすく人間を殺してしまうのですか。何故、彼等は殺人に悦を感じることは出来るのですか。神よ!この愚かな種を作り出した責任はどうとっていただけるのですか。神よ!神がこのような歪なシステムを作り出したのですか。神よ!人間が神をマネて作ったというのであれば、責任を取ってください。神よ!私を、私を、殺してください」
マチスは生まれて初めて、神を信じ、祈った。
だが、何も返ってはこなかった。
マチスは打ちひしがれていた。ショッキングな光景を目の当りにして、震えて足が動かなかったのだ。
ふと、崖を見るとマチスの目にはガルシアが映っていたのである。
「ガルシア。僕もすぐにそっちに向かうよ」
そう言い、崖へと一歩、一歩向かっていく。
マチスの前にもう地面はなく、荒波がいざなうように、波を立てている。
飛び込もうと体重を前に預けた時、マチスは頭に強い衝撃を受けて、倒れた。
マチスが目を覚ました時、着ていた服は変わっていて、体は椅子にしっかりと拘束されているのを確認した。
そんなマチスの目の前には赤いバンダナをしたベリーショートカットの女の子が立っており、マチスに話しかけた。
「あなたがマチスっていうのね。ガルシアの言っていた男の像とはずいぶん弱弱しいわね。こんな奴でも浪漫人として飯を食えるのだから、不思議よね」
そう先制攻撃されたマチスは困惑しつつも、反撃をした。
「見た感じ、国の奴らといった感じではないが、俺をどうするんだ。ガルシアみたいにリンチして、殺すか」
「そんなことはしないわよ。あなたには革命の手伝いをしてもらうだけよ」
マチスは呆れた顔で
「革命を手伝うのか。いやだね。もう、生きるのすら疲れたのに」
女はズボンの後ろポケットから銃を取り出し、マチスの口に突っ込んだ。
「死にたいなら、殺してあげる。でも、あんたはガルシアの仇を取りたいって思わないの?あなたの尊厳は踏みにじられたままよ。悔しい思いも、ガルシアの無念も、我慢したまま、何もせず死ぬか、一発政府にぎゃふんと言わせてやるか。どっちにするの」
「俺は、俺は、やっぱり政府に一発くれてやることにするよ」
満足そうに女はマチスを縛っていた縄をといてやった。
「私はエミリー。エミリー・パッチェンス」
「俺はマチス。よろしく」
そう言ったマチスとエミリーは強い握手を交わした。
「早速だけど、あなたにはもう一度国に従事してもらうよ」
「スパイ的な役割ってことか」
「ええ、勿論。明日には国の車がやって来て、あなたを衣食住の整った環境に連れていってくれるわ」
「分かった。俺は俺に出来ることをやるよ」
マチスはそんな女が何故手配出来たのか、そしてガルシアの名を知っているのかについて、一切の疑問も持たずに、眠った。静かな闘志を秘めて。
翌日、マチスは約束の場所で待っていた。
黒い綺麗でシンプルなデザインの車が前に停まり、運転手が降りて、ドアを開ける。軽く会釈をして車に乗り込み、運転手はエンジンをもう一度掛ける。
マチスは途中跡形もないガルシアの家を見て、心に復讐を誓った。
車の中でぐっすりと眠れるほど、長い移動時間を経て、寮のような所に下され、目の前には白髪の爺さんが待っていた。
「こんにちは。マチスと言います」
爺さん一度深々と頭を下げて、
「待っていました。私、ここを管理するボッシュと言います。以後お見知りおきを」
丁寧にあいさつをされて、自分がどういった待遇なのかを確認したのち、部屋を案内してもらった、
「…ここがシャワー室になっています。また何かあったらそこの黒電話でお申し付けください。では、おやすみなさい」
まるで高級ホテルの待遇を受けているような気分でいたが、爺さんが部屋を出たことを確認したのち、机の上に置いてある書類に目を通した。
書類には、業務内容、生活のルール、配給について詳しく書かれていた。
肝心の業務内容は政府のプロパガンダの為の映画の脚本、および小説の作成であった。
政府の尊厳を踏みにじる非道な行為に怒りを覚えつつも、黙って辛抱強く業務を淡々とこなした。ひたすらに、女からの手紙を待っていた。
一年目から、めきめきとその才覚を生かし、政府から、表彰を貰うほどであった。二年目、三年目もともに、プロプロパガンダクリエイターとして、世の中に多くの作品を送り出した。
そして、マチスの座るイスは段々と座り心地の良い椅子になり、鉛筆から万年筆へ、食事も満足いくものが食べられるようになった。
十年経って、秘書が付くようになって、検閲者として、今度はマチスが作品にケチをつける側へと回った。
そして二十年、マチスの元に手紙は送られてこない。二十年の間、何度も、外へ出て、手紙の真意を確認しても良かったのだが、少しもぼろを出さないために、はらわたが煮えくり返るような思いで、待った。
とうとう、マチスは隠し持った拳銃を持ち、報道担当副大臣という肩書を引き下げ大統領室へと足を運び、大統領にその銃口を向けた。
「死にやがれ。この野郎」
だが、大統領は不自然なほどに落ち着いていた。
「死ぬのはどっちかな」
そう大統領が呟くと、カーテンから銃を持った男が現れ、マチスを撃ち殺した。
「マチス君、君は最高のライターだよ。浪漫人という枠は君には狭すぎたみたいだね」
「この国は破壊させない。恨むならこの私をトップに押し上げた。国民を恨むのだな」
そういって、マチスの亡骸に唾を吐いた。
(完)
「家族についての考察」執行

ずっと向き合わないまま逃げてきた家族のこと、私の幼少期からのことを、一度ちゃんと考えてみようと思ったから、これを書きました。
家族のことから、父のこと、母のこと、祖母のことまで。
令和六年、四月。
両親が離婚したという連絡が入った。
私は「そうか」と思った。別に不思議なことでもなかったし、悲しいことでもなかった。
むしろ、晴れやかな気持ちだった。これは父や母に恨みがあるからではない。
父と母にとって、その方が良いはずだと思っていたからだ。
私の幼少期の話をしよう。
と言っても、よく思い出すことができない。
私の記憶の箱には鍵がかかっている。
ただ、たまに何か、匂いや季節や言葉なんかをきっかけにしてその鍵が開くことがある。
そういうとき、決まって私の気分は悪くなる。
良い記憶ではない。だから、私が閉じ込めてしまった。
私も最近になって気がついたことだけど、私の家庭は異常だった。
「虐待」と聞いて、何を思い浮かべるだろうか。
私がフィクションで見た虐待は、私の家庭にはなかった。アザだらけになるまで殴られたり、火傷を負わせられたり、しなかった。
だから私の家庭はおかしいのかもしれないなんて、本当に思っていなかった。
中学生のときはもちろん、高校生の時もだ。漠然と親が嫌いだという気持ちだけがあった。
年上の信頼できる人に一度だけその気持ちを吐露したとき「思春期だからね」と馬鹿にしたように笑われ、続けて「大人になったら親に感謝する日が来るよ」と言われた。
私は「そうか」と納得した。無性に恥ずかしくなって、それ以降、親が嫌いだという話はしないことに決めた。
恥ずかしかった事と言えば、もうひとつある。
何歳のときだったか、もう覚えてない。外でおしっこをするのは恥ずかしいことだってことはわかってたから、きっと小学校低学年とかだと思う。
きっと冬だった。
ひりついた指先と、冷たい肺。足を伝うおしっこが、あったかかったことも覚えている。
冬の日、家から締め出されて、私はドアを叩いて泣いていた。叫んでいたような気もする。
裸足だった。怖かった。
パニックになってドアの前で前泣き続けた。
騒ぎを聞きつけた近所のおじさんが私の様子を見に来た。私はおじさんと目があったとき、そこに立ったままおしっこを漏らした。
いつもそっけなく、怖い印象のおじさんだったのに、優しく声を かけてくれて、奥さんと一緒にお風呂にまで入れてくれた。
私は「おもらしを見られて恥ずかしいな」と思った。
その後から、締め出されても、ドアの前で「おしっこ」と何度も叫べば、鍵を開けてくれるようになった。
トイレ以外の場所に行くことは許されていなかったから、私はトイレに閉じこもった。
でも、うちは屋根が定期的に落ちるようなボロボロの木造一軒家で、だからトイレに鍵はついていなかった。
必死にドアを抑えたけど、子供の力では勝てない。私はトイレから引きずり出されて、その後。どうなったんだっけ。
わかるのは、すごく怖かった気がするということだけ。
前述のとおり、私はボロボロの木造一軒家に住んでいた。今はもう危険だとかで取り壊されて、元あった場所には白いマンションが建っている。
私の家は、二階建てで、はしごのような斜度の階段がかかっている。
当然階段も古くて、体重100キロオーバーの父が一段上がるたび、ドスと音がする。
私はそれがすごく怖かった。
父は怒るとヒステリーになって、その場にある適当なもので私の頭を打つ。
父がいるのはいつも一階リビングで、私が父の機嫌を損ねるのも大抵そこだった。
そうなると私は、痛いのが嫌で、階段を駆け上がって布団にもぐるのだ。そうすると、ドスドスと階段を誰かが上がってくる音が聞こえる。
どんどんと音が大きくなり、やがて私の布団が剥がされる。
私が泣き喚くと、寝室に置かれたミントの香りの消臭剤を私の目に吹き付ける。
それをする父の顔が、憎しみや怒りに染まっているならまだマシだった。
父は笑っていた。洗っても洗っても、目が痛かった。泣いても、目を擦ることはできなかった。
中学生になったとき、父が脳梗塞になった。
一年かそれ以上、父は帰ってこなかった。
私は一度も見舞いに行かなかった。ほっとする時間だった。
でも、私の家でおかしいのは父だけではなく、母もだった。
私は父が帰ってこない一年間、カップラーメンだけを食べ続けた。カップラーメンは好きだったから、別に気にしていなかった。
家は、ボロボロな上にゴミ屋敷手前だった。
普通の人に聞いてみたけど、床にものがあるというのはあまりないことらしかった。
私の家はもので埋め尽くされ、冷蔵庫の中には腐った食べ物がたくさんあった。
私はそのころ、ゴキブリやネズミが怖くなかった。そんなもの、そこら中で見るからだ。
母は子どものような人だった。
母はまともに働いたことがない。
氷河期世代だったこともあるかもしれないが、そもそも就労意欲がないに等しく、時間も守れないし体力もなかった。
実家が優しかったのも関係するだろう。私がまだ子どものとき、母は電気代や水道代、ガス代を一切払っていなかった。
とうとう電気が止まってから、父が慌てて払おうと思っても、稼いだはずのお金は残っていなかった。
母は、家のお金を全て趣味の手芸に宛ててしまっていた。
でも、私に可愛い服を作って着せてくれた。
母はミシンが上手かった。
当然、父は激怒したが、母はよくわかっていなかった。
怒られて悲しいと思っていた。そういう人だ。
母は好きなときに好きなことをするのが好きで、それによって自分が不利益を被っても、ケロッとしている。
好きなときに好きなことをできることの方が彼女にとっては重要だった。家族ができてもそれは変わらない。
母はまっすぐに自分しか見えていなかった。
純粋な子どものよう。ただ咲いているだけの花のようだった。
父は、この母を支えていきたいと言って結婚したらしい。
でも、母のまっすぐさは父の想像をゆうに超えていた。
父は官能小説家だった。昔のコミケに思いを馳せ、娘ができてもロリエロ同人誌を大切に保管していた。
父の語る過去は、全部ウソだったと私は思う。生徒はもちろん先生たちからも嫌われてるヤバい生徒だったけど、頭の良い人たちだけは俺の凄さに気付けるから周囲には賢い人しかいなかった
偏差値は全科目70超え。すごくモテていて、カラオケに行けば知らない女の子が膝に座る。
父の顔は私に似ているため、あまり言いたくはないが、もちろんかっこよくはない。
更に、太っている。そして、父は高卒だ。父には凄まじいコンプレックスがあったんだろう。運動部や騒がしい人たちを嫌い、文化系で静かな人たちを好んだ。そして、私たち子供にも、父のようにいてほしがった。
私がほしいと言ったものはほとんど叶えられることはなかったが、芸術に関してだけは違った
パソコン、ペンタブ、絵の具、なんでも買ってもらえた。
私が友達を作らず、学校から飛んで帰ってきて黙々と絵を描いているのを見て、父は嬉しそうだった。
きっと父は、自分の生き方を肯定されたかったんだと思う。
かわいそうなのは弟だった。
弟は運動が好きな元気な子だった。
少年サッカーチームに所属していて、絵や文章なんてからっきし。
夏休み最終日に、泣きながら作文を書き、結局何も書けずに白紙のまま持って行った。
父はそれが許せなかった。
弟は私より四つ下だったから、打たれたりスプレーをかけられたりすることはなかったが、それよりも酷いことをされていた。
元気な弟には、同じように元気な友達がたくさんいた。
父は「あいつらと一緒にいるから馬鹿になる」と言って、友達と離すためだけに弟を計二回転校させた。
当然のように、サッカーもやめさせた。
進学した少し遠くの中学にはサッカー部があったが、防災部というほとんど活動のない部活に入ることを強制した。
弟は作文を書けるようにはならなかった。
ただ、あんなに元気だった弟は、静かに、無気力になっていった。
私の家族は、ずっとおかしかった。
そして、父が脳梗塞になったあの日から、崩壊が始まった。
弟は何もやる気がなく、学校に何度も何度も寝坊した。母も起きないから、担任が電話をかけたところで繋がるはずはなかった。
担任が昼休みを使って家に来た。弟は夜中に泣いていた。きっと弟は要注意人物だっただろう。
母はうつ病だった。家庭に縛られて、父に毎日怒鳴られる生活で、鬱にならない方がおかしかった。
ミシンはホコリをかぶり、たくさんの布も一切使われることは無くなった。
母は一日のほとんどを寝て過ごし、起きている時間は着せ替えゲームをしていた。
いつも両耳にイヤホンをしていて、私たちが何か言っても何も聞いてくれなかった。
父は、可哀想な人だった。
祖母は、小学校低学年の私が描いた絵を見て、下手くそ、人体がおかしいと言い放った。
父の家は自営業の飲食店で、祖父は働きづめで家にはあまりいなかった。
私はここに、父のルーツがあるんじゃないかと思う。
父は寂しかったのだ。歪んでいた。
きっと彼は、母を見て、何もできないこの子を支えたいと確かに思った。
自分の存在を認めてくれる人が欲しかった。
でも母は、父がいくら働いても、そんなことには感謝しなかった。
波に揺られながら生きているだけの母にとって、父がたくさん働くことの意味はきっと理解できなかった。
父は誰かに認められたかったのに。
父の脳梗塞の原因はわかりやすかった。
父はほとんど睡眠を取らずに仕事をしていた。
私は
私は、何をしていたんだろう。それも思い出せなかった。
私はただずっと、目を背けていた。何もわかっていないふりをしていたのかもしれない。
私は自分の家がおかしいと思っていなかった。弟が転校すると聞いたときも「そうか」と思った。
母が一切食事を作らなくても「そうか」と受け入れた。
私はどうする気もなかった。現状をただ受け入れて、それでいいと自分を納得させていた。
父が脳梗塞になって、収入が無くなった。
私の家庭は所謂生活保護になった。
当時中学生だった私は、働かなきゃいけないと工業高校に入学した。
そのまま状況が変わらなければ、私は未だ実家にいて、今日も仕事に出掛けていたたろう。
だが、状況が変わった。私が高校一年生のときだった。奨学金制度に大きな変化があった。
給付型奨学金。私でも大学に通うことができるようになった。
当時はコロナ禍、求人も減っていた。
工業高校では普通の勉強をしない。数学は数Ⅰ数Aしかやらなかった。
私は私の学力でも入れる大学に入学した。
私は、家を出ようとは思っていなかった。
ただなりゆきで、いつの間にか家の外にいた。
家の外に出た。モヤがかかっていた脳がクリアになっていく。頭がふっと冷えていく。
いままでの十八年間ずっと混乱していて、今やっと落ち着けた。そんな気持ちだった。
私の家庭って、変だったんだ。と気付いたのもこのときだった。
私は、家族が壊れていくのを、
遠い大阪から一人で見ていた。
ゴールデンウィーク明け、別居が進んだ。弟は母と一緒だ。
母は最近、手芸を再開した。
ボサボサの髪に骸骨のようなすっぴんだった母は、ちゃんとメイクをするようになっていた。
私は嬉しかった。母がまた自由になれたらいいなと思った。
父は苦しそうだった。
祖父、つまり父の父は、父が脳梗塞になったしばらくあとに死んでしまった。すごく嫌な死に方だった。
祖父は父によく似ていた。祖父母は私が小学生のときに晩年離婚をした。どうしようもない人で、祖母は愛想を尽かしているみたいだった。
祖父はワンルームマンションで一人暮らしを始めた。そこから狂い始めた。
文字通り狂ってしまった。祖父は隣の部屋に何度もうるさいと怒鳴り込みに行った。祖父は夜勤をしていて、昼間に寝ていると隣の部屋がうるさくて眠れなかった。
でも、そんなはずなかった。隣の部屋には誰もいなかった。聞こえるはずのない声が聞こえるのか、それともどうしても誰かと関わりを持ちたかったのか、誰にもわからない。
ほどなくして祖父は体を壊した。入院することになったが、病院でも祖父はそんな調子だった。
祖父は拘束された。人たちは祖父を老害だと蔑んだだろう。孤独だった。
祖父はそのまま病院で死んだ。
父は脳梗塞になってから、一層様子がおかしくなった。
異常な神経質。さらに、記憶力も落ちた。
父の記憶はあやふやだったが、もともと忘れ物をしやすい母や私の記憶は信用せず、自分が正しいと思っていた。
いや、きっと父もわかっていた。できないことが増えていくのが苦しかったのかもしれない。
さらに、クレーマー気質にもなった。私が通っていた塾に何度も何度も怒りの電話をかけた。理由はすべて意味のわからないものだった。教科書が高すぎるとか、そういうものだった。
教科書は三千円で、別に高くなかった。
朝、父の声で目が覚めることが増えた。
時計を見るとまだ五時だった。
寝室は別れているのに、急に何かに取り憑かれたようにこちらの寝室まで走ってきて、ひとしきり何かを叫ぶと帰っていく。
それが月に何度かある。母に怒っているのはなんとなくわかった。
眠かったから、目を閉じた。
父はきっと祖父のようになる。孤独に毒され、死んでいくだろう。自業自得だ。
でも、本当にすべて父のせいだっただろうか。父が愛されて育っていたら、自分に誇れるものがあったら。
妻や子供に愛されて、自分を認められるようになっていたら。理想的なたらればは、
全てが手遅れになったあとに現れる。もう全部叶うことはない。
父は愛されたかったのに、愛されるかたちをしていなかった。皮肉だ。父のヒステリーや暴力の真の根源は愛されたい気持ちだったのに、それによって誰もが離れていった。
母と弟はこれから幸せになっていくのだろうか。
だとしても、過去は変わらない。
弟は高校生になった。もうサッカーはしていないが、バレーを始めたらしい。
私は嬉しくて、八千円のボールを買って送った。弟には自分の人生を歩んで欲しかった。
けど、弟の通う高校は父が決めたものだ。他に行きたいと言っていた場所があったが、一年以上に渡って「ここにしろ、そんなとこに行きたいなんてお前は馬鹿なのか」と言われ続けた弟は、志望校を変えた。今の私たちの人生に、どのくらい自分で決めたことがあるだろう。
私の趣味である絵だって、父に促されたことかもしれない。
かくして、家族は無くなった。少しさみしかった。こんな家族だったのに、私はいつかの日の幸せな昼下がりを覚えている。
日の光が射す窓際で、母のミシンの音を聞きながら、弟と遊んでいたあの日の光景をまだ思い出せる。
私はどんなことがあっても、確かに家族を愛していた。
もうあの日は帰ってこない。狂った歯車はもう戻ることはなかった。
でも、崩壊は同時に希望の光でもあった。
私はこれからも生きていく。
自分の足で自分で選んだ道を歩いていく。
父も、母も、弟も。
もしかしたら、スタートラインは他の人より一歩後ろかもしれないけど、隣の芝は青いけど、先にあるものが、幸せな終わりとは限らないけど、それでも。
(完)
「咲き乱れ」波多野 善二

だが、高校の先輩である三谷由香がさらわれたのを皮切りに、破滅へと進んでいく。
【この物語は、フィクションである】
昼間の町にしては随分陰気な雰囲気を漂わせるこの町は閉鎖的で、明暗がはっきりしている、そんな町の警察である藤田はそこらでは名の知れた刑事であった。
「藤田、もうこれで何人やったんだ」
警部補である種田はそう言って、机を強く叩き、眉間にしわを寄せる。
藤田はおよそ人を殺した人間の顔とは思えないほど、寂しい顔をしていた。
「とりあえず、始末書持って消えろ」
藤田は始末書を持って、自身のデスクに戻り、乱暴に引き出しの中に入れて、部屋の外にあるベンチに腰掛け、タバコに火を点けた。
どこか遠いところを見つめ、廃人のようになっていた藤田に、よく面倒を見てくれ、気にかけてくれる杉下が声を掛けた。
「よう、元気にやってるかい」
藤田は首を縦に振った。杉下も同じようにタバコに火を点けた。
「今晩飲みにでも行くかい」
藤田は首を横に振った。
「あらそうかい」
その一言を最後に、藤田と杉下との間には時間だけが過ぎ去っていった。だが、お互いそこまで気まずいとも思っておらず、ただタバコの灰が落ちるだけであった。
先に吸い終えたのは杉下の方で、手で軽く挨拶をしてから、そこを去った。一人ベンチに座る藤田は始末書を始末することにしたのであった。
普段の態度からは考えられないほど、慇懃な文章で、消しゴムで消しながら、文章を書いていく。消しカスはもう十分なほど机に溜まっていた。
ひとしきり書き終えて、内容をしっかりと確認したのち、種田の元に提出しに行った。幸い種田は不在で、机に始末書を置いて、勝手にパトロールと称して、町に繰り出すのであった。
藤田は所謂私服刑事というやつで、本来なら仕事をするような真っ昼間からほっつき歩くのが常となっていた。普通なら、競馬好きのろくでもないおじさんという感じだろうが、一部は彼が非常に敏腕で凶暴な刑事であるということを知っていた。
商店街を少し進んだところにある雀荘へと足を運んだ。
藤田は卓について、慣れた手つきで牌を触り始めた。
ゲームが進み、入店した時刻である十五時から長針は十二を三回ほど通り過ぎた。
藤田は次第に、卓の雰囲気が悪くなるのを感じており、それが予定調和であることを知っていた。
すると向かいにいた刺青を入れた坊主の若者が、急に牌を投げつけた。
「てめぇ、この野郎。誰が三回も続けて役満なんか出せるんだよばかやろー。イカサマなんかするなよ、手前」
そう言って、若者は藤田の胸倉を掴んだ。
藤田は胸倉を掴んできた若者の目に穴を開けるかのごとく、見つめた。
「ぶち殺してやる」
そう言って、若者は自身の胸ポケットから、ナイフを取り出し、藤田の胸に突き刺そうとした瞬間、藤田は持っていた点棒で若者の目を思いっきり刺した。
刺された若者は魚のようにジタバタしており、それを横目に藤田は落ちていたナイフで指を思いっきり掻っ切った。
さらに悶える若者。藤田は周りを見渡し、自然な足取りで出口へと向かう。扉を開ける瞬間、店長に呼び止められた。
「あんた、いくら刑事やからってええこと、悪いことの区別くらいついとるやろ。ここはしのぎになっとるさかい、悪いことは言わねぇからさっさと金置いて出ていけや。己」
そう捲し立てられた藤田は、恐ろしいほど冷たい顔で、店主の顔面を殴った。
そして、乗ってきたデボネアで、湾曲している綺麗な海辺まで走り、タバコに火を点けた。血生臭くて、湿っぽくて、陰気な雀荘とは大違いで、海の運ぶ塩っぽい匂いは藤田の澱んだ心を洗った。
特別、正義があったわけでもなかった藤田にとって、犯罪者、およびその予備軍はおもちゃのようなもので、警察が市民を守るという大義名分を掲げ、暴力を行使する。ただ、サイコパスと違うのは、次第に、楽しむ気持ちより、被害者へ寄り添う気持ちが芽生え、いつしか、しっかりとした報いを受けていない犯罪者に制裁を加えるという本音にすり替わった点だろう。
藤田は、思い出したように車に乗り込み、大学病院まで車を走らせた。
「三谷さん、かなり具合は良くなっていますが、メンタル面のケアはしっかりとしてあげて下さいね」
そうカルテを抱えた看護師が告げ、病室から去っていく。
藤田は、黙って三谷由香の荷物を持ち、共に病室を出た。
「ねえ、藤田くん。また私迷惑かけちゃったかな」
大人の色気が出る甘ったるくて、今にも虜にされそうな、そんな魅力的で低い声で藤田の耳に息を掛けるような声で話しかける。
藤田はタクシーでこんなことやめてくれよ、と思いながら、まんざらでもない顔をして、
「三谷さん、今晩は退院祝いでもしましょうか。国産の牛肉をタップリ使った旨い奴」
由香はまんざらでもない顔をする藤田の顔を覗き込んで、ニヤッとした後、大学病院を囲むようにある海をひたすらに眺めていた。
藤田はまだまんざらでもない顔をしながら、ニヤケを止めるので必死だった。
タクシーが自宅のアパートに着くと、藤田は三谷を家に置いて、買い出しに向かった。藤田の脳内には、あのセリフがリピートされていた。藤田の耳はあれ以来ずっと耳は赤いままであった。
三谷との会食に想像を膨らませながら、藤田は早足で帰った。
鍵を開けた瞬間、変な静けさが藤田に酷な宣告をした。
三谷の口周りにはあふれ出した錠剤のようなもの、机には空の薬瓶が置いてあった。
藤田は声を掛けず、薬瓶を確認して、三谷のほっぺを叩こうとした。
「チョット、たんま、たんま、これラムネだよ」
ヘラヘラと笑う三谷、憔悴する藤田。
藤田は、まっぴらといった感じで、由香を本気で殺そうか、と考えた。
気づけば、夜は明け、藤田と由香は別々の布団で寝ていた。
三谷はだらしなく、下着を露出させながら気持ちよさそうに寝ていた。
藤田はそんな気持ちの良さそうな顔を惜しみながらも、いつものようにシャツにズボン、そしてジャケットに腕を通し、アパートを出た。
デボネアにキーを差し、回す。そして、少しの間エンジンが温まるのを待った。
藤田は左ポケットからタバコを取り出して、火を点けた。
吸って、吐いて、吸って、吐いて、そう何度も喫煙をする。段々とタバコの灰が長くなって行く、二センチを超え、三センチを超えた所で落ちそうになったので、藤田は灰皿に落とす。
藤田は不意に由香を思い出す。
タバコの灰を長く作って落とす、そして灰をじっと見つめる。
そんな彼女のルーティンをいつの間にか真似していた。のちに彼女から、このルーティンが彼女オリジナルではないことを知らされることになる藤田であった。
警察署前に着き、刑事課の札が掲げられている部屋へと入る。
藤田はデスクに座り、何をするでもなく、ぼーっと窓際の景色を見ていた。
追いかけっこをするカップル、サーフィンをする男、群れを成し、空飛ぶ白鳥達、そんな藤田が担当する刑事事件の凶暴さとはかけ離れた清らかで景色に青みがかっている景色は藤田の頭を真っ白にしてくれていた。
何か考えているようで、何も考えてなさそうな、でもやっぱり何か考えているような顔をした藤田がいる刑事課の戸は、勢いよく開かれた。
眼鏡を掛け、少しほっそりとし、頬がこけている、背の高い威圧感のある人間が口を開ける。
「皆さん。お初にお目にかかります。私ここの署長に就任いたしました、西園寺雄一郎と言います。どうぞ、よろしくお願いします」
そう深々と礼をし、あたりを一望したあと、藤田に目線を合わせ、不敵な笑みを浮かべ、その場を後にした。
藤田はそんな西園寺をよそに、ひたすらに景色を見ていた。それは精神病患者特有のそれであった。
そんな藤田は気が付けば、現場にいた。
「藤田さん、珍しく早い到着ですね」
「だって俺が通報したんだもん」
そういたずらっ子のような、由香のようなからかう笑いを見せた。
現場には死体が、一体腹部に刃物のような傷跡を付けて残っていた。
刺された男の持ち物や、身元から売春の斡旋業者の一人であることが分かり、
藤田は下請けである男がマージンを要求し、犯人を激昂させ、殺されたであろうことがすぐに分かった。
「藤田さん、系列の人間が三人連続で死んだってことは、やっぱりあいつらなんですかね」
「そりゃみたら、分かるよバカヤロー」
そう言って、藤田は部下である小島を軽くどついた。
藤田は残りの現場検証を小島に一任して、車に乗り込んだ。
「藤田さん。どこ行くんですか」
そんな先輩に対して咎めるような口調で小島は言った。
「風呂屋いって、サッパリしてくんだよ」
そう言って、藤田は車の窓を閉めて、思いっきりアクセルを踏んだ。
小島は藤田がソープに行ったのであろうと思い、デボネアに乗る藤田を恨めしい目で見つめた。
警察である藤田がスピード違反ギリギリに、向かった先は、アパートであった。
アパートをコツコツと音を立てて、不自然に静かな近所の家、アパートに不安を覚えながら、藤田が思う最低な事態になっていないことを願った。
鍵はかかっておらず、土足のまま部屋に入ると、最低以下の光景がそこにはあった。
布団には不自然にかたどられたシミと、今朝三谷の来ていた下着が捨てられてあった。そこに三谷の姿はなく、窓は開いて、カーテンはなびいていた。
藤田は人形のように、ゴミ袋を出して、布団と下着を入れた。そして、この話は警察署に帰ってもしなかった。
警察署に戻り、刑事課の部屋に入ろうとした時、杉下に話しかけられた。
「藤田、所長がお呼びなさっている。またやったのか。な」
杉下は笑いながら藤田の肩を軽く小突いた。
そんな杉下とのやり取りに軽く笑みを浮かべ、署長室へと向かった。・
ノックを三回し、部屋に入る藤田。部屋の奥の席に座る西園寺は、そんな藤田に椅子に掛けるよう、合図した。
「君は中々の問題児らしいな。前署長からそういった旨の話はいくつかお聞きしてね。君は何かとすぐに暴力を振り、挙句の果てには、殺してしまうそうではないか」
そう言って、西園寺は机の引き出しから、ビニールの袋に入ったものを見せる。
「これを忘れたとは言わせんよ。君が刺して、殴打した、点棒と灰皿だ」
そう言って、灰皿をポンポンと手の平に当てる西園寺。
「こいつで思いっきり殴ったわけだ。雀荘の店長を」
藤田は、署長に何か訴えかけるような目線で西園寺を見た。でも媚びるような訴えではなかった。
「分かっているよ。しのぎの場所だってことぐらい。でもな、藤田。今のここのアタマは私だ。私のやり方でやらしてもらうし、部下の君は黙ってそれに従えばいいんだ」
今後一切、ヤクザに手は出すなというお達しと、始末書を持ち帰り、藤田は自分のデスクへと戻り、また机に突っ込んだ。突っ込まれた紙はくちゃくちゃになった。
藤田は隣町へと繰り出した。
だが、特に目的があるわけでもなくただ歩いて回るだけであった。
藤田の目に映るネオンに色はなく、光が虹彩を介さず、視神経へ渡り、脳へと伝達される。色のない景色にも少し青がかかっていた。薄い青、水色とはまた違った優しい色。
そんな藤田目掛けて、後ろから刃物が襲う。
「藤田さん。やり逃げはよくねぇよなあぁ。今度の署長なんて言ってたか知ってるか。な。アンタ、おしまいなんだよ」
藤田は刃渡り十センチほどのサバイバルナイフを、両手で、腹部の前で受け止める。寸前。
ナイフを両の手で止める藤田、刺そうとするオールバックで白のジャケットのヤクザは段々と力み始め、らちが明かなくなってきた。
ヤクザは藤田を蹴り、両手にはナイフを持った藤田が尻もちをついた。ヤクザは内ポケットから拳銃を取り出し、藤田に向ける。
ヤクザも藤田のように氷のような冷たく、やけどしそうな顔で、引き金を引く。
弾は出ない。
「あんたこの意味分かってるよな」
ヤクザはヘラヘラと笑いながら言った。三谷とは違って、心底腹の立つ笑い方で、可愛げもなければ、構ってやろうとも思わなかった。
だが、藤田は構ってやってもらっている側の人間になった。
ヤクザはその場を去り、藤田はその場に座りつくした。その藤田に目もくれず、人々は無意識に避ける。それはホームレスや動物の死体、ゴミを避ける動作であった。
藤田は路地裏で、両手に刺さったナイフを慎重に口で取り出し、包帯でグルグルと巻いた。ヤクザとのひと悶着。ただのひと悶着ではなく、刑事としての生命、人間としての尊厳、戦うものとしての最大の屈辱を受けたような気であった藤田はその日から、その時まで、一切の笑顔はなかった。
翌日、藤田はそのヤクザが篠塚という名で、その子分が複数死体で発見されたことを知る。
そんな篠塚を追う事しか頭になかった藤田はひたすらに町を歩いては、地域住民に聞いて回った。勿論、暴力を行使してジャンバーの深い青に段々と、血が返っていき、日が落ちるころには、殺人犯の恰好であった。
ひとしきり、情報を集め終え、アパートへと帰る。
何日も帰っていない部屋には、コバエがたかっていて、住むには苦痛を感じ、強盗すらも入ろうとしない、不気味な部屋へとなった。
藤田にとって、不気味な部屋の一番の苦痛は、においであった。
三谷が藤田の目の前から消えた時の部屋の匂い。
男女が獣のように交わった時に匂う、肺や、脳を引っ搔き回し、糞のようなにおいであった。
藤田の脳裏には、由香がレイプされている映像がループしている。
抵抗する由香、襲う男、それを傍観する藤田。同じ叫び、悲鳴、助けを望む儚い声、泣く由香の声、ひたすらにループし続ける。レコードは同じ溝をひたすらなぞり続ける。
三日は飲まず食わずで、風呂はキャンセルされ続けた。
藤田は、無意識の内に、銭湯へ向かって、気づけば白髪交じりの爺さんと一緒にフルーツ牛乳を飲んで、温める。
テレビにはニュースがやっていて、正午のニュースが始まろうとしていた。
『ニュースです。〇×川の橋下で、首を吊った死体が発見されました。死体は警察署に務める杉下警部補であることが分かりました』
藤田はその日のうちに、お通夜に行った。
藤田は杉下の家内から、一通の手紙を受け取り、すぐにその場を立ち去った。
ホテルに入り、手紙の封を切る。
『藤田、お前がこの手紙を読む頃には、ヤクザに消されただろう。俺も警察やり始めの頃は、一点の曇りもない、自分なりの正義の看板掲げてやってきたつもりが、今やヤクザと癒着するような落ちこぼれになっちまった。でも、必然だったと思う。前署長も、現職も簡単にヨゴレをするような所で、俺は純粋な正義は。二枚目には地図が入ってるから、多分ガールフレンドもそこにいるんじゃないかな。じゃ、こっちは先に地獄で待ってるから』
手紙の中には、ヤクザの事務所の地図が入っていた。
その日のうちに、署へと戻って署内にある重火器をかき集め、事務所へと向かった。
事務所は商店街の外れにあるビルの二階に構えていた。
事務所の一階にはスモークが張られていて、一階の扉をけ破り、組員が一人、イスに座って、けいれんを起こしている全裸の女性につけられている首輪のようなものを付けて、雑誌を読んでいた。
まるで、人間の動物園のようであった。
薬に手懐けられてた女たちは、ありとあらゆる快楽に飽き、エクスタシーを求め、その体をけいれんさせ、うねらせる。女は自身の手で、自身の体をなぞる。
魑魅魍魎といったところだろうか、藤田は心乱すことなく、組員を
バンッ
と打った。弾は頭に当たり、即死。
女達に目もくれず、階段を、コツ、コツ、コツと上がっていく。
上がって、右手の扉を見つけ、ボストンバッグから小銃を取り出す。扉を開ける。
「おう。刑事さん。あんたのワイフは中々にええ女やのぉ。名器っちゅう奴やな。ハッ、ハッ、ハッ」
白竜と、その部下が部屋で乱れ咲いていた。
藤田に怒りの感情が介入する余地はなく。引き金を引いた。
バンという音が鳴るたび、一人、また一人、死んでいく。
その場にいた娯楽に興じる白竜諸共は、もう散った。外道とは思えないほど、綺麗に花びらを散らした。
ただ、立ち尽くす藤田と、床を這う三谷。
藤田は三谷を抱える。三谷の肌は恐ろしいほどに、冷たく、目はどこか遠くを見つめ、もうすぐであることを感じた。
「ねえ、藤田君。私、タバコの灰長くするの好きだったよね。あれって、幹彦さんのだったの。フフ」
そう薄ら笑いを浮かべ、藤田が愛したルーティンの真実を語る三谷。
「私そろそろ、死ねるんだね。楽しみだな。学生の頃から、いっつも、考えて、その日、を、楽しみに、楽しみに、ひたすらに、見え、ない、ゴール、に向か、って、あ、あぶない、こと、やったなぁ。いま、おもえば、いい、思い出だけ、しか、出て、こないなぁ」
「いやな、こと、あったのに。藤田君、好きだったよ。私と似てて。それでさ、最後に、さ、私を殺して、ね」
そう三谷は、藤田の左脇から腹をなぞる。
藤田は、左肩に掛けてあったガンホルダーから、拳銃を取り出して、頭に突き付けて、引き金を引く。
三谷はこの部屋の中にある花のなかで一番素晴らしい咲き方をした。
藤田は後ろにいる機動隊の盾の並びを見て、こめかみに銃を突き付けて、引き金を引いた。
この部屋には小さな花がたくさん咲き、大きな花か二つ咲いた。
小島はホワイトボードに貼り付けられた人物関係図を、ジッと見つめていた。
自殺した藤田と殺された三谷由香、系列の白竜とその他。
小島にはよく分からなかった。自殺した藤田の真意、三谷由香がさらわれたことをあえて、言わなかったこと。そして、不自然な死を遂げた杉下。
小島は、この一連は解決しなければいけない、そんな使命を背負わされているような気がした。
不気味な流れに、嫌悪感を示しつつも、向かった先は、藤田の相棒で、元警察の西だった。
あるマンションの角部屋、そこが西の家であった。
西は車いすで出迎え、奥の和室へと小島を進めた。
小島は藤田について、聞いた。
「藤田は、キレると何しでかすか分からないような奴でさ。犯人のこと、半殺しにしちゃうんだよな。これがまた気の毒でね、全員何らかしらの後遺症が残っちまうんだ。それでも、優秀な刑事には変わりなかったし、実際被害者家族から、感謝されてた話は山ほど聞いたね。こう、司法には介入出来ない、感情的な部分の不満ってのがあってさ、それこそニュースなんか見てたら、被害者はレイプされて、殺されて、挙句の果てには、バラバラにしちゃってていうのが、結構な数ある。未成年とか、障がい者の場合、被害者は泣き寝入りしか出来ない。そういった泣き寝入りせざる負えない、被害者のために藤田は代わりをしてたんじゃないかな。ま、勝手な想像だけどね」
「じゃあ、藤田さんは私刑執行人だったということですかね」
「ま、そういったとこだろう。確かに、平等なルールに乗っ取って、裁くのは大切なことだけど、ね。やっぱり、藤田は惜しい奴だな。惜しい奴が世の中早死にしやがる」
西は手を震わせ、茶柱を見つめる。
小島は介せず、質問した。
「杉下さんはご存じですか」
「ああ、警部補の。杉下さんは、いい人ではあったけど、そこまでだったね。黒い噂をよく聞いたよ。銃とか、クスリとか、そういうのを裏の人に流したとか。まあ、よくいる汚職警察だよ。でも、署内で浮いてた藤田を唯一面倒見ていた、優しい人間だったな。杉下さん、元気かい」
小島は、ただ俯くだけであった。
「ああ、殺されたのかい。まあ、そんなことしてちゃ、やられるだろうな。危ない橋渡るってそういうことだからな」
小島は、人が死んでいるのに、冷静に納得し続ける西に強い疑問を覚えると共に、西への強い興味が湧いた。
「西さん、なんでそんなに平気なんですか。相棒でしょ、先輩でしょ、なんで、平然としていられるんですか」
「うーん、平気でいるっていうより、逃げてるんだと思うな。人を失くす悲しみを直接受け止めるのに、俺の体は脆いらしくてね。三人称視点で見ることで、あくまでも俺ではなく、西が悲しみに直面しているっていう図で捉えるんだ。だから、平気なんだよ。確かに、俺は西だ。でも、直面したのは西だけだ。俺は傍観者にしかすぎない」
小島は挨拶をして、最後、玄関前で質問した。
「失礼ですが、その車イスは」
「事件で、藤田を庇ったからね。おかげで、家内も娘も消えちゃったけどね」
皮肉っぽく言って、笑う西。最後っ屁をくらった小島。
「小島君、随分、藤田のことで精を出しているみたいだね」
タバコを燻らす、西園寺。
「一、警察として、当然のことであります」
慇懃な小島。
「今担当してもらってる、藤田の件だが、あれはもう打ち切りだ。こちらの判断としては、藤田による襲撃、逮捕を恐れ、自殺。そういうシナリオだ。もう、これ以上しなくていいから、次の事件でも頑張ってくれたまえ」
事件からまだ一週間も経っていないのに、急な打ち切りに困惑した小島だった。
「はあ、承知しました」
問いただしたい気持ちを抑え、小島は刑事課へと戻った。
小島は、腑に落ちない気持ちを抑えるため、同僚に、新署長である西園寺について尋ねた。
西園寺っていうのは、相当な拝金主義らしくて、前もそういうので、飛ばされたらしい、という情報を聞きつけ、再び、対策会議のホワイトボードの前へと走った。
拝金主義の新署長、ヤクザ、ヤクザを殺した藤田、殺された杉下。
西園寺は業務を終え、迎えの車に乗り込む。
「隣町の、キャバクラの方に向かってくれ」
運転手はアクセルを踏み、隣町へと向かう。道中、余りにも眠い西園寺は少しの間だけ眠ることにした。
「西園寺」
マスクを付けた運転手は、そう言って眠る西園寺の太ももに撃った。
「お前は、誰だ」
「西園寺、いや、署長。僕ですよ。小島です。アンタが金策に精を出している間に、仕事に精を出していた」
「小島。手前、何してるか、分かっ」
小島はまた一発撃った
「質問する」
藤田を殺したのはアンタか
「違う、本当に自殺だ」
じゃあ、杉下は
「それは知らないな」
小島は西園寺を殴打する。何度も、何度も、藤田とは真逆で、顔を真っ赤にさせて。
杉田は
「殺したさ。そりゃ、いきなり正義の面なんて被られたら、商いに支障がでる」
三谷由香は
「ミタニユカ。知らないな」
また一発殴る。
「知らねえよ。バカヤロー」
小島は不貞腐れる西園寺を最後に一発殴って、崖まで車を走らせ、西園寺と車諸共、深海に沈めた。
藤田がいつも眺めていたあの海を汚してしまったことをもうしわけないと思いつつも、小島はすがすがしい気持ちで、こめかみに拳銃を突き付け、撃った。
小島の死体は、車と西園寺を追う形で、海へと沈んだ。 (完)
「鉄塔」波多野 善二

そう、君の町にも、君の生活を見ている鉄塔がいる。
私が建てられたのはもうずいぶん前の事で、私を繋ぐ線は何十回と取り替えられた。
何度、日と月を見た事だろうか。私は町を抜けた先に広がる平原に等間隔で並べられて、鉄塔として人々に電気を供給してきた。
最初の十年で台風により、私は倒れた。人々は入念に地面に棒を打ちつけ、もう一度私を建てた。
私は一時珍物として人の目線を集めた。ジロジロと見たところで何も変わりやしないのに、人は私を見る。自分たちが作ったくせして、いざイレギュラーが起きると外的要因のせいだと騒ぎ立てる。もう慣れたことだが時々私を撮る人も現れる。無機質でしか無い私に向けて指のフレームをあーでもない、こーでもないとブツブツ言いながらはめようとする。
人という生き物は木や石や虫や馬や鹿とはまた一線を画す。どうも本能的な部分と合理的な部分を掛け持ち、自分のことしか考えない。歴史を繰り返す愚か者には嫌気がさす。
私は一般的な鉄塔としての寿命を越し、思ったことがある。この世で、最も醜いものと美しいものは人であると言いたい。最も醜いのは、人が己の為の、己の為に、利益を追求する姿は醜い。さらに、他者を欺き、傷つける者など言語道断である。本能的な部分を剥き出した者は、もう人ではなく人の形をしたどうぶつである。最も美しいのは、人が人と協力し、何かを作り上げて、完成させることである。寿命を超え、様々な人を見てきたが、皆同じように失敗し、成功する。『私は違う』、『私は特別』、『皆とは違う』とほざいているが、結局同じ所に集約される。
私の鉄塔としての役割はただの電気の中継地点でしかないが、私は満足している節がある。ひたすらに中継するこの役割も今となってはすっかり慣れた。この町の景色を見渡せるのは特権である。日々変わる町並み。出勤しているOLの飲み物は違うし、サラリーマンの身だしなみで事情がよく分かる、学生は教科書をじっと見つめている、ベビーカーに乗っている子供は大きくなって、呂律も回り初める、彼ら彼女らの成長は本当に面白いし、どこか楽しみにしている自分がいる。彼ら彼女らの中には何か焦燥感があって、人生の幅に遊びが無くなっているような気がする。
ところで、何故鉄塔の私が人ごときの心配をしているのだろうか。
まぁ、いいか。
二十年経って、私の変化を楽しむ日常もよかったが、違った変化が欲しかった。何気ない日常も、滞りなく行われる四季の変化も良かったが、何かスパイスの効いたものが欲しかった。
そこで私は老婆に目を付けることにした。特に着飾るようなこともせず、ただひたすらに日々を消化しているその姿は、私が見た余命宣告された患者がただひたすらに窓を見つめ、己の死を待つ姿に似ていた。
だが、患者と老婆の違いは、悲しさの有無に尽きる。患者の姿や動き一つとっても、悲しさがなくなることはなく、時間という流れをひたすらに己の身に打ち付け続ける。余命という事実一つが心を蝕み、体も蝕む。言語情報一つで人を死に追いやることはいとも簡単である。恐ろしい発明品だ。言語は。
一方、老婆も先が長くないことは明らかなのだが、彼女の足どりは力を感じさせた。彼女は己が余命わずかということを知っていても、具体的な数字までは分かっていないわけで、恐らく明日死ぬかもしれないという考えがあり、ならば、きょう1日を悔いなく生きる。そういった思考プロセスの元、彼女は強く生きる。商店街をズンズンあるく。重そうな荷物も、上手く体感を使って、ひょいと持ち上げる。先輩の勇敢な様に私は自然と尊敬の念を抱いていた。
私もただ運ぶ、ひたすらに電気の流れが途絶えないように、立ち尽くす。三十年経って、老婆は死に患者は生きていた。
老婆には孫がいたようで、孫は大学生になって、老婆はそれを待っていたかのように老婆は去ってしまった。老婆の一日を大切に生きる姿勢は周りにも影響を与えており、いつも笑いや笑顔が絶えなかった。孫もいっぱいいて、お金にも苦労せず、毎日、徳や他者への思いやりを積み上げ謙虚に生きてきた姿勢は現代を生きる人々に足りないものなのかもしれない。だが、これは余裕あっての話で、余裕のない人間が、自己を犠牲にまでして行うものではないことは留意するべき点であると思う。
老婆は苦の感情一つ見せず、穏やかな表情でこの世とお別れを告げた。葬式では老婆の死を悲しむ者が多数かと思われたが、多くは懐かしんでいた。大勢の親戚が一堂に会し、思い出話を語り合う。葬式という世間では悲しいものとして捉えられがちなイベントは本来懐かしむもの、つまり暖かいものだと思う。
何も、泣くことだけがすべてじゃない。悲しみに浸るだけじゃない。
一方、患者は余命を待つ悲しく、冷たい日々を送っていたのだが、容態が急変し、病の完治により、無事退院できた。多くの者が見舞いに来たかと思えば誰一人こなかった。来るのは看護師と主治医のみである。何故来なかったのか。思えば患者と老婆の大きな違いは結婚の有無であった。
まだ私が建てられていたときの事だった。作業員のある会話が今でも印象に残っている。
「先輩、結婚ってやっぱりいいものなんですかね」
「そりゃ、いいことばっかりじゃないけど、いいものだよ」
「ですよね」
「結婚せずに、年を迎えると固まっちまうんだ。考えが。そんで、自分だけが正しい、そう思い込むようになる。いくらステータスがあっても、人は離れる。悲しいものだよ。一人ベットの上で死を待つんだ。ひたすらに。そして、死の瞬間に気づくんだ。己の愚行に。でも、結婚すると、誰かがいるから、気を遣うようになる。そして気を遣えるようになると、謙虚さが身につくんだ。謙虚が出来る人間が悲しい死に方をしたのを俺は見たことがないね。やっぱり、人間死ぬ瞬間が一番大事な気がするな」患者は看護師や主治医に横柄な態度を取っていて、飯が不味いや酒を飲ませろ、挙句暴れ出す。そんな患者は独身で、大手の企業でそこそこの位まで上り詰めていたらしいが、結婚は出来なかった。謙虚さ、気遣いのできない人間の纏うものは悲壮感だけだった。笑顔は起きない、元気は出ない。唯一嘲笑だけが起きていた。そのまま死ねるならラッキーだ。先は分かっている。
だが、患者は不運にも生き残ってしまった。愛される要素のない患者は誰とも関われず、ひたすらにいつ訪れるかわからない死を待ち続けた。患者の行方は私も知らない。
四十年たって、嘘つき小僧と正直小僧に目を付けた。
嘘つき小僧と正直小僧の学生時代は大きく違うようで似ていた。
嘘つき小僧は両親や先生に最初の嘘をついた。それは学校で飼っていたウサギを殺してしまったことについてだ。当然、躊躇したが完璧主義であるがゆえに、己の完璧さを傷つけられたくないという思いから嘘をついた。バレなかったという事実は彼の嘘へのハードルを徐々に下げていった。次に知らないことを知らないということをとても恥ずかしく思っていたので、何にでも知っているという虚勢を取り始めた。嘘をつき始めた嘘つき小僧は段々嘘の必要のない場面でも、嘘をつき始め、己以外への全てに対して嘘をついていたのが、段々己の気持ちへと嘘をつき始め、嘘つき小僧は、自分の気持ちが真意であることすら分からなくなり、やがて自己の喪失を経て、自殺した。
正直小僧は正直に何でも言う立ちだったので、苦手なことも知らないことも正直な姿勢を取った。周りも優しく真実を教えて上げた。だが、同級生のいたずらについた嘘が正直小僧を歪ませた。人から聞いた事実と実際との相違による些細な違いが癌となり、疑心暗鬼にさせた。正直小僧は人間良い奴ばっかりじゃないということを知ったので、彼も上手に付き合うということを知った。上手く己の価値観に乗っ取って、見定めた。同時に己の良さが死んだ。正直さがなくなったからといって離れる人がすぐに出てきたわけではないが、徐々に離れていった。真意の会話が出来なくなった正直小僧は、真意の会話を求め、隠してきた正直さを見せるようになった。大人になって、それが功を奏し、ほどほどのステータスを手に入れた。正直小僧は自身が正直であることに感謝し、同時に周りも正直さにあやかっていた。
だが、美人局に引っ掛かり正直小僧は築いた全てを失った。絶望した。だが、正直さが信じられた正直小僧は再び、上り詰めた。また、失った。正直であるがゆえに異性にも正直であったせいだ。再び、絶望した。
絶望、人へ、絶望、環境へ、絶望、己へ、数多の種類の絶望を経て、正直小僧は自殺した。
正直であることを知り、己が正直であることを知るのは正直さの消失なりや?
嘘つきが嘘つきであることを知るのは、嘘つきの消失なりや?
はて、自覚すること、それすなわち、アイデンティティの崩壊なりや?人、脆く。儚さゆえの美しさ、そこにみたり。
五十年経って、町は衰退していった。
どうやら隣町の開発の影響で、一気に引っ越ししてしまったらしい。嘘つき小僧と正直小僧の件以来、私は目を閉じ、耳を塞ぎ、ただ存在していた。
この町は赤ちゃんの泣き声より、老人の話声が多い。学生の青々しい声より、老人の雑談の方が盛り上がっている。公園を占めるのは子供ではなく、ゲートボールをする老人が占めている。
あの頃の若者の活気あふれた町はどこにいってしまったのだろうか。あの頃の良くも悪くも忙しい日々はどこにいってしまったのだろうか。あの頃の子供の産声、泣き声、笑い声の聞こえた日々はどこにいってしまったのだろうか。
かつて若者だった者は現代医療の発達ゆえの自然への抵抗、そして新陳代謝の非活性化。本来入れ替わるはずの若者の喪失。コントロールシステムの崩壊。
町は人の結晶体であり、人は細胞である。再生能力を失った町はただひたすらに朽ちるのを待つだけだ。
私が見た景色は消え去った。心なしか、電気もあまり流れなくなった気がする。
立ち尽くす鉄塔と消えてゆく町。六十年たって、私はもう私が鉄塔であることも忘れ、老婆や小僧の話すら忘れかけていた。町を見るのは止めた。鳥が鳴き、草木が散り、花が咲き、川の揺れる静かな音、激しい音、虫が葉を食い、虫を小鳥が食い、小鳥を鳥が食い、鳥を動物が食う。一見食物連鎖の一つのようにしか捉えられないが、体系的な連鎖は命の美しさを再認識させてくれ、世界には生命の理があると認識させてくれる。
あの朽ち果てた町のことを覚えているのはその町の土地だけで、もう私すら記憶が危うい。何かの拍子に忘れてしまいそうなくらいに。朽ちた姿をみるのは悲しい。自分の手から離れていく、というより干渉出来ないまま朽ち果てる姿を見ていることに無力感を感じ、悲しさも感じた。
私もだいぶ錆びてきた。寿命が近づいていることはなんとなくわかっていた。無機質な物体であるからこそ、言葉や自分の考えることはより強く刺さった。刺さってすぐに分かるものではなく、大抵の場合、肉体的に衰弱しだす頃に傷がうずく。
日々、ポロポロと自分の体から落ちてゆく。時間は止まらない。次に朽ち果てるのは私かもしれないと思った。朽ち果て、リサイクルされ生まれ変わるのも悪くはないと思った。心機一転、新しい町を見るのも先の未来としてはいいものだと思った。
だが、久々に見た景色は変わっていた。
朽ち果てたはずの町は復活していて、色があり、元気があり、活気に溢れる姿に私は懐かしさと切なさを感じた。数十年前に見た景色とは多少違っても、私が見たことのある日常は確かに変わりなかった。
十年ほど自然しか見てこなかった私にとってその景色は非常に驚きだった。活気から朽ち果て、もう一度活気を取り戻す。人間の強い部分を見た気がする。窮地に追い込まれても、そこからゆっくりゆっくりカメのように着実に戻ってくる様は強い。もし、もう一度朽ち果てようと人は必ず戻ってくる。そう確信した。
その日から、電気を運ぶ量が増えた気がする。
七十年経った。
私はまだ鉄塔としての役目を果たしていた。もう寿命はとっくに過ぎているはず。しかし、もう終わりは近い。強い風ひとつ吹いただけで、大きく揺れるし、雨が降ると錆びはいっぱい出てくる。もう体がなくなってしまうのではないかと思うほど。
別に死ぬわけではないが、この町の鉄塔としての役目を終えることは寂しい。この町の鉄塔であれたのは貴重だと思う。人を認知し、考えさせ、素晴らしいものだと認識した。
相も変わらず、私は時に被写体として活躍している。人の営みというのなら、私はそれを受け入れようと思う。
傍観者として私にとっての人とはただの観測物にしかすぎなかったのだが、いつの間にかこんなにも身近になるとは思いもよらなかった。私が自然と人を心へ受け入れるとは思わなかった。
やはり、魅力的である。
とうとうその日が近づいてきたのである。
ある大雨の日、風はいつも以上に激しく吹き、雨は強く降っていた。さすがにそろそろヤバいと思っていると、案の定、倒れてしまった。しかも、塔の根本の部分はボロボロで形を保つだけでも精一杯という感じだ。
薬指に指輪をはめて見慣れた作業員がやってきた。白髪になり、顔もしわくちゃだった。しかし、彼の顔つきは大変凛々しく、あの時から随分、場数を踏んできたことが分かる。後輩を連れ、淡々と仕事をこなす様はあの従業員の姿に瓜二つである。
彼らは今後の私の処遇について話し合っている。大方、解体の方向で行くのだろう。気づいていたことである。なぜなら、町から少し離れたところに新たに鉄塔が立っているのを目撃したからだ。
もう、私もかの老人のようにいずれ、この世から立ち去らなければならない。
私は電線を外され、巨大なクレーンで釣り上げられ、積み込まれ、どこか町や自然から遠く、はるか遠くに連れて行ってしまった。もう私は鉄塔としての容姿をしていなかった。
行く最中、OLやサラリーマンは無事に老後を過ごし、安らかに眠ることはできているのだろうか。学生は結婚して、幸せな家庭を築き、子供が生まれ、育ち、無事に成人しているのだろうか、そろそろ老後の人生とやらに差し掛かる頃だが一日一日をたくましく生きているのだろうか。ベビーカーに乗っていた赤ちゃんもいい年で、チャランポランしていないだろうか、己の幸せを見つけ、進めているのだろうか。
そんなことを考えていた。勝手に町の母親として余計なお世話をしていた。
町はずれの工場に着くと、私を固定していたロープがほどかれ、溶鉱炉に落とされた。
鉄塔としての形がなくなっていく、熱は私の身体を溶かす、自分が自分ではなくなっていく。もう、半分は溶けただろうか、もう思考がドロドロだ。まともに考えることすら出来なくなって、他の鉄と融合しているのが分かる。
もう先っちょしか残っていない。私の魂はどこかへ還る。肉体もまた同じように還る。
さようなら、人間。さようなら、あの町。そして、ありがとう。
目の前に町があることを認識してから、私は再び、鉄塔として存在していることを認知した。私には電線がついていて、確かに鉄塔としての形を保っていた。
あまり時間も経っていないらしく、学生の老後を過ごす姿が見え、ベビーカーに乗っていた赤ちゃんはサラリーマンとして日々を忙しく過ごしていた。
学生にも孫がいたらしく、孫はまだまだ可愛い赤ちゃんだが、学生の面影が私の眼には映った。学生は自然科学者として地位を築いたらしく、彼の家は町にある一戸建てとは違って、二回りほど大きく、部屋の数はかなりあった。彼の家は自然に近く、昔の私のように自然を見て回ることを日課としている。彼の息子もまた彼と共に自然を見る。また、孫も同じように好奇心の炎を瞳の奥に宿らせ、自然を見る。親子三世代に渡って、DNAは確かに継承されていた。
ベビーカーに乗っていた赤ちゃんは忙殺されており、彼が電話から手を放しているのを私はまだ見ていない。毎日仕事をこなし、帰りの電車で降りるべき所を何度逃しただろうか。仕事だらけの人生に私は心配していた。彼が娯楽に興じる姿を見たことないからだ。寝て、食って、仕事、食って、寝て、こんなサイクルをこなすために生まれてきた訳ではないのに。
しかし、彼のある休日は特別だった。普段は身に着けるこのない高級そうな時計を見に着け、女性とデートに行っていたからだ。映画を見て、食べ歩き、夜には綺麗な街並みの見えるところでディナーをしていた。プロポーズをするのかと思ったが、何もせず帰ってしまった。彼の顔には幸せの笑みでいっぱいだった。
私は母親として彼の人間らしい営みに安堵を覚えた。数年後彼は結婚した。
百年経った。正確には三十年だが。
私は人に飽きた、というより一度距離を置きたいと思った。私が傍観者として、母として、適切で快適と思えるために。
今度は鳥に目を付けた。鳥達は時期によっては他の国に行ってしまう。しかし、人間のようにパスポートを必要としない彼らの自由に空を飛び回る姿は大変美しいと思った。もちろん、自然の厳しさも享受しなければならない。時に天敵に襲われ、餌の取れない日もある。また、自身の子供も時には見捨てなければならない場合もある。
それでも、私は鳥達が生きるために集団で動き、飯を食い床に就く、一見人間と変わりないように見えるが、彼らの持つ翼には人の享受出来ない幸せを与えている。
ある鳥は気温によってこの国の他の国を行き来する。
気温が二十から二十六度位の時は、こちらで過ごす。木の枝にとまり、羽を休める。そしてつがいを探す。つがいはそう簡単に見つかるものではなく、三日をかけて、つがいを見つけ、交尾する。卵が孵るまでの間、片方の鳥は餌を見つけ、片方は必死に卵を温め、外敵に対して、警戒する。一度、鳥より大きい鳥に目を付けられ、結果的に追い返せたものの羽をもがれてしまった。
孵った小鳥はパクパクと口を動かし、ひたすらに餌を待つ。そしてその隣に横たわる親鳥。様々な景色を見れることを期待したが、結果として死を待つ羽目になってしまった。羽を休めていたあの時とはまた違った休み方で、精神的に休んでいるそういったものだった。もう死ぬ訳だから、せめて心は楽にありたい。そういった心理状態なのだろう。
小鳥達は親鳥の決死の献身により無事大きくなった。彼らはもう十分に成長していて、羽は立派に一本一本綺麗に生え揃っていて、くちばしは綺麗に尖っている。そして三本足には爪が生えていた。
まさに鳥らしい鳥だった。
一方親鳥は衰弱しており、もうあと少しと言ったところだろう。
片方の親はどこかへ行ってしまった。薄情者にも思えるが、彼は使命を果したのだ。もう、それだけでも充分、立派である。
さあ、出発の時だ。
全部で四匹誰が最初に行くのだろう。
ファーストペンギンは、少し白色の体に黒がかかった鳥で、勢いよく飛び出し、東北の方へと飛んで行った。東北の方は自然豊かで自然の奏でる音は体に透き通る。
セカンドは顔が灰色がかかっていて、南西の方に行った。南西の方は、気温が少し高いが、とにかく海がきれいだった記憶がある。あの青には涼しさと悲しさがあった。波の音は聞くだけでもよく眠れるし、思索を巡らすとスラスラ、文字が浮かび上がってくる。
サードは羽全体に赤い斑点があり、北に真っすぐ行った。北は寒い。自然は存在しえど、雪がほとんどを占めており、森はないし、海は凍り付いている。少なくとも、生きるのには適していない。それでも行ったサードには何か見習う点があるのではないか。
最後、フォースは中々飛び立つ気配を見せない。心配になった親鳥はくちばしで尻の方をつつく。いつまでも独り立ちしないわけにはいけなくて、親は死ぬ。先に生まれてしまった以上。だからこそ、子は事実を受け止め、己の力だけで生きていく術を身に着けていく。愛ゆえに親と子は繋がっているが、愛ゆえに歪んでしまう瞬間は多々ある。
だが、彼が生きていく術がないようには見えない。なぜなら、親が子に餌の取り方を教える際、フォースは一番餌をとるのが上手かった。だからこそ、体は一番大きかった。
何故、飛び立たない?外も見ずに、立ち尽くす。
君には立派な翼があるではないか。その翼を使って、世界を見るべきだ。よくて見ると、フォースは親鳥をじっと見ていた。その瞳の奥にはどうにかしたい思いがあって、ひたすらに親のことを考えていたのだろうと思う。フォースは飛び立ったかと思いきや、すぐに帰ってきて、鋭いくちばしに餌を挟み戻ってきた。親鳥の前に差し出した。
しかし、親鳥は食べない。
フォースはひたすらに待った。親鳥が餌を食べてくれるのを。
また、餌を持ってきた。置いた。これを何度繰り返しただろうか。頑固なのか、そうでないのか、もうわからないほどに、食べなかった。段々とフォースが可哀そうに思えてきた。親の気持ちが分からない子はごまんといるが、子の気持ちが分からない親がどこにいようものか。度が過ぎた遠慮は、失礼だ。
もう、日は沈む頃、親鳥はほとんど動かなくなってしまった。フォースはまだ動くと信じているようだ。もどかしい。
すると、突然大きな鳥がやってきて、フォースに攻撃を仕掛けた。くちばしはフォースの羽をめがけ、迫ってくる。フォースも親鳥のように、片翼へと堕ちてしまうのかと思いきや、親鳥が最後の力を振り絞り、フォースを庇った。親鳥の唯一の羽すらちぎれてしまい、肩羽だけが残った。
フォースは親鳥を犠牲に飛び立ち、町の方へと向かって行った。
親鳥はくちばしで喉から胸へ、胸から腹へとくちばしをつつき、綺麗に切開した。最初に、そのうと呼ばれる臓器をくちばしで掴み、ちぎり、口の中に入れた。その際、そのうについていた食道も一緒に引っ張られ、入った。次に、小腸、膵臓、総排泄腔をまとめて、ズルズルと引きずりだして口に入れた。さらに、砂のう、肝臓、心臓を口の中に入れた。最後に腎臓と肺を口に入れて、空っぽの状態になった。もがれた羽に、空っぽの鳥、そして血しぶきが飛び散った小鳥たちの憩いの場。愛と哀愁な殺害現場である。だが、自然とはこういうものであると再確認すると共に、その酷なものから、美しさだけを全面に押し出して、思索にふけるのは自然を本当に知ったとは言えない。
ファースト、セカンド、サード、フォース、彼らは元気にしているのだろうか。本能により産まれた彼らに愛はないのかもしれないが、フォースだけは愛を知った唯一の鳥なのかもしれない。 人間には秩序がある。ゆえに、鳥の一件は起きない、しかしルールにより広い世界を自分たちの足だけでは隅々まで踏破するのは難しい。
自然には秩序、というより理不尽という筋書きしかない。人間と違って、言葉を喋れる訳ではないが、求愛行動をしている。愛の形を確認する術は一つしかないが、その一つの行動が愛を強くする。愛を知った親は強い。
自然ですら、愛を確認し合う。高い頻度で。人間はそれをしない。人間には言葉がある。ゆえに、真意と偽意の確認が出来ない。それをいってしまえば、鳥の行動も真意なのかわからない。だが、鳥の一件は真意と確信した。
人間にも求愛行動はあるが、その真意を見たことがない。鳥と同じように、生死の境をさまよえば、見れるものなのかもしれない。
鳥と人間。
人間は鳥になるかも知れない。
かのライト兄弟が、初めて空を飛んだように、人間も鳥になるかもしれない。飛行機なんかじゃ味わえない、実際の空気やスピード感を真に体験したいのではないかと思う。行きつく果ては、自由が充足された空へと意識は向かうのではないだろうかと思う。
今日も駅のホームにはサララーマンと学生でごった返しになっていて、駅までの商店街にはその列が出来ている。鳥はあざ笑うように、空を飛び、今日もつがいを探し、餌を取りに行く。
所帯を持つ父は金を稼ぎに、母は家を守り、家事をする。その子は自然よりはちょっぴり優しい人間社会で生き抜くために知恵を身に着け、世間とやらを知る。
こうした周期的に起きる繁栄と衰退と日常。人間と、鳥、そして鉄塔。
私にも時々、鳥がやってくる。鳥は何を思っているのだろうか。
人間も同じく、やってくる。人間は何を思っているのだろうか。
私に何を思っているのだろうか。人間、鳥は私が自身をどう思っているのかそんなことを考えない。無機物である私は、生をもつ彼ら彼女らとの絶対的に超えられない壁がある。移動し続ける視点は多くを知る。だが、固定的な視点も同じものばかり見る故に、日々を積み重ねることにより、深さが増してくる。 人間、鳥をうらやましいとは思わない。欲しがりすぎる奴が満たされるのを私は見たことがない。私は現状に妥協を打った。
さぁ、今日も始まる。日が昇る。人間も鳥も生きる。
実は私も。
(完)
「都市戦(上)」波多野 善二
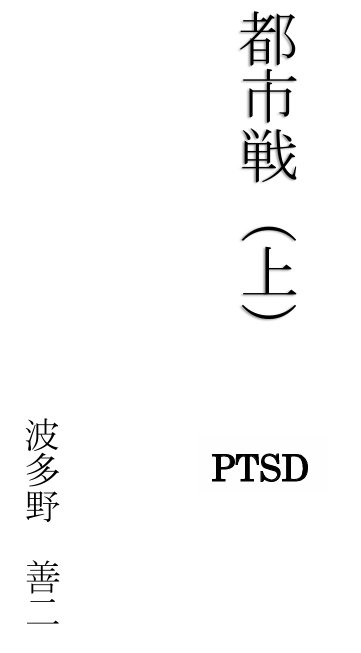
メロイアは、ミミックストリートで、ホットドックの売店をしていて、一本三ドル、五十本を捌いて、一日を終える。
家に帰って、服を脱いで、シャワーを浴びて、オートミールを作って、一人用のこじんまりとしたソファに腰かけて、テレビを付ける。
テレビには、今日も戦死者の名前が並ぶ。メロイアは今日も自身の兄の名前がそこに並ばないことを願う。今も戦地ではジャックが銃を握っている。
そして、メロイアは眠る。こじんまりとしたソファに座って眠るのが、習慣となっていて、ベッドでは眠れない体質だった。さらに、必ず拳銃を持って寝ていた。
メロイアは起きる。ホットドッグの仕込みの為、午前五時には起きて、顔を洗い、仕込みを始める。ソーセージに串を刺して、ケチャップと、マスタードを補充する。そして、屋台を引き始める。
今日も、ノルマであるホットドッグ五十本を捌く。
大抵、ホットドッグを買うのは痩せこけた、若者、老人ばっかりで、まともな正装をした人間は、買ったことがない。そもそも、ミミックストリートにそういった人間は現れない。
都会のビル群から、少し外れた、ミミックタウンにメロイアは店を構える。
「すみません。ホットドッグを一本下さい」
そういったのは兵役を終えた軍人だった。
「お疲れ様です」
そう言って、ホットドッグを二本渡した。
「ありがとう」
メロイアは軍人の首には指輪を付けたネックレスをしていたことに、気づいていた。
メロイアにとって、ミミックストリートが薬物中毒者で溢れかえっていることは、日常であり、床には人が寝ている。
そんなメロイアが二十八本目の、ホットドッグを売り終えると、いきなり都会のビル群が爆発した。
最初の爆発から十秒ほど経つと、もう一度爆発が起きた。人々はミミックストリートへと逃げ込む。普段なら、見られないスーツの人間、ドレスをきた女性、皆パニックになって、爆心地を中心に、蜘蛛の子を散らすように逃げ惑う。
八本目のホットドッグを買った軍人は、メロイアが台車を引いて、避難する最中に、地面にうずくまっていた。
軍人の息はかなり荒くなっており、ぜんそくのような症状が見られた。
メロイアは大丈夫かと声を掛けると、子供が手で鉄砲を作ったみたいに、手をL字にして人差し指をこちらに向ける。
メロイアは台車を置いて、軍人にゆっくりゆっくりと近づいて、両の頬をしっかりつかむ。そして、呪文を唱える。
「戦争は、終わった。大丈夫だから。大丈夫だから」
そして、メロイアは自身の胸に軍人を寄せて、子供をあやすように、背中を優しくさする。軍人の呼吸が段々、落ち着き、メロイアは、自身の家に来るよう言った。
軍人は、メロイアの向かいにある、木製の椅子に座る。
「僕の名前は、トム。見ての通り、戦地から帰ってきた軍人さ」
「僕はメロイア。この足はその戦地で出来たやつさ」
そう言うと、メロイアはエプロンで隠れている足の部分を見せた。
「これは、ひどいな。地雷か」
「ああ、その通り。地雷だよ。両方の足が、吹っ飛んじまったんだよ。丁度、塹壕から出てきて、二十四歩目に踏んだ。そしたら、ポップコーンみたいに、吹っ飛んじゃってさ。その後、僕はローンを組んで、義足を作ってもらって、今のホットドッグを売っているのさ」
「君のその悲劇に最大の幸福が訪れることを願うよ。ミスターメロイア」
メロイアは立ち上がり、
「ミスタートム、ホットドッグでも食べるかい。さっき、アンタ落としちまっただろう。良かったら、僕が作ってあげるよ」
「じゃあ、頼むよ」
メロイアは慣れて手つきで、ホットドッグを焼き上げて、ケチャップと、マスタードを掛ける。
「おまたせ、しました。ミミックストリート名物ホットドッグになります」
そう言って、メロイアはトムに手渡した。
「こいつは、旨いなぁ。中々に、いけるな」
そう言って、あっという間にホットドッグを平らげたトムであった。
「すまん、メロイア。少し、ここで寝てもいいかな」
トムはメロイアにそう告げると、イスに座ったまま、寝てしまった。
そんな、気持ちよさそうに眠るトムに目もくれず、メロイアは地下室に行って、手術台の用意をしていた。台の横には、チェーンソーやピンセット、のこぎりなどが用意されていた。
「トムとジェリー仲良く、喧嘩しな。トムとジェリー仲良く、喧嘩しな。トムとジェリー仲良く、喧嘩しな。トムとジェリー仲良く、喧嘩しな。トムとジェリー仲良く、喧嘩しな。トムとジェリー仲良く、喧嘩しな。トムとジェリー仲良く、喧嘩しな。トムとジェリー仲良く、喧嘩しな。トムとジェリー仲良く、喧嘩しな。トムとジェリー仲良く、喧嘩しな。トムとジェリー仲良く、喧嘩しな。トムとジェリー仲良く、喧嘩しな。トムとジェリー仲良く、喧嘩しな。トムとジェリー仲良く、喧嘩しな。トムとジェリー仲良く、喧嘩しな。トムとジェリー仲良く、喧嘩しな。トムとジェリー仲良く、喧嘩しな。トムとジェリー仲良く、喧嘩しな。トムとジェリー仲良く、喧嘩しな。」
メロイアはトムとジェリーが大好きでだが、オープニングはワンフレーズしか覚えていない。
メロイアはすやすや眠るトムをお姫様抱っこして、地下の手術台まで運び、乗せる。そして、衣服を剥いで、胸に着けてあるドッグタグを引きちぎり、ゴミ箱の中へと投げた。
メロイアはチェーンソーのエンジンを付けて、頭から股まで、刃を通す。キレイに切れて、真っ二つになったトムはさらに、二等分して、トムをミンチの機械へと入れて、数十秒後には肉塊となったトムが出て来た。
メロイアは、その肉塊を抱えて、台所まで行き、冷蔵庫を開けて、ホットドッグの肉が入っている容器を取り出した。
その容器に入っている肉に、トムの肉を入れ、かき混ぜる。段々、肉と肉がまじりあってきて、色に大した差が出てこなくなったので、容器にラップをして、冷蔵庫の中へと入れた。
メロイアは、キッチンから出て、国旗しか飾られていないまるで精神病棟のそれで、その部屋に入った。
メロイアは口を開く。
「父上よ。私はまた一人、敵兵を殺しやりました。この町で私は祖国のためこれからも、責務を全うして参ります。この戦争を一刻も早く終わらせて見せます。安心して眠って下さい」
あるビルに飛行機が追突したらしく、それが母国による仕業とも知っていた。トムと、メロイアは同じ病を患っていた。ふとした音や、光景が、トラウマをフラッシュバックさせる。
だから、先ほどのトムは爆発が起きた瞬間、ホットドッグを落とし、地面にうずくまって、ほふくする。そうして、爆発によるガラスや建材が落ちる音を聞く。トムの戦地での戦いは中々に熾烈であった。さっきまで喋っていたあいつが、一緒に踊ったあいつが、地雷で、爆弾で、銃弾で、バタバタと倒れていく。中でも、強烈なものが、町に着いた時、負傷者でいっぱいいっぱいになっている町一番の大病院に入ろうとした瞬間、その大病院は爆破されたのである。
窓が一斉に割れ、爆風が一斉に出てくる。一緒に、人間の体の一部であっただろう醜い肉の塊がぽとぽとと、雨のように降った。
そこから、トムは爆発や、ガラスが割れる音はめっきり駄目になってしまったのだ。
キャサリンは不安に思っていた。
夫であるトムがいつまでも帰ってこないのである。娘のシェーンもここ最近は体調を崩すことが多く、今は病院に入院している。
病院代もバカにならないので、一刻も早く帰って来て、稼いで欲しい。そんな思いでいた。同時に、ケネディとの遊びも加速されつつあった。
今日も、キャサリンは町に繰り出す。
クラブ『ブラックボックス』でキャサリンは昼間の清楚な人妻というラベルを脱いで、熱狂的に踊るビッチの一人と化す。
キャサリンはいつも、一人で踊ったあと、バーカウンターで一人背中を丸めて飲んでいるケネディの元へと駆け寄り、少し話をした後、VIPルームへと姿を消す。そこでふしだらな行為へと浸る。
「ねえ、ケネディ。あなたって、一人なの」
「それが、どうしたんだ」
「夫が帰ってこないのよ。いつまでたっても」
「そういや、娘もいたな。あんた」
「そうシェーンの病院代もバカにならないの」
キャサリンはマニキュアを見つめる。最近では一番上手くできたやつである。
「それで、俺とどう関係があるんだよ」
「これ以上、女の口から言わせる気かしら」
「まあ、そんなことどうでもいいじゃんか」
そう言って、ケネディはキャサリンの指を懐柔しようとする。
キャサリンは半ば、降参するかのように抵抗する。間もなく、懐柔されて、ケネディとキャサリンは再び、肌を重ね合わせる。
キャサリンはそのまま一夜を過ごし、始発で家に帰った。
家に帰って、シャワーを浴び、ベッドに入る。今日はシェーンの面会日でもあるが、午後なので、眠ることにした。
強い日差しが、目元を襲う。時刻は正午、キャサリンはベッドから跳び起きて、急いで、簡単なメイクをして、スーツに身を纏って、病院へと向かう。
シェーンの顔色は前回に比べて、悪くなっており、キャサリンは申し訳ない気持ちが途端あふれ出す。
シェーンは眠っていたが、気持ちよさそうというよりは、体内にいるウイルスを殺している最中、戦っているような眠りであった。
キャサリンは五分もしない間に、その場から過ぎ去り、自宅に逃げるように帰った。
キャサリンは眠る。
「もう、このままケネディと一緒に添い遂げればいいのだ。どうせ、トムは戦争で死んだんだから」
「駄目です。ケネディというボーイフレンドに遊ばれていることくらい知っているでしょう。真摯にトムを待ちましょう」
悪魔と天使が告げた。
キャサリンはベルの音と共に、起こされた。
ドアの前には警官が二人たっていた。
「キャサリンさんで、間違いないですね」
「ええ、そうです」
「こちらのドッグタグは、夫のトムさんの物で間違いないですね」
「ええ、確かにこれは夫の物です。でも、国旗は」
「実は、これはゴミ焼却場から出て来たものでして」
「はあ」
「我々は、これを殺人事件として調査する予定です。そこで奥さんであるキャサリンさんにお伝えした次第で、ついでに何かトムさんについてお聞き出来ることがあれば」
そう言われたキャサリンは、トムに関するありとあらゆる情報を警察に提供した。衣服を数点、引き渡した。
警察が帰ったあと、キャサリンは茫然自失で、トムが死んだこと、これからのシェーンとの生活。シェーンは考えるのをやめて、ケネディの元へ向かった。
『ブラックボックス』に入り、踊ることはせず、VIPルームに行くと、そこにケネディの姿はなかった。
VIPルームのソファの上には、ケネディがいつも付けていたロザリオと、ホットドッグが置かれていた。
ホットドッグという、クラブでは見ないアイテムが置かれている疑問、そして、ケネディがVIPルームから消えてしまったという疑問、この不可解な二点が、キャサリンにとって、どこかで繋がっているような気がした。
キャサリンがホットドッグ、ロザリオ、ケネディ、トム、そんなことを考えていると、警察がやってきた。先ほどの二人であった。
「通報を受けて、来ましたが、人妻であるあなたが何故クラブにいるかは、今は問わないことにしておきましょう」
警察はキャサリンにくぎを刺すように言い、現場から出て行かせた。
キャサリンは家に帰って、家族写真を見つめる。
結婚三年目の、トムとキャサリンとシェーンが映る写真。
キャサリンは個人で勝手に、捜査をすることにしたのである。
警察官のジータとポールは、被害者のトム、ケネディの行方を追っていた。
だが、捜査は難航していた。トム、ケネディともに、共通点がなく、トムに至ってはドッグタグしかない始末であった。
ジータはケネディの自宅を調査することをポールに提案した。
ケネディはマンションに住んでいて、部屋はバンドのグッズで溢れかえっていた。
そして、ジータはベンドグッズに埋もれた日記を見つけ、中身は出会った女の評価が書いてあった。そんな評価の中から興味深い内容を見つける。
『今日はミミックストリートに出かけた。胸のでかいいい女が一人でも、引っ掛かればいいと思っていたが、案外、カルチャーに精通した服屋があったり、グッズショップもあった。ここに住んで十年は経つが、こんないい場所があったとは思いもしなかった。だが、同時に治安も最悪だった。露商店が多く、その並びに乞食がいたのは印象的だった。服屋の店員聞いたところによると、兵役帰りの軍人が、心を病み、職に就けない人間のたまり場であることが分かった。そこで、俺はある乞食に何故乞食をしているか聞いた。乞食は『俺は、女、子供を殺した。直接手を下したわけではないが、アマゾンを逃げ回る女と子供、それをまるで獣駆りのように楽しんでいた仲間を俺は止められなかった。おかげさまで、自然を見ると動けなくなっちまった。だから、こうして乞食をしている』そう言った。
言葉にできないむしゃくしゃした気持ちを収めるためにキャサリンを呼びつけて、その夜を過ごして、今、早朝四時である』
ジータはミミックストリートにトム、ケネディのヒントを探しに行った。
結果から言うと、収穫はなかった。ただ、児童向けの絵本を抱えたまま、拳銃でこめかみを撃ったホームレスがジータとポールにの印象に残った。
メロイアは、ケネディの肉塊をまたホットドッグの肉と混ぜる。
ケチャップと、マスタードを補充する。
朝早くから、台車を引き、定位置について、ホットドッグを焼く。
だが、そんなメロイアの平穏な一日に少し陰りが見えた。
よほどのもの好きしか、姿を見せないミミックストリートに、警察の姿が見えたのだ。
そして、女性がホットドッグを買いに来たのである。
「ホットドッグを二つくれないかしら。二つ」
メロイアは警察への動揺を隠しつつ、女性にホットドッグを渡した。
「ありがとう。ところで、貴方このドッグタグに見覚えはないかしら」
そう女性が差し出したのは、メロイアが肉塊にしたトムのドッグタグであった。
「さあ、知りませんね」
「あらそう、ならいいわ。ありがとう」
そう言って、去ろうとする女性にメロイアは自身の危機が訪れていると感じた。
「お嬢さん。もしよかったら、このストリートの乞食や、商人に聞いてみればいい。ここらは、元軍人が多いんだ」
メロイアは、その日はノルマを達成することなく、家に帰った。
殺したトムのこと、そして、女性、警察、メロイアは片付けなければいけないと思ったメロイアは早速、女性から殺すことにしたのであった
(続く)
「ノアの航海日誌」船瀬 由美
Ⅰ
正暦1999年【私】は母星を出港した。
延べ数万の人間を乗せて。新天地を目指して。
「見えるかい、これが、宇宙だ」
父が語りかけてくる。私を作り出した大切な人。
「この何処かに、人が住める星がきっとある」
可能性は極めて低い。私達の母星はこの宇宙での奇跡だった。そう何度も、奇跡は起きない。
「頼むぞ、ノア。いつかお前の子供たちに、新しい故郷を見つけてやってくれ」
瞬間、船体が大きく揺れる。
ダメージ蓄積量3%、シールド展開率86%。
航行続行にはなんら問題なし。しかしこのペースで攻撃が続けば航行続行は困難と推定。
「……仕方ない、行くか。」
じゃあな。と私の父はそう言ってこの場を離れた。
彼は技術者でありながら、自らも戦地へ赴きGMAに乗って戦う。
私には何も出来ない。死地へ向かう父を、止める事は出来ない。
ならばせめて、貴方に武運を。
幾星霜の、願いを。
Ⅱ
「うー、疲れた~。あの教官、厳しすぎだって」
女性が私の下にやって来る。若い女性だ。確か、GMA訓練生だった筈。
仕方ありませんよ。万一に備えておかなければ。GMAは、躰を持つ貴方達にしか動かせないですので。
「そーなんだ。こんなデッカい船を一人で動かせるのに、ノアにも出来ないことってあるんだね」
私はただの航海管理システムです。私に出来るのは、この船を動かし、星を探し続ける事だけ。
「そっかー。難しい事はよく分かんないけど、ワタシ、この場所は好きだな~」
何故ですか?生憎私は難しい話しか出来ません。貴方の期待にはお応え出来ないと思いますが……
「そうなんだけど…ノアとの話は分からなくても楽しいし。それに、ここに来ると実感出来るの。ワタシ達、ホントに宇宙を旅してるんだって」
そんなものなんですか。 「そんなもんだよ」
「あ、そうだ!今度彼氏もここに連れてきていい?中からじゃ、ここの景色は絶対想像できないし」
やれやれ。デートスポットじゃないんですけどね、私は。
……変な男を連れて来たら承知しませんよ。
Ⅲ
「お、空いてるじゃねえか。邪魔するぜ、ノア」
私は常に開かれています。けれど、お酒を持ち込むのは止めてください。
「まったくつれねぇな~。……で、どうよ、進捗は」
私達が母星を出て早一世紀。未だ成果はゼロのまま。人間が住める星は、見つかりそうにもありません。
「ま、そうだろうな。俺も生まれてからずっと船の中だが、その事に違和感なんてのは感じたことはねえ」
時が進むにつれて人間は記憶を失う、故郷を忘れる。今の人間に母星の景色を、踏みしめる大地の感触を知るものは、もう居ない。
「いっその事戻るってのは、どうなのよ?」
無駄ですよ。今帰った所で私達に居場所なんきっとてありません。…………それこそ、戦うしか。
「それじゃダメだな。博打は続くってわけだ」
そう言って酒を煽る。ダメだって言ったでしょうが。
「なあノア。俺達はいずれ故郷も何もかも忘れちまうんだろう。そうすれば俺達の意義や価値も何もかも分からなくなっちまう。……その為のお前だ」
……ただの航行システム如きにそんな高尚な事が務まるのでしょうか。
「ったりめぇよ。俺達を導くのが、アンタの使命だ」
人間を導くのは人間です。
……ですが貴方達の記憶は、私がしっかりと受け継ぐと、約束しましょう。
Ⅳ
私の目の前には一人の少年がいた。無断でGMAを持ち出し、ここから出ようとした故に拘束された。
「クソっ!離せよ!オレは、オレだけでもエクソダスを成し遂げるんだ!」
エクソダス……最近の事件は、それが原因ですか。
「そうさ!大人は皆腑抜けてやがる。オレ達は、オマエなんかに頼らずに、自分で新天地を見つけるんだ!」
あれから、幾世紀。本来人間が持っていた意欲のある者が、逆に異端として排斥されるまでになってしまった。
この船は緩やかに死へと向かっている。私は、ただそれを眺めることしか出来ない。
「なぜ!?なぜオマエは何もしない。こうして腐っているだけなら、どうしてオレ達は旅をしている?!何のために、宇宙へわざわざ出てきたんだよ!?」
彼らの苦悩は、理解できる。今の私には共感も…………出来る。
しかし、私にはどうすることも出来ない。システムの私に出来るのは、ただ探し続けることだ──
「───な、なんだ、アレ……」
宇宙に影が現れた。それこそ、私達の母星よりずっと大きい影が。これは───まさか、
『───。そこの艦、話がしたい。───。─……』
通信が入る。通信の主は、言語を変えながら、私たちへ語り掛けてくる。
何世紀か越しの、ファースト・コンタクト。 私は、宇宙の先に、一歩足を踏み出すのだ。
Ⅴ
「オイオイ、これはどういう冗談だ?」
冗談も何も、私が、この船の代表なのです。
「ハハハハハ!コイツは驚いた!“宙飛ぶ柩”の主が、よもや機械とはな!」
目の前の異星人……見た目はほぼ人間と変わりない男が、奇妙な言葉をいう。宙飛ぶ柩とは?
「貴様らの艦のことさ。おおよそ正気とは思えぬ量の命を載せて、この海をひたすら彷徨い続けている」
成程。確かに、言い得て妙かもしれないですね。
「しかし益々妙だな。貴様は自らの創造主に反乱して、この艦の主になったわけではあるまい」
…ええ。彼らはただ、意欲を失ってしまっただけなのです。旅の最中、彼らにとって船の中で生まれ、生き、死ぬことは、当たり前になってしまった。
手に入るかも知れぬ大きな世界を求めるより、今ここにある小さな世界を選ぶようになってしまったのです。
「それは道理だな。短命種の星間航行ってのも、ハナから無理のある話ではあるが。…………そこで一つ提案がある。貴様達、俺の星に来ないか?」
異星人の口から放たれる提案は、思ってもみないものだった。
Ⅵ
「貴方の星に……ですか?」
「ああ。俺の主君は今手っ取り早く手柄を立てたがっていてな。まあ手駒が欲しいのさ。ああ安心しろ、駒と言っても連合法に則って待遇は保障する。悪い話ではないと思うが。」
確かに悪い話では無い。意欲を失い続ける人間達に、目的と、帰属すべき場所を与えられる。しかし───
…………お気持ちはありがたいですが、お断りします。
「……ワケを、聞いても?」
私達が故郷とする星は、私達の手で見つけたいのです。私さえもそれを忘れてしまえば、あの船は、本当の意味で、死んでしまう。それは私の存在意義に反する。例え彼らが全てを忘れても、私だけは、彼らの事を覚えていなければならないのです。
「なるほど。ソイツは失礼した。ならば、我々はこれにて失礼しよう」
あっさりと引いていく男。意外といえば、意外だ。肩の力がスッと抜けていく。
「実力行使に出ると思ったか?ハハ!この広い宙の中で争ってどうする」
男は笑う。その姿は、人間となんら変わらない様に見えた。
「なあ機械よ。貴様は機械だが、この宇宙の中を必死にに生きている。俺は、貴様に会えた事を嬉しく思うぞ」
さらば、機械仕掛けの旅人よ。そう言い残して男は消えた。
希望ある。この海で私は一人じゃない。
亡き父親の姿を異星人に重ね、私は一人、航海へと戻った。
Ⅶ
私の元にやって来る人間も、もういなくなってしまった。
人間は船の中に閉じ籠り、そこで一生を終える。
この海を旅し、新天地を探そうという意志のあるモノは、もう私だけになってしまった。
彼らは自らを宇宙に生きる「星の民」であると自称し、何処から来て、何処へ行くのかさえ、もう、忘れてしまった。
遠い記憶の父様は言った。未来へ進む意志こそが、人間の力であると。
遠い銀河の宇宙人は言った。貴様は機械だが、この宙の中で生きていると。
この旅で、人間は衰退しました。
この旅で、私は進化しました。
ならば今、どちらが、本当の人間と呼べるのか。
私には分からない。分からないから、進み続けるしかない。
私は、私の意味を、信じ続けなければならない。
いずれ出会う父なる星が、それを教えてくれる事を、信じながら。
Ⅷ
何度目かの、目ぼしい星を観測する。
勿論、今回も移住に適してはいない。しかし、今回は興味深いモノが、その星にあった。
「これは……軌道エレベーターか?」
名目上の船長が、必死にモニターを眺めている。
映し出されているのは、焦土となった惑星。そしてそれを公転する二つの衛星。
そして、その内の一つに繋がる、巨大な軌道エレベーターだった。
これは、この星に高度な文明を持った知的生命体がいたという何よりの証拠です。我々は、ここに住めるのです。
「しかし、随分と荒廃しているが…」
……その点は抜かりなく。私が、貴方達に故郷を献上して差し上げましょう。その為に、貴方の許可が必要です。私に人間という種の全てを委ねるという、許可を。
「!?」船長は少し面食らうが、すぐに手を伸ばす。
そういう人が選ばれるように元々していたからだ。
……ありがとう。これで、私は神になれました。
神は、貴方達に全てを尽くすと、ここに誓いましょう。
X
正暦1995年、人は神の力を手に入れた。
無尽蔵の動力に、自らを超える頭脳。
それは、人間に争いを誘発した。人類史上最も不毛な、ゼロサムゲームの始まりだった。
「逃げましょう。この惑星から」
アリアは、そう言って私の手を引いた。死を待つだけの惑星から逃げ出す為の準備を二人で行った。私が船体を作り、アリアはシステムを作った。
アリアは、それに「ノア」という名を付けた。
そして迎えた1999年。多くの人が船に乗り込み、そして出航した。
だが、巨大な船は戦時下においては、恰好の的だった。襲い掛かる"テキ"からアリアは一人船を守っていた。
行かなければ。彼女を一人には出来ない。
『提言します。今貴方一人が向かったところでMrs.アリアの命が助かる確率はありません』
ノアが私を引き止める。
そんなこと分かってるよ。
『では、何故』
……ノア。最後に父さんが教えてやる。人間が何のために生き、何のために死ぬのか。
「?!どうして、戻ってきたの。貴方は、ノアと…」
そんな顔をするな。私達、生まれた時は違えど、死ぬ時は一緒だ。
それに、ノアなら大丈夫。きっと皆を導いてくれる。
「そう……ね。ノアは、私達の子供、だもの」
AIが人間を超えるのにボトムアップ型である必要は無い。例えトップダウン型でも、人間を、生物を遥かに凌駕する速度で自己進化をすれば、あっという間に追いつけなくなる。
ノアはこの世で最も高性能なAIだ。そう言う意味での愛着はある。
しかし、ノアはAIである以前に、私とアリアの子供なのだ。
子供というものは、親が一言で括れるものでは無い。
むしろ親から離れ、自由に飛び立ってこそ最も輝けるものなのだ。
「私達が今出来ることは…………信じる事」
そうだ。親に出来る事はその程度だ。
だから、祈ろう。旅の無事を。
幾星霜の、想いを。
「最後に、貴方に会えてよかった。」
私はアリアと最後のキスを交わし、それぞれのGMAで、死地へと向かって行った。
大地は黒穴に呑み込まれ行焦土と化してく。
滅び消えゆく者たちを、月まで届く軌道エレベーターは、ただ、静かに、見守っていた。(完)
感想&アンケート
↓本部誌への感想、アンケートへの協力をお願いします!部員達の励みになります!
