
生きていく大変さ、悩ましさ、ちゃんと見えるところに置いておこう -社福設立前に話したかったこと-
地域に溶け込み、開かれ、誰でも居られる“ごちゃまぜの場”を創ろう。そのために、社会福祉法人の設立を行なっていきたい。
2023年度のビジョン共有会で、代表の不破からスタッフにそんな方針が語られました。
法人設立10周年(2022年)の事業部マネージャー・リーダーが集まる経営会議では、「5年後、私たちは何をしていたい?」という対話がありました。そこで、制度や枠といった“利用資格”を越え、暮らしに溶け込むような「ごちゃまぜの複合施設」という言葉、考えがメンバーからも出されました。

私たちの拠点やサービスを利用したい人の数に対し、支援者の数は常に不足しています。そんな社会で、「支援する人・される人」という関係性には限界がないか?そもそも、この立場は状況によって変わるし、固定されたものでもないはず。そんな違和感が、ここ数年で強く渦巻いたのです。
もっともっと、まちそのものから育まれる暮らしやすさ、居心地のよさを見つめてみよう。
そんな旅を始める手段として、社会福祉法人の設立に向け歩き出しました。
一度始めたらその前には戻れない、今考えていることを残しておきたい!と、NPO代表の不破と社会福祉法人準備室室長の綾部が対談しました。
私たちの社会福祉法人設立とはなんなのか?今の思いや大事にしたいスタンスについて語り合います。
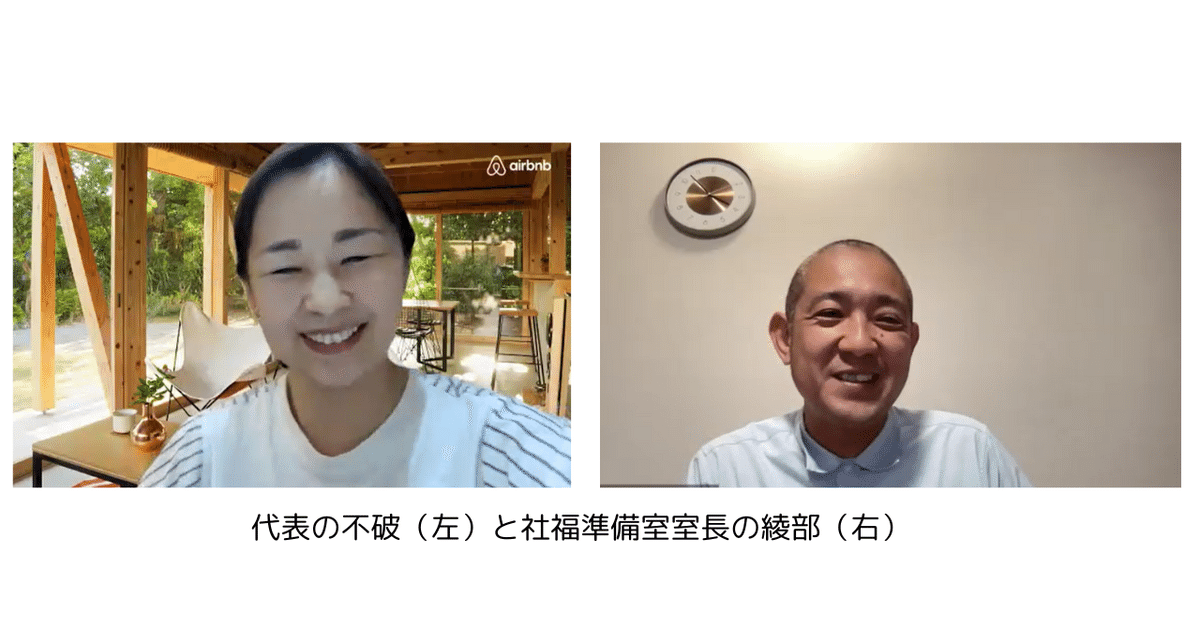
“在る”ことで生まれる安心感がある
不破 実は、社会福祉法人(以下、社福)の設立自体は2018年頃からずっと考えてきたことで。NPO法人ではできない事業があるし、地域の中で必要とされ、より長期的に残していくものを創るなら、制度的な観点からも社福がある方がいいし必要だと思っていました。
コロナの影響もあって一度それどころではない状況が生まれたけど、ここ数年で、今なら一歩踏み出せるかも、と思えた。昨年、綾部さんも学習支援のマネージャーを他のメンバーに任せることができて、本格的に動き出せたよね。

綾部 そうでしたね。社福の設立って、ただ単に新たな法人格を作るという話ではないですよね。社福化の背景について、不破さんが浅草寺に感動した話をしてくれたことがありました。あのお話、僕もすごくわかる気がしたんです。
不破 あ、そうそう、浅草寺の話。
移住先の沖縄で歴史的に大規模な台風が上陸して、身の周りのものが一瞬で壊される風景を目の当たりにし悲しく不安定な気持ちになっていた2023年の夏、帰省で浅草寺を訪れる機会があって。
「どんなことが起きようとも、浅草寺はこの場所に1000年以上ずっと変わらずにあったんだ」そう思ったら、なんだか涙が出てきて、“存在”に救われるってこういうことなんだ、と思ったんだよね。
綾部 ダイバーシティ工房(以下、工房)が今までやってきたことは、困りごとがある子どもやご家庭に対する支援、相手に何かをする“Doing”の部分が大きかったですよね。これからは、在る、つまり存在の“Being”になっていくことが社福化をする意味だと、僕も思っています。
不破 今すぐ使うわけではなくても、「ここいいな」と思える場所が身近にあるのを知っているだけで安心することって、あると思うんだよね。
私自身、助産院とか子どもが使う場所とか、「辛くなったらここ行こう」「あの人に相談しよう」って思える場が、4年前に沖縄に移住してから色々あった。それってすごく大事。
綾部 近年、スタジオplus+を卒業していった子たちが、高校卒業や社会人になるタイミングで、実はあまり食事がとれていないとか、生活のこんなところに困っているとか、ふと相談に来てくれたりすることがあるんです。
専門性としては学習支援の拠点なんだけど、「困ったな」というときに、思い出してくれたんだなと思いました。

実際に高校生のある保護者の方が、「スタジオplus+に通わなくなってからも、『もし困っても、この場所がある』と思えるだけで安心できました」と言ってくださったことがあって。長く続く事業をする意味って、そうやって存在自体が誰かの安心感に繋がることなんだと思いました。
悩んでもがいて生きづらい、それで大丈夫
綾部 社福設立に向けて、他団体の活動を見させてもらったり、事務的な書類の準備を進めたり、建物に関する契約や購入の現場に立ちあったりしています。
その中で、きれいな部分だけではなく、大変なことは大変だと見せていくことが大事ではないかと思ったんです。僕たちの社福設立とは、色々な人が利用できる大きな建物を作って終わりではなく、その内外で人々が混ざり合う「場づくり」をしていくことです。そこには当然、大変さや苦労も伴いますよね。

不破 私もそれは、すごく思う。きれいごとばかりじゃないから。
でもその、悩んでいる、もがいている、っていう状態でこそ大丈夫っていうマインドでいたい。
今までも複数の生活支援施設を開設して、常に周囲から歓迎されるわけではなくて、場所によっては反対されることもあった。現場で直面するスタッフって本当に大変だし、かなり苦しい思いをする。
すごく大変ではあるんだけど、でも、そんな簡単に受け入れてもらえるものではないという体感を経て、その上で改めて、人の生きづらさを包括していける場所って何が魅力的なのか、とか、暮らしやすさや居心地のよさってなんなのか、というのを探求したいと思ったんだよね。
「素敵な仲間と素敵な場を創りました!」だけは、私はおもしろくないなと思っていて。人ってやっぱりそれぞれ苦労があって、生きづらくてしかたない。
私たちがやる場づくりには、生きづらい人や葛藤が含まれていないといけないと思う。私自身、人間臭さや苦労が見えにくくされている場所を訪れても、自分の団体に持ち帰りたいと思うような体験や物語はないと感じてしまうんだよね。
綾部 きれいでいい感じの場所を作りたいというだけで、その地域で暮らす子ども、お年寄り、障害のある人もみんな混ざっていられる場所になっていないなら、「そこの主人公は誰なの?」と思っちゃいます。
それからやっぱり、地域に根付いていることも大事にしたいです。建物をポンと作っちゃったというようなものではなく、ちゃんと地下から湧き出ている温泉みたいな場所がいい。

人の“変なところ”を笑える自分か?
不破 そうやって、きれいなことだけじゃない大変さも伴うことを、色んな人と関わりながらやっていくとき、私は“自分の度量を広げていく”ことが大事なんじゃないかと、最近すごく思っているんだよね。
例えば仕事相手や同僚とか、日常的に関わる人に対して、あの人ちょっと変わってるな、この人自分に合わないな、って思ったりすることは誰でもあると思う。
それでも関わることなしにはやっていけないとき、ユーモアをもって相手をみれるか。
「変な人だな」と思っていた相手の中に、その人らしさやおもしろさを見つけて、人を許せる自分になれたりすることってあると思うの。
そんな意味での度量って、現場で働く私たちには特に大事なんじゃないかな。自分からは変だな、嫌だな、怖いな、とかに見える相手の行動の中に、実はその人が生きる上で大事にしている何かが隠れていることもあるかもしれないよね。
綾部 その場にいる誰もが変わらないから、全員ずっと苦しいみたいな状況ってあると思います。相手が変わらないことに腹が立っているとき、全部を受け入れたり許したりできなくても、「あの人ってそういうところあるよね」って少し思えるだけで気持ちが楽になること、確かにあると思います。
不破 今、工房で所有している沖縄の古民家を使って民泊をやっているんだけど、そこでこの夏ちょっとハプニングがあって…。
外部でお願いしている清掃の時間がいつもよりかなり長めにかかってて、連絡もすぐにつかない状況で、どうしたんだろう?と思ったら、「洗濯・乾燥を待っている間、うっかり寝落ちしてしまいました。申し訳ありません…」って連絡が来て。実はそのお掃除の人、清掃先である宿に一泊寝て泊まっていたの。
人によっては「仕事なのにあり得ない!」って怒る人もいると思う。でも私は、乾燥待ってたら眠くなっちゃったんだ(笑)何度もお掃除に来てて泊まりたくなっちゃったのかな、っておもしろくなっちゃったんだよね。

綾部 僕は、ちょっと怒っちゃうかもしれないですね(笑)。
不破 そうかそうか(笑)。私も昔は怒ってたと思う。でも、この自分の反応を見て、昔に比べてイライラしなくなったなと思った。
人が、ある面から見れば“失敗”や“間違い”にあたるようなことをしてしまったとき、それを笑えるかどうかって、自分自身が健康でいられることにも関係していると思うんだよね。
もちろん許せるかどうかはその程度にもよるし、本当に危険な人に対しては危機感を持って対応する必要がある。それは前提としつつ、日々の暮らしの中で起きることの大半って、弁護士や警察が登場する問題ではなく自分が相手とどう折り合いをつけ、対処するかという話だったりする。自分の捉え方が変われば見える世界も変わる、という気持ちは持っていたいと思うんだよね。
綾部 そうですね。
不破 少し話は変わるけど、組織運営の視点からも、スキルチェックとか制度って、こうなるといいなっていう希望や、相手の成長を願う気持がないと機能しないんだって長年やって気がついたんだ。
こうしましょう、っていうルールがあるだけでは意味がない。例えば相手がそれに沿わないとき、なんでその人は違うことをするのか?そしてなぜ自分はこんなに許せないのか?を探求して、お互いが少しずつ変わって、相手の成長や幸せを願えないと、よい関係性にはならないと思う。
綾部 工房の事業がよい状態のときって、やっぱりスタッフ同士の関係性も良いときですよね。
僕自身は最近、人とよい関係性を築くうえでも、自己覚知していくことを大事にしたいなと思っています。これいいな、好きだな、苦手だな、なんか違うな、という感覚に意識的になるということです。
今までであれば、最終的にはそれがどんな支援を提供する場を創りたいかに影響してきたし、今後はより広く、工房がどんな場を創り、どんな存在でありたいかに繋がってくるのかなと思います。
不破 私はやっぱり愛とユーモアをもって人や物事に接して、「おもしろい」と感じられる自分の器を広げていきたい。
ごちゃまぜの場の実現って、自分がどれだけそこにおもしろさを感じられるか、だと思うから。
いいなと思ったら応援しよう!

