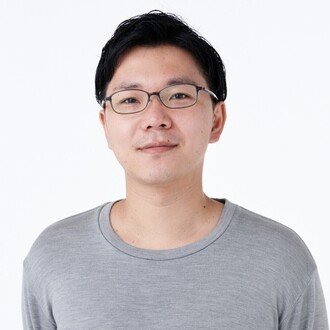企業が知るべきスポーツの3つの価値
はじめに -スポーツ産業の伸びしろ-
ビジネスパーソンは、ビジネス拡大のため、もっとスポーツの価値を知っていたほうがお得、そして活用すべき、という話です。
「クラブ売上1兆円?スポーツ市場規模まとめ」で書いたように、日本のスポーツ市場は世界的にみてまだまだ小さく、「伸び代」があります。
そして、この「伸び代」は、日本企業のスポーツに対する理解度の低さ(というか関心の低さ)によって生まれています。
企業がスポーツの価値を知らないと、当然スポーツに投資されるお金・人が限られます。これが日本のスポーツ市場に「伸び代」がある大きな理由の一つです。
もちろん、理解度が低い(関心が低い)という現状は企業だけの責任ではなく、仕方のない日本独特の背景があります。
①「スポーツ」が「体育」と誤訳されたことで、エンターテイメントやビジネスというより、教育の一環という印象が強くなった
②ビジネス部門ではなく広報部やCSR部が主体となってスポーツを扱っている企業が多く、情報が隔離されている
③海外資本規制やスタジアム・アリーナ管理規制等により多様な資金調達手段が発展せず、「スポーツは優良企業が赤字で支えるもの」というイメージが根付いた etc...
しかし、日本企業がスポーツの価値を知り、ビジネス拡大のために活用するようになれば、スポーツ市場の「伸び代」が一気に埋まっていきます。
そこで、企業が知るべきスポーツの3つの価値をまとめてみました。この価値に気づいている企業は、「ビジネスとして」腰を据えてスポーツと向き合っています。
※既に取り組まれている方々にとっては当たり前すぎる話だと思いますが、大企業内で仕事をしながらスポーツへの関わり方を模索している僕のようなビジネスパーソンには意外にもほとんど浸透していない考え方だと思います。
スポーツの価値① リアルタイム
一つ目の価値はそのリアルタイム性です。
エンターテイメントとしての価値
まずエンターテイメントとしていかにリアルタイムであることの価値が高いかに触れてい行きます。
今の時代、ほとんどの商品・サービスはすぐ真似され、コモディティ化してしまいます。映画や音楽などのエンターテイメントは、Netflix・Appleによってコモディティ化され、定額で楽しめるようになりました。
しかし、リアルタイムのドラマを楽しむスポーツは絶対にコモディティ化しません。スポーツが、ある日ある場所で1度きりのドラマを提供するエンターテインメントである以上、その有限性・希少性が陰ることはなく、コモディティ化していく商品・サービスと比して、相対的にコンテンツとしての価値が高まっていくでしょう。
NFLの入場料が過去最高水準になっていることが分かり易い例です。2.5時間の観戦体験が平均70万円、最も高い座席に至っては700万円。
当然ながら、NFLは広告価値も非常に高くなります。2019年は、30秒のCM枠に5.5億円の値段がつきました。
これは、市場世界最高額のCMと言われています。同じ時間に1億人以上が観る、というコンテンツのリアルタイム性が影響してこのような価格になっているのでしょう。
また、あのFacebookが今年になって初めてスーパーボールへの広告出稿をしたことも話題となりました。スキャンダルを乗り越えるための信用力回復、かつ新機能を世の中に広げるために、これほど魅力的な媒体はないのでしょう。
新技術の実験場としての価値
また、スポーツのリアルタイムという特性に着目し、新技術の実験場として活用している企業も多くあります。最も有名な例はドイツのIT企業SAPでしょう。
SAPは、2013年頃に「高速データ解析」を売りとした「SAP HANA」という新しいソリューションを立ち上げていました。その際に、サッカードイツ代表のスポンサーとなり、試合や選手の分析にソリューションを導入してもらいました。結果としてサッカードイツ代表は2014年のW杯王者となり、SAPはスポーツというリアルタイムな分析が求められる領域でソリューションの素晴らしさを証明することに成功しました。
SAPのイノベーション担当役員は下記のように語っています。
当時の『SAP HANA』の位置付けとしては、“超高速”のデータ処理を特徴とする新型データベースでした。この“超高速”という価値を、どのようにして世の中に訴求していくか。そこで、スポーツの持つ“リアルタイム性”との親和性が高いと考えたのです。
この取り組みを通じ、SAPはERPパッケージが9割を占めていた状態から、SAP HANAがもう一つの収益事業となり、時価総額は約5年で3倍の17兆円となりました。
日本でも、ソフトバンクやソニーなどの大企業がスポーツを活用して5Gの実証実験を行うなど、スポーツのリアルタイム性を持って新技術のテストを行う企業は増えています。
「スポーツの価値① リアルタイム」のまとめ
このように、スポーツがリアルタイムであることで、そのコンテンツの価値が高まるだけでなく、リアルタイム性が求められる新技術の実証実験の場としても活用されています。
スポーツの価値② グローバル
二つ目は、スポーツがグローバルコンテンツであるという価値です。
世界中から観られている価値
スポーツは、そのルールさえ覚えてしまえば、国籍が関係なく楽しめるエンターテインメントです。また、絵画や建築物などのアートと同じように、スポーツを楽しむためには必ずしも言語を必要としません。
翻訳が必要なく、世界中の誰もが同時に楽しめるコンテンツはという意味で、スポーツはグローバルなコンテンツです。
その価値が一気に認知されたのは、スポーツビジネス元年といわれる1984年に開催されロス五輪でしょう。
1984年までは、五輪は大赤字が当たり前のイベントでした。例えば1964年の東京五輪は、当時の国家予算の約1/3にあたる1兆円をかけたプロジェクトであり、そのほとんどがインフラ投資に向けられました。翌年1965年に財政悪化した日本は、戦後初めての国債を発行して資金調達しています。
一方、民間による初開催だったロス五輪は、なんと270億円の黒字でした。この成功以降、特にアメリカではスポーツが企業のマーケティングツールとして注目されるようになります。
なお、ロス五輪の収入源の9割以上は、当時驚くほど高値に設定された放映権とスポンサーシップ収入でした。当該五輪を先導した実業家のピーター・ユベロス氏は、「一つのコンテンツを世界中の人が同時に楽しむことができる」というスポーツの価値に新たな次元の値付けをしました。
※なお、スポーツの商業的な歴史に興味がある場合は下記の本がお勧めです。
1984年をきっかけに、特に企業によるスポーツスポンサーシップの活用が急増しました。それは、スポーツが国籍・言語の壁を超え、多くの人が同時に観るグローバルなコンテンツだからです。
現代の具体例で分かりやすいのは楽天です。楽天は、2017年に、バルセロナと4年間約260億円のスポンサー契約を締結しました。
記事の中で三木谷社長は、このように語っています。
年間65億円という金額は、広告宣伝費という考えに立つと、経済効果的にはもう十二分に採算はあっているんです。世界でのブランドの露出効果を考えた場合、実際に広告換算したらいくらになるのかということを考えると、少なくともその数倍の価値はある。
ちなみに、バルセロナのSNSフォロワー合計数は2億人を超えています(2019)。スポーツは簡単に国境を越えて楽しまれるコンテンツであるからこそ、それを可能にするインターネットと相性が良いのでしょう。
ちなみのちなみに、日本で最もFacebookフォロワーが多いのはC大阪の約120万人です。
また、バルセロナの年間放映権料は200億円を超えています。これも、世界中のテレビ局、動画配信業者にコンテンツとして認められている表れでしょう。
ちなみに、JリーグがDAZNと大型の放映権契約を締結しましたが、その年額が約200億円です。この契約も、Jリーグというコンテンツがアジアマーケットの成長を享受できるということで算出された大型契約ですが、バルセロナは1チームでJリーグ全体のコンテンツと同じくらいの視聴者を抱えていることになります。
そう考えると、三木谷社長の「すでに露出効果でペイできている」という発言もうなづけますね。
グローバル展開の足掛かりとしての価値
また、スポンサーはその活用戦略(アクティベーション)によって、事業のグローバル展開の足掛かりにもなります。楽天は上記のバルセロナだけでなく、同年にNBA当時王者のウォリアーズとスポンサーシップ契約(3年間66億円)を締結していますが、それと同時に、海外売上比率を2020年までに50%にするという目標を掲げ、コーポレートロゴ「Rakuten」に変更をしています。
収益柱であるクレジットカードでバルセロナ公式オリジナルカードを発行する等、スポーツは三木谷社長の海外事業拡大の足掛かりとなっています。また、楽天の投資事業は好調な理由は、スポンサーシップを通じて地域の投資家ネットワークに入り込み有力な投資案件情報を取得しているからとも言われています。
まだ三木谷社長が掲げた海外売上比率は達成されていませんが、勝手ながら、動向を追っていきたいと思います。
多くの日本企業はスポンサーシップをフル活用できていない
蛇足になりますが、このスポンサーシップについては日本では残念な現象が起きています。
米国でスポンサーシップというと、スポーツチームがその企業の事業価値に貢献するためのコンサル契約を指すのに対して、日本では広告媒体を買うという認識が強いため、どうしても「広告換算価値」だけでスポンサーの費用対効果が計測されてしまいます。
結果的にスポーツコンテンツ側も「露出」というリターンだけをセールストークとして、本質的なアクティベーションに繋がりません。
グローバルなコンテンツであるスポーツはそのアクティベーションによって、国内マーケットの縮小に悩む日本企業は大いに活用できるはずです。
米国から学ぶべき最も重要な部分は、「アクティベーションにはスポンサーシップ契約金額の何倍もの投資が必要」という考え方でしょう。これはコカ・コーラでは、『1:5の理念』と呼ばれるそうです。
同社では、1億円で買ったスポンサーシップを活用するために5億円の予算を用意することを意識しているそうです。当然ではありますが、スポンサーシップは単純なエントリーにすぎず、そのアセットを活用して事業的メリットを得るには当然より本気の投資が必要だということです。
「スポーツの価値② グローバル」のまとめ
このように、スポーツがグローバルな認知を取りやすいコンテンツがゆえ、多くのグローバル企業がスポーツに対して多額の投資をしているのです。
スポーツの価値③ ローカル
最後に、スポーツの地域性という価値について触れたいと思います。
「②グローバル」と相反するようですが、スポーツのローカルな側面は、最も重要な部分かもしれません。
思い出という価値
ご存じの通り、ほぼすべてのスポーツクラブが、ある特定地域をホームタウンとして活動しています。スポーツクラブが同じ地域にずっとあるからこそ、世代・性別を超えてその地域住民を繋ぐハブとなり得ます。
そして、スポーツを通じて、家族・友人との思い出が生まれます。
この家族・友人との思いでという部分は非常に重要です。①でも触れましたが、全ての商品・サービスはコモディティ化しています。一方、絶対にコモディティ化しないものの一つは「家族・友人との思い出」です。
上述の通り、スポーツはその地域に根差しているその特性から、親・子・孫・友人・恋人等との思い出という情緒的な価値を帯びてきます。
僕自身、地域に根差したスポーツが盛んなドイツに赴任したことがありますが、その際にケルン出身の友人と、ビールを飲みながらFCケルンの試合観戦をした思い出が強烈に記憶に残っています。
またドイツでは、「観るスポーツ」だけでなく「するスポーツ」も盛んです。「3人いればすぐ部活動をつくる」というジョークがあるほど、スポーツクラブが多く、なんと、ドイツ・オリンピック・スポーツ連盟に正式に登録されている団体だけでも10万団体あり、会員数は約3,000万人も登ります。街中で、老若男女が一緒にサッカーやジョギングを楽しむ姿が印象的でしした。
ドイツほどではないにせよ、どの国においても、スポーツは、地域住民が強く繋がり忘れられない「思い出」が生まれるきっかけとなります。
この「思い出」は、マーケティング用語でいうところの「情緒価値」に当たります。
繰り返しになりますが、ほとんどの商品・サービスはコモディティ化します。とくに「安さ」や「便利さ」といった機能価値はあっという間に真似されコモディティ化してしまいます。
一方、その商品・サービスを体験した人の感情「情緒価値」はなかなかコモディティ化しません。
上記の記事で良い例として記載されているiPhoneは、スティーブジョブズがいなくなったことで情緒価値(カッコイイ商品を使っているという自信、ジョブスのミッションへの共感)が薄れたと言われています。
このように、スポーツの地域性は、iPhoneですら失いつつある「情緒価値」を帯びやすく、相対的に陳腐化しにくいコンテンツと言えます。
地域コミュニティとしての価値
さらに、日本においてはこの「地域とのつながり」はより重要性を増しています。
それは、「家族」「職場」というコミュニティが崩壊し始めているからです。
少子高齢化・核家族化によって「家族」というコミュニティが縮小していることに加えて、終身雇用が常識ではなくなる「職場」も安定感のあるコミュニティではなくなります。
その象徴的なニュースが、トヨタの労働組合から提示された能力主義の給与制度でしょう。
能力主義が駄目というわけではありません。これまで終身雇用を前提とし、全従業員にとって平等の賃上げを要求することが当たり前だった労働組合が、年齢関係なく能力に見合った給与体系を提示していることが重要です。
この動きは多くの会社で起こるでしょうし、同時に「兼業解禁」の動きも重なり、より従業員の流動性が高まり、「職場」というコミュニティがこれまでより希薄になっていくでしょう。
このように「家族」「職場」というコミュニティが崩壊していきます。
そして、その受け皿となるのは「地域」です。
そもそも、地域への貢献は、人間の幸福度に大きく影響することが科学的に証明されています。
さらに、スポーツは、老若男女を超えて地域住民で一緒に楽しむことがコンテンツです。スポーツクラブの勝利や、スポーツクラブの社会活動を応援するほど分かりやすい地域貢献はないかもしれません。
具体例にも触れましょう。スポーツの地域性をうまく活用している日本企業の例の一つにDeNAが挙げられます。
横浜DeNA初代社長の池田純氏は、地域に密着した経営戦略を実践することで、20憶円超の赤字球団を5年間で黒字化しました。
今では、ベイスターズの営業利益は約40億円となり、ゲームの業績が厳しいDeNAにおいて中核事業の一つとなっています。
スタジアム・アリーナという箱物の価値
今後、オリンピックを契機として、スタジアム・アリーナ、スポーツ総合施設が全国に建設されますが、これもスポーツの地域性という価値を倍増させる可能性が高いでしょう。
例えば広島のスポーツ以外の人も交流できるように設計された「マツダスタジアム」には大きな可能性を感じます。
マツダスタジアムを設計した上林氏は、公園や遊具を数多く設計した建築家・仙田氏に師事した経験を活かし、「都市スケールの遊具」としてスタジアムを設計しました。
マツダスタジアムが他のスタジアムと大きくことなる点は、スタジアム周辺を回遊する半数近い人が「野球観戦者ではない人」というところです。
家族連れが楽しめる空間を多く用意することで、スポーツ好きが家族を連れてこれたり、家族ずれで遊んでいたらスポーツを好きになったりという現象が生まれますし、何より多くの地域住民がある場所を繋がりを創ることは地域住民の幸福に繋がります。
これから箱物が日本中に増えることにネガティブな意見もあるものの、うまくこの流れを活用できた自治体・デベロッパー等には大きくポジティブな結果をもたらすのではないでしょうか。
ファイナンス母体としての価値
少し話の方向性は変わりますが、地域住民の自分ごと化を促すことで、安定的なファイナンスも可能です。
バルセロナは昔から地域住民から年会費を集める代わりに、経営判断に対して投票権を与えています。年会費はファンクラブという形でどんなスポーツチームでも実施していますが、ファンに対して実質的な経営権を渡すことにクラブ側の覚悟を感じます。
ブロックチェーンなどの新技術や、PPP/PFIなどの新しい金融スキームも組み合わせると、より小口で面白い資金調達手段が様々考えられます。しかし、そのほとんどがスポーツの地域性に依存しています(地域住民限定の非金銭リターンを設計できる、自治体と連携した金融スキームを設計できる等)。
※少し前に、金融機関で新規事業開発に取り組んでいた時期に、下記のような特集に参加させてもらい、スポーツにおけるファインナンスについて少しだけ語りましたが、もしお時間があればご笑覧ください。
日本でも、本田圭佑選手が新たにサッカークラブを立ち上げるプロジェクトを立ち上げ、東京で資金調達を実施しています。「スポーツチームのオンラインサロン」で、参加者は監督やユニフォームの投票権を持っており、まさに日本版&現代版ソシオへのチャレンジと言えるかもしれません。
「スポーツの価値③ ローカル」のまとめ
このように地域密接に繋がることで、中長期的に安定した経営基盤を築くことができるのがスポーツコンテンツです。特にマーケティング、ファイナンスという領域において、あまりにそのコンテンツのバリューが軽視されていると思います。
また、その地域性が生み出す情緒価値は、あらゆる商品・サービスがコモディティ化する世界において、相対的に魅力が増していくでしょう。
まとめ
今回は企業が活用すべきスポーツの価値「リアルタイム」「グローバル」「ローカル」についてまとめてみました。

今度は、別記事で『企業がスポーツを活用する方法』についてまとめてみようと思います。
最後に、今回は無理やりスポーツの価値を3つにまとめるチャレンジをしてみたので、疑義がある方も多いと思います。
ぜひ奇譚なきご意見を頂けると嬉しいです。スポーツビジネス談義いたしましょう。
いいなと思ったら応援しよう!