
江戸時代の家族と家(江戸・明治の暮らしの基礎知識①)
家に対する考え方は現代とは大違いでした。
家には家業(多くは農業)があり、それを引き継いでいくのが江戸時代の家で、そのメンバーが家族でした。個人事業主一家ですね。
当時の人たちは、親から引き継いだ家を維持し、発展させることが一番の願い。家がなくなると収入源がなくなってしまいますからね。
*現代の感覚では記事「江戸・明治に学ぶ、○○○」を理解し難たそうなことを「基礎知識」としてアップしていていきます。
ヘッダーの写真は昔からの農村が残る長野県・青鬼集落
1.「家業」は必須!
家には必要なものは3つ。まず、「家業」。食い扶持ですね。農業や漁業が85%でした。
次に、「家産」。家業を行うための財産で、農業では田畑や農具、漁業では舟や網などです。代々受け継ぎます。
最後は「家名」。当主は代々同じ名を名乗りました。歌舞伎役者と同じですね。
跡継ぎがいなければ養子を迎えて家を継続させました。養子が入らず、直系だけで続けていった家はほとんどないと思います。
「家業」「家産」「家名」が一体となった家は、先祖も、これから生まれる子孫も含めた永続的な生活の単位であり、生産の単位だったのです。
(参考:『渡辺尚志[2009]「百姓たちの江戸時代』筑摩書房)

2.「家業」を継ぐありがたさ
当時の人たちは、先祖から家業と家産を受け継いだ”おかげで”食べていけました。
墓と仏壇、先祖へのお参りを大切にするのは、当たり前のことだったのでしょう。家名も喜んで受け継ぎました。たとえ義理の関係であっても、子どもは祖父母が育てたので、親子の絆はつながっていきました。
私たちの家庭は事情が違います。
多くの人は引き継いだ家業・家産によって日々の糧を得ていません。先祖や親への感謝の気持ち、子孫を思う気持ちは希薄になりがちです。
墓をどう受け継ぐのか、仏壇をどう受け継ぐのかは、我々の悩みどころですね。家業も家産もないのに家を継げ、親の世話をしろといわれても困惑してしまうのです。
「家(=家業+家産)を継ぐ」というのは、封建的で息苦しいとは思いますが、生き方としてはわかりやすく、経済的でもあります。
自由に仕事と住む場所を選んでローンを払いおわったら定年、というのとは違います。資産が親から子へとつながっています。

https://www.loc.gov/item/2020637886/
3.江戸・明治時代の家族構成
○平均像
人口が3千万人台で安定していた18~19世紀(江戸中期から明治初期)、子どもの数は2~3人と、今よりもやや多いくらいでした。祖父母を入れると6~7人家族ですね。
乳幼児死亡率が高いため平均寿命は30代後半でしたが、成人すれば50歳以上まで生きました。
初婚年齢は男25~28歳、女18~24歳。
ちなみに、私が結婚した1990年ごろは男28歳、女24歳でしたので、大差ありません。しかし、2022年は男31歳、女30歳と急速に晩婚化しています。
○中高年になった独身者の暮らし
多くは結婚している兄弟とともに暮らしました。
その家で農作業をし、家事をしました。動力機械も家電もない時代、仕事も家事もすることが多かったのです。
農作業が困難になると子どもたちの世話をし、負荷の少ない仕事(わら細工など)や家事をしました。働く姿を甥や姪、その子どもたちに見せることが大切です。
都会で働いていた叔母さんがひとりで暮らしていけなくなって家に来た、遠くに住んでいた叔父さんが要介護になって家に来た、というのとはわけが違います。家族に貢献した実績があるのです。
○離婚と再婚
当時は離婚も再婚も多いです。離婚率はいまの2~3倍だったようです。
女性は出産時に死亡することが少なくありませんでした。そうすると男性に縁談が持ち上がり、1年ほどで再婚しました。女性の場合も離婚後に縁談が持ち上がるのが早かったと思います。
パートナーを「労働力」と見ていたのかどうかわかりませんが、「家」という組織では主人のパートナーが必要だったのです。今とは違いますね。
なお、江戸市中では状況が異なり、男性独身者が多くいました。職を求めて出てきた人たちです。江戸には大工などの仕事がたくさんありました。
○隠居
40歳を過ぎ初老の祝いが済むと、隠居の支度をはじめました。早いですね。
息子が嫁をもらい孫ができれば隠居することが多かったのです。
体力が必要な漁家では50歳ぐらいで隠居しました(西日本の海岸地方)。
隠居したら村の共同作業(溝掘り、屋根葺き、田植えなど)には出ません。共同作業は年に100日を超え、対馬では200日を超える村もありました。
次男三男が養子に出ていなければ、隠居した後も働いて、子どもが分家できるようにしました。
60歳ごろまでは中老(中爺・中婆)とよばれ、還暦の祝いをすますと大老(大爺・大婆)になり、村の祭りや葬式の世話、政治も担いました。
(参考:宮本常一[1967]『宮本常一著作集3風土と文化』未来社)
隠居すると同じ敷地内の別宅に移ることもありました。

<トピックス:隠居料>
千葉県流山市の名主・吉野家の日記には、村方三役の組頭が名主に隠居の報告をしたことが記載されています。1813(文化10)年11月4日のことです。
組頭が、酒を持ってやって来て「昨夜の親類寄合で隠居が認められた」と報告。隠居するに当たっての取り決めとして次項が書かれています。
①隠居料に当てる田畑
②娘さんが嫁入りする時の入用金の負担
③隠居の小遣いの原資(馬の駄賃を当て、馬は息子が飼うこと)
④妻の物詣料の原資(村の萬講くじの掛け金を回すこと)
決めておかないともめ事になったのでしょうね。
奥さんの参詣費用の原資も確保していて、参詣が妻のかけがえのない楽しみだったことがうかがえます。

まとめ
江戸時代の「家」は、個人経営の会社のような存在。家業があり、家族が働き、子々孫々、生計を立てていきます。家を継続させ、発展させることが人々の願いでした。
田畑などの家産は先祖から引き継ぎました。仏壇もお墓も大切にする気持ちがわかりますね。
親から離れて新たに家庭を築く人が多い現代とは、「家」に対する考え方が違いました。
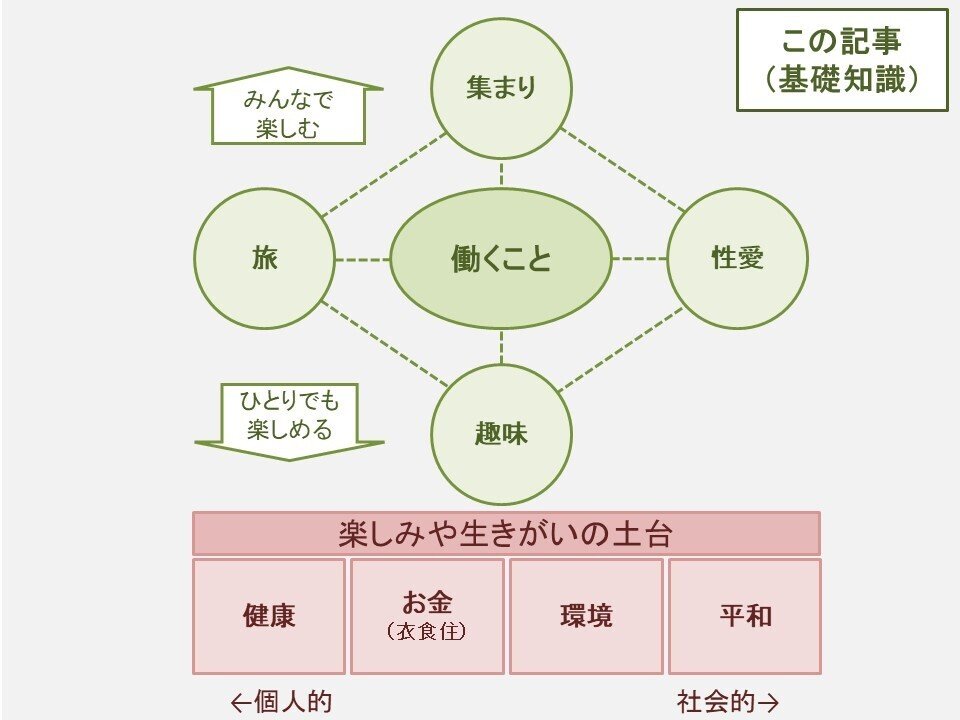
出典:『定年後を豊かにするシンプルライフ』ごきげんビジネス出版
■次の記事 江戸・明治に学ぶ、働く楽しみ(動物とともに働き、暮らし、癒やされる)
■前の記事 江戸・明治に学ぶ、働く楽しみ(子どもも老人もみんなで働く)
■最初の記事 江戸・明治に学ぶ、心豊かなシンプルライフ
■私の書籍

電子書籍(Kindle版)https://amzn.to/40GFdaq ペーパーバック版 https://amzn.to/4jopR1x
下の出版社のnoteでは「第1章 どうする定年後、あなたは何してる?」が公開されています。
■私のブログ (つたない英語に日本語を併記しています)
