
江戸・明治に学ぶ、人生を楽しむための 4つの土台
1. 日々を楽しんでいた江戸・明治時代の人たち
不便でモノやサービスも少なかった江戸時代・明治時代でしたが、農民や漁民たちは日々の暮らしを楽しんでいました。
日々の楽しみの中核は、自然のなかで働いて目に見える成果を得ること。仕事のあとの楽しみは、ご近所での集まり。飲んで食べて歌って踊りました。お伊勢参りや湯治などの旅、句作などの趣味、もちろん男女の交わりも楽しんでいました。(詳しくは前の記事で:江戸・明治に学ぶ、心豊かなシンプルライフ)

(出典:「定年後を豊かにするシンプルライフ」ごきげんビジネス出版)
ただし、人生を楽しむための4つの土台が必要です。
私たちが人生を楽しむためには、最低限の衣食住(あるいはそのために必要なお金)と健康を手に入れる必要があります。これは社会の支援を受けてでも何とかせねばなりません。
一方、環境と平和は個人の努力だけでは如何ともしがたく、国際機関や政府にリードしてもらわねばなりません。
2. 健康と最低限の衣食住の確保
健康面では当時の人たちは悲惨でした。新生児どころか出産時の母親も死亡率が高く、伝染病が流行っても、飢饉を含めて天災が起こっても、祈るばかりで多くの死者や障害者を出してしまいました。
現代では医療や防災が発達し、私たちは長寿を謳歌するどころか、安楽死が話題になるほどです。ありがたいことですね。
他方、最低限の衣食住の確保については、当時の人たちに軍配が上がります。私たちと比べると粗衣粗食ですが、自給自足の能力をもっていました。
しかも飢饉のときは山へ入って縄文人スタイル(狩猟採集生活)で生き延びる、といった最後の一手もありました。私たちのように、外国からの供給に支えられているわけではなかったのです。
私たちには衣食住のためのお金が必要ですし、食品を買い付けられる経済安全保障が必要であり、脆弱なのです。江戸時代の3500万人は、輸入なしで食べていたのですが・・・。

3. 環境の尊さ ーサステイナブルでミニマリストだけど楽しんでいた人たちー
当時の人たちは、自然が許す範囲で生きていました。サステイナブルな暮らししかできなかったのです。
しかも、モノやサービスは少なく、結果的にミニマリストでした。
彼ら彼女らの暮らし方の特長は、次の3つだと考えています。
①モノを買わない自給自足生活
食べ物は、作るか獲るか物々交換で手に入れます。服も作り、家も山から木材を切り出して建て、修繕をしました。里山には果樹だけでなく建築用の木も植えたのです(栗はどちらにも使えますね)。
買ったのは、塩や油、鍬の先のような鉄製品、陶器など簡単には自作できないものです。余裕があると漆の椀やべっ甲の装飾品も買いましたが、子孫代々大切に使いました。
②モノを捨てずにリサイクル・リユースする生活
稲わらは袋(俵など)、衣服(蓑など)、敷物などとして使用され、傷んでくると土に戻し肥料にします。他のものも同じく土に戻します。天然素材ですから。焼いて灰にしてから土に戻す場合もあります。稲わらを土に戻すのは今も同じですね。
私が驚いたのは、家が焼けたあとの木材を橋として再利用したこと。捨てるという発想がないのですね。
③身近にある天然素材を使う生活
建材にする木だけでなく、服を作る綿(綿が育たない寒冷地では藤蔓などの植物)、食器などの日用品になる竹も育てました。トラックがないので遠くから資材を運ぶことはたいへんなのです。そして、使いおわると土に戻します。
サステイナブルですが、資材を育てる里山は必要で、大切に手入れしました。

4. 平和の尊さ ー楽しめなかった幕末の人たちー
戦争は人々の日常生活をめちゃくちゃにします。国を守るといいますが、国土を守るだけで国民は犠牲になります。
ヨーロッパでは国土を守らないと別の民族が住みついてしまう、といった歴史があり、大きな犠牲を払ってでも戦ってきました。日本人は国土から追い出された経験はありませんが、内外で戦いを起こし、ヒト・モノ・カネを注ぎ込めるだけ注ぎ込んできました。
私にはお気楽だったと思える江戸・明治時代の人たちも、戦いがはじまると人格を変えられるほど、どっぷりと巻き込まれてしまいました。
戦場近くに住む人たちは山に入り難を避けますが、徴集された農民もいて、人夫として戦場へ行きました。迷惑なことです。
千葉県流山市の名主の日記には、幕末の天狗党の乱で村人たちが年間43回も運搬業務に駆り出されたと記載されています(2年前は8回)。酔っ払った村人が名主に怒鳴り込んでくるなど人々の不満が溜まり、村の空気がトゲトゲしくなりました。
戦争が起こると私たちの心はすさんでしまい、人生を楽しむどころではありません。
と、思いきや、名主の妻は追討軍の新発田藩主(10万石)が江戸へ戻る時、子どもを連れて〝ご通行見物〟に行っています。当時の人たちは、貴人の行列を見るのが好きなのです。しかし、その日は予定変更で行列は通らず、3日後あらためて出かけました。沈んでいるだけではない庶民の強さです。
まとめ
人生を楽しむためには、自分が健康であること、自給自足でも社会の援助を受けてでも衣食住をまかなえることが、まず必要です。
そして生業を営める環境と平和が維持されていることが必要ですね。
これらがあれば、たいていの人は楽しく幸せに人生を送れるはずです。
(4つの土台の詳細はのちほど記事にしますね)
■次の記事 江戸・明治に学ぶ、トキ消費(そこにある〝時〟を楽しむ)
■最初の記事(前の記事) 江戸・明治に学ぶ、心豊かなシンプルライフ
■私の書籍
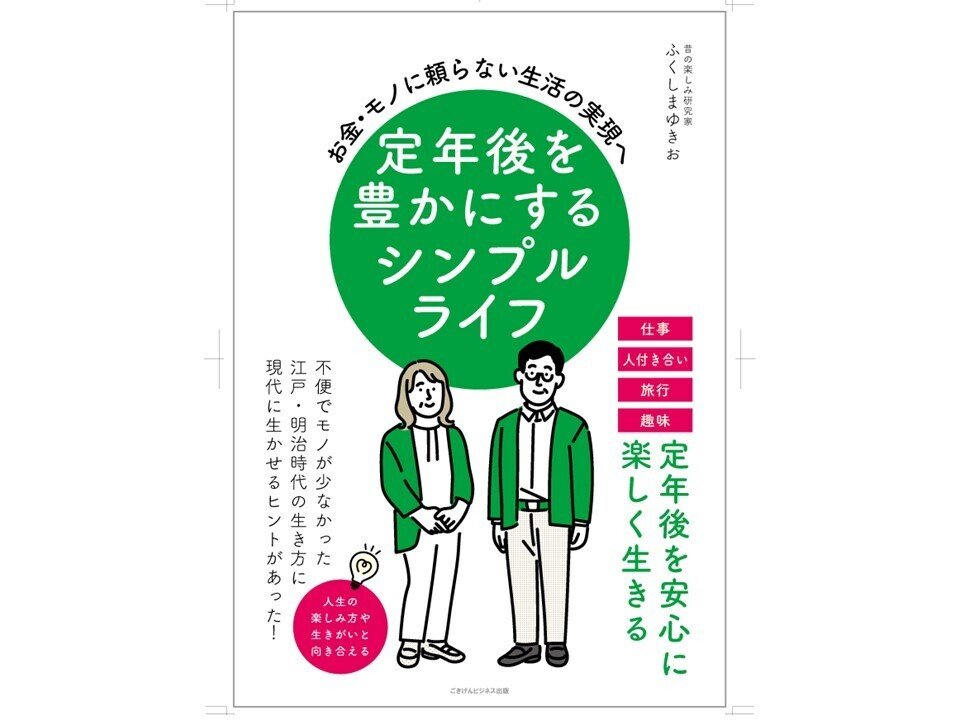
電子書籍 (Kindle版)https://amzn.to/40GFdaq ペーパーバック版 https://amzn.to/4jopR1x
下の出版社のnoteでは「第1章 どうする定年後、あなたは何してる?」が公開されています。
■私のブログ (つたない英語に日本語を併記しています)
