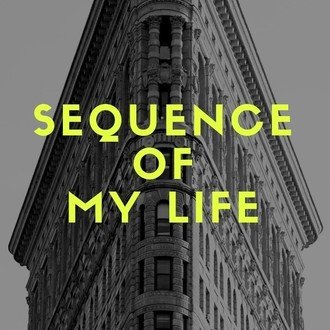流れるようにこちら側
まず君は目覚める。
そうじゃなきゃ話は進まないだろう? 嬉しい事に、君はとても寝覚めが良い。おかげで君のママが買ってくれた高価な時計のアラーム機能は、しょっちゅう無言で泣いているんだ。それで続きだけど、ありがたく無いことに今日に限って君の目は、泥水がたっぷり入ったバケツみたいになっている。なんてたってスコット・ヘッドフィールドの夢を見たからさ。どうやら君は、スコットが夢に登場した事ぐらいしか覚えていないようだけど、僕は君の夢の内容を全て知っているんだな。スコットとペティ・スミスがキスをしている。君はただ黙っている事しか出来ないんだ。そしてスコットはペティ・スミスの顔面を何回も殴って、彼女はそれに笑顔で応える。もし今日の寝覚めが、もっとすっきりとしたものだったら、君は発狂していたかもね。全く一途だよ、君は。
ぱっとしない気持ちのまま、君は一階へと降りる。既に他の奴らは朝食を終えていたみたいで、テーブルに置いてあるオートミールは君の分だけだ。でも君は内心うんざりしているんだ。この寮での朝食と言ったらオートミールぐらいだからね。でも君は黙々とそれを口に運び続ける。僕に言わせれば、君は年頃の従順で内気なシャイボーイに見えるな。
けれども、胃に入れば皆同じって言う言葉通りに全て平らげた君は、まだうまく動かない体を叱りつけて制服に着替え始める。その後歯磨きをして、顔を洗い、学校指定の鞄を持って登校。出際に管理人のボブじいさんに部屋のキーを預け歩みを進める。これが君の今朝の風景さ。
学校に来てまず最初に君が思う事は、ペティ・スミスと話せるかどうか、それだけに限る。登校時間はそりゃ皆一緒な訳ないから、そうそう会えるってもんじゃない。それに君は律義だから、昇降口にに入り辺りをぐるっと見回して、それでも彼女が見つからないのならば、ぶちぶち言わずにさっぱりと諦めて三階の教室に向かう事にしている。その時以外では滅多に彼女に会えないと分かっているのにだ。
君は全身の血液を総動員して、哀れな心臓をこき使いながら、校内へと入って行く。今の君の顔つきと言ったら!まるで、ペティ・スミス以外の人間はこの世から消し去ってやる、そう思われても仕方無かったんじゃないかな。
回りを見渡すと運の悪い事に、スコットが男子トイレから出てきたところだった。君は面食らって、急いで身を隠す為に、途中で何度もつまづきながら、掃除用具入れの影に隠れる。君はどう思っているか知らないけど、僕はそういうのを見ているとうんざりしてくるんだよな。おかげでスコットは気付かずに行ってしまったけどさ。
でも次の瞬間、君は飛び上がらんばかりに喜ぶ事になる。ペティ・スミスが女子トイレに入って行くのを目撃したからね。鷲のように気高いブロンドの髪、それと良く合う鳶色の瞳、パリッと着こなしている制服が理知的でストイックだ。今の君の気持を代弁するとそうなるな。僕にはこれっぽっちも理解出来ないけど。
彼女がトイレに入ったのを見計らって、君は素早く男子トイレの前まで移動し、彼女が女子トイレから出てくるのを待つ。君のプランはこうだ。女子トイレからペティ・スミスが出てくるのと同時に、君もたった今トイレから出てきたという風に、何気無く立ち去ろうとする。真面目で律儀なペティ・スミスは、知り合いの君に声をかける。君は、まさか彼女が後ろから来るだなんて思わなかったという感じで返事を返す。つまり二人は偶然会うって寸法さ。ペティ・スミスの性格を熟知した、実に君らしい巧妙な作戦だ。まぁ僕には理解出来ないけどね。
でもそんな事を考えている内に、ペティ・スミスは君をとっくに追い越している。チーズに逃げられた鼠のような顔をして、君は慌てて追いかける。そして、用意周到な君は既に第二のプランを考えていた。人混みに紛れ込み、気付かれないように彼女の前まで移動する。そしてわざと遅く歩き、彼女に自分の背中をアピールするんだ。恐れ入るよ。
「あら、ジェリーじゃない」
案の定彼女は君の目論見にはまる。
「やぁ、ペティじゃないか」全然気付かなかったよ、と続け君はぼろが出ないように自然な動作で振り向く。
「私も全然気付かなかったわ」
にこやかに微笑む彼女の雪のように白い歯は、君の思考をいとも簡単に凍らせる。
「あ、相変わらず君の髪は美しいね」停止した脳が何とか捻り出したその言葉に君は、あまりの恥ずかしさで身が焼けるようだったけれど、ペティ・スミスの「そう?ありがとう!」という嬉しそうな顔を見て、そんなの何処かへぶっとんで行ったみたいだ。そしてその後、スマートなウィンクと一緒に彼女の口から出た、「あなたこそ、今日もとびきりハンサムよ」という言葉は、君の全てを貫き、心臓はそのまま破裂しそうなぐらいにフル稼働し、普段はクールを決め込んでいるその顔も、タコのようにふにゃふにゃになっている。
「じゃあ私はこっちだから」じゃあね、と言って走り去る姿を、君は一世紀前のからくり人形みたいに手を振って見送る。私事だけど、僕はあまりペティ・スミスが好きじゃない。ストイックな女はどうも僕を狂わせるんだ。
良い事が起きたら悪い事も起きるのは当たり前だよね。何故かと言うと、スコット・ヘッドフィールドが教室にいるのを、君は知っていたからさ。まぁ君は良く頑張って誤魔化していたけれど、教室に赴く足取りはどう考えてもスキップじゃない。教室から聞こえる喧騒の中に、スコットの下卑た笑い声があるのを聞いて、君が歩いている廊下は泥沼に変わって行く。
教室に入ると、スコットは数人の悪友と共にポーカーをやっていた。もちろん、彼がでんと腰掛けている椅子は、本来君の座るべき場所さ。ゲラゲラ笑ってレイズした彼は、視界の端っこに君の姿を目に留めるや否や、「これはこれは!」そう言って机をなぎ払い、強引にゲームを終らせる。実際彼の手札は完璧にブタだったしね。「女子トイレを覗いてた覗き屋トムジェリーくんじゃないか!」これには思わず笑ってしまったね。確かにあの時、君は鼠だったに違いない。
「覗いてなんかいないよ!」君は集まる周りの視線を気にしながら、おどおどと小さな声で弁解する。「でもなんで分かったんだい?」
しまった、と君が思ったのはスコットの馬鹿笑いを見てからだった。「はっ、はっ!はぁ!」スコットは涙を流して笑う。周りの連中も同じように笑う。「マジかよジェリー!」赤い顔で恥ずかしそうにうつ向く君には堪えるだろうけど、ようはカマかけられたんだよね。
さっきから分かっていた事だけど、君の机は今やスコットのものになっている。彼の机がどうなったかは、多分君は知らないだろう。彼はね、外に投げ捨てたんだ。きっと今頃バラバラさ。彼のやり方にはいつも感心させられるよ。相手を傷付ける時は自分にも同じ事を課すんだ。
君は、今かなり頭にきていてショックも受けている。そんなの誰が見たって明らかで、今や君の顔はレンジに詰め込んだソーセージのように膨らんでいたし、熟れ過ぎたトマトのように真っ赤になっているからね。
自分を強く見せようと、君はトッド・クラチットの席を奪う事を決める。賢明な判断だと思うな。何故なら、トッド・クラチットは弱いからだ。見ているだけでフリーキックしたくなるぐらいの超が付く弱者で、世界広しと言えども彼の右に出る者はそうそういないだろう。もがき、喚き、泣き叫び、見苦しく、そして尚、弱虫な毛虫だ。ガラス窓をスパイクシューズでひっかくような声で付く嘘は数知れず。動く度に頭からフケをまきちらし、マッシュルームカットは森に生えたキノコさながらだ。
「そこをどけよトッド」
と君はなるべく声にドスを効かせ、威圧的に彼に言う。やっぱりトッド・クラチットを選んで正解だよ。もし彼以外にそんな事をしても、鼻であしらわれるか、顔に真新しいアザをこさえるかのどっちかだしね。現にトッド・クラチットは、その言葉でかなりビビッている。肺から空気を締め出したような声を出し、ばねみたいにイスから飛び上がる。彼は君の表情をちらちら窺いながら媚へつらうように笑い、君に席を明け渡す。君は彼のイスにでんど座り込み、スコットの背中に一瞥をくれる。トッド・クラチットは自分がこれからどうすれば良いのか分からず、廊下や教室をうろうろした結果、生活指導の先生に捕まりこっぴどく説教を食う。そんなこんなが朝の学校での風景さ。
時間を飛んで放課後について話そう。
君はかなり参った様子で道をてくてくと歩いている。
結局トッド・クラチットは例の件を先生にチクり、問い詰められた君はスコットの事をチクった。君とスコットはくそったれの教師達にうなされそうなくらいに叱られ、罰として学校中の掃除を言いつけられた。まぁ当たり前と言ったらその通りだけど、一番不幸なのはトッド・クラチットだよ。
君は寮に戻り、部屋のキーを貰おうと管理人のボブじいさんの所に行く。耳の遠いボブじいさんに、なるたけ大きな声でキーを返してくれと言うと、彼はよぼよぼの目をさらにくしゃくしゃにして、冬の木のように笑う。
「ジェリー坊や。いくらわしが老いぼれたじじいだからって、からかっちゃあいけない。さっき取りに来たばかりじゃないか」
もちろん、君は身に覚えがない。しきりに、たった今帰って来たところだと言っても、ボブじいさんはそれをぽかぽかと受け流す。
とうとう折れてしまった君は、ジョークさ、と曖昧に笑いながら言い捨て、その場を後にした。
息を切らせながら、ようやく自分の部屋に着いたと同時に、君は背筋が凍るのを感じる。まるで、入ってくれと言わんばかりに開け放たれているからだ。普通ドアは勝手に開いたりはしない。意志を持っているならば別だけど。
「やぁジェリー」
彼は手を振って親しげに話しかけてくる。背丈は君と同じくらいで、一緒の制服を着ている。人混みの中で必ずは見かける顔つきで、髪は君と全く逆の色をしている。優雅な動作で髪を払い、ギャツビーのように柔和に笑う。
「お、お前は誰だ」
君はビビりながらそう言う。それが普通の反応さ、君。でも彼はうやうやしい溜め息でそれに応え、「何でそんな事を気にするのかな」と言う。
「ジェリー、お互い遠慮する事はないんだ。さぁこっちに来なよ」
「誰だって聞いているんだ!」
君が語気を強めると、彼は「ジェイさ」と肩をすくめ、「なぁもっと他の話しをしないか?」目を細めて頬杖をつく。
「例えば君がペティ・スミスに抱いている淡い想いとかさ」
君は雷に打たれたようになり、みるみる内に朱を帯び始める。分かるよ。想い人の存在はなるべく黙っておきたいよね。その方が余計な心配をしなくて済むし、断然うまくいくってもんだ。うまくいくのさ。
ふと君は眠気に襲われる。時計を見やると――目は覚めないけど――驚愕する。だって短針は十二を指しているのだから。君は七時にジェイと会った。
「ジェリー。僕は君の事を何でも知っているよ」
君を見つめる瞳には、彼が写っていて、その瞳にはその瞳が写っていて。同じ事を何千、何万と繰り返し、君は眠くてその場にしゃがみ込む。
「そんなに眠い?」
微笑みながら、君を起こさないように彼は立ち上がり、最初から決めていたように目覚まし時計を抱いて、蜃気楼みたく影ごと消え去る。ドアは何かを渇望するように開き、廊下にはボブじいさんのいびきが響き渡っている。
この記事が気に入ったらチップで応援してみませんか?