
「石川遼を風呂で取材する記者」が僕に教えてくれたこと。
娘が5歳になった。
お風呂に入れて、頭を洗ってあげるのは父の務めなのだが、最近は「自分でやる」と言われることがある。
浴室の外に閉め出されるたびに、よみがえる記憶がある。
記者としての「敗北」を容赦なく突きつけられた思い出だ。
どうやら浴室の中では、頭を洗い終えた娘がリンスを始めたようだ。
序盤の構成を頭の中でつくっていく時間ができてしまった。せっかくなので、そのままの勢いで書かせていただきたい。
![]()
2012年11月11日、静岡県御殿場市。
太平洋クラブ御殿場コースのクラブハウス周辺では、多くの報道陣がうろうろと歩き回っていた。
1時間ほど前、石川遼プロが2年ぶりのツアー優勝を果たしていた。
だが、一通りの取材対応を終えた彼は、どこかに姿を消してしまった。
スポーツ新聞は各紙とも翌日の1面扱いが決まっていた。
追加取材もして、涙の復活優勝を彩る記事をつくりあげたいところだ。記者はみな、あわてて遼プロを探し始めた。
僕もそのひとりだ。
何とかマネジメント担当の板谷篤さんを見つけたので「プロはどちらですか?」と聞いた。
「風呂だよ」
「あっ、そうだったんですね。でも試合会場でシャワー浴びていくなんて、珍しくないですか?」
「シャワーじゃない。風呂。今日は一緒に入る相手がいるから」
「えっ?」
嫌な予感がした。
遼プロを探して右往左往する記者の中に、スポニチの担当記者の姿がなかったのが気になっていた。
「もしかして…」
「そう。クラセコ記者と入っているよ」
思わず天を仰いだ。

何社かの記者が抗議している。
それに対し、板谷さんは毅然と受け答えをされていた。
「遼は皆さんに対しても、一通りの取材対応をきちんとしたと思うけど。そこからは取材努力じゃないんですか?何より遼が望んだことだから。クラセコ記者が遼を拉致したとかでもない」
本当にその通りだ。
だから僕は、抗議の輪に加わる気持ちにもなれず、ただただクラブハウスの片隅に座り込んでいた。
優勝直後に単独インタビュー。しかも風呂で。前代未聞と言っていい。
明日のスポニチには、いったいどんな記事が出てしまうのか…。各社とも焦りに焦っている。
「遼プロとクラセコを2人きりにしてしまったのがまずかった」
そう"反省"する記者の声が聞こえたが、それは違うと感じた。勝負は今日じゃない。とっくの昔についていたんだろうと思った。
なぜ自分は、遼プロを信じて取材し続けられなかったのか…。
そんな後悔だけが、ぐるぐると頭の中を回っていた。

その2年前。
サッカー担当からゴルフ担当に配置が変わった僕は、越後湯沢にいた。
駅前の居酒屋に入ると、知った顔を見つけて驚いた。
「えっ?興梠選手?」
「ん?おー!おつかれさまですー」
鹿島アントラーズの興梠慎三選手が隣のテーブルで食事をしていた。
サッカー担当を離れる直前の2か月だけ、僕は臨時でアントラーズ担当をしていたので、顔だけは覚えてもらっていた。
聞けば、友人と一緒にスノボに来ているのだという。
「そっちは何しているんですか?ウィンタースポーツの担当になったの?」
「いや、実はゴルフ担当で」
「えっ?なのになんでここに?」
「石川遼くんがスキー合宿をしているんだよ」
「えーっ!マジで!!」
いつもひょうひょうとしている興梠選手が、見たこともないテンションで話しかけてくる。
「遼くんに会いたい!会えないかな…?」
彼がゴルフが好きだということももちろんある。
だがそれ以上に、石川遼といえば「国民的なスター」だからだ。

スキー合宿を皮切りに、僕は石川遼プロを追い続けることになった。
2月にはアメリカ西海岸に飛び、アメリカ男子ツアーに参戦する所を取材した。他のスポーツ各紙も同様に、現地に記者を派遣していた。
3月には東日本大震災が起きた。僕は手を挙げて被災地取材班に回してもらった。
アメリカで転戦を続けていた遼プロは「賞金を全額寄付」と宣言し、話題になっていた。
5月。ゴルフ担当に戻ると、会社からは再び「とにかく遼を追え」と念を押された。
現場の記者もみんなそうだった。他の選手そっちのけで、みんなが遼プロだけを見ている状況だった。
そんな中で、僕はたまたまだが、遼プロの最大のライバルとされていた池田勇太プロと打ち解けるようにもなった。
他にも魅力的な選手はいる。そんな思いから、僕は会社の方針とぶつかるようになった。
その年の全英オープン。
現地で取材した僕は、遼プロではなく勇太プロの記事を大きくしたいと主張して、先輩記者ともデスクとも大ゲンカになった。
遼プロに何かをされたというわけではない。
だが、思う通りの取材をさせてもらえないことへの反発から「遼プロをまごころ込めて取材したい」という気持ちが生まれないようになっていった。
今考えても、遼プロの記事にニーズがあったのは間違いない。
我ながらひどく子供じみていた。
![]()
それに比べて、遼プロの方ははるかに大人だった。
ある朝。
ラウンド取材開始に備えてクラブハウスの周辺にいた僕は「塩畑さん」と声をかけられて振り向いた。
遼プロだった。
「お、おはようございます」
「おはようございます!ちょっと聞いてもいいですか」
「は、はあ」
「塩畑さんって、いつも勇太さんのラウンドについて回っているんですよね?」
「は、はい…」
「今度ぜひ、ゆっくり話を聞かせてください」
頭を下げると、踵を返して去っていく。

それから、遼プロと話す機会が急に増えた。
勇太プロのラウンド取材を終えて、残り数ホールの遼プロのラウンドに合流すると、すぐに目が合う。
そして、ホール間を歩いている時に近くに来ると「おつかれさまです!勇太さんのところに行ってたんですよね?」と声をかけてくる。
ホールアウト後には「調子良さそうですよね?」「パターなんで変えたんですか?」と根ほり葉ほり聞いてくる。
本人に聞けばいいのに…と思っている間に、話題は徐々に僕自身のことにもなった。
サッカー担当として誰を取材したのか。取材現場の雰囲気はゴルフとどう違うのか。あまりにも聞き上手なので驚いた。
マネジメント担当の板谷さんに、このことを話してみた。
すると「塩畑記者が勇太プロをよく取材しているとか、もともとサッカー担当で中村俊輔選手を取材していたとかいう話はしたかな」と明かしてくれた。
「こっちとしては、話をしてもらえるとうれしいよ。世界が広がる。あとは何より、番記者といい関係をつくるっていうのも、ああいう選手には大事だから」
それで気づいた。
遼プロは、自分と微妙な距離をうろつく気難しい番記者に、手を差し伸べてくれていたのだ。

遼プロはそうやって、本当にいい取材をさせてくれた。
その頃は、ゴルファーとしても進化を遂げようとする時期でもあった。
2012年は3月のプエルトリコオープンで2位に。そして「準メジャー」とも言われる5月のメモリアル・トーナメントでも9位に入った。
常にアグレッシブに攻める10代当時のスタイルから脱皮し、世界の舞台でも通用する戦略的なゴルフを身につけつつあった。その様子を取材するのは、本当に楽しかった。やりがいがあった。
しかし、レベルの高いアメリカツアーへの出場数を増やしたことで、遼プロが「優勝」に絡むチャンスは減った。
現場から日本のデスクに電話をすると、決まって「最近遼くんは勝てないね」と言われた。当たり前だと言い返したが、なかなか分かってはもらえなかった。
そもそも、ゴルフの勝った負けたを、野球やサッカーのような感覚で語るのが間違っている。
野球もサッカーも、2チームのうちどちらかが勝つ。だがゴルフはまったく違う。勝てるのは、試合に出場する150人のうちひとりしかいないのだ。
「遼プロは確実に強くなってますから。周りのレベルが高いだけで」
僕は意地になってそう言い返していた。だが8月下旬から遼プロが日本のツアーに戻ると、一気に旗色が悪くなった。
2週連続で予選落ち。決勝ラウンドに残れても、優勝争いに絡めない。
「やっぱりダメじゃん」。社内の各方面からそう言われ、返す言葉がなかった。
ちょうど勇太プロが、毎試合のように優勝争いを演じるようになった時期でもあった。
ようやく遼プロが優勝争いに絡んだ10月のキヤノンオープンでも、最終日最終組で一緒になった勇太プロが圧倒し、試合にも勝った。
遼プロが優勝から遠ざかる期間は、2年になろうとしていた。
僕はついに、彼の力を信じることをやめてしまった。
![]()
キヤノンオープンの翌週は、ゴルファー日本一を決める国内メジャー戦、日本オープンだった。
ここでも勇太プロが優勝争いを演じた。まだアマチュアだった松山英樹選手も最終日に浮上し7位。そんな中、遼プロは35位と静かに試合を終えた。
この頃の僕は、試合終了後に遼プロにあいさつをすることすら怠っていたような気がする。
彼はそのまま韓国に渡り、翌週には韓国オープンに出場。
その次週は兵庫で行われるマイナビABC選手権でプレーしたが、日刊スポーツ新聞社からは僕ではなく、大阪を拠点とする記者が現地に派遣されることになった。
「なぜスポーツ紙って、毎週違う記者の方がいらっしゃるんですか?他のスポーツでもそうなんですか?」
一瞬だけ、遼プロのそんな言葉がよみがえった。
番記者がどこまでも追うサッカーやプロ野球と違い、ゴルフ取材では西日本で開催される試合の取材は、大阪の記者にバトンを渡すのが通例だった。
僕はこの年「遼プロもこう言っているので」と主張し、遼プロが出場する男子の試合は、西日本開催でも取材させてもらうようにしていた。
だがこの時は、取材を申し出ることすらしなかった。

「すごくよかったんだよ、この2週間の遼のプレーは」
太平洋クラブ御殿場コースのクラブハウス。
僕は遼プロが風呂から出てくるのを待っていた。憔悴しきった様子を見かねたのか、マネジメント担当の板谷さんが話しかけてきてくれた。
「クラセコ記者は先週から『時間の問題ですね、優勝は』と言っていた。だから、ムリをしてここに来たんだよ」
東と西で記者が切り替わるのは、スポニチも一緒だった。
だから普通なら、御殿場での試合は東京の記者がカバーする。その通例を、志願してやぶったというのだ。
スポーツの現場に少なくないのが「競技を面白がれない記者」だ。
「その競技を見すぎて」というパターンがひとつ。また「つまんない試合」と評することで「自分は競技を見る目がある」という演出をはかっているパターンもあるように感じる。
スポーツニッポン新聞社大阪本社の倉世古記者は、そうした記者とは一線を画していた。いつも新鮮な気持ちで取材をしていた。誰よりも面白がって、思い入れを持って対象、事象を追う記者だった。
マイナビABC選手権。遼プロは6位に終わったが、そのプレーぶりをみた倉世古記者は「すぐに勝つ」と確信をした。
ムリをして訪れた御殿場で遼プロが低迷をすれば、社内からは「見る目がない」「出張費のムダ」と言われただろう。そのリスクも承知で、彼は東へ飛んできた。
これこそ、番記者の仕事だ。
優勝直後に一緒に風呂に入って取材する、という状況は垂涎ものではある。ただそれで明日の紙面にどれだけの差がつくか、という話ではない。
それ以前に僕は、番記者としてのスタンスですでに負けていた。負け切っていた。
![]()
「あー、そんなこともありましたね」
コーヒーショップのテーブル席で、遼プロが懐かしそうに笑う。
2014年4月、アメリカ・サウスカロライナ州のヒルトンヘッドアイランド。
アメリカ男子ツアー戦、RBCヘリテージの初日を終えた遼プロは、試合用のウェアのままで店に入ってきた。
私服姿以上にあからさまに「あの石川遼」である。騒ぎになりかねない。
ただ、ここはアメリカだ。「日本じゃ考えられないよね」と遼プロがいかにもおかしそうに言う。
その前週。僕はゴルフファン以外にも知られる世界のメジャー大会「マスターズ」を取材した。
普通ならそのまま帰国するところだ。だが滞在予定をのばして、マスターズに出場していない遼プロを取材することにしていた。マスターズ直前のパーマー招待で8位に入るなど、いいプレーが続いていたからだ。
だがヘリテージの初日、遼プロは124位と大きく出遅れてしまった。2日目終了時点の上位70人という予選通過枠に入るのも難しい位置になった。
それにも関わらず、彼は明るかった。ラウンド後の取材対応が終わると「塩畑さん、この後って何をしているんですか?」と向こうから聞いてきた。
原稿は日本時間の午後、つまり現地時間の翌日午前2時に書き上げればよかった。
「しばらくヒマよ」と言うと「じゃ、スタバで合流しますか?」と提案してくれた。
![]()
遼プロはカウンターでバナナフラペチーノを受け取った。
ちょうど日本で「売り切れ続出」とニュースになっていた。「いやー、こっちなら余裕で買えるね」といたく喜んでいる。
「それにしても、ゴルフの試合を記事にするのって、難しいですよね」
「そうかな?選手はみんな協力的で、取材はしやすいけど…」
「いや、試合の途中経過を記事をするというところ、ですね。サッカーとか野球では考えられないでしょう」
確かにそうだ。ゴルフの試合は4日間かけて行われる。3日間は途中経過を報じなければならない。
「正直、僕らからすると、最終的な結果から逆算しての1ラウンドであり、1打1打なんですよね。試合が終わらないと、その1打の価値も確定しない。それを記事にするというのは…どうなんでしょうね」
うならされた。ものすごく本質的な議論だと感じた。
同じような話は、のちに西武ライオンズを取材した際に、中村剛也選手からも聞くことになる。
試合中にテレビやラジオの中継向けにホームラン談話を求められるが、彼は必ず「打ててよかったです」と言うにとどめる。
勝つためにプレーしている以上、試合の結果が出るまでその1本の評価なんかできない、というのだ。
あれだけ喜んで買ったバナナフラペチーノのグラスに手もつけず、遼プロは「本質」について熱心に語ってくれている。
本当にその通りだと感じた。取材を受ける意味について、これだけ突き詰めて考えていることにも胸を打たれた。
急に表情を緩めて、遼プロは言った。
「つまり、今日の77打の意味も、まだ決まってません。オレ、このコース本当に好きだなぁって思うんです」

深夜2時。日本のデスクとの電話のやりとり。
「ダメだな遼は。やっぱりムダ足だったな。予選落ちしたら、すぐ帰ってくるんだよな?」
「いえ…、できれば来週もこっちで遼プロを取材したいです」
「はぁ?…まあ、いいや。とりあえず、原稿は確認したよ」
![]()
翌日。遼プロは3つスコアを伸ばした。58位に浮上し、予選通過。
決勝ラウンドでも伸ばし続けて、最終的に18位に入った。
初日から100人抜き。たらればに意味はないが、2日目からの3ラウンドに限ったスコアなら全選手中トップだった。
遼プロのスタバでの言葉がよみがえる。
初日の77打がそんな意味を持つことになるとは…。
「それはまさに、たらればですよ」
本人はそう笑い飛ばした。
「でも、内容はホントよかったです。ボールを操れている、という感覚を持ちながらプレーできました」
小さく、力強くうなずくと、握手を求めてくる。
「この試合を取材してもらえたのはうれしいです。ありがとうございました」
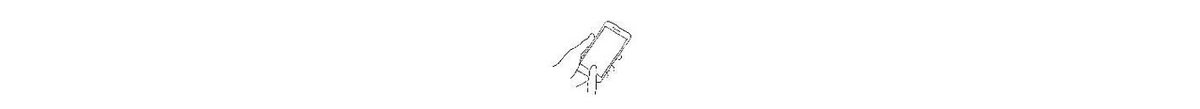
目先の結果を追うのも、もちろん大事な仕事だ。
だが番記者であるからには、取材しているからこそ見えるものを信じて、結果に左右されずに追い続けることもまた大事なのではないか。
倉世古記者と遼プロのおかげで、僕のその後の取材スタンスは変わった。
そして今では取材の現場を離れ、ニュースプラットフォーム側で働いている。
取材者とはまったく違う立場になり、見えてきたものはある。
今の世の中は、ネットの力もあいまって、ニュースであふれている。
加えて、時の流れは速い。大震災やコロナ禍のように、価値観自体をひっくり返してしまうようなことも起きる。
情報はともすれば「バリュー」とか「賞味期限」みたいなもので機械的に仕分けをされてしまう。そうでもしないと、とても扱いきれないからだ。
1つ1つの取材成果が、きちんと吟味された上で世の中に広まっていくというのは、以前にも増して難しくなったようにも感じる。
◇ ◇ ◇
ただ、だからこそ少しでも、という思いはある。
先週は秋田魁新報さんに、歴史的なスクープ記事の裏側を伝える記事をLINEニュース向けに書き下ろしていただく、という貴重な機会に恵まれた。
こうした「継続的な取材に裏付けられた、本質的で熱のこもった記事」を広めるお手伝いを、これからもさせていただきたい。強くそう思っている。
こういった記事には、その日のうちに記録されるページビュー数だけでははかれない「力」がある。それこそ、遼プロの1打1打のように。
幸い、LINEニュースはそういう機会をつくらせてくれる。
そして、取材現場にいた自分だからこそ、プラットフォーム側でできることはある。そう信じたくも思う。
倉世古記者や遼プロが教えてくれたこと。
それは今も僕の胸に深く刻まれている。
