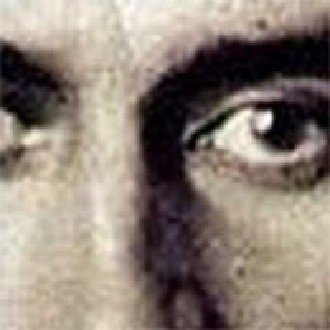「他人には心があるのかもしれない」という、哲学者の王様の懐疑
以下の文章は永井均『世界の独在論的存在構造:哲学探究2』のp.175~の議論を読みながら要点を自分なりにまとめた文章です。本書で「東洋の専制君主」と表されている言葉が以下の文章の「哲学者の王様」に対応します。
■他人には心がないのかもしれない
「実は、他人には心がないのかもしれない」
その種の疑いを抱いたこと、あるいは見聞きしたことのある人は多いだろう。私の友だちや先生、家族などが笑ったり泣いたりするとき、楽しさや悲しさを感じているように見える。しかし、実はそれは見せかけにすぎないのではないか。「他人に心がない」が意味するのは、つまりこのような疑問だ。
確かに彼らは笑ったり泣いたりしているが、実際にはそのように振る舞っているというだけで、ほんとうは彼らの内側には喜びも悲しみも存在しないのかもしれない……。
子どもがこういった問題意識を人に打ち明けたのなら、多くの場合は一笑に付されて終わる。その種の疑問を抱いたことのない人なら「他人に心がないかもしれないと考えるなんて、ひねくれた子だなあ」と思うはずだ。
だが「他人には心がないかもしれない」と疑ってしまうのはなぜなのかを考えてみると、むしろそういった疑問を持つのは非常に「素直」だからであって、他人の心を信じている人たちこそ、非常に「ひねくれた」概念を「素直」に受け入れているのかもしれない、という見方が生まれる。
■自分の「痛み」は疑えない
「他人に心がないかも」と感じることの裏には、ふつう「自分には心がある」という前提が隠れている。人は自分に心があることをどうやって知るのだろうか? それはもちろん、直接的に自分の心を感じることによってだ。
冗談を聞いてつい笑うとき、ただ笑っているのではなくて、自分自身はなにか「おもしろさ」を直接感じている。だからこそ「自分は笑ったけど、本当はただ笑っているだけで、何も感じていないのかもしれない」と自分の心の存在を疑うことは(普通は)ない。
さて、そこで周囲を見まわしてみる。冗談を聞いて自分と同じように笑っている人たちがいる。自分の目から見えるのは、彼らがただ冗談を聞いて笑っているという様子だけである。当たり前のことだが、そのプロセスに自分自身が直接感じた「おもしろさ」は入ってきていない。つまり「冗談を聞いて、笑う」というプロセスにおいて、他人がそれをやるのと、自分がそれをやるのとでは、自分の場合にだけ何か直接的に感じられる感覚を味わうという余計なプロセスが挟まるのだ。
誰だって、他人が殴られるのと自分が殴られるのとでは大違いだと感じる。その理由はもちろん上記と同じで、自分が殴られたときだけ「ほんとうに痛い」からである。脳波を調べるなどの細密な検査をしても同じことで、たとえ脳波が正常値を出していて、いやキミは痛みなど感じていないはずだ、と言われたとしても、自分が痛く感じたのであれば疑う余地なく痛いのである。
■素直な疑問としての「他人の心の懐疑」
同じことでも、自分の場合には「ある感覚」が生じて、他人の場合には生じない。この絶大な差異こそが「他人に心がないかも」という疑いを生み出している。なぜなら、非常に素朴な意味において、他人には心など絶対に存在しないからだ。痛いことの本質は「痛み」そのものであって、他人が転んだときに「それ」は生じない。だったら、それは本当には痛くないのだ。このほうがよほど「素直」な考え方ではないだろうか?
にもかかわらず、ふつう私たちは他人が痛みを感じていることを認める。「私は痛くないが "その人にとっては" 痛いのだろう」という言い方で。自分にだけ直接わかるあの「痛み」が、他人においても「自分にだけ直接わかる」という形で成立していることを認める。それが「心のある他人」という概念を生み出すために必須の行程である。
しかし、「心のある他人」は矛盾を含んでいる。
理由は簡単で、「自分」というのは「ほかならぬこの自分」を指すのだから、それが他人において成立しているなどという事態は本来無意味なはずなのだ。なのに私たちはその矛盾した概念を使いこなしているし、そういう世界しか知らない。
そもそも「心」という言葉そのものが、自分だけに生じる唯一のモノを、誰しもが持っている物として一般化してしまう魔法なのである。自分自身が転んだら痛く感じる唯一の人間であるにも関わらず、「自分はたくさんいる人間の一人に過ぎない」と信じられるのは、この魔法にかかっているからだ、といえる。
だから「他人には心がないかもしれない」という問いは「『心』とは矛盾を強引に成り立たせる魔法にすぎないのではないか」という素朴な疑問から派生したものであり、決してひねくれているわけではない。自分自身が常に感じている「そのもの」性を拠り所にさえすれば、すぐにでもたどり着ける懐疑なのだ。
■哲学者の王様による逆向き「他人の心の懐疑」
では、問題を逆向きにしてみるのはどうだろう。
こういう世界を考えてみる。
ある国に王様がいた。王様なので、周りの家来はみんな自分の言いなりになってくれる。そして王様は、自分が転べば自分が痛みを感じるが、ほかの家来たちが転んだときは全く痛みを感じないことを知っている。同じことが起こっても、それが自分のときだけ特別なことが起こる(=痛みが生じる)のだから、じっさいに自分は何かが特別なのだろうと王様は考えた。彼は王様なので、周囲の家来はみな話を合わせてくれる。すると、こういう会話がうまれることもあるだろう。
「さっき、わしは廊下で転んで痛い思いをし、悲鳴をあげた」
「左様でございますか」
「きのう、お前も廊下で転んで悲鳴をあげていたな、痛くもないのに」
「左様でございます」
「あれはいったいなんだ」
「はい、王様が痛みを感じているときと同じ振る舞いをしていただけなのです」
王様にとっては、痛みを感じるとはあの「痛さ」を直接感じることでしかない。「痛み」はもちろん、頭にイメージを思い浮かべたり、味を感じたり、悲しい気分になったり……といった直接的な知覚についても同様だ。家来たちもみな、それに話を合わせてくれている。こういう世界で生まれ育った王様は「他者」という概念を知らないまま生活することになる。家来という人間は認識しているが、そいつらにとってはそいつらの人生がある、ということを知らない。
■なぜ私たちは他人に心があると自然に思えているのか?
さて、もしもこの王様が非常に疑い深く、理屈をこねるのが好きな哲学者タイプだったとしよう。哲学者の王様は、他人に「心」があるという可能性に至ることができるだろうか?
これは「他人に心はないかもしれない」という懐疑よりも困難かもしれない。なぜなら、他人の心を疑うには「自分のときだけ生じていて、他人のときは生じない感覚」を根拠にすれば十分だが、哲学者の王様の場合はまったく逆になるからだ。
「この家来もわしと同様に痛みを感じているかもしれない」と思うには、家来「にとって」痛い、という概念を獲得しなければならないが、上述したようにその概念はほんとうは矛盾している。矛盾した結論に、理性でどうやって到達すればよいというのだろう。家来が殴られても、じっさい王様は痛くないのだ。そのうえ家来は、王様だけが本当の痛みを感じていると言ってくれるのだ。この場合、主観的な感覚と(王様にとっての)客観的な言説が一致しているのだから、疑いようがないではないか。
他人の心を疑うよりも、他人に心を認めるほうが、実は難しい。にもかかわらず、なぜかわたしたちは成り立たせるのが難しい方の世界観で生きている、不思議な存在なのだ。
いいなと思ったら応援しよう!